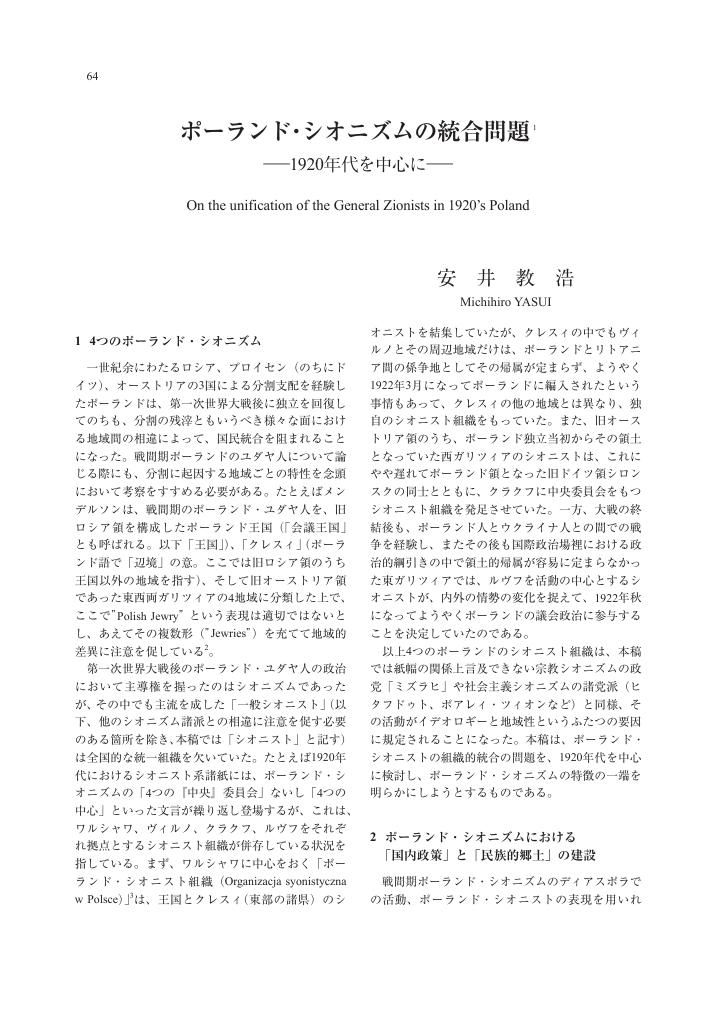2 0 0 0 OA 伝統文化の真正性と歴史認識 : ヴァヌアツ・アネイチュム島におけるネテグと土地をめぐって
- 著者
- 福井 栄二郎
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.1, pp.47-76, 2005-06-30 (Released:2017-09-25)
- 被引用文献数
- 1
本稿は、筆者が調査を行ってきたヴァヌアツ共和国・アネイチュム島の事例をもとに、彼らの伝統文化の真正性が変動する、その様態を明らかにするものである。アネイチュム語で「ネテグ(netec)」とは土地保有集団、親族集団を指し、一般的には父系の理念で成員権が決定される。またネテグは個人名の保有集団としても機能している。つまりあるネテグにはつけてもよい個人名が決められていて、それらを他のネテグの成員に命名してはいけないとされる。しかし実際には、非男系成員の編入も、個人名の他ネテグへの拡散も、相当数存在している。たしかに理念には抵触するのであるが、これまでそうした事象は、事実上「黙認」されていた。ただ近年になってこのような「黙認」の事象が引き金となり、土地問題が生じてきている。そこで彼らはこれまで「黙認」だった事象を「間違った」ことと捉え直すようになり、今後は禁止しようとしている。つまりある事象に対して「黙認」から「禁止」へと真正性が変動したのだと考えられる。このように、ある伝統的事象が「正しい」とか「間違っている」と考える際、彼らが参照にしているのが、西洋人がやってくる以前の「かつての姿」である。そこで本稿では、島民たちの考える「かつての姿」を歴史資料を用いて多面的に考察するが、彼らの認識は必ずしも「事実」ではないのかもしれない。ただ重要なことは、それが「事実」かどうかなのではなく、伝統文化をはかるときのメルクマールとして実際に機能しているという点である。つまり彼らの「歴史」はひとつのリアリティを有しているし、換言すれば、伝統文化とは彼ら自身の歴史認識を抜きに理解することができないのだと結論づける。
2 0 0 0 OA 日本の戦争責任を謝罪することば
- 著者
- 遠藤 織枝
- 出版者
- 社会言語科学会
- 雑誌
- 社会言語科学 (ISSN:13443909)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.51-64, 2000-12-31 (Released:2017-04-27)
1998年11月,江沢民中国主席が訪日した際,「おわび」「謝罪」のことばがとびかった.これをきっかけとして,日本の戦後処理に関する謝罪のことばが,過去においてどのようなものであり,現在どのように使われているかを確認したいと考えた.その方法と手順は以下のとおりである.1.発話行為としての「謝罪」のことばのあり方を考える.2.日本政府首脳と天皇の,主として中国・韓国首脳との会談の言辞を歴史的な流れの中でとらえる.3.それらが,中国・韓国側にどのように受け止められたかをみる.その結果,日本政府は,1990年以降は韓国に対しては,明確に「おわび」を繰り返しているが,中国に対しては細川首相が93年に訪中した際の1度だけ「おわび」のことばが述べられていることが明らかになった.また,日本政府の謝罪に関する発話行為が,70年代の「反省」「遺憾」という不完全なものから,90年代の「反省とおわび」という完全なものへと推移する経過を跡づけた.それは,「話し手の責任」の認識の変化と並行するもので,その変化は,今次の戦争について述べることばの変化に表されている.すなわち,「不幸な一時期」というあいまいな表現から「過去の戦争への反省」へ,さらに「侵略戦争」「植民地支配」へと具体化しており,この変化に合わせて相手側の受容-謝罪の遂行-の傾向が強まってくる動きをとらえることができた.
2 0 0 0 OA オンライン型小児病院前救護トレーニングコースの開発と展望
- 著者
- 問田 千晶 六車 崇 賀来 典之 塚原 紘平 安達 晋吾 光銭 大裕 新田 雅彦 野坂 宜之 林 卓郎 松浦 治人 守谷 俊
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.57-61, 2022-02-28 (Released:2022-02-28)
- 参考文献数
- 9
目的:オンライン型PPMECコース用の教材を作成し,オンライン型PPMECコースの理解・満足度と課題について検証した。方法:オンライン型PPMECコース受講前後のアンケート結果を用いて,新規教材およびオンライン型PPMECコースの理解度と満足度を量的に分析した。完全満足評価群と他評価群の2群比較および多重ロジスティック回帰分析を実施し,オンライン型PPMECコースの満足度に影響する因子を抽出した。結果:オンラン型PPMECコースは少数のインストラクターで多数の受講生に対して実施でき,一定の理解度と満足度を得ていた。完全満足群では教育内容を「十分に理解できている」と回答した受講生の割合が高かった。また,コースの満足度には「小児の評価」および「小児basic airway」の理解度がコース評価に有意に影響していた。結論:オンライン型PPMECコースは受講生の満足度と理解度を得ることにつながっていたが,理解しやすい教育教材への改良などによりコースの質を向上させることが課題である。
2 0 0 0 OA Electrochemical Synthesis of Dibenzothiophene S,S-Dioxides from Biaryl Sulfonyl Hydrazides
- 著者
- Yasuyuki OKUMURA Eisuke SATO Koichi MITSUDO Seiji SUGA
- 出版者
- The Electrochemical Society of Japan
- 雑誌
- Electrochemistry (ISSN:13443542)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.11, pp.112007, 2023-11-28 (Released:2023-11-28)
- 参考文献数
- 34
The electrochemical synthesis of dibenzothiophene S,S-dioxides was achieved by the anodic oxidation of biaryl sulfonyl hydrazides. The use of Bu4NOTf as the electrolyte in HFIP/CH3NO2 (15 : 1) is essential. Several biaryl sulfonyl hydrazides followed by dibenzothiophene S,S-dioxides under mild electrochemical conditions. Control experiments and density functional theory calculations suggested that the electrooxidation of biaryl sulfonyl hydrazides would generate sulfonyl radicals or sulfonyl cations which were converted to dibenzothiophene S,S-dioxides.
2 0 0 0 OA Cathodic N–O Bond Cleavage of N-Alkoxy Amide
- 著者
- Eisuke SATO Sayaka OGITA Koichi MITSUDO Seiji SUGA
- 出版者
- The Electrochemical Society of Japan
- 雑誌
- Electrochemistry (ISSN:13443542)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.11, pp.112005, 2023-11-28 (Released:2023-11-28)
- 参考文献数
- 26
Cathodic reduction efficiently cleaved N–O bonds. The simple cathodic reduction of Weinreb amides in a divided cell afforded the corresponding amide in good yields. Cyclic voltammetry experiments and density functional theory calculations suggested that the direct reduction of the N-methoxy amide generates the methoxy radical and amide anion. The release of methanol derived from methoxy radical would be the driving force of the N–O bond cleavage.
- 著者
- Tatsuhito II James K CHAMBERS Ko NAKASHIMA Yuko GOTO-KOSHINO Kazuyuki UCHIDA
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.23-0339, (Released:2023-12-08)
Our previous study indicated that cytotoxicity of intraepithelial lymphocytes is a poor prognostic factor in feline intestinal T-cell lymphoma (FITL), but the effect of cytotoxic lymphocytes on mucosal epithelium is still unknown. Thus, we investigated the association between cytotoxic lymphocytes and mucosal epithelium in 71 cases of feline intestinal T-cell lymphoma (FITL): epithelial injury, basement membrane injury, cleaved-caspase-3 positivity of epithelial cells, and the number and Ki67 positivity of intraepithelial lymphocytes in granzyme B (GRB)+ and GRB- FITLs were evaluated. Epithelial injury score and the number of intraepithelial lymphocytes in granzyme B (GRB)+ FITL were significantly higher than those of GRB- FITL (P<0.05, P<0.05), but no significant differences were found in the basement membrane injury score, the percentage of cleaved-caspase-3+ epithelial cells, and the percentage of Ki67+ intraepithelial lymphocytes. There was a significant correlation between the epithelial injury score and the number of intraepithelial lymphocytes (P<0.05), but no significant correlation was observed between the epithelial injury score and Ki67+ percentage of intraepithelial lymphocytes. Because epithelial cell cleaved-caspase-3 positivity was observed in FITL, regardless of GRB expression in lymphocytes, GRB-mediated apoptosis may not contribute to epithelial injury in FITL. The association between increased number of intraepithelial lymphocytes and epithelial injury suggests that intraepithelial lymphocytes infiltration may contribute to epithelial injury in FITL.
- 著者
- Hidetaka NISHIDA Riku KAKIMOTO Shunsuke NOGUCHI Ryoji KANEGI Shunsuke SHIMAMURA Toshiyuki TANAKA Tamiko FUMIMOTO Kento NISHIBATA Hidemasa FUJIWARA Hideo AKIYOSHI
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.23-0370, (Released:2023-12-11)
A 5-year-old neutered female mixed cat presented with reduced activity and ataxia of the hind limbs. Computed tomography and magnetic resonance imaging revealed an extradural mass compressing the spinal cord on the dorsal aspects from the 7th to 8th thoracic vertebra. Dorsal laminectomy was performed on the 7–8th thoracic vertebra and the cyst was totally removed, giving full resolution of the clinical signs. The cyst was diagnosed as a dermoid cyst. To our knowledge, this is the first report of feline dermoid cyst compressing the spinal cord that was diagnosed antemortem. The prognosis is favorable when the cyst is completely resected.
2 0 0 0 OA 不搬送という課題~蘇生を希望しない終末期患者への対応~
- 著者
- 高橋 功
- 出版者
- 一般社団法人 日本在宅救急医学会
- 雑誌
- 日本在宅救急医学会誌 (ISSN:2436066X)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.12-16, 2023-10-31 (Released:2023-12-02)
- 参考文献数
- 11
2 0 0 0 OA 夜間頻尿にNSAIDsが有効である : ロキソプロフェン60mg就眠前1回内服の効果
- 著者
- 荒木 徹
- 出版者
- 一般社団法人 日本泌尿器科学会
- 雑誌
- 日本泌尿器科学会雑誌 (ISSN:00215287)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, no.2, pp.394, 2002-02-20 (Released:2017-04-06)
- 著者
- Takato Hara Reina Kumagai Tohru Tanaka Tsuyoshi Nakano Tomoya Fujie Yasuyuki Fujiwara Chika Yamamoto Toshiyuki Kaji
- 出版者
- The Japanese Society of Toxicology
- 雑誌
- The Journal of Toxicological Sciences (ISSN:03881350)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.12, pp.655-663, 2023 (Released:2023-12-01)
- 参考文献数
- 39
Vascular endothelial cell growth is essential for the repair of intimal injury. Perlecan, a large heparan sulfate proteoglycan, intensifies fibroblast growth factor-2 (FGF-2) signaling as a co-receptor for FGF-2 and its receptor, and promotes the proliferation of vascular endothelial cells. Previously, we reported that 2 µM of lead, a toxic heavy metal, downregulated perlecan core protein expression and then suppressed the growth of vascular endothelial cells. However, since the mechanisms involved in the repression of perlecan by lead remains unclear, we analyzed its detailed signaling pathway using cultured bovine aortic endothelial cells. Our findings indicate that 2 µM of lead inhibited protein tyrosine phosphatase (PTP) activity and induced cyclooxygenase-2 (COX-2) via phosphorylation of the epidermal growth factor receptor (EGFR) and its downstream extracellular signal-regulated kinases (ERK1/2). In addition, among the prostanoids regulated by COX-2, prostaglandin I2 (PGI2) specifically contributes to the downregulation of perlecan expression by lead. This study revealed an intracellular pathway—the EGFR-ERK1/2-COX-2-PGI2 pathway activated by inhibition of PTP by lead—as a pathway that downregulates endothelial perlecan synthesis. The pathway is suggested to serve as a mechanism for the repression of perlecan expression, which leads to a delay in cell proliferation by lead.
- 著者
- 鳥羽 耕史
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.11, pp.14-26, 2010-11-10 (Released:2017-08-01)
一九六〇年代の小松左京は、SFやルポルタージュや評論によって、「日本」を探究したが、その結論は意外にも古き良き故郷であり、開発を望むものではなかった。『日本沈没』も田中角栄『日本列島改造論』への批判として書かれ、沈没する日本は古代に遡行したものとなっていた。この小説は現在に至るまでマンガ、ラジオドラマ、映画、テレビドラマなど、様々なメディア向けに脚色され続けているが、その流れを追っていくと、サブカルチャーを介した日本回帰という「J回帰」の特徴が出ていることがわかる。
2 0 0 0 OA <史料紹介>『合武末書』─紀州徳川藩の忍術伝書─
- 著者
- 中島 篤巳
- 出版者
- 国際忍者学会
- 雑誌
- 忍者研究 (ISSN:24338990)
- 巻号頁・発行日
- vol.2021, no.4, pp.37-44, 2021 (Released:2022-09-02)
2 0 0 0 OA 『確率論』と「若き日の信条」
- 著者
- 平井 俊顕
- 出版者
- The Japanese Society for the History of Economic Thought
- 雑誌
- 経済学史学会年報 (ISSN:04534786)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.42, pp.18-31, 2002 (Released:2010-08-05)
- 参考文献数
- 35
The purpose of this paper is to examine Keynes as a philosopher in view of the relation among A Treatise on Probability (1921), Ramsey's criticism (1926), Keynes' acceptance of Ramsey's criticism (1931), “My Early Beliefs” (1938), and Keynes' criticism of Tinbergen (1939).The conclusion is as follows:(1) In his youth, Keynes firmly believed in human rationality, as described in his philosophical work, A Treatise on Probability and his memoir, “MyEarly Beliefs.” However, in the midst of the chaos of post-WW 1 Europe he became more and more skeptical of human rationality and showed a greater awareness of the emotional aspect of human nature, which is typically shown in his criticism of the market society and his advocacy of the New Liberalism in The End of Laissez-Faire (1926). As the years went by, Keynes' skepticism became deeper and deeper and came to stress the importance of custom and tradition, while he came to revalue the market society in face of the realities of the Soviet society.(2) Keynes abandoned the most essential part of his A Treatise on Probability, which regards probability as degrees of rational belief between propositions, and the justification of induction based on it, in the face of Ramsey's criticism. This is evidently recognizable in his obituary of Ramsey and “My Early Beliefs”. However, he did not abandon his theory of probability completely, which is shown in his critical review of Tinbergen (1939). In Part V (The Foundations of Statistical Inference) of A Treatise on Probability, Keynes had criticized the mathematical use of statistical frequencies (Methods of Laplace) and defended the inductive use of them (Methods of Lexis). Keynes' criticism of Tinbergen's method is mainly based on this stance. We have Keynes who accepted Ramsey's criticism on the one hand, and retained the Methods of Lexis on the other. A logical fissure seems to run between Part III (Induction and Analogy) and Part V.
2 0 0 0 OA 安全ランプとガスマスク ―アレクサンダー・フォン・フンボルトの世界 (2) ―
- 著者
- 柴田 陽弘
- 出版者
- ゲーテ自然科学の集い
- 雑誌
- モルフォロギア: ゲーテと自然科学 (ISSN:0286133X)
- 巻号頁・発行日
- vol.1993, no.15, pp.36-45, 1993-11-03 (Released:2010-02-26)
- 参考文献数
- 28
- 著者
- 箱﨑 太誠 村田 祐樹 﨑濱 星耶 大見 卓司
- 出版者
- 一般社団法人 日本アスレティックトレーニング学会
- 雑誌
- 日本アスレティックトレーニング学会誌 (ISSN:24326623)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.1-10, 2023-10-31 (Released:2023-11-07)
- 参考文献数
- 20
本研究は,コンタクトスポーツを行う大学クラブを対象に,頭部外傷の安全管理対策への取り組みの実態と障壁を把握することを目的に質問紙調査を行った.その結果,頭部外傷発生時における対応に関する質問項目は実施率が高く,重症頭頚部外傷に備えた搬送方法の練習,脳振盪を評価するツールのベースライン評価および脳のメディカルチェックなど頭部外傷発生時に備えた事前準備に関する質問項目は実施率が低いことが確認された.
2 0 0 0 OA 片麻痺者の歩行パターンの違いによる歩行時の筋電図・運動力学的特徴
- 著者
- 田中 惣治 山本 澄子
- 出版者
- バイオメカニズム学会
- 雑誌
- バイオメカニズム (ISSN:13487116)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.107-117, 2016 (Released:2017-08-01)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 9 2
麻痺側立脚期の膝関節の動きにより片麻痺者の歩行パターンを分類し, 歩行パターンの違いにより歩行時の下肢筋活動と運動力学的特徴が異なるか, 三次元動作分析装置と表面筋電計を用いて分析した. 回復期片麻痺者35名を対象とし, 歩行時の膝関節と下腿傾斜角度から, 健常者の膝の動きと近い健常膝群 (15名), 荷重応答期と単脚支持期にそれぞれ膝関節が伸展する初期膝伸展群 (5名) と中期膝伸展群 (15名) に分類した. 結果, 健常膝群は荷重応答期で腓腹筋の筋活動を抑えながら前脛骨筋が働くため十分な背屈モーメントを発揮し, 踵ロッカーが機能した. 中期膝伸展群は荷重応答期で腓腹筋の筋活動が大きいため背屈モーメントが十分に発揮されず, 踵ロッカー機能が低下しており, 初期膝伸展群は荷重応答期で前脛骨筋の筋活動が小さく背屈モーメントが発揮されないことから, 踵ロッカーが機能しないことが明らかになった.
2 0 0 0 OA 深層展開に基づく信号処理アルゴリズムの設計 ―収束加速とその理論的解釈―
- 著者
- 和田山 正 高邉 賢史
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.60-72, 2020-07-01 (Released:2020-07-01)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 3 4
深層学習技術は,深層ニューラルネットワークの学習に利用できるだけではなく,入出力を伴う “微分可能な反復型アルゴリズム” の内部パラメータ最適化に適用可能である.従前から知られている優れた反復型アルゴリズムを基礎として,その内部に学習可能パラメータを埋め込むことで,データに基づく学習可能性をもつ柔軟な派生アルゴリズムを構成できる.このアプローチを深層展開と呼ぶ.本稿では,線形逆問題の一つであるスパース信号再現における再現アルゴリズムを中心として,深層展開の概要とその特徴を紹介する.本稿の前半では,深層展開により導かれるスパース信号再現アルゴリズムの実例(TISTA)を紹介するとともに,深層学習に基づいて構成されたアルゴリズムで見られる収束加速について解説する.本稿の後半では,収束加速の要因となる学習後パラメータに関する理論的成果(チェビシェフステップに基づくスペクトル半径制御)について概説する.そこでは,なぜ深層展開が収束加速を与えるのか,という問いに対する一つの回答が与えられる.
2 0 0 0 OA 台湾における地理学
- 著者
- 葉 倩瑋
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.121, no.5, pp.841-855, 2012-10-25 (Released:2012-12-05)
- 参考文献数
- 83
- 被引用文献数
- 1 1
In Taiwan, geographical research, especially human geography reflects contemporary political and social changes. This paper examines the transformation of geographical research under a period of social and political changes in Taiwan. After the Japanese colonization ended in 1945, The Republic of China, led by the Kuo Ming Tang (KMT, Nationalist Party) became the new ruler of Taiwan. In 1949, the KMT moved its government to Taiwan and placed martial law. Until martial law was lifted in 1987, Taiwanese society experienced political turmoil, and the academic environment was also affected. The history of geographical research in Taiwan began in 1946, when the first geography department was established at National Taiwan Normal University (NTNU), a university that specialized in training high-school teachers. Geography came under the Department of History and Geography until 1962, when an independent Department of Geography was established. The initial mission of the department was to cultivate patriotism and loyalty to the government. The second department was founded at the National Taiwan University (NTU) in 1955 with the meteorology division under the Faculty of Science. The third department of geography was established in 1963 at a private university, Chinese Culture University, and was affiliated with the university's Faculty of Science. Two other departments were established at Changhua University of Education and Kaohsiung University of Education in the 1990s. The fact that these departments were affiliated with the Faculty of Science shaped the initial characteristics of geographical research, which emphasized the physical sciences. This bias was also rooted in the Japanese colonial period (1895-1945), because the only Japanese geographer at that time, Tomita Yoshiro, specialized in geomorphology. After Japanese colonization, those geographers who had gained advanced degrees in Japan considerable influence on research in this field. They brought the prevailing Japanese methodology of geography, particularly of geomorphology, climatology, and regional/settlement geography. This methodology was characterized by detailed ethnographic field investigation. Due to this institutional background, during the early stage of the development of geography in Taiwan physical geography was predominant, while human geography was studied only as a part of regional and industrial geography. The political situation intensified this tendency in academia; themes related to political and social issues were avoided in academic research.View PDF for the rest of the abstract.
2 0 0 0 OA ポーランド・シオニズムの統合問題 ―1920年代を中心に―
- 著者
- 安井 教浩
- 出版者
- 日本ユダヤ学会
- 雑誌
- ユダヤ・イスラエル研究 (ISSN:09162984)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.64, 2013 (Released:2020-09-16)
2 0 0 0 OA 慢性疼痛下におけるモルヒネの精神依存形成抑制と鎮痛作用の感受性低下の分子機構
- 著者
- 成田 年 鈴木 雅美 成田 道子 新倉 慶一 島村 昌弘 葛巻 直子 矢島 義識 鈴木 勉
- 出版者
- Japan Society of Pain Clinicians
- 雑誌
- 日本ペインクリニック学会誌 (ISSN:13404903)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.4, pp.397-405, 2004-10-25 (Released:2009-12-21)
- 参考文献数
- 30
神経因性疼痛下ではモルヒネに対する鎮痛作用の感受性が低下することが知られているが, その詳細な分子機構はほとんど解明されていない. 本稿では, 神経因性疼痛下におけるモルヒネの鎮痛作用の感受性低下と神経因性疼痛を含めた慢性疼痛下におけるモルヒネの精神依存形成抑制の分子機構について検討した結果を紹介する. 坐骨神経結紮により, 脊髄後角において protein kinase C (PKC) および脳由来神経栄養因子 (brain-derived neurotrophic factor: BDNF) の免疫活性の増大およびアストロサイトの著しい形態変化が観察された. また, このような変化は非疼痛下でモルヒネを慢性処置することによりモルヒネの鎮痛耐性が形成された動物の脊髄においても認められたことから, こうした変化は神経因性疼痛下におけるモルヒネの鎮痛作用減弱の一因である可能性が示唆された. また, 神経因性疼痛下では, モルヒネの精神依存形成が著明に抑制されることを確認した. さらに, 神経因性疼痛下では, 腹側被蓋野においてγ-aminobutyric acid (GABA) 含有神経上に存在するμオピオイド受容体の機能低下が引き起こされること, また, ドパミン神経上における extra-cellular signal-regulated kinase (ERK) 活性の著明な減弱が引き起こされることが明らかとなった. 一方, ホルマリンの足蹠皮下投与による炎症性疼痛モデルにおいても, モルヒネの精神依存形成は有意に抑制された. この現象は, κオピオイド受容体拮抗薬の前処置によりほぼ完全に消失した. これらのことから, 神経因性疼痛下においては, 腹側被蓋野におけるμオピオイド受容体の機能およびERK活性の低下が, また, 炎症性疼痛下では, 内因性κオピオイド神経系の活性化が主因となり, モルヒネの精神依存形成が抑制されたと考えられる.