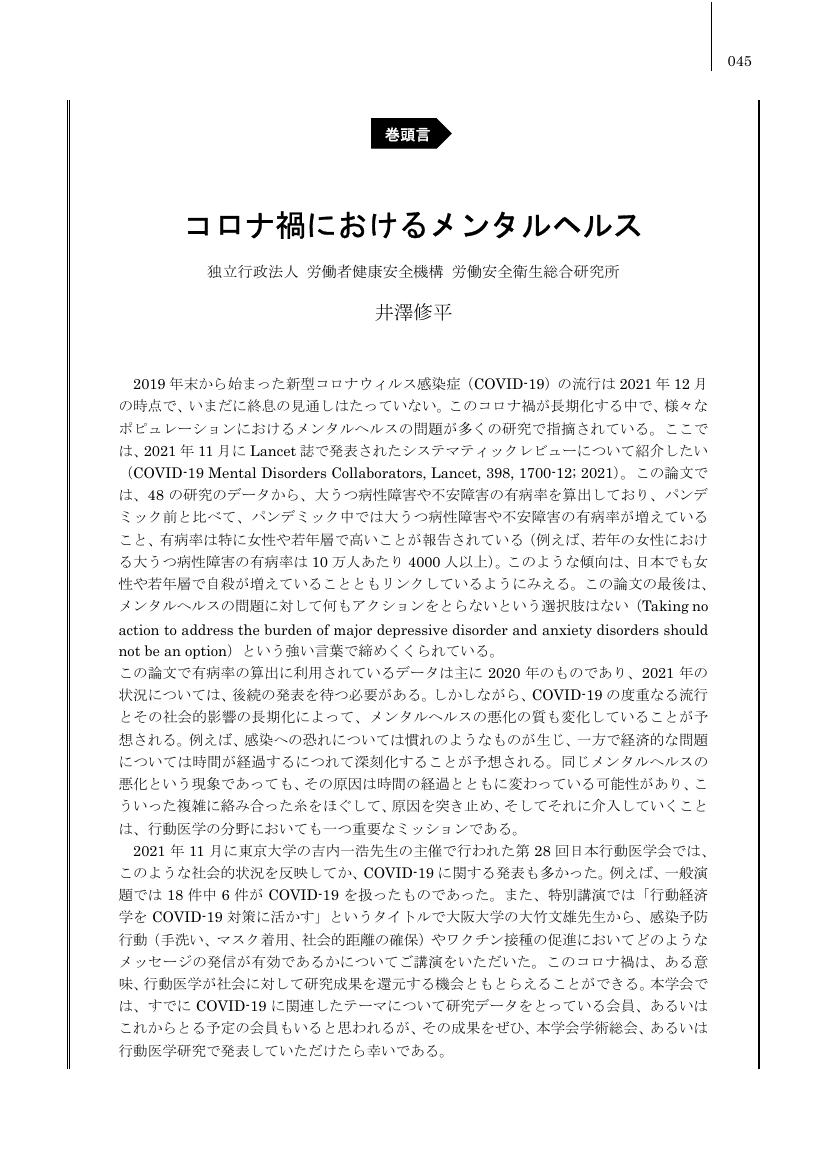5 0 0 0 OA 小学校第5学年におけるグラフ解釈に関する短時間学習の効果
- 著者
- 槇 誠司 佐藤 和紀 板垣 翔大 齋藤 玲 堀田 龍也
- 出版者
- 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.Suppl., pp.045-048, 2018-03-01 (Released:2018-03-01)
- 参考文献数
- 7
情報化社会に向かう今日において,統計的リテラシーを身につけることがより重視されている.本研究では,グラフの傾向を読み取り,考察し,それを根拠にして示された事象について批判する能力(以下,グラフ解釈能力と呼ぶ)を短時間で児童に身につけさせるための学習を授業時間内で実施した.この学習は,児童がグラフ解釈を行った結果を100字以内でまとめ,それらの内容を隣同士で互いに話し合い,最後に全体に向けて発表するまでを10分間でおこなう学習活動である.グラフ解釈に関する短時間学習を14回実施した場合,クラス全体のグラフ解釈能力は7回目頃から向上する傾向にあることが示唆された.さらに,グラフ解釈に関する短時間学習を経験した児童は,これを経験しない児童と比較して,グラフ解釈に関するテストの得点が高いことが明らかとなり,本学習の効果が示唆された.
5 0 0 0 OA 現代英語の迂言的doを遡る
- 著者
- 宮前 和代
- 出版者
- 専修大学外国語教育研究室
- 雑誌
- 専修大学外国語教育論集 (ISSN:13403303)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, pp.27-49, 2020-02-28
5 0 0 0 OA 東京中央郵便局沿革史 : 日本初の地下電車 : 郵便物搬送用地下軌道
- 著者
- 井上卓朗
- 出版者
- 郵政博物館
- 雑誌
- 逓信総合博物館研究紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.平成24年度, no.4, 2013-03-08
5 0 0 0 OA 日本における慣習的信仰の基礎的研究
- 著者
- 東海林 克也 ショウジ カツヤ Katsuya Shoji
- 雑誌
- 21世紀社会デザイン研究 : Rikkyo journal of social design studies
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.45-54, 2016
- 著者
- Keisuke Kojima Naoki Sunagawa Yoshihisa Yoshimi Theodora Tryfona Masahiro Samejima Paul Dupree Kiyohiko Igarashi
- 出版者
- The Japanese Society of Applied Glycoscience
- 雑誌
- Journal of Applied Glycoscience (ISSN:13447882)
- 巻号頁・発行日
- pp.jag.JAG-2021_0017, (Released:2022-03-05)
- 被引用文献数
- 7
Endo-type xylanases are key enzymes in microbial xylanolytic systems, and xylanases belonging to glycoside hydrolase (GH) families 10 or 11 are the major enzymes degrading xylan in nature. These enzymes have typically been characterized using xylan prepared by alkaline extraction, which removes acetyl sidechains from the substrate, and thus the effect of acetyl groups on xylan degradation remains unclear. Here, we compare the ability of GH10 and 11 xylanases, PcXyn10A and PcXyn11B, from the white-rot basidiomycete Phanerochaete chrysosporium to degrade acetylated and deacetylated xylan from various plants. Product quantification revealed that PcXyn10A effectively degraded both acetylated xylan extracted from Arabidopsis thaliana and the deacetylated xylan obtained by alkaline treatment, generating xylooligosaccharides. In contrast, PcXyn11B showed limited activity towards acetyl xylan, but showed significantly increased activity after deacetylation of the xylan. Polysaccharide analysis using carbohydrate gel electrophoresis showed that PcXyn11B generated a broad range of products from native acetylated xylans extracted from birch wood and rice straw, including large residual xylooligosaccharides, while non-acetylated xylan from Japanese cedar was readily degraded into xylooligosaccharides. These results suggest that the degradability of native xylan by GH11 xylanases is highly dependent on the extent of acetyl group substitution. Analysis of 31 fungal genomes in the Carbohydrate- Active enZymes database indicated that the presence of GH11 xylanases is correlated to that of carbohydrate esterase family 1 acetyl xylan esterases (AXEs), while this is not the case for GH10 xylanases. These findings may imply co-evolution of GH11 xylanases and CE1 AXEs.
5 0 0 0 OA PMSMをボールねじと一体としたアクチュエータ駆動システムの高精度位置決めに関する研究
5 0 0 0 OA 日本産Monographis屬の1新種
- 著者
- 三好 保徳
- 出版者
- Arachnological Society of Japan
- 雑誌
- Acta Arachnologica (ISSN:00015202)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1-2, pp.1-8, 1947-03-20 (Released:2008-12-19)
- 被引用文献数
- 5 5
5 0 0 0 OA 新聞記事からみた京都における地蔵の配置変化に関する考察
- 著者
- 竹内 泰 牧 紀男
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.766, pp.2573-2583, 2019 (Released:2019-12-30)
- 参考文献数
- 17
The purpose of this study is to clarify the characteristics of the positions of Jizo in Kyoto through analyzing the newspaper articles and photos especially about Jizo and Jizo-bon festival from early modern period to today. In this paper, we clarified the transformation of the social position of Jizo that had been emerged by the social problems through Jizo. The results of this study are as follows. After the order in 1871 to remove Jizo on the street, there were 4 periods the number of articles of Jizo increases as follows. ①The first period from 1887 to 1892 that the revival of Jizo-bon festival was paid attention as the curious affair. After this period Jizo and Jizo-bon festival became to be general as the usual situation before the order. ②The second period from 1929 to 1941 that Jizo and Jizo-bon festival had been the object of deeper and various interests, and after the outbreak of the Shino-Japanese War and the Pacific War, had been influenced strongly and utilized enhancing national prestige. ③The third period from 1952 to 1958 that Jizo-bon festival was appealed for the purpose of the democratic education after the war as the festival mainly for and by the children. ④The fourth period from 1971 to 1984 that the most interest was drawn, and the Jizo-bon festival was recognized to be necessary for the community work or the community formation, and such the recognition became established. The revival of Jizo-bon festival was reported from 1881, and it became established again as the urban festival in Kyoto city in around 1899. And the changes of the road environment influenced to remove the location of the Jizo-bon festival in the 30’s of Showa period. Through this study the process of the Jizo’s re-position facing to the street has been clarified that the position of the Jizo in usual situation was seen in some of Cho in around 1892, and they began to be positioned under the eaves of the shop house facing to the street in around 1900. Before early Showa period such the positions became general. Analyzing through the newspaper photos, the outside location of Jizo-bon festival had been changed from the road into the other outside space like the alley, the rooftop, the temple, the park or the primary school, or into the inside space of the house or the temple. And the elements of the festival became to be composed from the long-term setting materials into the short-term ones. These changing terms were from the 30’s to the 50’s centering the 40’s of Showa period, and these periods overlap with the changing periods of the road environment.
5 0 0 0 OA 動物の歩容遷移を再現する4脚ロボット
- 著者
- 大脇 大
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.126-131, 2019 (Released:2019-03-20)
- 参考文献数
- 61
- 著者
- 宮澤 一 内田 訓 大槻 穣治 森田 健 森田 良治 松山 優子 畑山 美佐子
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, 2008-04-20
【はじめに】プロボクシングは両拳によって相手の顔面、腹部の急所を狙ってダメージを競い合うコンタクトスポーツであり、その競技特性上、外傷・障害は避けられず、時に生命に危険を及ぼすことさえ有り得る。平成7年より日本ボクシングコミッション(以下JBC)認定のプロボクシングジムから要請を受けサポート活動を開始し、平成10年からはチーフセコンド(試合中、一人だけリングに入ることが許され、選手に戦略や指示を与える係)およびカットマン(試合中、選手の受けた外傷の止血や応急処置を行う係)として試合に帯同する機会を得た。今回、日本タイトルマッチ5回を含む10年間の活動をまとめ、今後の課題を検討する。<BR>【対象】平成10年から平成19年の10年間で、JBC認定ジム所属のプロボクサー25名(18歳~35歳)による全156試合。<BR>【結果】156試合中97試合(62.2%)で129件の外傷・傷害が発生した。受傷機転からグループ分類すると頭部顔面の裂傷・外傷群56件(43.4%)、中手骨頭・手指打撲群53件(41.1%)、脳損傷・脳震盪群14件(10.9%)、その他障害は6件(4.6%)であった。対応としてはアイシング75件、テーピング58件、止血処置38件、医療機関に同行5件、徒手療法3件、その他3件であった。 <BR>【考察】打撃を顔面に受けることや頭部同士が接触することにより、頭部顔面の裂傷・腫脹などの外傷の発生は競技特性からも避けられず、最も多い結果であった。小さな裂傷であれば1分間のインターバルで止血処置をして試合再開となるが、危険と判断されるレベルに達した場合、試合は中止される。短時間での適切な止血処置能力や腫脹を軽減させる技術力向上も要求されるが、ダメージが大きい場合は選手の将来を考えて試合中止を申し出る判断も必要と考える。<BR>また打撃を与える拳のダメージも同様に多く、中手骨頭骨折で引退となったケースもあった。試合前に予防としてのバンデージを両拳に巻くことがルールで認められているが、これまでの伝統的な方法にPTの知識を生かして、より衝撃を軽減し、拳や関節を保護できるような方法を考案していきたい。<BR>また全体の約10%は脳自体のダメージと考えられるもので、試合直後に開頭手術を要した1件(現在は社会復帰)を含め医療機関に直行したケースは5件(うち救急車要請2件)であった。試合後の選手の状態には細心の注意を払い、状態悪化時の初期対応についてもスムーズに実施できるよう手順が確立されていることが必要とされる。近年、安全管理面から早めのストップが提唱されているものの実際に死亡事故も発生している。外傷障害に対する応急処置や知識の啓蒙だけでなく、練習過程から試合後のフォローまでの総合的なコンディショニング管理をとおして、PTの視点から出来ることを今後も模索していきたいと考える。 <BR><BR><BR>
- 著者
- 佐藤 翔 石橋 柚香 南谷 涼香 奥田 麻友 保志 育世 吉田 光男
- 出版者
- 情報知識学会
- 雑誌
- 情報知識学会誌 (ISSN:09171436)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.3, pp.268-283, 2019 (Released:2019-11-15)
- 参考文献数
- 25
本研究では非専門家にとっての論文タイトルの「面白さ」を得点化し,Twitterからの言及数が多い論文と言及されたことのない論文でこの得点に差があるかを検証した.Twitterからの言及数データはCeek.jp Altmetricsから収集し,2008年に出版された論文の中でTwitterからの言及回数が特に多い論文103本と,言及回数が0の論文の中からランダムに選択した100本を分析対象とした.4名の非専門家が各論文タイトルの「面白さ」を7段階で評価し,その点数の合計を「面白さ」得点と定義した.分析の結果,Twitterからの言及数が多い論文グループと,言及数が0の論文グループで「面白さ」得点には有意な差が存在し,Twitterからの言及数が多い論文の方がタイトルが「面白い」傾向が確認された.さらに,この差は分野別に分析しても確認された.
5 0 0 0 IR 八百比丘尼伝承の死生観(木山英雄教授退職記念号)
- 著者
- 小野地 健
- 出版者
- 神奈川大学
- 雑誌
- 人文研究 : 神奈川大学人文学会誌 (ISSN:02877074)
- 巻号頁・発行日
- vol.155, pp.A51-A72, 2005
5 0 0 0 OA E・ニーキッシュの「抵抗思想」について ―そのナショナル・ボルシェヴィズムとはなにか―
- 著者
- 古田 雅雄
- 出版者
- 奈良産業大学法学会
- 雑誌
- 奈良法学会雑誌 = Nara Law Review
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.1-29, 2014-03-31
5 0 0 0 OA 障害理解教育の必要性や実施に関する実態調査
- 著者
- 佐野 舞花 関原 真紀 Maika SANO Maki SEKIHARA
- 出版者
- 上越教育大学
- 雑誌
- 上越教育大学教職大学院研究紀要 = Bulletin of Teaching Profession Graduate School Joetsu University of Education (ISSN:24359637)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.131-141, 2022-02-28
- 著者
- 四方田 健二
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, pp.757-774, 2020 (Released:2020-11-18)
- 参考文献数
- 54
- 被引用文献数
- 3 6
The novel coronavirus (COVID-19) pandemic has seriously affected individual lifestyles and circumstances. This study aimed to explore the public concerns and stress caused by the pandemic. Data were collected from Twitter posts that included the terms ‘corona’ AND (‘fatigue’ OR ‘stress’ OR ‘depression’) from January 15 to March 17, 2020 (9 weeks; 63 days). Text data in 241,720 posts were analyzed using a quantitative text analysis technique employing KH Coder software. The results showed that concerns and stress related to coronavirus varied over a wide range of aspects, including fear of infection, stress due to restriction of daily behavior and recreational activities, concerns over government epidemiological measures and economic damage, and concerns arising from media information. In particular, concerns and stress resulting from restriction of daily behavior and recreational activities were found to have increased through the lengthening of restrictions. These results suggested a need for public support in order to maintain physical and mental health. It was also suggested that school health education and social health promotion should be considered to include approaches for managing stress and practical knowledge of media literacy which adapt to the spread of social network communication during the pandemic phase.
5 0 0 0 OA かつおだし及びその原材料等の抗酸化能発現に関する研究
- 著者
- 根來 宗孝 香西 彩加 澤村 弘美 榎原 周平 渡邊 敏明 前川 隆嗣
- 出版者
- 日本微量栄養素学会
- 雑誌
- 微量栄養素研究 (ISSN:13462334)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.33-37, 2020-12-15 (Released:2021-12-13)
- 参考文献数
- 14
There are only a few reports on the antioxidative activity of bonito bouillon (Katsuo-Dashi soup stock),a traditional Japanese seasoning, and their raw materials. The Dashi packs (powder-type soup stock) and evaporated Dashi (liquid type soup stock) are popular and are often used in Japanese meals, in which raw materials comprising dried bonito (Katsuo-bushi),dried kelp (Kombu),and dried shiitake mushroom (Lentinula edodes) are mixed. However, how much each raw material contributes to the antioxidative activity of the final products is unknown. So, we evaluated the antioxidative activity by 1, 1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging capacity. In addition, dried bonito (Katsuo-bushi) are classified into the sub-groups of sun-dried bonito (Tempi-bushi),smoke-dried bonito (Arabushi) and smoke- and mold-dried bonito (Kare-bushi). There have been several reports of antioxidative effects of phenolic compounds absorbed by Katsuo-bushi during the smoking processes of fresh bonito (making Katsuo-bushi). Several phenolic compounds with methoxy or acetyl groups have been identified as aromatic components that increase during the production of Ara-bushi and Kare-bushi. Here, we also report the relationship between the chemical structure of hydroxy methoxy acetophenone and the expression of its antioxidative activity by the 1, 1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) method. These results indicate that Dashi Packs and evaporated Dashi including a lot of Katsuobushi have a high antioxidative activity, which may originate from phenolic compounds that increased in volume during the smoking process.
5 0 0 0 IR 加藤周一の思想史的考察 ―その本質と軌跡―
- 著者
- 久保 雄太郎
- 出版者
- Tohoku University
- 巻号頁・発行日
- 2021
課程
5 0 0 0 OA コロナ禍におけるメンタルヘルス
- 著者
- 井澤 修平
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.45-1, 2021 (Released:2022-01-23)
5 0 0 0 OA 通常の学級と通級における効果的な連携の在り方に関する研究
- 著者
- 佐野 舞花 関原 真紀 Maika SANO Maki SEKIHARA
- 出版者
- 上越教育大学
- 雑誌
- 上越教育大学教職大学院研究紀要 = Bulletin of Teaching Profession Graduate School Joetsu University of Education (ISSN:24359637)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.71-80, 2021-02-28
5 0 0 0 伊吹島アクセントに重大な疑問
- 著者
- 山口 幸洋 名倉 仁美
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 國語學 (ISSN:04913337)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.3, pp.100-101, 2001-09-29
香川県伊吹島方言は昭和41年の和田実の報告以来,1200年前のアクセント(以下アと略)を保つものとして学界の定評を成している。山口は当時その検証調査によって,その事実を追認したものとして責任がある。山口,名倉は,平成12,13年の調査で,その疑問が明らかなものとして,その反省を述べる。疑問点は,方言ア研究上異例の,言語外事実とのギャップにある。すなわち,燧灘海中の伊吹島は人口定住400年の地で,そこに1200年前のアを認めるのは不自然である。400年前無人島だったことに論議の余地はない。島の生活は少雨地帯で知られる瀬戸内海にあっても,とりわけ,全島岩盤で川も湧き水もなく,飲料水は,地中の岩盤に穿鑿した貯水槽の天水に依存して来た。このとき言語学が,人間の存続に関わる水や人口の問題を,言語外事実ゆえ取り上げるべきでないと済ませて超然とすることは,大仰に言って言語学そのものに関わる問題である。本発表では,伊吹島のアを,純粋に言語的(言語地理学,社会言語学)に次のように考察する。(1)そもそも,伊吹島アに見られる「二拍名詞類別体系(五つの区別)」は,平安時代「類聚名義抄」と同一のものであるにしても,音調そのものが同質のものかどうかに疑問がある。(2)徳川宗賢によって系統樹的方言変化シミュレーション「系譜論」で「類聚名義抄五つの区別」が頂点に据えられ,類別は,「統合することはあっても分裂することはない」というテーゼによって,諸方言の類別体系が考古学の地層のような年代測定に利用されることの是非。(3)伊吹島二拍名詞3類における「下降調」を,「日本祖語」の音調と比定することの是非。それらすべてに疑問を提出し,代わって伊吹島アが香川県の讃岐式ア,愛媛・阪神の京阪式ア,岡山・愛媛の東京式アすべての接点にあるという言語地理的背景ゆえの交流接触,それに加えて,伊吹島の江戸時代以降の阪神方面との関係(組織的な西宮灘の宮水運搬,泉佐野市方面への出漁),大正昭和の漁業振興に伴う異常な人口増大(転入)とともに当アが混淆成立したとする社会言語学的解釈を述べた。