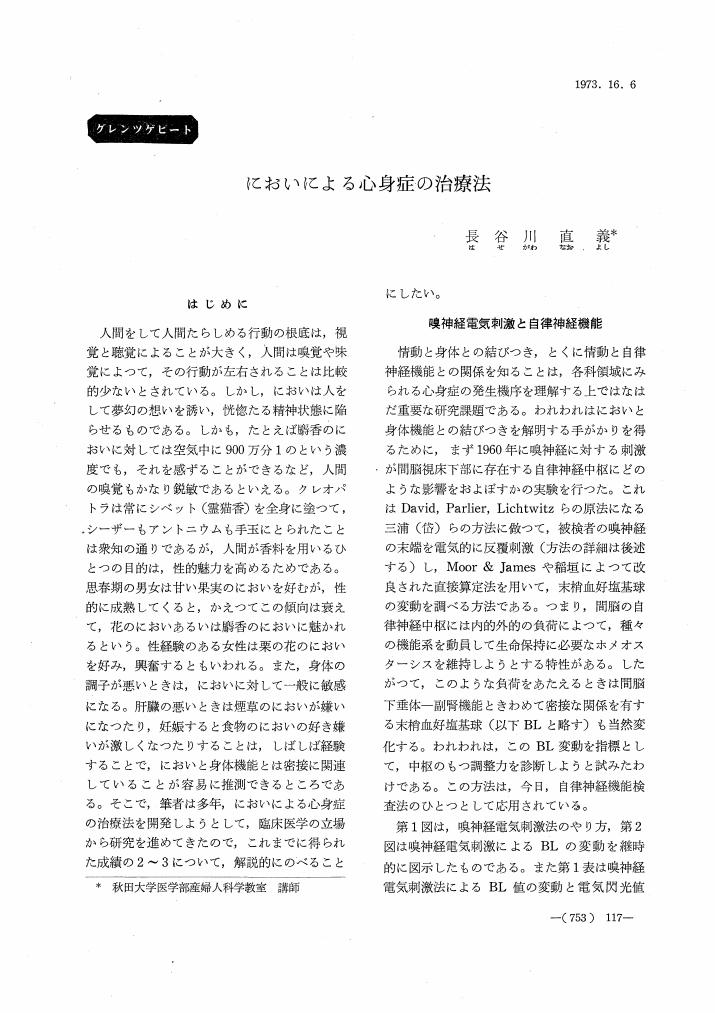5 0 0 0 OA プラトン『法律』の議論と筋書き(1)
- 著者
- 石崎 嘉彦
- 出版者
- 政治哲学研究会
- 雑誌
- 政治哲学 (ISSN:24324337)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.99-123, 2016 (Released:2019-09-05)
本翻訳は、Leo Strauss, The Argument and the Action of Plato's Laws, The University of Chicago Press, 1975 (Midway reprint 1983)のうち、ジョゼフ・クロプシーの「前書き」と「第一巻」を訳出したものである。
5 0 0 0 OA 哺乳類の日本語分類群名,特に目名の取扱いについて —文部省の“目安”にどう対応するか—
- 著者
- 田隅 本生
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.83-99, 2000 (Released:2008-07-30)
- 被引用文献数
- 3
5 0 0 0 OA 子どもの虐待へのアプローチ
- 著者
- 信田 さよ子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.3, pp.286-295, 2001-09-30 (Released:2007-12-27)
- 参考文献数
- 8
5 0 0 0 OA 【35】ハンブルグ高架鐵道の新自動連結器(11.鐵道および鐵道車輛)
- 著者
- 多厚 祐重
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 機械學會誌 (ISSN:24331546)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.130, pp.54a-55a, 1928-02-20 (Released:2017-08-01)
5 0 0 0 OA ディーゼル機關車に就て
- 著者
- 多賀 祐重
- 出版者
- 一般社団法人 日本エネルギー学会
- 雑誌
- 燃料協会誌 (ISSN:03693775)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.11, pp.1290-1297, 1931 (Released:2011-10-21)
ディーゼル機關を機關車に應用すれば理論上種々の利益あり、その爲めディーゼル機關を機關車の原動力として採用することが相當古くから研究され來りしも、ディーゼル機關車は今日尚研究時代を脱することを得ざる程度の發達を示し居るに過ぎず、此の原因としては技術上と経濟上との困難を考へられる前者の問題は漸次解決せられ來りしも経濟上の問題の解決は今後に俟つべきものなりとす
5 0 0 0 OA 歯科訪問診療において義歯装着可否を判断するための予測因子の探索
- 著者
- 小出 勝義 赤泊 圭太 吉岡 裕雄 後藤 由和 渥美 陽二郎 白野 美和
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年歯科医学会
- 雑誌
- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, pp.220-226, 2021-12-31 (Released:2022-01-28)
- 参考文献数
- 25
歯科訪問診療の患者背景は複雑であり,担当歯科医師はそのなかから義歯製作後に患者が使用可能か不可能かを客観的に判断することは難しい。そこで,新義歯装着の可否を判断する予測因子を探索することを目的として,2013年から2018年の5年間に当科での歯科訪問診療の要請があった初診患者において義歯製作を行い,その後継続して義歯の使用が可能であった患者を「義歯使用可能群」,義歯製作を行ったがその後義歯が使えず使用を中断した患者を「義歯使用不能群」に分類した。義歯使用可能群294名と義歯使用不能群25名における患者の口腔内状態,全身状態,治療依頼者などとの関連について調査した。 義歯使用不能群では,義歯使用可能群と比べ座位保持状態が不良な者の割合が多かった(オッズ比7.870,95%信頼区間=3.098~19.992,p<0.001)。また,義歯使用不能群では,パーキンソン病の既往を有する者(p=0.048),含嗽不能の者(p=0.012)の割合が多かった。座位保持は,義歯の装着に影響を及ぼす身体機能を判断するのに有効であり,義歯を必要とする高齢者の義歯使用可否にも大きく影響すると考えられる。 歯科訪問診療において座位保持の可否が義歯装着の可否を判断する一助となる可能性が示された。
5 0 0 0 OA 星状神経節近傍への直線偏光近赤外線照射が手と頭部の体温および血流に及ぼす影響
- 著者
- 西村 友紀子 森山 直樹 石部 裕一
- 出版者
- Japan Society of Pain Clinicians
- 雑誌
- 日本ペインクリニック学会誌 (ISSN:13404903)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.137-140, 2003-04-25 (Released:2009-12-21)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 2
目的: 星状神経節近傍への直線偏光近赤外線照射が手と頭部の体温および血流に及ぼす影響を調べた. 方法: 健康成人20人で二重盲検比較試験を行った. 直線偏光近赤外線治療器 (SUPERLIZER HA-550®, 東京医研) の通常装置と出力0%のダミー器を用い, 日を変えて左側星状神経節近傍に7分間の照射を施行した. 測定項目は, 室温, 両側手掌深部温, 両側第3手指尖表面温, 両側拇指球血流速度, 両側鼓膜温, 左側中大脳動脈血流速度および両側前額部頭蓋内酸素飽和度で, 照射15分前から照射後30分までの各パラメータを連続測定し, 照射開始前, 照射7分終了時, 照射終了から30分後の3時点の値を記録した. 結果: 照射により, 同側の第3手指尖表面温と中大脳動脈血流速度は有意に上昇したが, 対側ならびにダミー群との間にはすべてのデータにおいて有意差が認められなかった. 結論: 左側星状神経節近傍への直線偏光近赤外線照射は, 健康成人の手と頭部の体温および血流に影響を及ぼさない.
5 0 0 0 OA 北海道民間説話の研究 (その9) : コロポックル伝説生成資料
- 著者
- 阿部 敏夫
- 出版者
- 北星学園大学
- 雑誌
- 北星学園大学文学部北星論集 (ISSN:0289338X)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.98-74, 2012-03
- 著者
- 赤川 学
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.1, pp.20-37, 2005
「男女共同参画が実現すれば, 出生率は上がる」.これは現在, もっとも優勢な少子化言説である.本稿ではリサーチ・リテラシーの手法に基づいて, これらの言説と統計を批判する.<BR>第1に, OECD加盟国の国際比較によると, 女子労働力率, 子どもへの公的支出と出生率のあいだには, 強い正の相関があるようにみえる.しかしこのサンプルは, しばしばしばしば恣意的に選ばれており, 実際には無相関である.<BR>第2に, JGSS2001の個票データに基づく限り, 夫の家事分担は子ども数を増やすとはいえない.第3に, 共働きで夫の家事分担が多い「男女共同参画」夫婦は, 子どもの数が少なく, 世帯収入が多い.格差原理に基づけば, 彼らを重点的に支援する根拠はない.<BR>第4に, 政府は18歳以下のすべての子どもに, 等しく子ども手当を支給すべきである.それは, 子育てフリーライダー論ではなく, 子どもの生存権に基礎づけられている.現在の公的保育サービスは, 共働きの親を優先している.親のライフスタイルや収入に応じて, 子どもが保育サービスを受ける可能性に不平等が生じるので, 不公平である.もし公的保育サービスがこのような不平等を解決できないなら, 民営化すべきである.<BR>最後に, 子ども手当にかかる財政支出は30歳以上の国民全体で負担しなければならないが, この支出を捻出するには, 3つの選択肢がありうると提案した.その優先順位は, (1) 高齢者の年金削減, (2) 消費税, (3) 所得税, である.この政策により, 現行の子育て支援における選択の自由の不平等は解消され, 年金制度における給付と拠出の世代間不公平は, 大幅に改善される.
5 0 0 0 IR 戦後日本における障害者福祉・職業リハビリテーション法政策小史
- 著者
- 金 蘭九
- 出版者
- 九州看護福祉大学
- 雑誌
- 九州看護福祉大学紀要 = The Journal of Kyushu University of Nursing and Social Welfare (ISSN:13447505)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.13-21, 2020-03
戦後における障害者政策の成立を明らかにし、以降の政策展開を見出していくには、占領初期の障害者政策、具体的に福祉・雇用法政策の動向に関する考察が重要である。ただ、終戦直後、主に1946年から1947年までの障害者政策の時期的動向に特化したアプローチは皆無に等しい。 このような問題意識に基づき、本稿の目的は、戦後、1946年と1947年における障害者政策、とくに福祉・雇用法政策の動向を考察することである。本稿の意義は、当時における障害者福祉・雇用法政策動向の解明に一助となることである。また、本稿の研究内容は、傷痍者対策の出発点、傷痍者保護対策、傷痍者保護対策へ向けた動き、職業安定法の制定と身体障害者職業安定要綱、障害者運動と盲人の針灸存続運動、考察などである。 To clarify the establishment of the postwar disability policy and determine the subsequent policy development, it is important to consider the policy in the early occupation, specifically law policies trends in welfare and employment. However, immediately after the war ended, no approaches primarily focused on the temporal trends of disability policies from 1946 to 1947. Based on this awareness of the problem, this paper aims to consider trends in postwar disability policies, especially law policies about welfare and employment in 1946 and 1947. The significance of this paper is to help elucidate the law policy trends of the welfare and employment for the disabled during that time. Additionally, the research content herein includes the starting point for measures against the injured person, measures for protecting the injured person, movement to protect the injured person, establishment of the employment stabilization law and employment stability summary for the physically disabled, a practitioner in acupuncture, and moxibustion persistence and disability movements, among others.
5 0 0 0 IR ホロコーストとルーマニア(前篇)
- 著者
- 野村 真理
- 出版者
- 金沢大学経済学経営学系 = Faculty of Economics and Management, Kanazawa University
- 雑誌
- 金沢大学経済論集 (ISSN:18840396)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.1-33, 2015-12
- 著者
- 林 隆之 藤垣 裕子
- 出版者
- 研究・イノベーション学会
- 雑誌
- 年次大会講演要旨集 13 (ISSN:24327131)
- 巻号頁・発行日
- pp.45-50, 1998-10-24 (Released:2018-01-21)
- 参考文献数
- 10
5 0 0 0 OA グレンツゲビート
- 著者
- 長谷川 直義
- 出版者
- 耳鼻咽喉科展望会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科展望 (ISSN:03869687)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.6, pp.753-761, 1973-12-15 (Released:2011-08-10)
5 0 0 0 IR 食卓で学ぶ甲殻類のからだのつくり--エビ・カニ・シャコ類の教材化に関する研究
- 著者
- 富川 光 鳥越 兼治
- 出版者
- 広島大学大学院教育学研究科
- 雑誌
- 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 = Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. 2, Arts and science education (ISSN:13465554)
- 巻号頁・発行日
- no.56, pp.17-22, 2007
External morphologies of three major edible crustaceans, prawns, crabs, and squillas, are described and compared. Additionally, an example of summary of observation results is shown. The possible availability of crustaceans in education is discussed.
5 0 0 0 OA マグマの情報をもたらすSO2 放出量—火山ガス測定技術の現在とその課題—
- 著者
- 風早 竜之介
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本火山学会
- 雑誌
- 火山 (ISSN:04534360)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.347-368, 2021-12-31 (Released:2022-02-22)
- 参考文献数
- 92
Volcanic gases are high temperature gases degassed from a magma at depths, emitting to the surface. The volcanic gases give us important clues for understanding of eruptive phenomena as their emissions are closely related to the amount of degassed magma within the volcano. The quantification of the volcanic gases is also important for environmental problems and disaster preventions because they contain toxic species. The main components of the volcanic gases are water, carbon dioxide, and sulfur dioxide (SO2). The SO2 gas has been used as an index of volcanic gas flux because SO2 is readily quantified using remote-sensing techniques based on ultraviolet (UV) spectroscopy and the atmospheric air is SO2 free. In this article, the importance of the SO2 flux and overview of current and future remote-sensing approaches from ground are discoursed. Benefits for practical operations given from the recent developments are highlighted, stressing how these brand-new techniques could be applied to help monitoring of volcanoes.
5 0 0 0 OA 社会科学と火山防災研究
- 著者
- 地引 泰人
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本火山学会
- 雑誌
- 火山 (ISSN:04534360)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.369-374, 2021-12-31 (Released:2022-02-22)
- 参考文献数
- 21
5 0 0 0 OA アメリカ社会進化論で読む『お国の慣習』
- 著者
- 木戸 美幸
- 出版者
- 京都光華女子大学
- 雑誌
- 京都光華女子大学研究紀要 = Research bulletin of Kyoto Koka Women's University (ISSN:13465988)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.55-76, 2008-12
5 0 0 0 OA 大野一雄のダンス教育に関する一考察 ─捜真女学校時代の指導経緯を中心として─
- 著者
- 高橋 和子
- 出版者
- 公益社団法人 日本女子体育連盟
- 雑誌
- 日本女子体育連盟学術研究 (ISSN:18820980)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.1-20, 2011 (Released:2012-03-23)
- 参考文献数
- 47
本研究は,世界最高齢の舞踏家大野一雄が38年間勤務した捜真女学校における「ダンス授業」や「クリスマス行事での聖劇」に着目し,どのようなダンス教育をしたのかを舞踏活動との関連も含めて探ることを目的とする。研究方法として,文献,大野一雄アーカイブ資料,および女学校関係者への半構造化面接法などにより得られた資料を,(1)経歴(教育・舞踊関連年表)の作成,(2)体育教科におけるダンス指導とマスゲーム『美と力』振付の点検評価,(3)聖劇とサンタクロース扮装の点検評価,などの観点から分類整理し,考察を行った。その結果,大野は半世紀以上にわたり捜真女学校に関わり,ダンスや聖劇を通して「形を教え込む」のではなく,「真剣な言葉かけ」によって自己の内面に対峙させ,「自由な表現を引き出した」ことが明らかになった。教育者であり舞踊家であった大野は,謙虚さと奉仕と愛情に満ち溢れた信仰心で子どもや生徒に接し,一連の教育法は世界的に活躍する舞踏家となっても変わることなく,人間の可能性を引き出し生と死のテーマを表現してきたといえる。大野の生き方は創作ダンスや教育の原点にも通じ,ダンス指導法への示唆を得ることができた。
- 著者
- 塚本 博樹 久田 末雄 西部 三省
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.9, pp.4069-4073, 1985-09-25 (Released:2008-03-31)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 41 45
Two biologically active coumarins, scopoletin (1) and isofraxidin (2), along with known coumarins, esculetin (3), fraxetin (4), esculin (5) and fraxin (6), were newly isolated from the bark of Fraxinus japonica BLUME (Oleaceae). On the other hand, the bark of F. mandshurica RUPR. var. japonica MAXIM gave only known coumarins, fraxetin (4), fraxinol (7) and mandshurin (8).