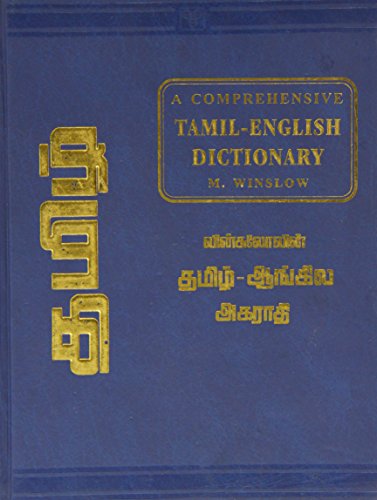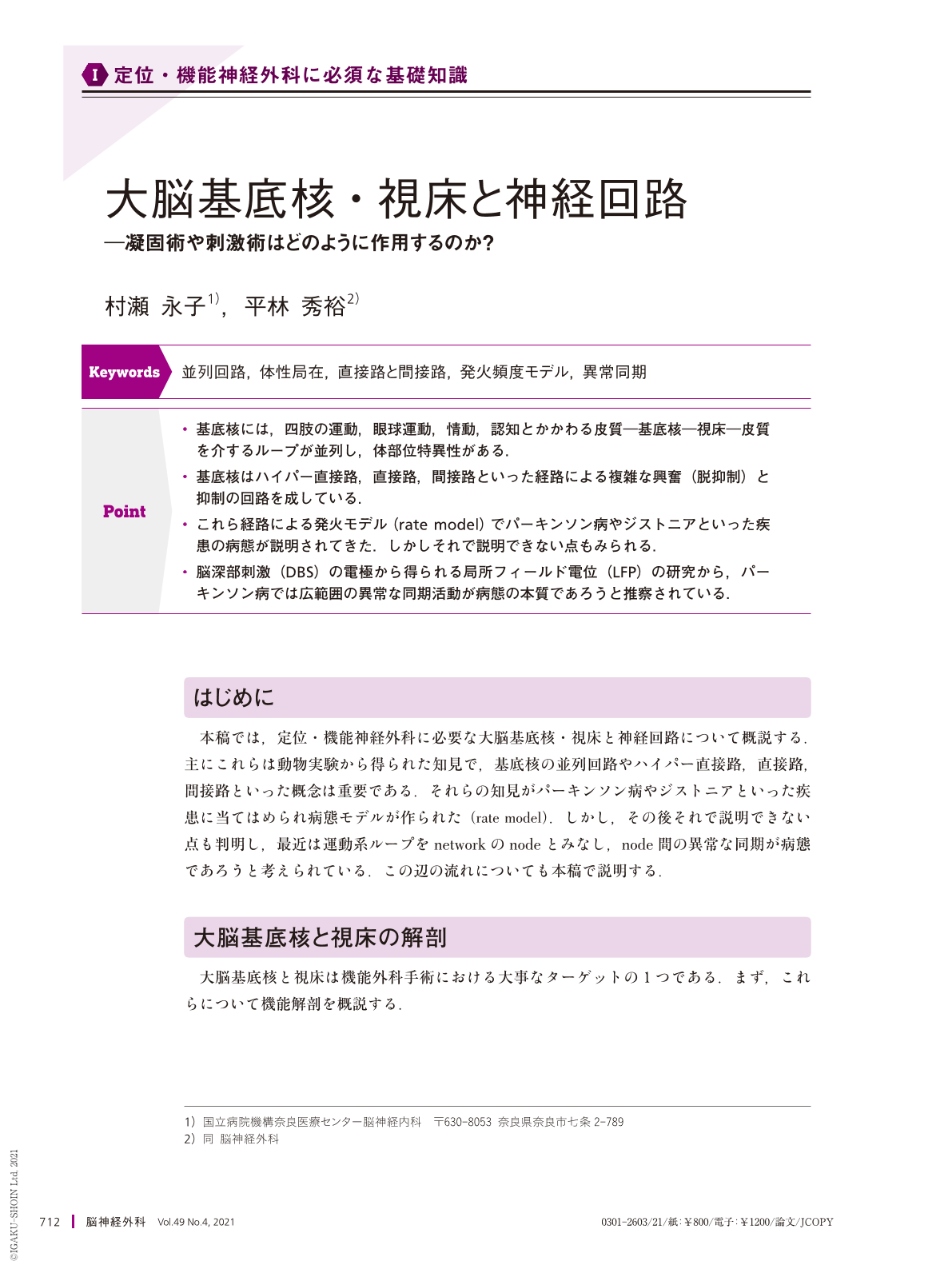- 著者
- M. Winslow
- 出版者
- Asian Educational Services
- 巻号頁・発行日
- 1979
Point・基底核には,四肢の運動,眼球運動,情動,認知とかかわる皮質—基底核—視床—皮質を介するループが並列し,体部位特異性がある.・基底核はハイパー直接路,直接路,間接路といった経路による複雑な興奮(脱抑制)と抑制の回路を成している.・これら経路による発火モデル(rate model)でパーキンソン病やジストニアといった疾患の病態が説明されてきた.しかしそれで説明できない点もみられる.・脳深部刺激(DBS)の電極から得られる局所フィールド電位(LFP)の研究から,パーキンソン病では広範囲の異常な同期活動が病態の本質であろうと推察されている.
5 0 0 0 OA 条件関係と因果関係
- 著者
- 鈴木 延寿
- 出版者
- 科学基礎論学会
- 雑誌
- 科学基礎論研究 (ISSN:00227668)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.53-59, 2002-03-25 (Released:2009-07-23)
- 参考文献数
- 6
5 0 0 0 OA 柔道の礼法における戦中・戦後史
- 著者
- 中嶋 哲也
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, pp.573-590, 2021 (Released:2021-09-01)
- 参考文献数
- 71
The present study aimed to clarify the establishment of Judo etiquette during the wartime and postwar periods. Nakamura (2011) discussed Japanese martial arts etiquette in modern Japan. In his work, however, he dealt largely with Kendo etiquette, and inadequately addressed the history of Judo, as well as overlooking the period of Allied occupation (1945–1952). This article focuses on the reformation of Judo etiquette in that period and clarifies its historical background. It was revealed that, first, the enactment of etiquette in August 1940 was intended to be a criticism of Taro Inaba, who was excommunicated at the Kodokan. Inaba had criticized the Kodokan and the Dai Nippon Butokukwai, stating that when a judoka stands and bows with shizen hontai (natural posture) it reflects disrespect to the emperor. During the war, with the increasing influence of State Shinto, Inaba’s claim could have undermined Judo’s social credibility. Therefore, the Kodokan and Butokukwai abolished shizen hontai and in its place instituted the posture of attention, the basic Shinto posture, and this was also followed by the military and adopted in middle school games; thus, the current system of courtesy was established during this period. Furthermore, the practice of sitting on tatami mats with the left knee and standing up with the right foot was adopted in 1943 to match the postures stipulated in State Shinto. The etiquette established during the war was modified during the Occupation, when bowing to feudal seniors and the kamidana were abolished. In addition, the choice of bowing posture, whether at attention or a natural posture, was left to the practitioners. In this way, it can be said that Judo etiquette was democratized. However, college students’ conduct during Judo bouts was disturbed after the Tokyo Olympics in 1964. Consequently, wartime etiquette was revived. However, the Kodokan did not disclose that its etiquette was influenced by State Shinto and the military. The official line was that the etiquette was based on principles of Judo such as seiryoku-zenyo (maximum use of energy) and jita kyoei (mutual welfare and benefit).
5 0 0 0 OA <追悼文>山口不二雄先生のご逝去を悼む
- 著者
- 中俣 均
- 出版者
- 法政大学地理学会
- 雑誌
- 法政地理 = JOURNAL of THE GEOGRAPHICAL SOCIETY OF HOSEI UNIVERSITY (ISSN:09125728)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, pp.1-6, 2015-03
5 0 0 0 OA 日本統治期の台湾における軒下歩道の利用と管理
- 著者
- 西川 博美 中川 理
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.699, pp.1265-1272, 2014-05-30 (Released:2014-07-15)
This study clarifies how a Din-a-ka (a roofed walkway), a remarkable characteristic of historical city landscaping in Taiwan, led to problems of control and correspondence in their administration. A Din-a-ka was formed in 1900 by the “Taiwan Building Regulation”. It was put in place in the scope of the City improvement project that was carried out throughout Taiwan, starting in 1905. A Din-a-ka had two aspects: while being private property, it was also public space. This is because a Din-a-ka was the walk way connecting the private properties along commercial streets. A Din-a-ka would often lose its function as a walkway, due to the fact that the owners of the occupied the space with goods and empty boxes and their children rode their bicycles along it. In 1918, the Street control regulation was promulgated. By giving the police a legal basis for managing a Din-a-ka, the consolidation of a Din-a-ka gradually continued. In the street control regulation, a Din-a-ka was recognized as private property but was officially given the status of a public walk way.On the other hand, the aligned perspective of a Din-a-ka itself was considered to be a form of beauty. According to this view, the urban beauty of Taiwan was an extension of the Japanese urban beauty campaign.
5 0 0 0 OA A Case of Streptomycin-Induced Pneumonitis
- 著者
- Hisanori Machida Tsutomu Shinohara Yoshio Okano Fumitaka Ogushi
- 出版者
- Japanese Society of Allergology
- 雑誌
- Allergology International (ISSN:13238930)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.259-261, 2013 (Released:2013-06-11)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 2
5 0 0 0 OA トヨタの労使関係の現状と問題点
- 著者
- 猿田 正機
- 雑誌
- 中京経営研究 = CHUKYO KEIEI KENKYU
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.27-44, 2010-03
5 0 0 0 IR ロマン主義絵画と崇高の美学 (美学・西洋美術史特集)
- 著者
- 千足 伸行
- 出版者
- 成城大学
- 雑誌
- 美學美術史論集 (ISSN:09132465)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.111-200, 1980-03
5 0 0 0 OA 抗がん剤による末梢神経障害の治療薬の現状
- 著者
- 江頭 伸昭 川尻 雄大 大石 了三
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.136, no.5, pp.275-279, 2010 (Released:2010-11-10)
- 参考文献数
- 53
- 被引用文献数
- 1
近年,がん化学療法の有用性が高まってきたが,タキサン系抗がん剤であるパクリタキセルや白金系抗がん剤であるオキサリプラチンは,末梢神経障害を高頻度で発現し,身体的苦痛から患者の生活の質(Quality of Life: QOL)を著しく低下させるだけでなく,がん治療の変更や中止を余儀なくさせることから,臨床上大きな問題となっている.無作為化二重盲検臨床試験において,オキサリプラチンの末梢神経障害に対しては,カルシウム/マグネシウム静脈内投与,グルタチオンおよびキサリプロデンの有用性が報告されているが,いろいろな理由により臨床現場ではほとんど用いられておらず,パクリタキセルの末梢神経障害に対しては明らかに有用な効果を示す薬物はない.抗がん剤による末梢神経障害動物モデルでは,パクリタキセルは坐骨神経の変性に伴い機械的アロディニアならびに低温知覚異常を発現する.オキサリプラチンは急性期より低温知覚異常を,その後遅発的に機械的アロディニアを発現するが,前者はオキサレート基で後者は白金を含む部分の化合物で発現される.今後は,末梢神経障害の発現機序を明らかにして,予防策や治療法の確立には発現機序に基づいた取り組みが重要である.
5 0 0 0 OA 労働調査報告
- 著者
- 大阪市社会部調査課 編
- 出版者
- 弘文堂書房
- 巻号頁・発行日
- vol.第28号 (朝鮮人労働者問題), 1924
5 0 0 0 OA 分類をみつめなおす:区分原理に注目して
- 著者
- 緑川 信之
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.6, pp.254-259, 2016-06-01 (Released:2016-06-01)
分類といってもその意味するところは多様である。まず2章で分類の全体像を概観した。3章では,分類の最も基本となる区分原理について,血液型の分類,学問分類,生物分類を例にして考察した。4章では,ネットワーク時代における分類を考えるために,オントロジーを分類体系と比較して検討した。その結果,オントロジーにおいても区分原理が基本であることが明らかとなった。このように,分類においてもオントロジーにおいても最も基本となるのが区分原理であるが,区分原理自体については深く検討されて来なかったように思われる。区分原理に焦点をあてた総合的な研究が期待される。
- 著者
- 篠原 拓也
- 出版者
- 一般社団法人 日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.38-48, 2015-08-31 (Released:2018-07-20)
わが国では児童虐待問題の深刻化に伴い種々の法改正がなされてきた.親子分離の必要性が強く説かれるなか,社会福祉学においても児童福祉の現場実践の規範に関わることであるから,児童相談所の介入に関する法整備のあり方についての議論を進めるべきである.本稿ではConvention on the Rights of the Child (=政府訳「児童の権利に関する条約」)に照らしつつ,児童相談所による親子分離について,子どもの権利への配慮のうえでどのような不備を抱えているのかを指摘した.公権力による親子分離を原則禁止しているArticle 9.1,特にjudicial review(司法審査)の文言について,客観的解釈のほか,主観的解釈・目的論解釈を含めて総合的に検討・考察した.その結果,司法による事前審査の必要性,いっそう厳密な調査の必要性など,児童相談所の権限行使についての一定の抑止力を確保しでおく必要性が指摘できた.
5 0 0 0 OA COVID-19重症肺炎患者1例に対する急性期リハビリテーションの報告
- 著者
- 草野 佑介 上田 将也 宮坂 淳介 南角 学 松田 秀一
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.4, pp.543-546, 2021-08-15 (Released:2021-08-15)
- 参考文献数
- 4
要旨:本症例はCOVID-19重症肺炎に罹患し,長期の気管内挿管,深い鎮静,長期臥床により重篤なICU-Acquired Weakness(ICU-AW)およびADL低下を認めた.我々はCOVID-19リハビリテーションチームを編成し,感染対策および集中的なリハビリテーションを実施したことで,対象者は病前の生活に復帰することができた.本稿の目的は,COVID-19重症肺炎患者1例に対する急性期の作業療法の経験を報告することである.学際的チームアプローチによる作業療法が,集中治療後症候群の重症化を予防し,対象者の日常生活への復帰に貢献したと考えられた.
5 0 0 0 OA 近代日本における, 函数の概念とそれに関連したことがらの受容と普及 (数学史の研究)
- 著者
- 公田 藏
- 出版者
- 京都大学数理解析研究所
- 雑誌
- 数理解析研究所講究録 (ISSN:18802818)
- 巻号頁・発行日
- vol.1787, pp.265-279, 2012-04
5 0 0 0 OA Risk of Transmission of Airborne Infection during Train Commute Based on Mathematical Model
- 著者
- Hiroyuki FURUYA
- 出版者
- The Japanese Society for Hygiene
- 雑誌
- Environmental Health and Preventive Medicine (ISSN:1342078X)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.78-83, 2007 (Released:2007-04-24)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 2
Objective: In metropolitan areas in Japan, train commute is very popular that trains are over-crowded with passengers during rush hour. The purpose of this study is to quantify public health risk related to the inhalation of airborne infectious agents in public vehicles during transportation based on a mathematical model. Methods: The reproduction number for the influenza infection in a train (RA) was estimated using a model based on the Wells-Riley model. To estimate the influence of environmental parameters, the duration of exposure and the number of passengers were varied. If an infected person will not use a mask and all susceptible people will wear a mask, a reduction in the risk of transmission could be expected. Results: The estimated probability distribution of RA had a median of 2.22, and the distribution was fitted to a log-normal distribution with a geometric mean of 2.22 and a geometric standard deviation of 1.53, under the condition that there are 150 passengers, and that 13 ventilation cycles per hour, as required by law, are made. If the exposure time is less than 30 min, the risk may be low. The exposure time can increase the risk linearly. The number of passengers also increases the risk. However, RA is fairly insensitive to the number of passengers. Surgical masks are somewhat effective, whereas High-Efficiency Particulate Air (HEPA) masks are quite effective. Doubling the rate of ventilation reduces RA to almost 1. Conclusions: Because it is not feasible for all passengers to wear a HEPA mask, and improvement in the ventilation seems to be an effective and feasible means of preventing influenza infection in public trains.
5 0 0 0 OA 「終わらない対話」に関する考察
- 著者
- 矢守 克也
- 出版者
- 日本グループ・ダイナミックス学会
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.198-210, 2007 (Released:2007-09-05)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 1 5
本論文は,環境,医療,防災,福祉,土木など多くの分野で,専門家と非専門家(一般の人びと)との間の「対話」が重要視されている現状を踏まえ,新たな対話形態として「終わらない対話」というあり方を提示しようとするものである。まず,「終わらない対話」を実現しようとした具体的な試みとして,矢守・吉川・網代(2005)が開発した「クロスロード」と呼ばれるゲーミング技法について紹介した。次に,歴史的な意味でも論理的な意味でも,「終わらない対話」に先行する対話形式として位置づけることができる「真理へと至る対話」,「合意へと至る対話」の2つに言及し,これら2つの対話形式との異同を通じて「終わらない対話」の性質を明確化した。さらに,「クロスロード」を活用した防災実践活動における対話の特徴をルーマンのリスク論に依拠して考察し,「クロスロード」が「終わらない対話」に結びつく根拠を理論的に示した。最後に,「クロスロード」は,「終わらない対話」のみならず,上述の3つの対話形式をすべて包含した重層的な対話メディアであり,専門家と非専門家との対話には,今後,こうした重層的なメディアやアプローチが不可欠であることを指摘した。
- 著者
- 菊地 茂雄
- 出版者
- 防衛省防衛研究所
- 雑誌
- 安全保障戦略研究 = Security & strategy (ISSN:24357871)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.55-81, 2020-08
- 著者
- 岡本 正志
- 出版者
- 日本物理教育学会
- 雑誌
- 物理教育 (ISSN:03856992)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.4, pp.388-391, 2001
19世紀の英国における心霊研究に多くの一流科学者が関わっていた。心霊現象に対して,懐疑的な立場から積極的に肯定するものまで様々であったが,心霊現象を科学的に研究しようとはしていた。しかし,実際にはトリックによって騙されていた。こうした状況を生み出す背景と個人的特徴とを分析し,今日への示唆や教訓を汲み取ろうとした。