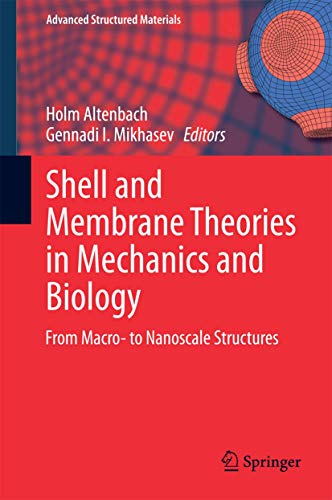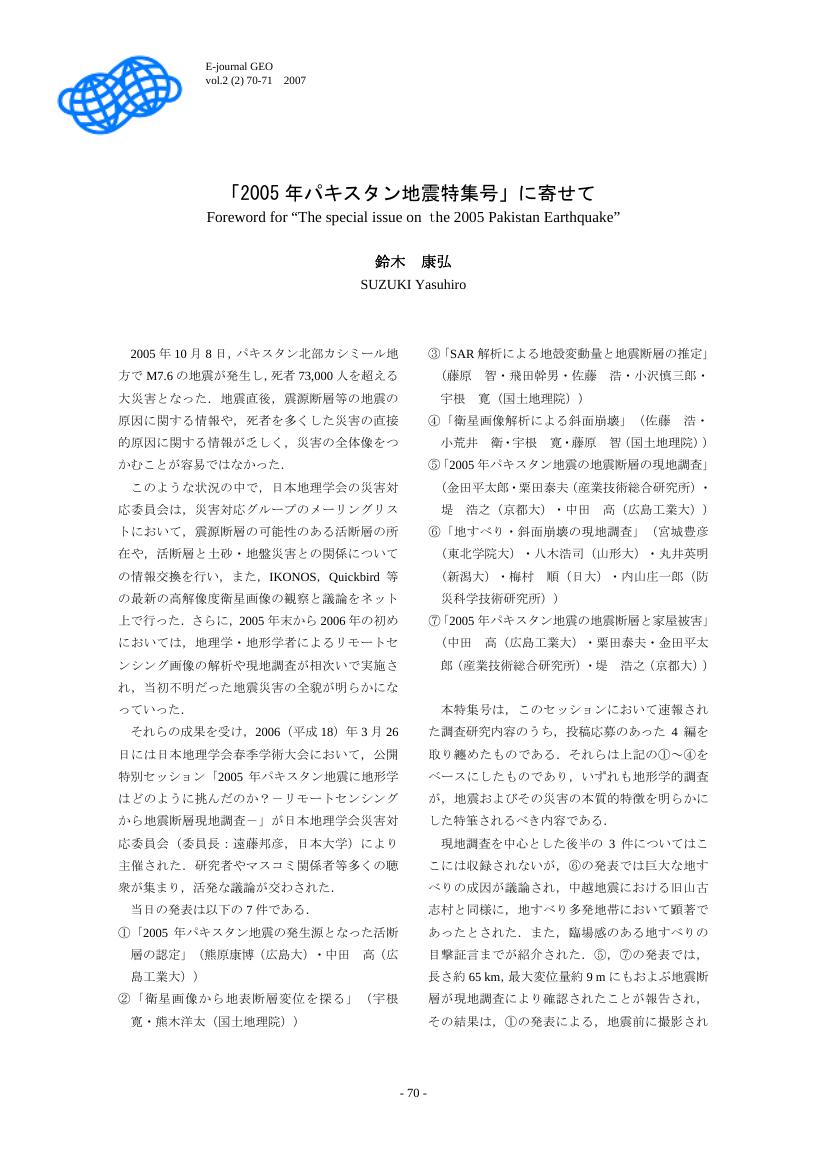1 0 0 0 IR 氷床深層ドリルの開発
- 著者
- 藤井 理行 本山 秀明 成田 英器 新堀 邦夫 東 信彦 田中 洋一 宮原 盛厚 高橋 昭好 渡辺 興亜 Yoshiyuki Fujii Hideaki Motoyama Hideki Narita Kunio Shinbori Nobuhiko Azuma Yoiti Tanaka Moriatsu Miyahara Akiyoshi Takahashi Okitsugu Watanabe
- 雑誌
- 南極資料 = Antarctic Record (ISSN:00857289)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.303-345, 1990-11
南極氷床のドーム頂上での深層コア掘削計画(ドーム計画)の準備の一環として, 1988年から掘削装置の開発を進めている。本報告は, 2年間の基礎開発段階における研究と実験の結果をまとめたもので, 今後の実用機開発段階を前にした深層掘削機開発の中間報告である。掘削方式としては, 消費電力が少なく, 装置の規模が小さいエレクトロメカニカル方式を採用することとし, 効率の良いドリルをめざし, 切削チップの輸送・処理・回収機構, 切削機構, アンチトルク機構, センサー信号処理と掘削制御機構など各部の検討, 実験を進めた。特に, 液封型のメカニカルドリルの最も重要な切削チップの処理機構では, A型からE型までの方式を比較実験し, A型とC型が優れた方式であることが分かった。国内および南極での実験を通じ, ドリル主要機構の諸課題が解決され, 実用機開発にめどが立った。A deep ice coring system, which is to be used a top the Queen Maud Land ice sheet in 1994-1995 with a plan named "Dome Project", has been developed since 1988. A mechanical system was adopted because of its less power consumption and smaller size compared with a thermal system. Experiments were done for mechanisms of ice cutting, chip transportation, chip storage, antitorque, monitoring sensors, and winch control with a 20-m drill experiment tower. Experiments were also done in Antarctica. This is an interim report of the development of the JARE deep ice coring system.
1 0 0 0 OA 古事記 : 新訂要註
- 著者
- Holm Altenbach Gennadi I. Mikhasev editors
- 出版者
- Springer
- 巻号頁・発行日
- 2015
1 0 0 0 OA 2005年パキスタン北部地震による斜面崩壊の分布
- 著者
- 佐藤 浩
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- E-journal GEO (ISSN:18808107)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.104-120, 2007 (Released:2010-06-02)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
パキスタンが実効支配しているカシミール地方で2005年10月8日,パキスタン北部地震(Mw7.6)が発生した.震源近くで撮影された1 m解像度のIKONOSカラー単画像を用いて斜面崩壊を判読したところ,11 km×11 kmの広さで約100箇所の斜面崩壊を認定した.単画像のため,崩壊が斜面横方向に連なる場合,個々の斜面崩壊を認定することは難しかった.さらに,2.5 m解像度の白黒SPOT5ステレオ画像を用いて55 km×51 kmを対象に斜面崩壊を判読したところ,2,424箇所の斜面崩壊を認定した.現地調査によると,ほとんどが岩石の浅層崩壊である.しかし,SPOT5の解像度と白っぽい画質のため,地すべりのタイプの分類や地形学的特徴を詳しく判読できなかった.IKONOS,SPOT5いずれの画像判読の場合も,斜面崩壊は起震断層であるバラコット-ガリ断層の上盤側で多発していた.2,424箇所の斜面崩壊は,断層から1 kmの範囲内にその1/3超が集中していた.1/100万地質図と重ね合わせたところ,最多(1,147個),最高密度(3.2個/km2),最大崩壊面積比(2.3 ha/km2)の斜面崩壊がそれぞれ,中新統の砂岩及びシルト岩,先カンブリア系の片岩と珪岩,暁新統と始新統の石灰岩と頁岩に見出された.2,424箇所のうち,約79 %の1,926箇所は小規模な崩壊(崩壊面積0.5 ha未満),大規模な崩壊(崩壊面積1 ha以上)は約9 %の207箇所だった.大規模斜面崩壊の分布を米航空宇宙局のスペースシャトル搭載レーダー観測(SRTM: Shuttle Radar Topography Mission)による90 m 解像度の数値地形モデル(DEM: Digital Terrain Model)と傾斜データ(SRTM-DEMから計算)に重ね合わせたところ,斜面崩壊は断面的に凸な斜面のほうが凹な斜面よりも,また,35°以上のほうがそれ未満よりも,わずかに多い傾向が見られた.
1 0 0 0 OA 衛星SAR解析による2005年パキスタン北部地震の地殻変動量と地震断層の推定
- 著者
- 藤原 智 飛田 幹男 佐藤 浩 小沢 慎三郎 宇根 寛
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- E-journal GEO (ISSN:18808107)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.95-103, 2007 (Released:2010-06-02)
- 参考文献数
- 8
地震に伴う地殻変動の面的分布を求めることで地震時の地下の断層の位置とその動きを推定することができる.2005年パキスタン北部地震について,人工衛星ENVISATの干渉SARおよびSAR画像のマッチング技術を用いて,地殻変動を面的かつ詳細に求めるとともに,断層モデルを作成した.1m以上の地殻変動は全長約90kmの帯状に北西-南東方向に広がり,最大の地殻変動量は6mを超えている.地震断層推定位置は,既存の活断層に沿ってつながっており,活断層地形で示される変動の向きなどとも一致している.これらのことから,今回の地震は過去に繰り返して発生した地震と同じ場所で発生していることがわかった.地殻変動のパターンから,大まかに見て2つの断層グループが存在する.大きな地震被害が発生したムザファラバード付近は,この2 つの断層グループの境に位置するとともに,最大の地殻変動量が観測された.
1 0 0 0 OA CORONA偵察衛星写真の判読に基づく2005年パキスタン地震の起震断層の認定
- 著者
- 熊原 康博 中田 高
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- E-journal GEO (ISSN:18808107)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.72-85, 2007 (Released:2010-06-02)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1 4
本研究では,2005年10月に発生したパキスタン地震(Mw=7.6)の起震断層を明らかにするため,CORONA偵察衛星写真を用いて断層変位地形の判読をおこなった.その結果,長さ66km,北西―南東走向,右横ずれ変位成分をもつ北東側隆起の逆断層タイプの活断層が認められた.活断層の特徴が地震のメカニズム解と整合すること,断層トレースに沿って地表地震断層が生じていることから,この活断層は本地震の起震断層であると認定される.この活断層をバラコット―ガリ(Balakot-Garhi)断層と呼称する.断層破壊方向と断層トレースの分岐パターンの関係によると,震源付近から両端に向かって断層破壊が伝播したことが推定され,実際の震源過程と調和している.地震前後の衛星画像から地震に伴う斜面崩壊を抽出すると,震源周辺及び断層トレースから上盤側5km以内に斜面崩壊が多いことが明らかになった.
1 0 0 0 OA 「2005年パキスタン地震特集号」に寄せて
- 著者
- 鈴木 康弘
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- E-journal GEO (ISSN:18808107)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.70-71, 2007 (Released:2010-06-02)
1 0 0 0 OA ウェブ検索者の情報要求観点の集約と俯瞰におけるトピックモデルの有効性の評価
- 著者
- 守谷 一朗 今田 貴和 宇津呂 武仁 河田 容英 神門 典子
- 出版者
- 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, 2014
本論文では,検索対象に対して,検索エンジン・サジェストを通して収集され るウェブページの内容を集約・俯瞰するタスクにおいて,収集されるウェブペー ジ集合に対してトピックモデルを適用することにより話題の集約を行った結果 と,従来型の検索結果上位のスニペットとの比較を行い,トピックモデルを用 いた話題集約・俯瞰方式の有効性を評価する.
1 0 0 0 Masonry 2014
- 著者
- editor Michael J. Tate
- 出版者
- ASTM International
- 巻号頁・発行日
- 2014
1 0 0 0 航空機の動態情報を利用する近接検出手法
- 著者
- 福田 豊
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. SANE, 宇宙・航行エレクトロニクス (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.665, pp.35-40, 2003-02-21
- 被引用文献数
- 4
航空機が保持する針路,速度,ロール角等の動態情報を管制システムがデータ通信で取得し,航空機の間隔が管制間隔を満足しない近接状態を予測検出する手法について検討した.2機の航空機が水平面で接近するシミュレーションを実施し,レーダの観測位置のみを利用する方法と観測位置に加えてロール角,速度,選択針路,通過予定ウエイポイント等の航空機の動態情報を利用する方法を比較した.航空機の動態情報を利用する方法は,観測位置のみを利用する方法に比べて,航空機の針路変更時の不要警報と警報の検出遅れの発生を低減できることがわかった.
1 0 0 0 講義中の反応に基づく説明方法と教材の改善
- 著者
- 奥井 善也 原田 史子 高田 秀志 島川 博光
- 出版者
- 情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.361-371, 2009-01-15
- 被引用文献数
- 2
日本の大学では大人数の学生に対して教員1人が講義を行う形式が多くとられている.日本の学生は,大勢の人々がいるまえでは質問しにくいと感じることが多いので,教員に質問できない状況に陥りやすい.よって,教員が講義中に学生の理解度を判断することは難しい.学生と教員の間でコミュニケーションがとりくにいことが教材の改善を困難にしている.そのため日本の大学では教員からの一方向教育となり,これが理解に行き詰まる学生を減らせない1つの原因となっている.本論文では,双方向教育を実現するため,講義中に教え方を修正し講義後に教材を改善するという,2つのフェーズに分けた講義支援を提案する.講義中のフェーズにおいては,教員の説明に対する学生の反応を獲得し,講義中の学生の理解度を学生と教員との間で互いに共有する.講義後のフェーズにおいては,講義中に取得した学生の学習項目別の理解度と学習項目間の依存関係を考慮し,学生の理解困難箇所を特定し教員に提供する.本手法の講義中のフェーズにおける講義支援を大人数講義に適用した結果,適用しないクラスに比べ試験の平均正答率が50点満点中2.22点向上した.また,大学生5人に対し講義を行い,学生に理解に行き詰まった内容に対するアンケートを実施したところ,理解困難に陥る原因は,理解困難に陥ったときに学習していた項目の依存知識と相関することが判明した.In many classes of universities in Japan, a teacher gives a lecture to a lot of students. Japanese students would hesitate to ask questions in front of many people. It is difficult for a teacher to judge the understanding level of each student during a lecture. Therefore, the teacher is not able even to improve his approach to teaching and the teaching materials according to the understanding level of students. This paper proposes a method for teachers to improve teaching faculty. The proposed method consists of two phases. In the first phase, a teacher can acquire students' responses. Students and the teacher share students' understanding levels from the responses during a lecture. The other phase identifies difficult learning items from dependency among learning items. The method identifies difficult learning items from acquired student understanding level during the lecture and the dependency to improve learning materials after the lecture. We applied our method to actual classes which consist of many students during a lecture. The student examination scores in the class to which our method is applied have been superior to that in a class without our method by 2.22 point. A verification experiment has proven that we should consider the dependency among learning items as a possible cause of difficulties to understand learning items.
1 0 0 0 OA ブレード型インプラント
- 著者
- 柳澤 定勝
- 出版者
- 社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会雑誌 (ISSN:03895386)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.6, pp.1335-1342, 1987-12-01 (Released:2010-08-10)
- 参考文献数
- 26
1 0 0 0 OA <報告>看護学生の視覚遮断体験における気づきの検討
- 著者
- 穴井 めぐみ
- 出版者
- 西南女学院大学
- 雑誌
- 西南女学院大学紀要 (ISSN:13426354)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.57-64, 2003-03-29
目的:看護学生の視覚遮断体験の実態を明らかにすることに加えて,その体験からの気づきを検討する。方法:看護学生の視覚遮断体験後の感想文から内容分析を行い抽出された項目の検討を行った。対象:本大学看護学科2年生63名に研究の目的について説明し,研究に使用することに同意が得られた63名の学生の感想文。結果:1.学生は視覚以外の感覚の鋭敏化や時間・空間感覚的体験,不安・緊張感・いらいらの感情などの感覚遮断体験をしていた。2.感覚遮断体験から,食べ物は視覚によっても味わっていること,空間的感覚の喪失は危険予知力の低下につながることに気づいていた。3.感覚遮断体験から,介助者の非言語的・言語的コミュニケーションに安心感を見出していた。
1 0 0 0 OA [駒場]2001
- 著者
- 東京大学大学院総合文化研究科 東京大学教養学部 教育・研究評価委員会 駒場2001編集小委員会
- 出版者
- 東京大学大学院総合文化研究科
- 雑誌
- [駒場]
- 巻号頁・発行日
- vol.2001, 2002-03-31
(表紙から目次)
1 0 0 0 OA 伊沢修二における「国楽」と洋楽 : 明治日本における洋楽受容の論理
- 著者
- 竹中亨 タケナカトオル TAKENAKATORU
- 出版者
- 大阪大学大学院文学研究科
- 雑誌
- 大阪大学大学院文学研究科紀要 (ISSN:13453548)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.1-27, 2000-03-15
- 著者
- 杉本 正毅
- 出版者
- 遠見書房
- 雑誌
- N:ナラティヴとケア (ISSN:18846343)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.11-20, 2010-01
- 著者
- 宮内 宏 尾花 賢 森 健吾
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会誌 (ISSN:09135693)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.5, pp.331-336, 2003-05-01
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 2
2002年に電子投票法が施行になり,地方自治体の選挙の電子化が可能になった.電子投票の進展については,第一段階(指定された投票所にて電子投票機での投票),第二段階(任意の投票所での投票),第三段階(自宅等のコンピュータからの投票)が考えられている.電子投票では,有権者認証,無記名性確保,正当性検証の3要件を満たす必要がある.これらの要件を満たすための実現方法や情報セキュリティ技術を上記3段階に対応して述べる.特に第二,第三段階を実現するミックスネット方式について詳しく説明する.
- 著者
- 兒玉 隆之 中林 紘二
- 出版者
- JAPANESE PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION
- 雑誌
- 日本理学療法学術大会
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, pp.A3O1045-A3O1045, 2010
【目的】脳内神経活動に伴う局所脳血液供給量の増加が報告(Roy, 1890)されて以来、さまざまな脳機能イメージングを用いた脳機能評価が報告されてきた。中でも、近赤外線分光法(Near infrared spectroscopy; NIRS)は、局在神経活動と相関する毛細血管の血行動態変化を反映することが示唆されており(Yamamoto, 2002)、脳機能評価には非常に有用である。しかし、原理的に空間分解能が低く、脳深部を含めて脳機能の局在を細かく決定することには困難を要する。そこで本研究では、表情のもつ情動刺激による課題を用いて、精神生理学的指標である事象関連電位(ERPs)P300成分の脳波・脳磁場解析プログラムLORETA(Low Resolution Brain Electromagnetic Tomography)による神経活動源推定と、NIRSによる脳血流量(Oxy-Hb)変動の同時測定を行い、時間的空間的解析による詳細な脳機能評価を試みる。<BR>【方法】対象は、健常ペイドボランティア20名(男性9名、女性11名、平均年齢27.5±4.1歳)。測定デザインはブロックデザインを用い、Taskを4回(Rest5回)施行した。Task時の課題には、情動的作用を有するヒトの「泣き顔」および「笑い顔」を標的刺激(出現率30%)、「中性」表情(出現率70%)をコントロールとした視覚オッドボール課題を用いた。測定方法は、脳波電極を国際10-20法に基づき、average referenceによりFp1・Fp2・F7・F3・Fz・F4・F8・T3・C3・Cz・C4・T4・T5・P3・Pz・P4・T6・O1・O2・Ozの部位へ装着、NIRS(日立メディコ社製, ETG-4000)も同法に基づきT3T4を端点とした3×5のプローブ(左右44チャンネル)を装着し、神経活動電位測定とOxy-Hb測定を同時に記録測定した。得られたERPsデータをもとに、Microstate segmentationによるP300成分出現時間域を算出後、LORETAによる課題施行時の脳神経活動解析を行い、Task時のOxy-Hb変動をNIRSにより検討した。<BR>【説明と同意】総ての被験者に、測定前に研究内容を説明し書面にて同意を得た。尚、本研究は久留米大学倫理委員会の承認を得て行った。<BR>【結果】Microstate segmentationの結果から、P300出現時間域は、「泣き顔」刺激課題時361~476ms、「笑い顔」刺激課題時367~482msとなり、LORETA解析では、「中性」、「笑い顔」に比べ「泣き顔」の刺激課題時に扁桃核、前頭前野で有意に高い神経活動を認めた(p<0.05)。さらに、NIRSにおいても、「笑い顔」より「泣き顔」の刺激課題時に前頭前野におけるOxy-Hbの増加を認めた。<BR>【考察】本研究は、脳機能を詳細に評価するため、LORETA解析による神経活動についての時間的空間的分解能と、NIRSによる脳血流動態の同時測定を行った。結果、前頭前野が担う認知機能は表情のもつ情動的作用の影響を受けることが強く示唆された。また、NIRSが脳神経系の電気的興奮過程を反映したものであることが明らかとなり、脳機能評価としてのマルチモーダルモニタリングとして有用であることが示唆された。<BR>【理学療法学研究としての意義】脳機能評価において、非侵襲的脳機能計測法であるLORETA解析とNIRSの同時測定は、詳細な時間的空間的解析の一助として理学療法学研究において有用であると考える。
1 0 0 0 コミュニティ力と治癒力 (私の実践とナラティヴ(第1回))
- 著者
- 佐藤 元美
- 出版者
- 遠見書房
- 雑誌
- N:ナラティヴとケア (ISSN:18846343)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.71-75, 2010-01