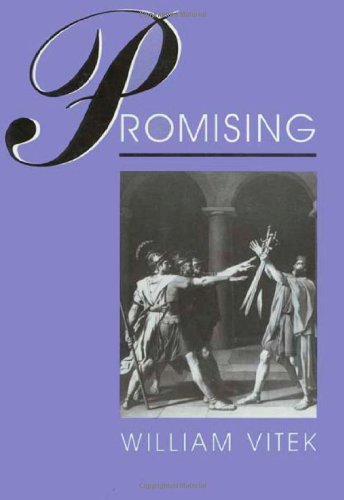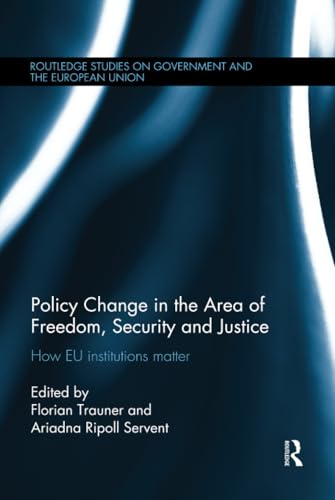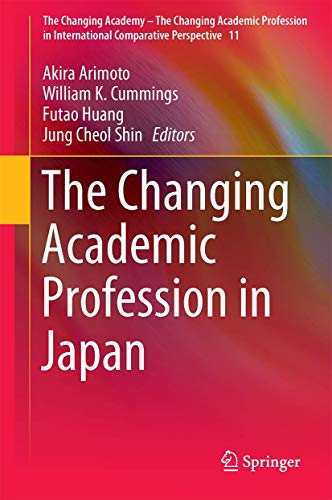1 0 0 0 OA グリルパルツァー作«ザフォー»におけるザフォーの悲劇について
- 著者
- 堀 勇夫
- 出版者
- JAPANISCHE GESELLSCHAFT FUER GERMANISTIK
- 雑誌
- ドイツ文学 (ISSN:03872831)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.89-96, 1960-11-05 (Released:2008-03-28)
Sapphos Tragik erklärt Benno von Wiese wie folgt: "das Vernichtende für Sappho liegt nicht nur darin, daß ihre Liebe verschmäht und ihre Person falsch bewertet wird, sondern daß in ihrem Innern Gefahren ausgelöst werden, die sie nicht mehr bannen kann. Sappho, die sich der Kunst entfremdete um des Lebens willen, hat sich zu tief mit ihm eingelassen, um jetzt nicht seine brutale Nähe als verwundend und schmerzhaft zu empfinden...... Sie stirbt, weil sie rich nur so vor dem verletzenden, qualvollen Zugriff des Lebens zu schützen vermag……“.Manche Kritiker sind derselben Meinung. Und Sappho scheint selbst mit ihren letzten Worten zu dieser Auslegung zu verhelfen.Nachdem ihre Liebe verschmäht war, verstrickte sich Sappho gewiß in die Affekte der Leidenschaft, der Eifersucht und der Rache; aus ihr wurde eine eifersüchtige Furie. Und sie mußte vor sich selbst Furcht haben. Was sie doch in Wirklichkeit zur Verzweiflung trieb, war etwas anders als dies: es war ihre noch schmerzhaftere Selbsterkennung, daß sie nicht als eine Frau, sondern nur als die Göttin der Dichtkunst für Männer reizend war, und aus dem menschlichen Liebesgenuß ausgeschlossen war. Außerdem erkannte sie, daß die Göttin der Dichtkunst in der Menschenwelt nichts anders als ein Idol war.Deshalb entschloß sie sich, wenn sie in der Welt nur ein Idol sein und bleiben müsse, so nchme sie von der Welt als ein Idol Abschied. So führte sie zum letzten Abschied eine Szene auf: "Ein Idol kehrt zu den Göttern züruck!“. In dieser Vorstellung war ihr Tod allerdings eine wirkliche Tatsache, "Zu den Göttern zurückkehren“ aber blieb bedauernswert nur ein Schauspiel. Diese klägliche Sachlage symbolisiert das tragische Schicksal einer Dichterin, die weder eine Frau noch eine Göttin werden konnte.
1 0 0 0 IR 女医の三冠と三関門 (トピックス 女医問題II)
- 著者
- 森 美也子
- 出版者
- 神緑会
- 雑誌
- 神戸大学医学部神緑会学術誌 (ISSN:09149120)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.97-98, 2000-08
1 0 0 0 OA 「共通価値の創造(CSV)」を軸とした水ビジネスの将来的展望
1 0 0 0 Promising
- 著者
- William Vitek
- 出版者
- Temple University Press
- 巻号頁・発行日
- 1993
1 0 0 0 OA 「地理」と防災教育
- 著者
- 熊木 洋太
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集 2010年度日本地理学会春季学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.1, 2010 (Released:2010-06-10)
地理学は現実社会のさまざまな問題の解決に役立つ学問である。特に災害の研究は,地理学が社会に直接貢献できる分野である。このような観点から,日本地理学会災害対応委員会では,2003年の春季学術大会以来,これまで8回の公開シンポジウムを開催してきた。これらのシンポジウムでは,専門研究者の立場からの発表が中心であったが,自然災害を防止したりその被害を軽減させたりするには教育の役割が大きいということがくり返し言われてきた。 すなわち,自然災害が多発するわが国において,国民の「防災力」を高めるには国民の間に自然災害に関する的確な知識が共有されていることが必要であり,このためには,初等・中等教育の段階から自然災害について学ぶ防災教育が重要であるということである。自然災害は自然現象であると同時に,その地域の社会構造とも密接に関係するので,土地の自然的性質や,土地利用,地域の空間構造などを取り上げ,地域の自然と社会を総合的に扱う「地理」は,災害の学習に最も適した科目・分野であると思われる。2004年12月のスマトラ沖地震津波の際には,プーケット島に滞在中のイギリス人少女が「地理」の時間に習った津波の来襲だと周囲に告げたため,多くの人が助かったと報道された。近年ハザードマップの重要性が指摘されることが多いが,これはまさに災害の地理的表現にほかならない。災害を引き起こす自然現象について学ぶ分野として,高等学校では「地学」もあるが,それを履修する生徒がきわめて少数である現実を考えると,「地理」の果たす役割は大きい。 日本学術会議は2007年の答申「地球規模の自然災害の増大に対する安全・安心社会の構築」において,学校教育における地理,地学等のカリキュラム内容の見直しを含めて防災基礎教育の充実を図ることを提言している。また同年の地域研究委員会人分・経済地理と地理教育(地理教育を含む)分科会・地域研究委員会人類学分科会の対外報告「現代的課題を切り拓く地理教育」では,地域防災力を高め安心・安全な地域作りに参画できる人材の育成と,そのために必要な自然環境と災害に関する地理教育の内容の充実を提言している。これらを踏まえ,2009年8月に活動を開始した地域研究委員会・地球惑星科学委員会合同地理教育分科会では,12月に下部組織として環境・防災教育小委員会を発足させ,地理教育における防災教育のあり方について検討を始めた。 初等・中等教育に関しては,学習指導要領の改訂が行われたところであり,新学習指導要領は小学校が2011年度,中学校が2012年度,高等学校が2013年度から完全実施される。地理に関しては全体的に地図の活用が強調されている等の特徴があるが,高等学校「地理A」において,「我が国の自然環境の特色と自然災害とのかかわりについて理解させるとともに,国内にみられる自然災害の事例を取り上げ,地域性を踏まえた対応が大切であることなどについて考察させる」という記述が新たに加わったことが注目される。 このシンポジウム「『地理』で学ぶ防災」は,以上の状況を踏まえ,日本地理学会の災害対応委員会と地理教育専門委員会によって計画され,日本学術会議との共催で実施される。小学校,中学校,高等学校,大学の各段階での実践例に基づく発表を軸として,地理学・地理教育の立場から学校教育の中での防災教育のありかたや方法を取り上げて検討する。
- 著者
- edited by Florian Trauner and Ariadna Ripoll Servent
- 出版者
- Routledge
- 巻号頁・発行日
- 2015
- 著者
- 葛西 映吏子 Eriko Kasai
- 雑誌
- 関西学院大学先端社会研究所紀要 = Annual review of the institute for advanced social research (ISSN:18837042)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.55-71, 2012-10-31
- 著者
- Akira Arimoto ... [et al.] editors
- 出版者
- Springer
- 巻号頁・発行日
- 2015
- 著者
- 丸尾 はるみ 橋本 景子 下田 恵子 島貫 金男 中山 徹 山口 博明 椎貝 典子 内村 公昭 三ツ林 隆志 赤坂 徹 前田 和一 岡田 文寿 鈴木 五男
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.7, pp.621-630, 1990
- 被引用文献数
- 7
1988年, 小児気管支喘息の長期予後と予後に影響する因子を明らかにするため, 1,592名(男1,038, 女554)を対象としてアンケート調査を行った.調査時の年齢は平均20歳(観察期間は平均12年)であり, 長期予後は緩解が75.6%, 軽快が18.2%, 不変が4.0%, 悪化が0.9%, 死亡が1.3%であった.発症年齢は平均2.7歳であり, 20年前の報告と比べて約1歳低年齢化していた.治癒年齢は男子が平均13.0歳, 女子が12.3歳であった.発症年齢が2歳以下, 発症から初診までの期間が10年以上, 初診時の重症例, 入院歴のある者, 食物アレルギーの有る者の緩解率は不良であった.食物アレルギーが有る者は喘息発症年齢が約1歳低く, 初診時の重症例, 乳児期湿疹のある例, 喘息以外のアレルギー疾患を2つ以上合併している例が多かった.このような乳児喘息例を難治性喘息のハイリスク児としてとらえ、綿密な指導と経過観察が必要であると考えられた.
1 0 0 0 OA アメノウズメの<神がかり>・<わざをき> : 天岩戸と天孫降臨
- 著者
- 吉田 修作
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.1-10, 2011-02-10
天岩戸と天孫降臨神話に記述されたアメノウズメの所作である<神がかり>、<わざをき>に焦点を当てると、天岩戸でのウズメの所作は書紀の<神がかり>の表記やアマテラスとの問答などから、ことばによる<神がかり>が内包されており、天孫降臨のウズメの所作はサルタヒコの「神名顕し」を促し、天岩戸でのアマテラスの「神顕し」と対応する。ウズメの所作は天岩戸では一方で<わざをき>とも記されているが、<わざをき>は本質的には制度化されない混沌性を抱え込んでおり、それが<神がかり>と通じる点である。
- 著者
- 永藤 靖
- 出版者
- 至文堂
- 雑誌
- 国文学解釈と鑑賞 (ISSN:03869911)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.12, pp.21-28, 2004-12
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 高桑 枝実子
- 出版者
- 至文堂
- 雑誌
- 国文学 (ISSN:03869911)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.12, pp.49-56, 2006-12
1 0 0 0 夏季のガラス温室における室内気温低下への細霧冷房の効果
- 著者
- 片岡 圭子 小西 剛 西川 浩次
- 出版者
- 京都大学農学部附属農場
- 雑誌
- 京大農場報告 (ISSN:09150838)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.7-12, 2001-03
- 被引用文献数
- 2
大阪府高槻市古曽部町のシクラメンを栽培中のガラス温室(約93.8m2)に細霧冷房装置を導入し,夏季の冷房効果について検討した.温室内は二重遮光を行い,ノズル数は29個,5分間おきに1分間噴霧,3分間おき1分間噴霧および無噴霧の処理を設けた.2000年8月5日から8月17日の期間において,外気温および室内気温を30秒間隔で測定し,午前10時から午後4時までの間の平均気温を比較したところ,外気温よりも,5分間おき1分間噴霧で約2℃,3分間おき1分間噴霧で約3℃の室内気温の低下が認められた.無噴霧では外気温との差はほとんど認められなかった.7月14日から8月31日の期間について,細霧冷房を導入した2000年と細霧冷房未導入であった前年(1999年)との平均気温を比較したところ,約0.8℃の冷房効果が認められた.シクラメンの生育は前年までよりも良好で,出荷期の前進が認められた.病虫害の増加は認められなかった.
1 0 0 0 焼酎白麹の各種酵素生産に及ぼす製麹条件の影響
- 著者
- 岩野 君夫 三上 重明 福田 清治 能勢 晶 椎木 敏
- 出版者
- Brewing Society of Japan
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.3, pp.200-204, 1987
- 被引用文献数
- 6
焼酎白麹の各種酵素生産に及ぼす製麹条件の影響について検討し次の結果を得た。<BR>1.白麹菌は40℃においてAAase, GAase, TGaseおよびRSDの生産が大であり, 酸の生産は30℃, 35℃で大であった。APaseとACPaseの生産は製麹温度の影響が少なかった。<BR>2.白麹菌は精米歩合が90%以上の白米で酵素生産が大であり, 精米歩合が85%以下になると急激に酵素生産が低下する。特にAAase, GAase, ACPaseおよびTGaseでこの傾向が大であった。<BR>3.白麹菌の酵素生産に及ぼす吸水率の影響は製麹原料が破砕精米とコーン・グリッツでは少なく, 麦類では大きく, 吸水率が40-50%と高いほど酵素生産が大であり, 酸の生産も大きかった。<BR>4.白麹菌の酵素生産は菌体量と極めて高い正の相関関係が認められた。<BR>5.米焼酎仕込みにおける麹歩合を酵素活性の面から検討し, 白米1g当りAAaseが約20単位, GAaseが約33単位ほどが必要酵素量でないかと推論した。<BR>最後に臨み, 本研究の遂行に当り御指導を賜わりました当試験所中村欽一所長に深謝致します。
1 0 0 0 OA 2)炎症性腸疾患と発癌
- 著者
- 渡辺 守 土屋 輝一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, no.9, pp.2152-2156, 2009 (Released:2012-08-02)
- 参考文献数
- 12
1 0 0 0 IR マカオ・メキシコから見た華夷変態
- 著者
- 中砂 明徳
- 出版者
- 京都大學大學院文學研究科・文學部
- 雑誌
- 京都大學文學部研究紀要 = Memoirs of the Faculty of Letters, Kyoto University (ISSN:04529774)
- 巻号頁・発行日
- no.52, pp.95-194, 2013-03
1 0 0 0 OA 一七世紀徳川外交の研究
1 0 0 0 ホイップクリームの物理化学的特性ならびに嗜好特性
- 著者
- 菊地 和美 鮫島 邦彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.35-40, 2004
本研究は,ホイップクリームの物理化学的特性及び嗜好特性を明らかにすることを目的として実施した. 1.色調のうち,乳脂肪クリームは植物性よりもC*値(彩度)や黄色を示すb値が高く,糖類添加によってL値(明度)の減少とC値の増加が観察された. 離水量は植物性クリームの方が少なかった. 2.貯蔵弾性率では,5~20℃ 付近の周波数グラフが平坦部を示し,35℃ 以上になると低周波数での応答が認められなかった. 3.DSC測定結果では,糖類添加クリームの吸熱エンタルピーが大きくなって温度に対する安定性がみられ,この傾向は糖類の種類によっても同様であった. 4.官能検査により,好まれているホイップクリームはグラニュー糖20%添加,グラニュー糖10%添加,無糖という順であった. 5.因子分析により,グラニュー糖を添加したホイップクリームが総合評価で好まれており,原料別にホイップクリームを比較すると植物性クリームでは色や形という外観に特徴がみられ,乳脂肪クリームでは味や濃厚さという味に特徴がみられた. 本研究は,日本調理科学会平成14年度大会において口頭発表したものである. 謝辞 ホイップクリームの物性測定にあたり,ご指導賜りました酪農学園大学食品科学科食品物性学研究室中村邦男先生ならびに同研究室の皆様に感謝申し上げます. 多変量解析の因子分析ならびに分散分析にっいて,ご指導賜りました東海学園大学山口蒼生子先生にお礼申し上げます.
- 著者
- 黒木 晶子
- 出版者
- 広島文教女子大学国文学会
- 雑誌
- 文教国文学 (ISSN:02863065)
- 巻号頁・発行日
- no.46, pp.106-90, 2002
1 0 0 0 目的論的機能主義に基づく心の自然化
心は環境に対する主体の適応を促進するための装置であるという目的論的機能主義の立場から、心の自然化を試みた。とくに志向性と意識の自然化をめぐる諸問題の解決を目指した。その結果、以下のような成果が得られた。1.信念や欲求のような命題的態度とよばれる心的状態は構文論的構造をもち、論理的な推論に従う点に特色がある。しかし、コネクショニズムによれば、脳状態はそのような構文論的構造をもたず、力学的なパターン変換に従う。このことから、命題的態度は個別に脳状態に対応せず、たかだか全体論的に対応するにすぎないことが言える。ただし、意識的な命題的態度に関しては、発話ないし脳の運動中枢の興奮パターンとして個別的に実現されていると考えられる。2.命題的態度は合理性に従うことをその本質とする。そして合理性は一群の規則として体系化できないという意味で非法則的である。従って、命題的態度の目的論的機能は非法則的な合理的機能ということになる。このことから、行為の理由となる信念と欲求は必ずしもその行為の原因とは言えないという、行為の反因果説を支持する論拠が得られる。しかし、このような反因果説につながる非法則的な合理的機能はコネクショニズム的なメカニズムによって実現可能であり、けっして自然化不可能な機能ではない。3.知覚や感覚のような意識的な心的状態はそれに特有の感覚的な質を備えているが、この感覚質は意識的な心的状態の内在的な性質ではなく、その志向的内容に属する性質であると考えられる。このことから、痛みの経験のようなふつう非志向的と解される心的状態も実は志向的であり、痛いという性質は身体の客観的な性質であると考え直す必要が出てくるが、そのような再解釈は十分可能である。