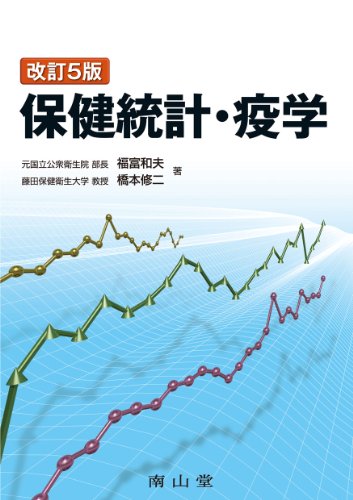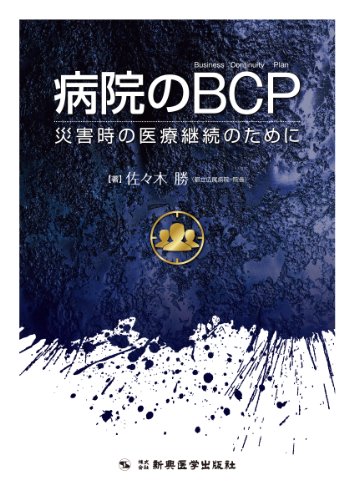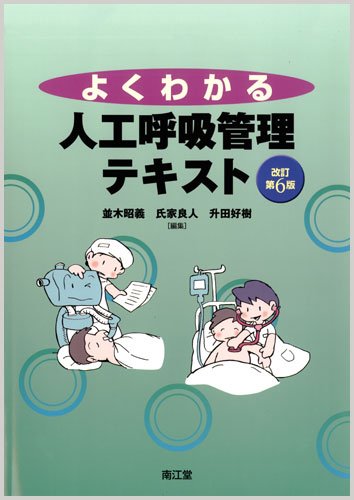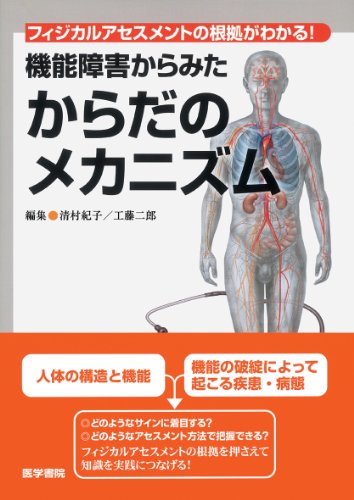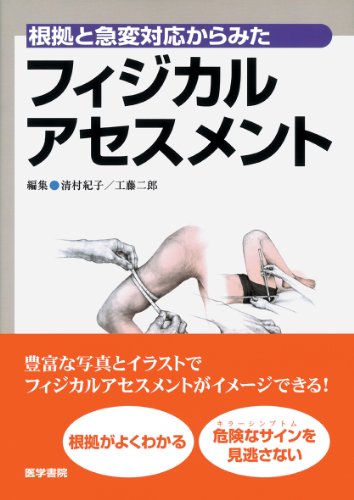1 0 0 0 保健統計・疫学
- 著者
- 福富和夫 橋本修二著
- 出版者
- 南山堂
- 巻号頁・発行日
- 2014
1 0 0 0 病院のBCP : 災害時の医療継続のために
1 0 0 0 よくわかる人工呼吸管理テキスト
- 著者
- 並木昭義 氏家良人 升田好樹編集
- 出版者
- 南江堂
- 巻号頁・発行日
- 2014
- 著者
- 清村紀子 工藤二郎編集
- 出版者
- 医学書院
- 巻号頁・発行日
- 2014
1 0 0 0 根拠と急変対応からみたフィジカルアセスメント
- 著者
- 清村紀子 工藤二郎編集
- 出版者
- 医学書院
- 巻号頁・発行日
- 2014
1 0 0 0 OA 視覚障害者のための自律移動型歩行補助システムの開発
1 0 0 0 思い出表現を構成するもの
私たちは「思い出を記録するワークショップ」を2006年から行っている。ここでの表現には「写真」と「語り」が使われている。本稿では開発した「Zuzie」を使用したミニワークショップを行った。そこでの「語り」は次の4種類あった。1語りたい語り、2写ってない語り、3見てない語り、4本当かどうかわからない語り。「思い出を記録するワークショップ」では、参加者は、表現方法についてはすぐに話し合えるが、個人の思い出に関して語るには時間がかかる。このミニワークショップでは、一つの写真に対して、いくつもの視点からみることによって、いくつもの「語り」を行うことができた。このことが、表現の共同体を構成するための重要な要素となると言える。
1 0 0 0 OA iPS細胞を用いた小児神経伝達物質病モデルの創出
小児神経伝達物質病は、シナップスでの神経伝達物質の異常によって起こる遺伝性疾患群である。当教室が中心として行ってきた全国疫学調査により、臨床症状および臨床検査所見が明らかとなってきた。従来の血液検査、髄液検査等では、神経症状の病態を説明できない症例も存在している。また、個々に希少疾患であるため、体系的な治療法の開発手段は存在しない。今回、小児神経伝達物質病患者由来iPS細胞を樹立し、神経系細胞へ分化することで、細胞レベルでの病態の解明を目指すた。患者由来iPS細胞からの神経分化誘導を行い、細胞レベルでの機能解析、増殖能、神経突起をリアルタイムで解析し病態を解明する系を確立できた。
1 0 0 0 障害児放課後活動グループにおける学校との情報交換の実態と課題
- 著者
- 奥住 秀之 端山 花子 村岡 真治
- 出版者
- 東京学芸大学
- 雑誌
- 東京学芸大学紀要. 総合教育科学系 (ISSN:18804306)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.1, pp.231-236, 2010-02
1 0 0 0 仏説摩訶酒仏妙楽経謹解
- 著者
- 石井 公成
- 出版者
- 駒沢大学仏教文学研究所
- 雑誌
- 駒沢大学仏教文学研究 (ISSN:13440888)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.37-88, 2009-03
1 0 0 0 IR 仏説摩訶酒仏妙楽経謹解
- 著者
- 石井 公成
- 出版者
- 駒澤大学仏教文学研究所
- 雑誌
- 駒沢大学仏教文学研究 (ISSN:13440888)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.37-88, 2009-03
1 0 0 0 OA スタンダールの死後出版作品集における異文研究
本研究は,フランスの作家スタンダールの死後,その従弟で遺言執行人のロマン・コロンが出版したエッツェル版『パルムの僧院』,ミシェル・レヴィ版『アルマンス』と『カストロの尼』のテクストとそれぞれの初版の本文とを照合してヴァリアントの有無を精査し,『パルムの僧院』についてはエッツェル版に含まれる異文が,1842年2月26日に作家が行った修正を採録したものであることを,書簡,備忘,同小説の作家の手沢本などの網羅的調査をつうじて解明し,その成果を日本スタンダール研究会,フランスの国際スタンダール研究誌等で発表した。
1 0 0 0 湊さんの「グリン・タフ地域の問題」を讀んで その1
- 著者
- 牛来 正夫
- 出版者
- 地学団体研究会
- 雑誌
- 地球科學 (ISSN:03666611)
- 巻号頁・発行日
- no.11, pp.29-30, 1953-03-10
- 出版者
- 新潮社
- 雑誌
- 週刊新潮 (ISSN:04887484)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.48, 2009-12-17
- 著者
- 渡邉 千恵子
- 出版者
- 至文堂
- 雑誌
- 国文学 (ISSN:03869911)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.6, pp.155-162, 2007-06
1 0 0 0 OA バガヴァティー・アーラーダナーの新校訂本作成と全訳によるジャイナ教の断食死研究
1 0 0 0 IR 家事サ-ビスの利用要因に関する構造的分析-1-基本的属性を視点として
- 著者
- 壁谷沢 万里子 長沢 由喜子 KABEYASAWA Mariko NAGASAWA Yukiko
- 出版者
- 日本家政学会
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.11, pp.p1141-1153, 1988-11
The purpose of this study is to grasp the actual conditions of the use of domestic services, to discover the use-factors, and to clarify the use-structure. Part 1 is a report on the factors which were extracted from the analysis of housewives in their use-tendency according to age, family type, occupation, and education. The results obtained were as follows : 1) Especially in the services relative to food, the controlling factors of use were at work in the older group. 2) The promoting factors of use which worked on the younger group were their tendency to convenience and evaluation of quality. 3) The peculiarities of use-tendency in the single or couple family type were recognized. 4) In the services relative to clothing, the tendency of those working full-time was remarkable. Evaluation of quality in these worked as the promoting factors of use and caused the use-fixation. 5) The economic condition of lower educated group worked as the controlling factor of use. 基本的属性との関連において家事サービスの利用傾向について分析を行った結果, 利用促進および利用抑制要因に関して得られた考察の要約は次のとおりである. 1) 食品関連項目のなかで, とくに新たな加工形態の食品 (冷凍食品・レトルト食品・半調理品など) は51歳以上の高年齢群に利用抑制が強くはたらく事実が確認された. 2) 高年齢群の利用拒否の根強さは, 利用動機からもうかがえ, 家事に対する保守性・利用に対するうしろめたさ・加齢に伴う食嗜好の変化などが抑制要因としてはたらくことによると推察される. 3) 若年齢群の利用促進要因としては, 第1に利便性志向が指摘され, 第2に他年齢群に比較して質評価が高いことがあげられ, とくに家族との外食において顕著である. 4) 高年齢群の単独・夫婦のみ世帯において, 家族人数・経済性・手軽さ・夫の好みなどの点により, 外食より出前を志向する傾向が認められた. 5) 核家族において, 家族との外食に利用促進要因が働く事実が確認され, 雰囲気としての楽しみを求める, 新たな価値意識に基づく質評価が利用定着を誘因している. 6) 勤務者の利用が衣生活関連サービスにおいてきわ立ち, 専業主婦でも質評価をしている場合には利用が高まる傾向が認められたことより, 質評価が時間的拘束度をしのいで利用促進要因として働くことが明らかとなった. 7) 質評価が高い場合には今後の利用意向が高く, 質家事サービスの利用要因に関する構造的分析 (第1報) 評価と利用定着との結びつきが確認され, とりわけこの傾向は高学歴群において顕著である. 8) 低学歴群における経済性が, 家族との外食およびセータークリーニングにおいて利用抑制要因として働くことが認められた. 以上「利用」および「非利用」に分けて利用傾向を検討することにより, 利用傾向の特異性をより鮮明にとらえることができた.基本的属性のなかではとくに年齢が利用と深くかかわっており, それに伴って生活意識とのかかわりの重要性が浮かび上がった.さらに外食の余暇化現象の確認, 高齢者世帯における外食サービスのあり方に関する示唆, 今後の利用を予測する上でのサービスの質と利便性評価のもつ役割など, 新たな生活様式形成予測の手がかりを若干でも得ることができたと考える.家事サービスの利用要因の一部をそのはたらきとしてとらえたにすぎないが, 生活意識との分析を重ねることで, より利用構造の把握に近づくことになろう. なお, 本研究は昭和60年度日本家政学会東北・北海道支部第30回研究発表会および昭和61年度日本家政学会第38回大会においてその概要を発表した.
- 著者
- 山口 征啓
- 出版者
- 南江堂
- 雑誌
- 内科 (ISSN:00221961)
- 巻号頁・発行日
- vol.112, no.5, pp.937-940, 2013-11
1 0 0 0 国語科教育を軸としたメディア・リテラシー教育の実証・開発研究
最終年の本年度は、二度の予備調査を踏まえ、2003年2月〜3月にかけて、国語科メディア・エデュケーションを標榜した単元学習を開発、実施、検討を行った。また、前年度から継続研究である英国映画研究所教育部門開発の教授法の考察ならびにドイツにおけるメディア教育の検討を基礎研究として行い、教授法ならびに教材開発を多角的に行うよう努めた。合わせて、予備調査を踏まえた子ども用国語科学習ソフト作成への見通しをつけた。具体的には、大阪府下・兵庫県下の公立小中学校ならびに大阪教育大学附属中学校の計10校の協力を得て、大阪教育大学との連携システムを構築し、テレビ・アニメーションを用いた読解表現単元を構想し、指導法ならびに教材資料の開発、指導前、中、後指導を行い、実施、検証した。パイロット授業は、作り手の立場に立って読む・表現することを目的とした単元学習「新しい国語「名探偵コナン」の予告編を作ろう」(全8時間)で、「子どものメディア環境アンケート」を補助調査として実施した。授業展開の大要は、動画の基礎読解→動画粗筋の作成→粗筋と予告編の違いに気づく→予告編の意図、機能および視聴者を意識した予告編案の作成→大学において子どもの予告編案の映像化→相互批評会→オリジナル予告編の批評→アンケート調査であった。短編中心の物語小説教材を扱うことの多い国語科にあって、30分番組という中篇物語を作り手の立場に立って読解し、受け手を意識して予告編に再構築するという学習活動は、学習者にとって予想外の困難さを伴う、新鮮な活動と映ったようであった。動画リテラシーを全面に取り立てた授業に対する子どもの反応と学習のさまは、ワークシートの学習記録ならびに事後のヒアリングによって検証した。大学において映像化をサポートした本研究の授業法によって、設備面で困難な学校でも実施が可能になり、小中校の実践者の方々にとって具体的な意欲付けになった。
1 0 0 0 OA デカルトからモーペルチユイへ
- 著者
- 山崎 英三
- 出版者
- 明治大学
- 雑誌
- 明治大学科学技術研究所紀要 (ISSN:03864944)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.205-230, 1964
Au 17 eme siecle Descartes s'est occupe de construire les lois de choc pour demontrer celles de propagation de la lumiere. Apres une centaine d'annees, Maupertuis a propose le principe de la moindre action, en pretendant que son principe peut deduire non seulement les lois de propagation de la lumiere, mais les lois de choc pour les corps elastiques et pour les corps durs (non-elastiques). L'un et l'autre ont recherche le premier principe de la nature. Descartes ayant vecu dans le temps ou la mecanique newtonienne etait a l'aube du jour, il a cru qu' il pourrait construire la science physique avec ses idees innees : l'extension et le mouvement. Aux jours de Maupertuis, Newton avait deja developpe sa mecanique. Cependant, plus la mecanique newtonienne s'est developpe, plus on a du reconnaitre que son applicabilite etait bien restreinte. La mecanique newtonienne etait trop impuissante pour expliquer toutes les phenomenes de la nature. On n'a pu se confier a l'extension ou au mouvement de Descartes. Aussi en mettant l'extension au meme rang que toutes les qualites sensibles, Maupertuis a-t-il etaye l'idealisme de Berkeley. Cependant, il est tres curieux que les pensees de Maupertuis laissent des fragments de metaphysique cartesienne. C'est peut-etre parce que Maupertuis, en croyant l'universalite de son principe de la moindre action, n'a pas cesse d'avoir la preference pour le systeme qu'on reprochait tant au 18 eme siecle.