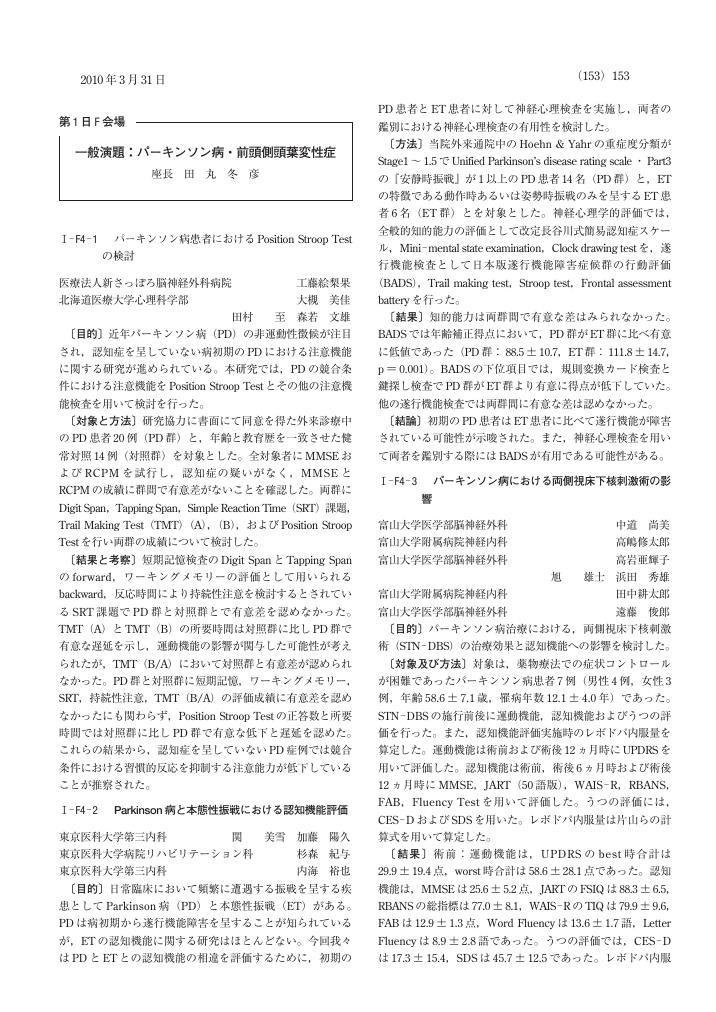1 0 0 0 中国大都市における住宅の市場化とその地域的展開
本研究は,現代中国において改革開放政策導入以後,急速に展開されている住宅改革の実態と都市地域構造の変化における意味を明らかにすることを目的としていた。本研究の具体的な研究テーマは,中国における住宅改革の特質を明らかにすること,中国国内における都市の住宅の市場化の地域的特質を明らかにすること,北京と上海における住宅開発のタイプとその開発の地域的特質を明らかにすること,住宅建材を含めた中国独特の住宅供給構造を明らかにすることの4点である。これらのテーマに関して,代表者と各研究分担者は海外共同研究者の協力を得て,中国現地において不動産企業や行政機関などへの聞き取り調査や統計・文献資料の収集と整理を行った。土居は住宅改革およびその市場化に関して,文献・統計資料を用いて全国的な動向を把握して北京市と上海市の全国的な位置づけを確認するとともに,北京市における不動産企業への聞き取り調査を進めて,住宅開発が行われるメカニズムを明らかにした。山崎は北京市における住宅開発の地域的動向を統計資料と開き取り調査によって明らかにし,住宅開発が北京市の都市地域構造の変化に持つ意味について考察した。香川は上海市における住宅開発の地域的動向を分析するとともに,インターネットを通じた住宅物件情報の整備状況を調査した。木本は建設業者や内装設備等の関連業者への聞き取り調査を進め,日本とは異なる中国独自の住宅開発プロセスおよび住宅産業の特質を明らかにした。なお,香川と木本は共同で北京市,上海市において,住宅入居者に対するアンケート調査を用い,住宅購入の動機や住宅選択の要因などを考察した。以上の研究成果を通じて,経済成長が急速に進む中国の大都市において,居住環境の改善を求めて住宅を購入する市民,中国独自の土地・住宅制度のもとで住宅開発を行う住宅開発企業,さらに社会主義的特質の維持にも努力する政府・行政機関それぞれの特質と3者の相互関係が明らかになるとともに,このような住宅市場の形成によって都市地域構造が急速に変容していることが確認された。
1 0 0 0 思いは生きている : 想念形体
- 著者
- アニー・ベサント C.W.リードビーター共著 田中恵美子訳
- 出版者
- 神智学協会ニッポンロッジ
- 巻号頁・発行日
- 1983
本研究は天然漆の長期安定性に及ぼす影響因子と漆構造との関係解明と漆の更なる有効利用を目的とした新規な機能材料の創製を目的としている。本研究では産地の異なる漆(ベトナム、ミャンマー、中国)塗膜を調製し、各種構造解析を行い基本物性を明らかにした。また漆の構成成分である水球サイズに着目し、この水球の大きさ、分散状態の異なる漆液を調製し、その漆塗膜の紫外線劣化と水球の状態に関係があることを見出した。これは水球中に存在する酵素の反応性が大きく関係するものであった。漆の有効利用を目的として、漆を用いた電波吸収特性を有するハイブリッド材料の創製では漆が酸化鉄等の多量の金属フィラーを含有することのできる優れたバインダー特性を有することを明らかにした。また漆の構成成分であるウルシオールと類似構造体のバイオマスである非可食なカシューナッツシェルリキッドに着目し、エポキシ反応、プレポリマー化(酸化重合)により新規なバイオベースエポキシ材料を得た。このエポキシ材料は市販品のものよりも乾燥性、耐熱性に優れるものであった。また加熱により熱硬化特性を示す材料であった。またアミン化合物を含有した複合材料では、大腸菌、黄色ブドウ球菌に対する抗菌特性を有することを明らかにし、医療用塗料への可能性を見出した。漆は通常の環境下で優れた長期耐久性や美的な外観特性を有する。この漆の優れた機能を学びそれらを再現することを目的として、このカシューナッツシェルリキッドを原料としたカテコール類の合成と酵素重合を用いたポリカテコールの研究と新規な合成漆を開発した。得られた合成漆は黄色い外観であり、この発色原因が乾燥(重合)過程で生じるキノンに由来することを明らかにした。
1 0 0 0 OA ウィトルーウィウスの技術学(1) : 技術の学的認識
- 著者
- 小川 清次
- 出版者
- 大阪府立工業高等専門学校
- 雑誌
- 大阪府立工業高等専門学校研究紀要 (ISSN:0387365X)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.1-10, 2008-07
本稿はウィトルーウィウス『建築の書』における「技術」と「学」との関係を考察したものである.この書は紀元前1世紀に,「建築」やさまざまな人工物の「教本」として著された.しかるに,そこには単に設計指南書的な性格だけでなく,建築や人工物の設計,製作という営みのなかに学の契機を取り出そうとする意図をも読み取ることができる.本論考では,それらを「自然学」(ギリシア自然哲学)および哲学,幾何学(シュムメトリア論)に限定する手続きを先ず展開した.そして,「自然学」および哲学が『建築の書』でどのような基盤をなしているか,概観し,次いで,『建築の書』の設計理論の骨格をなすシュムメトリア論を簡単ながらもやや詳しく,現代的に解釈した.最後に,『建築の書』において建築という営みのうちに見出されるとされる「学」のあり方を,考察した.
- 著者
- 平井 智尚
- 出版者
- 公益財団法人 情報通信学会
- 雑誌
- 情報通信学会誌 (ISSN:02894513)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.4, pp.61-71, 2012-03-25
- 参考文献数
- 39
本論ではウェブで炎上がなぜ起こるのかという問題を日本のウェブ文化の観点から明らかにする。炎上とはブログ、ミクシィ、ツイッターなどに投稿されたメッセージの内容に対して、批判や非難が巻き起こる現象を指し、ブログの普及以後、たびたび発生している。それに伴い、炎上に対する社会的な認知も高まり、新聞、雑誌、ニュースサイトなどで言及が行われている。しかし、学術的なアプローチをとった考察は今のところ多くはなく、考察の余地も残されている。<br>本論ではまず炎上の事例を歴史的に整理する。次いで、先行研究への言及をかねてフレーミング現象との比較検討を行う。この作業を通じてフレーミングと炎上の違いを示したうえで、電子掲示板2ちゃんねるの文化と、若年層が担う携帯電話の文化の両面から炎上が起こる理由の説明を行っていく。そして最後に、炎上とは対極に位置するように見えるウェブと公共性に関する考察を展開していく。
- 著者
- ROSER Barry・P
- 出版者
- 島根大学
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2001
本州、北海道、韓国の主要なテレーンで採取した砂岩-泥岩試料は全岩化学組成の上から顕著なコントラストを示す。本州では、四万十-丹波、三波川、黒瀬川テレーンにおける砂岩-泥岩試料は主・微量成分、希土類元素に関して、比較的分化の進んだCIAまたはACM堆積物の特徴を示す。コンドライトで規格化したREEパターンはLa_N/Yb_N比平均値はそれぞれ10.4-10.9、8.2、9.2であり、また、Gd_N/Yb_N比はそれぞれ1.72-1.33、1.45、1.71と違いがある。低いGd_N/Yb_N比はジルコンやガーネットの濃集を示している。負のEu異常はこれら3テレーンのすべてに共通して認められる(Eu/Eu*平均値は0.77-0.73,0.63,0.79)。渡島半島テレーン(北海道)の珪質岩に於ける高いLa_N/Yb_N比(平均値11.00)とより大きな負のEu異常(Eu/Eu*=0.64)は比較的成熟した起源物質を示している。蝦夷層群下部イドンナップ帯岩石における低いLa_N/Yb_N比とEu/Eu*比(平均値9.74と0.69)は苦鉄質物質のより大きな影響を反映して、より上位に向かって減少(6.76と0.78)していく。Gyeongsang累層群(韓国)における平均的なLa_N/Yb_N比(13.5)は、この累層群に対比される関門層群中のもの(8.8)に比べ、より大きいが、Eu/Eu*比平均値は類似している。四万十、三波川、大島、蝦夷イドンナップテレーンのNdモデル年代は著しく異なる。四万十帯のモデル年代は、大部分が1.0-1.4Gaにはあるものの、0.74から1.6Gaの幅を示し、領家と肥後テレーンの起源物質の中間的な年代値となっている。二つの三波川結晶片岩試料は1.04と1.2Gaという類似したモデル年代を示し、四万十帯プロトリス、つまり源岩の共通性の可能性を示唆する。渡島半島テレーンのモデル年代は著しく古く(1.44-1.85Ga)、Yangtzeクラトンの年代と類似し、おそらくそれらを起源とする。下部蝦夷イドンナップテレーンのモデル年代は、渡島半島テレーンものより若く(1.05-1.31Ga)、上部蝦夷イドンナップテレーンにおいてはさらに若く(0.71-0.93Ga),このことはおそらく付加体内においてリサイクルした海洋地殻の影響が反映されているのであろう。造山帯としての日本列島の平均的な上部地殻組成(JOAUC)に対する元素組成規格値は、同じテレーンにおいて、REEやHFSEは良く類似しているにもかかわらず、ある種の元素(例えば、Fe,Mn,Mg,Ca,P,Sc,V,Cr,Niなど)は負の異常を示す。元素の枯渇は渡島半島、蝦夷イドンナップ、四万十テレーンにおいてもっとも顕著であり、また、泥岩に比べ砂岩で著しい。この異常はJOAUC平均値の中で、ある種の元素については修正しなくてはならないであろうことを示している。
1 0 0 0 政治参加と政治的帰結との間の関係
近年のアメリカの福祉政策の変容を理解する上で、1996年福祉改革は非常に重要な分析対象である。同改革がもたらした重要な変化は、以下の二点である。第一に、連邦政府の定める福祉受給資格が厳格化され、福祉政策が抑制的なものへと変化した。第二に、州政府は、連邦政府が定めた福祉受給資格よりも厳格な基準を設定することが認められ、大幅な裁量権を得た。既存研究の多くは、近年の福祉政策の変容の要因を96年福祉改革にばかり求めていた。しかし、同改革がもたらした重要な変化の一つである州政府への権限移譲については、1962年社会保障法改正で挿入され、現在まで存在する第1115条(ウェイバー条項)の中に、その萌芽が認められる。ウェイバー条項は、社会保障法のもとでは連邦政府のみが有していた福祉受給資格を設定する権限を、例外的に州政府に与え、独自の政策の実施を認める制度である。また、ウェイバー条項の運用目的と運用数は、時代を経て大きく変化した。1962年から1986年までの実証試験のうち、その多く福祉拡充を意図したものであった一方で、受給資格の制限などの福祉縮減を意図した実証試験は稀だった。ところが、1987年以降になると、福祉拡充を意図したウェイバー条項の運用は全く実施されなくなり、反対に、福祉縮減を意図したウェイバー条項の運用が、突如として増大した。すなわち、96年福祉改革の特徴とされる、福祉の縮減と州への権限委譲という福祉政策の変容は、ウェイバー条項に基づく実証試験の実施という形で、ロナルド・レーガン政権から、すでに生じていたと捉えなければならない。そこで本研究では、なぜ、レーガン政権以降、福祉縮減のためのウェイバー条項の運用が拡大したのかという問いを設定した。主にロナルド・レーガン大統領図書館、ジョージ・H・W・ブッシュ大統領図書館、ビル・クリントン大統領図書館において収集した政権内部の資料を用いて、レーガン政権が意図的にウェイバー条項の運用を転用させ、それがその後のウェイバー条項の運用拡大を導いていたことを明らかにした。本研究成果の一部は、2013年日本比較政治学会年次大会にて報告した。
1 0 0 0 OA ハルモニア(音階)の有するエートスの問題
- 著者
- 山本 建郎
- 出版者
- 日本西洋古典学会
- 雑誌
- 西洋古典學研究 (ISSN:04479114)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.20-30, 2003-03-20
As is well known, in the Respublica III Plato remarks many kinds of harmoniai, among which he selects the Dorian and the Phrygian as fitting subject matter for education of the young The aim of this paper is firstly to find out the real nature of Dorian and other harmoniai The detailed structures are shown in the additional paragraph of Aristides Quintihanus (Arq)' De Musica I ch 9 as old-fashioned harmoniai, according to which we can guess that Plato's Dorian is akin to the form of disjunction of two tetrachords, the standard style of a scale of an octave On the other hand the rationalized styles of harmoniai as the species of an octave are also described in Arq (I ch 8) These structures correspond to the modes of Western Medieval and Renaissance music Historically speaking the standard schema of an octave has developed through Terpander's improvement Terpander's schema has been guessed to be conjunction of tetrachords added the tonos uppermost But this schema shows the Mixolydian octave instead of the Dorian To be Dorian the schema must be the form of disjunction As an evidence of the disjunct octave we can take up Nicomachus' description of Philolaus' scale in the Enchilidion ch 9 This passage is opposed to the description of Pythagoras' scale (Ench ch 5), which is an improvement of the old-fashioned conjunct scale Compared to Nicomachus' passages we can conclude that Terpander's schema must have been the disjunct schema devoid of the trite Terpander arranged the old-fashioned Dorian which had appeared much earlier into the rationalized schema of the disjunct octave Contrary to the Dorian the other old-fashioned harmoniai are supposed to come into existence respectively These traces could be seen in Plutarch's description (mainly on the Mixolydian) So the rationalized style of harmoniai which form the species of an octave should have come into existence somewhat later They might have been constructed artificially about BC430 when Eratocles (an inventor of the circularity of a scale) and Damon were both in their akme Plato's so called Dorianism is supposed to be a reaction against the overflowing of ethos of his age But Plato was not a theorist of harmonics, so he was unable to make an actual reformation It was Aristoxenus (Arx ) who reformed the musical situation by replacing the species with tonoi (pitch) Each tonos is also the same fragment as the species of an octave, but there is a central note, the mese, around which all of the other notes move As the mese works as a central note, many kinds of ethos in the species of an octave disappear, and the scale is reduced to the Dorian The system of tonos presupposes the Great Perfect System (GPS), two octaves system which has the mese as a central note Usually GPS wasconjectured to be arranged about at the middle of the 4^<th> century BC and succeeded by Arx , but I assert as a conclusion that it was invented by Arx constructing the system of tonos
1 0 0 0 現代家族の育児困難・育児不安と子育て支援に関する研究
本研究は、乳幼児を養育中の母親の意識や子育ての実態を把握し、適切な社会的支援のあり方を明らかにすることを目的としている。595人の親へ質問紙を配布したところ、365人から回答が得られた。その結果、親になるまで赤ちゃんの世話をした経験がある人は3割に過ぎず、経験がある人に比べ、経験の無い人の育児不安はより高い傾向がみられた。また、出産前のイメージと現実とのギャップがあったと答えた人は52.5%で、そのうち、76.5%が現実の子育ては思っていたよりも大変だと答えている。なお、イメージと現実とのギャップがあったと答えた人たちの方が育児不安は高い傾向がみられた。養育態度や意識について把握したところ、子どもを感情的に叱ったり、体罰を多用する傾向がみられた。例えば、大きな声で叱るが85.8%、叩いて叱るが55.1%(複数回答)という結果であった。子どもに苛立つことがあるという回答は68.4%、自分は育児に向いていないと感じることがあるという回答は53.4%であった。また、子育てに疲れるという回答は82.3%、時間的なゆとりがほしいという回答は91.9%であった。母親たちの自由時間はほとんど無く、専業の母でも平均2時間で、有職の母の平均1時間とあまり差がなかった。夫の家事・育児参加に満足している妻は、3人に1人に過ぎなかった。さらに、近隣からのサポートも受けられず、孤独な育児を強いられている実態が浮き彫りになった。なお、母親が育児に専念すべきと考えている人は、3.8%に過ぎず、28.7%の母親は保育所を利用したいと希望しており、48.7%は時々保育を受けたいと希望していることがわかった。これらのことから、親の不安や負担感の軽減を図るためには、必要なときにはいつでも利用できる保育システムを整え、養育技術を学習する機会等を保障することが不可欠になってきているといえよう。
1 0 0 0 第一鹿島海山の地形・地質
- 著者
- 東海大学海洋学部第一鹿島海山調査団
- 出版者
- 地学団体研究会
- 雑誌
- 地球科学 (ISSN:03666611)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.4, pp.222-240a, 1976
Daiichi-Kashima Seamount is located on the junction of Japan and Izu-Bonin Trenches, and the top of seamount is characterized of guyot at 3,700 m in depth. The basement structures of Daiichi-Kashima Seamount seems to continue to Mineoka up-lift zone. The seamount is consisted with four acoustic layers. The broadly outcropping sediment layer (Su. 1) is composed with Cretaceous Limestone, ineluding foraminifera (Orbitorina sp.) and Stromatopora. Generally, it seems to be corresponded to Barremian to Cenomanian. The second layer (SU. 2) presumes to consist of tuffaceous sandstone. The third layer (Su. 3) is the major parts of the seamount bodies and Su. A is the debris layer derived from lower layers. The olivine dolerite, olivine augite basalt, trachyte and trachytic andesite were obtained from the dredging samples at the summit of seamount. Also the materials of surface sediments and core might be originated from volcanic ash on the top of seamount. The clay minerals in the core sample of St. 2 show the same composition as recent sediments in the adjacent sea of Japan. From our biostratigraphic investigation, microfossils of the core were deposited on the latest Pleistocene, and it is indicated that the environment of sea changed to become colder at lower than 40 cm in depth. This seamount was also studied geomagnetically this time as follows. There are some high magnetic anomalies and they would be due to the matters related to the crustal structures about 4-5 km from sea surface. The reason why this seamount is located in such a depth as 3,700 m may be explained by the eustatic movement, rising of sea level, after middle Cretaceous time.
1 0 0 0 OA 主に捧げる新しい歌 : J・マッテゾンによるルター精神の再興
- 著者
- 礒山 雅
- 出版者
- 美学会
- 雑誌
- 美學 (ISSN:05200962)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.26-38, 1985-06-30
Bisher ist J. Mattheson nur als radikaler Aufklarer, der den traditionellen Musikbegriff des deutschen Barocks, d.h. des Luthertums, aufloste, betrachtet worden. Das ist aber eine einseitige Betrachtung. Vorausgesetzt, dass man den Musikbegriff des Luthers selbst und den der lutherischen Orthodoxie klar unterscheiden muss, behaupte ich, dass Mattheson das Wesen des Musikbegriffs von Luther in einer verneuerten Form wiederaufgebaut hat. Es handelt sich vor allem um die Musik-Mathematik-Beziehung. Der mathematische Musikbegriff der orthodoxischen Musiktheoretiker stammt nicht aus Luther selbst, sondern aus der Tradition seit dem Mittelalter. Luther selbst hat die Musik vom Zwang des Quadriviums befreit. Mattheson liest den Text von Luther exakter, versteht ihn treffender und zitiert ihn sehr oft-beim Klagen uber den Verfall der Musik in der Vorrede des "neuen eroffneten Orchestres", beim Widerlegen gegen J. H. Buttstett, den konservativen Theoretiker, im "beschutzten Orchestre" und beim Verteidigen der opernhaften Kirchenmusik im "musikalischen Patriot". Aufgrund der Bibel und Luthers Auslegungen behauptet Mattheson, dass die theatralische Kirchenmusik eigentlich von Gott selbst befohlen ist. Mattheson besteht gar nicht auf den alten Choralen, sondern fordert im Gottesdienst die Musik voll von gegenwartiger Lebenskraft auszunutzen. In diesem Sinne kann man sagen, dass Mattheson Luthers Idee nach zwei Jahrhunderten wieder lebendig gemacht hat.
1 0 0 0 OA 放射音を用いたCFRP構造の異物衝突・衝撃損傷モニタリング法の開発
本研究では,運用中の航空機CFRP構造に小石等が衝突するときの荷重位置・荷重履歴を,異物衝突時の放射音を用いて非接触・実時間でモニターする手法を確立するとともに、同定した最大衝撃荷重および荷重~時間関係より,CFRP構造の衝撃損傷の有無・大きさを実時間で評価する手法を開発することを目的とした。すなわち、異物衝突時のマイクロホンへの放射音到達時間から異物衝突の位置を判定し、音圧情報より荷重履歴を推定するとともに,同定した荷重履歴より衝撃損傷を評価する非接触・実時間の異物衝突・衝撃損傷モニタリング法を開発し,CFRP積層板およびCFRPサンドイッチ板により本手法の有効性を検証した。
1 0 0 0 OA 國安洋, 『<藝術>の終焉』, 春秋社, 一九九一年, 三三二頁
- 著者
- 岩城 見一
- 出版者
- 美学会
- 雑誌
- 美學 (ISSN:05200962)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.67-71, 1995-06-30
1 0 0 0 OA ハンガリーにおける日本語教育史概観
- 著者
- 大杉 千恵子 Osugi Chieko
- 出版者
- Graduate School of International Development. Nagoya University
- 雑誌
- Forum of International Development Studies (ISSN:13413732)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.177-200, 2003-03 (Released:2006-03-28)
JOCV(Japan Overseas Cooperation Volunteers)are Japanese skilled young people who work abroad for assisting the people of the recipient countries. Dispatching the JOCV is one of the responsibilities of JICA(Japan International Cooperation Agency)that is the main organization implementing Japan’s ODA(Official Development Assistance). The recent growth and development of Japanese language education in Hungary have been remarkable. At this time it is worthwhile to examine the history of Japanese language education in Hungary and consider its present situation. In my observation, the historical development of the Japanese language education can be divided into three phases : I. Introduction, II. Early development, and III. Maturity. The period of introduction is from the 1920s to the late 1980s that is slightly before the termination of the Soviet influence. Interests in‘exotic’Japan was one of th e critical triggers for Japanese language learning in this period. During this time some of the people who later developed Japanese language education in Hungary appeared on the scene. After the compulsory study of Russian ended, Japanese language became popular among other foreign languages. During this period of early development(late 1980s-2000), many JOCV Japanese teachers came and the number of Japanese learners increased a great deal. Not only the numbers, but also the area of Japanese language education expanded to local cities. Japan’s ODA played a very important role in this large growth. Since the year 2001, the Japanese language education in Hungary entered a new mature phase. The establishment of the Hungarian Association of Japanese Teachers symbolizes the beginning of this new era. The number of Japanese language learners seems to have stabilized, and the Association is working on improvement of education quality. The JOCV Japanese teachers played an epoch-making role to develop the foundation of the Japanese education in Hungary. Hopefully the Japanese language education will contribute to multilingualism that is the key to harmonious co-existence of peoples.
1 0 0 0 OA パーキンソン病・前頭側頭葉変性症
- 出版者
- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会
- 雑誌
- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.153-154, 2010-03-31 (Released:2011-05-11)
1 0 0 0 OA 飯田修一,大野和郎,神前 煕,熊谷寛夫,沢田正三編:放射線測定
- 著者
- 山本 格治
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理 (ISSN:03698009)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.11, pp.946a-946a, 1967 (Released:2009-02-09)
1 0 0 0 OA カルドアのインド税制改革案における事業利潤の取り扱いと会社課税
- 著者
- 森 俊一
- 出版者
- 三重大学社会科学学会
- 雑誌
- 三重大学法経論叢 (ISSN:02897156)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.49-86, 2008-03-01 (Released:2017-02-17)