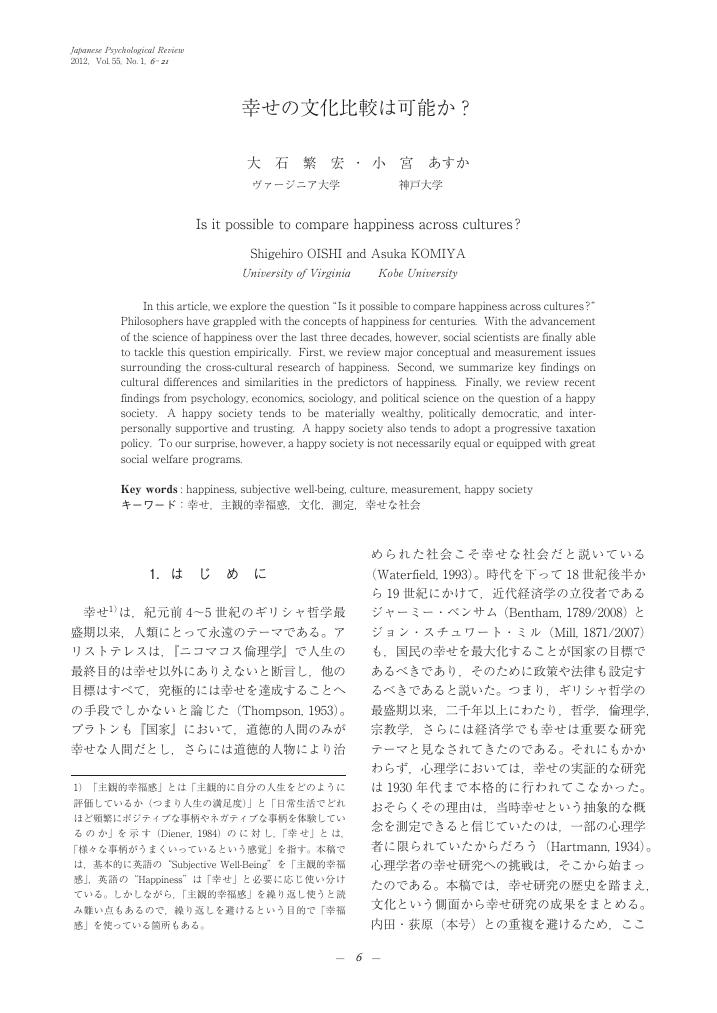2 0 0 0 OA 歴代学会会長、編集委員長
- 出版者
- 日本生気象学会
- 雑誌
- 日本生気象学会雑誌 (ISSN:03891313)
- 巻号頁・発行日
- vol.Suppl., pp.162, 2012 (Released:2012-03-27)
2 0 0 0 OA 新型乳剤におけるハロゲン化銀結晶の動向
- 著者
- 笹井 明
- 出版者
- 社団法人 日本写真学会
- 雑誌
- 日本写真学会誌 (ISSN:03695662)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.4, pp.255-263, 1984-08-28 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 44
2 0 0 0 OA 幸せの文化比較は可能か?
- 著者
- 大石 繁宏 小宮 あすか
- 出版者
- 心理学評論刊行会
- 雑誌
- 心理学評論 (ISSN:03861058)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.6-21, 2012 (Released:2018-08-18)
2 0 0 0 OA 成長期腰椎分離症の診断と治療
- 著者
- Yukio IKEDA Tadashi SUEHIRO Shigeo YAMANAKA Yoshitaka KUMON Hiroshi TAKATA Shojiro INADA Naoko OGAMI Fumiaki OSAKI Mari INOUE Kaoru ARII Kozo HASHIMOTO
- 出版者
- The Japan Endocrine Society
- 雑誌
- Endocrine Journal (ISSN:09188959)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.5, pp.665-670, 2006 (Released:2006-10-31)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 6 10
The oxidative modification of low-density lipoproteins (LDL) plays a central role in the initiation and acceleration of atherosclerosis. Iron plays a part in the formation of highly toxic free radicals such as hydroxide and superoxide anions, which can induce lipid peroxidation. We investigated whether serum iron status was associated with circulating oxidized LDL (oxLDL) levels in type 2 diabetic patients, in whom oxidative stress and susceptibility to lipid oxidation were supposedly increased. Serum ferritin levels were significantly correlated with plasma oxLDL concentrations in both male and female patients (p<0.02 and p<0.05, respectively). No correlation was detected between ferritin and LDL-cholesterol (LDL-C) concentrations despite the close correlation between LDL-C and oxLDL concentrations (p<0.0001). Stepwise regression analysis showed that ferritin concentration was an independent positive determinant of oxLDL level, in addition to triglyceride concentration, body mass index and sex. This is the first report to show that serum ferritin is associated with circulating oxLDL levels in patients with type 2 diabetes. Further work is required to establish a causative link between iron excess and the development of diabetic vascular complications.
- 著者
- Christina RUSLI Agussalim BUKHARI Nurpudji A. TASLIM Suryani AS’AD Haerani RASYID
- 出版者
- Center for Academic Publications Japan
- 雑誌
- Journal of Nutritional Science and Vitaminology (ISSN:03014800)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.Supplement, pp.S25-S31, 2020 (Released:2021-02-22)
- 参考文献数
- 26
Overweight or obesity will increase the risk of morbidity and mortality from cardiovascular disease. In older people, the risk is higher, but also paradoxically associated with lower mortality rates. Overweight patients vary in body composition and when it coupled with limited reliable sources to make caloric requirements estimation will make nutrition therapy extremely challenging. This case study reveals the nutrition therapy support in critically ill overweight elderly patient with heart failure, myocardial infarction, pneumonia, and chronic kidney disease. An 80-year old moderate malnourished male patient (body mass index 24.6 kg/m2) with acute lung edema, cardiogenic shock, myocardial infarction, pneumonia, and chronic kidney disease was admitted in the cardiovascular intensive-care unit. The patient was treated with diuretics, vasopressor support, and antibiotics. Oral intake was reduced due to shortness of breath and loss of appetite. The physical examination revealed basal lung rales, wheezing, muscle wasting, edema. Blood tests showed hyperkalemia, leucocytosis, depletion of the immune system, hyperuricemia, hypoalbuminemia, and dyslipidemia. The patient was on stage 5 renal failure (GFR 6.2 mL/min) but refused hemodialysis treatment. Nutritional therapy was given gradually with calorie target 1900 kcal and protein 0.6–1.2 g/ideal body weight/d using normal foods, oral nutrition supplement, and amino acids parenteral nutrition. After 13 d of nutritional treatment, the patient was discharged from the hospital with no shortness of breath, adequate nutrition intake, increased renal function (GFR 22.4 mL/min), and improvement of the blood test results (immune status, uric acid, albumin, and lipid profile). Critically ill overweight elderly patients are hypercatabolic and have increased nutrient demands. Nutritional support in these patients is required to provide necessary nutrient substrates and to alter the course and outcome of the disease.
- 著者
- 北川 一夫
- 出版者
- 日本脳神経外科コングレス
- 雑誌
- 脳神経外科ジャーナル (ISSN:0917950X)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.12, pp.901-908, 2008-12-20 (Released:2017-06-02)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1
これまで原因不明とされてきた脳梗塞の中で,大動脈粥状硬化病変からの塞栓症である大動脈原性脳塞栓症,卵円孔開存などの右左シャントに起因する奇異性脳塞栓症が,経食道心エコー検査を用いて正確に診断されるようになってきた.大動脈弓部に内膜中膜厚4mm以上,または可動性プラーク,潰瘍形成を認めるプラークは塞栓源として認識されている.再発予防にはスタチン製剤と抗血小板薬または抗凝固薬の使用が推奨される.卵円孔開存は一般健常人でも約20%観察されるため,奇異性脳塞栓症の診断には右左シャントの証明だけでは十分でない.下肢深部静脈血栓症や肺塞栓症の存在を確認する必要がある.下肢静脈エコー検査は,深部静脈血栓,特にヒラメ静脈血栓症の検出に有用である.卵円孔開存を伴う脳卒中症例の再発予防には,深部静脈血栓症あるいは全身の凝固元進状態を合併していればワルファリンが,これらの合併がない場合は抗血小板薬が推奨される.
- 著者
- 丸山 悟 吉井 彰宏 水落 芳明
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.Suppl., pp.133-136, 2013-12-20 (Released:2016-08-10)
本研究では,ティーム・ティーチング(以下,TTとする)の授業形態において,同時通話のできるトランシーバーを用いて,教職経験のない大学院生(以下,学卒院生とする)が教員の大学院生(以下,現職院生とする)の発話を聴取可能にすることで,学卒院生の発話に与える効果について検証した.その結果,授業実践の経過と共に,学卒院生の学習者を指導する具体的な発話数が増加したことが確認された.また,学卒院生は指導の不安感が軽減し,学習場面に応じて発話を主体的に選択できるようになったことが明らかになった.以上から学卒院生が現職院生の発話を聴取可能にすることにより,効果的な発話の情報を獲得できることが示唆された.
- 著者
- Masatomo Ogata Satoru Morikubo Naohiko Imai Yugo Shibagaki Masahiko Yazawa
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- pp.8285-21, (Released:2021-10-19)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 2
Serum tonicity is defined by the serum concentrations of sodium (sNa) and glucose, which can promote free water movement across intra/extracellular compartments. Rapid changes in serum tonicity can cause brain damage. We herein report an educational case of a patient with hyponatremia (sNa: 112 mEq/L) concomitant with acute alcoholic pancreatitis. The cause of hyponatremia was considered complex. Pseudo- and trans-locational natremia was secondary to hyperglycemia (721 mg/dL) and hypertriglyceridemia (1768 mg/dL), respectively, and true hypotonic hyponatremia. Regarding sNa correction, rapid correction was suspected. However, this was safely managed by monitoring tonicity (not sNa or osmolarity), thereby avoiding brain damage.
- 著者
- 樋口 義治 平山 篤志 児玉 和久
- 出版者
- 一般社団法人 日本循環器学会
- 雑誌
- 循環器専門医 (ISSN:09189599)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.35-42, 2021 (Released:2021-09-01)
- 参考文献数
- 23
2 0 0 0 OA 心原性か大動脈原性かの脳塞栓症診断に苦慮した1例
- 著者
- 上野 祐司 卜部 貴夫 服部 信孝
- 出版者
- 一般社団法人日本脳神経超音波学会
- 雑誌
- Neurosonology:神経超音波医学 (ISSN:0917074X)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.1-2, 2015-04-30 (Released:2015-05-29)
- 参考文献数
- 5
- 著者
- Yuichi Ueya Masakazu Umezawa Yuka Kobayashi Kotoe Ichihashi Hisanori Kobayashi Takashi Matsuda Eiji Takamoto Masao Kamimura Kohei Soga
- 出版者
- The Japan Society for Analytical Chemistry
- 雑誌
- Analytical Sciences (ISSN:09106340)
- 巻号頁・発行日
- pp.21P283, (Released:2021-10-15)
- 被引用文献数
- 5
2 0 0 0 OA 18-20世紀の朝鮮と日本の月別出生数変動
- 著者
- 川名 はつ子 野中 浩一 三浦 悌二
- 出版者
- 日本生気象学会
- 雑誌
- 日本生気象学会雑誌 (ISSN:03891313)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.31-36, 1994-04-01 (Released:2010-10-13)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1
日本では早生まれの多い現象が1960年代半ばにはほとんど消えて, 1年中ほぼ平均して生まれるようになった.隣接する韓国・朝鮮との差異を検討するため, 日本人と朝鮮・韓国人の出生季節分布を, 古くからの記録を用いて約300年にわたり比較した.出生数の「早春の山と初夏の谷」の傾向が最もはっきりしていたのは, 19世紀以降のおよそ1世紀半の間の日本であり (山/谷比=約1.5) , その間, 朝鮮・韓国では分布の形は日本と同様ながら, その変動幅は小さかった (山/谷比=約1.1) .ところが日本で季節性の消失した1960年代以降にも, 韓国では早生まれが減少せず, とくに1970年代には「早春の山と初夏の谷」はむしろ明瞭になりつつあるという違いが生じている.日本の早生まれ喪失現象が, 一般に言われていたような, 冷暖房や冷蔵庫の普及などによる脱季節化に起因するものならば, 韓国でも何年かの時差はあっても同様の経過をたどるはずなのに, 却って差が拡大していることから, 冷暖房や冷蔵庫の普及などとは別の要因が働いているらしいことが示唆された.
2 0 0 0 OA 飼育下のキジ(Phasianus versicolor)における雄変の報告
- 著者
- 佐藤 真
- 出版者
- 市立大町山岳博物館
- 雑誌
- 市立大町山岳博物館研究紀要 (ISSN:24239305)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.71-74, 2016 (Released:2020-10-01)
市立大町山岳博物館付属園では2005年よりキジ(Phasianus versicolor)の飼育を行っている. 本稿では, 性成熟後のメスにおいてオスの形態的・生態的特徴を呈することを雄変と定義し, 当館付属園の飼育下個体における雄変の報告及びその原因と雄変の適応的意義について考察した. 当館付属園では, 主に雌雄同居の平飼いを行っており, これまでに計13羽を飼育し, 自然繁殖によって第2世代までみている. 2014年7月16日に雌雄ペアで飼育していたメス個体の頭部にオス特有の羽装色が見られた. また, 同個体は2013年まで放卵を行っていたが, 2014年以降には放卵は行っていない. 雄変の原因として, 先天性である遺伝子疾患や発現異常なども考えられるが, 少なくとも当館付属園の飼育個体においては, 野生由来の卵から孵化し産卵経験もあるため, 老齢化によって内分泌系やホルモン機能環に異常が生じた可能性が最も高い.
2 0 0 0 OA 神戸層群の地質年代
- 著者
- 尾崎 正紀 松浦 浩久 佐藤 喜男
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.2, pp.73-83, 1996-02-15 (Released:2008-04-11)
- 参考文献数
- 52
- 被引用文献数
- 11 20
2 0 0 0 OA [44] 360度パノラマ画像を用いた書道展のデジタルアーカイブ化
- 著者
- 林 知代 梶原 麻世
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.s1, pp.s57-s60, 2020 (Released:2020-10-09)
- 参考文献数
- 7
本稿では、書作品の鑑賞における展示会の意義をアンケート調査により明らかにし、360度パノラマ画像による展示会のデジタルアーカイブ化による書道鑑賞の充実を試みた。書道を学ぶ学生へのアンケート調査の結果、書作品の鑑賞は書道展が重要な役割を果たしており、書作品の雰囲気、構成、書き振りが感じられるデジタルアーカイブが必要であることが明らかになった。360度パノラマ画像の記録し、VRコンテンツを制作し、検証したとこと、展示会の雰囲気を味合うことはできたが、作品の雰囲気を味合までには達することができなかった。詳細なデータ記録をすることで、VR技術を用いた書作品の鑑賞を現実的なものとすることができると考える。
2 0 0 0 OA 界面活性剤の味覚神経反応におよぼす影響
- 著者
- 杉原 邦夫 山本 隆 河村 洋二郎
- 出版者
- Japanese Association for Oral Biology
- 雑誌
- 歯科基礎医学会雑誌 (ISSN:03850137)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.3, pp.463-468, 1977-09-30 (Released:2010-10-28)
- 参考文献数
- 3
ラットを用い, 各種界面活性剤, ならびに, これらの界面活性剤を配合したモデル処方歯磨の味覚に対する作用を, 電気生理学的手法により検討した。蕉糖脂肪酸エステル (SE) それ自身では鼓索神経に著明な反応を生じさせず, また, 四基本味質の反応に対しても何ら影響をおよぼさなかった。ラウロイルサルコシンナトリウム (LS) 自身による神経反応はラウリル硫酸ナトリウム (SLS) と類似していたが, 弱く, SEと等モル混合することによりさらに減弱した。四基本味質反応に対する抑制作用もLSはSLSより弱く, 回復性の早いものであり, SEとの混合によりその作用は減弱した。SEおよびLSを配合したモデル処方歯磨の作用はSLSを配合したものに比べ, 四基本味質反応に対する抑制作用は弱く, 回復性の早い作用であり, 味覚への影響は少ないものと考えられる。
- 著者
- 西口 栄子 鈴木 幸江 山口 和美 神部 芳則
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本歯周病学会
- 雑誌
- 日本歯周病学会会誌 (ISSN:03850110)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.1-12, 2001-03-28 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 3 1
歯磨剤, 洗口剤の安全性を検討する目的で, 市販されている歯磨剤, 洗口剤の多くに含まれているラウリル硫酸ナトリウム (SLS) とglycerineの各種ヒト細胞に及ぼす影響を検討した。ヒト歯肉上皮細胞に各種濃度のSLSを作用させて細胞の形態を観察した結果, 細胞は, SLSの濃度依存的に変化した。0.01% SLSを作用させた場合, 作用直後細胞が小型化し, 1分後にはほとんどの細胞が溶解した。0.001% SLSを作用させた場合,作用後3分で細胞が小さくなり始めたがその程度は弱かった。ヒト赤血球に各種濃度のSLSを作用させると,赤血球は,SLSの濃度依存的に形態が正常の円盤型から外方突出型の金平糖状に変化し, 0.004%以上では作用後1分で溶血した。ヒト大動脈血管内皮細胞(HAEC)に各種濃度のSLSを作用させると, 0.0022%以上では作用後1分で変化が起こり, 5分ではほとんどの細胞が溶解した。諸細胞にglycerineを作用させた場合, glycerineによる細胞の障害は低濃度, 短時間では大きいものではなかった。ヒト赤血球を用いてSLSの作用点を観察した結果, 膜蛋白質の関与が観察された。これらの結果から, SLSやglycerine, 特にSLSは, 微量で, 短時間の作用でも諸細胞に障害を与えるため,使用に際しては十分な注意が必要と考える。
- 著者
- J. David Spence
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.2, pp.268, 2017-01-25 (Released:2017-01-25)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 3 6
- 著者
- Joya Yui Satomi Okano Hitomi Nishizawa
- 出版者
- The Society of Physical Therapy Science
- 雑誌
- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.10, pp.717-721, 2021 (Released:2021-10-13)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 4
[Purpose] Blood lactate reduction helps in understanding muscle recovery. Although light exercise and stretching are known interventions to reduce its concentration, the impact of skeletal muscle mass on blood lactate clearance is unknown. This study aimed to determine the relationships between blood lactate reduction and skeletal muscle mass following exercise. [Participants and Methods] Healthy non-athletic males performed squat jumps for 1 minute and 30 seconds. Blood lactate level was measured before and immediately after the exercise and then every 2 minutes for a period of 20 minutes. The decrease in blood lactate level was estimated as the difference between the minimum and maximum values. The rate of decrease was calculated by dividing the decrease in blood lactate level by time. Blood lactate level was measured using Lactate ProTM 2, while skeletal muscle mass was assessed using InBody 430. [Results] There was a significant positive correlation between skeletal muscle mass, the amount of blood lactate level reduction, and the rate of reduction of blood lactate level. [Conclusion] Our results demonstrated that greater skeletal muscle mass enabled a greater decrease in blood lactate level, suggesting that skeletal muscle mass may be involved in the reduction of blood lactate level after a squat jump. Interventions to increase skeletal muscle mass may promote more efficient lactate metabolism and muscle fatigue recovery.