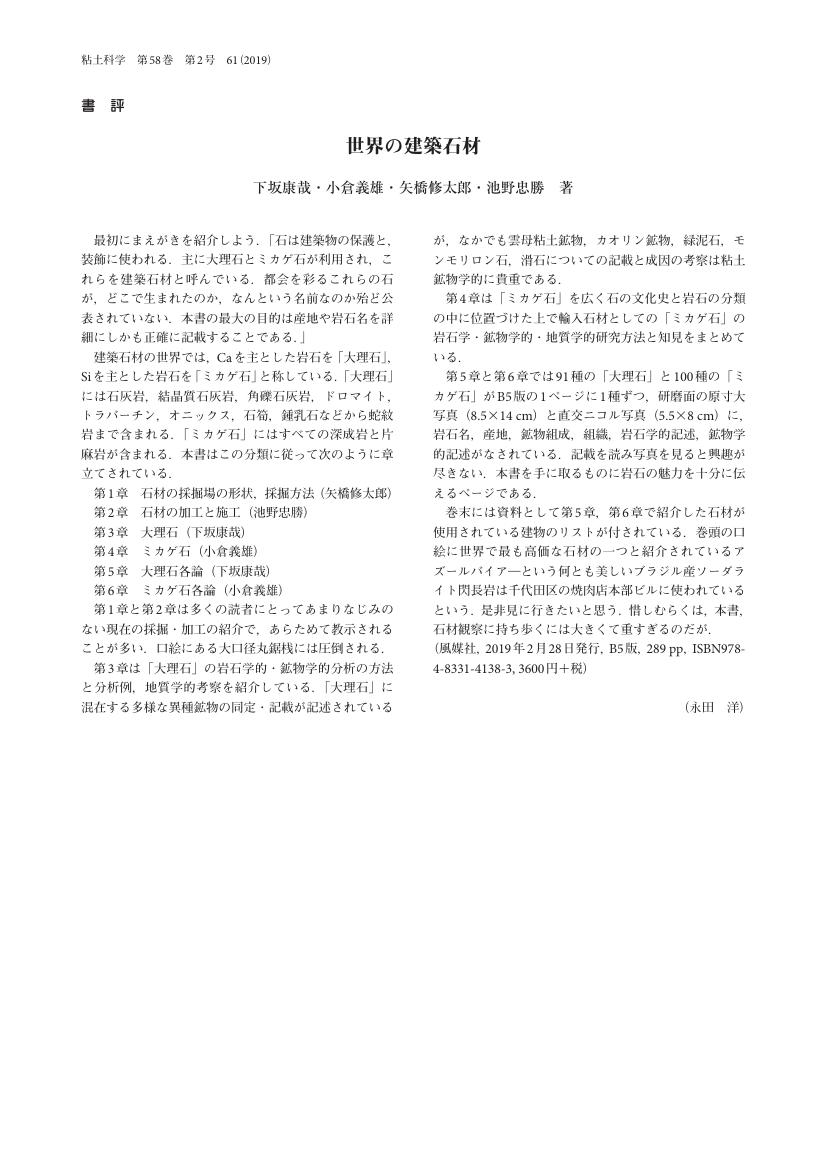2 0 0 0 OA 小児におけるプレバイオティクス・プロバイオティクスの活用
- 著者
- 橋詰 直樹 田中 芳明 深堀 優 石井 信二 七種 伸行 古賀 義法 東舘 成希 升井 大介 坂本 早季 靍久 士保利 八木 実
- 出版者
- 一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会
- 雑誌
- 日本静脈経腸栄養学会雑誌 (ISSN:21890161)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.5, pp.1111-1114, 2018 (Released:2018-12-20)
- 参考文献数
- 28
プロバイオティクスとプレバイオティクスは腸内細菌叢の是正を目的として古くから用いられる。新生児期から幼児期までに腸内細菌叢は多くの因子に影響を受けながら変動し形成される。新生児外科的治療後の抗菌薬使用や経腸栄養の制限、乳児期における持続性下痢症など、正常腸内細菌叢の獲得が困難な場合において、プロバイオティクスとプレバイオティクスの有効性は数多く述べられている。また消化管疾患のみではなく、アレルギー性疾患など消化管疾患以外の面でもその有効性は報告されている。今回はその活用例について報告する。
2 0 0 0 OA いじめの経済分析 傍観者達のモデルと実験的検証
- 著者
- 柴田 愛子 森 徹 曽山 典子 岡村 誠
- 出版者
- 公共選択学会
- 雑誌
- 公共選択の研究 (ISSN:02869624)
- 巻号頁・発行日
- vol.2000, no.34, pp.43-59, 2000-06-25 (Released:2010-10-14)
- 参考文献数
- 18
Bullying in school is a serious problem in Japan as well as in most other countries. Bystanders rarely report instances of bullying to teachers, parents and other authorities. In this paper, we model bystander behavior by utilizing the theory of non-cooperative games, which assumes that bullying acts are stopped by a classroom teacher only when more than a certain number of students report the instances. Every bystander stands to gain from the resolution of bullying activity. But when a bystander reports this activity, she will have to deal with psychological and/or physical costs if the total number of reports falls below the required minimum. Under this structure of payoffs in our “bullying game” it can be shown that if all bystanders maximize their expected payoffs, there are two stable symmetric Nash equilibria. At one equilibrium, all bystanders report the instances of bullying to their teacher, and at the other equilibrium, no one reports. We conducted a series of experiments in which subjects played our “bullying game” under various values of parameters. The results of our experiments support the expected payoff-maximizing behavior of bystanders. Based on this verification of expected-payoff maximizing behavior through experiments, we develop guidelines for policies which could serve to increase reporting activity of bystanders and dissolve bullying activity. These include reducing the threshold number for reporting from students, increasing the disutility of students' observing bullying behavior, mitigating the psychological and/or physical costs for the reporting of bullying, and scale down of class size. The effectiveness of each policy is then analyzed theoretically and compared with the other alternatives.
2 0 0 0 OA 1E2-3 片頭痛の過敏症を考慮したインテリアデザイン
- 著者
- 尾田 恵 辰元 宗人 中田 容子 平田 幸一
- 出版者
- 一般社団法人 日本人間工学会
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.Supplement, pp.S194-S195, 2014-06-05 (Released:2014-09-05)
2 0 0 0 OA 破壊現象としての水素脆性∼水素脆性機構∼
- 著者
- 南雲 道彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本高圧力技術協会
- 雑誌
- 圧力技術 (ISSN:03870154)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.4, pp.190-199, 2008-07-25 (Released:2008-09-19)
- 参考文献数
- 18
The function of hydrogen in the embrittlement of steels has been examined with respect to plasticity involved in the fracture process. Fractographic features and effects of stress state on the hydrogen embrittlement indicate promoted crack formation by hydrogen associated with strain localization. Hydrogen also enhances the creation of vacancy-type defects during plastic deformation, and correlations are shown between the density of strain-induced vacancies and the susceptibility to the hydrogen embrittlement. Analyses of the role of hydrogen in the fracture process have shown that hydrogen promotes the initiation of micro-cracks and reduces the resistance to the successive crack growth, being originated in vacancy formation. Interrelations between hydrogen effects in fatigue and delayed fracture have been shown, supporting the common effects of hydrogen through enhanced creation of vacancies. Various models of the mechanism of hydrogen embrittlement have been briefly and critically reviewed. Characteristic features of hydrogen embrittlement are the best explained with the hydrogen-enhanced strain-induced vacancies model that claims the primary role of vacancies rather than hydrogen itself in the embrittlement.
2 0 0 0 OA セリアック病と「氷山モデル」
- 著者
- 中澤 英之
- 出版者
- 信州医学会
- 雑誌
- 信州医学雑誌 (ISSN:00373826)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.4, pp.212-212, 2008 (Released:2010-11-30)
- 参考文献数
- 3
2 0 0 0 OA 母親の職種と出産後1年時までの児の死亡の関連:人口動態職業・産業別調査データより
- 著者
- 鈴木 有佳 仙田 幸子 本庄 かおり
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.10, pp.669-676, 2021-10-15 (Released:2021-10-06)
- 参考文献数
- 16
目的 出産を経ても就業を継続する女性の割合が増加している。欧米では,女性の特定の職種が出産時・出生後の児の死亡リスクと関連することが報告されているが,日本ではこの関連を検討した疫学研究はない。そこで本研究は,全国調査データを用い,母親の職種による妊娠12週以降出生までの児の死亡リスク(解析1),出生から出生1年後までの児の死亡リスク(解析2)について検討することを目的に実施した。方法 1995, 2000, 2005, 2010, 2015年度人口動態職業・産業調査(出生票,死産票)ならびに1995-96,2000-01,2005-06,2010-11,2015-16年度人口動態調査(死亡票)を用いた。解析1では生まれた児のうち,5,355,881人を対象とし,解析2では同期間に出生した児のうち,5,290,808人を対象とした。説明変数は母親の職種(管理・専門・技術,事務,販売,サービス,肉体労働,無職),目的変数は自然死産(自然死産なし=出生)(解析1),新生児・乳児死亡(新生児・乳児死亡なし=出生1年後生存)(解析2)とし,ロジスティック回帰分析を用いて解析した。また,有職者における職種に起因した自然死産の人口寄与危険割合を算出した。結果 自然死産は61,179人(1.1%),出生した児のうち新生児・乳児死亡は12,789人(0.2%)だった。出産時の母親の職種が管理・専門・技術と比較した,事務,販売,サービス,肉体労働,無職の,自然死産に関する調整オッズ比(95%信頼区間)は,1.24(1.20-1.29),1.48(1.41-1.56),1.76(1.69-1.83),1.54(1.46-1.61),0.95(0.92-0.98)だった。母親の職種と新生児・乳児死亡の関連は見られなかった。また,有職者における母親の職種が事務,サービスの自然死産に対する人口寄与危険割合は7.4%,12.3%だった。結論 本研究の結果,母親の職種により自然死産リスクに差が認められた。とくに,母親の職業がサービス職である場合,自然死産のリスクならびに人口寄与危険割合が最も高かった。一方,母親の職種と出生後の新生児・乳児死亡リスクには関連がみられなかったことから,母親の職種は妊娠期において児の状態に影響する可能性がある。本研究結果により,妊娠期の母親の職業に注意を払う必要が示唆される。
2 0 0 0 OA 1960年代における読書運動 ―飯伊婦人文庫の活動を中心に―
- 著者
- 山梨 あや
- 出版者
- 日本社会教育学会
- 雑誌
- 日本社会教育学会紀要 (ISSN:03862844)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.73-83, 2005 (Released:2021-02-02)
- 参考文献数
- 60
The purpose of this study is to explain the process of establishment and activities of Hanni-Woman Library, and investigate the meaning of women's reading activities in the 1960's. By analyzing the miscellany of Hanni-Woman Library, it is demonstrated that the women at that time were alienated from reading activities or other cultural activities because of pressure from their family, especially from their mother-in-law. Hanni-Woman Library gave them the opportunity to read. Although the number of library members were reduced because of women's participation in public and prevalence of television, there were some women who continued their reading activities. Through activities of the Hanni-Woman Library, women became to form a habit of reading and to find the importance of learning together. For them, reading activities were an essential source of their cultivation in order to decide things for themselves and act on their own judgments and present their thoughts and ideas.
2 0 0 0 OA 動物の道具使用と人類文化発生の条件
- 著者
- 杉山 幸丸
- 出版者
- Primate Society of Japan
- 雑誌
- 霊長類研究 (ISSN:09124047)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.3, pp.215-223, 1995 (Released:2009-09-07)
- 参考文献数
- 41
Tool-using behaviors of animals have been compared with those of early-man and examined the factors which differentiated the human culture from that of animals. Many tool-using behaviors of animals which are mainly found among birds and primates, particularly in chimpanzees, are flexible to environmental change and have local differences. The reason why they are remarkable only among some separated animal taxa are to be examined through their environment, life form, feeding repertoire and technique. Chimpanzees use and make many different kinds of tools, occasionally do more than one kind of tool for a single purpose and are expected to use a tool for making another tool which needs high intelligence and capability. Examination of local differences of tool-using repertoire of chimpanzees and their environment made clear that they maintain techniques through social tradition, which can be called “culture”. However, its elaboration to man-like culture needs further development of the motor function coordinating both hands and communication method by language.
- 著者
- A GETTELMAN P.M. de F FORSTER
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.4B, pp.911-924, 2002 (Released:2002-10-10)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 205 243
The tropical tropopause layer (TTL) is a transition region between the troposphere and the stratosphere. In this study the vertical extent of the TTL is diagnosed from radiosonde and ozonesonde profiles in the tropics and a climatology of this layer is presented. The radiative balance in the TTL is also characterized. The TTL is locally defined as extending from the level of the lapse rate minimum at 10-12 km to the cold point tropopause (CPT) at 16-17 km. The minimum in lapse rate represents the level of maximum convective impact on upper tropospheric temperatures, which is found to closely correspond to a minimum in ozone. Variations in this level are correlated with convective activity as measured by satellite brightness temperatures and Outgoing Longwave Radiation (OLR). At the cold point, the TTL height is nearly uniform throughout the tropics, and has a pronounced annual cycle. There are regional variations in the altitude of the lower boundary of the TTL. Interannual variations of the TTL result from changes in the large scale organization of convective activity, such as from the El-Niño Southern Oscillation (ENSO). Over the last 40 years, records indicate an increase (200-400 m) in the height of both the cold point tropopause and the level of minimum lapse rate. To better understand vertical transport in the TTL, the clear sky radiative heating rate is diagnosed using a sophisticated radiative transfer scheme. The level of zero radiative heating occurs roughly 1 km below the CPT, implying that convection needs to loft air 4-5 km above the base of the TTL if the air is to eventually enter the stratosphere.
2 0 0 0 OA 高濃度デンプンの熱水糖化
- 著者
- 新井 克大 船造 俊孝
- 出版者
- 公益社団法人 化学工学会
- 雑誌
- 化学工学会 研究発表講演要旨集 化学工学会第40回秋季大会
- 巻号頁・発行日
- pp.149, 2008 (Released:2009-02-24)
2 0 0 0 OA 「世界の建築石材」 下坂康哉・小倉義雄・矢橋修太郎・池野忠勝 著
- 著者
- 永田 洋
- 出版者
- 一般社団法人 日本粘土学会
- 雑誌
- 粘土科学 (ISSN:04706455)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.61, 2019-08-30 (Released:2019-09-03)
2 0 0 0 OA P2P技術がネットワークインフラに及ぼす影響と課題
- 著者
- 亀井 聡
- 出版者
- 日本ソフトウェア科学会
- 雑誌
- コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.3_8-3_18, 2005 (Released:2005-09-30)
インターネットにおいて,P2P (Peer-to-Peer) 技術の発展がめざましい.P2P技術は様々なメリットを持つ反面,インターネットのトラフィックの主流をこれまで占めていたウェブ等と異なる特性を持つため,ネットワークインフラに様々な影響を及ぼし始めている.本稿ではこのような現状を紹介するとともに,P2P技術とインフラの融合に向けての課題について述べる.
2 0 0 0 OA オリンピックのコスモポリタニズムにおける平和構想 ―カント哲学を参考にして―
- 著者
- 野上 玲子
- 出版者
- 日本体育・スポーツ哲学会
- 雑誌
- 体育・スポーツ哲学研究 (ISSN:09155104)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.109-120, 2017 (Released:2018-05-02)
- 参考文献数
- 55
- 被引用文献数
- 1 1
Although the Olympic Games have been holding as the sports festival with a view to promoting a peaceful society, they have ever been boycotted for political reasons and being used of as a means to an act of terrorism. The Olympic Games have opportunities to activate a sense of nationalism hidden in the background of their principle in the age of globalization. The difference between the principle to embody peace and the reality far removed from it is an issue which cannot be ignored. In this paper, we payed attention to cosmopolitanism, which is located comparatively in nationalism, and investigated the peace initiative in the Olympic Games while relating it to the issue of cosmopolitanism based on the idea of universal peace by Kant. The first half of this paper considered the theory of cosmopolitanism and peace by Kant and the second half did the peace initiative of cosmopolitanism in Olympics. The following three points were suggested according to this procedure.1.Any participant in the Olympic Games should take part in them as a cosmopolitan who has a sense of belonging to his/her own race or nation.2.Any participant as a cosmopolitan, who has the right of hospitality that enables to exchange one other, tries to establish friendly relations with other participants.3.Any participant, who has the right of hospitality that imposes restrictions on hostility one other, can drive out participants who did an act of hostility or violence.
2 0 0 0 OA さつまいもの加熱調理直後、冷蔵保存及び再加熱によるレジスタントスターチ量の変化
- 著者
- 亀井 文 高橋 遥
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集 69回大会(2017)
- 巻号頁・発行日
- pp.146, 2017 (Released:2017-07-08)
目的:レジスタントスターチ(RS)は胃や小腸で消化されず大腸に達するでんぷんであり、大腸の健康に重要な役割を果たしている。しかし、でんぷん性食品の加熱調理条件や保存条件によるRS生成の違いを調べている研究、特にさつまいもについての研究は少ない。そこで本研究はさつまいもを試料とし、茹で、蒸し、焼きの調理方法の違いと調理後直ぐ(直後)、24時間冷蔵保存(冷蔵)、冷蔵保存後電子レンジ再加熱(再加熱)のRS量の変化について調べた。 方法:試料は徳島県産なると金時(平成24年11月)で、皮なし直径約4㎝で2㎝厚さのものを用いた。茹では沸騰15分間、蒸しは20分間、焼きはオーブン予熱無しでアルミホイルに包み160℃20分間加熱した。水分量とRS量は各調理方法の、直後、冷蔵、再加熱の3条件を測定した。RS量測定は脱水操作後、Megazyme社のRS測定キットを使用した。 結果:茹でのRS量は直後6.17%、冷蔵7.32%、再加熱7.16%、蒸しのRS量は直後5.45%、冷蔵6.27%、再加熱5.78%、焼きのRS量は直後3.06%、冷蔵3.51%、再加熱3.06%であった。茹でのRS量は、直後、冷蔵、再加熱後の3条件とも一番高く、次いで蒸し、焼きの順であった。また、茹でについては、直後より冷蔵および再加熱後のRS量が有意に高く、蒸しでは直後より冷蔵後のRS量が有意に高い値となった。
2 0 0 0 OA 特集「量子水素の科学」に寄せて
- 著者
- 立川 仁典
- 出版者
- 日本コンピュータ化学会
- 雑誌
- Journal of Computer Chemistry, Japan (ISSN:13471767)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.5, pp.A51, 2016 (Released:2016-12-27)
2 0 0 0 OA ブルーギルが生態系に与える影響
- 著者
- 谷口 義則
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.5, pp.991-996, 2012 (Released:2012-10-11)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 2 3
2 0 0 0 OA マイノリティと社会の再生産
- 著者
- 山本 泰
- 出版者
- The Japan Sociological Society
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.262-281, 1993-12-30 (Released:2010-01-29)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1 1
一九九二年四月のロサンゼルス事件は、現代アメリカのマイノリティ問題の深刻さを改めて浮き彫りにした.この事件が黒人青年を暴行した警察官に対する無罪判決に端を発している以上、これは差別に対するマイノリティの大衆的抗議である.しかし、その背景についていえば、この事件は、 (1) 現代のマイノリティ問題の焦点は人種 (黒人) 問題ではなく、大規模な《都市アンダークラス》の問題であること、 (2) 都市貧困層=黒人ではもはやなく、そこには、きわめて多様な人種・民族が含まれること、 (3) 都市最下層の貧困は、六〇年代の公民権運動以来、少しも改善されていないこと、を劇的な形で示したのである.このような複合的な抑圧・葛藤関係はどのような構造のなかで、いかにして生み出されるのか、本論では、人種や民族に中立であるはずの自由主義的多元主義体制のもとにある現代のアメリカに、何故、人種や民族間の葛藤・反目がかくも顕在的にあらわれるのかを考察する.人種や民族の線に沿った集団形成やエスニシティの主張は下層の人々が上位者の資源独占に対抗する社会戦略であるが、この戦略は逆に、ルール指向・個人主義・手段主義といった基準になじまないが故に、中産階級が下層に対しておこなう差別に識別標識と正当化根拠を与えてしまうことになる.階層間葛藤は、自由主義的多元主義体制を仲立ちに人種間葛藤へと転態されるのである.
- 著者
- 川野 江里子 野原 佳代子 ノートン マイケル 那須 聖
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究 (ISSN:09108173)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.3_31-3_40, 2020-01-31 (Released:2020-02-25)
- 参考文献数
- 34
本研究は理工系大生と美大生の異分野間で協働するイノベーション・ワークショップを対象とし,ワークショップの空間を,参加者が実際にどのように捉え使いこなしているのか,その実態を明らかにすることを目的としたものである。会場のしつらえとアンケートから得られた参加者の印象・評価との関係を考察することでワークショップの物理的環境と議論の進んだ場所についての仮説を構築し,その上で,行動・会話観察をもとに会場における参加者の動きとコミュニケーション出現及び議論の内容との関係を考察した。議論時に思考の外在化を促す仕掛けとして準備したホワイトボード等の活用は,議論の活性化につながるコミュニケーション出現の起点となっており,議論中に思考が拡がるにつれ,使用する空間が面的に広がり,壁や窓,柱などの広い空間を利用しているケースが見られた。また,議論中の場所移動の様子からは,全てのケースに共通していることは見られなかったものの,一部のケースで,ワークショップ空間や空間移動を思考のためのツールやコミュニケーションのきっかけとしている事が確認された。
2 0 0 0 OA 去勢が雄ヤギの成長、肉生産ならびに臭気に及ぼす影響
- 著者
- 長嶺 樹 砂川 勝徳
- 出版者
- Japanese Soceity for Animal Behaviour and Management
- 雑誌
- 日本家畜管理学会誌・応用動物行動学会誌 (ISSN:18802133)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.4, pp.137-150, 2017-12-25 (Released:2018-02-21)
- 参考文献数
- 28
沖縄で雄ヤギの肉が流通しているのは、去勢ヤギの肉質が非去勢ヤギより劣るからであると推測されるが、雄ヤギの去勢が肉質に及ぼす影響は不明である。また、近年、雄ヤギに特有の臭気が原因でヤギ肉を食べたことがない人が増加しており、臭気の低減が不可欠であるが、雄ヤギの去勢が臭気に及ぼす影響は不明である。本研究では、雄ヤギの去勢が肉質と臭気に及ぼす影響を解明するために2つの実験を行った。実験1では、ヤギ(日本ザーネン×ヌビアンの交雑種、3ヵ月齢、試験開始時平均体重20.7kg)を6頭ずつ2群(非去勢群および去勢群:以下、NCGおよびCG)に配置した。CGのヤギは2.5ヵ月齢時に去勢された。9ヵ月間、ヤギには配合飼料とアルファルファヘイキューブを1日2回(10:00および16:00)給与し、クレイングラス乾草と飲水を不断給与した。体重と体尺を毎月測定した。1歳齢時にヤギを屠殺し、枝肉成績とロース肉の理化学的特性を調べた。実験2では、ヤギ(実験1と同品種、2歳齢、試験開始時平均体重85.1kg)を4頭ずつ2群(NCGおよびCG)に配置した。8ヵ月間、ヤギには10:00にアルファルファヘイキューブ、16:00に配合飼料とクレイングラス乾草を給与した。飲水を不断給与した。採食量を毎日測定し、肉の臭気度を計測した。CGのヤギの腹腔内脂肪重量はNCGのそれより重かった(p<0.05)。CGの肉中のタウリンなどの機能性成分の含量はNCGのそれらより少なかった(p<0.05)。CGの肉の臭気度はNCGのそれより低かった(p<0.05)。本研究の結果、雄ヤギの去勢は肉質を低下させ、臭気を低減できることが示された。
- 著者
- Kenjiro Kimura Noriaki Kimura
- 出版者
- THE INSTITUTE OF SYSTEMS, CONTROL AND INFORMATION ENGINEERS
- 雑誌
- システム/制御/情報 (ISSN:09161600)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.3, pp.87-91, 2020-03-15 (Released:2020-09-15)
- 参考文献数
- 7