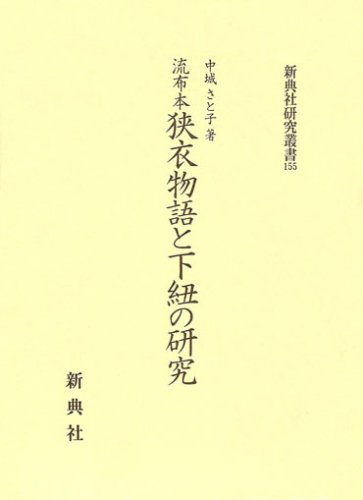- 著者
- 梶田 真
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.180-195, 2003-05-31
- 被引用文献数
- 1
バブル景気が崩壊した1990年代以降,わが国の建設業では大きな再編成が進みつつある.本稿は地理学的な観点から1980年代以降における建設業の動きを分析し,今後の動向を展望することを目的としている.本稿では特に土木業と公共投資の動きに注目する.オイルショック後の不況に対する1970年代後半の景気刺激策によって,1970年代の末期にわが国の財政は危機的な状況に陥る.1980年代に入ると欧米諸国では,小さな政府を志向したニューライトの台頭の中で公共投資が縮小し,工事内容でも維持・補修工事の比重が高まる.当時,わが国でも同様の動きが予想され,国はこのようなシナリオに基づいた建設業の産業ビジョンを発表する.しかし,バブル景気がはじまると建設需要は再び拡大し,さらに内需拡大を求める諸外国からの圧力によって公共投資額も再び増加した.これらの動きによって,わが国の建設業は1980年代に大きな再編成を経験することがなかった.しかし,1990年代に入って,バブル景気が崩壊すると民間需要は急速に縮小する.さらに,地価の大幅な下落によってゼネコン,特にバブル期に積極的に開発事業に乗り出した業者の経営状態は急速に悪化する.一方で,1970年代後半と同様に,国は1992年以降,毎年のように公共投資を中心とした景気刺激策を打ち出し,土木業中心の経営を行う地方の中小ゼネコンは好調な業績を上げた.地域的にも需要規模が急速に縮小した大都市圏と,民間需要の縮小を公共投資の拡大で補った地方圏との間で対照的な様相を呈する.1990年代後半に入ると長引く不況と,継続的に実施された景気刺激策によって国家財政は再び危機に陥る.当初,財政改革を主張する人々とさらなる景気刺激策を求める人々との間には激しい対立があった.しかし,1999年に公共投資額が減少に転じると,以後,わずか3年の間に公共投資額は10%以上も減少する.さらに,国は公共事業における事業コストの縮減と入札・契約改革を進め,再び建設業界の再編成を志向した産業ビジョンを発表する.市場の縮小によって経営状態が悪化した大手ゼネコンは事業コストの削減に乗り出し,情報化の進展による業者間競争の激化は,わが国の建設業の特徴の一つである,協力会組織の再編成をもたらしつつある.このように1990年代以降,わが国の建設業では大きな再編成が進んでいる.これは他産業において1980年代に生じた現象が,建設業ではバブル景気によって"延期された"ものと考えることができるだろう.
1 0 0 0 OA 七ツ伊呂波東都不二尽 ろ 本町丸綱五郎・日本橋富士
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ニューメディア (ISSN:02885026)
- 巻号頁・発行日
- no.1396, pp.2-3, 2013-12-02
プロ野球の2014年シーズン開幕に向けて、東経110度CS放送「スカパー!」のジャンルセットである「プロ野球セット」の構成チャンネルが変更される見込みとなった。 FOX インターナショナル・チャンネルズとTBSテレビはそれぞれ、「FOX ムービー プレミアム」と…
1 0 0 0 OA 牛わか伝次・番頭権九郎・新造白玉
- 著者
- 清水 領
- 出版者
- 日本ユダヤ学会
- 雑誌
- ユダヤ・イスラエル研究 = Studies on Jewish life and culture (ISSN:09162984)
- 巻号頁・発行日
- no.27, pp.1-12, 2013-12
1 0 0 0 IR 『稚児今参り物語』成立私考 : 和歌受容の側面から
- 著者
- 片岡 麻実
- 出版者
- 研究と資料の会
- 雑誌
- 研究と資料 (ISSN:03898121)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, pp.21-36, 2013-12
1 0 0 0 IR 『稚児今参り物語』における『木幡の時雨』受容補考
- 著者
- 片岡 麻実
- 出版者
- 研究と資料の会
- 雑誌
- 研究と資料 (ISSN:03898121)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, pp.37-40, 2013-12
1 0 0 0 OA 鋼の燒戻脆性に就て
- 著者
- 永澤 清
- 出版者
- 社団法人日本鉄鋼協会
- 雑誌
- 鐵と鋼 : 日本鐡鋼協會々誌 (ISSN:00211575)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.3, pp.174-196, 1933-03-25
In this investigation, a statistic survey on the phenomenon of temper-brittleness is made with 164 actual charges of plain carbon and special steels. The results show that the temper-brittleness is primarily related to the constitution of steel. The elements Cr, Mn, Si, Ni and P are confirmed to promote the phenomenon. Closer observation of the phenomena reveals the fact that there are two kinds of temper-brittleness : - the one is observed at the tempering range 450°∿525°, and is not affected by the rate of cooling after tempering, while the other occurs above 525° and shows the vast difference in the impact value between rapidly cooled and slowly cooled samples ; which has hitherto been known as the temper-brittleness. To distinguish these two kinds of temper-brittleness the present authur has called the former as the "First Temper-Brittleness" and the latter as the "Second Temper-Brittleness" respectively. The so-called carbide theory has been developed. When martensite, a super-saturated solid solution f carbide, is tempered, the precipitation of the carbide occurs at the tempering range 450°∿525°. This precipitation is the cause of the first temper-brittleness ; at the tempering temperature above 525° the redissolution of the precipitated carbide bigins to take place as the result of the increaing solubility of the carbide in α-iron. This causes the difference of impact value between rapid and slow coeled samples, that is the second temper-brittleness. The carbide, which causes the temper-bittleness, is ascertained to be Fe_3C or its solid solid solution ; and it is considered that the occurence of the temper-brittleness in steels depends on the correlation of these carbides and α phase. It is possible, in all steels, to observe more or less the first temper-brittleness, which is considered to be the combined effect of Si, Mn, P and eventually Cr present in the steels. It has often been reported that even in the case of samples having an identical composition and subjected to the same heat treatment, there is a great variation in the susceptibility of the temper-brittleness. The present authur believes that this is due to the existing oxides in the steels, and the more the oxides present, the larger the ratio of the susceptibility. The remeding action of Mo and W is confirmed in the temper-brittleness of several steels, and its mechanismis is described.
1 0 0 0 狭衣物語と下紐の研究 : 流布本
1 0 0 0 OA 砂浜のトビムシ群集の季節変化
- 著者
- 前田 真 田中 真悟
- 出版者
- 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.4, pp.483-489, 1982-12-30
- 被引用文献数
- 1
A sea-fronted sandy beach was selected as the study site for the seasonal change of vertical distribution of collembolan species. The dominant species there were Proisotoma sp. 1,Proisotoma sp. 2,Folsomina onychiurina, Parafolsomia sp. 1,Acherontiella sp. and Onychiurus sp. These species showed remarkable seasonal change in vertical distribution. Acherontiella sp., Proisotoma sp. 2,F. onychiurina and Parafolsomia sp. 1 inhabited in upper layer of soil from April to October, then shifted to deeper layer in winter. Onychiurus sp. showed a reciprocal pattern to this, namely its distribution shifted to deeper layer in summer. Proisotoma sp. 1 inhabited in upper layer throughout the seasons. Moreover, these specificities in the layer preference is related to the seasonal change in ambient temperature of microhabitat, and the temperature is correlated with the abundance of species population as an agent controlling the population level. Co-existence of many species, 23 species found in this study, in the same sandy beach is explained by these reciprocal pattern of seasonal abundance of species populations.
1 0 0 0 OA 梅不飛説 : 「こちふかば」の歌の解釈について
- 著者
- 志津田 藤四郎
- 出版者
- 九州龍谷短期大学
- 雑誌
- 佐賀龍谷學會紀要 (ISSN:02863758)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.29-60, 1960-12-20
- 著者
- 伊東 美緒
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 看護管理 (ISSN:09171355)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.11, pp.922-926, 2013-10
- 著者
- 伊東 美緒 本田 美和子
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 看護管理 (ISSN:09171355)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.11, pp.914-921, 2013-10
1 0 0 0 OA ナルディライジンによる体温恒常性維持機構の解明
- 著者
- 平岡 義範 西 英一郎
- 出版者
- 京都大学
- 雑誌
- 新学術領域研究(研究課題提案型)
- 巻号頁・発行日
- 2008
我々が作製したナルディライジン欠損マウス(NRDc-/-)は、寒冷環境下(4℃)での体温維持機構が破綻していた。寒冷環境下で適応熱産生を担っているのは、褐色脂肪組織(BAT)のミトコンドリア脱共役タンパク質(UCP1)である。寒冷負荷後のNRDc-/-のBATでは、UCP1の発現上昇が認められなかった。一方、NRDc-/-において熱放散が亢進していることを明らかにし、NRDc-/-における体温恒常性の破綻が、適応熱産生および熱放散抑制両者の障害によることを明らかにすることができた。
1 0 0 0 OA 予稿集
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器外科学会
- 雑誌
- 日本消化器外科学会雑誌 (ISSN:03869768)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.Supplement1, pp.1-1016, 2010 (Released:2013-05-01)
1 0 0 0 OA 瀬戸内海西部海域排出油等防除計画
- 出版者
- 海上保安庁
- 著者
- 名和 範人
- 出版者
- 京都大学数理解析研究所
- 雑誌
- 数理解析研究所講究録 (ISSN:18802818)
- 巻号頁・発行日
- vol.1430, pp.146-159, 2005-05
- 著者
- 黒川 忠英 鈴木 徹 岡内 正典 三輪 理 永井 清仁 中村 弘二 本城 凡夫 中島 員洋 芦田 勝朗 船越 将二
- 出版者
- 公益社団法人日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.2, pp.241-251, 1999-03-15
- 被引用文献数
- 32 22
アコヤガイの閉殻筋の赤変化を伴う大量へい死現象の人為的再現手法と, その病理組織学的診断手法の開発を行った。赤変異常貝の外套膜片の健常貝への移植および健常貝と赤変異常貝との同居飼育により, 赤変異常が再現された。よって, 赤変異常は感染症による可能性が極めて強い。また, 外套膜と閉殻筋の病変が, その病理組織学的診断指標として有効と判断された。