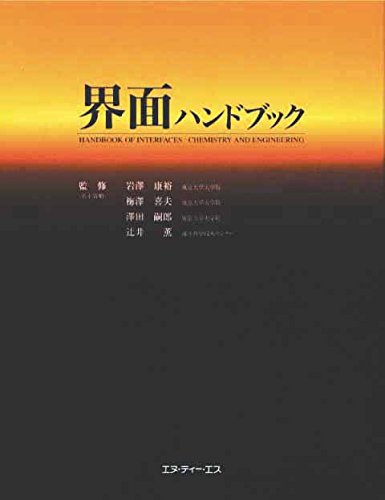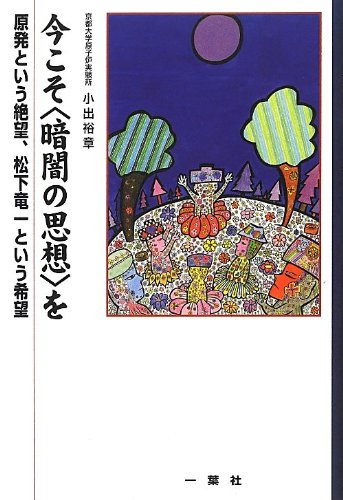1 0 0 0 OA 常盤津;戻り橋(一)
- 著者
- 河竹 黙阿弥[作詞]
- 出版者
- コロムビア(戦前)
- 巻号頁・発行日
- 1929
1 0 0 0 萬葉集の字余りと母音脱落現象
- 著者
- 佐野 宏
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 國語學 (ISSN:04913337)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, 2000-09-30
萬葉集の字余りと母音脱落現象とについては,その関連性を指摘する論が少なくない。両現象は,いずれも詳細な現象叙述によって規則性が発見されており,特に母音を中心とした古代日本語の音節構造を解明する上で重要な現象として位置づけられている。しかし,萬葉集の和歌を定型詩として捉えた場合に,字余りと母音脱落現象とがどのように共存していたのかということについては,一句中の単位が,文字数,音節数のいずれによって構成されているのかなど,その定型のあり方をめぐって,なお考察の余地が残されているようにも見受けられる。発表者は,字余りと母音脱落現象とが,どのような関係にあるのかを捉えるために,以下のような作業仮説を設けた。すなわち,字余りを回避するという動機付けによって,母音脱落現象が生じているのであれば,字余りの分布と脱落形の分布とは重なる,というものである。これが,立証されれば,字余りと母音脱落現象とは互いに密接な関係にあると判断され,母音脱落現象は字余りを回避するという動機付けによるといえるであろうし,逆にそうでないならば,両現象は,ひとまずは別に扱うべきであるということになる。本発表では,萬葉集における字余り句と母音脱落現象を生じている脱落形句との分布が具体的に重なるのか否かを,萬葉第四期の仮名書き例を対象として,毛利正守氏の字余り句の分類-A群・B群の別-をもとに調査した。その結果,A群には字余りが多く分布し,B群には字余りは稀であったのに対して,母音脱落現象-脱落形-は,むしろA群とB群とに均一に分布している。この調査結果からは,母音脱落現象は,字余りを回避するという目的ではあまり有効ではないと考えられる。したがって,字余りは,一方に脱落形を伴うと伴わないとにかかわらず,まずは和歌の唱詠上の現象として捉え,母音脱落現象は,和歌の唱詠とは関係なく,語構成上の現象と捉えた方が合理的であると考えられる。以上のことから,和歌の定型という場合に,一句中の文字数の制限はさほど強力ではなかった蓋然性が高い。
- 著者
- 柳沢 清久
- 出版者
- 日本薬史学会
- 雑誌
- 薬史学雑誌 (ISSN:02852314)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.p41-54, 1990
- 被引用文献数
- 2
1 0 0 0 IR 『エミール』における奇跡と啓示の問題
- 著者
- 吾妻 修
- 出版者
- 大阪教育大学
- 雑誌
- 大阪教育大学紀要. I, 人文科学 (ISSN:03893448)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.169-184, 2004-02
「サヴォワの助任司祭の信仰告白」第二部において、ルソーはキリスト教の不合理とカトリック教会の在り方に対する批判を展開している。批判の論議は主に奇蹟と啓示を巡って行われている。奇蹟と啓示の基本的な理解を踏まえながら、ルソーの批判がどのような意味を持つのかを探ってみる。"La profession de foi du vicaire savoyard" de l'Emile se compose de deux parties: la première décrit le vicaire qui, au bout des doutes sur la vie, tombe dans un désespoir et après des tentatives difficiles retrouve sa foi; c'es ce que nous avons déjà examiné;la deuxième présente le vicaire comme un personnage qui critique sévèrement le christianisme et l'église catholique. Nous espérons ici éclaicir les points essentiels de sa critique. Les thèmes qu'on a choises sont en générale les miracles et la révélation. Au début nous avons indiqué que la manière de critiquor dont Rousseau se sert est très particulière; Il donne toute la puissance à la raison,en supprimant le sentiment immédiat ou le bon sens, il repousse sans réserve l'ambigu et l'incompréhensible. D'ailleurs c'est sa mesure volontaire. En y faisant toujours attention, nous avons mis en œuvre une perspective toute contraire; nous avons eu recours à l'instinct, aux connaissances quotidiennes pour examiner des arguments de Rousseau; par cela nous avons cru pouvoir mettre en relief le vrai sens de ses travaux. Quant aux miracles, ce que Rousseau reproche c'est que des prodiges transmis sont écrits dans les livres et que pour les connaître il faut beaucoup de témoignages, même invérifiables, des gens inconnus. Il revendique le dialogue immédiat de Dieu et de l'homme. De notre côté nous avons indiqué que la croyance religieuse se fonde sur un artre niveau que la réalité de l'événement st dépasse le problème du vrai et du faux. En matière de révélation, Rousseau parle d'abord de l'existence des religions similaires dans le monde, à côté du chiristianisme. Or il n'y a pas moyen de discerner d'entre elles une seule vraie. Il nie ainsi la suprématie du christianisme. Puis il cite une autre difficulté: admettons que le christianisme soit une seule vraie religion; alors que doit-on penser d'un homme qui est mort sans avoir entendu des paroles de Jesus-Christ? En apparence les protestations de Rousseau sont de pure spéculation. Mais nous avons remarqué que ses idées suggerént l'existence de la vérité qui dépasse en même temps l'absolu et le relatif, et qu'elles nous donnent l'occasion de mettre en cause notre idée banele du temps. Pour conclure, nous avons su que Rousseau pratique la critique pour faire connaître des bornes de la raison, et à travers de son échec prépare une nouvelle approche du christianisme.
1 0 0 0 OA 光学文字認識によるタンジブルミュージックシーケンサの提案
- 著者
- 卯田 駿介 馬場 哲晃 串山 久美子
- 雑誌
- 研究報告エンタテインメントコンピューティング(EC)
- 巻号頁・発行日
- vol.2013-EC-27, no.26, pp.1-4, 2013-03-08
近年光学画像認識技術の発展により,実物体と画像認識を組み合わせた “AR” によるアプリケーションが多く報告されている.AR に利用されるマーカには,オブジェク卜の形,色の他,光学マーカと呼ばれる特殊な 2 次元マーカなどが利用されるが,これらは実物体の物理特徴や印刷パターンであるため,ユーザによって作りだすことはできない.そこで著者らは,ユーザによって手軽に AR マーカを作ることができれば,より多くのユーザにとって AR システムにおけるユーザビリティの向上につながると考えた.具体的な手法としては,光学文字認識を利用して,手書き文字を AR マーカのように扱うことを検討している.本稿ではそれらの実験段階として,実物体に印刷された文字を利用したシーケンス型電子楽器 「Alphabet Sequencer」 を制作した.本稿では,「Alphabet Sequencer」 のシステムとその体験結果を報告する.
1 0 0 0 日本人の在胎別出生時体格基準値
1 0 0 0 OA ホッキョクグマ(Ursus maritimus)咀嚼筋の扁平な頭骨形態への適応
- 著者
- 佐々木 基樹 遠藤 秀紀 山際 大志郎 高木 博隆 有嶋 和義 牧田 登之 林 良博
- 出版者
- 社団法人日本獣医学会
- 雑誌
- The journal of veterinary medical science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.7-14, s・iii, 2000-01
- 被引用文献数
- 3 8
ホッキョクグマ(Ursus maritimus)の頭部は,ヒグマ(U. arctos)やジャイアントパンダ(Ailuropoda melanoleuca)に比べて扁平で,体の大きさの割に小さいことはよく知られている.本研究では,ホッキョクグマとヒグマの頭部を解剖して咀嚼筋を調べた.さらに,ホッキョクグマ,ヒグマそしてジャイアントパンダの頭骨を比較検討した.ホッキョクグマの浅層咬筋の前腹側部は,折り重なった豊富な筋質であった.また,ホッキョクグマの側頭筋は,下顎骨筋突起の前縁を完全に覆っていたが,ヒグマの側頭筋は,筋突起前縁を完全には覆っていなかった.ホッキョクグマでは,咬筋が占める頬骨弓と下顎骨腹縁間のスペースは,ヒグマやジャイアントパンダに比べて狭かった.さらに,側頭筋の力に対する下顎のテコの効果は,ホッキョクグマが最も小さく,ジャイアントパンダが最も大きかった.これらの結果から,ホッキョクグマは,下顎骨筋突起の前縁を側頭筋で完全に覆うことによって,下顎の小さくなったテコの効果を補っていると考えられる.また,ホッキョクグマでは,咬筋が占める頬骨弓と下顎骨腹縁間のスペースが狭いことから,ホッキョクグマは,ヒグマ同様の開口を保つために豊富な筋質の浅層咬筋前腹側部を保有していると推測される.本研究では,ホッキョクグマが,頭骨形態の変化に伴う咀嚼機能の低下を,咀嚼筋の形態を適応させることによって補っていることが示唆された.
1 0 0 0 OA 中将姫説話の近世演劇化 : 土佐浄瑠璃「中将姫」を中心にして(水野弥穂子教授記念号)
- 著者
- 鳥居 フミ子
- 出版者
- 東京女子大学
- 雑誌
- 日本文學 (ISSN:03863336)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, pp.1-15, 1987-03-15
中将姫説話が江戸時代にどのように演劇化されていったかを、土佐浄瑠璃「中将姫」を中心にして考えてみたい。中将姫は当麻寺の曼陀羅の制作者として鎌倉時代以来喧伝されてきた女性である。その説話は、縁起・絵解き・絵巻などとなって、当麻寺の宣伝に一役を担って、大衆の間に根を下ろしていった。中世においては、物語化されてお伽草子となり、さらにこれが劇化されて、能にも作られている。江戸時代を迎えて、中将姫説話は、歌舞伎や浄瑠璃に仕組まれて、変貌しながら大衆の中に浸透していったのである。その変貌の様相に、中世説話の近世演劇化の実態を跡づけることができるように思われる。
1 0 0 0 界面ハンドブック
- 著者
- 岩澤康裕 [ほか] 監修
- 出版者
- エヌ・ティー・エス
- 巻号頁・発行日
- 2001
1 0 0 0 IR 環境と人間と文学--ケルトと出雲を繋ぐ八雲文学の一考察
- 著者
- 吉津 成久
- 出版者
- 梅光学院大学国際言語文化学会
- 雑誌
- 梅光言語文化研究 (ISSN:18842216)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.39-55, 2010-03
In the middle of the 21st century, in 2050, our earth is predicted to face a serious crisis because we shall run short of water by 75 percent that year. At present many scholars of authority in the world of environmental problems are formulating their theory that the way overcoming the crisis of the earth is found in learning from the traditional ways of living of two tribes, the Celts and the Japanese, especially the Izumo tribes. The ways of these tribes have beeninherited from ancient times. In the course of history these two tribes often suffered severe defeats. For instance, the Celts from whom European civilization had its origin were driven away from the central parts of Europe to the western fringes by the Romans and the Germans. Likewise the Izumo tribes of Japan, the torch bearers of the native culture of Japan, represented by Oh-kuni-nushi-no-Mikoto, were compelled to hand their territory over to the Yamato Imperial Court (the Yamato-Chotei). However, these two tribes are said to hold the key to the solutions of the question about the collapse of the earth. This paper explores this key and discusses the literature of Yakumo Koizumi, that is, Lafcadio Hearn, in his relationship with both the Celts and the Izumos.
1 0 0 0 OA 尿素の花(やってみよう界面の実験)(<特集>界面のはたらき)
- 著者
- 佐々木 恒孝
- 出版者
- 社団法人日本化学会
- 雑誌
- 化学教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.6, 1985-12-20
1 0 0 0 OA 独唱:ブラームスの子守唄
- 著者
- 旗野 十一郎[作詞]
- 出版者
- コロムビア(戦前)
- 巻号頁・発行日
- 1939
1 0 0 0 今こそ「暗闇の思想」を : 原発という絶望、松下竜一という希望
1 0 0 0 OA 震災直後の個人交通需要変動の事前評価に関する研究~経路依存性からのアプローチ~
- 著者
- 崔 宰英
- 巻号頁・発行日
- 2012
科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書:挑戦的萌芽研究2009-2011
1 0 0 0 OA 糖尿病自己管理行動のメカニズムモデルの開発
- 著者
- 柴山 大賀
- 巻号頁・発行日
- 2012
科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書:若手研究(B)2009-2011
1 0 0 0 OA 体育で習熟する子どもの運動能力を絶対評価する適応型コンピュータテスト
- 著者
- 西嶋 尚彦
- 巻号頁・発行日
- 2012
科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書:挑戦的萌芽研究2010-2011