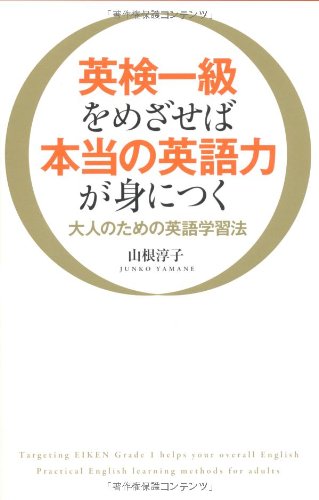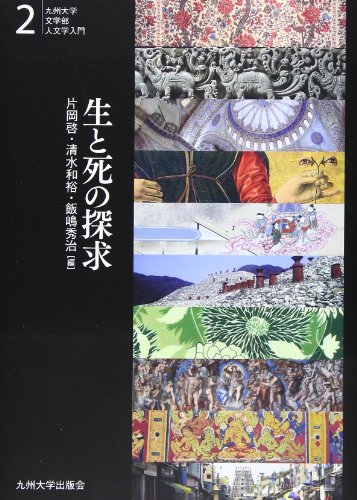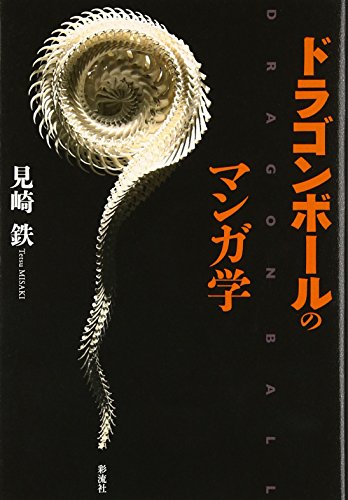1 0 0 0 IR ヴァイマル共和制末期における地方の農民団体とナチス : テューリンゲン州を中心に
- 著者
- 熊野 直樹
- 出版者
- 九州大学
- 雑誌
- 法政研究 (ISSN:03872882)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.933-970, 1999-12-20
- 著者
- 熊野 直樹
- 出版者
- 九州大学
- 雑誌
- 法政研究 (ISSN:03872882)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.2, pp.287-308, 2003-10-20
1 0 0 0 IR 高校生における居場所感と自己肯定感および無効化環境体験との関連性
- 著者
- 斎藤 富由起 小野 淳 社浦 竜太 守谷 賢ニ Fuyuki Saito Ono Atushi Syaura Ryuta Moriya Kenji 千里金蘭大学 生活科学部 児童学科 千里金蘭大学 生活科学部 児童学科 ものつくり大学 学生相談室 文教大学大学院 人間科学研究科
- 出版者
- 千里金蘭大学
- 雑誌
- 千里金蘭大学紀要 (ISSN:13496859)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.69-81,
子どもの権利研究において居場所感と自己肯定感の関連性が指摘されているが、これらを実証的に検討した研究は非常に乏しい。本研究では、子どもの権利における心理学的実証研究の一環として、全日制普通科高校生版居場所尺度の作成を試み、自己肯定感との関連性を検証した。その結果、信頼性と妥当性のある居場所尺度が作成された。研究2では、居場所感と無効化環境体験(Invalidating Environment)の関連性を検討した結果、両要因に負の相関関係が確認された。
1 0 0 0 エジプト、メンフィス・ネクロポリスの文化財保存面から観た遺跡整備計画の学際的研究 : 研究報告集 = The Memphite Necropolis site management studies
- 著者
- 吉村作治編著
- 出版者
- 早稲田大学エジプト学研究所
- 巻号頁・発行日
- 2011
- 著者
- 赤松 幹之
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会誌 (ISSN:09135693)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.11, pp.1176-1182, 1993-11-25
- 被引用文献数
- 15
形は視覚で知覚できるが,指で触ってでもできる.この異なるモダリティの間の対応関係は,能動的に触る運動をしたり,その運動が眼で見えたり,また触っている形の縁の触覚刺激があると,より正しく獲得される.その一方,視覚だけでなく触覚もあると,触る運動が速くなったりする.すなわち,視覚と触覚と運動とは相互に結び付きを強めるように働いている.そこで,視覚だけでなく触覚呈示もできるマウス型インタフェース装置を構築して,ポインティング操作の評価をしてみると,操作時間が短くなるなどの効果があることがわかった.
1 0 0 0 『ヒポクラテス全集』における排尿障害の記述について
- 著者
- 斉藤 博
- 出版者
- 社団法人日本泌尿器科学会
- 雑誌
- 日本泌尿器科學會雜誌 (ISSN:00215287)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.3, pp.432-441, 2005-03-20
- 被引用文献数
- 2
(目的)ヒポクラテス(紀元前460年頃)は古代ギリシア, コスの有名な医師で, 彼の業績は, 後世『ヒポクラテス全集』に記載されている.私は『ヒポクラテス全集』での排尿障害を検討した.(方法)『ヒポクラテス全集』での排尿障害をラーブ, 大槻, 今版で採集し, コス学派とクニドス学派とで排尿障害を比較した.(結果)排尿障害が67カ所(文, または, 節) : 排尿困難50, 尿閉15, 尿失尿2, または, 3(排尿困難との合併が1)記載されていた.術語としてストラングリエ(滴状尿)は20カ所中コス学派12(60%), クニドス学派5(25%), ドゥスリエ(排尿困難)は30カ所中コス学派13(43%), クニドス学派17(53%)であったが, 有意ではなかった(X^2検定で, p>0.05).激しい疼痛を伴う排尿困難, 尿閉はコス学派の記載で認められた.ストラングリエは慢性化するが, 合併症がなければ死ぬことはない.2種類の尿失禁があり, 多量の尿失禁と, 滴状尿失禁で, 前者は神経因性膀胱, 後者は溢流性尿失禁と考えられる.尿道カテーテル法, 利尿剤が, すでに, 『ヒポクラテス全集』に記載されていた.瀉血法, 鎮痛剤が排尿困難の治療に用いられていた.(結論)排尿障害は4種類認められる.すなわち, 排尿困難, または, ディスリア, 滴状排尿困難症, または, ストラングリ, 尿閉と尿失禁である.重症の排尿障害はコス学派の記載に多く認められる.
- 著者
- 本富 彰広
- 出版者
- 日本西洋史学会
- 雑誌
- 西洋史学 (ISSN:03869253)
- 巻号頁・発行日
- no.106, pp.p118-130, 1977
1 0 0 0 OA 審判記録が語る「漢奸裁判」
- 著者
- 劉 傑
- 出版者
- 早稲田大学社会科学部学会
- 雑誌
- 早稻田人文自然科學研究 = The Waseda journal of general science (ISSN:02861275)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, pp.65-89, 1998-03
論文
1 0 0 0 OA 日中戦争下の「親日派」-「漢奸裁判」試論・その二-
- 著者
- 劉 傑
- 出版者
- 早稲田大学社会科学部学会
- 雑誌
- 早稻田人文自然科學研究 = The Waseda journal of general science (ISSN:02861275)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, pp.79-111, 1999-03
論文
1 0 0 0 IR 日本人を対象とした室内温湿度条件の至適域に関する実験研究 : 夏季至適域の提案
- 著者
- 志村 欣一 堀越 哲美 山岸 明浩
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.480, pp.15-24, 1996
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 23 4
The objectives of this paper is to propose thermal comfort zone based on the experimental data of the optimum air temperature and humidity conditions for Japanese. Experiments were conducted on 650 Japanese young men and wemen in the summer season under 16 kinds of the following combined conditions : air temperature of 22℃, 24℃, 26℃ and 28℃, and absolute humidity of 7g/kg', 10g/kg', 13g/kg' and 16g/kg' under still air in which mean radiant temperature is nearly equal to air temperature. The following results were obtained : 1) The Comfort Zone for slightly clothed (0.45clo), sedentary young Japanese is represented in the envelope in which operative temperature range extents 24.7℃ to 27.6℃ on the 6g/kg' absolute humidity line, and 24.1℃ to 26℃ on the 80% relative humidity curve. 2) The mean skin temperature stands between 33℃ and 34℃ in the thermal comfort conditions.
1 0 0 0 IR 学習指導方法の習得過程に関する研究-教師の教育行為への知識社会学的接近-
- 著者
- 酒井 朗 島原 宣男 Akira Sakai Nobuo Shimahara 東京大学 ラトガーズ大学 University of Tokyo Rutgers University
- 出版者
- 東洋館
- 雑誌
- 教育社会学研究 = The journal of educational sociology (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, pp.135-153, 1991-10-20
- 被引用文献数
- 1
The purpose of this paper is to present, from a sociology of knowledge perspective, a critical analysis of dominant traditional teaching methods deeply rooted in the culture of teaching. The previous studies on this research topic were influenced by Western scholars and failed to offer a clear understanding of the process of learning teaching methods. We use an ethnographic approach to study the Process. Based on an analysis of our ethnographic data we conclude that: (1) Teachers uncritically accept the traditional teaching method as a taken-for-granted approach to teaching. These methods are not used as a survival strategy to cope with constraining situations they encounter. (2) The reason why teachers predominantly use the traditional method is grounded in ethnopedagogy which integrated various aspects of teaching. Beginning teachers come to share ethnopedagogy through intersubjective interaction with experienced teachers. Its emphasis is placed not on instructional methods but on the relationship of trust between teachers and students. Because the traditional instructional method is compatible with ethnopedagogy, teachers are not actively seeking new methods. (3) Structural factors contribute to the perpetuation of ethnopedagogy. First, the absence of interaction that exists between universities and schools tends to prevent infusion into schools of innovative pedagogical theories formulated by scholars. Second, relatively closed interaction among teachers is conducive to the continuation of traditional pedagogy. Third, ethnopedagogy is the most influential practical approach that integrated various aspects of teaching and teacher responsibilities. (4) Influence of official policies of the Ministry of Education on deciding teaching strategies is not obvious. Rather it is established in its control of curriculum and the legitimacy that suggest traditional instructional methods.
1 0 0 0 OA 教育管理職者の職業的社会化 : 全国公立小・中学校校長調査の分析(教師(2))
- 著者
- 篠原 清夫
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 日本教育社会学会大会発表要旨集録
- 巻号頁・発行日
- no.53, pp.306-307, 2001-10-06
- 著者
- 川村 光
- 出版者
- 滋賀大学
- 雑誌
- 滋賀大学教育学部紀要. I, 教育科学 (ISSN:13429280)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, pp.135-146, 2007
1 0 0 0 唯心の浄土 : 作品研究『当麻』 (佐々木孝二教授退官記念号)
- 著者
- 原田 香織
- 出版者
- 弘前大学
- 雑誌
- 弘前大学国語国文学 (ISSN:09113266)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.55-75, 1992-03
1 0 0 0 プラチナ化合物, 5-FU併用化学療法の基礎的検討
1 0 0 0 生と死の探求
- 著者
- 片岡啓 清水和裕 飯嶋秀治編
- 出版者
- 九州大学出版会
- 巻号頁・発行日
- 2013
1 0 0 0 ドラゴンボールのマンガ学
- 著者
- 斎藤 富由起 小野 淳 社浦 竜太 山内 早苗 井手 絵美 吉森 丹衣子
- 出版者
- 千里金蘭大学
- 雑誌
- 千里金蘭大学紀要 (ISSN:13496859)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.19-33, 2010-10-29
特別支援教育の中でADHDの特に衝動性と多動性が小学校内で「問題行動」と認識されやすいことが指摘されている(斎藤・小野・井手,2008).この結果は,家庭が行う支援構造と小学校での支援構造を比較検討することで,家庭と学校の支援への認識にずれがない「統合的な共通理解モデル」を作成する必要性を意味する.そこで本研究では家庭と小学校の調整役を担う臨床心理士に半構造化面接を試み,「家庭での支援モデル」と「小学校での支援モデル」を導いた.また両モデルの相異を踏まえ,時間軸の認識を書くとした協働的な「共通理解モデル」が提案された.
- 著者
- 井上 大介 山崎 祐二 筒井 裕文 清 和成 惣田 訓 藤田 正憲 池 道彦
- 出版者
- 公益社団法人日本生物工学会
- 雑誌
- 日本生物工学会大会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.21, 2009-08-25