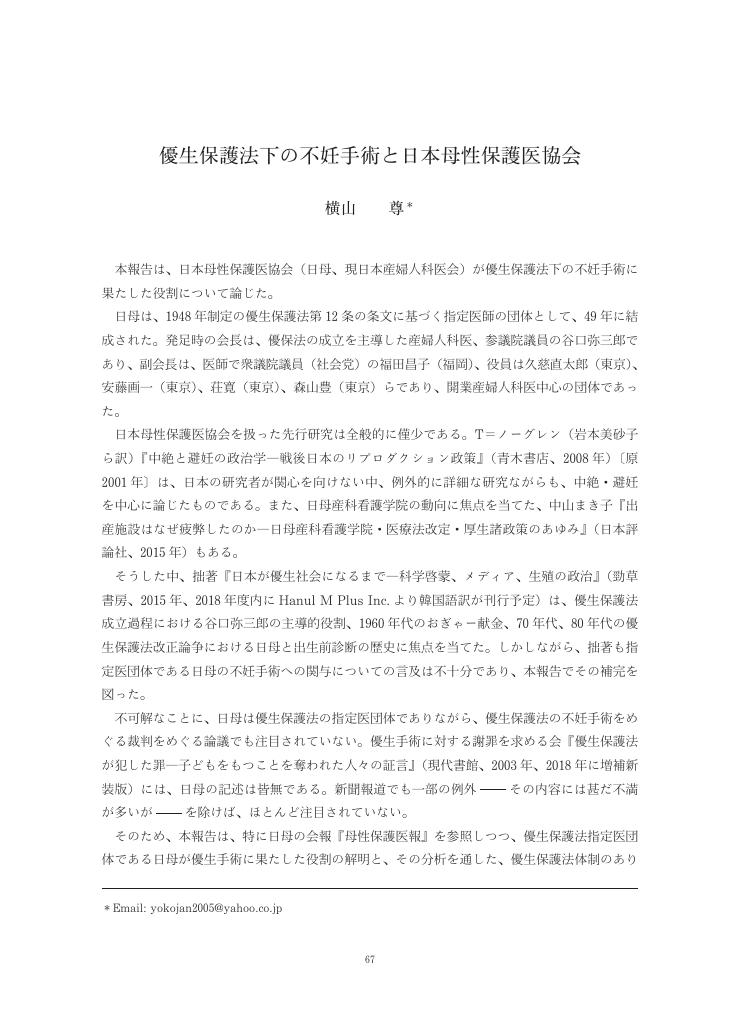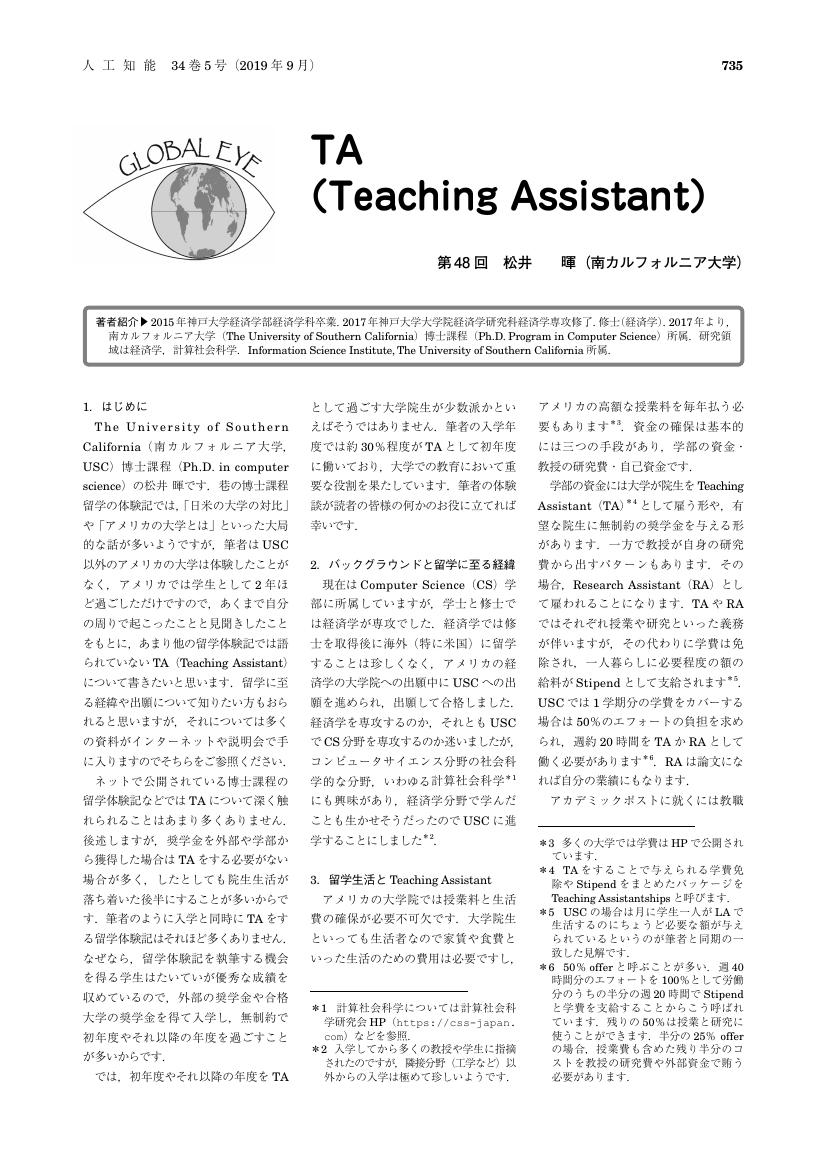4 0 0 0 OA 東急ハンズの誕生1と浜野安宏 : ストア・コンセプトの設計
- 著者
- 加藤 健太 Kenta Kato 高崎経済大学経済学部 Takasaki City University of Economics
- 雑誌
- 高崎経済大学論集 = The Economic Journal of Takasaki City University of Economics (ISSN:04967534)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.4, pp.29-49, 2013-03-18
4 0 0 0 OA 優生保護法下の不妊手術と日本母性保護医協会
- 著者
- 横山 尊
- 出版者
- 日本科学史学会生物学史分科会
- 雑誌
- 生物学史研究 (ISSN:03869539)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, pp.67-68, 2019-02-28 (Released:2020-09-08)
4 0 0 0 OA ミヒャエル・ハウスケラー+アリソン・ストーン「出生について」
- 著者
- 仲井 慧悟
- 出版者
- 『人文×社会』編集委員会
- 雑誌
- 人文×社会 (ISSN:24363928)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.7, pp.155-183, 2022-09-15 (Released:2022-09-19)
- 著者
- 伊藤 将人
- 出版者
- 『人文×社会』編集委員会
- 雑誌
- 人文×社会 (ISSN:24363928)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.2, pp.111-128, 2021-06-15 (Released:2021-06-18)
4 0 0 0 OA 反生殖主義とは何か その定義と内容に関する論点整理
- 著者
- 榊原 清玄
- 出版者
- 『人文×社会』編集委員会
- 雑誌
- 人文×社会 (ISSN:24363928)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.2, pp.35-51, 2021-06-15 (Released:2021-06-18)
4 0 0 0 OA 倫理的消費ともうひとつの快楽主義 K.ソパーによる消費主義批判の刷新
- 著者
- 畑山 要介
- 出版者
- 経済社会学会
- 雑誌
- 経済社会学会年報 (ISSN:09183116)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.55-65, 2020 (Released:2021-04-01)
This paper aims to consider an implication of ethical consumption as a pursuit of self-interests from the perspective of Kate Soper's concept “alternative hedonism.” Ethical consumption has been regarded as an expression of anti-consumerism, but Soper recognizes that ethical consumers experience the intrinsic pleasure in their environmental and social preservations. Soper emphasizes that ethical consumption should be understood on the base of the theory of hedonism rather than asceticism, however it does not mean maintain of existing consumerism but renovation of the criticism of consumerism. This paper examines the theoretical structure of alternative hedonism through Soper's criticisms of Amartya Sen and Theodor Adorno. In the criticism of Sen, Soper insists that citizenship and individual living standard should not be separated but should understand the concept of living standard in the term of quality of life and regard environmental and social consideration as an improvement of the living standard. Then, in the criticism of Adorno, Soper supports the Adorno's hedonistic position against modern consumerism but points out that he excludes any personal experiences and assume “true&rldquo; need which located in the sublime culture. Soper attempts “de-naturalization” of Adorno's hedonism through the studies about symbolism and provides the perspective that the pleasure of ethical consumption is contiguous with esthetics of ordinary and banal everyday consumption. The perspective of alternative hedonism, therefore, has an implication that ethical consumption would play an important role in steady-state economy but based on consumer's pursuit of own pleasure.
4 0 0 0 OA 日本仏教のグローバル化に関する一考察-経営とマーケティングの観点からの分析-
- 著者
- 中村 久人
- 出版者
- 学校法人 東洋大学現代社会総合研究所
- 雑誌
- 現代社会研究 (ISSN:1348740X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2019, no.17, pp.73-82, 2019 (Released:2020-04-24)
4 0 0 0 OA 斡里札河の戦いにおける金軍の経路
- 著者
- 白石 典之
- 出版者
- 内陸アジア史学会
- 雑誌
- 内陸アジア史研究 (ISSN:09118993)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.27-48, 2016-03-31 (Released:2017-05-26)
The purpose of this study is to clarify the war situation in the "Battle of the River Ulz (Ulja)" fought in 1196 between the Jin dynasty and the Tatars (Zubu). This battle is also famous for the fact that the young Chinggis khan participated in it on the Jin side. By contributing to the Jin victory, Chinggis khan obtained the backing of the Jin and grew powerful. The main documentation for the study is the Serven khaalga inscription discovered by the authors in Bayankhutag District, Khentii Province, Mongolia. It consists of two inscriptions, one in Chinese and one in Jurchen, and the major portion of both notes the names of the places which the Jin army passed through during the Battle of the River Ulz. By carrying out a multilateral examination of these place names, from a historical, geographical and archaeological perspective, the authors managed to show clearly the route of the Jin army on a map. They were also able to shed light upon the historical and geographical situation in the eastern part of the Mongol plain at that time. The results of the study should greatly contribute to our understanding of the Jin dynasty's control of the Mongol plain and the prehistory of the rise of the Mongol Empire.
4 0 0 0 OA 岐阜市郊外住宅地における高齢者の居住実態からみた 住み続けられる居住環境実現への課題
- 著者
- 久保 倫子 駒木 伸比古 田中 健作
- 出版者
- 日本都市地理学会
- 雑誌
- 都市地理学 (ISSN:18809499)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.76-90, 2020-03-15 (Released:2021-08-15)
- 参考文献数
- 80
- 被引用文献数
- 1
本研究は,高齢化と居住環境の悪化が進展する郊外住宅地の居住実態について,高齢者の身体・住宅,居住地域,さらに広域のスケールに着目し,高齢者の生活実態や生活上認識する不安,居住環境を総合的に分析することにより,高齢期に住み続けられる居住環境の実現に向けた課題を明らかにすることを目標とした.その一過程として,岐阜市郊外のK地区をとりあげた.特に本研究では,食生活,住宅の維持管理,居住地域の物質的・社会的環境, 広域的な活動および交通手段の考察に重点を置いた.その結果,事例地区の高齢者の多くは地域への愛着と自立した生活継続への希望を有しているが,身体,住宅,居住地域,より広域なスケールで不安や困難に直面しており,それらの克服に向けた調整を通じて住み続けられる条件を蓄えていることが明らかとなった.高齢化と都市縮退に対応した都市インフラ整備,サービス環境の充実,さらに高齢者の変化と多様性を踏まえた,総合的な議論が求められる.
4 0 0 0 血液脳関門を介さない皮膚から脳への新規薬剤輸送機構の解明
結節性硬化症(TSC)はmTORC1(エムトールC1)の恒常的活性化で、全身に腫瘍やてんかんを発症する遺伝性疾患である。TSCの皮膚病変治療薬である、mTORC1阻害薬シロリムスの塗り薬を使用していた患者の中に、皮膚への少量塗布で血中シロリムス濃度の上昇なく、てんかんが改善する患者が現れた。そこでてんかんを有するTSCのモデルマウスで検討したところ、マウスでも同様の結果が得られた。皮膚塗布により、シロリムスが血液を介さずに、脳へ輸送された可能性が考えられた。本研究ではその機構の解明を行う。
4 0 0 0 OA 朝鮮総督府鉄道局による複斜材型トラス橋梁の開発と耐弾性能
- 著者
- 高橋 良和 小嶋 進太郎 Mya San WAI
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集D2(土木史) (ISSN:21856532)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.1, pp.16-31, 2020 (Released:2020-01-20)
- 参考文献数
- 62
- 被引用文献数
- 1 1
本研究では,第二次世界大戦末期に朝鮮半島で建設された複斜材型トラス橋梁について,朝鮮総督府鉄道局の小田彌之亮技師による回顧や当時の雑誌等の記述を組み合わせることにより,その開発の経緯を整理した.戦争時に爆撃の対象となる重要構造物である橋梁について,昭和10年代に行われた耐弾性能を高めるための技術的検討を整理し,内的・外的不静定,吊構造などの異なる技術の組み合わせ(多様性)を推奨していたこと,また高次不静定橋梁の構造計算は,近似的解法による一次応力の算出だけではなく,曲げによる二次応力も算出し,その精度が極めて高いことを証明した.また,中国と北朝鮮間の国際橋梁である鴨緑江橋梁について,その設計,架設状況について整理するとともに,実際の被害を踏まえた耐弾性能について検証した.
4 0 0 0 OA 武家事紀
- 著者
- 素行子山鹿高興 著
- 出版者
- 山鹿素行先生全集刊行会
- 巻号頁・発行日
- vol.下巻, 1918
4 0 0 0 OA プライミングの認知心理学 潜在認知・潜在記憶
- 著者
- 川口 潤
- 出版者
- 日本失語症学会 (現 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会)
- 雑誌
- 失語症研究 (ISSN:02859513)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.225-229, 1995 (Released:2006-06-02)
- 参考文献数
- 12
本論文では,最近の認知心理学におけるプライミング研究について概観した。プライミング効果とは,先行刺激を処理することによって後続刺激の処理が促進されることを指すが,一般にプライミング効果と呼ばれている現象には,意味的プライミング効果と反復プライミング効果がある。意味的プライミング効果は,意味的関連のある先行刺激によってターゲット情報の処理が促進される現象であり,2刺激の時間間隔は数 10 msec から数秒以内である。一方,反復プライミング効果は,ターゲット情報と同一の先行情報によって処理が促進される現象であり,2刺激間の間隔は比較的長期間である。それぞれ,被験者が先行情報を意識的認知している場合といない場合との比較が関心を集めている。ただ,このような意識を伴わない処理 (潜在認知・潜在記憶) の測定には十分な注意が必要である。今後,認知心理学的研究と神経科学的・神経心理学的研究との連携が期待される。
4 0 0 0 OA グローバルアイ〔第48 回〕TA(Teaching Assistant)
- 著者
- 松井 暉
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.5, pp.735-738, 2019-09-01 (Released:2020-09-29)
4 0 0 0 陶彫家寺内信一に関する先行研究とその問題点
- 著者
- 西村 佳菜子
- 出版者
- 崇城大学芸術学部
- 雑誌
- 崇城大学芸術学部研究紀要 (ISSN:18839568)
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.3-25, 2013
4 0 0 0 OA エアフィルタユニットの性能
- 著者
- 上島 寉也
- 出版者
- 日本エアロゾル学会
- 雑誌
- エアロゾル研究 (ISSN:09122834)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.4, pp.265-277, 1989-12-20 (Released:2011-06-23)
- 参考文献数
- 16