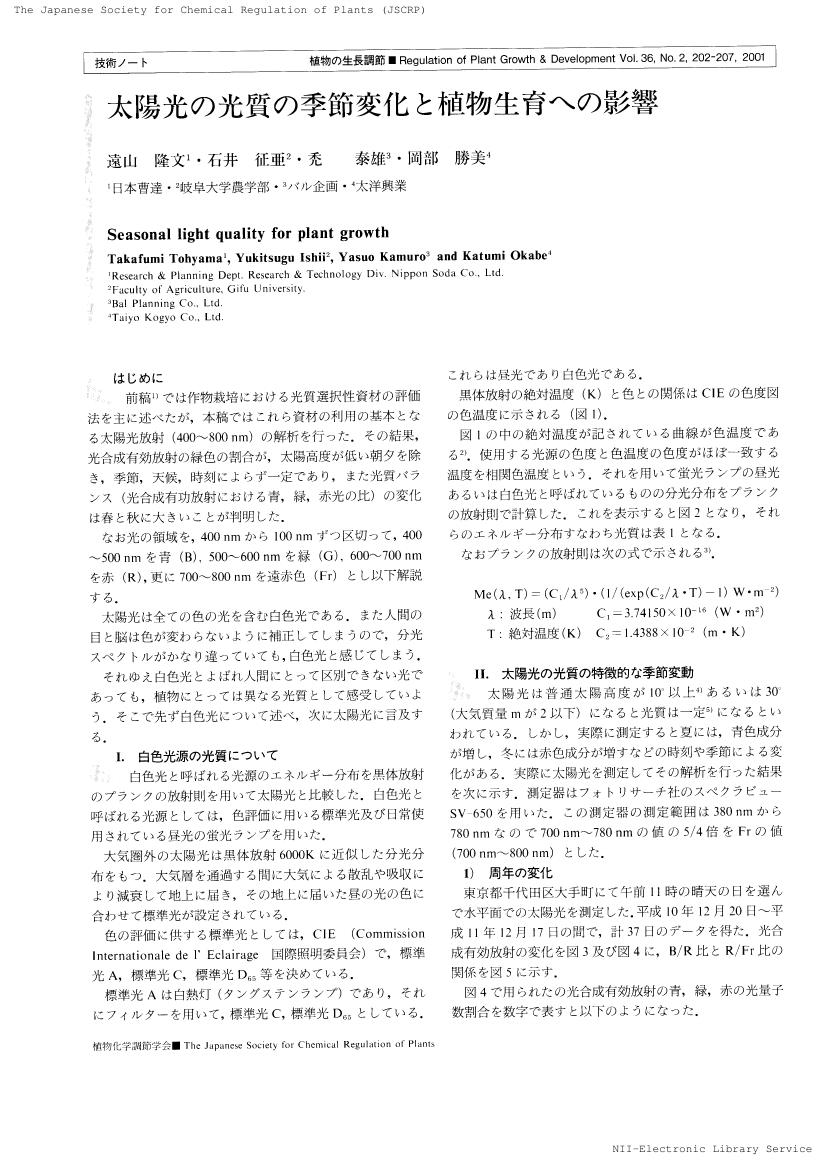2 0 0 0 OA 並行プロセス実験キット
- 著者
- 多田 好克 寺田 実
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告システムソフトウェアとオペレーティング・システム(OS)
- 巻号頁・発行日
- vol.1986, no.84(1986-OS-033), pp.1-7, 1986-12-12
本稿では,Unixの一ユーザプロセス上で動く「小さなプロセス」実現法を説明する.この方法を使えば,Unixのプログラミング環境下でスケジューリングやプロセス間通信等の実験を行うことができる.本実現法では,言語Cの一部の関数がプロセスのように振舞う.また,それらはCPU横取りによって継続的な実行を制限される.これらの仕組みは言語Cのみで記述されており,Unixのカーネルを変更する必要はない.なお,現実,この仕組みは,VAX-11 (4.2BSD) VAX-11(Ultrix) Sunワークステーション(4.2BSD) ME THEUS Lambda-710 (4.1BSD) SHARP IX-5 (System V) NEC PC-UX (System III)等,様々のUnixシステム上で稼働している.
2 0 0 0 OA 精神疲労の検査
- 著者
- 橋本 邦衛
- 出版者
- Japan Human Factors and Ergonomics Society
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.3, pp.107-113, 1981-06-15 (Released:2010-03-11)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 8 5
2 0 0 0 OA ジェイムズ・ステュアートの銀行論
- 著者
- 古谷 豊
- 出版者
- The Japanease Society for the History of Economic Thought
- 雑誌
- 経済学史研究 (ISSN:18803164)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.1-17, 2007-12-25 (Released:2010-08-05)
- 参考文献数
- 17
Much ink has been spent over the last few decades on James Steuart's theory on banks. Critics are united in the view that his ‘banks upon mortgage’ is an idea of central importance in Steuart's theory on banks. They propose that insofar as Steuart argued against bank lending upon mercantile credit because it is precarious, his concept of bank credit upon mortgage must be regarded as a representative pillar of his theory. This understanding has also supported the claim that Steuart's theory on banks is outmoded in the sense that it gives little or no allowance for banks providing mercantile credit.If we consider Steuart's theory on banks within his whole chain of arguments, that interpretation is open to question. Steuart's principles of political economy, including his theory on banks, are built within a historical structure. He denies bank credit based on mercantile credit, only when the society is in the infancy of trade. In his theory on banks, he posited three classifications: ‘banks upon private credit’ (i.e. upon mortgage), ‘banks upon mercantile credit, ’ and ‘banks upon public credit, ’ each with a different role in the development of the economy.Considered in this perspective, the significance of Steuart's theory on banks lies in that the principles on which bank credit is based extend according to the development of trade and industry and to the policy of statesmen. His theory of banks must be regarded as a part of his arguments on providing money in proportion to the circulation.
2 0 0 0 OA 名所江戸百景 びくにはし雪中
2 0 0 0 OA 太陽光の光質の季節変化と植物生育への影響
- 著者
- 遠山 隆文 石井 征亜 禿 泰雄 岡部 勝美
- 出版者
- 一般社団法人 植物化学調節学会
- 雑誌
- 植物の生長調節 (ISSN:13465406)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.202-207, 2001-11-30 (Released:2017-09-29)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 2
申請者の研究はベルクソン哲学を音楽との関わりについて考察するものである。これまでに(1)20世紀の作曲理論をベルクソン哲学の観点から解釈すること、(2)ベルクソンの哲学理論を演奏という具体的な芸術活動の場に置き直す、という二つの方向で研究を行ってきた。平成18年度は、上記二つの方向性をふまえながら、20世紀音楽とそれ以前の古典音楽の時間構造をより詳細に分析する研究を行った。音楽作品は通常、拍節構造とメロディという二重の時間構造を持つ。ある種の現代音楽は規則的な反復に基づく古典音楽の拍節構造を「音楽的時間を不当に束縛している」と考える。しかしベルクソンの時間概念に照らすと、古典的拍節は「自由」で「創造的」な持続(dur□e)の時間構造と矛盾しない。音楽家は規則的な拍子に従いつつも、厳密に均等な時間配分で演奏するわけではなく・現実的にはそれらを伸縮させつつ独自の旋律形体を創造する。ベルクソン哲学から導き出される創造的時間の本質は、数的計測と不規則に合致しつつ、創造的主体が自らの選択によって旋律形体を形作るプロセスに存在すると考えられる。このようなベルクソン的時間論から見た場合、規則的拍節を持たない20世紀音楽、および伝統的な東洋音楽の時間構造はどのように解釈されるだろうか。申請者は以上のような問題意識のもと、これまで行ってきたオリヴィエ・メシアン、ジョン・ケージの研究に引き続き・ピエール・ブーレーズ、ヤニス・クセナキスの音楽作品の分析に着手している。この研究のため、18年9月、ひと月間パリに滞在し、ジョルジュ・ポンピドゥーセンター付属の公共情報図書館および国立近代美術館資料室で文献・資料の調査を行い、執筆中の博士論文に有用な情報を収集した。
2 0 0 0 IR 身体障害者を取り巻く制度とその問題点 (特集 「豊かさ」のパラダイムシフト)
- 著者
- 高阪 悌雄
- 出版者
- 松山東雲女子大学人文科学部紀要委員会
- 雑誌
- 松山東雲女子大学人文科学部紀要 = Annual bulletin of the Faculty of Human Sciences, Matsuyama Shinonome College (ISSN:2185808X)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.77-83, 2013-03
福祉六法をはじめとした社会福祉の個別法では、ケースによっては、深刻な生活ニーズを持つ人に対応できないといった排除性の問題を抱える。 こうした問題を克服していく考え方にベーシック・インカムがある。 しかし、全国民一律に金銭給付が行われるベーシック・インカムの下では、個別の法律は不要となる。 筆者はこうした考え方に異を唱え、福祉関係六法をはじめとしたそれぞれの個別法を改善していくことの方が、多様な福祉需用者のねがいに対応できる可能性が拡がることを説いた。 その上で、社会福祉の個別法の一つである身体障害者福祉法と国民年金法の障害等級法の問題点及び改善点を指摘した。 特に医学モデルに基づいた数値化された診断基準をもとに年金給付を決定している現行の仕組みではなく、就業所得の不足分を保障していく仕組みに変えていくことの大切さを説いた。
2 0 0 0 OA 限定倫理性に基づくビジネス倫理学の展開 ― ベイザーマンからヘアそしてポパーへ―
- 著者
- 脇 拓也
- 出版者
- 日本経営学会
- 雑誌
- 日本経営学会誌 (ISSN:18820271)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, pp.58-71, 2021 (Released:2022-12-16)
- 参考文献数
- 27
Based on the premise that humans are bounded ethical beings, Bazerman (M.H. Bazerman) and Tenbrunsel (A.E. Tenbrunsel) posit that “ethical blind spots” and “ethical breakdown” occur. Both these concepts are important, and useful, when analyzing corporate scandals. However, there are several issues regarding how to respond to the ethical issues proposed by Bazerman and Tenbrunsel. To solve these problems, this paper analyzes the two-level utilitarianism based on preference utilitarianism, also known as preferentialism, as posited by Hare (R.M. Hare) and further informed by Popper's (K.R. Popper) critical rationalism. Thus, it is necessary to make the behavioral ethics developed by Bazerman and Tenbrunsel a more logical and consistent theory. This was achieved by solving ethical problems, that occur because of the bounded nature of human ethics, through the hierarchical viewpoint of Hare, and then is further informed by Popper's critical rationalism. The purpose of this paper then, is to clarify this research. First, after considering the “ethical blind spots” and “ethical breakdown” as posited by Bazerman and Tenbrunsel based on humanity's ethically bounded nature, the problems in their theories are highlighted. Then, it was explained that to solve this problem, the two-level utilitarianism theory based on preference utilitarianism by Hare would be necessary for addressing the ethical problems that were presented. However, when the problems with his theory were considered, Popper's critical rationalism was applied to improve Hare's theory. Finally, it became possible to address ethical problems such as “ethical blind spots” and “ethical breakdown” brought about by the bonded nature of human ethics.
2 0 0 0 OA 解肌について
- 著者
- 藤平 健
- 出版者
- The Japan Society for Oriental Medicine
- 雑誌
- 日本東洋醫學會誌 (ISSN:1884202X)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.3, pp.438-440, 1974-03-30 (Released:2010-11-29)
2 0 0 0 OA 冷泉為恭の仏画をめぐって
- 著者
- 日並 彩乃
- 出版者
- 関西大学大学院東アジア文化研究科
- 雑誌
- 文化交渉 : Journal of the Graduate School of East Asian Cultures : 東アジア文化研究科院生論集 (ISSN:21874395)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.21-40, 2014-09-30
The study of Reizei Tamechika’s Buddhist paintings is just as important as the study of his Fukko Yamato-e(restoration of Japanese painting). Fukko Yamato-e was a movement at the end of the Edo period, focused on the restoration of a traditional style of Japanese painting based on the masterpieces of the Heian and Kamakura eras. While Tamechika’s work is associated with the Kyokano area, he also produced many Buddhist paintings through his personal connection with Gankai. Tamechika also learned the archaic style of Buddhist painting of the Heian and Kamakura periods. However, seeing as Tamechika was born in Kyokano, it is possible that his Buddhist paintings were also influenced by his hometown. In this paper I will discuss the tradition of Yamato-e of the Kano school, from Sanraku to Eigaku and Eisho, and then Tamechika at the end of the Edo period. I wil also look at the changes that can be seen in Tamechika’s Buddhist painting.
2 0 0 0 OA インタフェースデザインにおけるメタファ : デスクトップから仮想空間、そして言語への回帰
- 著者
- 楠見 孝
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究特集号 (ISSN:09196803)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.64-73, 2002-09-30 (Released:2017-11-27)
- 参考文献数
- 36