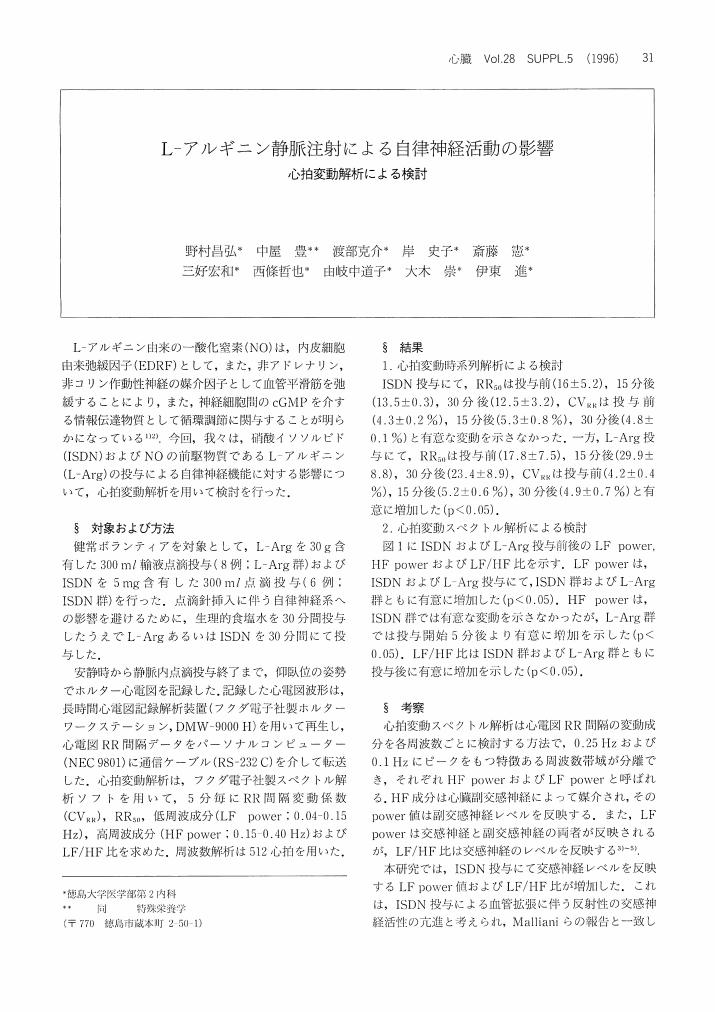2 0 0 0 OA AS3MT遺伝子多型がもたらすヒ素代謝能の人種差の解明
2 0 0 0 OA 地域課題解決型授業の教育効果 ~CBRプロジェクト前後比較での検討~
- 著者
- 元廣 惇 久野 真矢 仲田 奈生 山本 真理子 藤井 寛幸
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.126-132, 2021-02-15 (Released:2021-02-15)
- 参考文献数
- 23
要旨:本報告は,多職種連携・地域課題解決型授業である「CBRプロジェクト」を紹介すると共に,授業に参加した学生の変化を予備的に検討することを目的とした.CBRプロジェクトに参加した作業療法,および理学療法学生22名を対象として,授業実施前後の課題価値,職業的アイデンティティ,自己効力感,チームプロセスを比較した.その結果,課題価値の総得点,および下位因子の興味獲得価値,私的獲得価値,職業的アイデンティティ下位因子の必要とされることへの自負,チームプロセス尺度の総得点,および下位因子の相互援助,相互調整,活動の分析といった項目で有意差を認めた.作業療法教育にてCBR概念を導入した学外実習を行うことの有効性が示唆された.
2 0 0 0 OA (国際 HAIKU プロジェクトシンポジウム) 詩人と俳句--俳句と詩のバイリンガリズム
- 著者
- 九里 順子 坪井 秀人 宮崎 真素美
- 出版者
- 愛知県立大学文字文化財研究所
- 雑誌
- 愛知県立大学文字文化財研究所紀要 = Memoirs of the Cultural Documents Research lnstitute, Aichi Prefectural University (ISSN:21895287)
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.19-59, 2021-03-08
2 0 0 0 OA 針尖と針体の研究 (IV) 針メーカーから販売されている針の実態 (III)
- 著者
- 松元 丈明
- 出版者
- 公益社団法人 全日本鍼灸学会
- 雑誌
- 日本鍼灸治療学会誌 (ISSN:05461367)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.86-104, 1981-03-15 (Released:2011-05-30)
- 参考文献数
- 6
At the 28th Japan Acupuncture and Moxibustion Society Congress I presented a research report on the above theme. With the cooperation of the prefectural presidents of the Japan Acupuncture and Moxibustion Association nationwide, 19 acupuncture needle manufacturing companies were listed and 50 stainless steel 1.6 TSUN, No. 3 needles were collected from each manufacturer and examined. The results of that study showed imperfect needle tips to average 37.7% and imperfect needle bodies to average 52%.For this report, last Oct. the needle manufacturers were forewared that early this year a study of needle conditions would be repeated. In Mar. of this year, in the same manner stainless steel 1.6 TSUN, No. 3 needles, 50 each were collected and examined. These results showed imperfect needle tips to average 37.6% and imperfect bodies, 93.9%. From these results it can be said that quality control of the manufactured product is insufficient. I strongly feel that more consideration is necessary in the selection of needle materials.
2 0 0 0 OA 併病の概念からみた柴葛解肌湯 (浅田家方) の運用について
- 著者
- 木下 恒雄
- 出版者
- The Japan Society for Oriental Medicine
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.4, pp.607-611, 1994-04-20 (Released:2010-03-12)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 2
柴葛解肌湯 (浅田家方) は小柴胡湯と葛根湯の合方から人参と大棗を去り石膏を加えた合方的薬方であり, 薬方の構成や出典の記載内容から太陽病と裏的少陽証の併病に運用されるべきものと思われる。一方, 併病の治療において, このような病態に対しては太陽病と陽明病の治療原則に倣い先表後裏で対応するのが原則と思われるが, 本方証では例外的に表裏双解的効果を狙ったものと思われる。呈示した, かぜ症候群の症例は当初麻黄湯証と思われたが, 初診の翌日には裏的少陽証への転属すなわち太陽病と裏的少陽証の併病に移行したと診断した。そこで本方を用いたところ, 短時日で症状軽快をみた。このことは太陽病と裏的少陽証の併病の一病態に対する本方の有意性の一端を示すものではないかと思われる。併病治療に際しては治療原則を勘案の上, 本方証の如き例外的な薬方の運用もあることを念頭に置いておくべきではないかと思う。
2 0 0 0 IR グローバル時代に求められる総合的日本語教育と認知言語学
- 著者
- 森山 新
- 出版者
- お茶の水女子大学比較日本学研究センター
- 雑誌
- お茶の水女子大学比較日本学研究センター研究年報
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.111-117, 2007-03
グローバル時代を迎え、日本語教師は言葉だけ教えればよい時代は終わり、文化を含めた総合的な日本語教育が求められている。また異文化理解教育も、単に伝統文化などの知識を教えればよいわけではなく、異文化を読み解く能力(文化リテラシー)を育む教育が求められている。言語習得に対する考え方は、時代と共に行動主義、生得主義、認知主義へと大きく変化してきたが、21世紀を迎え、認知主義は応用認知言語学を提示し、言語教育に有益な示唆を与え始めている。グローバル時代に求められる総合的日本語教育にふさわしい言語観であると言える。
2 0 0 0 OA 『山海経』に見る帝俊説話 ―黄帝説話との比較を中心に―
- 著者
- 尹 青青
- 出版者
- 中央大学人文科学研究所
- 雑誌
- 人文研紀要 (ISSN:02873877)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, pp.81-109, 2017-09-30
『山海経』に見る帝俊説話について、先行研究ではこの人物を舜或いは帝嚳として解釈するが、客観性が十分であるとは考え難い。 本稿では、従来の先行研究と相反する視点を仮説に立て、『山海経』に見る帝俊説話を検討する。黄帝とあまり関係性を持たないとされた帝俊だが、『山海経』に見る帝俊説話と黄帝説話に関して、一言で無関係だとは判断できない。『山海経』に見る帝俊説話は如何なるものか、そして黄帝説話とはどのような関係性を持つのか、これらの疑問を明らかにするのが本稿の目的である。 帝俊の独自性を仮定した上、『山海経』に見る帝俊説話では、帝俊の神格がかなり強調されていることを確認する。その上で『山海経』に於いては帝俊説話が黄帝説話より優位に立つと考える。一方、黄帝説話が帝俊説話と関係性を持たないとは言えず、寧ろ帝俊説話を吸収する傾向が見えると推測できる。その傾向は既に『山海経』に見えると思われる。
2 0 0 0 OA 進化生物学と統計科学:系統樹の推定をめぐって
- 著者
- 三中 信宏
- 出版者
- 日本計量生物学会
- 雑誌
- 計量生物学 (ISSN:09184430)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.Special_Issue_1, pp.S25-S34, 2007-10-01 (Released:2011-09-25)
- 参考文献数
- 37
Contemporary evolutionary biology has used various statistical methods for collecting and analyzing data. Here methods for estimating phylogenetic trees are reviewed in the context of recent history of evolutionary biology, especially of systematics and phylogenetics. Estimating evolutionary history based on character data (molecular or morphological) poses a couple of epistemological problems all of which are common to historical sciences in general. Karl Popper's philosophy of science, in particular, his theory of falsification and corroboration has been espoused by many theoretical phylogeneticists. In this paper the long-standing controversy on philosophical aspects of phylogenetics and its implications for statistical methods in this discipline is discussed.
- 著者
- 駒林 邦男
- 出版者
- 岩手大学教育学部附属教育実践研究指導センター
- 雑誌
- 岩手大学教育学部附属教育実践研究指導センター研究紀要 = The journal of the Center for Educational Research and Practices (ISSN:09172874)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.19-41, 1992-03
拙論は、日本教育学会第50回大会・シンポジウム「学校知を問い直す」(1991/8/29)での提案資料(2)を、シンポジウム後、大幅に書き改めたものである。
2 0 0 0 OA アシジの聖フランシスコの「平和の祈り」の由来
- 著者
- 木村 晶子 藤女子大学人間生活学部人間生活学科
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.31-52, 2008-03-01
2 0 0 0 OA 男爵近藤廉平伝 : 附・遺稿
2 0 0 0 OA <<Vaghe stelle dell'orsa>> : forme e immagini della memoria : A Giovanna Karen, Aldo e Nella
- 著者
- Vagata Daniela Shalom
- 出版者
- イタリア学会
- 雑誌
- イタリア学会誌 (ISSN:03872947)
- 巻号頁・発行日
- no.57, pp.1-19, 2007-10-20
2 0 0 0 OA II. 200系新幹線電車
- 著者
- 木俣 政孝
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.2, pp.109-112, 1982-02-20 (Released:2008-04-17)
2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1938年09月26日, 1938-09-26
2 0 0 0 アミューズメント産業
- 著者
- アミューズメント産業出版 [編]
- 出版者
- アミューズメント産業出版
- 巻号頁・発行日
- vol.28(9), no.332, 1999-08
- 著者
- Mariko Kanamori Naoki Kondo Yasuhide Nakamura
- 出版者
- Japan Epidemiological Association
- 雑誌
- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.43-51, 2021-01-05 (Released:2021-01-05)
- 参考文献数
- 47
- 被引用文献数
- 2 5
Background: Recent research suggests that Japanese inter-prefecture inequality in the risk of death before reaching 5 years old has increased since the 2000s. Despite this, there have been no studies examining recent trends in inequality in the infant mortality rate (IMR) with associated socioeconomic characteristics. This study specifically focused on household occupation, environment, and support systems for perinatal parents.Methods: Using national vital statistics by household occupation aggregated in 47 prefectures from 1999 through 2017, we conducted multilevel negative binomial regression analysis to evaluate occupation/IMR associations and joinpoint analysis to observe temporal trends. We also created thematic maps to depict the geographical distribution of the IMR.Results: Compared to the most privileged occupations (ie, type II regular workers; including employees in companies with over 100 employees), IMR ratios were 1.26 for type I regular workers (including employees in companies with less than 100 employees), 1.41 for the self-employed, 1.96 for those engaged in farming, and 6.48 for unemployed workers. The IMR ratio among farming households was 1.75 in the prefectures with the highest population density (vs the lowest) and 1.41 in prefectures with the highest number of farming households per 100 households (vs the lowest). Joinpoint regression showed a yearly monotonic increase in the differences and ratios of IMRs among farming households compared to type II regular worker households. For unemployed workers, differences in IMRs increased sharply from 2009 while ratios increased from 2012.Conclusions: Inter-occupational IMR inequality increased from 1999 through 2017 in Japan. Further studies using individual-level data are warranted to better understand the mechanisms that contributed to this increase.