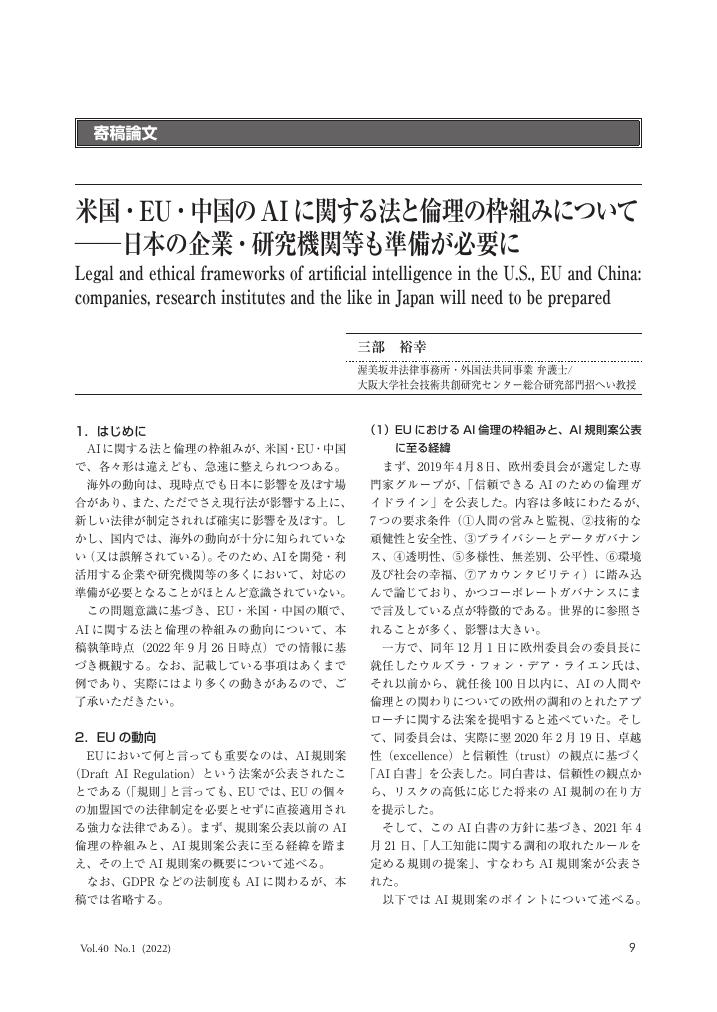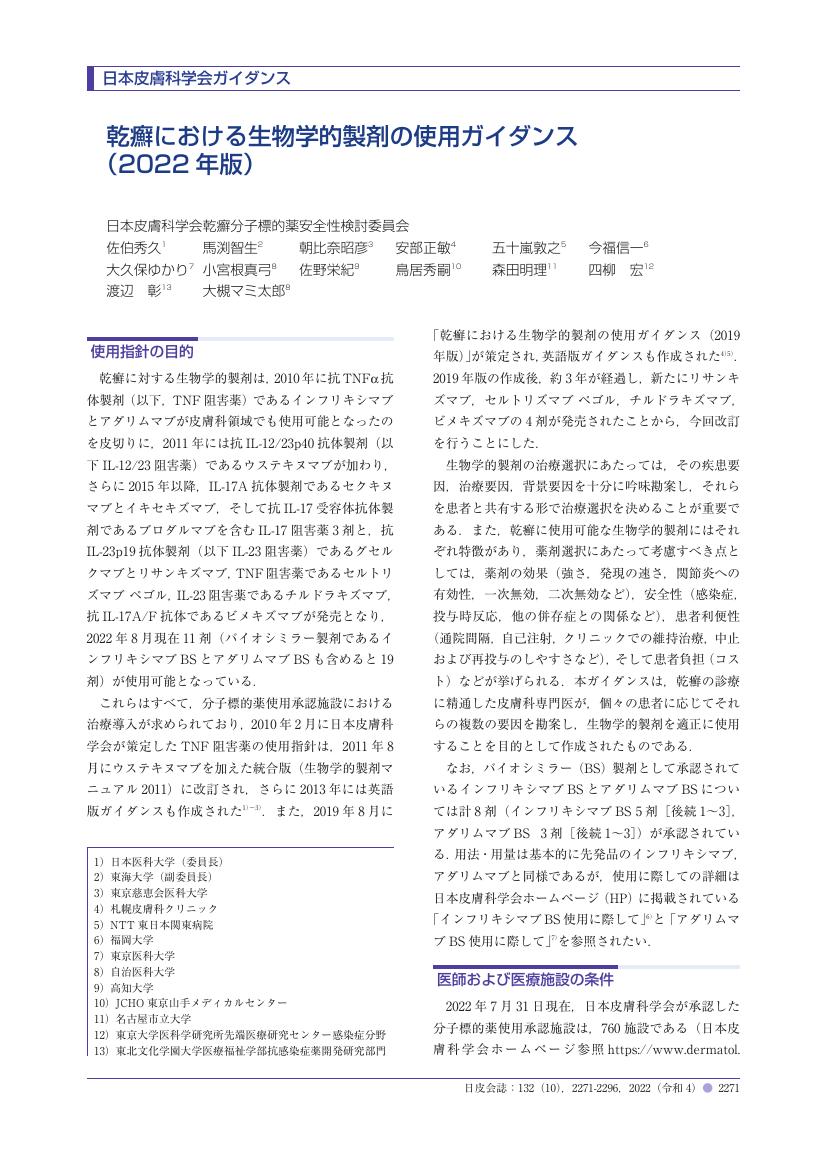2 0 0 0 虚血性心筋症-大動物モデルに対するHMGB1の心筋再生効果の検証
- 著者
- 後藤 隆純
- 出版者
- 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター(臨床研究支援センター)
- 雑誌
- 若手研究
- 巻号頁・発行日
- 2020-04-01
骨髄由来間葉系幹細胞を障害組織へ誘導し組織再生を促進させる因子であるHMGB1が組織リモデリングを抑制する薬剤候補として注目されている. 心筋梗塞モデルラットに対し, HMGB1による心機能改善効果を検証し, 梗塞後リモデリング抑制に関する有効性, 及び, 障害心筋に骨髄由来間葉系幹細胞の誘導が促進される機序を解明した. HMGB1による自己修復能の促進効果は, 心筋梗塞後心不全に対する既知の細胞治療の再生効果を更に強調する事が期待され, HMGB1の早期ヒト臨床応用に向けて, 大動物-心筋梗塞モデルを用いた前臨床試験の実施が必須である.
- 著者
- Katsuhito Ihara Shotaro Naito Tomokazu Okado Tatemitu Rai Yutaro Mori Takayuki Toda Shinichi Uchida Sei Sasaki Noriaki Matsui
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.1, pp.49-54, 2015 (Released:2015-01-01)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 2 3
A 33-year-old Japanese woman at 40 weeks gestation visited the maternity hospital after imminent labor had begun. After the delivery, persistent bleeding developed resulting in hemorrhagic shock. Although the hemorrhage was eventually controlled, hepatic and renal dysfunction occurred, leading to acute kidney injury (AKI). The patient's clinical presentation was suggestive of amniotic fluid embolism (AFE). We subsequently initiated continuous renal replacement therapy (RRT) for AKI. The patient's condition improved, she discontinued RRT, and her renal function recovered. We herein report a patient who successfully recovered from AKI caused by AFE.
- 著者
- Yuhko KANEKO Tohru OGIHARA Hiroto TAJIMA Fumio MOCHIMARU
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.9, pp.945-947, 2001 (Released:2006-03-27)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 21 27
We describe a 27-year-old woman with disseminated intravascular coagulation and shock due to amniotic fluid embolism after Caesarean section who responded well to continuous hemodiafiltration (CHDF) therapy. The effectiveness of CHDF in treating amniotic fluid embolism is also discussed.(Internal Medicine 40: 945-947, 2001)
2 0 0 0 OA 劇症型溶連菌感染症「劇症分娩型」に血栓性微小血管症の合併が疑われたが救命し得た一例
- 著者
- 山根 光知 青山 正 桃原 寛典 榎本 尚助 服部 晶子 野々垣 幹雄 竹市 広 足立 裕史
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.5, pp.403-407, 2020-09-01 (Released:2020-09-01)
- 参考文献数
- 13
40歳の妊婦が発熱,腹痛を主訴に前医を受診し,常位胎盤早期剥離およびhaemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count(HELLP)症候群の疑いで当院に救急搬送され,緊急帝王切開術を施行した。問診および術中所見から劇症型溶連菌感染症による「劇症分娩型」を疑い,アンピシリン,クリンダマイシンによる抗菌薬治療を術中から開始した。血液検査では溶血性貧血,腎機能障害を認め,血栓性微小血管症の合併が疑われ,早急に血漿交換を含む集学的治療を開始した。治療開始とともに全身状態が改善し,第7病日にICUから退室し良好な転帰を得られた。早期の抗菌薬治療の開始,昇圧薬投与,輸血療法,血漿交換を含む集学的治療により救命できたと考えられた。
2 0 0 0 OA 初期豪商田中清六正長について
- 著者
- 村上 直
- 出版者
- 法政大学史学会
- 雑誌
- 法政史学 = 法政史学 (ISSN:03868893)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.79-96, 1968-03-20
- 著者
- 三部 裕幸
- 出版者
- 公益財団法人 情報通信学会
- 雑誌
- 情報通信学会誌 (ISSN:02894513)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.9-14, 2022 (Released:2022-10-22)
2 0 0 0 OA 自律神経による代謝調節作用
2 0 0 0 現代上海語 : 詳註
2 0 0 0 OA 対西洋としての日本画の創出と再考
- 著者
- 小野 文子 間島 秀徳
- 出版者
- 大学美術教育学会
- 雑誌
- 美術教育学研究 (ISSN:24332038)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.129-136, 2016 (Released:2017-03-31)
- 参考文献数
- 16
本稿は,「日本画とはなにか」という問いに焦点をあて,現代と明治期それぞれの時代におけるグローバリゼーションに接点を見出し,明治期に始まる政策としての「日本画」創出について考察したものである。「日本画」の誕生には,明治期に欧化主義のなかで西洋の価値基準を取り入れ,新たに自国の絵画を作りだそうとした歴史的背景があり,お雇い外国人アーネスト・F・フェノロサの関与は,このことを明確に表している。さらに,フェノロサと金子堅太郎,J.McN.ホイッスラーとの関わりに着目すると,「日本画」の創出が,国家戦略,そしてグローバリゼーションによって広がる多様な価値観のなかで誕生したことが分かる。本稿では,対西洋としての「日本画」について,その誕生の歴史的経緯を吟味し,1980年代から90年代にかけての「日本画」の再考について論じた。
2 0 0 0 掌蹠角化症診療の手引き
- 著者
- 掌蹠角化症診療の手引き作成委員会 米田 耕造 久保 亮治 乃村 俊史 山本 明美 須賀 康 秋山 真志 金澤 伸雄 橋本 隆
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.130, no.9, pp.2017-2029, 2020
2 0 0 0 OA 乾癬における生物学的製剤の使用ガイダンス(2022年版)
2 0 0 0 OA 「ずーしーほっきー」のデザインを通した大学と地域の共創
- 著者
- 安井 重哉 木村 健一
- 出版者
- Japanese Society for the Science of Design
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集
- 巻号頁・発行日
- pp.101, 2014 (Released:2014-07-04)
2016 年3 月,北海道北斗市にある渡島大野駅に接続する形 で北海道新幹線の新ターミナル駅である新函館駅(仮称)の開 業が予定されている.2012 年11 月,これを契機に全国に知名度をアピールすべく,ご当地キャラクターの活用を企図した北斗市より,公立はこだて未来大学(以下,本学)へ,キャラク ターデザインの依頼について打診があった.本学は,情報デザインコースの機能を活用した地域社会への貢献,およびその地 域貢献のプロセスを通じた学内の人材育成という観点から,この依頼を受諾し,2013 年4 月から約1年を費やしてご当地キャ ラクターのデザインに取り組んできた.本稿は,この取り組みを,デザイン活動を通した社会貢献における大学と地域社会の共創モデルとして総括することを目的としている.
2 0 0 0 OA アンジオテンシン変換酵素阻害薬服用患者の咳発生頻度に及ぼす調査方法の影響
- 著者
- 後藤 伸之 白波瀬 正樹 八田 寿夫 政田 幹夫 李 鍾大 坪川 明義 清水 寛正 上田 孝典 中村 徹 北澤 式文
- 出版者
- The Japanese Society of Clinical Pharmacology and Therapeutics
- 雑誌
- 臨床薬理 (ISSN:03881601)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.4, pp.725-730, 1996-12-31 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 2 2
We performed a pharmacoepidemiological study on the effect of different types of questionnaires on coughing and the prevalence of this symptom in out-patients taking angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI) in Fukui Medical School Hospital.The following three types of quentionnaires were prepared:Type 1 ; Questionnaire asking whether the patient has a cough or no after implying that ACEI might cause this symptom.Type 2 ; Questionnaire on the general adverse effects of ACEI, including coughing.Type 3 ; Questionnaire on the general adverse effects of ACEI other than coughing.All questionnaires included a blank space in which the patients were asked to write any adverse effects. The patients were randomly divided into three groups. Each group was given one of the three questionnaires. In the type 3 questionnaire, no patient com-plained of coughing. The prevalence of cough was higher in type 1 questionnaire than in type 2 quetionnaire patients. These results indicate that the prevalence of adverse effects varies greatly depending the type of questions in the questionnaire.
2 0 0 0 IR イスラームにおける障害者に関する議論の諸相
- 著者
- 青柳 かおる
- 出版者
- 新潟大学人文学部
- 雑誌
- 人文科学研究 = Studies in humanities (ISSN:04477332)
- 巻号頁・発行日
- vol.149, pp.Y1-20, 2021-12
2 0 0 0 IR イタリアの国民形成について
- 著者
- 藤澤 房俊
- 出版者
- 東京経済大学
- 雑誌
- 東京経済大学人文自然科学論集 (ISSN:04958012)
- 巻号頁・発行日
- no.127, pp.101-110, 2009-03-04
2 0 0 0 OA Motor Planningの神経基盤
- 著者
- 稲垣 秀彦
- 出版者
- 日本神経回路学会
- 雑誌
- 日本神経回路学会誌 (ISSN:1340766X)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.3-4, pp.97-106, 2020-12-05 (Released:2021-01-08)
- 参考文献数
- 24
本稿では,脳がどのように動作を計画し実行するのか,その神経機構と情報処理について記述する.行動する際,我々はまずどのような動作をするかの意思決定を行う.その決定は短期記憶として維持され,脳が外部・内部情報に基づき,最適なタイミングと判断した時に実行される.例えば,バッターやテニスプレーヤーはボールがリーチに入る以前から,どのようにスイングするかを決め,それは短期記憶として維持される.そしてボールがリーチに入った瞬間,すなわちスイングするのに最適なタイミングだと視覚情報から脳が判断した際,計画された通りにスイングする.このように事前に計画された動作は,そうでないものに比べ,正確かつ初動(Reaction time)が速いことが知られている.このような動作計画の短期記憶は,Motor planningと呼ばれ,運動野及び,間接的・直接的に接続した他の脳領域が必要であることが知られている.動作の計画時,これらの脳領域では持続的神経発火(Persistent activity)が数秒以上に渡って観測され,それがMotor planningを維持していると考えられている.では,1)どのような数理的原理でこの持続的神経発火は維持されるのか?,2)どのような回路がこの持続的神経発火を維持しているのか?,3)どうして,この持続的神経発火は動作の情報を維持しながらも,動作を引き起こさないのか? これらについて,我々や他のグループが発見した最新の知見をまとめる.
2 0 0 0 OA 運動学習とリハビリテーション(<特集>運動学習)
- 著者
- 道免 和久
- 出版者
- バイオメカニズム学会
- 雑誌
- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.4, pp.177-182, 2001-11-01 (Released:2016-11-01)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 10 5
リハビリテーション(以下リハビリ)で重要な運動学習の概念を整理し,脳研究から明らかになった運動学習理論のリハビリ治療への応用を紹介した.古くからリハビリにおける運動学習で重要と言われてきたエングラムの概念は,現代の運動学習理論では,教師あり熟練学習における内部モデルの構築や順序学習の中に見いだすことができる.そのうち,内部モデルの再構築をめざす運動療法をフィードフォワード運動訓練と名付け,大脳錐体路障害の片麻痺患者の患側上肢で実践した.その結果,フィードバック誤差学習の回路が残存する例では,運動課題の繰り返しによって,徐々に運動のなめらかさの指標が向上し,運動学習が成り立つことがわかった.今後,運動学習理論をリハビリ治療の中で再検討することが重要である.
2 0 0 0 OA 明治末期における京都での鉄筋コンクリート橋
- 著者
- 山根 巌
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木史研究 (ISSN:09167293)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.325-336, 2000-05-01 (Released:2010-06-15)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 2
明治末期における京都での鉄筋コンクリート橋は、有名な田辺朔郎による明治36 (1903) 年の琵琶湖疎水に架けた日ノ岡の「孤形桁橋」に始まるが、明治38年から京都市の井上秀二により、高瀬川で4橋の小規模鉄筋コンクリート橋群が架設された。一方京都府においても、明治41 (1908) 年原田碧が長崎市から転勤して来て以後多数の鉄筋コンクリート橋が架設されたが、その代表は鞍馬街道の「市原橋」と「二之瀬橋」と言えよう。これ等の橋はメラン式を発展させた日本的な考え方の軸組方式で「鉄骨コンクリート構造」のアーチ橋とトラス橋として建設されている。また明治38 (1905) 年日比忠彦により導入されたモニエ式アーチ・スラブが、I字鉄桁に用いられて「鉄筋僑」と呼ばれ大正期末迄に多数建設され、市原橋の側径間にも採用されている。明治末期の京都での鉄筋コンクリート橋は、府市共にメラン式等の試験的な小規模の橋梁が多かったが、大正2 (1913) 年に完成した柴田畦作による、鴨川での鉄筋コンクリートアーチ橋の四条及び七条大橋の架設で、鉄筋コンクリート橋は大規模化し多様化して、日本の鉄筋コンクリート橋の発展に大きな影響を与えた。こうした明治末期における京都での鉄筋コンクリート橋の導入と発展の特徴について、調査した結果を報告する。