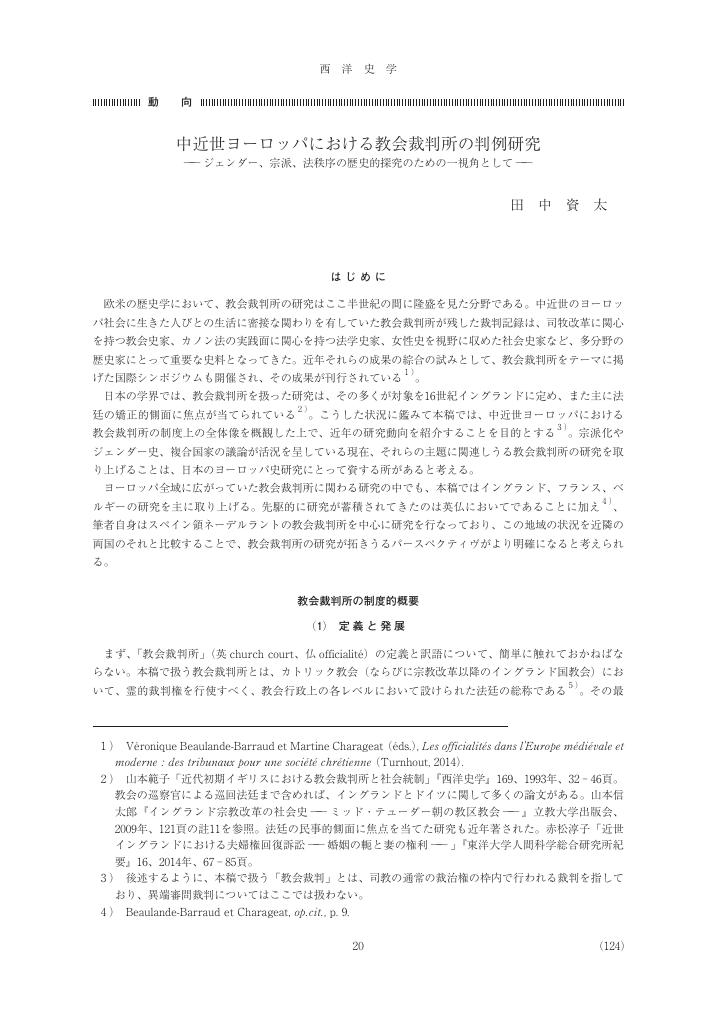2 0 0 0 特許情報と人工知能(AI):総論
- 著者
- 桐山 勉 安藤 俊幸
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.7, pp.340-349, 2017-07-01 (Released:2017-07-01)
人工知能の第三次ブームによりこの2~3年で巷の会話の中にでも頻繁に人工知能(AI)という言葉が聞くようになった。畳込み深層学習の進歩によりイメージネット大規模視覚認識コンテストの正解率が95%を超えた。更に,画像を見て言葉概念を理解する高度なレベルの研究が盛んになりつつある。AIの多方面への応用研究が急激に加速され,特許情報をその研究対象にすることに着目されるまでに至った。米国特許商標庁での先行技術調査への活用研究が盛んになって来た。プロバイダーでもその応用を特許情報サービスに活用しようと盛んになって来た。ここで,特集号にちなみ総論を纏める。
- 著者
- Yoshizawa Kazunori
- 出版者
- The Research Faculty of Agriculture, Hokkaido University
- 雑誌
- Insecta matsumurana. New series : Journal of the Research Faculty of Agriculture Hokkaido University, series entomology. (ISSN:00201804)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, pp.21-25, 2022-09
A new species of the genus Trichadenotecnum (Psocodea: Psocidae) belonging to the corniculum species group,Trichadenotecnum okuyamai, was described from Awajishima Island, Japan. This is the 25th species of the genus and the third species of the corniculum group recorded from Japan.
2 0 0 0 OA サステイナビリティ概念を問い直す : 人新世という時代認識の中で
- 著者
- 池田 寛二
- 出版者
- 法政大学サステイナビリティ研究センター
- 雑誌
- サステイナビリティ研究 = Research on Sustainability : The Academic Journal of the Research Center for Sustainability (ISSN:2185260X)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.7-27, 2019-03-15
「サステイナビリティ」という言葉は、現代社会に遍く通用している流行語のひとつである。だが、それゆえに、多方面の専門家らによって異なる観点から多様に意味づけられ、この言葉を用いた議論に少なからず混乱が見られることも事実である。本稿は、このような現状を踏まえて、サステイナビリティを、多義的な流行語もしくは標語としてではなく、「概念」として再検討することを目的とする。ここで「概念」とは、マックス・ウェーバーの言うところの、「経験的実在を思考により妥当な仕方で秩序づける」ための「装置」のことを指す。それは結果的に「理念型」、すなわち、無限に多様な経験的実在を構成する諸事象の連関を、それにどの程度近いか、または遠いかという観点から判断し叙述するための表現手段とするために、現実のどこかに経験的に見いだされることのない「ひとつのユートピア」概念として提示される。その際に、本稿で特に留意するのは、サステイナビリティの概念を「人新世(Anthropocene)」、すなわち、人間が地球環境に刻みつけた痕跡が人間以外の自然の巨大な力に匹敵するほどに地球環境の機能に大きな衝撃を与えるようになった産業革命期を起源とする時代に私たちが今生きている(その典型事例が気候変動)という地質学的な時代認識を前提にして検討することである。人新世の歴史観を踏まえ、シーレによるサステイナビリティの作業的定義とベッカーによる当該概念のコアにある三つの思考様式を手掛かりとし、さらに「トリプル・ボトムライン」や「サステイナビリティのトリプル・ヘリックス・モデル」、ケイトーのスキームなどサステイナビリティの概念をめぐる先行研究を参照しつつ検討した結果、本稿では、図1に素描されるように、人新世の自然、すなわち、自然が「(人間)社会が入り込んでいない自然」と「(人間)社会が入り込んだ自然」から構成されているという認識に立って、前者を「自然」、後者を「環境」と弁別したうえで、「サステイナビリティとは、社会と環境が持ち応え合う(bearable)関係で、環境と経済が育成し合う(viable)関係で、経済と社会が公平/公正を保障し合う(equitable)関係で重なり合っている状態を意味する」、そして環境と経済はいずれも社会関係に埋め込まれている、という定義を理念型として導き出すことができた。この理念型を再度シーレの作業的定義を参照しながら、倫理、科学、文化、世代間公正とサステイナビリティとの関連性を考察し、最後に、資本主義とサステイナビリティの関連性を検討した。その過程で、人間を人類として一様に捉える地球管理主義とそれを支える「地-権力」およびサステイナビリティを資本主義の枠組みに組み込んで無限の経済成長を喧伝する自然資本主義が、この理念型から遠ざかっていることを批判的に論じた。
2 0 0 0 OA 明治時代の局方における「錠剤」ラテン名の変遷および「錠」の語源についての一考察
- 著者
- 五位野 政彦
- 出版者
- 日本薬史学会
- 雑誌
- 薬史学雑誌 (ISSN:02852314)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.2, pp.169-174, 2013 (Released:2020-12-30)
Jo-zai or tablet is a most popular form of pharmaceutical dosage in modern Japan. The term jo-zai first appears in the Japanese Navy Pharmacopoeia, First Edition (1872). Its Latin name was translated as torikisuki and was written in Japanese katakana characters. Jo-zai translated as trochischi can also be found in the Japanese Pharmacopoeia, First Edition (JP1) (1897). Its Latin name and definition have changed several times : trochisichi ; pastilli, JP3 (1906) ; tablettae, JP5 (1932) ; tabellae : JP6 (1951), etc. The etymon of the word jo-zai is based on the English word, lozenge. Its square-shaped form is similar to old Japanese silver coins. During Japan's Edo era (1603-1868) and in ancient China, silver coins were called jo. Therefore the word lozenge was translated into Japanese as jo-zai,combining the character for coin with the one for drug, zai.
- 著者
- 石松 久幸
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.11, pp.557-562, 2009-11-01 (Released:2017-04-25)
- 参考文献数
- 8
カリフォルニア大学バークリー校東アジア図書館で行なわれている日本の古地図のデジタル化プロジェクトは同図書館のサイトで一般公開されており,古地図に新たなパースペクティブを与えるものとして,いま世界的な注目を集めている。このサイトの画像は単なるイメージの表示に留まらず,同時に提供されているツールを用いてより有効に地図を活用できるよう配慮されている。またGoogle Earthと古地図との重ね合わせもプロジェクトの一部として進行中である。本稿ではそのプロジェクトの内容,使用しているソフトウエアの利用法,デジタル化を行なうことの意義,影響,そして新たに起きた問題点などについて説明する。
2 0 0 0 OA 復讐の暴力、和解の暴力
- 著者
- 鵜飼 哲
- 出版者
- The Japanese Association of Sociology of Law
- 雑誌
- 法社会学 (ISSN:04376161)
- 巻号頁・発行日
- vol.2001, no.54, pp.13-26,258, 2001-03-30 (Released:2009-01-15)
- 参考文献数
- 24
La pensée juridique moderne exclut la vengeance hors de l'espace regi par la loi. Mais Nietzsche soutient que la vengeance est la première structure sociale qui permet de stabiliser le rapport entre les communautés. Dans l'Antiquité, Aristote intègre la vengeance dans l'ordre de la Cité en pensant qu'il est possible de controler la vengeance par la raison, l'essentiel étant de trouver le«juste milieu»dans la pratique vindicative. C'est à l'influence conjointe du stoîcisme et du christianisme qu'il faut attribuer l'exclusion définitive de la vengeance qui se réalisera à l'âge classique. Selon Nietzsche, le ressentiment est né de la vengeance inhibée et spiritualisée. La morale des eclaves, sous forme du judéo-christianisme, a fini par l'emporter sur la morale des maîtres. Le système juridique moderne en est l'avatar essentiel. C'est dans l'idée de révolution que la vengeance se réfugie depuis deux siècles. Et dans cette mesure, l'esprit révolutionnaire et l'esprit de la peine demort ont en commun la référence à la vengeance. Celle-ci trouve un autre asile dans la littérature et certains poètes qui s'associaient au mouvement révolutionnaire étaient souvent sensibles au caractère sublime de la vengeance. En Europe, l'idée de révolution se voit en déclin en même temps que l'abolition définitive de la peine de mort. Et on parle actuellement de la réconciliation nécessaire pour surmonter le conflit historique grave. Mais on doit mettre en question cette opinion qui veut que la réconciliation soit le contraire de la vengeance. Si la vengeance est à l'origine de tout calcul social, la réconciliation s'opère encore dans les limites de la période ouverte et limitée par la vengeance. Quand Derrida propose de distinguer le pardon de la réconciliation, it considère que cette dernière recèle sa propre structure violente. Le padon sur lequel it nous invite à méditer riendrait interrompre à la fois la violence de vengeance et celle de la réconciliation.
- 著者
- 髙見 啓一
- 出版者
- 特定非営利活動法人 組織学会
- 雑誌
- AAOS Transactions (ISSN:27582795)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.235-241, 2022 (Released:2022-09-16)
- 参考文献数
- 17
The third-place “TP” characteristics, which are noted from the study of Oldenburg (1998/2013), has not been noticed in existing studies of community of practice. However, TP characteristics are said to increase learning motivation and promote learning. The purpose of this study is to examine the preceding factors of TP characteristics, to present a hypothetical model to clarify how TP characteristics affect cross-border learning of community of practice, and to clarify future research issues. As a result of the research, the following three hypotheses were presented. "The thoughtful leadership of the coordinators of the community of practice enhances the TP characteristics of the practice community." "The informality of the community of practice enhances the TP characteristics of the community of practice." "The higher TP characteristics of the community of practice, the more cross-border learning of the community of practice is promoted." TP can be a key factor in the management of a community of practice.
2 0 0 0 OA 中等教育諸学校職員録
本研究では、フランス革命期以降の法システムを、社会契約論の再構成を通じた「社会」という観点から統一的に把握し、この「社会」の観念を基盤に、「意思」を持った「法的主体」が構成されることをあきらかにする。フランス革命期の「社会法」的な実践は、一般に考えられている以上に、新しい「社会」形成に不可欠の要素であったことを示し、19世紀末の「社会法」理論の系譜を革命期の理論にさかのぼって明らかにする。その上で、社会契約論とその再構成が18世紀末と19世紀末の二つの理論を結びつける鍵となっていることが示され、ヨーロッパ近代法の教義学的規範構造が明らかにされる。
2 0 0 0 OA 論文執筆のコツ―論理と図の構成―
- 著者
- 小山 哲男
- 出版者
- 一般社団法人 日本歯科麻酔学会
- 雑誌
- 日本歯科麻酔学会雑誌 (ISSN:24334480)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.14-18, 2022-01-15 (Released:2022-01-15)
- 参考文献数
- 14
2 0 0 0 OA 第2号「ダイヴァース先生とその弟子たち」の訂正
- 出版者
- 特定非営利活動法人 近代日本の創造史懇話会
- 雑誌
- 近代日本の創造史 (ISSN:18822134)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.21, 2007 (Released:2008-01-31)
2 0 0 0 OA 分光器觀測法小引
- 著者
- 山川 健次郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会、一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 東京數學物理學會記事 (ISSN:21852650)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.146-150, 1885 (Released:2006-03-27)
2 0 0 0 OA 化粧に関する研究
- 著者
- 平松 隆円 牛田 聡子
- 出版者
- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会
- 雑誌
- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.11, pp.682-692, 2003-11-25 (Released:2010-09-30)
- 参考文献数
- 5
大学生の化粧関心・化粧行動・異性への化粧期待の構造を解明するために, 大学生329名を対象に質問紙調査を実施した.日常的におこなわれると思われる化粧行動を, 施す部分によりヘア・フェイス・ボディに分類, また, 化粧品の種類としてケア・可逆的メイク・不可逆的メイク・フレグランスに分類し, それぞれに特徴的な26項目を設定した.主成分分析をおこなった結果, 化粧関心・化粧行動・異性への化粧期待において, 男女で異なる構造が確認された.また, 相関分析により, 化粧関心, 化粧行動, 異性への化粧期待の関連性が明らかになった.
2 0 0 0 OA 鉄道用PMSMドライブシステムにおける回転位相角センサレス制御の高度化に関する研究
2 0 0 0 IR 可能性としての誤審
- 著者
- 柏原 全孝
- 出版者
- 追手門学院大学社会学部
- 雑誌
- 追手門学院大学社会学部紀要 (ISSN:18813100)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.1-16, 2016
スポーツのエートス / 誤審 / テクノロジー / 構成的ルール
- 著者
- 田中 資太
- 出版者
- 日本西洋史学会
- 雑誌
- 西洋史学 (ISSN:03869253)
- 巻号頁・発行日
- vol.268, pp.20, 2019 (Released:2022-05-10)
- 著者
- 平野 智洋
- 出版者
- 日本西洋史学会
- 雑誌
- 西洋史学 (ISSN:03869253)
- 巻号頁・発行日
- vol.257, pp.21, 2015 (Released:2022-05-03)
2 0 0 0 OA イングリッシュネスと他者 婦人会から見た第二次世界大戦後のイギリス社会の変容
- 著者
- 溝上 宏美
- 出版者
- 日本西洋史学会
- 雑誌
- 西洋史学 (ISSN:03869253)
- 巻号頁・発行日
- vol.244, pp.38, 2011 (Released:2022-04-22)
2 0 0 0 OA 陸軍士官候補生受験者用数学撰題 : 附・解式
- 著者
- 神保長致, 鈴木敬信 著
- 出版者
- 中央堂
- 巻号頁・発行日
- 1893
2 0 0 0 OA 『ヴェリスラフ聖書』の図像読解と高校世界史教材化の試み
- 著者
- 藤井 真生 杉田 望 毛利 舞香 小林 実央
- 出版者
- 静岡大学人文社会科学部
- 雑誌
- 人文論集 (ISSN:02872013)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.2, pp.23-60, 2018-01-31