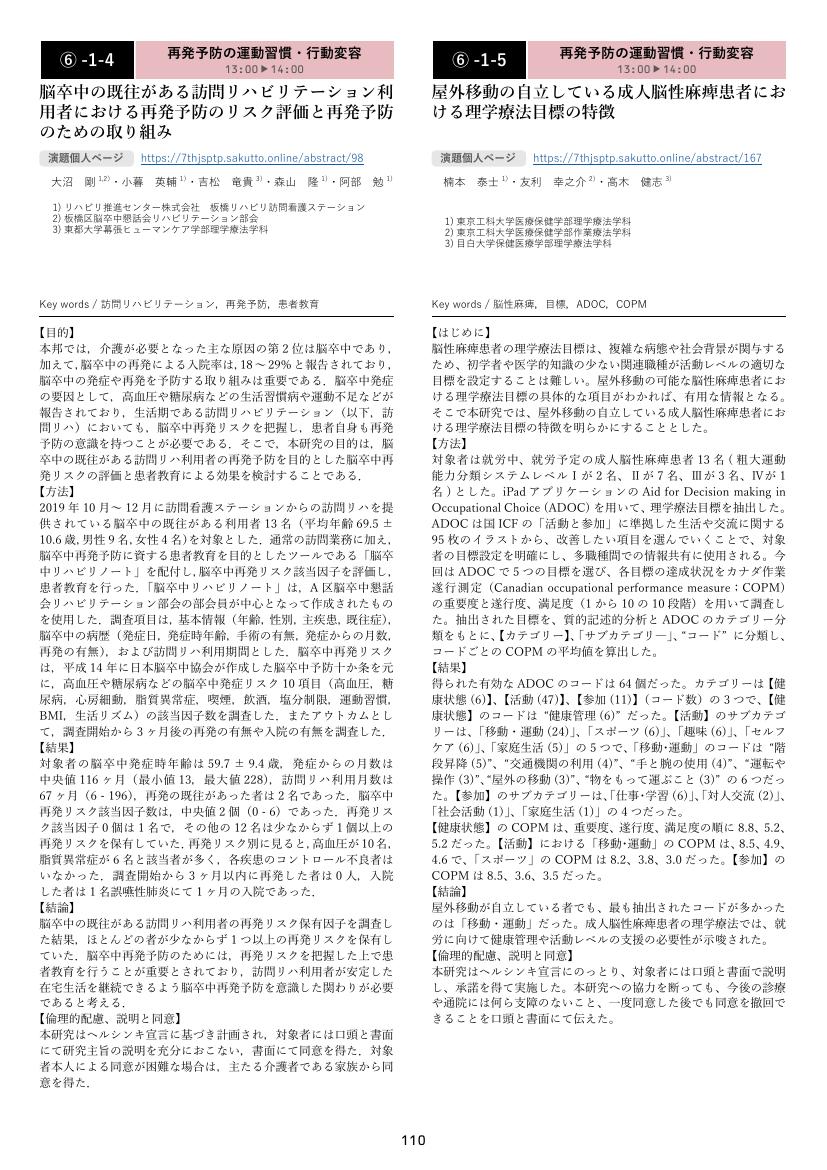- 著者
- 大沼 剛 小暮 英輔 吉松 竜貴 森山 隆 阿部 勉
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.48 Suppl. No.1 (第55回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.E-110_1, 2021 (Released:2021-12-24)
- 著者
- Toshinori Hirai Hidefumi Kasai Masahiro Takahashi Satomi Uchida Naoko Akai Kazuhiko Hanada Toshimasa Itoh Takuya Iwamoto
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.7, pp.948-954, 2022-07-01 (Released:2022-07-01)
- 参考文献数
- 35
Some population pharmacokinetic models for amiodarone (AMD) did not incorporate N-desethylamiodarone (DEA) concentration. Glucocorticoids activate CYP3A4 activity, metabolizing AMD. In contrast, CYP3A4 activity may decrease under inflammation conditions. However, direct evidence for the role of glucocorticoid or inflammation on the pharmacokinetics of AMD and DEA is lacking. The pilot study aimed to address this gap using a population pharmacokinetic analysis of AMD and DEA. A retrospective cohort observational study in adult patients who underwent AMD treatment with trough concentration measurement was conducted at Tokyo Women’s Medical University, Medical Center East from June 2015 to March 2019. Both structural models of AMD and DEA applied 1-compartment models, which included significant covariates using a stepwise forward selection and backward elimination method. The eligible 81 patients (C-reactive protein level: 0.26 [interquartile range; 0.09–1.92] mg/dL) had a total of 408 trough concentrations for both AMD and DEA. The median trough concentrations were 0.49 [0.31–0.81] µg/mL for AMD and 0.43 [0.28–0.71] µg/mL for DEA during a median follow-up period of 446 [147–1059] d. Three patients received low-dose oral glucocorticoid. The final model identified that AMD clearance was 7.9 L/h, and the apparent DEA clearance was 10.3 L/h. Co-administered glucocorticoids lowered apparent DEA clearance by 35%. These results indicate that co-administered glucocorticoids may increase DEA concentrations in patients without severe inflammation.
2 0 0 0 OA 「イノベーション政策」の概念変化に関する考察 : OECDの政策議論を中心とする
- 著者
- 姜 娟
- 出版者
- 研究・イノベーション学会
- 雑誌
- 研究 技術 計画 (ISSN:09147020)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.3, pp.267-287, 2009-02-23 (Released:2017-10-21)
- 参考文献数
- 115
21世紀に入って,世界中で「イノベーション」の言葉を冠した,各国政府による長期戦略が次々と打ち出されている。そうした長期戦略は時代変化の挑戦に対する意識的な応答といえるが,今日においては,「イノベーション」の用語が最も使用頻度の高い政策常套語になっている。しかし,「イノベーション政策」の概念の意味自体が,時を経て,変化してきている。本論考は,「イノベーション政策」とはどのような性格をもった政策的対応であるか,また「イノベーション政策」におけるイノベーションとは如何なることであるかを,今日の段階で改めて見極めることが重要であるという想定に立っている。その考察のためには,「イノベーション政策」の来歴,その後の展開,そして現在の到達点を跡づけてみることが必要であり,有用である。本稿においては,その発足時から現時点にいたるまでのOECDにおける関連領域の政策研究や論議を取り上げ,イノベーション政策の展開を学習過程として捉え,そこにおける政策ニーズと知的努力の間,政策アイディアと理論的,経験的研究の間の共進化を解明する。
2 0 0 0 OA フィードバック制御の性能限界
- 著者
- 劉 康志
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.10, pp.789-796, 2004-10-10 (Released:2009-11-26)
- 参考文献数
- 7
2 0 0 0 機能的・非機能的自己注目と自己受容,自己開示
- 著者
- 高野 慶輔 坂本 真士 丹野 義彦
- 出版者
- Japan Society of Personality Psychology
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.12-22, 2012
- 被引用文献数
- 6
自己注目は,自己に注意を向けやすい特性とされ,非機能的な側面である自己反芻と機能的側面である自己内省の2種類があることが知られている。こうした自己注目の機能性・非機能性に関する議論の多くは個人内の認知・感情の問題に焦点を当てて行われてきており,社会的・対人的な要因との関連はあまり検討されてこなかった。そこで,本研究では,自己注目の機能的・非機能的側面から,自己受容および自己開示との関連を検討した。大学生122名を対象として質問紙調査を実施し,自己反芻・自己内省の傾向,自己受容感,および不適切な自己開示の傾向を測定した。構造方程式モデリングによる分析の結果,自己反芻は,不適切な自己開示と直接的に関連するほか,低い自己受容感を媒介して,不適切な自己開示と間接的に関連していた。一方で,自己内省は,高い自己受容感を媒介して適切な自己開示と関連していることが示された。以上の結果から,自己反芻と自己内省は自己・対人プロセスの中で異なった役割を果たしており,心理的適応に影響を及ぼしていると考えられる。
2 0 0 0 OA ファカルティ・ラーニング・コミュニティの形成 ―対話型省察的実践のアクションリサーチ―
- 著者
- 杉森 公一
- 出版者
- 北陸大学
- 雑誌
- 北陸大学紀要 = Bulletin of Hokuriku University (ISSN:21863989)
- 巻号頁・発行日
- no.52, pp.309-319, 2022-03-31
Faculty Learning Communities (FLCs), a type of professional learning community,are attracting attention as a method of promoting reflective educational practice. FLCsare often composed of faculty members who are interested in a particular topic, and inthe North America, methods such as small-group intensive training (institutes),retreats, and cohort formation (fellowship system) have been developed and are beingimplemented as a variety of FLCs. In Japan, Ikeda et al. (2016) have created acommunity of practice, but comparative research and conceptualization of FLCs infaculty development (FD) practice and research is limited in Japan. This paper reportson the design and framework of dialogue-based educational development through FLCformation involving faculty members across multiple disciplines.
2 0 0 0 会津の史的風景 : 町、町並、街道を歩く
- 著者
- 会津若松市史研究会編集
- 出版者
- 会津若松市
- 巻号頁・発行日
- 2006
2 0 0 0 OA 銭大昕の「経史不二」説における歴史観と学問観 : 章学誠との比較を兼ねて
- 著者
- 胡 藤 Teng HU
- 出版者
- 島根県立大学北東アジア地域研究センター
- 雑誌
- 北東アジア研究 = Shimane journal of North East Asian research : North East Asian region (ISSN:13463810)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, pp.1-17, 2022-03-31
Qian Daxin is one of the most representative scholars of the School of Evidential (kaozhengxue, koukyogaku) in Qing Era. He has a keen command of history studies and claims that Confucian Classics studies (jingxue) and history studies should not be treated separately. He believes that only studying both could prevent knowledge from becoming impractical like the Neo-Confucianism (school of principle, lixue, rigaku). This article takes his assessment of the Shi Tong (by Liu Zhiji) as a clue to analyze his understanding of historical records and what he perceives as the ideal way of historiography. Qian Daxin holds the point that the facts should be truthfully recorded, though the recording may be subject to interference by the political power of the time to ‘create myths’ to legitimate its rule. It is thus valuable to document other narratives of various historical sources to resist such political interference. Only in this way will the historical records be free from becoming moral judgments. And this means reading history will be to understand the ancients immanently through historical records. Qian’s point of view is usually seen to be close to Zhang Xuecheng’s, who is believed to hold a modern historiographical perspective. Although Zhang makes a similar point with Qian that all Confucian Classics should be regarded as historical materials instead of principles, he still attempts to establish in his historiography a continuous "orthodoxy" where the authority of political power overrides scholarship. Qian, unlike Zhang, focuses on discovering and understanding the specific ‘Other’, which was shared by most scholars of the School of Evidential at that time and is thus seen as the motivation of their studies.
2 0 0 0 OA 怒りの動機と反応に対する自己意識の影響
- 著者
- 大平 英樹
- 出版者
- 日本社会心理学会
- 雑誌
- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.30-37, 1989-03-15 (Released:2016-11-23)
The purpose of this study was to investigate the influence of self-conciousness on motives and responses of anger, especially on discrepancy between want and action of responses following anger in an everyday situation. The author administered Averill's "experience of anger" questionnaire and self-consciousness scale to 104 university students. The main foundings were as follows : (1) There were four factors in the responses which were interpreted as direct aggression, displaced aggression, suppression of anger, and nonaggressive problem-solving. (2) The higher private self-consciousness was, the smaller want-action discrepancy in direct aggression, displaced aggression, and suppression of anger. (3) The significant positive correlation was obtained between want-action discrepancy and social anxiety in nonaggressive problem-solving. (4) The significant positive correlation was obtained between public self-consciousness and self-reported justice. And the negative correlation was obtained between want-action discrepancy and justice in direct aggression and displaced aggression.
2 0 0 0 OA 佐倉 朔先生を偲んで
- 著者
- 金澤 英作
- 出版者
- 一般社団法人 日本人類学会
- 雑誌
- Anthropological Science (Japanese Series) (ISSN:13443992)
- 巻号頁・発行日
- vol.123, no.1, pp.5-7, 2015 (Released:2015-06-20)
2 0 0 0 OA 多能性幹細胞の運命決定における薬学的制御と再生医療への発展
- 著者
- 西村 周泰 高田 和幸
- 出版者
- 京都薬科大学
- 雑誌
- 京都薬科大学紀要 = Bulletin of Kyoto Pharmaceutical University (ISSN:24354112)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.37-55, 2022-07-13
2 0 0 0 OA Petavatthu-Atthakatha に示される anumodana
- 著者
- 藤本 晃
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.448-446, 2000-12-20 (Released:2010-03-09)
2 0 0 0 OA 人工知能の社会的側面-ELSIに関わる動向
- 著者
- 西田 豊明
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.12, pp.586-590, 2018-12-01 (Released:2018-12-01)
2011年ころから第3回目のブームとなった現代人工知能技術の特色は,社会を広く巻き込んでいる点である。本稿では,人工知能の本質について議論した上で,倫理的,法的,社会的課題(Ethical, Legal and Social Issues, ELSI)への取り組みの現状を俯瞰し,その原則的な側面についての議論の概要をまとめ,利活用の視点からの検討を紹介する。さらに,ELSI問題のはっきりと捉えにくい側面についても触れ,今後の見通しを探る。
2 0 0 0 OA CBT得点と歯科医師国家試験合格率との関係
- 著者
- 安尾 敏明 友藤 孝明 田村 康夫
- 雑誌
- 岐阜歯科学会雑誌 = The Journal of Gifu Dental Society (ISSN:24330191)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.2, pp.121-127, 2021-10
CBTの得点(以下、CBT得点)結果と歯科医師国家試験の合否結果との関係については明らかになっていない。そこで、本研究では、歯学教育上の観点から、CBTの結果と歯科医師国家試験合格率(以下、合格率)との関係について明らかにすること、そして、歯学部学生と教員のために歯科医師国家試験に合格するための目安となるCBTの目標点を統計的に設定することを目的とした。資料は、朝日大学における直近6回(第109回~114回)の歯科医師国家試験を受験した学生のCBT得点とした。CBT得点に基づいて、①96-100点群、②91-95点群、③86-90 点群、④81-85点群、⑤76-80点群、⑥71-75点群、⑦66-70点群、⑧61-65点群および⑨0-60点群の9群と71点群から75点群の5群に分け、各群の合格率を算出した。その結果、①群から③群は100%、次いで④群は90.5%、⑤群は85.2%であった。一方、⑥群から⑨群は、順に、63.7%、50.0%、60.0%、30.0%と低値であった。⑥群を境に合格率が低値となっていたことから、その境目のCBT得点を明らかにするために、まず、⑥群を1点毎に5群に分けて検討した。その結果、各群の合格率は71点群から順に、50.0%、42.1%、73.7%、54.2%、88.5%であった。次に、受信者動作特性分析を行った。その結果、CBT得点の曲線下面積は0.809であった。また、Youden Indexに基づいた最適カットオフ値は74.50点であった。以上の結果から、朝日大学ではCBT得点が86点以上か否かで歯科医師国家試験に全員合格するかどうかの一つ目のボーダーがあり、次いで75点以上か否かで二つ目のボーダーがあるように考えられた。
2 0 0 0 「自由民権」時代 : 板垣伯から星亨まで
2 0 0 0 OA 馬尾性間欠跛行に対する運動療法の効果
- 著者
- 林 典雄 吉田 徹 見松 健太郎
- 出版者
- 日本腰痛学会
- 雑誌
- 日本腰痛学会雑誌 (ISSN:13459074)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.165-170, 2007 (Released:2008-01-22)
- 参考文献数
- 14
馬尾性間欠跛行を主訴に運動療法を実施した23例を対象とし,その効果について検討した.初診時実測した歩行距離に対し,硬膜管面積とわれわれが考案した腰椎後弯可動性テスト(PLF test)において,有意な正の相関を認めた.また22例に腸腰筋と大腿筋膜張筋に拘縮を認めた.われわれが行った,股関節ならびに腰椎の拘縮改善を目的とする運動療法は,21例(91.3%)に有効であり,初診時平均102.1 mの歩行距離が,1カ月後で8例(38.0%),2カ月後で15例(71.4%)で1 km以上の連続歩行が可能となった.その他の6例も,平均640 mの歩行が可能であった.股関節の拘縮の改善は,歩行時の骨盤前傾トルクの軽減ならびに腰椎過前弯の減少に寄与すると考えられた.また,腰椎後弯域の改善による動的pumping effectの促進は,硬膜外静脈叢の還流改善に作用し,歩行改善を得たと考察した.拘縮要素が存在する間欠跛行例では,2カ月程度を目処に運動療法を試みる価値があると考えた.
2 0 0 0 OA 一揆とコミュニタス・無縁・コモン : 二重社会という視点から
- 著者
- 小田 亮
- 出版者
- 東京都立大学人文科学研究科人文学報編集委員会
- 雑誌
- 人文学報. 社会人類学分野 = THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (JIMBUN GAKUHO) (ISSN:03868729)
- 巻号頁・発行日
- no.518-2, pp.1-18, 2022-03-22
2 0 0 0 樗牛・鴎外・漱石 : 明治の肖像画
2 0 0 0 随筆寄席 : 放談千夜
- 著者
- 辰野隆, 林髞, 徳川夢声 著
- 出版者
- 春歩堂
- 巻号頁・発行日
- vol.第3, 1960