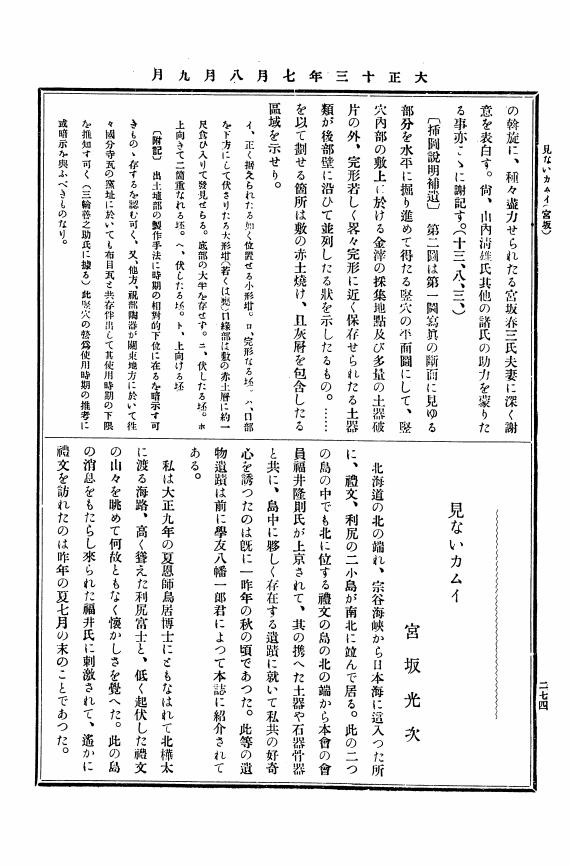2 0 0 0 OA <論文>脱商品化論におけるG. エスピン=アンデルセンとK. ポランニー
- 著者
- 永嶋 信二郎
- 出版者
- 学校法人白百合学園 仙台白百合女子大学
- 雑誌
- 仙台白百合女子大学紀要 (ISSN:13427350)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.35-56, 2017 (Released:2018-07-20)
2 0 0 0 OA ゴムホースのオゾン劣化
- 著者
- 牧野 保
- 出版者
- 一般社団法人 日本ゴム協会
- 雑誌
- 日本ゴム協会誌 (ISSN:0029022X)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.4, pp.314-317, 1967-04-15 (Released:2009-10-16)
2 0 0 0 OA 中高ドイツ語の宮廷叙事詩における愛の内面化について
- 著者
- 渡邊 徳明
- 出版者
- Tohoku University
- 巻号頁・発行日
- 2015-03-25
課程
2 0 0 0 OA 異形の図像学 -イタリア・ラヴェンナの怪物像をめぐって-
- 著者
- 松平 俊久
- 出版者
- 早稲田大学大学院人間科学研究科
- 雑誌
- ヒューマンサイエンスリサーチ (ISSN:09189769)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.133-149, 2004-07-30
- 著者
- 本田 優子
- 出版者
- 解放出版社
- 雑誌
- 部落解放 (ISSN:09143955)
- 巻号頁・発行日
- no.646, pp.94-97, 2011
2 0 0 0 OA 『ねじまき鳥クロニクル』第1部・第2部における「マクガフィン」
- 著者
- 野村 廣之
- 出版者
- 北里大学
- 雑誌
- 北里大学一般教育紀要 (ISSN:13450166)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.51-76, 2013-03-31
2 0 0 0 OA PCR/抗原・抗体検査から見た現状と今後-with COVID-19を踏まえて
- 著者
- 山田 全毅
- 出版者
- 一般社団法人 日本臓器保存生物医学会
- 雑誌
- Organ Biology (ISSN:13405152)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.31-36, 2021 (Released:2021-02-10)
- 参考文献数
- 13
Since the COVID-19 pandemic, there have been remarkable advances in diagnosis. Initially, the indication for diagnostic tests was strictly controlled by the government. Currently, however, various tests, from point-of-care testing to rapid PCR, are available for many clinics and hospitals. At the same time, the interpretation of test results became harder due to the existence of different types of testing as well as different qualities in the same type of testing. This review aims to overview the available test types and understand the basics of these tests to interpret the test results appropriately, especially in transplant recipients.
- 著者
- 宮野 晃寿 藤岡 正博 遠藤 好和 宮野 晃寿 藤岡 正博 遠藤 好和
- 出版者
- 筑波大学農林技術センター
- 雑誌
- 筑波大学農林技術センタ-演習林報告 (ISSN:09121765)
- 巻号頁・発行日
- no.27, pp.47-70, 2011-03
2 0 0 0 トンボ相修復に向けたビオトープ池に繁茂したスイレンの除去効果
<p>トンボ池創出後の園芸スイレンの繁茂に対し,除去効果を検討した。スイレンに覆われた水域に15m<sup>2</sup>のスイレンを除去した開放水面区画を設け,トンボ類の飛来回数を非除去区画と比較した。初夏から秋季にかけての計10回の調査により,3科9種の計127回の飛来を確認した。それぞれ飛来数の多くなる繁殖期間で比較すると,シオカラトンボ(開放水面区:平均1.5~4回,繁茂水面区:平均0.3~0.7回)とギンヤンマ(同:平均2~3.3回,同:平均0.7~1回)が開放水面区に有意に多く飛来していた。確認数は多くはなかったが,クロスジギンヤンマは非確認であった繁茂水面区に対し,開放水面区に飛来する傾向が認められた。一方,必ずしも繁殖に広い開放水面を必要としないアオモンイトトンボでは,条件間で飛来回数に有意差は認められなかった。繁茂スイレンの除去はトンボ相修復に対して一定の効果が期待されるものの,飛来が期待されたかつての生息記録種の飛来は多くはなく,対象水域周辺地域のトンボ類の生息状況も影響していると考えられた。</p>
2 0 0 0 OA タンザニアにおけるタケ酒の商品開発と環境保全
林の劣化が深刻なアフリカの半乾燥地域において、在来のタケを植林体系に組み込むことで環境保全と農村の生活改善を両立する可能性について検討した。タンザニア南部では、アフリカに広く分布するOxytenanthera abyssinicaという木本性のタケからウランジという酒を造り販売している。この研究では、世界的にも類い希なこの酒の製造方法を詳細に記録するとともに、そのメカニズムを解明した。また、ウランジ特有の風味を化学的に分析し、それを損なわずに再現できる方法を見つけ商品化の可能性を見いだした。さらに、この竹林がもつ環境保全の機能についても確認し、短・長期的な植生復興のあり方を構想した。
2 0 0 0 OA 明治以降昭和戦前までの北海道における観光的取組の展開過程に関する研究
- 著者
- 大西 律子 渡邉 貴介
- 出版者
- 日本観光研究学会
- 雑誌
- 観光研究 (ISSN:13420208)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.2, pp.25-34, 1998 (Released:2017-04-01)
This study aims to clarify the evolution process of tourism policies and developments in Hokkaido pushed by the authority since the Meiji era to the beginning of the Showa era. Based on related historical documents the chronological table is originally made, on which the analysis is concluded. The findings are as follows; (1) The development process can be divided into three stages in broad sense and into six in precise sense. (2) Through the process seven strategic ideas had been invented or introduced in Hokkaido, most of which were more leading than in other parts of Japan.
2 0 0 0 IR 企業売買におけるMAC条項の機能について -契約条項によるリスク配分の一例として-
- 著者
- 中村 肇
- 出版者
- 明治大学法科大学院
- 雑誌
- 明治大学法科大学院論集 (ISSN:2187364X)
- 巻号頁・発行日
- no.24, pp.25-59, 2021-03-31
2 0 0 0 IR 角倉素庵『和歌短冊(雨中鶯)』の再出現
- 著者
- 林 進
- 出版者
- 関西大学博物館
- 雑誌
- 阡陵 : 関西大学博物館彙報 (ISSN:09131906)
- 巻号頁・発行日
- no.82, pp.6-7, 2021-03-31
2 0 0 0 OA 中世における『源氏物語』古注釈の研究
- 著者
- カラーヌワット タリン
- 出版者
- 早稲田大学
- 巻号頁・発行日
- pp.1-180, 2017
早大学位記番号:新7763
2 0 0 0 OA ネットワーク社会における〈告白〉事情
- 著者
- 山口 達男
- 出版者
- 一般社団法人 社会情報学会
- 雑誌
- 社会情報学 (ISSN:21872775)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.2, pp.55-70, 2021-02-28 (Released:2021-03-16)
- 参考文献数
- 24
本稿は,Z. BaumanがSNSやインターネットへのアップロードを「告白」として捉え,それらが日常的に行なわれている現代社会を「告白社会」と評したことに対して,批判的に検討する試みである。その際にまずM. Foucaultの議論を参照し,4~5世紀の修道院で行なわれていた「エグザコレウシス」や,中世以降のキリスト教における「告解」の特徴を整理することで,キリスト教的告白には「権力関係」「言表行為」「文脈依存」「秘密主義」という四つの特徴があることを明らかにした。次に,非キリスト教的な在り方を探るため,日本近代文学で描かれてきた告白についても言及した。そこでもやはり「権力関係」「言表行為」という特徴を見出すことができた。他方,インターネットをコミュニケーションの技術的な基盤としている現代社会にとって,こうした特徴はすべて無効化されてしまう。「ネットワーク」の特性として「平面化」「データ化」「脱文脈化」「透明化」を挙げることができるからだ。つまり,ネットワークの特性は告白の特徴を無化してしまうのである。したがって,ネットワーク社会の現代では,SNSやインターネット上で告白するのは不可能な営みと指摘できる。むしろ,ネットワークの特性から窺えるのは,われわれのあらゆる情報がインターネット上に〈露出〉していってしまう状況である。すなわち,われわれはインターネットに向けて何かを告白しているのではなく,ネットワークの「運動」によってわれわれの営みが露出させられているのだ。このことを踏まえると,Baumanが評したのとは異なり,現代社会は「告白社会」ではなく〈露出化社会〉と称すべきだと言い得る。
2 0 0 0 重回帰分析を用いた病院毎の血液製剤使用量の予測モデルとその評価
- 著者
- 関本 美穂 今中 雄一 吉原 桂一 米野 琢哉 白井 貴子 ジェイスン ・リー 佐々木 弘真
- 出版者
- The Japan Society of Transfusion Medicine and Cell Therapy
- 雑誌
- 日本輸血細胞治療学会誌 (ISSN:18813011)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.347-353, 2010
Disease Procedure Combination(DPC)データには臨床情報および詳細な輸血情報が含まれるため,輸血リスクを考慮した血液製剤使用量評価に利用できる可能性がある.われわれはDPCデータを利用して,73の急性期病院における血液製剤使用状況を調査し,血液製剤を多く消費する疾患や手術を検討した.また病院ごとの血液製剤使用量を予測する3つの重回帰分析モデルを作成し,R<sup>2</sup>値を使ってその予測能を評価した.最初のモデルは,病院機能に関する5つの変数(病床数,全身麻酔下手術数,心臓手術の実施,造血幹細胞移植の実施,血漿交換の実施)を予測因子とした.2つ目のモデルでは,年齢分布および血液製剤を多く使用する疾患・手術の年間1病床あたり件数を予測因子とした.3つ目のモデルはDPC診断群分類を利用して血液製剤の使用量を予測した.血液製剤の大部分が,特定の疾患・手術を受けた患者により消費されていた.診断群分類を用いた予測モデルは,輸血のリスクや血液製剤の使用量を診断群分類ごとに細やかに考慮できるために高い予測能を示した.一方,血液製剤の使用量が多い疾患や手術の症例数から使用量を予測するモデルも,比較的良好な予測能を示した.しかし病床数や全身麻酔下手術数は,血液製剤の使用量と関連しなかった.DPCデータを利用した血液製剤使用状況の解析は,少ない労力で大量のデータを処理でき,また各病院における疾患分布を考慮して血液製剤使用量を評価できる.<br>
2 0 0 0 OA 見ないカムイ
- 著者
- 宮坂 光次
- 出版者
- 一般社団法人 日本人類学会
- 雑誌
- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.7-9, pp.274-279, 1924-11-14 (Released:2010-06-28)