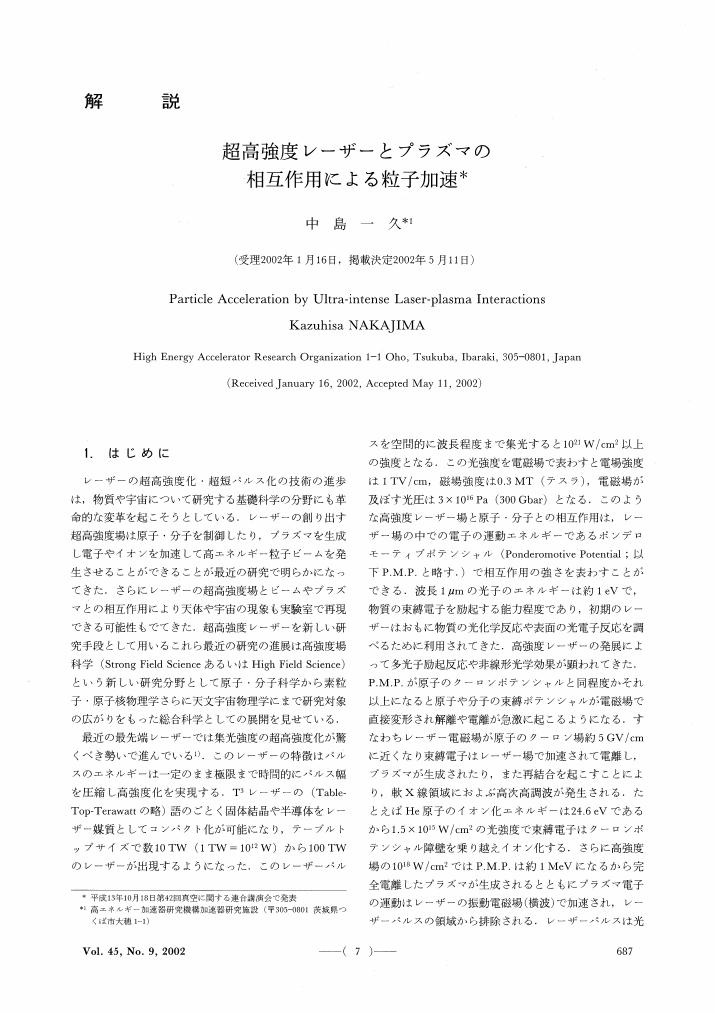2 0 0 0 OA グレーン・ウィスキーの樽貯蔵について
- 著者
- 辻 謙次
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.7, pp.481-486, 1991-07-15 (Released:2011-09-20)
- 参考文献数
- 17
洋酒の代表であるウィスキーは蒸留酒であるが, あのすばらしい香味の発現は熟成過程を経過することにより得られる。特に樫樽との関係は切っても切れない関係にあり, 品質を左右する大きな鍵を握っていると言っても過言ではない。そこで, ウィスキーの熟成等の研究を通じて, 最高級のウィスキー造りに情熱を燃やしておられる筆者に, 樫樽貯蔵中における熟成のメカニズムについて解説していただいた。
2 0 0 0 体言承接のタリの位置づけ
- 著者
- 吉田 永弘
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.78-92, 2006-01-01
いわゆる断定の助動詞のタリは,従来ナリと比較して考察され,ナリに比して文体・用法の面で制約のあることが明らかになった。しかしながら,それが何を意味するのかについては必ずしも明らかになっているとは言えない。そこで本稿では,タリの制約の理由を明らかにし,語法上の位置づけを試みる。まず,主として文体・上接語の偏りに着目し,タリがナリとではなくニテアリと相補的な関係にあることを指摘する。そして,断定表現ではなく存在表現であることを主張し,文法化を果たさなかった形式であることを述べる。あわせて,ニテアリが中世に文法化することを確認し,タリが衰退する契機をニテアリの文法化に求める。
2 0 0 0 事実上の公務員の法理--フランス公法学における三変化
- 著者
- 木村 琢麿
- 出版者
- 千葉大学
- 雑誌
- 法学論集 (ISSN:09127208)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.79-139, 2000-07
2 0 0 0 OA ポストモダン教育社会学の展開と隘路,そして生政治論的転換
- 著者
- 加藤 隆雄
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, pp.5-24, 2014-05-31 (Released:2015-06-03)
- 参考文献数
- 49
「ポストモダン」論によって影響を受けた1980年代後半の日本の教育社会学を「ポストモダン教育社会学」と呼ぶことにする。それは,「モダン」としての教育・学校制度の異化に向かったが,アリエス,ブルデューと並んでインスピレーションの供給源となったのが,『監獄の誕生』におけるフーコーの「規律訓練」の視点であった。しかし,1990年代以降の教育システムの変動によって,異化の手法で捉えられた教育・学校制度の理解は不十分なものとなり,ポストモダン教育社会学の訴求力も低下していく。他方,フーコー研究においては,2000年代以降,規律訓練の概念が「生政治」論の一部であることが明らかになるのだが,1990年代以降の教育システムは,まさにこの生政治論的視点からよりよく捉えうることをフーコー理論を概略しながら論じた。
2 0 0 0 OA 霞堤の機能と語源に関する考察
- 著者
- 大熊 孝
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 日本土木史研究発表会論文集 (ISSN:09134107)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.259-266, 1987-06-20 (Released:2010-06-15)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 2
霞堤の機能は、従来の河川工学関係書では、堤防の重複部分における遊水による下流に対する洪水調節効果が、第一番に挙げられてきた。しかし、霞堤は一般的には河床勾配が600ないし500分の1より急な河川において造られており、その場合、遊水面積が限定されており遊水効果はほとんど無く、むしろ、万一破堤した場合の “氾濫水のすみやかなる河道還元” に主限があった。本論文は、まず、このことを明らかにする。しかし、愛知県の豊川と三重県の雲出川では、河床勾配が数千分の1から千分の1. という緩いところに、霞堤と呼ばれる不連続堤がある。この場合の霞堤は、洪水遊水効果に第一の目的があると言わねばならない。ところで、急流河川における霞堤は現在でも各所で見かけることができるが、緩流河川における霞堤は管見にして豊川と雲出川だけである。豊川や雲出川の洪水遊水方式は、江戸時代では一般的に採用されていた治水方式でもある。しかし、これらは江戸時代に霞堤とは呼ばれていない。一方、急流河川の霞堤も、江戸時代には「雁行二差次シテ重複セル堤」と表現されてはいるが、霞堤という呼称は与えられていない。急流河川の霞堤と緩流河川の霞堤とでは、形態上は似ていても機能上はまったく異なるわけであり、何故同じ名称で、何時からそう呼ばれるようになったかが問題である。そこで、本論文の第二の目的として、霞堤の語源について探索してみる。結論として、“霞堤” なる言葉は江戸時代の文献には現われず、明治時代以降に定着したものであり、その際、急流河川と緩流河川の不連続堤の機能上の違いを明確に認識しないまま、両者とも霞堤と呼ぶようになったことを明らかにする。そして、今後は少なくとも、“急流河川型霞堤” とか “緩流河川型霞堤” とか、区別して呼びならわす必要があることを提言する。
2 0 0 0 OA 日本英文学会第 41 回新人賞選評・第 42 回新人賞規程
- 出版者
- 一般財団法人 日本英文学会
- 雑誌
- 英文学研究 (ISSN:00393649)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, pp.181, 2018 (Released:2018-12-31)
2 0 0 0 漢方薬で蘇った金魚の治験例
2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1947年10月10日, 1947-10-10
- 著者
- 神永 正史
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.1-15, 2015-04-01
日本語の大きな変革期にあたる中世末期の口語資料である狂言台本虎明本には,有情物を主語とし,動詞連用形に「〜てある」がついた形で,アスペクトの動作の完成(〜シタ)の意味を表す用例が多数みられる。中古の「〜てあり」には全くみられなかったこの用例が,なぜ中世末期という時期にみられるのか,主語が有情物なのにどうして「〜ている」が用いられなかったのか,また,この用例がその後みられなくなったのはなぜかなどについて,抄物資料の「中華若木詩抄」や,狂言台本の虎寛本,および近松の世話浄瑠璃等を資料にして考察を試みた。その結果,完成の「〜てある」の出現は,テンス形式(た)の発生に伴う「たる」の衰退によるものであり,また,その消滅は,その後の,「たる」から生じた「た」への吸収によるものであることを明らかにした。
2 0 0 0 OA 成形圖説
- 著者
- 曽槃, 白尾國柱 [ほか編]
- 巻号頁・発行日
- vol.巻13, 1800
2 0 0 0 ハネナシナガクチキの採集法と幼生期の生態
- 著者
- 蟹江 昇
- 出版者
- むし社
- 雑誌
- 月刊むし : a monthly journal of entomology (ISSN:0388418X)
- 巻号頁・発行日
- no.515, pp.36-38, 2014-01
2 0 0 0 OA On the Authorship of the Genus-group Name Curtipleon (Crustacea: Tanaidacea: Metapseudidae)
- 著者
- Keiichi Kakui Takafumi Nakano
- 出版者
- The Japanese Society of Systematic Zoology
- 雑誌
- Species Diversity (ISSN:13421670)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.179-180, 2019-07-25 (Released:2019-07-25)
- 参考文献数
- 15
The genus-group name Curtipleon Bǎcescu, 1976 is not available due to Bǎcescu’s failure to fix its type species in the original publication. This genus-group name should be attributed to Sieg (1983)—the work accidentally validated the genus-group name under Article 13 of the International Code of Zoological Nomenclature.
- 著者
- 大塚 文彦 小島 昭 居石 浩己 平野 享
- 出版者
- 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会技術報告 (ISSN:13426893)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.5, pp.37-39, 2004-01-30
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 五ツノダルマ ヘイ吉捕物帖 第六話
2 0 0 0 OA 超高強度レーザーとプラズマの相互作用による粒子加速
- 著者
- 中島 一久
- 出版者
- The Vacuum Society of Japan
- 雑誌
- 真空 (ISSN:05598516)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.9, pp.687-692, 2002-09-20 (Released:2009-10-20)
- 参考文献数
- 11
2 0 0 0 神戸市新交通システム調査(海岸線)報告書
- 著者
- 運輸経済研究センター [編]
- 出版者
- 運輸経済研究センター
- 巻号頁・発行日
- 1976
2 0 0 0 OA 翅のはばたきによる力を考慮した蝶の飛翔モデル
近年,バーチャルリアリティなどの映像表現のために,動物のコンピュータグラフィックスに関する研究が行われているが,蝶などの昆虫の例は少ない.本報告では蝶の飛翔のリアルタイム表示を目的とした飛翔モデルを提案する.本モデルでは,翅のはばたきによる力によって蝶を飛翔させる.これにより蝶らしい飛翔,すなわち,ひらひら舞う様子を表現でき,モデルのパラメータ調整により実際の蝶の典型的な飛翔形態を表現することができる.
2 0 0 0 OA 印度支那総覧
- 著者
- るべ博覧会印度支那委員会 等編
- 出版者
- Roubaix博覧会印度支那委員会
- 巻号頁・発行日
- 1915
- 著者
- 清水 房 池田 揚子 小笠原 庸子 SHIMIZU FUSA IKEDA YOKO OGASAWARA YASUKO
- 出版者
- 岩手大学教育学部
- 雑誌
- 岩手大学教育学部研究年報 = Annual report of the Faculty of Education, University of Iwate (ISSN:03677370)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.3, pp.73-84, 1970-12-01