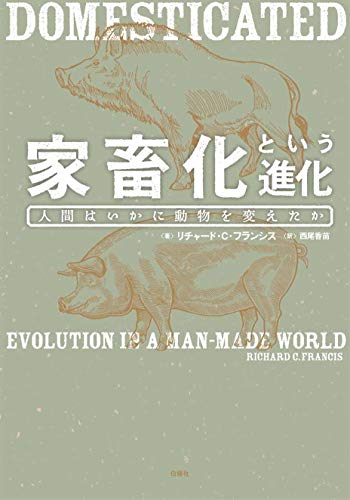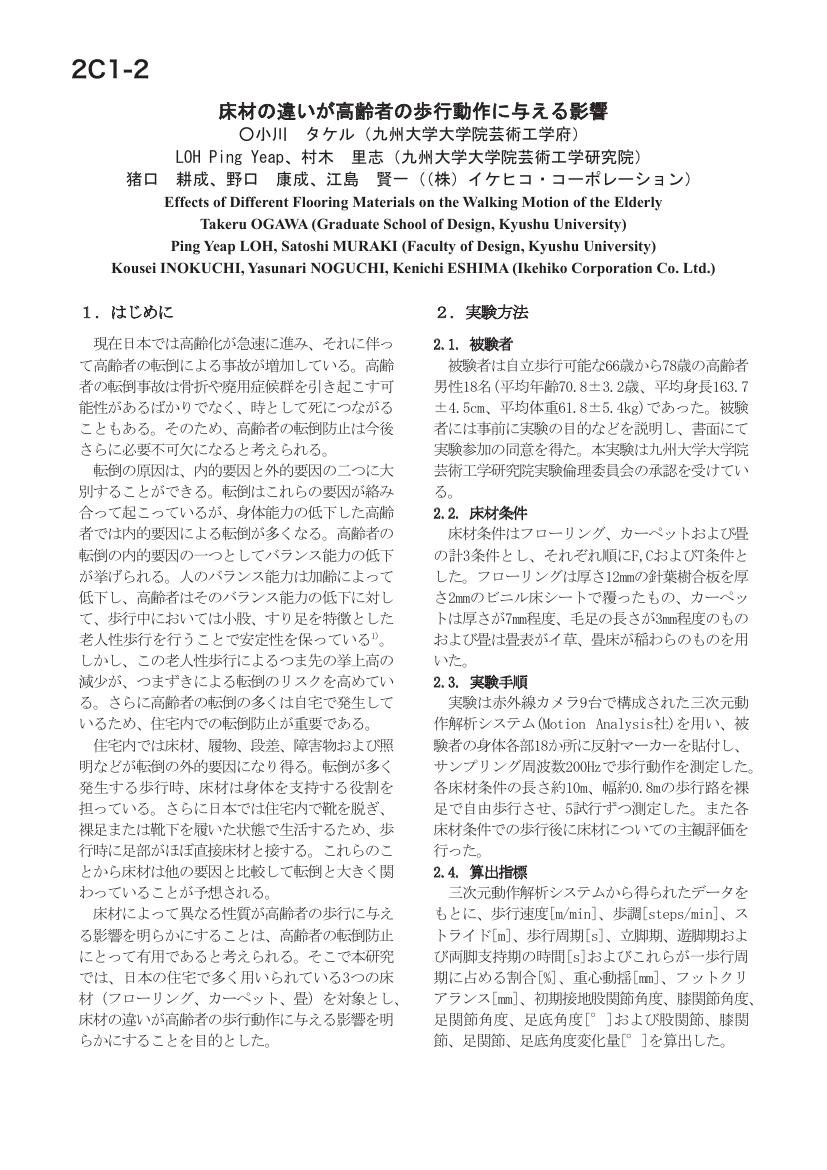- 著者
- 西垣 順子
- 出版者
- 大阪市立大学
- 雑誌
- 大学教育 (ISSN:13492152)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.1-12, 2012-09
2 0 0 0 OA 浦井康男著『露語からチェコ語へ ロシア語学習者のためのチェコ語入門(文法編)』
- 著者
- 佐藤 規祥
- 出版者
- 日本ロシア文学会
- 雑誌
- ロシア語ロシア文学研究 (ISSN:03873277)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, pp.248-253, 2018-10-15 (Released:2019-05-22)
2 0 0 0 IR 拡大パーソナルネットワーク概念と年賀状事例調査の方法論的検討 (特集 都市の環境と社会経済システム) -- (地方都市住民の拡大パーソナルネットワーク--年賀状調査にもとづく事例分析)
- 著者
- 矢部 拓也
- 出版者
- 東京都立大学都市研究センター
- 雑誌
- 総合都市研究 (ISSN:03863506)
- 巻号頁・発行日
- no.76, pp.97-113, 2001-12
本研究の目的は、拡大パーソナルネットワーク分析を目的として、これまで2度行ってきた年賀状事例調査の方法論的検討を行うことである。本研究と同様の拡大パーソナルネットワークを研究対象としているボワセベンの研究と比較することで、年賀状事例調査の特徴を整理した。その結果、年賀状事例調査は、基本的には対象者と直接の紐帯をもつ人々との関係(2者間の相互作用上の関係)に関しては、多くの要因に関して分析可能であるが、ネットワークの構造を現す諸変数に関してはわずかに「規模」と間接的に「クラスター」を測定できるに留まっていることが明らかになった。また、ボワセベンのパーソナルネットワークのモデルでは、ネットワークは「親しさ」という一元的な規準によって同心円的に配置されるが、年賀状調査の結果では、「親族」「友人」「同窓生」「同僚」「サークル仲間」・・・・といった、社会的文脈ごとにパーソナルネットワークがまず区分され、その上で各カテゴリーごと独自の分類規準が存在している様相が明らかになった。そしてこれらの社会的文脈は、対象者のライフヒストリーとも関連している。そのため、年賀状事例調査では、パーソナルネットワーク形成過程とライフヒストリーとの関連を明らかにすることができるという利点をもっている。最後に、このような年賀状事例調査の利点が生かせる対象である武蔵野市のコミュニティ活動のリーダー2名のパーソナルネットワークの事例分析を行った。コミュニティ活動に参加する過程を、ライフヒストリーと既存のパーソナルネットワークの再編過程から描き、パーソナルネットワークの形成発展過程の一事例を示した。The purpose of this paper is to reconsider the method of a case study of personal network using New Year's Cards (Nengajo). The case study of this kind was conducted twice for the analysis of the loose-network (week ties). I have compared the method of our study with Boissevain's network study for the clarification of the advantage of the method used in our study. The case study using New Year's Cards has an advantage in analyzing interrelationship between ego and others. However,it also has a disadvantage in analyzing the structure of the network (e.g. the density of network). This study describes the inner-structure of individuals' personal network. At first individuals' personal network is classified into some categories based on social contexts,for example,kin,friends,colleagues,club activity's members and so on. Second,each category is subdivided. There are many criteria for such subdivisions of personal networks,for example,intimacy,frequency of meeting,and so on. These factors are closely related to individuals' life-course. Therefore,it is possible that we describe the processes of how individuals' personal networks come to form and how their life-course is related in such processes. Furthermore,two case studies are examined,using New Year's Cards as a methodological tool. They clearly show the methodological advantages described above. The two informants in this study are the members of a community organization in the Musashino-city. I have described the process of their participation in community activities from a viewpoint of the relationship between their life-course and reorganization of their personal network.
2 0 0 0 OA OS-07 人工知能の法学への応用 背景と概要
- 著者
- 見供 翔 市川 和奈 宇佐 英幸 小川 大輔 古谷 英孝 竹井 仁
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.6, pp.869-874, 2017 (Released:2017-12-20)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 2
〔目的〕中殿筋各線維間の異なる作用を明らかにすることとした.〔対象と方法〕健常男性(平均年齢22~34歳)とした.運動課題は30%最大随意収縮の強度での異なる方向への静止性股関節外転運動(1:外転,2:外転+屈曲,3:外転+伸展)とした.運動課題前後の中殿筋各線維の筋厚と筋腱移行部距離は超音波画像から計測し,ぞれぞれの変化率を算出した.〔結果〕筋厚に関して中殿筋前部線維は課題2で,中殿筋後部線維は課題3で有意に高い変化率を示した.筋腱移行部距離変化率は筋厚変化率と同様の結果を示した.〔結語〕中殿筋前部線維は股関節外転作用に加えて屈曲作用を,中殿筋後部線維は伸展作用を有していることが示唆された.
2 0 0 0 IR 文学性の生成モデル
- 著者
- 橘高 眞一郎
- 出版者
- 佛教大学
- 雑誌
- 文学部論集 (ISSN:09189416)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, pp.77-91, 2009-03-01
文学性とは何なのか。その生成過程はどのようなものなのだろうか。本稿では、まずロシア・フォルマリズムのV.Shiklovskyの異化やプラハ言語学派のR.Jacobsonの詩的機能を基にしたD.Miall and D.Kuikenのモデル、D.Sperber and D.Wilsonの関連性理論(詩的効果)や認知科学でいう認知的ずれを取り入れた内海のモデル、スキーマ理論を基にしたP.Stockwell のモデルを比較検討し、それら3つのモデルが補完的な関係にあることを指摘する。次にJ.Kristeva の提唱した間テクスト性が、それらのモデルが相互作用するための文学作品の認知という基盤を提供すると同時に、創造的な読み(間読み性)を生成することを指摘し、そのことを考慮した間テクスト性基盤モデルを提案する。最後に、そのモデルを用いて、E.Hemingwayの短編小説を分析し、文学性が生成される過程を検証する。
2 0 0 0 家畜化という進化 : 人間はいかに動物を変えたか
- 著者
- リチャード・C・フランシス著 西尾香苗訳
- 出版者
- 白揚社
- 巻号頁・発行日
- 2019
2 0 0 0 OA 熟成蒸留酒の平衡蒸気成分
- 著者
- 赤星 亮一 大熊 広一
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.135-141, 1985 (Released:2008-11-21)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 1 1
市販の熟成ブランデーおよび熟成ウィスキーの蒸気圧,その平衡蒸気成分を測定し,熟成現象とこれらの関係について明らかにした. (1) 長年月貯蔵熟成した蒸留酒のエタノール蒸気分圧および気相エタノール濃度は,同濃度のエタノール水溶液より低く,貯蔵期間に比例して低下してゆく. (2) 蒸留酒のエタノール蒸気分圧,気相エタノール濃度に影響を与える微量成分として考えられる酢酸エチル,アセトアルデヒド,イソブタノール,イソアミルアルコール,酢酸,メタノール,樽材浸出物について,その影響を明らかにした. (3) 熟成蒸留酒では,上記微量成分の影響以上にエタノール蒸気分圧および気相エタノール濃度が低下していることが判明した. (4) 熟成蒸留酒におけるエタノール蒸気分圧,気相エタノール濃度の低下は,液相中でエタノール分子が強く束縛されていることを示している.熟成した蒸留酒では,エタノール分子と水分子が水素結合により会合し,安定なクラスターが生成していると考えられる. (5) 長期間貯蔵した蒸留酒のエタノール蒸気分圧,気相エタノール濃度の減少は,熟成によってエタノール特有の刺激が減少する香味の円熟をよく説明している.
2 0 0 0 OA 熟成蒸留酒の融解潜熱について
- 著者
- 赤星 亮一 大熊 広一
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.1-9, 1985 (Released:2008-11-21)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1 1
DSCを用いてエタノール水溶液および長年月熟成のウィスキー,ブランデー,エタノール水溶液の熱分析を行い,蒸留酒の熱的挙動と熟成の関係について研究を行った. (1) 熟成蒸留酒,エタノール水溶液いずれも,その融解サーモグラム上に2つの吸熱ピーク1, 2と1つの発熱ピーク3が観測された. (2) 熟成蒸留酒の各ピークの出現温度は,同エタノール濃度のエタノール水溶液と同じで貯蔵期間による差異は認められなかった.一方,各ピークの面積から算出した融解熱については,ピーク2およびピーク3に大きな差異が認められ,熟成蒸留酒では著しく減少していることが認められた.熟成蒸留酒におけるピーク2の減少は貯蔵期間に比例していた. (3) 蒸留酒中の主要微量成分である酸,エステル,アルデヒド,フーゼル油,樽材浸出物等が融解サーモグラムに与える影響について検討を行った.エステル,アルデヒド,フーゼル油の場合,いずれも含有される濃度範囲においては,その影響はほとんど認められなかった.酸および樽材浸出物はピーク2の融解熱を減少させるが,熟成に伴う熱量値の減少は,これらの影響よりもはるかに大きいものであった. (4) これらの実験結果は,熟成蒸留酒中ではエタノール分子が強く束縛されていることを示しており,熟成した蒸留酒やエタノール水溶液が固体に近い凝集状態に移行し,安定な液体構造が形成されていると考えられる.熟成によってエタノール特有の刺激が減少する蒸留酒の香味の円熟をよく説明しているものといえる.
2 0 0 0 OA 蒸留酒のまろやかさと物理的熟成
- 著者
- 古賀 邦正
- 出版者
- 公益社団法人 高分子学会
- 雑誌
- 高分子 (ISSN:04541138)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.9, pp.695, 1980-09-01 (Released:2011-09-21)
- 被引用文献数
- 1 1
2 0 0 0 OA ポスト・コミュニタリアニズムの展開─「リベラル・コミュニタリアン論争」以後の位相─
- 著者
- 坂口 緑
- 出版者
- 明治学院大学社会学部付属研究所
- 雑誌
- 明治学院大学社会学部付属研究所研究所年報 = Bulletin of Institute of Sociology and Social Work, Meiji Gakuin University (ISSN:09114831)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, pp.57-64, 2018-03-20
【研究論文/Articles】
- 著者
- 呉 揚
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.1-17, 2015-01-01
空間的配置動詞「そびえる」は、金田一(1950)では終止述語になるとき必ずシテイル形式になるとされる。一方、影山(2012)では「そびえる」にはシテイル形式もスル形式もあるとし、両形式によって事象叙述と属性叙述が区別されると主張する。本稿では、テクストとの相関性を全面的に視野に入れ、「そびえる」のアスペクト・テンス形式のテクストにおける分布の実態を調査し、その意味と機能について考察した。その結果、「そびえる」は、非アクチュアルなテクストに現れ、恒常性を表す客観的用法を基本とするが、出来事の展開のあるアクチュアルなテクストでは、書き手と登場人物の捉え方や他の出来事との時間関係が浮かびあがってきて、主観的な側面とタクシス的機能が前面に出てくることが明らかになった。「そびえる」に限らず、空間的配置動詞のアスペクト・テンス形式を分析する際には、テクストとの相互作用を考慮しなければならない。
2 0 0 0 OA 酒
- 著者
- 石本 省吾
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.8, pp.850-851, 1968-08-15 (Released:2011-11-04)
2 0 0 0 OA 沖繩返還交渉-日本政府における決定過程
- 著者
- 福井 治弘
- 出版者
- JAPAN ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RELATIONS
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.1975, no.52, pp.97-124,L3, 1975-05-10 (Released:2010-09-01)
- 参考文献数
- 51
The article attempts to analyze and explain the decision process of Okinawa reversion in the Japanese government as a case of what the writer calls a model of “critical” decision making. The model and its general paradigmatic perspective are outlined in the first section, while the middle section discusses in terms of the model five selected events in the evolution of the reversion issue in the years 1964-69. The last section summarizes the major points of the discussion and suggests that the model used in the study deserves further elaboration and refinement as a potential additional tool of empirical research and theory building in foreign policy decision making, in the Japanese government and in general.
2 0 0 0 OA 介護支援専門員調査より得られた薬剤師が優先的に取り組む要介護者の抱える薬の問題
- 著者
- 堀井 徳光 井上 直子 大嶋 繁 冲田 光良 秋元 勇人 根岸 彰生 大島 新司 沼尻 幸彦 小林 大介
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年薬学会
- 雑誌
- 日本老年薬学会雑誌 (ISSN:24334065)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.2, pp.28-33, 2018-09-30 (Released:2019-10-07)
- 参考文献数
- 19
In the Integrated Community Care System, pharmacists are expected to play a central role in addressing patients’ drug problems. Therefore, it is necessary to know the patients’ drug problems as well as the occupations of professionals in solving these problems, and to clarify the problems to be preferentially resolved. Thus, we surveyed care managers working in a district near the Josai University pharmacy about their drug problem recognition and the professionals who solved these problems. Many of the care managers identified “the patient has leftover drugs” and “the patient has declining cognitive abilities” as drug problems. Many of the care managers expected pharmacists to solve the problems of “the patient has leftover drugs” and “the patient does not understand the dosage regimen.” “The patient has leftover drugs,” “the patient needs allotting of drugs to ensure adherence,” “the patient does not understand the significance of the meditation,” and “the patient does not understand the dosage regimen” are drug problems in which pharmacists should preferentially intervene and play a role in the Integrated Community Care System.
2 0 0 0 OA 恐怖消去の性差を担う分子機構
- 著者
- 松田 真悟
- 出版者
- 日本生物学的精神医学会
- 雑誌
- 日本生物学的精神医学会誌 (ISSN:21866619)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.57-59, 2018 (Released:2019-07-30)
- 参考文献数
- 16
恐怖記憶と関連のある精神疾患の多くは有病率に性差が認められ,女性のほうが高い。この性差の生物学的背景を解明するために,恐怖記憶を忘れる過程(恐怖消去)に着目した研究が進められている。恐怖関連疾患の一つである外傷後ストレス障害の患者は恐怖消去の安定性が低いことから,恐怖消去の性差を担う分子機構を解明することで恐怖関連疾患の有病率の性差に対する生物学的背景の解明やそれを利用した新規治療法の開発へ発展することが期待される。
2 0 0 0 OA 2C1-2 床材の違いが高齢者の歩行動作に与える影響
- 著者
- 小川 タケル Ping Yeap LOH 村木 里志 猪口 耕成 野口 康成 江島 賢一
- 出版者
- 一般社団法人 日本人間工学会
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.Supplement, pp.2C1-2, 2018-06-02 (Released:2018-07-10)