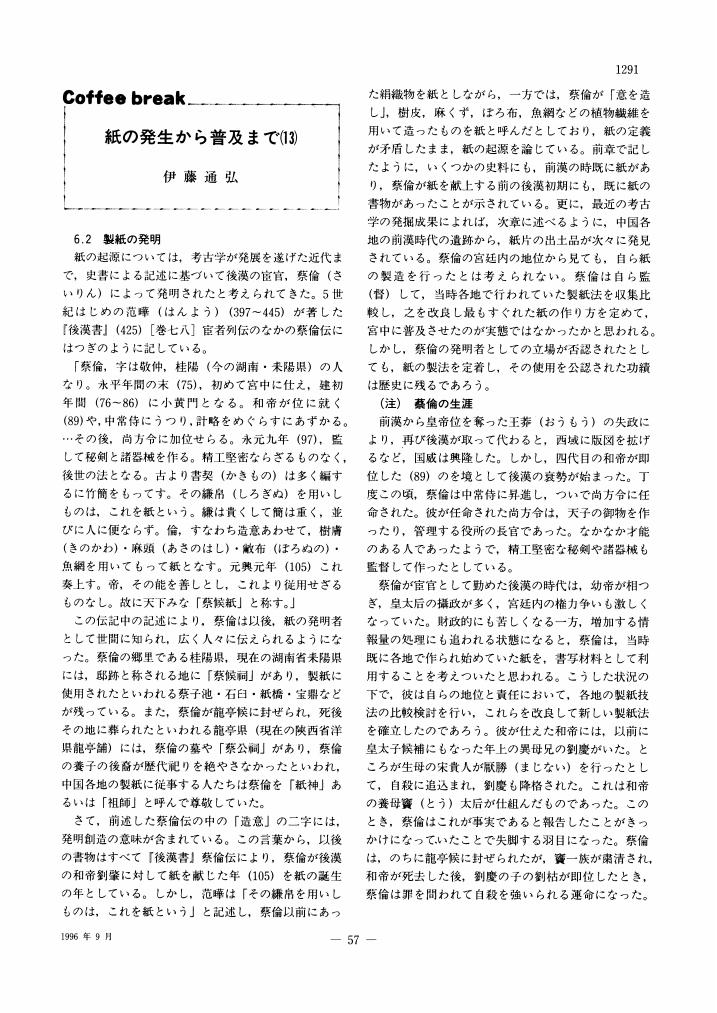1 0 0 0 OA フレッシュコンクリートのレオロジー定数推定に関する基礎的研究
- 著者
- 山田 義智 赤嶺 糸織 伊波 咲子 浦野 真次
- 出版者
- 一般社団法人 セメント協会
- 雑誌
- セメント・コンクリート論文集 (ISSN:09163182)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.661-668, 2013-02-25 (Released:2013-12-02)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1 2
本研究では、ペーストからモルタルさらにコンクリートへと展開する新たな粘度式を提案した。そして、この粘度式を用いて、ペースト、モルタル、コンクリートのレオロジー定数を調合(配合)から推定する手法を示した。ここで、提案手法で求めたペーストとモルタルのレオロジー定数の有効性については、既往の実験結果との関係を比較・検討することで確認した。一方、コンクリートのレオロジー定数の有効性については、提案手法で求めたレオロジー定数を入力値として有限要素法でスランプシミュレーションを行い、実測結果と比較することで確認を行った。
1 0 0 0 OA 張芝草書の実相
- 著者
- 福田 哲之
- 出版者
- 書学書道史学会
- 雑誌
- 書学書道史研究 (ISSN:18832784)
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, no.18, pp.17-30, 2008-09-30 (Released:2010-02-22)
1 0 0 0 OA 日本産鑛物資料(その十七)
- 著者
- 星埜 由尚
- 出版者
- 日本地図学会
- 雑誌
- 地図 (ISSN:00094897)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.2, pp.2_29-2_30, 2009 (Released:2014-11-28)
1 0 0 0 OA ダイズ突然変異体リソースの開発とその活用
- 著者
- 穴井 豊昭
- 出版者
- 近畿作物・育種研究会
- 雑誌
- 作物研究 (ISSN:1882885X)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, pp.67-72, 2016 (Released:2016-12-26)
- 参考文献数
- 16
ダイズ[Glycine max (L.) Merr.]は,種子乾燥重量の約40%のタンパク質と約20%の脂質を含み,食料および飼料用として重要なマメ科作物の一つである.また,近年の健康食志向の高まりを受け,種々の機能性成分についても注目が集まっており,機能性を強化した品種の開発に対する期待も大きい.加えて,2010年には全ゲノム塩基配列が決定されており,その塩基配列から予測された約5万4千個の遺伝子については,既にデータベース上に公開されているが,これらの大部分についての機能は明らかにされておらず,効率的な遺伝子機能解析ツールの開発が待たれていた.本稿では,我々がこれまでに開発してきたダイズ突然変異体リソースの特徴と新規育種素材として期待される突然変異体の単離技術について紹介する.
1 0 0 0 OA Coffee break紙の発生から普及まで (13)
- 著者
- 伊藤 通弘
- 出版者
- 紙パルプ技術協会
- 雑誌
- 紙パ技協誌 (ISSN:0022815X)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.9, pp.1291-1291, 1996-09-01 (Released:2009-11-16)
1 0 0 0 OA タンザニア連合共和国滞在中に感染したスナノミ症の1例
- 著者
- 山本 紗規子 吉田 哲也 齊藤 優子 佐々木 優 矢野 優美子 小林 正規 佐藤 友隆
- 出版者
- 日本臨床皮膚科医会
- 雑誌
- 日本臨床皮膚科医会雑誌 (ISSN:13497758)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.193-197, 2015 (Released:2015-08-27)
- 参考文献数
- 11
スナノミ症はTunga penetransと呼ばれるスナノミが感染して生じる寄生虫性皮膚疾患である.スナノミはアフリカ,南米,西インド諸島を含む熱帯,亜熱帯の乾燥した砂地に生息する.雌の成虫が宿主の皮膚に侵入し“ネオゾーム”と呼ばれる腫大した構造を呈し,これがスナノミ症を引き起こす.スナノミ症の好発部位は足の爪周囲や趾間であり,症状は刺激感や瘙痒,疼痛を生じることが多い.治療はノミの除去である.スナノミ症は細菌による二次感染をおこすため,感染に対しては抗生剤の投与を行う.スナノミ症は通常,蔓延地域への渡航歴や,特徴的な臨床所見,病変から虫体や虫卵を確認することで診断できる. KOH直接鏡検法を用いて虫体や虫卵を確認し診断に至ったスナノミ症の1例を報告する.患者は67歳男,タンザニア連合共和国に仕事で滞在中,左足第�趾爪囲の色調の変化に気がつき急遽日本に帰国し当科を初診した.初診時,左足第�趾の爪は一部爪床から浮いており爪周囲は暗紫色調を呈し浮腫状であった.趾先部の中心に黒点を伴う角化を伴った黄白色の結節を認め,スナノミ症を疑い変色部位を爪とともに一塊に切除した.自験例では皮膚の変性,壊死が強く臨床的には虫の存在は明らかではなかったが,KOH直接鏡検法を用いたところ虫体の一部と多数の虫卵を認めることができスナノミ症と診断した.病理組織でも虫体構造物を確認した.感染部位を摘出後,軟膏による潰瘍治療と抗生剤の内服で軽快,治癒した. 病変部位から虫がはっきりと見えない場合,KOH直接鏡検法はスナノミ症の診断に有用である.
- 著者
- Yasuhiro TAKASHIMA Isako ONODA Shin-Pin CHIOU Katsuya KITOH
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医学会
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.16-0461, (Released:2016-12-30)
- 被引用文献数
- 2
Platelet function hyper-activity has been reported in Dirofilaria immitis (heartworm, HW)-infected dogs. Although the mechanism of increased platelet hyper-activity has not yet been elucidated, it is suggested to be mediated by unknown factors, which may be related to adult HW components. This study aims to determine whether adult male HW whole body extract induces canine platelet aggregation in vitro. The results indicate that HW extract caused an aggregation of canine platelets in a concentration-dependent manner. This aggregation ability of the HW extract was not mediated by the adenosine diphosphate receptor. In addition, the mechanisms of aggregation did not require cyclooxygenase-dependent pathways, and the aggregating activity of substances contained in the HW extract was heat stable; therefore, the active substances may be different from collagen. Furthermore, the platelet aggregating activity remained within the molecular weight (MW)≥100,000 fraction obtained by ultrafiltrating the HW extract. In contrast, the MW<100,000 fraction also had a platelet aggregation ability, but the aggregation pattern was reversible and the maximum extent decreased, compared with the MW≥100,000 fraction response. Our experiments have been conducted using a whole body extract from adult HWs to determine with certainty the aggregating activity of HW elements on canine platelets. More studies are necessary to evaluate the effects of the metabolic products released from live adult worms in pulmonary arteries and the symbiont bacterium Wolbachia-derived antigens on canine platelet aggregation.
1 0 0 0 OA 各種動物ニ於ケル肝臟及ビ腎臟ノ排泄機能
- 著者
- 矢野 義雄
- 出版者
- 財団法人 日本消化器病学会
- 雑誌
- 實驗消化器病學 (ISSN:21851166)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.10, pp.1005-1022, 1927-01-10 (Released:2010-03-19)
- 参考文献数
- 20
各種動物ニヨリ其ノ生物學的進化ノ階梯ニ應ジテ各種器官ノ生理的機能ニ差異アルベキハ動カス可ラザル事實ナルガ如キモ此ノ方面ニ關スル生物學的研究ノ領域ハ猶未充分ニ開拓セラレズ。且又從來諸家ノ肝臟乃至腎臟ノ色素排泄機能ニ關スル業績ハ多キモ、各其對象動物ヲ異ニシ、其成績又區々ニシテ甲論乙駁セルモ、動物ノ種類ニ應ジテ其肝臟若クハ腎臟ノ機能ニモ大ナル差異アルベキノ事實ヲ等閑ニ附セルガ爲ニ、獨斷的錯誤ニ陷リ未問題ノ核心ニ觸ル、能ハザルノ憾アリ。茲ニ於テ著者ハ此等ノ問題ヲ徹底的ニ解決スル所アラントシ、各種ノ動物ニ就テ、多數ノ色素ヲ用ヒテ其肝臟並腎臟ノ排泄機能ノ檢索ニ着手シ、先第一着手トシテ冷血動物(蛙)ト温血動物(鶏)ニ於ケル肝臟及腎臟ノ排泄機能ニ就テ比較實驗シ、兩者ノ間ニ於テ其肝臟腎臟ノ排泄機能ニ格段ノ差異優劣アルヲ明ニシ、殊ニ温血動物ニ於ケル肝臟ノ排泄機能ガ冷血動物ノ夫レニ比シテ甚シク旺盛ナルノ事實ヲ確認セリ。(自抄)
1 0 0 0 OA 本覚思想に対する批判論
- 著者
- 田村 芳朗
- 出版者
- JAPANESE ASSOCIATION OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.918-925, 1973-03-31 (Released:2010-03-09)
- 著者
- Haruna SAWAGUCHI Jiale XU Takahiro KAWAI Takashi MINETA Yoshimune NONOMURA
- 出版者
- 公益社団法人 日本セラミックス協会
- 雑誌
- Journal of the Ceramic Society of Japan (ISSN:18820743)
- 巻号頁・発行日
- vol.124, no.6, pp.753-756, 2016-06-01 (Released:2016-06-01)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 4
Apatite-coated silicon wafers are expected to be utilized for novel biosensors or implants. However, the mechanism and optimum conditions for the formation of an apatite layer on silicon wafer surfaces are unclear. Herein, we examined the effect of pretreating silicon wafers with titanium sputtering and weak alkali aqueous solutions before immersing them in a simulated body fluid (SBF). A week after immersion, silicon wafer surfaces coated with thin titanium layers were covered by hemispherical apatite particles that were produced in a heterogeneous nucleation reaction, whereas untreated silicon wafer surfaces were covered by spherical particles that were produced in a homogeneous reaction. Pretreatment of titanium-coated silicon wafers with 0.1 M NaOH aqueous solution assured heterogeneous apatite formation. Both titanium-coated and untreated silicon wafers were fully covered by the apatite layer after soaking in the SBF for 2–3 weeks. These findings show that pretreatment of silicon wafers with titanium sputtering and weak alkali aqueous solution is effective for obtaining apatite-coated silicon wafers.
- 著者
- 徐 嘉楽 野々村 美宗 峯田 貴
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会論文誌E(センサ・マイクロマシン部門誌) (ISSN:13418939)
- 巻号頁・発行日
- vol.136, no.10, pp.432-436, 2016-10-01 (Released:2016-10-01)
- 参考文献数
- 7
In this paper, we fabricated periodic micro-bump array structure on Si substrate to evaluate their tactile sensations. Fine-edged Si micro-bump array structures can be easily fabricated by photolithography and dry etching processes. Sensory evaluation of tactile feeling of roughness and frictional resistance with human finger was conducted with paired comparison method. In addition, friction coefficient between the micro-bump array and an artificial finger model that mimics our fingertip was evaluated. The result of sensory evaluation showed that rough feeling was affected by edges of the micro-bump structures even though the grooves between the micro-bumps were narrow as 20 µm. In contrast, frictional resistance feeling did not depend on the effect of the edges. It was strongly affected by a contact area between the micro-bump structure and finger skin. When the width of the grooves between the bump were 100 µm, finger skin entered and touch the bottom of the grooves, and then, the rough feeling and frictional resistance feeling were increased due to the contact area increment. The rough feeling and frictional resistance feeling have little correlation with the frictional coefficient measured with artificial finger model. It was more easy for human skin to enter the narrow grooves, in particular when the groove width was 100 µm.
1 0 0 0 OA 歯科医師会と連携して行ってきた「口腔がん検診」(総説)
- 著者
- 片倉 朗
- 出版者
- 一般社団法人 日本口腔腫瘍学会
- 雑誌
- 日本口腔腫瘍学会誌 (ISSN:09155988)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.4, pp.197-206, 2016-12-15 (Released:2016-12-29)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
本学では地域の歯科医師会と共同した口腔がん検診事業を1990年から開始し,本年で25年が経過した。現在までに本学の3つの附属病院の口腔外科,歯科・口腔外科ならびに口腔がんセンターが協力して,連携する各地域の環境にあった口腔癌検診事業を継続的に行ってきた。1992年に千葉市歯科医師会と本格的に開始した口腔癌検診事業は2015年9月現在,千葉県,東京都,埼玉県の14の市に広がり,それぞれの地域性に合わせた形式で年1~3回の集団検診を行っている。1992年から2008年までの集団検診において千葉県全域では7,030名の検診を行った。その中で,口腔癌8名,前癌病変60名,検査または治療が必要な口腔粘膜疾患(良性腫瘍,扁平苔癬など)707名が抽出され,口腔癌の発見率は0.11%であった。この発見率は各年の累計でもほぼ同様であった。また,口腔癌検診の普及のために以下のことに取り組んできた。(1)市民への口腔癌の周知活動,(2)地域歯科医師会の会員をはじめとした一般の歯科医師への生涯教育活動,(3)行政への口腔癌の予防,早期発見の重要性の説明,(4)口腔癌スクリーニングのためのインフラの整備ならびに検査機器や検査方法の開発,などである。これらの活動の成果として,4つの市区では行政からの予算の補助によって恒常的に歯科診療所における任意型の検診を実施するに至った。
1 0 0 0 OA ICUにおける家族看護の満足度:看護師と家族に対するアンケート調査から
- 著者
- 下河邊 美香 星 拓男 柏 旦美 上田 昌代 吉田 千賀子 吉良 淳子
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.3, pp.359-363, 2016-05-01 (Released:2016-05-02)
- 参考文献数
- 10
看護師および患者家族にアンケート調査を行い,家族看護に対する看護師の自らの意識と行動の満足度と看護を受ける家族の満足度ならびに実際の面会状況を調査した。看護師24人と58人の家族から回答を得た。家族へのサポートや情報提供に関しては看護師,家族ともに高い満足度であった。面会に関しては,看護師は面会時間や面会者の制限をあまり守れていないと感じているのに対し,家族の満足度は高い結果となった。家族の面会は規定時間よりも長く滞在していた。一方,患者の傍に家族が落ち着ける場所がないと患者家族は感じており,インターホンでの対応までの時間の長さや,1回の面会時間が短すぎるなどの意見も聞かれた。この結果から今後介入策を考え,スタッフに教育的な介入ができるようにしたい。
1 0 0 0 OA 認知動作型トレーニングが発育期の少年の走力に及ぼす影響
1 0 0 0 OA 無機ヒ素のメチル化に関するS-アデノシルメチオニンの効果
- 著者
- 高橋 啓子 山内 博 益子 まり 山村 行夫
- 出版者
- 日本衛生学会
- 雑誌
- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.2, pp.613-618, 1990-06-15 (Released:2009-02-17)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 3 7
We studied the role of S-adenosylmethionine (SAM) as a methyl group donor in the methylation of inorganic arsenic in mammalians.The SAM and S-adenosylhomocysteine (SAH) levels in the livers of untreated hamsters were 74.3±8.2 and 40.0±6.4nmol/g, respectively. The SAM level was 63.9±6.5nmol/g following oral administration of 1.5mg/kg of arsenic trioxide, which was 14% lower than the control level (t-test, p<0.05). This fall of the SAM level in the liver presumably derived from the SAM having acted as a methyl group donor.Oral administration of 1.5mg/kg of arsenic trioxide once only to hamsters pretreated intraperitoneally with 2.0mg/kg of SAM once only gave the following arsenic levels in the liver and urine. The dimethylated arsenic (DMA) levels in the livers of hamsters treated with SAM plus arsenic trioxide were significantly high, that is, 2 times as high as the control value at 6 hours, and 1.5 times as high as the control value at 24 hours after the administration of arsenic trioxide. The urinary DMA excretion rate in the hamsters treated with SAM plus arsenic trioxide during the first 24 hours after the administration was significantly higher, that is, higher by 36%, than the control value. The urinary DMA excretion rate following pretreatment with SAM was not dose-dependent. Pretreatment with methionine failed to exert any significant acceleratory effect on the methylation of arsenic trioxide.The decreasing pattern of the SAM level in the liver following administration of arsenic trioxide and the DMA behavior in the liver and urine following administration of SAM and arsenic trioxide revealed that SAM accelerated the methylation of inorganic arsenic. In other words, it appeared that SAM could be a very potent methyl group donor to inorganic arsenic.
1 0 0 0 OA 石鹸清拭と熱布清拭による気分とストレスの変化
- 著者
- 小池 祥太郎
- 出版者
- 日本看護技術学会
- 雑誌
- 日本看護技術学会誌 (ISSN:13495429)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.126-131, 2014-08-20 (Released:2016-06-06)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
本研究の目的は,熱布清拭と石鹸清拭が気分とストレスに与える影響を明らかにすることである.研究方法は対象者10名に対して熱布清拭と石鹸清拭を行い,日本語版POMS短縮版と唾液アミラーゼ活性にどのような変化があるかを比較した.また,熱布清拭と石鹸清拭の影響を比較するために,両清拭における日本語版POMS短縮版のT得点の変化量を比較した.その結果,熱布清拭前後における日本語版POMS短縮版のT得点はすべての項目において有意な差は認められなかった.一方で,石鹸清拭前後における日本語版POMS短縮版のT得点は「抑うつ-落込み」「混乱」で有意な減少,「活気」で有意な上昇が認められた.熱布清拭と石鹸清拭の日本語版POMS短縮版T得点の変化量の比較は,石鹸清拭が熱布清拭と比較し「活気」に及ぼす影響が有意に高い結果となった.なお,唾液アミラーゼ活性は両清拭とも有意な変化は認められなかった.この結果から,石鹸清拭は熱布清拭と比較し精神的効果が高い援助方法であることが示唆された.
1 0 0 0 OA 動的類似度を用いたワンショット学習則
- 著者
- 出村 公成 安西 祐一郎
- 出版者
- 日本神経回路学会
- 雑誌
- 日本神経回路学会誌 (ISSN:1340766X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.4-10, 1995-03-05 (Released:2010-12-01)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1 1
We have proposed the one-shot learning algorithm called SOLAR (Supervised One-shot Learning Algorithm for Real number inputs) which needs only a single presentation of training examples, and the learning speed is extremely fast. However, the generalization ability is not satisfactory. In this paper, we propose SOLAR 2 which has good generalization ability. To improve the generalization ability, we introduce the concept of Adaptive Similarity for grouping the training examples. Adaptive Similarity adapts the similarity measure on the course of training. The characteristics of SOLAR 2 are as follows: it learns extremely fast, constructs the network automatically, and it has no local minima problem.
1 0 0 0 OA 先人に学ぶ生態教育の重要性
- 著者
- 嶋田 正和
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.669-670, 2016 (Released:2016-12-28)
1 0 0 0 OA 短距離走により症状を呈した両側膝蓋腱内骨化の1例
- 著者
- 坂井 一夫 伊藤 謙三 南 芳樹 鈴木 勝己
- 出版者
- 西日本整形・災害外科学会
- 雑誌
- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.1-3, 1988-10-25 (Released:2010-02-25)
- 参考文献数
- 7
A rare case of intratendinous ossifications of the bilateral patellar tendons was reported. A fourteen-year-old boy, who was a superior short runner, visited our office, complaining of pain in both knees after running. Physical examination revealed hard masses in bilateral patellar tendons and tenderness of those. No other abnormalities were noted. Roentgenograms of both knees showed ossification in the area of the patellar tendon. Of course, those were extra-articular, arthrographically. Differential diagnosis was made from patella biprtita, Osgood-Schlatter disease and others. Conservative therapies consisting of anti-inflamatory drugs, local injection and others were effective, but the symptom arose repeatedly because he trained hard. We are planning to resect the ossifications after the running seasen.