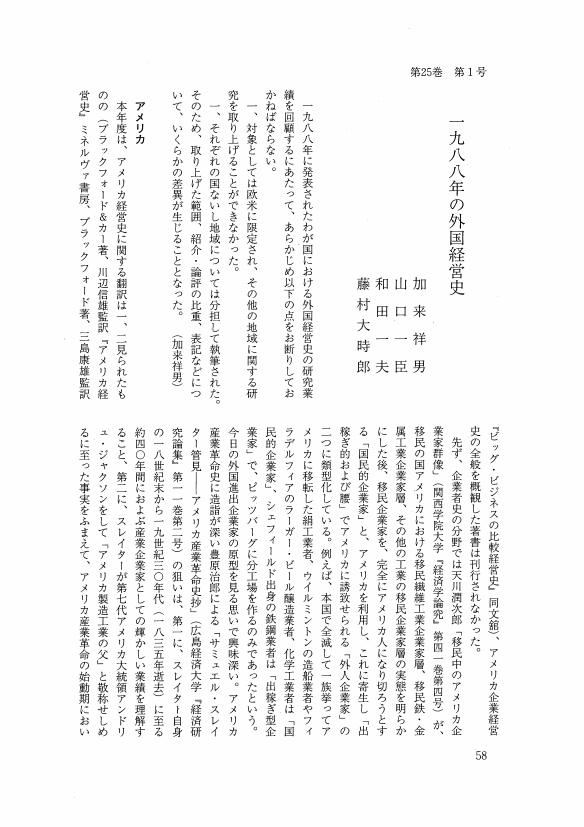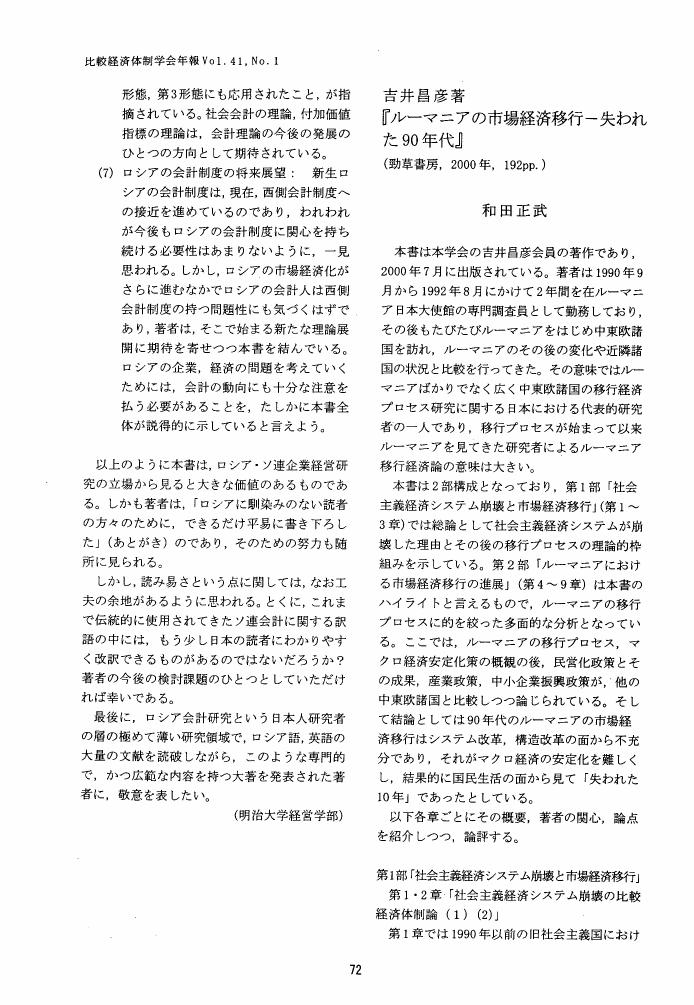- 著者
- 和田 賢治
- 出版者
- 神戸大学大学院国際協力研究科
- 雑誌
- 国際協力論集 (ISSN:09198636)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.109-127, 2012-07
1 0 0 0 OA 近赤外光による脳血流の制御:基礎と臨床
- 著者
- 苗代 弘 和田 孝次郎 魚住 洋一 小林 弘明 竹内 誠 長谷 公洋 川内 聡子 佐藤 俊一
- 出版者
- 一般社団法人 レーザー学会
- 雑誌
- レーザー研究 (ISSN:03870200)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.4, pp.265, 2012 (Released:2020-07-16)
- 参考文献数
- 17
Positive behavioral improvement has been observed following transcranial near-infrared light therapy in humans with chronic traumatic brain injury and acute stroke. We first examined the effect of 808 nm laser diode irradiation on regional cerebral blood flow (rCBF) in mice. An 808 nm CW diode laser was applied to the hemisphere transcranially. Transcranial near-infrared laser irradiation increased rCBF by 30% compared to control value in mice. Near-infrared laser irradiation also provoked a significant increase in cerebral nitric oxide concentration. In the clinical setting, transcranial near-infrared lightemitting diode irradiation to the forehead in a patient with persistent vegetative state following head injury was done. rCBF showed focal increase of 20%, compared to the pre-treatment value. The patient showed some improvement in his neurological condition after light-emitting diode therapy. Transcranial near-infrared irradiation might increase rCBF with some improvement of neurological condition in patients. Further study is warranted.
1 0 0 0 OA 拒食訓練の考察
- 著者
- 山田 大 多和田 悟 益野 健平
- 出版者
- 日本身体障害者補助犬学会
- 雑誌
- 日本補助犬科学研究 (ISSN:18818978)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.31-37, 2009 (Released:2011-02-10)
盲導犬として多く活躍するラブラドール・レトリーバーは、食べる事が好きな犬種である。視覚障害者と生活する盲導犬は、スーパーやレストランなどの食べ物を扱う公共の施設に出入りする機会がある。そのような場所で、盲導犬は人の食べ物に反応してはならない。訓練の段階で、食べ物に反応する犬がどの程度いるか調査をした。その中でも特に食べ物に対する反応が強い犬に対して、拒食訓練を行った。そして拒食訓練終了後にスーパーやレストランを利用して、模擬試験的にその犬の食べ物に対しての反応の変化を検証した。特定の食べ物や状況で勝手に人の食べ物を食べない事を教える事は可能であると考えられた。しかし一度人の食べ物の味を知り、興味を持ってしまった犬に対して、食べ物に全くの興味を持たない事を教える事は難しいと考えられた。盲導犬の候補となる子犬の頃から、人の食べ物に対して反応しない事を教えておく必要性がある事が示唆される。
1 0 0 0 OA 308 反応拡散系による負荷適応骨リモデリングモデル : iBone
- 著者
- 手塚 建一 和田 義孝 高橋 昭如 吉田 隆弘 菊池 正紀
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- バイオエンジニアリング講演会講演論文集 2003.15 (ISSN:24242829)
- 巻号頁・発行日
- pp.73-74, 2003-01-20 (Released:2017-06-19)
- 著者
- 岩野 吉宏 Zhou Yuqing 田仲 正明 和田 敦 吉川 勝治 川本 敦史 野村 壮史
- 出版者
- 公益社団法人 自動車技術会
- 雑誌
- 自動車技術会論文集 (ISSN:02878321)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.51-57, 2021 (Released:2020-12-24)
- 参考文献数
- 8
三次元的に配向を制御した連続繊維複合材料で自動車のフレーム構造の最適設計と試作を実施。最適設計には異方性トポロジー最適化を、試作にはTFP (Tailored Fiber Place) を用いた。従来は基布が平面であったが、これを三次元的構造に拡張し、最適化結果の試作検証を実施。
1 0 0 0 OA 大阪湾・播磨灘および周辺沿岸地域における大気汚染物質の高濃度化要因
- 著者
- 川本 雄大 田内 萌絵 山地 一代 中坪 良平 板野 泰之 山本 勝彦 和田 匡司 林 美鶴
- 出版者
- 公益社団法人 大気環境学会
- 雑誌
- 大気環境学会誌 (ISSN:13414178)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.35-42, 2021-02-07 (Released:2021-02-05)
- 参考文献数
- 13
瀬戸内海周辺地域は全国的に見て相対的に大気汚染物質濃度が高い状態にあり、この原因の一つが、船舶由来の排気ガスとの指摘がある。本研究では、瀬戸内海海上と周辺陸上局にてそれぞれ測定された大気中のSO2、NOx、PM2.5の時空間変動の特徴とその要因を考察した。垂水局と兵庫南部局にてConditional Bivariate Probability Function解析等を行った結果、SO2濃度は海風の進入とともに上昇し、高濃度時には船舶の往来が集中する明石海峡方向からの大気の流入が確認できた。これは、二山型の日内変動を示すNOxとは異なる傾向となった。PM2.5は、春から秋にかけて日中の濃度上昇が確認できたが、SO2やNOxと比較して日内変動幅は小さく、広域的な汚染であることが示唆された。海上のSO2濃度は、最大で陸上局濃度の約5倍となり、他方、NOxは陸上局と同程度あるいは低濃度、PM2.5は陸上局とほぼ同程度であった。大阪湾・播磨灘および周辺沿岸地域において、SO2とNOxの主要な発生源は、それぞれ海上と陸上に存在する可能性が示された。
- 著者
- 栗原 恵美子 和田 早苗
- 出版者
- 日本家庭科教育学会
- 雑誌
- 日本家庭科教育学会大会・例会・セミナー研究発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.61, 2018
<目的><br> 平成29年3月に中学校学習指導要領が告示され、移行期間を経て平成33年度より全面実施される。実践研究してきた余熱保温調理の学習に関して振り返ると、新学習指導要領の基本理念、技術・家庭科の目標の実現、SDGsの実現、に合致する内容が多いことがわかった。<br> そこで平成33年度に向けて、今まで実践してきた内容を更に省察し、余熱保温調理の学習の効果と課題を明確にし、また家庭科教育及び学校教育で、SDGsへの意識を高める余熱保温調理の学習の可能性を提案すること、を目的とした。<br><br><方法><br> 先行研究として、保温調理に関する文献等にあたり、保温調理のメリット・デメリット等を調べた。その後、中学校家庭科調理室で保温実験等実施し、授業への展開を探り、授業実践研究を行った。<br> 学習後、生徒へ自主的な取り組みとして課した探究活動レポートを分析し、また振り返りアンケートを実施し、学習の効果等を明らかにした。<br> また実施上の課題解決の方策を検討すべく、協力を得られた教員にインタビュー調査を実施し、余熱保温調理学習の可能性を探った。<br><br><結果・考察><br> 第2次世界大戦中の余熱保温調理に関して記載している文献(沼畑金四郎著・宮崎玲子著等)があり、それらから「…助炭と称して、やかんを覆う綿入れカバー、鍋の保温におがくずや綿を詰めた保温箱…」等、当時限られたエネルギーを大切に使う様子が掴め、また先行研究・著書(香西みどり著『加熱調理のシミュレーション』)より「…沸騰を続けなくても比較的高い温度が保たれれば、温度に応じた反応速度で調理が進んでいく…」等の情報を得ることができ、授業実践研究に活かすことができた。<br> 都内の国立大学附属中学校調理室で諸条件の下実施した、温度降下測定実験(2014年5月)では、約1時間保温後は約98℃から約90℃、約2時間保温後は85℃前後、と充分調理に適する温度が得られることがわかり、授業実践に繋げることができた。<br> 授業では、市販の保温鍋と手作り保温鍋(鍋を新聞紙とフリース布地で包んだもの)の温度降下等の比較実験を実施し、生徒は調理したスープを試食した。「思っていたよりも温度が下がらず、多くの利点があると思った」等、授業後に回収した生徒のワークシートの自由記述から、驚きと楽しく学べた様子や意欲等みとれ、学習の効果が確認できた。<br> 長期休みに生徒が自主的・発展的に取り組んだ余熱保温調理レポート(2014年度実施 n=11)分析からは、保温方法として「発泡スチロールの箱」や「どてら」を利用する等の様々な創意・工夫が見られ、余熱保温調理のレポート発表後のワークシートでは「100年後も同じ空が見ていられるために」といった標語を記す等、持続可能な社会の構築に向けて、生活を工夫し創造しようとする実践的な態度がみとれ、余熱保温調理の学習の効果が確認できた。<br> アンケート調査(2017年3月実施 n=112)では、エネルギーを大切に使う意識は93.8%が高まったと答えている。<br> 一方実践研究をすすめる中、学校によっては、授業内での保温時間の確保や、食中毒の懸念といった余熱保温調理の学習の課題が明確になった。そこで複数校の教員(n=5)にインタビュー調査をし、実施可能な対応策として、休み時間を利用しての計測、総合的な学習の時間を利用、食中毒の直前学習等様々な方策が上がり、実施するために可能性を検討できた。SDGsに直接的・間接的に繋がる、可能性のある余熱保温調理の学習を、継続研究し、家庭科授業から教育の場全体に提案したい。
1 0 0 0 OA 自動車産業における階層的企業間関係の形成 トヨタ自動車の事例
- 著者
- 和田 一夫
- 出版者
- 経営史学会
- 雑誌
- 経営史学 (ISSN:03869113)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.1-27, 1991-07-30 (Released:2009-11-06)
- 被引用文献数
- 1
The production of an automobile requires the assembly of over twenty thousand parts. Automobile manufacturers do not make such a large number of parts within their own firms but purchase, to varying extents, some parts from suppliers. Therefore, the purchasing policies and relationships with their suppliers have considerable effects on the quality and cost of their final products. Japanese automobile manufacturers organise suppliers in a hierarchical order: its first-tier suppliers form a Kyôryoku-kai (Cooperative Association of Suppliers). First-tier suppliers in turn organise second-tier supplier groups. The Japanese automobile manufacturers claim to maintain long-term relationships with their suppliers and tc, cooperate closely. This is often claimed to be the opposite to American automobile manufacturers' approaches to suppliers: they do not organise suppliers in a hierarchical order; and they often purchase parts on a spot-price basis, without developing long-term relationships and close cooperation with suppliers.This paper traces how the existing inter-firm relationships were evolved at Toyota, the largest automobile manufacturer in Japan, and also elucidates what “close cooperation” between an automobile manufacturer and its suppliers means for the suppliers. After presenting the historical evidence. this paper comes to the conclusion that: Toyota's managerial efforts shaped such peculiar inter-firm relations; Toyota developed and refined its own monitoring system over suppliers; confident with its monitoring system, Toyota transferred it to its first-tier suppliers, hoping they in turn could monitor the second-tier supplier group; Toyota and its suppliers cooperated closely. but Toyota always monitors suppliers' performances closely in terms of cost, delivery, quality and other factors; with such a monitoring system, Toyota facilitates competition among suppliers, who compete vigorously against one another to obtain more orders from Toyota and show their superiority over the others.
1 0 0 0 OA 一九八八年の外国経営史
- 著者
- 和田 英敏 加藤 昌一 本村 浩之
- 出版者
- 国立大学法人 鹿児島大学総合研究博物館
- 雑誌
- Ichthy, Natural History of Fishes of Japan
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.1-4, 2020
1 0 0 0 IR 全日本柔道強化選手の意識調査からみる、国士舘大学柔道部の今後の指導方針への一考察
- 著者
- 吉永 慎也 鈴木 桂治 田中 力 佐藤 雄哉 横沢 翔平 古田 仁志 和田 貴広 田中 力 鈴木 桂治 亀山 歩
- 出版者
- 国士舘大学体育学部附属体育研究所
- 雑誌
- 国士舘大学体育研究所報 = The annual reports of health, physical education and sport science (ISSN:03892247)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.83-89, 2019
プロジェクト研究課題:アスリートの競技能力と生理学的応答の関係における多角的評価プロジェクト研究の概要:本プロジェクトでは、大学生世代のアスリートを対象として、①各競技種目に求められる運動強度を生理学的指標を用いて定量化すること、②運動負荷試験を実施し各競技及び性に応じたトレーニング強度について検討した。本年度は、夏季、冬季の記録系種目における大学生アスリートの最大及び最大下運動能力を定量化し、各種目の至適トレーニング強度を横断的に比較した。本報では、その成果について報告する。
1 0 0 0 図形の動的な見方の構造について : 比喩的認識の視点から
- 著者
- 岡崎 正和 岩崎 秀樹 影山 和也 和田 信哉
- 出版者
- 日本教科教育学会
- 雑誌
- 日本教科教育学会誌 (ISSN:02880334)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.53-62, 2012
本研究の一連の目的は,算数から数学への移行という視座から,子どもの図形認識が発展し,証明に繋がる端緒を明らかにすることであり,本稿では図形の論理的・関係的性質の理解の前提になると考えられる図形の動的な見方の構造を明らかにすることを目的とした。その為に,我々がこれまでに同定してきた図形の動的な見方を単純な文の組み合わせとして表し,隠喩,換喩,提喩を用いて特徴付け,それらの複合性について分析した。その結果,動的な見方は次の5つに集約されることが分かった:視覚的類似性に基づく図形の変形,図形全体の動きを点の動きで捉える,不変性を意識化する,可逆的な見方,不変性と変数性の同時的意識化。また,これらを比喩的認識の複合性の視点から分析した結果,図形の動的な見方は階層的に整理され得ることが示唆された。
1 0 0 0 OA 吉井昌政著『ルーマニアの市場経済移行―失われた90年代』
- 著者
- 和田 正武
- 出版者
- 比較経済体制学会
- 雑誌
- 比較経済体制学会年報 (ISSN:13484060)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.72-77, 2004-01-31 (Released:2009-07-31)
1 0 0 0 OA 移行経済下における産業構造の変化
- 著者
- 和田 正武
- 出版者
- Japan Association for Comparative Economic Studies
- 雑誌
- 比較経済体制学会年報 (ISSN:13484060)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.39-52,121, 2003-01-01 (Released:2009-07-31)
移行経済下,産業構造は大きく変化する。それは社会主義時代に人為的に作られた産業構造が新しい市場ニーズにみあったものへ変化する過程である。ここではポーランドにおける経済改革の10年の中で,産業構造の変化の実態を見,また事例として繊維産業,鉄鋼産業の内部でその生産構造がどのように変化したかを検討する。次ぎに,その変化をもたらした要因を貿易面,企業の発生面,さらにFDIの実績から分析し,最後に新たに形成された産業構造がポーランドにとって望ましいものであったかどうかの評価を産業構造の高度化の観点から論じる。
1 0 0 0 OA 創刊のことば : たゆとうことなき前進
- 著者
- 和田 隆夫
- 出版者
- 関西法政治研究会
- 雑誌
- 法政治研究 (ISSN:21894124)
- 巻号頁・発行日
- vol.First, pp.1-2, 2015-03-29 (Released:2017-07-06)
1 0 0 0 OA 教育と生死の風景
- 著者
- 和田 修二
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, no.89, pp.42-47, 2004-05-10 (Released:2009-09-04)
1 0 0 0 OA 養生雑感
- 著者
- 和田 修二
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1999, no.79, pp.110-116, 1999-05-10 (Released:2009-09-04)
1 0 0 0 OA 教育哲学雑感
- 著者
- 和田 修二
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1991, no.64, pp.72-73, 1991-11-11 (Released:2009-09-04)