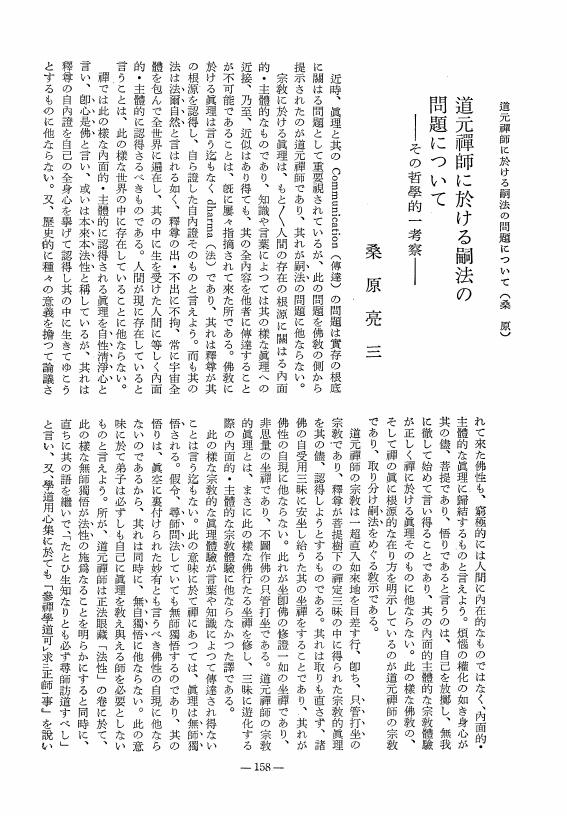1 0 0 0 OA ルーブリックを使用した管理栄養士養成課程における臨地実習の評価
- 著者
- 内堀 佳子 正木 緑 本吉 杏奈 山田 晶世 平澤 マキ 石井 克枝 雀部 沙絵 桑原 節子 Yoshiko Uchibori Midori Masaki Anna Motoyoshi Akiyo Yamada Maki Hirasawa Katsue Ishii Sae Sasabe Setsuko Kuwahara
- 雑誌
- 淑徳大学看護栄養学部紀要 = Journal of the School of Nursing and Nutrition Shukutoku University (ISSN:21876789)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.19-27, 2020-03-16
【目的】管理栄養士養成課程において、学生の臨地実習の事前事後の学修成果について到達度評価に適しているとされるルーブリックを用いて評価し、総合演習を含む事前事後指導の在り方を振り返る。【方法】本校において設定された管理栄養士養成課程におけるルーブリックによる自己評価を臨地実習の事前と事後に実施し学修成果を分析した。【結果及び考察】臨地実習前の評価では、3年生女性では、主体性及びコミュニケーション力を除いた4項目(課題設定・解決力、情報活用力、知識と情報の統合力、職業観)で評価規準3または4と評価した学生が少なく、知識と情報の統合力の評価規準を1と評価した学生が2割いた。3年生男性は、コミュニケーション力の評価は高いが、その他の5項目(主体性、課題設定・解決力、情報活用力、知識と情報の統合力、職業観)の評価が低かった。またコミュニケーション力以外の項目で3年生の女性と同様に評価規準4と評価した割合が低かった。4年生の女性は、知識と情報の統合力の項目を除いた5項目(主体性、コミュニケーション力、課題設定・解決力、情報活用力、職業観)について半数以上の学生が評価規準3または4と評価し3年生女性より評価規準が高かった。男性については、該当人数が4名と少ないが、すべての項目で評価規準2または3と評価し評価規準4と評価した学生はいなかった。臨地実習後の評価については、3年生女性は課題設定・解決力が若干低かったが、それ以外の5項目について評価規準3または4と評価した学生が多くなり、3年生の男性は、主体性及び情報活用力以外の4項目について評価規準3または4と評価した学生が多かった。4年生女性の事後評価では、評価基準の各項目において評価規準3と評価した割合が高くなり評価規準4と評価した割合が減少した。4年生の男性は主体性及び情報活用力を除いて全員が評価規準3または4と評価した。どの項目も実習後の評価は評価規準3または4に評価した学生が増加し、その割合は6割強以上となり、管理栄養士として備えたい必要な力についておおむね獲得できたこと、本大学の学生は社会における管理栄養士としての資質(知識、技術、態度)についての理解が臨地実習後におおむね獲得できたという評価となり、今回用いた「管理栄養士課程における臨地実習ルーブリック」により臨地実習の教育効果を可視化できたととらえることができた。
1 0 0 0 OA 2.副作用の情報収集
- 著者
- 砂金 信義 桑原 聖
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.6, pp.1163-1167, 2007 (Released:2012-08-02)
- 参考文献数
- 5
医薬品の副作用に関する情報源には医薬品添付文書があり,当該医薬品にとって特に注意を要する「重大な副作用」と「その他の副作用」に区分されて記載されている.薬剤性肺疾患を誘発する医薬品は多岐にわたるが,誘発疾患としては肺炎,間質性肺炎が多い.間質性肺炎誘発の恐れがある薬物には,抗悪性腫瘍薬,βラクタム系抗生物質,ニューキノロン系抗菌薬,抗リウマチ薬,抗てんかん薬,抗結核薬などがある.また,OTC薬あるいは健康食品でも発症が報告されており,医薬品,健康食品を用いるにあたっては間質性肺炎発症に留意する必要がある.
1 0 0 0 OA 蒲寿庚の事蹟 : 宋末の提拳市舶西域人
1 0 0 0 OA 蒲寿庚の事蹟 : 唐宋時代に於けるアラブ人の支那通商の概況殊に宋末の提挙市舶西域人
1 0 0 0 OA 慢性腎不全と関連する猫モルビリウイルスの病原性発現機構の解明
- 著者
- 宮沢 孝幸 坂口 翔一 小出 りえ 谷利 爵公 入江 崇 古谷 哲也 水谷 哲也 神道 慶子 野田 岳志 桑原 千恵子 酒井 沙知 浅井 健一 川上 和夫
- 出版者
- 京都大学
- 雑誌
- 挑戦的萌芽研究
- 巻号頁・発行日
- 2016-04-01
これまで猫の腎炎とウイルスの関係に注目した研究はほとんどなかった。しかし、2012年に香港で尿細管間質性腎炎と関連するネコモルビリウイルス(FeMV)が発見された。FeMVはパラミクソウイルス科モルビリウイルス属に分類されるウイルスで、猫の尿や糞便から検出されている。アジア、ヨーロッパ、アメリカの様々な国でFeMVの検出がなされていることから、同ウイルスは世界中に広まっていると考えられている。しかし、その一方でこのウイルスの病原性発現機構は不明である。そこで本研究においては、FeMV感染時の宿主の免疫応答に着目し、FeMV感染とウイルス性腎炎の関係を明らかにすることを目的として研究を行った。
1 0 0 0 OA 往復動形圧縮機の最近の技術動向
- 著者
- 村井 謙介 石毛 秀明 桑原 光由
- 出版者
- 一般社団法人 ターボ機械協会
- 雑誌
- ターボ機械 (ISSN:03858839)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.6, pp.349-355, 1994-06-10 (Released:2011-07-11)
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 地盤沈下
- 著者
- 桑原 徹
- 出版者
- 公益社団法人地盤工学会
- 雑誌
- 土と基礎 (ISSN:00413798)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.93-95, 1978-01-25
1 0 0 0 学力テストと学習権
- 著者
- 桑原 作次
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.90-93, 1962
1 0 0 0 OA 回転する高温熱源による熱対流における渦崩壊 (複雑流体の数理)
- 著者
- 小紫 誠子 河村 哲也 桑原 邦郎
- 出版者
- 京都大学数理解析研究所
- 雑誌
- 数理解析研究所講究録 (ISSN:18802818)
- 巻号頁・発行日
- vol.1081, pp.180-191, 1999-02
1 0 0 0 OA 道元禪師に於ける嗣法の問題について -その哲學的一考察-
- 著者
- 桑原 亮三
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.158-159, 1962-01-25 (Released:2010-03-09)
1 0 0 0 OA 反復性他動ストレッチングのハムストリングス伸張に及ぼす効果
- 著者
- 桑原 拓也 饗場 和美 豊岡 浩介 山路 雄彦 渡辺 秀臣
- 出版者
- 北関東医学会
- 雑誌
- 北関東医学 (ISSN:13432826)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.159-166, 2008-05-01 (Released:2008-06-13)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
【背景・目的】 他動的なスタティック・ストレッチングは運動器の維持・向上に大きな役割を果たしている. 伸張時間と頻度において有効な活用法の確立と温熱療法の相加的効果について検討した. 【対象と方法】 健常大学生22名を対象とし, ストレッチング10秒間を5回施行する群と50秒間を1回施行する群に分け, これに温熱療法を併用しストレッチング前と直後, 10分後の3回, 下肢伸展挙上 (straight-leg raising, SLR) 角度と手掌にかかった圧を測定し伸張強度を求めた. 【結 果】 10× 5群ではスタティック・ストレッチングによりSLR有意な角度の改善が認められたが, 50×1群では有意な改善が得られなかった. 温熱の相加的効果は確認されなかった. 10× 5群ではスタティック・ストレッチングにより有意な伸張強度の増加が確認された. SLR角度と伸張強度の変化率には10× 5群のみ有意な相関が確認された. 【結 語】 ストレッチングによるSLR角度の増加は10秒を5回繰り返す方法が有効であり, この短期の改善効果は神経生理学的要因が関与し, 長期持続には組織構造の変化を導くストレッチングの継続が必要と考えられる.
- 著者
- 肥沼 康太 山中 晃徳 渡邊 育夢 桑原 利彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本塑性加工学会
- 雑誌
- 塑性と加工 (ISSN:00381586)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.709, pp.48-55, 2020 (Released:2020-02-25)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1
Deformation of an aluminum alloy sheet is affected by its underlying crystallographic texture and has been widely studied by the crystal plasticity finite element method (CPFEM). The numerical material test based on the CPFEM allows us to quantitatively estimate the stress-strain curve and the Lankford value (r-value), which depend on the texture of aluminum alloy sheets. However, in the use of the numerical material test as a means of optimizing the texture to design aluminum alloys, the CPFEM is computationally expensive. We propose a methodology for rapidly estimating the stress -strain curve and r-value of aluminum alloy sheets using deep learning with a neural network. We train the neural network with synthetic texture and stress-strain curves calculated by the numerical material test. To capture the features of synthetic texture from a {111} pole figure image, the neural network incorporates a convolution neural network. Using the trained neural network, we can estimate the uniaxial stress-strain curve and the in-plane anisotropy of the r-value for various textures that contain Cube and S components. The results indicate that the neural network trained with the results of the numerical material test is a promising methodology for rapidly estimating the deformation of aluminum alloy sheets.
1 0 0 0 仮想学級における雰囲気のパラメータ化生成モデルの構築手法の提案
- 著者
- 福田 匡人 黄 宏軒 桑原 和宏 西田 豊明
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌 D (ISSN:18804535)
- 巻号頁・発行日
- vol.J103-D, no.3, pp.120-130, 2020-03-01
現在の教職課程では様々な学校問題に対応する指導力を養成するカリキュラムが組まれているが,実際の教育現場において指導力を養う機会は少ない.教育現場では実際の現場に近い環境下で訓練を行う環境が求められている.この問題を解決すべく我々は,教員志望者が生徒としてのCGキャラクタ(仮想生徒)とのインタラクションを通して,指導力を養う新たなプラットホームの構築を進めている.実際の授業現場に近い環境を再現するには,複数の仮想生徒が授業に応じて適切な振る舞いを実施し学級の雰囲気を表出することが求められる.一方でCGエージェントが雰囲気を表出可能な群行動の制御手法は未だない.そこで本研究では専門家の協力のもと実験を実施し,パラメータ化された雰囲気の生成モデルの構築手法について提案する.
- 著者
- 桑原 公徳
- 出版者
- 花園大学文学部
- 雑誌
- 花園大学研究紀要 (ISSN:02882620)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.p139-170, 1981-03
1 0 0 0 OA 佐久間周波数変換所
- 著者
- 桑原 進
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.925, pp.1625-1634, 1965-10-01 (Released:2008-11-20)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 OA 〈原著論文〉 項目反応理論によるサッカー選手のスプリントドリルの達成度評価
- 著者
- 桑原 鉄平 見汐 翔太 中山 雅雄 Kuwabara Teppei Mishio Shouta Nakayama Masao
- 出版者
- 筑波大学体育科学系
- 雑誌
- 体育科学系紀要 (ISSN:03867129)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.51-58, 2012-03
1 0 0 0 OA 上肢神経伝導検査で診断する筋萎縮性側索硬化症 : split hand
- 著者
- 桑原 聡
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床神経生理学会
- 雑誌
- 臨床神経生理学 (ISSN:13457101)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.6, pp.504-508, 2015-12-01 (Released:2016-12-30)
- 参考文献数
- 12
3カ月の経過で左手内筋の筋力低下・萎縮を呈した69歳女性例を提示した。臨床的に母指球筋 (APB) と第一背側骨間筋 (FDI) が高度に萎縮し, 小指球筋 (ADM) が保たれていたことから筋萎縮性側索硬化症 (ALS) を疑い, 系統的な針筋電図で広汎な脱神経所見を認めた。ALSではsplit handと呼ばれる特異的な小手筋萎縮のパターンが認められ, 注目されている。APBとFDIが優位に萎縮し, ADMが保たれるために手の外側筋群が萎縮し内側が保たれて萎縮の有無を分割するような線が引ける (split) ことから命名された。いずれの筋肉も同じ髄節 (C8–T1) 支配であり, この解離性筋萎縮は解剖学的には説明できず, ALSに特異的とされている。Split handは神経伝導検査において上記3筋の複合筋活動電位振幅で定量できる。Split handのメカニズムとして皮質運動ニューロンレベルで母指球側筋が優位に障害される中枢説と, 脊髄運動ニューロンにおいて母指球筋支配軸索の興奮性が生理的に高いことによる末梢説が提唱されている。母指球筋は小手球筋と比べてヒトの日常動作において使用頻度が高いために, 代謝要求が高く, 酸化ストレスに暴露されやすい。Split handはALSにほぼ特異的に認められ, 臨床診断における意義は非常に高い。
1 0 0 0 OA 脊髄・脊椎疾患における手の症候学 : 筋萎縮性側索硬化症におけるSplit Hand
- 著者
- 桑原 聡
- 出版者
- 日本脊髄外科学会
- 雑誌
- 脊髄外科 (ISSN:09146024)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.3, pp.248-251, 2011 (Released:2017-05-11)
- 参考文献数
- 13
1 0 0 0 心・身体・社会をつなぐアート/技術
ヒトが生み出す物質文化には、身体機能の拡張を果たす技術と、感性や価値観にうったえてヒトの心を動かす芸術という二つの側面がある。本計画研究では、「アート」として包括されるその両面が身体を介して統合される様相に焦点を当て、日本列島、メソアメリカ、アンデス、オセアニアにおけるアートの生成と変容の特性を比較検討する。アート(技術・芸術)によるヒトの人工化/環境のヒト化という現象を、考古学的・人類学的・心理学的に分析することにより、社会固有のリアリティ(行動の基準となる主観的事実)が形成される歴史的プロセスを解明し、新たな人間観・文化観を提示することを目的とする。