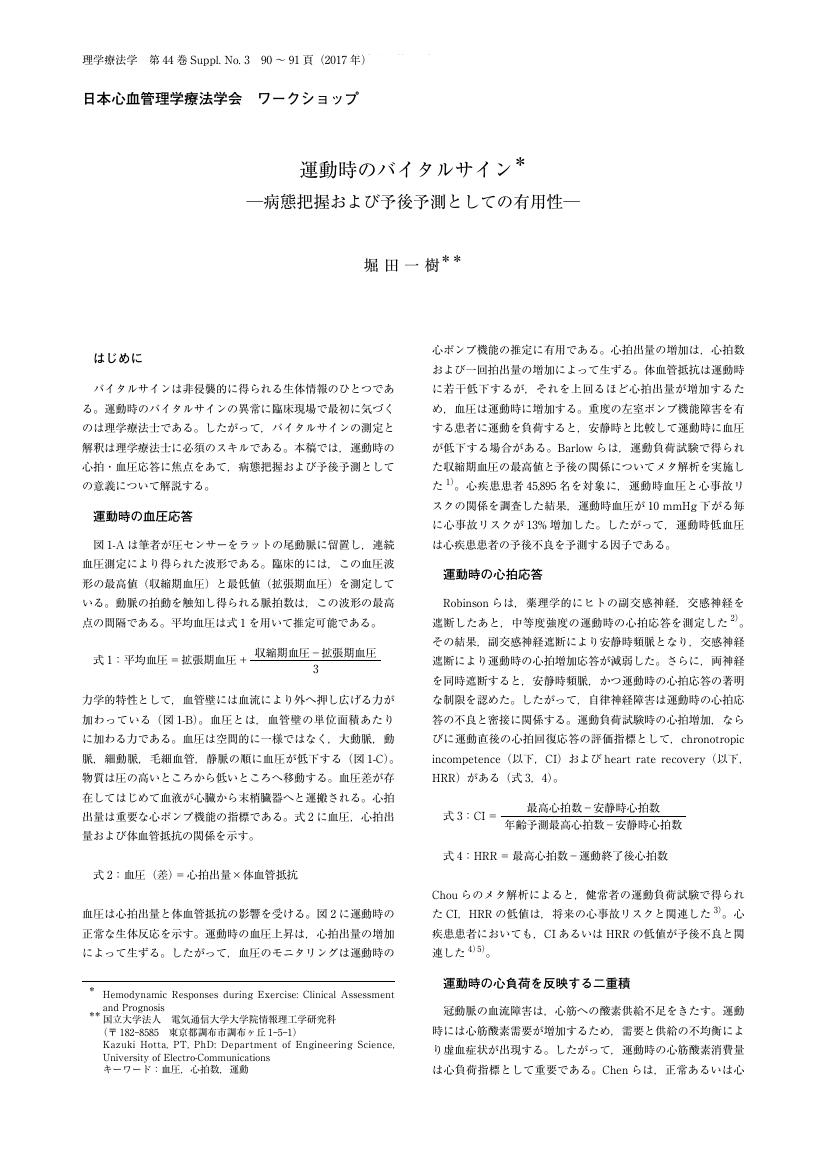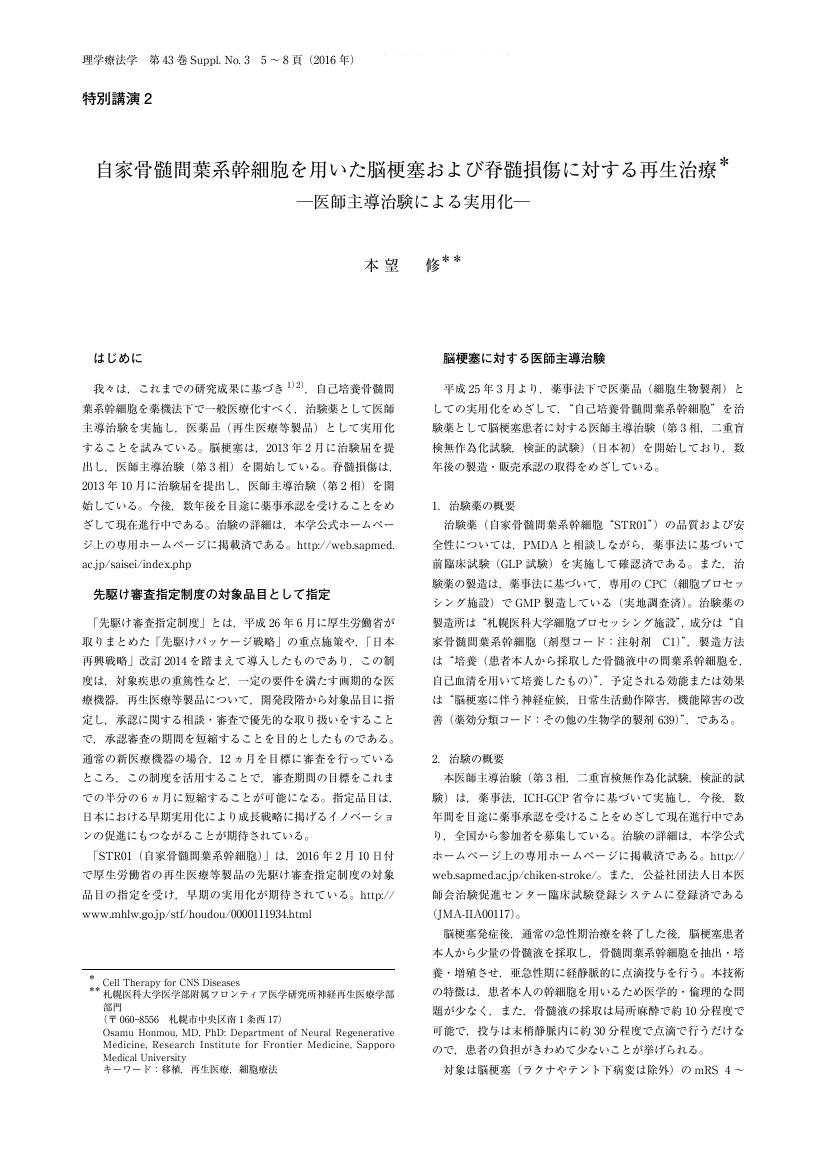2 0 0 0 OA 運動時のバイタルサイン
- 著者
- 堀田 一樹
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.44 Suppl.3(第52回日本理学療法学術大会(千葉))
- 巻号頁・発行日
- pp.90-91, 2017 (Released:2017-10-20)
- 参考文献数
- 6
2 0 0 0 OA 線維筋痛症に対する物理療法の介入効果
- 著者
- 濱上 陽平 本田 祐一郎 片岡 英樹 佐々部 陵 後藤 響 福島 卓矢 大賀 智史 近藤 康隆 佐々木 遼 田中 なつみ 坂本 淳哉 中野 治郎 沖田 実
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.44 Suppl. No.2 (第52回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.0076, 2017 (Released:2017-04-24)
【はじめに,目的】線維筋痛症は全身の激しい痛みと軟部組織のこわばりによって特徴づけられる難治性の慢性疾患であり,本邦における推定患者数は200万人以上といわれている。線維筋痛症に対する理学療法アプローチとしては,運動療法に加えて鎮痛を目的とした各種の物理療法が行われているが,線維筋痛症の原因・病態が明らかにされていないがゆえに,物理療法に効果があるのか否かは未だ議論が続いており,エビデンスも示されていない。そこで今回,これまでに発表された線維筋痛症に対する物理療法の効果を検証したランダム化比較試験(Randomized controlled trial;RCT)を検索し,メタアナリシスを行ったので報告する。【方法】医学文献データベース(Medline,CINAHL Plus,Pedro;1988年~2016年8月に発表されたもの)に収録された学術論文の中から,線維筋痛症に対する物理療法の効果を検証した論文を系統的に検索・抽出した。その中から,ヒトを対象としたもの,研究デザインがRCTであるもの,アウトカムとして痛みの程度(VSA),圧痛箇所数(Tender point),線維筋痛症質問票(Fibromyalgia Impact Questionnaire;FIQ)のいずれかを用いているもの,結果の数値が記載されているもの,適切な対照群が設定されているもの,言語が英語であるものを採用し,固定効果モデルのメタアナリシスにて統合した。なお,有意水準は5%未満とし,採用したRCT論文はPEDroスコアを用いて質の評価を行った。【結果】抽出された227編の論文のうち,採用条件のすべてを満たした論文は11編であり,PEDroスコアは平均5.82ポイントであった。検証された物理療法の内訳は,低出力レーザーが5編で最も多く,全身温熱療法が4編,電気刺激療法が1編,磁気刺激療法が1編であった。次に,メタアナリシスにおいて,物理療法による介入の有無によって痛み(VAS)の変化を比較した結果,低出力レーザー,全身温熱療法,電気刺激療法,磁気刺激療法のすべてで有意差を認め,効果が確認された。同様に,圧痛箇所数およびFIQの変化を比較した結果,低出力レーザーと全身温熱療法で有意差を認め,効果が確認された。なお,採用した論文の中に電気刺激療法,磁気刺激療法の効果を圧痛箇所数およびFIQで検証したものはなかった。【結論】今回の結果,低出力レーザー,全身温熱療法,電気刺激療法,磁気刺激療法のすべてにおいて線維筋痛症の痛みに対する効果が確認された。採用論文は多くはないが,線維筋痛症に対する物理療法の効果をメタアナリシスで検証した研究は国内外で他に見あたらず,本研究の結果は物理療法のエビデンスの確立に寄与するものと思われる。ただ,電気刺激療法と磁気刺激療法に関しては採用した論文はそれぞれ1編であったため,エビデンスが示されたとは言い難く,今後さらにRCTの発表と蓄積が求められる。
2 0 0 0 OA ラット膝関節拘縮に対する関節可動域運動が坐骨神経周囲組織に与える影響
- 著者
- 吉田 信也 松崎 太郎 大下 美奈 坂下 茉以 堀 健太郎 森 和浩 細 正博
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.41 Suppl. No.2 (第49回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.0775, 2014 (Released:2014-05-09)
【はじめに】関節可動域制限の原因の一つとして神経系の可動性や柔軟性の低下が関与していることが考えられており,我々は先行研究においてラット膝関節拘縮モデルにおける坐骨神経周膜の肥厚および坐骨神経束と神経周膜の密着(神経周囲腔の消失)を報告し,これが神経の滑走を妨げている可能性を示した。また膝関節不動化期間中に拘縮予防目的に関節可動域運動(以下,ROM-ex)を行った結果,神経周膜と神経束の間に神経周囲腔が観察され,神経の滑走が神経周膜と神経束との間で生じている可能性を報告した。そこで今回,ラット膝関節拘縮モデルに拘縮治療目的でROM-exを施行し,それが坐骨神経周囲組織に与える影響について病理組織学的に検討することを目的に実験を行った。【方法】対象には9週齢のWistar系雄ラット28匹を用い,それを無作為にコントロール群(n=7),拘縮群(n=14),実験群(n=7)の3群に分けた。拘縮群および実験群は麻酔後,右膝関節をキルシュナー鋼線と長ねじを使用した創外固定を用いて膝関節屈曲120°にて不動化した。この際,股関節,足関節に影響が及ばないように留意し,ラットはケージ内を自由に移動でき,水,餌は自由に摂取可能とした。コントロール群は自由飼育とした。実験群は不動化処置の2週間後より腹腔内にペントバルビタールナトリウム溶液(40mg/kg)を注射して深麻酔下で膝関節に対しROM-exを2週間行い,ROM-ex時以外の期間は不動化を維持した。ROM-exはラットの体幹を固定した状態で行い,まず膝関節屈曲位を5秒間保持し,次にバネばかりを使用して右後肢を坐骨神経に伸張ストレスが加わるように体幹より120°腹頭側方向へ約1Nで牽引し5秒間保持する運動を3分間繰り返した。ROM-exは1日1回,週6回,2週間施行した。拘縮群の半数(n=7)は不動化2週間後にジエチルエーテルにて安楽死させ,可及的速やかに右後肢を股関節より離断し標本を採取した。実験期間終了後,同様に残りのラットを安楽死させ,右後肢を標本として採取した。採取した右後肢は10%中性緩衝ホルマリン溶液にて組織固定を行い,次いで脱灰液を用いて脱灰を4℃にて72時間行った。その後,大腿骨の中間部にて大腿骨に垂直に切断し大腿部断面標本を採取した。5%硫酸ナトリウム溶液で72時間の中和後,パラフィン包埋して組織標本を作製した。作製したパラフィンブロックをミクロトームにて約3μmにて薄切した。薄切した組織切片はスライドガラスに貼付し,乾燥後にヘマトキシリン・エオジン染色を行い封入した。観察部位は大腿中央部の坐骨神経周囲組織とし,光学顕微鏡下に病理組織学的に観察した。【倫理的配慮】本実験は所属機関の動物実験委員会の承認を受けて行われたものである。【結果】コントロール群は全例で坐骨神経束は神経周膜と遊離しており,神経周囲腔が観察された。実験群においては7例中6例で神経周囲腔を認めた。一方,拘縮群では全例で坐骨神経内の各神経束は神経周膜と密着しており,神経周囲腔の消失が観察された。また拘縮群および実験群では神経周膜の線維性肥厚が全例で観察された。【考察】今回,ラット膝関節拘縮に対してROM-exを行った結果,坐骨神経の神経束と神経周膜の間に神経周囲腔が観察された。これは神経の滑走が神経周膜と神経束との間で生じている可能性を示唆するものであると考えられる。また,一度拘縮を生じた膝関節にROM-exを行うことで,坐骨神経の神経周囲腔に関しては可逆的な組織学的変化が生じ,コントロール群に類似した組織像が観察されたと考えられる。一方で,神経周膜の線維性肥厚は拘縮群と同様に実験群全例で観察されており,ROM-exは神経周膜には影響を及ぼさないものと思われた。【理学療法学研究としての意義】臨床場面において使用頻度の高い治療手段であると思われるROM-exが坐骨神経周囲組織に与える影響について病理組織学的に観察・検討することにより,神経滑走性に対するROM-exの治療効果やその運動方法などの妥当性に対して示唆を与えうると考えられる。
2 0 0 0 群馬県高校野球メディカルサポートにおける筋痙攣対応状況
- 著者
- 宇賀 大祐 阿部 洋太 高橋 和宏 浅川 大地 遠藤 康裕 中川 和昌 中澤 理恵 坂本 雅昭
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2014, 2015
【目的】群馬スポーツリハビリテーション研究会では,県内の各高校野球大会にて傷害に対するテーピングや応急処置,試合後のクーリングダウン等のメディカルサポートを実施している。筋痙攣は最も多い対応の一つであり,選手交代を余儀なくされることもある。本研究の目的は,メディカルサポートにおける筋痙攣の対応状況を明らかにし,適切な対応策について検討することである。【方法】対象は過去7年の全国高等学校野球選手権群馬大会とし,メディカルサポートの全対応人数・件数,筋痙攣の対応人数・件数,好発部位,各試合日の1試合当たりの発生件数(発生率),発生時間帯,発生イニング,プレー復帰状況を調査した。また,気候の影響を検討するため,気象庁発表の気象データを元に,気温及び湿度,日照時間と発生率について,ピアソンの積率相関係数を用いて検討した。【結果と考察】全対応数は199名・273件であり,そのうち筋痙攣は75名(37.7%)・146件(53.5%)であった。好発部位は下腿及び大腿後面であった。発生率は大会初期の1,2回戦が平均0.37件/試合と最多で,その後は徐々に減少した。時間帯による発生件数はほぼ同様で,イニングは各試合後半の7,8,9回が多かった。気象データと発生率は,いずれも相関は認められなかった。夏季大会の筋痙攣は熱中症症状の一つとして現れることが多いが,気象データとの関連はなく大会初期に多いことから,大会前の練習内容や体調管理等による体温調節能の調節不足が一要因として大きな影響を及ぼし,そこに疲労が加わることで試合後半に多発するのではないかと考えられる。また,プレー復帰状況は,36.8%の選手が選手交代を余儀なくされており,試合の勝敗に影響を与えかねない結果となった。発生予防が重要な課題であり,大会中の応急処置のみでなく,大会前のコンディショニングや試合前や試合中の水分補給方法等の暑さ対策を中心に指導することが重要と考える。
2 0 0 0 OA 55 大殿筋筋力増強肢位の筋活動について
- 著者
- 鶴見 隆正 松本 規男 上田 哲士
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 臨床理学療法 (ISSN:02870827)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.2, pp.147-148, 1980-12-15 (Released:2018-07-25)
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 複合性局所疼痛症候群TypeIに対して各神経ブロックと理学療法併用した2症例
- 著者
- 大友 篤 遠藤 雅之 小野寺 真哉 坂上 尚穂 伊達 久
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.44 Suppl. No.2 (第52回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.0196, 2017 (Released:2017-04-24)
【はじめに,目的】複合性局所疼痛症候群(以下CRPS)は,アロディニア・痛覚過敏・浮腫・異常発汗・運動障害・萎縮性変化などの症状があり,理学療法の施行を困難なものとする。今回,CRPS TypeIに対して,各神経ブロックと理学療法を併用により,痛みが軽減し,身体機能が改善を呈した2症例を報告する。【方法】症例1:19歳女性,平成X年10月専門学校の体育祭で左膝を捻り受傷。その後痛み継続,他院で精査,治療するも増悪,平成X+1年8月に当院入院。主訴左下肢(左膝関節内側中心)の痛み。安静時痛あり。動作時増悪。左下肢知覚障害,アロディニアあり。左下腿浮腫あり。膝関節制限あり,左下肢荷重不可,両松葉使用していた。症例2:28歳女性,平成X年4月に右前十字靱帯,内側側副靱帯損傷。MRI所見では靭帯損傷は軽度。他院で筋力強化を目的とした理学療法を行ったが,痛みで運動が困難であった。症状悪化したためX年8月当院受診。可動域制限なし,右膝関節内側・膝中央に,安静時・アロディニア・荷重時・膝屈伸時に疼痛出現。大腿四頭筋・ハムストリングス筋力低下あり,独歩可能だが,仕事の継続が困難であった。【結果】症例1:入院初日持続硬膜外ブロック施行及び理学療法開始。理学療法は週2回行い,他の日は自主トレーニングとした。7日目左膝関節可動域改善,左下肢部分荷重。14日目左下肢全荷重可能,歩行時両松葉杖使用。17日目持続硬膜外ブロック終了。24日目安静時痛・運動時痛なし,膝内側の圧痛あり階段昇降時痛みあるが,可動域改善・筋力向上・独歩可能にて退院に至った。症例2:平成X年8月22日~平成X+1年8月5日の約12ヶ月の間に,週に1~2回程度,腰部硬膜外ブロックの前後に理学療法を行った。平成X年8月22日,腰部硬膜外ブロックと理学療法を併用した治療開始。平成X+1年4月には痛みが軽減し,持続歩行が可能となる。同年6月から介護職ではないが,社会福祉士の資格を生かした相談役として職場復帰に至った。【結論】CRPSの運動障害としては,患肢を自分の一部と感じない,患肢を動かす為に視覚的に注意を向けないと運動できないといった認知機能異常や,心理学的要因などの症状もあり,様々な要因が混合しあい,痛みを複雑なものとしている。そのため,身体機能の低下を招き,日常生活の制限をきたす。理学療法を施行する際,痛覚過敏・アロディニアまた,心理的要因が関与し,治療に対して受動的になり,理学療法を困難にしている。各神経ブロック併用により,理学療法を促進するなどの,互いの相乗効果により,痛みの軽減が図れたと考える。また,理学療法を施行する上では,CRPS患者は痛みに対する訴えが強く心理的側面の影響も強いため,理学療法を施行する際は,痛みだけでなくすべての訴えに耳をかたむけていく姿勢が必要になると考える。
2 0 0 0 OA 同種感覚情報の一致が下肢の複合性局所疼痛症候群の改善に有効であった1症例
- 著者
- 村部 義哉 高木 泰宏 上田 将吾 加藤 祐一
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.42 Suppl. No.2 (第50回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.0372, 2015 (Released:2015-04-30)
【はじめに,目的】複合性局所疼痛症候群(CRPS:Complex Regional Pain Syndrome)の発症メカニズムとして,視覚と体性感覚といった異種感覚情報の不一致(sumitani 2009)が報告されている。しかし,下肢は視覚的に制御される機会に乏しいため,主に足底での皮膚感覚や下肢の各関節での深部感覚などの複数の体性感覚といった同種感覚情報により制御されており,これらの不一致が下肢のCRPSを誘発している可能性がある。今回,下肢のCRPSを呈し,異種感覚情報の一致を意図した治療介入では改善が停滞した症例に対して,同種感覚情報の一致を意図した治療介入へと変更したところ,更なる症状の改善を認めたため報告する。【方法】対象は恥骨骨折受傷後,保存療法にて4ヶ月が経過した90代女性。下腿前面から足背部にかけて皮膚の発赤や光沢化を認め,同部位にはアロディニア様症状による接触時痛を認めた。浮腫による足関節の可動域制限を認め,下腿周径は28cmであった。これらの評価結果と本邦のCRPS判定指標から,本症例の症状をCRPSと判断した。痛みの程度はマクギル疼痛質問票(MPQ:McGill Pain Questionnaire)にて44点であった。感覚検査では足底の触圧覚は中等度鈍麻,足関節や足趾の位置・運動覚は重度鈍麻であり,自己身体描写では足部や足趾が不鮮明であった。屋内外の移動はピックアップ型歩行器を用いて近位見守りレベルで可能であったが,実用性は低く,Timed up and go test(TUG)は139秒であり,Functional Independence Measure(FIM)は104点であった。長谷川式簡易知能評価スケールの点数は27点であり,コミュニケーションや指示理解に問題は認めなかった。痛みに対する医療的処置や服薬内容の変更および皮膚疾患や循環器疾患などの合併症の診断は認めなかった。訓練1:患者の足関節を底背屈位,内外反位のいずれかに動かし,患者が感じている足関節の角度と一致する写真を選択させることで,視覚情報から足関節の傾きを識別させた。写真は矢状面にて底屈20°,40°,背屈10°,20°,前額面にて内反15°,30°,外反10°,20°に足関節を傾けたものを使用した。訓練2:患者の足関節を動かし,足底の触圧覚が生じる部位と足関節の位置・運動覚を一定の規則性のもとに一致させることで,足底の触・圧覚から足関節の傾きを識別させた。規則性は①「小指-底屈内反」②「前足部-底屈」③「母指-底屈外反」④「踵外側-背屈内反」⑤「踵部-背屈」⑥「踵内側-背屈外反」とした。各訓練ともに介入頻度は2回/週,20分/回であった。訓練は患者から自身の下肢が見えない環境にて端座位で行った。毎治療開始時にオリエンテーションを実施し,各訓練はランダムに20回行った。訓練1の正答率は介入4週目で25%から100%であり,その後更に4週間同様の訓練を継続したが,症状の改善には至らなかった。その後,治療介入を訓練2へと変更した。訓練2の正答率は介入8週目で25%から95%であった。【結果】下腿前面から足背部にかけての皮膚の発赤や光沢化は消失し,アロディニア様症状の軽減を認めた。浮腫の軽減により下腿周径は24cmへと変化し,関節可動域の向上を認めた。よって,本邦のCRPS判定指標から,本症例のCRPSは改善したものと判断した。痛みの程度はMPQにて2点へと変化した。感覚検査では足底の触圧覚や足関節や足趾の位置・運動覚は正常となり,自己身体描写では足部や足趾が鮮明となった。屋内外の移動はピックアップ型歩行器にて自立レベルとなり,TUGは39秒へと変化し,FIMは117点となった。【考察】今回,視覚と体性感覚といった異種感覚情報の一致を意図した治療介入では十分な改善が得られなかった下肢のCRPSを呈した症例に対して,複数の体性感覚といった同種感覚情報の一致を意図した治療介入に変更したところ,症状の改善を認めた。神経生理学的に,感覚情報処理には階層性があり,異種感覚情報を統合する前段階に同種感覚情報を統合する過程が存在し,同領域(5野:上頭頂小葉)には下肢に関する神経が豊富に存在するとされている(Rizzolatti 1998)。以上より,下肢のCRPSの背景には複数の体性感覚といった同種感覚情報の不一致が存在しており,足底の皮膚感覚と下肢の各関節の深部感覚の一致を意図した治療介入が下肢のCRPSの改善に有効となる可能性がある。【理学療法学研究としての意義】下肢のCRPSに対する治療方法の1モデルの提案。
- 著者
- 濱田 孝喜 貞清 正史 坂 雅之 竹ノ内 洋 伊藤 一也 蒲田 和芳
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2013, 2014
【はじめに,目的】野球では外傷よりも野球肩などスポーツ障害の発生率が高いことが知られている。近年,肩後方タイトネス(PST)に起因する肩関節内旋可動域制限の存在が示され,PSTと投球障害肩発生との関連性が示唆されたが,高校野球においてPSTおよび肩関節可動域制限の予防策の実施状況は報告されていない。また,予防策実施と肩障害発生率との関係性は示されていない。そこで本研究の目的を高校野球において,肩関節可動域制限の予防策の実施状況および予防策実施と肩関節痛の存在率との関連性を解明することとした。【方法】長崎県高等学校野球連盟加盟校全58校へアンケート用紙を配布し,アンケート調査を高校野球指導者と選手に実施した。指導者には練習頻度・時間,投球数に関する指導者の意識調査,選手には肩障害の有無・既往歴,ストレッチ実施状況・種類などを調査した。調査期間は平成25年1月から3月であった。【倫理的配慮,説明と同意】アンケート調査は長崎県高校野球連盟の承諾を得た上で実施された。アンケートに係る全ての個人情報は調査者によって管理された。【結果】1.選手:対象58校中27校,673名から回答を得た。対象者は平均年齢16.5歳,平均身長170.1cm,平均体重66.1kgであった。アンケート実施時に肩痛を有していた者は全体の168/673名(24.9%)であり,肩痛の既往がある者は全体の367/673名(54.5%)と約半数にのぼった。疼痛を有する者のうちストレッチを毎日または時々実施している者は147/167名(88%)であった。疼痛の無い者のうちストレッチを実施している者は422/490名(86%)であった。投手のみでは,肩痛を有する者が22/133名(16.2%),肩痛の既往は82/136名(60.3%)であった。疼痛を有する者のうちストレッチを毎日または時々実施している者は20/22名(90.9%)であった。疼痛の無い者のうちストレッチを実施している者は107/111名(96.4%)であった。2.指導者:58校中24校,33名から回答を得た。練習頻度では,週7日が9/24校(38%),週6日が13/24校(54%),週5日が8%(2校)であった。練習時間(平日)では,4-3時間が14/24校(58%),2時間以下が9/24校(38%),回答なしが1校であった。練習時間(休日)では,9時間以上が2/24校(8%),7-8時間が8/24校(33%),5-6時間が9/24校(38%),4-3時間が5/24校(21%)であった。投球数(練習)では50球以下が3%,51-100球が24%,101-200球が24%,201球以上が0%,制限なしが48%であった。投球数(試合)では50球以下が0%,51-100球が9%,101-200球が42%,201球以上が0%,制限なしが48%であった。3.指導者意識と肩痛:投手の練習時全力投球数を制限している学校は12校,制限ない学校は12校であった。全力投球数制限ありの投手は45名で,肩痛を有する者は8/45名(18%),肩痛が無い者は37/45名(82%)であった。全力投球数制限なしの投手は60名で,肩痛を有する者は11/60名(24%),肩痛が無い者は49/60名(75%)であった。【考察】肩関節痛を有する者は全体の24.9%,投手のみでは16.2%であり,肩痛の既往歴が全体の51.5%であった。ストレッチ実施状況は肩痛の有無に関わらず約80%の選手が実施していた。肩関節可動域制限に対してスリーパーストレッチ,クロスボディーストレッチによる肩関節可動域改善効果が報告されている。本研究ではストレッチ実施の有無を調査しているためストレッチ実施方法の正確性は明らかではないが,ストレッチのみでは投球障害肩予防への貢献度は低いことが考えられる。障害予防意識に関して練習時・試合時共に制限をしていない指導者が48%であった。高校生の全力投球数は1日100球以内と提言されているが,部員が少数である高校などの存在は考慮せざるを得ない。練習時全力投球数を制限している者のうち肩痛を有する者は18%,制限の無い者のうち肩痛を有する者は24%であった。1試合または1シーズンの投球数増加は肩障害リスクを増大させると報告されている。アンケート調査を実施した期間はオフシーズンであり,指導者の投球数に関する意識が選手の肩障害に関与する可能性があると考えられる。以上より,高校野球選手において一定の効果があるとされるストレッチを約8割の選手が実施していたにも関わらず肩痛の存在率は高かった。この原因としてストレッチ方法の正確性及びオーバーユースや投球動作など他因子との関連が考えられる。今後はこれらの関係性を明確にし,障害予防方法の確立が重要課題である。【理学療法学研究としての意義】スポーツ現場において障害予防は重要課題である。これまで障害予防方法の検証はされてきたが,現場ではその方法が浸透していないことが示唆された。医学的知識や動作指導が可能な理学療法士の活躍がスポーツ現場での障害予防に必要である。
2 0 0 0 ストレッチポールエクササイズが胸椎可動性に与える影響
- 著者
- 石川 大輔 仲澤 一也 鴇田 拓也
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, pp.48101186, 2013
【目的】 脊柱アライメントの変化は、整形的疾患や内科的疾患、また心理面に影響を及ぼし、日常生活動作や生活の質の低下に関与すると報告されている。特に胸椎後彎角の変化は脊柱や骨盤の障害に大きな影響を及ぼすと考える。 脊柱アライメントの改善を目的に用いるツールの1つとして、ストレッチポールがある。 ストレッチポールエクササイズ(以下SPex)が与える影響として先行研究では、杉野らによる脊柱リアライメント効果(2006)、秋山らによる胸郭機能改善(2007)などの報告が散見される。 また、胸椎に関しては、蒲田らがSPex前後において胸郭のスティフネス低下、胸椎伸展へのリアライメントなどの効果があると報告している。 しかし、SPex前後での胸椎可動性の変化について調査した研究は少ない。 そこで、本研究の目的は、SPex前後で胸椎後彎角に与える影響として中間位・屈曲位・伸展位の3つの肢位で調査することである。【方法】 対象は健常成人、10名(男性10名 平均年齢33.5±7歳)とした。本研究ではSPex前後に安静立位姿勢から中間位・屈曲位・伸展位の順で胸椎後彎角を計測した。 安静立位姿勢の規定は、我々の先行研究に準じ、矢状面から観察し耳孔と大転子が同一垂線上になるようにし、足幅は肩幅とし、両手は胸骨部を両手が重なるように触る肢位とした。 胸椎可動性の計測は、自在曲線定規を使用し、予めC7とTh12をランドマークしてから、自在曲線定規を胸椎カーブに当て計測をおこなった。 自在曲線定規のデータは、方眼紙上にC7棘突起とTh12棘突起の位置に印をして胸椎カーブをトレースし、肢位ごとにトレースをおこなった。 胸椎後彎角度については、トレースした用紙から長さと高さを算出し、Milneらの計算方法に準じて後彎角θを求めた。また、屈曲位と伸展位の差をトータルアークとした。 ストレッチポールの課題には、日本コアコンディショニング協会が推奨しているベーシックセブンを使用し、10分程度実施した。 統計処理として、SPex前後で中間位・屈曲位・伸展位の胸椎可動性及びトータルアークをt検定で比較した。有意水準は5%未満とした。【説明と同意】 本研究への参加についてヘルシキン宣言に基づき、説明書および同意書を作成し、研究の目的、進行および結果の取り扱いなど十分な説明を行った後、研究参加の意思確認を行った上で同意書へ署名を得た。【結果】 SPex前後で胸椎後彎角は中間位で35.4度から28.1度、屈曲位で50.3度から44.8度、伸展位で26.8度から21.8度と有意に減少した。(p<0.05) トータルアークは、23.7度から22.9度と有意な変化は見られなかった。(p=0.8)【考察】 本研究の結果より、SPex前後で中間位、屈曲位、伸展位の胸椎可動性を有意に減少させた。 この結果は、SPexで胸郭可動性を改善させ、肋椎関節や肋横突関節のモビライゼーション、胸筋群のリラクゼーション効果により胸椎可動性が変化したと考える。また、各肢位において胸椎可動性が減少したにも関わらず、トータルアークが有意な変化が見られなかったことは、立位姿勢において、胸椎アライメントが伸展方向へのシフトしたことも示唆される。 さらに成書にSPexが身体に及ぼす影響として、胸椎伸展へのリアライメントや胸椎のモビライゼーションなどの効果があることを示唆しており、我々の研究結果からも同様な結果であることが証明できた。 今後の課題として、SPexの即時効果だけではなく長期的効果の研究や高齢者や脊柱疾患を有する者などの変化についても行なっていきたいと考える。【理学療法学研究としての意義】 今回の研究でSPexは胸椎可動性の後彎角および可動性に影響を与えることが示唆された。このことは、胸椎後彎が強いことにより障害や伸展可動域の不足などにSPexを適用することで、臨床上有益な効果が期待できると考える。
2 0 0 0 OA ハイヒール靴に対するインソールの有効性
- 著者
- 今 美香 苫米地 真理子 三浦 雅史
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.35 Suppl. No.2 (第43回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.C1440, 2008 (Released:2008-05-13)
【目的】ハイヒール靴は外反母趾の原因の1つとされ、広く知られている。この原因の一つとしては、ヒール高のために足部が前方へ滑り、足尖部が靴とぶつかり、母趾が外反することが挙げられる。そこで今回、ハイヒール靴に対し、足部が前方へ滑らないようにするインソールを作成し、その有効性として足底圧、アンケート調査により検討したので報告する。【方法】対象は外反母趾などの足部疾患の既往がなく、足趾の変形や疼痛がない女子大学生10名とした。対象にはインフォームドコンセントを行い、同意を得た。使用したインソールは一般に市販されているポリエステル素材で、厚さ5mmのものを使用した。踵部分を切り取り、足部の前方への滑りを減少させた。また切り取った3cm幅のインソールを中足部に重ねることで厚くした。次に足部の第1中足趾関節(以下、MP関節)部分に5mmのEVAシートを削りインソールに貼った。これは個々のMP関節部にフィットさせるため、両面テープを用いて自由に位置を変えられるようにした。使用したハイヒール靴は6.5cmのヒール高とした。この靴にインソールを挿入していない状態(以下、インソールなし)と挿入した状態(以下、インソールあり)で、対象にそれぞれ5秒間の片脚立位、10歩の歩行を行った。足底圧の測定は富士フィルム社製圧力測定フィルム富士プレスケールを2cm×2cmに切り取り、母趾球部と踵部に貼り付け測定した。圧力の判定は貼り付けたプレスケールに写し出される赤色痕をもとに行った。また測定終了後にa.つま先の疼痛、b.足の甲の圧迫、c.足の甲と靴の間の隙間、d.足の土踏まずの適合性、e.ヒールの安定感、f.母趾MP関節の圧迫感、といったアンケートを行った。統計学的処理は対応のあるt-検定にて2群間の比較を行った。有意水準を5%未満とした。【結果】片脚立位、10歩の歩行共に、母趾球部の足底圧はインソールありで有意(p<0.05)に低値を示し、踵部ではインソールありで有意(p<0.05)に高値を示した。アンケートの結果、インソールありでおおむね好評な結果であった。【考察・まとめ】今回の結果より、インソールを挿入することで踵部に圧がかかり、それに伴い母趾球部への足底圧が減少し、足部が前方へ滑り込まなくなったことが考えられる。よって、母趾に対する内転方向への外力が減少し、外反母趾を引き起こすような外力は軽減できたのではないかと考えている。またアンケート結果からは、MP関節部のEVAシートの厚さやインソールそのものの厚さ等について改良の余地があることが明らかとなったが、おおむね好評な結果を得ることができた。以上より、外反母趾予防という観点から、ハイヒール靴に対するインソール挿入は有効であることが示唆された。
2 0 0 0 転倒経験と生涯スポーツとの関係
- 著者
- 堀 秀昭 藤本 昭 木下 寛隆 久保 憂弥 林 正岳
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, pp.E3P2215, 2009
【目的】高齢者の転倒による骨折は、筋骨格系の廃用症候群を生じさせ、全身の心身機能、生活機能が低下するといわれている.特に要支援、要介護1等の軽度者に、転倒骨折を予防する目的で運動器の機能向上が実施されている.前回学会で、生涯スポーツ別の身体能力を調査し、生涯スポーツ実施の有無で身体機能に有意な違いが見られ、生涯スポーツの実施による介護予防を提唱した.今回、転倒経験と生涯スポーツ、身体機能との関係について調査した.<BR>【方法】対象は、765名(平均年齢73.3±7.3、男性248名、女性517名)で、スポーツ実施高齢者366名(平均年齢69.8歳)とスポーツ非実施高齢者399名(平均年齢76.5歳)とした.スポーツの種類は、エスキーテニス、バウンドテニス、ラージボール卓球、シルバーバレーボール、グランドゴルフ、マレットゴルフ、ゲートボール、太極拳とした.身体機能評価は、片脚立位時間、握力、5m速度とし、同時に転倒経験について調査した.分析は、SPSSVer11にて、ロジスティック回帰分析、変数増加法ステップワイズ(尤度比)により分析した.またROC曲線を用いてカットオフ値を求めた.尚対象者には研究に関する説明を行い同意を得た.<BR>【結果】1、転倒経験とスポーツ実施の関係:転倒経験を従属変数としスポーツ実施、年齢、性別を共変量としてロジスティック解析を行った結果、スポーツ実施が有意な関係を示し(p<0.05)、オッズ比0.654であった.スポーツ実施者は366名中44名(12%)、非実施者は399名中69名(17.3%)に転倒経験があり、χ<SUP>2</SUP>検定で両群に有意に違いが見られた.2、転倒経験とスポーツ種目別の関係:転倒経験を従属変数としスポーツ8種目を共変量としてロジスティック解析を行った結果、太極拳が有意な関係を示し(p<0.05)、オッズ比0.217であった.3.転倒経験と身体機能の関係:5M歩行速度に有意な関係(p<0.05)を示し、オッズ比1.179であり、カットオフ値3.0秒であった.4.スポーツ実施と身体機能の関係:5M歩行速度と握力に有意な関係(p<0.01)を示し、オッズ比0.237、1.163であり、カットオフ値は、3.0秒と25.6Kgであった.<BR>【考察】今回転倒経験と生涯スポーツとの関係について調査し、生涯スポーツを実施している高齢者は、転倒経験が少なく、特に太極拳を行うと転倒の0.217倍となることが分かった.敦らによる太極拳は足関節の柔軟性の改善に有効としており、太極拳の運動要素を実施することでバランス機能が維持されるのではないかと考える.また転倒経験と身体機能の5M歩行と握力に関係が認められ、目標数値として5Mを3秒、握力25.6Kgが示されたことで、今後の介護予防事業につなげていきたい.また今回、転倒経験と年齢の関係が認められず、これはスポーツを実施することで高齢者においても転倒の危険性が軽減することが示された.
- 著者
- 楠 正和 百武 大志 田中 芳征
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.44 Suppl. No.2 (第52回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.1765, 2017 (Released:2017-04-24)
【はじめに】近年リハビリテーションにおけるレセプト減額査定が増加している。平成27年度,福岡県理学療法士会の減点査定調査結果によると,年齢により一律に減額査定されている傾向があり,特に80歳以上が6単位を超える単位数を「過剰」という理由で減額査定されている。また平成28年より,回復期リハビリテーション病棟(以下回復期病棟)では,アウトカム評価を実績指数で表し27未満の場合に,6単位を超える介入が入院料に包括される事となった。そこで本研究は,80歳以上の患者に対する6単位を超える介入が,80歳未満の患者と同等の効果があるのか,アウトカム評価である実績指数を用いて比較検討をおこなった。【方法】対象は当院回復期病棟を2013年4月1日~2014年3月31日までに退棟した351名のうち,算定区分が脳血管疾患のもの113名と運動器疾患のもの160名とした。除外基準は在棟中の死亡患者,回復期病棟対象外患者とした。後方視的に診療録から,年齢,1日あたりの単位数,FIM(入棟・退棟・利得),在棟日数を収集した。また,実績指数と,その計算式の分子に当たる運動項目FIM利得(以下m-FIM利得),分母にあたる算定上限日数比(在棟日数を回復期病棟入院料の算定上限日数で除した値)を患者あたりにて算出した。疾患別の対象を80歳以上と80歳未満の2群にわけ,各項目の比較検討をおこなった。統計解析にはSPSS ver16を使用し,Mann-Whitney U検定とχ2検定にて検討した。有意水準は5%未満とした。【結果】脳血管疾患:80歳以上/80歳未満(対象:50/63名,年齢:85.6/70.9歳(p<0.05),1日あたりの単位数:7.10/7.25単位,入棟FIM:58.1/78.9点(p<0.05),退棟FIM:75.5/104.4点(p<0.05),FIM利得:18.7/25.1点,在棟日数:43.2/49.4日,m-FIM利得:14.4/20.9点(p<0.05),算定上限日数比:0.27/0.31,実績指数:65.4/94.1)運動器疾患:80歳以上/80歳未満(対象:104/56名,年齢:87.4/65.6歳(p<0.05),1日あたりの単位数:6.51/6.85単位(p<0.05),入棟FIM:71.8/96.5点(p<0.05),退棟FIM:89.9/111.6点(p<0.05),FIM利得:18.1/15.2点,在棟日数:34.6/28.5日(p<0.05),m-FIM利得:16.6/13.4点,算定上限日数比:0.38/0.32(p<0.05),実績指数:56.6/54.4)【結論】脳血管疾患と運動器疾患は共に,実績指数に有意差はみられなかったことから,80歳以上の患者であっても,80歳未満の患者と同等の改善効果があることが示唆された。80歳以上の患者は実績指数が27を大きく超えており,平成28年の回復期病棟連絡協議会における全国平均データ(脳血管:FIM利得17.7,在棟日数88.2,運動器:FIM利得17.2,在棟日数56.7)においても,上回る成績であった。これらのことから,80歳以上の患者の6単位を超える介入は過剰ではなく,年齢で一律に減額査定されるべきではないと考える。
- 著者
- 沖 侑大郎 田中 直次郎 沖田 啓子 渡邉 光子 岡本 隆嗣
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, pp.Da0991, 2012
【はじめに、目的】 延髄外側症候群(以下:Wallenberg症候群)とは、1895年にAdolf Wallenbergが発表し広く知られるようになった。球麻痺、小脳失調、交代性解離性感覚障害の所見を呈し、50%以上に嚥下障害を合併するといわれている。今回、Wallenberg症候群で嚥下障害を呈した症例に対し、理学療法学的観点から頸部可動性、舌骨上筋群の機能を中心に評価し、アプローチすることで改善が認められたので報告する。【方法】 本症例は、60歳代男性で、右椎骨動脈閉塞による右延髄外側の梗塞を発症し、左片麻痺、左失調症状、右側温痛覚障害、構音障害、嚥下障害を呈し発症51日目に当院に入院した。独歩でADLは自立しており、意識障害、高次脳機能障害は認めず、嚥下障害が主な問題点であり、藤島の摂食・嚥下能力のグレード7であった。神経学的所見として、Brunnstrom stageは左上下肢ともに6レベル。体幹機能は頸・体幹・骨盤帯運動機能検査で5レベルであり、座位および立位保持は安定。Berg's Balance Scaleで56/56でADL上バランス機能に問題は見られなかった。嚥下障害に対する問題点を頸部可動域低下、舌骨および喉頭挙上不全、舌骨上筋群筋力低下とし、Videofluorography(以下VF)上で軟口蓋および舌骨の挙上不全により十分な嚥下圧が得られないことによる喉頭蓋谷、梨状窩の残留を認めた。今回の評価方法として、藤島による摂食・嚥下能力のグレード(以下Gr.)、頸部伸展および回旋の関節可動域、相対的喉頭位置(以下T-position)、舌骨上筋群筋力評価スケール(以下GSグレード)、VF上で第3頸椎の内側縦長を基準とし、舌骨と喉頭それぞれの最大前方移動距離と最大挙上距離(前方/挙上)を用い、退院までの経過を評価した。問題点に対し、頸部可動域改善に向け、頸部・肩甲帯リラクゼーション後、舌骨上筋群へのマイオフェイシャルリリース、ダイレクトストレッチおよび舌骨モビライゼーションを行った。また、舌骨上筋群を強化して舌骨および喉頭運動を改善させ、食道入口部の開大を目的に、頭部挙上練習30回反復後、頭部挙上位1分間保持3回を1セットで構成されるシャキア法を、1日3セットを週5回で退院までの1ヶ月間継続的に行った。その際、通常のシャキア法では、腹筋群での代償が生じやすいと考え、頭部挙上練習は背臥位でセラピストが頸部を軽度屈曲位になるように後頭部を介助することで頭部の重さをサポートし、患者が顎を引くことに対し、セラピストが抵抗を加えた。頭部挙上保持は、セラピストが両肩関節を床面に向かい抵抗を加えながら行うことで腹筋群の代償の軽減を図りながら舌骨上筋群の筋力強化を図った。【倫理的配慮、説明と同意】 本症例には症例報告をさせて頂く主旨を紙面上にて説明し同意を得た。【結果】 上記の評価項目を用い、退院までの経過を評価した。評価結果(入院時評価→退院時評価)として、(食形態)Gr.7→9、(頸部伸展)50°→60°、(頸部回旋左右)50°→60°、(T-position)0.44→0.416、(GSグレード)1→3、VF上で舌骨・喉頭移動距離(前方/挙上)は、(舌骨)11.7/4.4cm→12.9/14.7cm、(喉頭)22.0/10.4cm→25.9/12.9cmの項目に改善が見られた。【考察】 本症例に対し頸部・舌骨上筋群を中心としたストレッチを行うことで、頸部伸展および回旋可動域、T-positionの改善が認められた。頸部の可動域制限は、舌骨や喉頭を過剰に固定し挙上運動の制限因子となる。頸部ストレッチを行うことで伸張刺激が加わり舌骨・喉頭の挙上運動が働きやすい状況になったと考える。更にGSグレードの改善からも分かるようにシャキア法により喉頭挙上筋である舌骨上筋群の筋力が改善している。つまり、筋の長さ-張力曲線の原理から考え、頸部の伸張性が改善したことにより喉頭挙上に関する筋力が動員されやすい状態となった。さらに舌骨上筋群の筋力が改善したことにより舌骨・喉頭挙上運動が増大した。このことは、VF所見から舌骨前方および挙上移動距離の改善していることから明らかである。以上より今回の症例に対して舌骨上筋群のストレッチ、シャキア法が、嚥下機能改善に対する有用なアプローチ法であること、加えて詳細な評価が有効であることが考えられる。【理学療法学研究としての意義】 今回理学療法の観点からの嚥下障害に対する間接的アプローチを行うことで、改善が見られた。吉田らによると嚥下障害改善群は、頸部伸展・回旋、舌骨上筋群筋力が有意に改善すると報告しており、本症例においても嚥下機能改善に伴い、頸部伸展・回旋、舌骨上筋群筋力、T-positionの改善が見られておりアプローチ方法は有用であったと考える。今回着目した頸部の可動性、舌骨上筋群の筋力を中心に正確な評価指標をもって病態を把握し、嚥下運動に対してのより効果的なアプローチが可能になると考える。
2 0 0 0 OA 歩行における履物の違いが重心の軌跡に及ぼす影響について
- 著者
- 鶴田 猛 富崎 崇 酒向 俊治 太田 清人 田上 裕記 南谷 さつき 杉浦 弘通 江西 浩一郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.37 Suppl. No.2 (第45回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.E4P3193, 2010 (Released:2010-05-25)
【目的】我々は、日常生活における活動場面において、その活動目的や趣味、嗜好に合わせ履物を選択し使用している。仕事で使う安全靴やスポーツ活動で使用する運動靴、外見の美しさを追求するパンプスなど、履物の種類は多種多様である。様々な活動に必要な姿勢変化や動作が安定して行われるためには、足底と床とが十分に接し、足部にて荷重を適切に受け止める必要がある。歩行による、骨・関節、軟部組織など足部の機能変化は、支持基底面や足部支持性に影響を及ぼし、安定した立位や歩行などの能力改善をもたらすものと考える。これまで、履物と歩行との関連に関する研究は多数報告されているが、足部機能等の評価法の一つである「足底圧」との関連を報告した例は少ない。本研究は、歩行時における履物の違いによる重心の軌跡の変化を捉えることにより、履物が足部機能に与える影響を明らかにすることを目的とする。【方法】対象は健康な若年成人女性6名(年齢18~32歳)とし、使用した履物は、一般靴及びパンプス、サイズはすべて23.5cmとした。歩行にはトレッドミルを用い、速度4km/h、勾配3%に設定し、裸足、一般靴、パンプスを着用し、1分間の慣らし歩行の後、30秒間(各靴3回測定)の足圧測定を行った。足圧測定には、足圧分布測定システム・F―スキャン(ニッタ株式会社製)を使用し、裸足、スニーカー、パンプス着用時の重心(圧力中心)の移動軌跡長を比較検証した。実験より得られた足圧分布図において、重心点の開始位置(始点・踵部)及び終了位置(終点・踏み付け部)を算出し、(1)始点(2)終点(3)重心の長さの3項目について、それぞれの全足長に対する割合を求め、裸足、一般靴、パンプスにおけるそれぞれの値を対応のあるt検定にて比較検討した。【説明と同意】被験者には、本研究の趣旨、内容、個人情報保護や潜在するリスクなどを書面にて十分に説明し、同意を得て実験を行った。【結果】始点において、裸足は一般靴及びパンプスとの比較で有意に値が小さく、パンプスは一般靴よりも有意に大きな値が認められた。終点において、裸足はパンプスとの比較で有意に小さな値が、パンプスは一般靴よりも有意に大きな値が認められた。裸足と一般靴との間に有意差は認められなかった。重心の長さにおいて、裸足は一般靴及びパンプスとの比較で有意に大きな値が認められた。一般靴とパンプスとの間に有意差は認められなかった。 始点は、裸足、一般靴、パンプスの順で裸足が最後方(踵部)に最も近く、終点は、一般靴、裸足、パンプスの順でパンプスが最後方(踵部)から最も遠く、重心の長さは、パンプス、一般靴、裸足の順でパンプスが最も短かった。【考察】裸足歩行では、一般靴及びパンプスを着用した歩行に比べて重心の長さが顕著に長く、始点が最も後方に位置していることから、踵部でしっかりと荷重を受けた後、踏み付け部に重心が至るまで、足底全体を使って歩行していることが分かった。また、足圧分布図の重心軌跡を見てみると、重心線の重なりが少なく、履物を着用した歩行の重心軌跡に比べて、足部内外側へのばらつきが大きいことが見られたことから、履物を着用することにより、足関節及び足部関節の運動が制限され、結果的に重心の移動範囲が限定される傾向があることが示唆された。 パンプスを着用した歩行では、始点・終点ともに最も前方に位置していることから、本来、踵部で受けるべき荷重の一部が前足部に分散し、前足部における荷重ストレスが増強していることが推測される。更に、踵離地における荷重が踏み付け部前方もしくは足趾においてなされている傾向があり、蹴り出しに必要な足趾の運動が制限されるなど、足部が正常に機能していない可能性がある。また、重心の軌跡が最も短いことから、足部の限局した部位を使用した歩行であることが示唆された。このような足部の偏った動きが、将来足部病変をもたらす可能性につながると思われる。【理学療法学研究としての意義】我々は、ライフスタイルや職業の違いにより、様々な履物を着用して活動しているが、外反母趾や扁平足、足部の痛みや異常を訴えるケースは非常に多い。歩行時における履物の違いが足部に与える影響を理学療法学的に検証することで、より安全で機能的な履物の開発の一翼を担うことができ、国民の健康増進に寄与できるものと考える。
2 0 0 0 OA 体幹深層筋の活性化は体幹表層筋の活動性を減少させる
- 著者
- 三浦 拓也 山中 正紀 武田 直樹
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.40 Suppl. No.2 (第48回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.48101189, 2013 (Released:2013-06-20)
【はじめに、目的】体幹の安定性は従来,腹直筋や脊柱起立筋群などの体幹表層筋群の同時収縮により提供されると考えられてきた.しかしながら近年,これらの筋群の過剰な同時収縮はまた腰椎にかかる圧迫力を増加させ,腰痛発症のリスクとなり得るということも報告されており,体幹表層筋への依存は腰椎の安定性に対して負の影響をもたらす可能性が示唆されている.対して,腹横筋や腰部多裂筋を含む体幹深層筋群は直接的に,もしくは筋膜を介して間接的に腰椎に付着するため,その活動性を高めることで腰椎安定性を増加させることが可能であると言われている.しかしながら,増加した体幹深層筋群の活動性が表層筋群の活動性にどのような影響を与えるかについて同一研究内で報告したものは見当たらない.本研究の目的は,体幹深層筋群の活性化が表層筋群の活動性に与える影響について筋電図学的に調査することである.【方法】対象は,体幹や下肢に整形外科学的または神経学的既往歴の無い健常者6名(22.4 ± 1.1歳,166.9 ± 2.0 cm,60.5 ± 3.6 kg)とした.筋活動の記録にはワイヤレス表面筋電計(日本光電社製)を周波数1000 Hzで使用し,対象とする筋は右側の三角筋前部線維,腹直筋,外腹斜筋,内腹斜筋-腹横筋,脊柱起立筋,腰部多裂筋とした.実験プロトコルに関して,立位姿勢にて重量物(2,6 kg)を挙上させる課題を異なる条件にて実施した.条件は特に指示を出さずに行う通常挙上と,腹部引きこみ運動(Abdominal drawing-in maneuvers;ADIM)を行った状態での挙上の2つである.各条件において測定は計5回ずつ行い,得られた筋電データはband-pass filter(15-500 Hz)を実施した後にroot-mean-square(RMS)にて整流化した.全課題を終えた後に各筋における5秒間の最大等尺性収縮(MVIC)を取得し,これを用いて筋電データの標準化を行った.重量物挙上のonsetを加速度計にて決定し,その前後200 ms間の筋電データを解析に使用した.統計解析は各課題(2-N;2 kg-通常挙上,2-A;2 kg-ADIM挙上,6-N;6 kg-通常挙上,6-A;6 kg-ADIM挙上)の比較に一元配置分散分析(SPSS Advanced Statistics 17,IBM 社製)を使用し,post-hocにはFisher’s LSDを用いた.有意水準は5%未満とした.【倫理的配慮、説明と同意】本研究の被験者には事前に書面と口頭により研究の目的,実験内容,考えられる危険性,データの取り扱い方法等を説明し,理解と同意を得られた者のみ同意書に署名し,実験に参加した.本研究は本学保健科学研究院の倫理委員会の承認を得て行った.【結果】外腹斜筋は6-A挙上時,6-N挙上と比較して有意に活動量が減少し(p<0.05), 2-N挙上と比較して6-N挙上では有意に活動量が増加した(p<0.05).内腹斜筋-腹横筋では2,6 kgのそれぞれでADIM挙上時,通常挙上と比較して有意に活動量が増加した(p<0.05).脊柱起立筋では6-A挙上時,6-N挙上と比較して有意に活動量が減少し(p<0.05), 2-N挙上と比較して6-N挙上では有意に活動量が増加した(p<0.05).腹直筋および腰部多裂筋においては有意差は認められなかった.【考察】ADIMを行った状態での挙上課題において,外腹斜筋および脊柱起立筋では筋活動量の減少が認められた.このことは重量物挙上による体幹動揺に抗するための体幹表層筋群への努力要求量が減少したことを示唆するかもしれない.この努力要求量の減少は,ADIMにより体幹深層筋群が活性化され,これに伴う体幹安定性の増加がもたらしたものと推察される.実際に内腹斜筋-腹横筋ではADIM挙上時に有意にその活動量が増加している.腹直筋や腰部多裂筋において有意な差が認められなかったことについては,主に体幹伸展モーメントを必要とする本研究の課題特性が影響したものと考えられる.体幹深層筋群の筋活動計測に対してはこれまでワイヤー筋電計などの手法が用いられてきたが,本研究結果はそれら先行研究と同様の結果が得られたため表面筋電においても体幹深層筋群の活動性を捉えることが可能であると示唆された.また,体幹表層筋群の同時収縮は腰椎に対して力学的負荷増加といったリスクを伴う可能性があるため,その活動性を減少させる体幹深層筋群の活性化は腰椎の安定性に対して重要な働きを持つものと考えられる.この体幹深層筋群の活性化による腰椎安定性増加は,将来的な腰痛発症を予防するという観点から臨床家が取り組むべき課題であると思われる.【理学療法学研究としての意義】本研究により,体幹深層筋群の活性化が体幹表層筋群の活動性を減少させることが示唆された.本所見は将来的な腰痛発症を防ぐためにも重要な知見であり,腰痛に対するリハビリテーションの一助となるものと考える.
2 0 0 0 上肢拳上運動における運動速度が肩甲骨周囲筋の活動順序に与える影響
- 著者
- 松村 葵 建内 宏重 永井 宏達 中村 雅俊 大塚 直輝 市橋 則明
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, pp.Aa0153, 2012
【はじめに、目的】 上肢拳上動作時の肩関節の機能的安定性のひとつに肩甲骨上方回旋における僧帽筋上部、下部線維と前鋸筋によるフォースカップル作用がある。これは僧帽筋上部、下部と前鋸筋がそれぞれ適切なタイミングでバランスよく作用することによって、スムーズな上方回旋を発生させて肩甲上腕関節の安定化を図る機能である。これらの筋が異常な順序で活動することによりフォースカップル作用が破綻し、肩甲骨の異常運動と肩関節の不安定性を高めることがこれまでに報告されている。しかし先行研究では主動作筋の筋活動の開始時点を基準として肩甲骨周囲筋の筋活動のタイミングを解析しており、実際の肩甲骨の上方回旋に対して肩甲骨周囲筋がどのようなタイミングで活動するかは明らかとなっていない。日常生活の場面では、さまざまな運動速度での上肢の拳上運動を行っている。先行研究において、拳上運動の肩甲骨運動は速度の影響を受けないと報告されている。しかし、運動速度が肩甲骨周囲筋の活動順序に与える影響については明らかになっておらず、これを明らかにすることは肩関節の運動を理解するうえで重要な情報となりうる。本研究の目的は、上肢拳上動作の運動速度の変化が肩甲骨上方回旋に対する肩甲骨周囲筋の活動順序に与える影響を検討することである。【方法】 対象は健常男性10名(平均年齢22.3±1.0歳)とした。表面筋電図測定装置(Telemyo2400, Noraxon社製)を用いて僧帽筋上部(UT)・中部(MT)・下部(LT)、前鋸筋(SA)、三角筋前部(AD)・三角筋中部(MD)の筋活動を導出した。また6自由度電磁センサー(Liberty, Polhemus社製)を肩峰と胸郭に貼付して三次元的に肩甲骨の運動学的データを測定した。動作課題は座位で両肩関節屈曲と外転を行った。測定側は利き腕側とした。運動速度は4秒で最大拳上し4秒で下制するslowと1秒で拳上し1秒で下制するfastの2条件とし、メトロノームによって規定した。各動作は5回ずつ行い、途中3回の拳上相を解析に用いた。表面筋電図と電磁センサーは同期させてデータ解析を行った。筋電図処理は50msの二乗平均平方根を求め、最大等尺性収縮時の筋活動を100%として正規化した。肩甲骨の上方回旋角度は胸郭に対する肩甲骨セグメントのオイラー角を算出することで求めた。肩甲骨上方回旋の運動開始時期は安静時の平均角度に標準偏差の3倍を加えた角度を連続して100ms以上超える時点とした。同様に筋活動開始時期は安静時平均筋活動に標準偏差の3倍を加えた値を連続して100ms以上超える時点とした。筋活動開始時期は雑音による影響を除外するために、筋電図データを確認しながら決定した。筋活動のタイミングは各筋の筋活動開始時期と肩甲骨上方回旋の運動開始時期の差を求めることで算出し、3回の平均値を解析に用いた。統計処理には各筋の筋活動開始時期と肩甲骨上方回旋の運動開始時期の差を従属変数とし、筋と運動速度を要因とする反復測定2元配置分散分析を用いた。事後検定として各筋についてのslowとfastの2条件をWilcoxon検定によって比較した。有意水準は0.05とした。【倫理的配慮、説明と同意】 対象者には研究の内容を十分に説明し同意を得た。なお本研究は本学倫理委員会の承認を得ている。【結果】 屈曲動作において、slow条件ではAD、UT、SAが肩甲骨上方回旋よりも早く活動を開始していた。一方でfast条件では全ての筋が上方回旋よりも早く活動を開始していた。分散分析の結果、筋と運動速度の間に有意な交互作用が得られ(p<0.01)、事後検定の結果、運動速度が速くなることでMTの筋活動は有意に早く開始していた。外転動作において、slowではMD、UT、MT、SAが肩甲骨上方回旋よりも早く活動を開始していた。一方でfastでは全ての筋が上方回旋よりも早く活動を開始していた。分散分析の結果、筋と運動速度の間に有意な交互作用が得られた(p<0.05)。事後検定の結果、運動速度が速くなることでMTとLTの筋活動が有意に早く開始していた。【考察】 本研究の結果、運動速度を速くすることで屈曲動作においてMTが、また外転動作においてはMTとLTの筋活動のタイミングが早くなることが明らかとなった。また運動速度を速くすると、肩甲骨の上方回旋の開始時期よりもすべての肩甲骨固定筋が早い時期に活動し始めていた。これは運動速度が肩甲骨固定筋の活動順序に影響を及ぼすことを示唆している。拳上動作の運動速度を増加させたことにより、速い上腕骨の運動に対応するためにより肩甲骨の固定性を増大させるような戦略をとることが考えられる。【理学療法学研究としての意義】 本研究の結果、運動速度に応じて肩甲骨固定筋に求められる筋活動が異なることが示唆され、速い速度での拳上動作では、肩甲骨の固定性を高めるために僧帽筋中部・下部の活動のタイミングに注目する必要があると考えられる。
2 0 0 0 OA 重症心身障害児(者)における摂食状況について
- 著者
- 島 栄恵 港 敏則
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.36 Suppl. No.2 (第44回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.B3P3315, 2009 (Released:2009-04-25)
【目的】重症心身障害児(者)の摂食にあたっては、誤嚥による肺炎の併発に注意が必要となる.そして重症になるほど、摂食に対し慎重にならざるをえず、経鼻経管栄養を余儀なくされる.今回、重症心身障害児(者)の摂食状況を調査し、摂食機能についてどのような発達段階にあるのか検討した.【対象】摂食可能な2~22歳(平均9.25歳)の重症心身障害児(者)12名.摂食は全員介助を要す.改訂大島分類では、A1:5名、A2:3名、A3:2名、A4:1名、B1:1名.そのうち、気管切開2名、人工呼吸器の装着はなし.1名は喉頭気管分離術を施行している.食形態は軟食3名、トロミ食9名.摂食機能に関わる原始反射の出現状況と捕食機能における口唇閉鎖の有無を、摂食機能の正常発達と比較検討した.保護者に文章による同意を得て行った.【結果】捕食時に口唇閉鎖がみられたのは軟食を摂取している3名で、咀嚼は歯茎で押しつぶすような動作を1~2回行い、すぐに嚥下動作を行っていた.一方、残りの9名は、捕食時口唇閉鎖せずに、開口したままの状態であった.そして、咀嚼は、スピードや動きに差があるものの、開口したままで下顎の上下運動と舌の前後・上下運動を行なうマンチング(munching)が主にみられていた.また、その9名は口唇閉鎖をせずにサックリング(suckling)での嚥下がみられた.捕食時に口唇閉鎖を行なっていた3名は、軽く口唇閉鎖をしたサッキング(sucking)がみられていた.また、サックリング(suckling)での嚥下を行う7名に量に差はあるものの、舌で多くの食塊を口腔外へ押し出す行為がみられていた.またその中で5名においては誤嚥がみられていた.【考察】捕食時に口唇閉鎖がみられない理由として、生後5~6ヶ月頃消失する探索反射が残存している場合、口唇部にスプーンが接触すると探索反射が誘発され口唇閉鎖に至らないと言われており、そのためと考える.また舌で多くの食塊を口腔外へ押し出す現象も、探索反射や吸啜反射に基づく反射的吸啜が残存している場合、口唇閉鎖ができない状態で舌が前後に動くため大部分が押し出されると言われている.また、口唇閉鎖がみられた3名において、十分な咀嚼は行なわれておらずほぼ丸飲みの状態で、これは食塊が口腔内に入ることにより、6~7ヶ月に消失する咬反射の残存による弱い咀嚼と、丸飲みはマンチングの段階の咀嚼と言われており、その状態であると考える.【まとめ】摂食機能に関わる原始反射の消失は、生後5~6ヶ月に集中しており、離乳期に合わせて消失時期に入る.しかし、今回、評価を行った12名の重症心身障害児(者)の摂食状況には探索反射、吸啜反射に基づく反射的吸啜や咬反射などの原始反射の残存、マンチングの段階の咀嚼機能であることから、12名において乳児嚥下の状態が続いているといえる.
2 0 0 0 OA 自家骨髄間葉系幹細胞を用いた脳梗塞および脊髄損傷に対する再生治療
- 著者
- 本望 修
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.43 Suppl. No.3(第51回日本理学療法学術大会 講演集)
- 巻号頁・発行日
- pp.5-8, 2016 (Released:2016-10-20)
- 参考文献数
- 3
2 0 0 0 趣味活動の実施が高齢者のやる気スコアに与える影響の検討
- 著者
- 田中 彩子 川合 里奈 林 涼子 鈴木 学
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2014, 2015
【はじめに,目的】意欲とは物事を積極的に対処しようとする思考や行動であり,リハビリの遂行に重要で,ADLの自立度に影響するといわれている。意欲を向上させるには,楽しみや交流,目標設定が関係しているといわれている。趣味活動も例外ではなく,実際に導入している施設も多々存在している。先行研究で趣味活動の実施が廃用予防に効果的であったという報告はあるが,趣味活動が意欲向上に効果的であるという報告は極めて少ない。【方法】群馬県内の介護老人保健施設を利用する高齢者41名に,面接形式でアンケートを実施した。趣味に関するアンケートは,趣味の有無,内容,1週間の活動時間とした。そして意欲の程度に関しては「やる気スコア」を使用した。これは,14問の質問項目を3(全くない)~0(大いにある)の4段階判定とし,得点化した。統計処理は,Mann-Whitney検定を用いて,趣味の有無および文化的趣味と運動的趣味による「やる気スコア」得点の差異を検討した。また,趣味の頻度と「やる気スコア」得点との関係についてSpearmanの順位相関分析を用いて検討した。さらに,説明変数を趣味の頻度,目的変数を「やる気スコア」の得点に設定した単回帰分析を実施した。統計ソフトはSPSS20を使用し,有意水準は5%未満とした。【結果】アンケートに回答したのは41名(男性10名,女性31名)で年齢86.0±7.3歳であった。趣味の有無では,ある26名(63.41%),なし15名(36.58%)であった。趣味の内容に関しては,文化的趣味が20名(76.92%),運動的趣味が6名(23.07%)であった。「やる気スコア」は,趣味あり13.35±5.78点,趣味なし21.22±6.36点で前者が有意に高かった(p<0.01)。しかし,文化的趣味と運動的趣味との比較では有意差はみられなかった。また,1週間の趣味活動の合計時間とやる気スコアとの関係はp=0.481(p<0.05)となり,やや強い有意な相関がみられた。因果関係は回帰分析では,R2値は0.061と,このモデルの予測力は十分ではなかった。調整済みR2値は0.036と大きく低下していた。また,モデルの有意性もF(1.37)=2.422(p>0.05)と確立できなかった。標準回帰係数は0.248で,1週間の趣味活動の程度はやる気スコアに負の影響の傾向はあるものの,有意差はみられなかった。【考察】今回の結果から趣味活動が意欲向上に関与していることが示唆された。しかし,趣味の内容は特に関係はみられなかった。そして趣味の頻度は意欲向上に正の影響がみられることから回数の増加はよい効果をもたらすことが示唆された。しかし明らかな因果関係がみられないことから2つの因果関係は確立できず,他の要因が関係していると考えられた。【理学療法学研究としての意義】本研究では趣味活動の有無や程度と意欲向上との関係について検討し,身体機能が低下した高齢者の今後の理学療法に対する意欲や活動性向上の一助にすることを目的とした。
- 著者
- 石元 泰子 池田 勘一 藤川 大輔 小林 裕和 安倍 浩之 冨岡 貞治 寺本 裕之 田川 維之 柴田 知香 大藤 美佳 中島 あつこ
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2002, pp.480, 2003
【はじめに】打撃動作は、投球動作と同様に両下肢から体幹・両上肢へと全身の各関節が連動しながら遂行される。打撃動作のスキル向上を目的とするならば、障害予防だけではなく、打撃動作の運動特性を捉える必要があると考える。そこで今回我々は、2001年度より定期的に実施している高校野球チームに対するメディカルチェックの中から、打撃動作時のバットヘッドスピードと各関節の可動域との関係を検討し若干の知見が得られたので、考察を加えて報告する。【対象】某高校野球部に所属していた高校生32名(右打者30名・左打者2名)を対象とした。【方法】野球部員に対して実施したメディカルチェックの中から関節可動域測定値、三次元動作解析器による打撃動作解析結果を用い、分析した。 関節可動域は、肩関節外・内旋、肘関節屈曲・伸展、前腕回内・回外、SLR、長座位体前屈(以下FFD)、股関節屈曲・伸展・外・内旋、膝関節屈曲・伸展、足関節背屈、体幹回旋・屈曲・伸展を測定した。尚、肩関節外・内旋においては、肩関節基本肢位(以下1st)、90°外転位(以下2nd)、90°屈曲位(以下3rd)にてそれぞれ測定した。 動作解析には、三次元動作解析system(ヘンリージャパン株式会社製)を用いて、打撃動作を分析し、バットのヘッドスピードを算出した。 統計処理は各関節可動域測定値、三次元動作解析器による打撃動作解析の各項目とバットのヘッドスピードとの相関分析を行った。【結果および考察】 バットのヘッドスピードと左肩3rd外旋可動域(r=0.393)、右肩3rd内旋可動域(r=0.487)、左股関節屈曲(r=0.373)・外旋可動域(r=0.554)、右SLR(r=0.423)、左SLR(r=0.334)、右足関節背屈可動域(r=0.295)、両体幹回旋可動域(右回旋r=0.535・左回旋r=0.272)、体幹屈曲可動域(r=0.428)等との間にそれぞれ有意な相関関係が認められた。 以上の結果から、打撃動作のスキルを向上させるためには、打撃動作において運動学的に要求される関節可動域が確保されていること。また、例えば、左股関節外旋可動域は、打撃動作中に運動学的には要求されないが、硬化した内転・内旋筋よりも柔軟性に富んだ内転・内旋筋を確保しておくこと、つまり、測定項目の拮抗筋の柔軟性確保が重要であると推察できる。換言すれば、柔軟性に富んだ筋は、機能を発揮しやすいことを裏付けている。 本学会において更にデータ解析、考察を加え詳細について報告する。