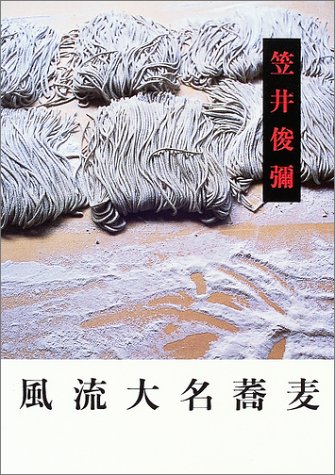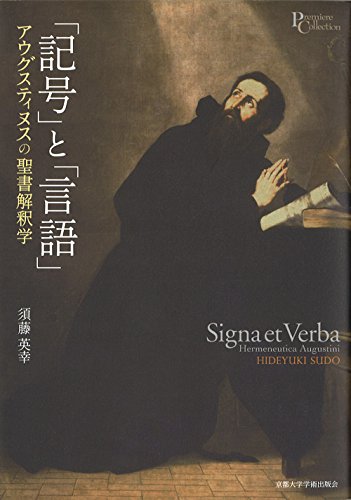1 0 0 0 OA 過酷環境下での遠隔レーザー分析技術
- 著者
- 大場 弘則 若井田 育夫 平等 拓範
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.5, pp.263-267, 2020 (Released:2020-11-01)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 3
福島第一原子力発電所の廃炉においては,世界でも例のない事故炉からの溶融燃料デブリ等の安全かつ円滑な取り出しが求められている。我々は,事故炉内の高放射線,水中等の過酷環境下において,炉内の燃料デブリ性状把握等サーベイランスが可能な遠隔分析を実現するために,レーザー光およびプラズマ発光を耐放射線性光ファイバーで長距離伝送するレーザー誘起ブレークダウン分光(LIBS)法を提案し,技術開発を進めている。本稿では,光ファイバー伝送LIBS技術を利用して様々な環境下や試料を用いて遠隔迅速その場分析を実証した試験結果,および過酷な環境へのセラミックマイクロチップレーザーを利用した遠隔LIBS分析技術の適用可能性について解説する。
1 0 0 0 IR 韓国ソウル市の歩行空間におけるバリアフリー現状と方向性
- 著者
- 柳 尚吾 リュ サンオ Ryu Sano
- 出版者
- 大阪大学未来戦略機構第五部門未来共生イノベーター博士課程プログラム
- 雑誌
- 未来共生学
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.353-366, 2014-03-31
1 0 0 0 リフレクトアレーアンテナの測定による利得低下の要因分析法
- 著者
- 深谷 芽衣 牧野 滋 瀧川 道生 中嶋 宏昌
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌 B (ISSN:13444697)
- 巻号頁・発行日
- vol.J105-B, no.1, pp.14-20, 2022-01-01
本論文では,リフレクトアレーアンテナの測定結果から利得低下の要因分析を可能とする測定法について示す.特徴として,リフレクトアレーアンテナと同じスピルオーバー損失となるようなパラボラアンテナを試作し測定結果を比較することで,損失の切り分けを容易にし,利得低下の要因を分析する.結果としてリフレクトアレーアンテナとパラボラアンテナの測定値の差と,利得低下分析より求めたリフレクトアレーアンテナ固有の損失の差は測定誤差の範囲内であり,利得低下分析は妥当であることがわかった.
1 0 0 0 OA 戦史は書き換えられたか-ベトナム症候群克服の試み-
- 著者
- 松岡 完
- 出版者
- 財団法人 日本国際政治学会
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.2002, no.130, pp.160-174,L15, 2002-05-31 (Released:2010-09-01)
The Vietnam War had hardly ended when intensive efforts to “correct” the war narratives were commenced within the United States. The challenge to the once seemingly established fact that the United States had suffered a humiliating defeat came to its peak in the middle of the 1980s. Revisionists such as the former and incumbent Presidents Richard Nixon and Ronald Reagan aimed to cure the Americans of the Vietnam syndrome, and to help them regain their self-confidence and a sense of national integrity.The withdrawal of American troops, the revisionists insisted, should never be portrayed as a surrender, instead merely as an American unilateral decision to leave Vietnam. The defeated, if any, were the South Vietnamese, not the Americans. The United States was actually a winner there, for it helped the anti-Communist regime in South Vietnam survive for two decades so that other nations in Southeast Asia could develop their economic and political strength. Moreover, American soldiers were always victorious in any encounter with the Communist guerrilla or regular forces.The revisionists believed that the United States could have won at an earlier stage if only it had used its military power in an overwhelming way. The United States was on the verge of triumph by the end of 1972, almost forcing the leaders in Hanoi to accept American terms in peace talks through its massive bombing attacks in central North Vietnam. Then, suddenly, the revisionists argue, the U. S. Congress, intimidated by an unjustified fear of United States inability to win the war, threw in the towel.Political leaders in Washington came under the attack of the revisionists. The United States lost this war for several reasons, namely because the government was unable to offer the American people a definite war objective, placed exceedingly unnecessary restrictions upon the military, failed to demonstrate sufficient will to win, and was unsuccessful in fully mobilizing the public behind the war effort.American mass media, including television, was another target. The correspondents were criticized for being too young and too inexperienced to grasp the reality of battleground and sometimes too naive to shelter themselves from the influence of the Communists' propaganda. Hence, their reporting across the Pacific contributed to serious increases in anti-war sentiment back home, which in turn caused extreme damage to the American war strategy.The majority of the American people were, however, far from being persuaded by such revisionist arguments. They knew that they had never fulfilled their objective of building a strong and viable anti-Communist regime in Vietnam, that they had been responsible for the South Vietnamese deficiencies, that winning in a shooting war had been irrelevant to the political future of the country, that the results of truce negotiations could hardly have been American triumph, and that blaming politicians and reporters merely was a means to protect the military from further criticism. That is why, to the regret of the revisionists, the memory of defeat in Vietnam still haunts the American people.
- 著者
- 山口勝
- 出版者
- みずほコーポレート銀行
- 雑誌
- Mizuho industry focus
- 巻号頁・発行日
- vol.2008(1), no.63, 2008-01-23
- 著者
- 山口 敬之 遠山 文雄 Hawkins Joe 学生ロケットプロジェクトチーム
- 出版者
- 一般社団法人日本機械学会
- 雑誌
- 年次大会講演論文集 : JSME annual meeting
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, no.5, pp.463-464, 2004-09-04
- 被引用文献数
- 2
We have collaborated a student rocket project with the University of Alaska Fairbanks (UAF) since 1995 and two student sounding rockets were launched in 2000 and in 2002. The student rocket is designed and made by students during from the planning to analysis. The third launch will be at Alaska in March 2005. The apogee altitude of rocket is designed to 100 km. Tokai student team has made a UV. sensor, a digital sun sensor and a 3-axial fluxgate magnetometer on this rocket. We have a plan to measure ultraviolet ray in the polar region. By UV measuring, we may estimate the ozone density and total ozone quantity as a scientific mission. We also can measure a rocket attitude performance by a magnetometer and a sun sensor as the second task.
1 0 0 0 IR 核付きトマホーク(TLAM-N)とは何か : 核の傘における日米間の認識のズレとその収束
- 著者
- 田中 慎吾
- 出版者
- 大阪経済法科大学アジア研究所
- 雑誌
- 東アジア研究 (ISSN:13404717)
- 巻号頁・発行日
- no.74, pp.17-28, 2021
1 0 0 0 OA 語の学習における制約 (原理) : どこまで生得でどこまで学習か
- 著者
- 針生 悦子
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.1_99-1_111, 1997-03-01 (Released:2008-10-03)
- 参考文献数
- 43
Pointing to an object and saying a word is an ambiguous form of reference, because there are an indefinite number of logically possible hypotheses about the meaning of a word. But children are very proficient at learning words. That led us to postulate constraints on the hypotheses that children consider about the meanings of words. In fact, the previous studies have shown that children aged two or over are highly biased word learners (Landau et al., 1988; Merriman & Schuster, 1991). Much of the debate has centered on whether this idea of constraints implies innate and fixed word learning principles, and whether these principles are by nature domain-specific. This paper reviewed the studies concerned with this debate. The previous studies showed that those learning principles emerged in the course of early word learning (Jones et al., 1992), and that children's use of them became more domain-specific with age (Smith et al, 1994). These findings suggest that the principles and the domain-specific use of them may be the consequence of word learning, not innate. But following two facts are notable. First, young children rapidly find the principles in the course of learning first 50 words, although it is difficult for children of this age to examine possible hypotheses systematically. Second, some findings (Haryu, 1996; Smith et al., 1996) suggest that the use of principles in early word learning is not accesible to deliberate control. These facts lead me to assume that infants are born, not with some concrete beliefs about word meanings, but with some constrained mechanism that guides infant's learning the principles about word meanings.
1 0 0 0 「記号」と「言語」 : アウグスティヌスの聖書解釈学
- 著者
- 青木 美智男
- 出版者
- 校倉書房
- 雑誌
- 歴史評論 (ISSN:03868907)
- 巻号頁・発行日
- no.530, pp.p67-74, 1994-06
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA セットスクラムにおけるロックの「押し」について : 10.体育方法に関する研究
- 著者
- 藤井 主計 河瀬 雅夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会号 第26回(1975) (ISSN:24330183)
- 巻号頁・発行日
- pp.566, 1975-08-20 (Released:2017-08-25)
- 著者
- 山本 巧 松元 秀雄 日比野 弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会号 第40回(1989) (ISSN:24330183)
- 巻号頁・発行日
- pp.717, 1989-09-10 (Released:2017-08-25)
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経コンストラクション (ISSN:09153470)
- 巻号頁・発行日
- no.624, pp.30-33, 2015-09-28
「午後には雨がやむはずだから、大丈夫だろう」。小雨が降り始めていたにもかかわらず、橋脚のコンクリート打設を決行。その結果、1カ月後のコア抜き検査で強度不足が判明し、造り直すことに──。
1 0 0 0 OA 精神科デイケアにおける定期的な体力テストの効果
1 0 0 0 禿げ山から地域に親しまれる森林に復旧した田上山の治山事業
- 著者
- 河崎 則秋
- 出版者
- 水利科学研究所
- 雑誌
- 水利科学 (ISSN:00394858)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.123-135, 2016
田上山は,滋賀県南部に位置する田上山系と金勝山系の山々の総称であり,一丈野国有林(大津市)と金勝山国有林(栗東市)は,この田上山に属し,水系は淀川流域の上流部になる。(図1,2)田上山は,「うっそうたる大森林」であったと奈良朝時代の古文書により推定されている。しかし,690年代に藤原宮の造営に要する木材の伐出や,740年代には石山院(現在の石山寺)造営に際し木材が伐出したとされ,そういった長期乱伐の結果,桃山時代(1600年頃)には既に荒廃の一歩手前にあり,江戸期(1640年頃)に入ると燃料としての盗掘や戦禍による焼失を重ねた結果,荒廃が進行したうえに,地質が風化の進んだ花崗岩であったことから,降雨のたびに土砂流出が発生して下流の人々を苦しめてきた。荒涼とした山は,その姿から「田上のはげ」として全国に知られることとなった。慶長13年(1608年),17年(1612年),19年(1614年)に淀川流域一帯に大水害が発生し,承応2年(1653年)には,野洲川が決壊し約50町歩の田畑が荒地となった。幕府は万治3年(1660年)に,大和,伊賀,山城の国に対し「木根掘取禁止,禿山に苗木植付,土砂留の施工」を命じている。寛文の時代に入り,2年(1662年)と5年(1665年)には栗太郡も災害を受け,翌6年(1666年)には幕府が「諸国山川の掟」を発令し,草木の根を掘り取ることを停止し,川上の樹木なき所に苗木を植付,焼畑および河辺の開こんを禁止している。9年(1669年)に幕府は主要な役人に畿内の被災状況を実地検分させ,淀川の浚渫費を各大名に課している。翌10年(1670年)には瀬田川の浚渫が施工されている。このように江戸時代は治山治水対策が組織的な事業として行われたが,安永・天明年間(1772年~1788年)の飢饉等で農村が不況に陥って以降,幕府の監督体制もゆるみ,設計・施工技術の低下をはじめ,山腹工事の施工自体が衰退した。当時の主な工種は,山腹工では,鎧留(別添図1),築留(図2),石垣留(図3),石篭留(蛇篭留)(図4),井堰留(図5),掻上堤工(図6),杭柵留(図7),逆松留(図8),蒔わら工(葺わら留)(図9),筋粗朶工(図10),雑木苗植込,筋芝植込(図11),飛芝植込(図12),飛松留(図13),実蒔留など,渓間工では,鎧留,築留,石垣留(図14),砂留(図15,16),流路工などである。江戸時代最後(慶応4年)の淀川大水害に見舞われた明治政府は,淀川の船運確保対策を考え,木津川の付替工事を始めるとともに,土砂留調査に着手し,治水(船運)のためには,山林の整理に併せて砂防(治山)事業の緊急性を痛感した。なお,森林の所有については,明治2年(1869年)に官林制度が定まり,翌3年(1870年)には社寺有林の上地命令がなされており,大津国有林の母体(所有形態)が形成されたと思われる。ただし,管理は県に委託されている。明治4年(1871年)になり,政府は5畿内(山城国・大和国・河内国・和泉国・摂津国の令制5か国)および伊賀国に対し「砂防5カ条」を布達し,木津川水源土砂留工事費を当分官費をもって支払う旨を通告している。翌5年(1872年)には,施行対象地として,大戸川,草津川及び野洲川の水源禿赭地(はげ山)と記録され,工事費は全額国費で賄われた。明治29年(1896年),河川法が制定され,翌30年(1897年)には,森林法及び砂防法が制定され,国有林野事業として治山事業が開始された。
1 0 0 0 OA M.シェーラーの「愛」の思想(その2)
- 著者
- 平野 真弓 Mayumi Hirano
- 雑誌
- 生活学園短期大学紀要 = Bulletin of Seikatsu Gakuen Junior College (ISSN:03879917)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.19-33, 1985-03-25
1 0 0 0 OA 国会審議の非会議録研究の試み:安倍首相の国会発言における変化
- 著者
- 増山 幹高 政策研究大学院大学 / National Graduate Institute for Policy Studies
- 出版者
- GRIPS Policy Research Center
- 雑誌
- GRIPS Discussion Papers
- 巻号頁・発行日
- vol.21-05, 2021-12
国会審議には会議録に含まれない様々な情報がある.本稿では,文字情報に偏ってきた国会審議や立法過程に対する従来のアプローチから脱し,音声や画像,映像を活用する試みとして,まず国会審議について議員の発言内容に対応する審議映像を検索し,該当する審議映像の部分的視聴を可能にする「国会審議映像検索システム」を概説する.その国会発言の音声認識によるテキスト・データと会議録を同期させることで審議映像の時間情報と文字情報を同刻させる利点を生かし,音声認識と会議録との差分分析から両者の相違を「正文率」と捉え,その時系列的な分析から安倍首相の国会発言における変化を解明することを試みる.
- 著者
- 荒木 勉 小西 康久
- 出版者
- 兵庫教育大学
- 雑誌
- 兵庫教育大学研究紀要. 第3分冊, 自然系教育・生活・健康系教育 (ISSN:09116230)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.185-198, 1985-01