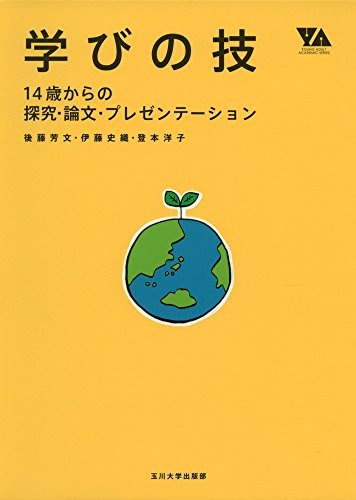2 0 0 0 身体性を考慮した着ぐるみ装着者支援システムの設計と実装
- 著者
- 岡崎 辰彦 寺田 努 塚本 昌彦
- 雑誌
- 研究報告エンタテインメントコンピューティング(EC)
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, no.21, pp.1-6, 2011-05-06
現在,着ぐるみは様々なイベントで数多く利用されている.しかし,多くの着ぐるみは体の大きさや形が人間と異なっており,着ぐるみ装着者が自分の姿勢を認識することが難しい.また,着ぐるみ装着者の視界は制限されており,周囲の人々の存在を感知しづらく,人々とスムーズにコミュニケーションを行うことが難しい.そのため,着ぐるみ装着者がそのキャラクタらしく振る舞うためには高度な技術や十分な修練が必要となる.そこで本研究では,着ぐるみ装着者がそのキャラクタらしく振る舞うための支援を行う着ぐるみ装着者支援システムを提案する.評価実験の結果から,提案システムを用いることでスムーズなコミュニケーションが行えることを確認した.Recently, stuffed suits are widely used in various events. However, performances with stuffed suits have several difficulties; performers cannot recognize their posture because of the difference in shape and size between stuffed suits and physical human body, and it is difficult to communicate with other people smoothly because of limited visibility. These problems lead the performers to train too hard to acquire high skill of performances. The goal of our study is to construct a system for supporting performers in stuffed suits, which enables performers to act like the character of stuffed suits. From the evaluation results of our prototype system, we confirmed that our method is effective for supporting performers in stuffed suits.
2 0 0 0 コンピュータによる顔の認識 : サーベイ
- 著者
- 赤松 茂
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌. D-II, 情報・システム, II-情報処理 (ISSN:09151923)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.8, pp.2031-2046, 1997-08-25
- 被引用文献数
- 175
コンピュータによって顔画像の個人認識を行う技術の最近の研究動向について述べる. まず, これまでに多くの研究が行われてきた正面顔画像による個人識別を目的とした顔パターンの表現法について紹介すると共に, 更にこれらを顔の姿勢変化による見え方の変化を許容する方向に拡張しようとする研究の動向について述べる. また米国においてそのようなロバストな顔認識技術の確立を目指した研究の推進の原動力の一つとなっている顔認識技術開発計画FERETの動向についてもあわせて解説する. 更に, コンピュータによる顔の認識をコンテンツによる映像データベースの検索や編集というメディア処理の要素技術の一つとしてとらえ, 顔が伝える感性的な情報に対する人間の認知特性をコンピュータによる顔の認識に反映させることを狙いとして, 人間による顔認識過程をモデル化しようとしている試みについても紹介する. 最後に, 個人識別やデータベース検索など, 顔に対するさまざまな高次視覚情報処理を実現する前提として重要な, シーン画像から顔パターンを抽出する機能の実現についての研究の現状を述べる.
2 0 0 0 OA イデオロギー研究の方法論的基礎
- 著者
- 田中義久
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.20-40,102, 1967-06-01 (Released:2009-11-11)
- 参考文献数
- 54
2 0 0 0 OA 「アスペクト盲」は何が出来ないか
- 著者
- 奥 雅博 オク マサヒロ Oku Masahiro
- 出版者
- 大阪大学人間科学部
- 雑誌
- 大阪大学人間科学部紀要 (ISSN:03874427)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.21-40, 1989-03
- 著者
- 若井 一樹 佐々木 良一
- 雑誌
- 研究報告コンピュータセキュリティ(CSEC)
- 巻号頁・発行日
- vol.2014-CSEC-67, no.2, pp.1-8, 2014-11-28
Twitter におけるスパム行為となりすまし行為の検知手法を提案する.これらの検知手法はスパム行為となりすまし行為の様々な特徴から検知対象であるか判定する項目を複数個作成し,それら項目を数量化理論の適用によって最適な項目組み合わせを選定することによって検知するものである.またこれら手法を実装するとともに,検知結果をユーザにわかりやすく提示するよう Twitter の表示系を強化したアプリケーション LookUpper の開発と評価を行った.この結果,本検知手法ではスパム行為となりすまし行為どちらも 90% 以上の的中率で検知することが可能であった.LookUpper の開発と評価について,本検知手法を実装し検知結果をわかりやすく表示する機能を開発し,被験者 10 人によってなされた LookUpper のユーザビリティに関する実験結果から全体的に高い評価を得るとともに,今後 LookUpper の改良を行っていくためのアイディアを導く種々のコメントが寄せられた.
2 0 0 0 OA 対人判断における社会的カテゴリー適用可能性の効果とその個人差
- 著者
- 森 津太子
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- 性格心理学研究 (ISSN:13453629)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.27-37, 1997-03-31
- 著者
- 林原 史明 ハヤシハラ フミアキ Hayashihara Fumiaki
- 出版者
- 大阪大学大学院人間科学研究科 社会学・人間学・人類学研究室
- 雑誌
- 年報人間科学 (ISSN:02865149)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.147-151, 2013-03-31
2 0 0 0 OA 化学切削用感光性ガラス
- 著者
- 松浦 孝
- 出版者
- 一般社団法人 表面技術協会
- 雑誌
- 実務表面技術 (ISSN:03682358)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.11, pp.552-558, 1988-11-01 (Released:2009-10-30)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1 2
2 0 0 0 OA マス・コミュニケイションにおける説得
- 著者
- 柳井 道夫
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.2-19,104, 1967-06-01 (Released:2009-11-11)
- 参考文献数
- 2
2 0 0 0 OA ロシア 地方自治体制度改革
- 著者
- 小泉悠
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)
- 巻号頁・発行日
- vol.(月刊版. 260-2), 2014-08
2 0 0 0 OA マス・コミュニケーションと個人的意見傳達
- 著者
- 佐藤 智雄
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.3, pp.23-38, 1953-04-30 (Released:2009-11-11)
- 参考文献数
- 20
There are already many studies of media and content of mass communication, but the effect of its content remains to be carefully studied. In accordance with the classification adopted by messrs. Berelson and Merton the content of mass communications may be divided into emotional and rational components. This article points out that rational content alone is not sufficient to achieve the desired effects because it can not be understood by mass audiences. The role of personal communication in bridging interrupted communication channels and the image of the transmitter of opinion in its relationship to the structure of the group sponsoring the opinion are discussed. Transmitters of opinion are classified into three types according to their degree of leadership and the functions performed by each of them in the community are then touched upon. This leads to a consideration of the structure of mass communication and points out the danger that the content of communication will be further distored by personal prejudices and propagandistic intentions.
2 0 0 0 学びの技 : 14歳からの探究・論文・プレゼンテーション
- 著者
- 後藤芳文 伊藤史織 登本洋子著
- 出版者
- 玉川大学出版部
- 巻号頁・発行日
- 2014
- 著者
- 川鯉 光起 中矢 誠 富永 浩之
- 雑誌
- 研究報告コンピュータと教育(CE)
- 巻号頁・発行日
- vol.2013, no.20, pp.1-10, 2013-03-08
書籍関連サイトと連携した研究室規模の蔵書管理システムを構築し,その上に文献共有による学習支援を提案する.蔵書管理の対象は情報系の専門書であり,目的は知識や技能の向上のための精読である.そこで,貸出履歴や既読者のコメントを活用し,書籍利用を活性化させるため,記録部と分析部を追加した.また,文献共有による精読の形態を,個読・引継・輪講の3通りに分類し,支援に必要な機能を検討する.本論では,特に,プログラミングの解説書を題材とする演習付の輪講に着目し,コードレビューを取り入れた支援システムを検討する.レビュイーが書いているコードの編集状況をリアルタイムに中継し,レビュアーがその場でコメントを付与していく.その過程を,スナップショットとして保存し,後から再生して追体験することができる.試作版として実装した機能を議論し,ユーザによるシステムの試用結果について報告する.We have proposed a library management system in a laboratory scale for common use books about technology and science. The system cooperates with several book search and seller sites in order to acquire book information. We also consider learning support functions using common use books, especially about information engineering. We added record and analysis sub-modules into the system. We regard careful reading as three types; self-pace, inheriting and synchronic. We focus lectures and exercises in turn for a handbook of programming as the third aspect. We designed a support tool with code review functions for peer review. It offers streaming view of a coding program by a reviewee and real-time chat for comments of reviewers, which are recorded as snapshot series. We report results of experiments of a prototype tool.
- 著者
- 新保 史生
- 出版者
- 日本図書館協会
- 雑誌
- 現代の図書館 (ISSN:00166332)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.3, pp.180-186, 2013-09
- 著者
- 杉 正人 川村 隆一 佐藤 信夫
- 出版者
- 社団法人日本気象学会
- 雑誌
- Journal of the Meteorological Society of Japan. Ser. II (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.3, pp.717-736, 1997-06-25
- 参考文献数
- 51
- 被引用文献数
- 15
気象庁全球モデルを用いて、アンサンブル気候実験を行い、海面水温 (SST) 変動に強制されて起きる大気の長期変動と、季節平均場の予測可能性について調べた。モデルの34年時間積分を3回実行した。3つの時間積分はいずれも1955-1988年の実測のSSTを境界条件としているが、大気の初期状態が異なっている。季節平均場の全変動のうち、SSTの変動で強制されて起きている変動の割合 (分散比) を計算した。この分散比は、SSTが完全に予測された場合の最大予測可能性 (ポテンシャル予測可能性) を示すものと考えられる。気圧場の分散比は一般に熱帯では高い (50-90%) が、中高緯度では低い (30%以下)。このことは、季節平均気圧場の (ポテンシャル) 予測可能性は、熱帯では高いが、中高緯度では低いことを示唆している。一方、季節平均降水量の分散比は、ブラジルの北東部の74%、インドモンスーンの31%というように、熱帯の中でも地域によって大きく異っている。全球平均の陸上の地表気温の分散比は高い (66%) が、ほとんどの陸上の地点での局地的な地表気温の分散比は低く (30%)、海面水温予測にもとづく局地的な陸上の気温の予測可能性が小さいことを示唆している。
2 0 0 0 OA 第36回日本音声言語医学会総会特集
- 出版者
- 日本音声言語医学会
- 雑誌
- 音声言語医学 (ISSN:00302813)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.82-130, 1992-01-20 (Released:2010-06-22)
- 著者
- 小野 友道
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, no.11, pp.1355-1363, 1997-10-20
2 0 0 0 OA 絵本と子どもの人間形成論 : 他者との邂逅の不可能性と可能性
- 著者
- 久保田 健一郎 クボタ ケンイチロウ Kubota Kenichiro
- 出版者
- 大阪大学大学院人間科学研究科教育学系
- 雑誌
- 大阪大学教育学年報 (ISSN:13419595)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.89-100, 2012-03-31
2 0 0 0 OA 技術者の軍民転換と鉄道技術研究所
- 著者
- 沢井 実 サワイ ミノル Sawai Minoru
- 出版者
- 大阪大学経済学会
- 雑誌
- 大阪大学経済学 (ISSN:4734548)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.1-19, 2009-06