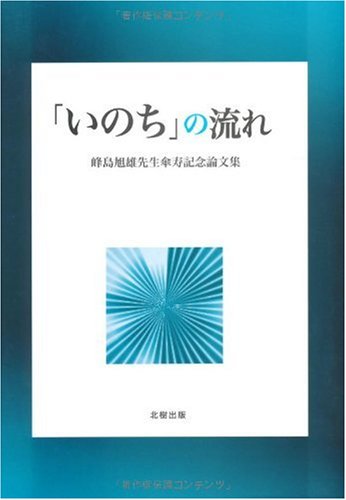2 0 0 0 IR 多くの観測点の資料による脈動の研究(其の1) : 脈動源について
- 著者
- Santo Tetsuo A.
- 出版者
- 東京大学地震研究所
- 雑誌
- 東京大學地震研究所彙報 (ISSN:00408972)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.307-325, 1959-08-25
I・G・Yの日米国内の脈動観測資料を用いて,各地の脈動嵐が何の影響でどんな起り方をするか,また各地の脈動嵐相互間の時間的な関係はどのようにかつているかを,天気図と対照しつつ調べた.その結果,1)低気圧や台風が日本の東方海上を東北進する場合には,脈動嵐はそれを追いかけるようにして西南日本から東北日本へと移つてゆく.そしてこの場合,ある地区に脈動嵐が一番ひどくなる時期は,低気圧や台風の中心がかなり行きすぎてしまつてからである.この傾向は,低気圧の場合に特に著しい.
2 0 0 0 OA 巨大長周期地震動を受ける鋼製橋梁の動的耐荷性能評価と動的設計法の開発
海溝型巨大地震のような長周期・長継続時間地震波を受ける鋼製橋梁の耐震性能の把握が重要である。そこで,都市高速に多用されている鋼製橋脚を対象とし,ハイブリッド実験,静的繰返し載荷実験およびFE非線形解析により,最大耐力履歴後の数十回に及ぶ繰返し変位による耐力低下を検討した。その結果,最大荷重履歴後,初等はり理論で弾性範囲と考えられる数十回に及ぶ変位載荷により,耐力は10%程度低下する可能性のあることが分かった。また繰返し振幅範囲が大きいほど,繰り返し数が多いほど耐力低下の割合が大きいことがわかった。
2 0 0 0 サハリンの活断層の分布と概要
- 著者
- 鈴木 康弘 堤 浩之 渡辺 満久 植木 岳雪 奥村 晃史 後藤 秀昭 STREL'TSOV Mihail I. KOZHURIN Andrei I. BULGAKOV Rustam TERENTIEF Nikolai IVASHCHENKO Alexei I.
- 出版者
- Tokyo Geographical Society
- 雑誌
- 地學雜誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.109, no.2, pp.311-317, 2000-04-25
- 被引用文献数
- 1 4
We have prepared a preliminary active fault map of Sakhalin, Russia, based on an interpretation of aerial photographs and satellite images. Major active structures include 110-km-long active faults along the western margin of the Yuzhno-Sakhalinsk Lowland in southern Sakhalin and 120-km-long active faults along the western margin of the Poronaysk Lowland in central Sakhalin. These active faults are parallel to but are located as far as 10 km east of the Tym-Poronaysk fault. Geomorphic surfaces on the upthrown side of the fault are tilting westward, therefore, the faults are considered to be west-dipping low-angle reverse faults. The vertical component of slip rates of these faults are >0.3 mm/yr in southern Sakhalin and 1.0-1.5 mm/yr in central Sakhalin. The net-slip rates could be much greater because the faults are low-angle reverse faults. If these faults rupture along their entire length during individual earthquakes, the earthquakes could be as great as M7.6-7.7. In northern Sakhalin, we have identified a series of right-lateral strike-slip faults, including the 1995 Neftegorsk earthquake fault. The slip rates for these faults are estimated at 4 mm/yr. The right-lateral shear in northern Sakhalin and east-west compression in central and southern Sakhalin may reflect relative plate motion in far-east Asian region.
2 0 0 0 OA 湿潤変動帯における台風頻度が斜面崩壊の規模-頻度と土砂生産に与える影響の評価
- 著者
- 齋藤 仁
- 出版者
- 関東学院大学
- 雑誌
- 研究活動スタート支援
- 巻号頁・発行日
- 2013-08-30
本研究では、2001~2011年に降雨に起因して発生した4,744件の斜面崩壊を対象とし、斜面崩壊の規模-頻度と雨量との関係、および台風の影響を解析した。その結果、累積雨量~250 mm、最大時間雨量~35 mm/h、平均雨量強度~4 mm/h を超えると、規模の大きな斜面崩壊の頻度が高くなり、台風の寄与率は最大で約40%であった。また、現在の気候下において斜面崩壊の頻度とそれによる総侵食量を最大にする降雨イベントが存在し、それらの再現期間は約40年以下であることが示唆された(Saito et al., 2014, Geology)。
2 0 0 0 IR (雑誌抄録)「リツトル」氏腺なる名称を解剖学名中より抹殺せよ
- 著者
- 小原 清信
- 出版者
- 久留米大学法学会
- 雑誌
- 久留米大学法学 (ISSN:09150463)
- 巻号頁・発行日
- no.56, pp.41-136, 2007-05
- 著者
- 田中 景子 飯島 洋一 高木 興氏
- 出版者
- 有限責任中間法人日本口腔衛生学会
- 雑誌
- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.215-221, 1999-04-30
- 被引用文献数
- 2
エナメル質ならびに象牙質の脱灰病変に,重炭酸イオンを作用させることによって,再石灰化の過程にどのような影響を及ぼすかをin vitroで検討した。試料には50歳代の健全小臼歯を用いた。脱灰は0.1M乳酸緩衝液(Ca 3.0mM, P 1.8mM, pH 5.0)で7日間行い,続いて再石灰化溶液(Ca 3.0mM, P 1.8mM, F 2ppm,pH 7.0)に7日間浸漬した。この再石灰化期間中,8時間ごとに再石灰化溶液から取り出し,30分間,4種の異なった重炭酸イオン溶液(0.0, 0.5, 5.0, 5O.OmM)に浸漬した。薄切平行切片を作成し,マイクロラジオグラフによってミネラルの沈着を評価した。エナメル質では重炭酸イオン濃度の増加に伴って,病変内部に再石灰化が発現する傾向が認められたが,統計学的な有意差はなかった(p=0.09)。一方,象牙質では表層に限局した再石灰化が認められた。特に5.0mM群では著明であったが,エナメル質と同様,統計学的な有意差は認められなかった(p=0.08)。エナメル質と象牙質で異なる再石灰化の所見が発現した理由は,重炭酸イオンの浸透性の違いによるものであると推察される。
2 0 0 0 OA 千葉卓三郎にみる「外来青年」についての研究
- 著者
- 川原 健太郎
- 出版者
- 早稲田大学大学院教育学研究科
- 雑誌
- 早稲田大学大学院 教育学研究科紀要 別冊 (ISSN:13402218)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.11-21, 2003-09-30
2 0 0 0 OA 公共図書館経営の進め方 ―新任図書館長の皆さんへ―
- 著者
- 薬袋 秀樹
- 巻号頁・発行日
- 2013-02
平成24年度新任図書館長研修のまとめ
2 0 0 0 日本列島における中新世のコールドロンの配列に関する数値実験
- 著者
- 小室 裕明
- 出版者
- 地学団体研究会
- 雑誌
- 地球科學 (ISSN:03666611)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.115-123, 1986-03-25
- 被引用文献数
- 1
本宿型陥没構造(cauldron)は,1.ドーム隆起,2.陥没形成,3.噴火,という形成過程をふみ,いくつかの陥没が討究する傾向がある.隣接する陥没盆地間の中心距離は,数km〜30km,平均して20km程度である.このように陥没盆地がある一定の距離を隔てて等間隔配列をするのは,それぞれの盆地に対応してマグマ溜りが深部の低密度の部分溶融層から浮上してきたためと考えられる. Rambergによる重力不安定の理論式にもとずいて,20kmの卓越波長を生じる条件を数値計算した.モデルは2層構造であり,上層/下層(浮上層)の比が,0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0の6通りのケースを設定して,粘性係数比と肩摩の関係を求めた.その結果,卓越波長は,上層の厚さ(部分溶融層の深さ)にはほとんど無関係であり,部分溶融層の厚さに大きく影響される.20kmの卓越波長を与える溶融層の厚さは6km以下である必要がある.
2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1894年01月31日, 1894-01-31
2 0 0 0 OA 自己炎症疾患
- 著者
- 井田 弘明
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.97, no.2, pp.438-447, 2008 (Released:2012-08-02)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 2 2
自己炎症疾患(autoinflammatory disease)は,自己炎症症候群(autoinflammatory syndrome)とも呼ばれる新しい疾患概念である.繰り返す全身性の炎症を来す疾患で,多くは発熱がみられ,関節·皮膚·腸·眼などの部位の炎症を伴う.症状としては,感染症や膠原病に類似しているが,病原微生物は同定されず,また,自己抗体や抗原特異的T細胞も検出されない.近年,Toll-like受容体や細胞内のNLRファミリー蛋白の分子機構の解明が進み,また,これらの分子が,一部の遺伝性周期熱症候群の疾患遺伝子でもあったことから,自己炎症疾患の概念が提唱され,現在注目されている.欧米の疾患と思われていた遺伝性周期熱症候群は,本邦でも存在が確認され,不明熱の鑑別疾患に挙げる必要性がでてきている.本稿では,自己炎症疾患の概念,分類を紹介するとともに,各疾患の臨床像と病因を簡単に解説した.
2 0 0 0 OA 〈実践報告〉分配法則を軸とした乗法始動の試み
- 著者
- 須田 勝彦 氏家 英夫
- 出版者
- 北海道大学教育学部教育方法学研究室
- 雑誌
- 教授学の探究 (ISSN:02883511)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.147-174, 1984-03-31
- 著者
- 研谷 紀夫
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 研究報告人文科学とコンピュータ(CH)
- 巻号頁・発行日
- vol.2013, no.2, pp.1-5, 2013-07-27
2010 年代より普及した、タブレット端末に対応する Digital Cultural Heritage が多数開発され公開されてきている。タブレット端末が普及する黎明期に、どのような文化資源を対象としたコンテンツが発売されたかを把握することは、将来 Digital Cultural Heritage の歴史を編成する上で、重要な記録となろう。記録を行う上では、文字によるメタデータの形で残すことが必要であるが、どのような項目を遺すべきかについて検討する必要がある。また、メタデータ情報を形成する場合、Apple 社の Apple iTunes Store などの公開頒布サイトで公表されているメタデータを活用することが考えらえる。本試論では、主に公開頒布サイトで公開されているメタデータが Digital Cultural Heritage の記録を遺すメタデータとしてどの程度有効であるかを検証する。その上で、タブレット向けの Digital Cultural Heritage の存在をどのように後世に残していくかについても検討する。Digital Cultural Heritage has been developed and published for the tablet machine which spread out in 2010s.It becomes important for considering and descripting about the history of Digital Cultural Heritage in the future to record content of it. Although literal metadata should be reserved, we should consider what kind of element should be adapted. And, one method of constructing metadata is adapting metadata which published in Apple iTunes Store .In this tentative study, I verify the availability of metadata which published in Apple iTunes Store as preserved and succeeded metadata for Digital Cultural Heritage. Moreover, I considered how to record existence of Digital Cultural Heritage for tablet in the future.
- 著者
- Tanabe Akifumi S. Toju Hirokazu
- 出版者
- Public Library of Science
- 雑誌
- PLoS ONE (ISSN:19326203)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.10, 2013-10-18
- 被引用文献数
- 208
あらゆる生物の名前をDNAに基づいて特定する「DNAバーコーディング」の理論的枠組みを確立. 京都大学プレスリリース. 2013-10-19.
2 0 0 0 OA 地震と降雨による複合斜面災害の危険度判定と早期警報技術の適用に関する海外調査研究
- 著者
- 内村 太郎 古関 潤一 桑野 玲子 東畑 郁生 西江 俊作 WANG Lin QIAO Jian-Ping YANG Zongji HUANG Dong HUANG An-Bing LU Chin-Wei
- 出版者
- 埼玉大学
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2013-04-01
中国、台湾、日本で、強い地震によって損傷を受けた自然斜面が、その後の豪雨をきっかけに崩壊する「地震と降雨の複合的な作用」による斜面災害を対象として調査研究を行った。(1)地震で強震を受けた山岳地域の斜面で、踏査、機器を使った調査と観測、現地実験を行い、斜面の不安定化の実態とメカニズムを把握し、危険な斜面の抽出の方法や災害を軽減する方法を提案した。(2)低コストで簡易な斜面表層の変状の観測装置を用いて、斜面災害の前兆をとらえ、早期警報によって被害を軽減する技術の実用化を推進した。さらに、多点計測や、弾性波を用いた斜面監視など、新しい技術を開発した。
2 0 0 0 OA 本邦無線電信電話局所設備一覧表
2 0 0 0 「いのち」の流れ : 峰島旭雄先生傘寿記念論文集
- 著者
- 峰島旭雄先生傘寿記念論文集編集委員会編
- 出版者
- 北樹出版
- 巻号頁・発行日
- 2009