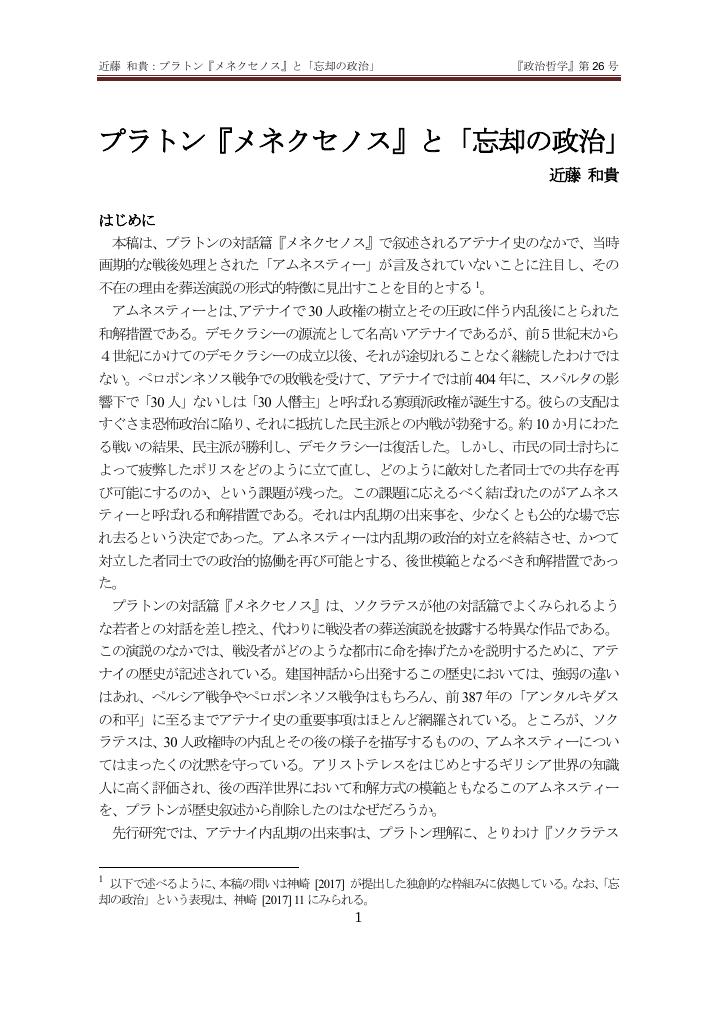1 0 0 0 OA ミャンマーに対するインドの「民主化支援」―民主主義的価値と地政学的利益との弁証法
- 著者
- 伊豆山 真理
- 出版者
- 一般財団法人 アジア政経学会
- 雑誌
- アジア研究 (ISSN:00449237)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.3, pp.84-96, 2023-07-31 (Released:2023-08-19)
- 参考文献数
- 38
Myanmar’s coup in 2021 surfaced India’s long-time challenge of democracy assistance in Myanmar. Resurgent debate on democratic value versus geopolitical interest as guiding principle for Myanmar policy has its origin in 1988 transition. India sided with Aung San Suu Kyi and other democratic leaders but turned to “two track policy” around 1993. Since then, phased engagement with military government evolved while uneasily searching for new format of democracy assistance.China’s expanding influence in Myanmar is often cited as India’s main geopolitical interest. However, India’s interest has been shifting over time, so it is too simplistic to see China factor as constantly dominant. This paper traces changes in weight and format of India’s democracy assistance. It focuses on geopolitical interest pertaining to land border, firstly necessity of border control and consequent importance of cooperation from Myanmar’s military regime, and secondly, land connectivity which Myanmar provides as gateway to ASEAN.Myanmar’s place in India’s “Look East” and later “Act East” is quite interesting. India's vision for its Northeastern area development was tied to its neighbor. Connecting Northeast to ASEAN through Myanmar was the key to its Look East policy. Thus, engaging military government of Myanmar became legitimate as a part of ASEAN connectivity. India’s diplomacy under Prime Minister Manmohan Singh emphasized democratic value than ever as India started to identify itself as rising “democracy.” The feature of India’s democracy assistance debate then was that democratic transition was presented as the mean for economic development. Also, democracy assistance was thought to be best done through building institution.Prime Minister Narendra Modi announced “Act East” policy at East Asia Summit held in Nay Pyi Taw in 2014. Under the Act East, India prioritized Bangladesh and Myanmar as recipients of capacity building. We can observe that India set to compete with China at this stage. Capacity building is a convenient policy tool which includes building education centers such as IIT and transferring submarine to Myanmar navy. India also supplied Covid-19 vaccine to Myanmar as humanitarian assistance.Regarding democratic value versus geopolitical interest, the real test for India is Rohingya crisis. Refugee and migrant in the Northeast is problematic as it has ramifications on citizenship issue. India changed its tolerant policy in 2017 and defined Rohingya as “illegal migrants.” Instead of extending asylum in India, India provided humanitarian assistance to Rohingya in Bangladesh as well as in Rakhine state.
- 著者
- 小林 直美
- 出版者
- 日本スポーツとジェンダー学会
- 雑誌
- スポーツとジェンダー研究 (ISSN:13482157)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.108-111, 2022 (Released:2022-11-20)
1 0 0 0 OA 戦国時代の公家・吉田兼見の茶の湯
- 出版者
- 茶の湯勉強会
- 雑誌
- 茶の湯文化研究 (ISSN:24356522)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.97-149, 2022-01-01 (Released:2022-07-01)
1 0 0 0 OA プラトン『メネクセノス』と「忘却の政治」
- 著者
- 近藤 和貴
- 出版者
- 政治哲学研究会
- 雑誌
- 政治哲学 (ISSN:24324337)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.1-18, 2019 (Released:2019-11-01)
- 参考文献数
- 28
1 0 0 0 OA 沖縄に生まれた共通語(文法編)
- 著者
- 永田 高志
- 出版者
- 法政大学沖縄文化研究所
- 雑誌
- 琉球の方言 = 琉球の方言 (ISSN:13494090)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.138-173, 1991-03-25
1 0 0 0 OA 熱対流の不安定性と遷移
- 著者
- 水島 二郎
- 出版者
- 社団法人 日本流体力学会
- 雑誌
- 日本流体力学会誌「ながれ」 (ISSN:02863154)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.5, pp.315-331, 2000-10-30 (Released:2011-03-07)
- 参考文献数
- 34
- 著者
- 井上 真理子 川上 正浩
- 出版者
- 北陸心理学会
- 雑誌
- 心理学の諸領域 (ISSN:2186764X)
- 巻号頁・発行日
- pp.2023-05, (Released:2023-11-10)
- 参考文献数
- 25
This study examined how university students’ self-control and attitude toward delay relate to their smartphone usage time. The study focuses on both subjective and objective smartphone usage time. Participants were 74 university students who use iPhones. First, we conducted a correlation analysis by measuring subjective and objective usage time for online use such as SNS, online video viewing, and games. Next, participants’ personal characteristics, such as self-control and attitude toward delay, were measured using a 6-item method and a 5-item method, respectively. Consequently, the study found a positive correlation between subjective and objective usage time for "SNS" and "games" during 24 hours. However, no correlation was found between "videos and the Internet" or "total time ". Additionally, a positive correlation was found with external control and a negative correlation with reformative self-control scores in subjective time spent on "video and Internet". Conversely, the score of reformative self-control negatively correlated with subjective time for "video and Internet", but no correlation was found with objective time for "video and internet." The findings suggest that self-control and smartphone use differ regarding subjective and objective measures, including the purpose of use.
- 出版者
- 日本獣医腎泌尿器学会
- 雑誌
- 日本獣医腎泌尿器学会誌 (ISSN:18832652)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.64-85, 2021 (Released:2021-12-12)
尿路疾患は犬・猫でよく見られる臨床症状であり、抗菌薬の処方理由として一般的である。本稿は、2011年版「犬・猫における尿路疾患治療に関する抗菌薬使用ガイドライン」の改訂拡張版であり、散発性細菌性膀胱炎、再発性細菌性膀胱炎、腎盂腎炎、細菌性前立腺炎、無症候性細菌尿の診断管理に関する推奨事項について述べる。尿道カテーテルに関する問題、内科的尿石溶解、泌尿器科処置の感染予防についても取り上げる。
1 0 0 0 OA 優秀演題
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本心臓血管外科学会
- 雑誌
- 日本心臓血管外科学会雑誌 (ISSN:02851474)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.Supplement, pp.S220-S224, 2020 (Released:2020-12-23)
- 著者
- 師井 聡子 柴田 良二 笹田 晋司 鉄谷 信二
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会
- 雑誌
- 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 (ISSN:1344011X)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.297-305, 2010-09-30 (Released:2017-02-01)
"Floating Words" is a new device for playing with words generated by CG technology in a small water pool. When a player says words to the megaphone-type microphone, the words drip into the water pool as letters. Then the player can scoop or stir them with a ladle. "Floating Words" is a beautiful and poetic interactive installation art work but also a tactile system with real water. In this system, players feel something comfortable and new although it has no artificial force feedback device.
1 0 0 0 OA 大学生における醜形恐怖心性とメンタライジングの関連
- 著者
- 坂田 浩之
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.101-110, 2021-09-16 (Released:2021-09-16)
- 参考文献数
- 23
本研究は,容姿にこだわる若者に対する理解を深めるために,醜形恐怖心性とメンタライジングとの関連について検討した。大学生689名に対して自己報告式の質問紙とReading the Mind in the Eyes Test (RMET)が実施された。本研究の結果,メンタライジングに関する自己認知は醜形恐怖心性と弱く関連することが示された。そして,メンタライジングに関する自己認知のうち,他者に関するメンタライジングは醜形恐怖心性と正の関連が,自己に関するメンタライジングは醜形恐怖心性と負の関連が示唆された。しかし,RMETで測定された,外的なものに基づく他者に関する顕在的なメンタライジングの正確さは醜形恐怖心性と関連しないことが示唆された。本研究の知見から,容姿にこだわる若者は,他者に関するメンタライジング能力を高く評価しがちで,自己に関するメンタライジング能力を低く評価しがちである可能性が検討された。
1 0 0 0 OA 降雨による粒子状物質の洗浄作用
- 著者
- 藤田 慎一
- 出版者
- Japan Society for Atmospheric Environment
- 雑誌
- 大気汚染学会誌 (ISSN:03867064)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.6, pp.335-341, 1988-12-20 (Released:2011-11-08)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1
ガス状・粒子状物質の長期湿性沈着量の推定モデルを導出し, 発生源の周辺における煤塵の沈着量を調べた。気象条件や粒径分布の設定値が, 沈着量の推定値に及ぼす影響についても検討を加えた。点源から大気中へ放出された粒子状物質の積算沈着量は, 無限遠で発生量に漸近するが, そのパタンは粒子の粒径によって異なる。ミクロン領域でも粒径が小さな粒子の沈着量の分布パタンは, 風向の出現頻度と比較的類似した分布パタンを示す。これに対して粒径が大きな粒子の沈着量の分布パタンは, 風速や発生源からの距離にも依存する。サブミクロン~ミクロン領域に分布を持つ煤塵の沈着量は, 発生源の周辺では粒径が大きな粒子に, 遠方では粒径が小さな粒子の挙動に支配される。このため重量を基準にした降水中の煤塵の粒径モードは, 発生源からの距離とともに粒径が小さな方へ遷移する。風系や降雨の統計データを用いると, 直接, 沈着量が推定できるため, このモデルは年~経年の長時間スケールにわたる湿性沈着量を推定するのに適している。沈着量を推定するうえでは, 気象条件とともに洗浄係数-つまり煤塵の粒径分布-を吟味することが, より重要な問題となる。
1 0 0 0 OA 術前診断が困難であった胃Glomus腫瘍の1例
- 著者
- 栃木 透 森 幹人 夏目 俊之 赤井 崇 林 秀樹 松原 久裕 大出 貴士
- 出版者
- 日本臨床外科学会
- 雑誌
- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.2, pp.386-390, 2013 (Released:2013-08-25)
- 参考文献数
- 18
Glomus腫瘍は四肢末端の皮下や爪下に好発し,胃原発のGlomus腫瘍はまれである.症例は52歳,男性.平成22年8月,胃粘膜下腫瘍の診断にて当科紹介.入院後精査から前庭部大彎の大きさ25cmの胃carcinoidの診断となり手術施行.病理組織所見および免疫染色から胃原発のGlomus腫瘍の診断であった.現在,WHOによるGlomus腫瘍のCriteriaによれば,大きさ2cm以上の胃Glomus腫瘍は,転移性病巣を形成するリスクのある悪性病変と定義されている1)2).しかし,本邦報告例では転移再発例はなく,海外の報告例4例のみであった.胃Glomus腫瘍に関して若干の文献的考察を加えて報告する.
本研究は、国際安全保障における協働化/分業化の状況を分析するため、アフリカに展開する国際平和活動の調査・比較を行う。国連と地域機構・準地域機構が協力して行うパートナーシップ国際平和活動は、アフリカでのみ発展している。なぜか。この問いに答えるために、本研究は、国際安全保障の協働化/分業化の仕組みに着目する。国連PKOが遂行できない武力行使を伴う活動をアフリカでは(準)地域機構が担うことができるため、パートナーシップ平和活動はアフリカでのみ進んできた、という仮説を検証する。主要なアフリカの国際平和活動に焦点をあてて、理論・組織・情勢分析を通じて、国際安全保障の協働化・分業化を解明する。
1 0 0 0 OA 『小學化學書』(明治7年)に見られる「乳鉢」の語とその背景
- 著者
- 五位野 政彦
- 出版者
- 日本薬史学会
- 雑誌
- 薬史学雑誌 (ISSN:02852314)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.90-93, 2012 (Released:2021-07-02)
The etymon of the Japanese word nyu-bachi (mortar) is unknown. The first step in the research process is to consult books on chemistry and pharmacy published in the 1870s, the first decade of the Meiji era when Japan began to modernize. The word nyu-bachi can be found in the Shogaku-Kagaku-Sho, published in 1874. Before 1873, the word usu (mil) is used in place of hachi or bachi, which also mean mortar. Before 1873, mills / mortars were used for crushing and grincling. In books published after 1873, one can find references in several books on chemistry and pharmacy to their use in mixing and dispensing. More in-depth research in the areas of pharmacy and Western-style cooking is necessary to determine the etymon.
- 著者
- 近藤 博隆
- 出版者
- ユーラシア研究所
- 雑誌
- ロシア・ユーラシアの社会 (ISSN:24353191)
- 巻号頁・発行日
- vol.2021, no.1056, pp.75-85, 2021 (Released:2023-03-08)
1 0 0 0 江戸城天守 : 寛永度江戸城天守復元調査研究報告書
- 著者
- 三浦正幸 中村泰朗 野中絢著
- 出版者
- 江戸城天守を再建する会
- 巻号頁・発行日
- 2016
1 0 0 0 OA 多義動詞を中心語とするコロケーションの習得
- 著者
- 大神 智春
- 出版者
- 公益社団法人 日本語教育学会
- 雑誌
- 日本語教育 (ISSN:03894037)
- 巻号頁・発行日
- vol.166, pp.47-61, 2017 (Released:2019-04-26)
- 参考文献数
- 21
中国語母語話者および韓国語母語話者を対象に,多義動詞「とる」で形成されるコロケーションの習得について調査した。まず(1)日本語母語話者が認識する「とる」の意味体系を整理した。次に(2)学習者が考える「とる」のプロトタイプ,(3)「とる」で形成されるコロケーションの理解について調査・分析した。その結果,(1)母語話者が考える意味体系と辞書的体系はおおよそ一致するが一部相違が見られる,(2)学習者と母語話者が考えるプロトタイプにはずれが見られ,学習者は独自の意味体系を構築していると考えられる,(3)学習者は多義性についてある程度習得するが,共起語として使用できる語の範囲は広がりに欠ける。各コロケーションの用例を「点」として習得し,習得した知識は「面」として広がりにくいことが示唆された。