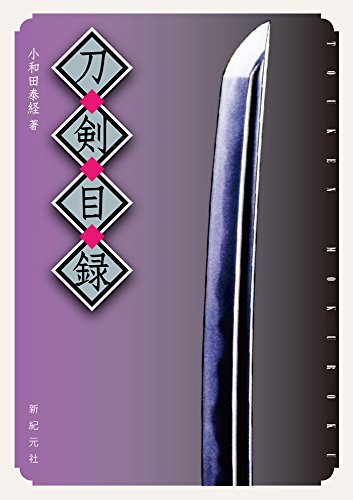11 0 0 0 OA 有用物質生産のための代謝ネットワーク設計
- 著者
- 田村 武幸
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本バイオインフォマティクス学会
- 雑誌
- JSBi Bioinformatics Review (ISSN:24357022)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.2, pp.37-46, 2021 (Released:2021-04-23)
- 参考文献数
- 31
生体の細胞内では数千以上もの化学反応が、適切なタイミングで適切な量おこることにより、多様な機能が維持されている。代謝ネットワークは、細胞内の化学反応と化合物の関係をネットワークとして表現する。代謝ネットワークの種々の数理モデルの中でも、制約モデルを用いた流束均衡解析(Flux balance analysis: FBA)はゲノムスケールの代謝ネットワークに対しても高速なシミュレーションが可能であることが知られている。しかし所望の性質を持つ代謝ネットワークのFBAに基づく設計は、シンプルなFBAシミュレーションに比べて所用計算時間が激増するので、数理的な工夫をしなければ最新鋭の計算機システムを用いても実質的に計算不可能な場合が多い。本稿では、有用物質生産のための制約モデルに基づく代謝機能設計について、数理的側面を中心に、図例を用いながら基本的な問題設定やアルゴリズム、分野の動向等を解説する。
- 著者
- 若林 一敏
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.37-50, 2012-07-01 (Released:2012-07-01)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 2 5
CやC++言語等のプログラム記述から,ASICやFPGAを設計するためのRTL記述を合成する「高位合成」技術の概要を述べる.まず,LSIの設計工程とその自動化の歴史と,LSIの大規模化による設計自動化の必然性について説明する.次に,高位合成技術の原理を工程ごとに解説する.高位合成は設計効率化以外に高性能化,低電力化,高信頼性化,再利用性の向上など様々な効果がある.なぜ,そのような効果が得られるかを,技術面から解説する.また,高位合成のターゲットアーキテクチャであるFSM(Finite State Machine)とデータパスからなるFSMDアーキテクチャ処理効率をCPUと比較して議論する.高位合成は基本原理が確立されプロトタイプシステムが出てから実用化まで長い時間がかかった.非常に広範な最適化技術の実装が必要だからである.これらの中から代表的な幾つかの技術を議論する.また,高位合成技術はアルゴリズム系のデータ処理回路だけでなく,制御系回路にも有効であることを示す.次に,ハードウェア向けのC記述の基本の考え方を紹介し,最後に,近年適用が広まっているFPGA向けの高位合成技術やそれを利用した新しい応用分野を紹介する.
- 著者
- 林 幸希
- 出版者
- 日本ペストロジー学会
- 雑誌
- ペストロジー (ISSN:18803415)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.33-34, 2021-03-25 (Released:2022-03-25)
- 参考文献数
- 5
2019年7月12日と同13日に宮崎県で初記録となるフタホシモリゴキブリを採集した.本種の日本国内における報告は3例目となる.
- 著者
- Yusuke Takashima Mai Suyama Kohei Yamamoto Tomohiko Ri Kazuhiko Narisawa Yousuke Degawa
- 出版者
- The Mycological Society of Japan
- 雑誌
- Mycoscience (ISSN:13403540)
- 巻号頁・発行日
- pp.MYC574, (Released:2022-06-17)
- 被引用文献数
- 1
Myconymphaea yatsukahoi is a fungus that has only been isolated once from a forest in the Sugadaira Research Station, Nagano, Japan. Over 20 y have passed since its first discovery but since then it has not been rediscovered. Here, we re-isolated M. yatsukahoi from the type locality and another location, Tambara Moor, Gunma, Japan. Sporophores of this species were detected by direct field observation in Sugadaira and by induction from soil from Tambara. We attempted to narrow down isolation sources of this species by investigating the excrements of Lithobiomorpha and Scolopendromorpha centipedes, which are frequently found in the two locations where the species is distributed. In both locations, we found M. yatsukahoi in the excrements of Lithobiomorpha but not Scolopendromorpha. Myconymphaea yatsukahoi appears to be a coprophilous fungus and the excrements of the predators living in soil may be promising isolation sources for understanding the hidden diversity of kickxellalean fungi.
11 0 0 0 OA 雑談対話システムにおける対話破綻を生じさせる発話の類型化
- 著者
- 東中 竜一郎 荒木 雅弘 塚原 裕史 水上 雅博
- 出版者
- 一般社団法人 言語処理学会
- 雑誌
- 自然言語処理 (ISSN:13407619)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.443-466, 2022 (Released:2022-06-15)
- 参考文献数
- 43
本稿では,雑談対話システムにおける対話破綻を生じさせる発話の類型を提案する.対話破綻の類型に関して先行研究では,「理論に基づいた類型」と「データに基づいた類型」が提案されてきた.前者は,依拠している人どうしの対話についての理論が,雑談対話システムの対話破綻現象を捉えるのに適さないことが多いという問題点がある.後者は,データを取得したシステムの対話破綻にしか対応できないという限界がある.本稿では,これら二つの類型の問題点をそれぞれが補い合う形で統合し,雑談対話システムにおける対話破綻を生じさせる発話の類型を新しく作成した.対話破綻類型アノテーション実験の結果,この統合的な類型は以前に提案された類型と比較して,Fleiss の κ 値において高い一致率を達成し,安定したアノテーションが行えることがわかった.
11 0 0 0 OA 福島県いわき市末続地区における原発事故後の共有知の経験
- 著者
- Jacques LOCHARD Ryoko ANDO Hiroshi TAKAGI Shinya ENDO Maiko MOMMA Makoto MIYAZAKI Yujiro KURODA Takeshi KUSUMOTO Masako ENDO Setsuko ENDO Yohei KOYAMA
- 出版者
- 日本保健物理学会
- 雑誌
- 保健物理 (ISSN:03676110)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.1, pp.39-52, 2021-03-31 (Released:2021-05-26)
- 参考文献数
- 26
11 0 0 0 OA 「訓練事例の影響の軽量な推定」の執筆
- 著者
- 小林 颯介
- 出版者
- 一般社団法人 言語処理学会
- 雑誌
- 自然言語処理 (ISSN:13407619)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.699-704, 2022 (Released:2022-06-15)
- 参考文献数
- 13
- 著者
- Seiji Yukimoto Kunihiko Kodera Rémi Thiéblemont
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- SOLA (ISSN:13496476)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.53-58, 2017 (Released:2017-04-04)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 8
A delayed response of the winter North Atlantic oscillation (NAO) to the 11-year solar cycle has been observed and modeled in recent studies. However, the mechanisms creating this 2-4-year delay to the solar cycle have still not been well-understood. This study examines the effects of the 11-year solar cycle and the resulting modulation in the strength of the winter stratospheric polar vortex. A coupled atmosphere–ocean general circulation model is used to simulate these effects by introducing a mechanistic forcing in the stratosphere. The intensified stratospheric polar vortex is shown to induce positive and negative ocean temperature anomalies in the North Atlantic Ocean. The positive ocean temperature anomaly migrated northward and was amplified when it approached an oceanic frontal zone approximately 3 years after the forcing became maximum. This delayed ocean response is similar to that observed. The result of this study supports a previous hypothesis that suggests that the 11-year solar cycle signals on the Earth's surface are produced through a downward penetration of the changes in the stratospheric circulation. Furthermore, the spatial structure of the signal is modulated by its interaction with the ocean circulation.
11 0 0 0 OA 日本における原子力開発利用の民営化について
- 著者
- 吉岡 斉
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 現代生命論研究 = Recent Developments in Contemporary Life Studies
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.273-282, 1996-01-31
11 0 0 0 OA 軍需会社と徴用法規集
- 出版者
- 工場管理研究所
- 巻号頁・発行日
- 1944
11 0 0 0 OA 大阪府史蹟名勝天然記念物調査報告書
11 0 0 0 OA 江戸戯作の「連載」構想(<特集><連載>の場と力学)
- 著者
- 小二田 誠二
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.11, pp.2-10, 2004-11-10 (Released:2017-08-01)
新聞小説のもとになったと言われる続き物は、江戸戯作の作法に倣った物であるという。実際、江戸戯作の中には読者の好評を理由に当初の計画よりも長編化する作品が少なくない。定期刊行物に連続して掲載されるという意味での連載以前に、分割して出版された小説における本文生成について、『椿説弓張月」『春色梅児誉美』『道中膝栗毛』を材料に、それぞれに異なる「長編化」方法の意味を考察する。
11 0 0 0 OA 腸管免疫におけるビタミンAの役割
- 著者
- 岩田 誠
- 出版者
- 公益財団法人 腸内細菌学会
- 雑誌
- 腸内細菌学雑誌 (ISSN:13430882)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.4, pp.297-304, 2007 (Released:2007-11-27)
- 参考文献数
- 27
広い表面積で外界と接する腸管では,免疫細胞の配備が必須である.一般に,リンパ球の組織への配備は一定のルールに則って行われる.ナイーブT細胞は,リンパ節などの二次リンパ系器官には移入できるものの,非リンパ系組織には移入できない.二次リンパ系器官で抗原刺激を受けてエフェクター/メモリーT細胞となると,その二次リンパ系器官が所属する組織に選択的に移入(ホーミング)できるようになる.例えば,腸の二次リンパ系器官であるパイエル板や腸間膜リンパ節で抗原刺激を受けたT細胞は,小腸特異的ホーミング受容体(インテグリンα4β7とケモカイン受容体CCR9)を発現し,小腸に移入できるようになる.我々は,腸の二次リンパ系器官の樹状細胞がT細胞に抗原提示をすると同時にビタミンAからレチノイン酸を生成し与えることで,小腸特異的ホーミング受容体を発現させていることを見出した.同様に,ナイーブB細胞が抗原刺激を受け,小腸へのホーミング特異性を獲得するためにも,また,さらにIgA抗体産生細胞へと分化するためにもレチノイン酸が必須であることを明らかにした.
11 0 0 0 OA 韓国におけるいじめ対策法制
- 著者
- 藤原夏人
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)
- 巻号頁・発行日
- no.256, 2013-06
11 0 0 0 OA 新型コロナウイルス感染症に関する壮年パネル調査 ―概要と記述統計分析―
- 著者
- 飯田 高 石田 賢示 伊藤 亜聖 勝又 裕斗 加藤 晋 庄司 匡宏 ケネス・盛・マッケルウェイン
- 出版者
- 国立大学法人 東京大学社会科学研究所
- 雑誌
- 社会科学研究 (ISSN:03873307)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.2, pp.95-125, 2022-03-08 (Released:2022-04-28)
11 0 0 0 OA 翻訳伸長ダイナミクスと新生鎖フォールディング
- 著者
- 田口 英樹 茶谷 悠平 丹羽 達也
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.3, pp.137-140, 2019 (Released:2019-05-25)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1
Proteins do not instantaneously finish the synthesis and folding into functioning products, but experience the nascent peptidyl-tRNAs, defined as “nascent chains”, during the translation. So far, nascent chains are regarded as transient intermediates during the protein synthesis. However, recent advances have revealed that nascent chains are directly involved in a variety of cellular processes including self-maturation and the quality control system of protein and mRNA. In this review, we summarize recent progress on noncanonical translation dynamics and co-translational folding.
11 0 0 0 OA 史料紹介『看聞日記』現代語訳(二四)
- 著者
- 薗部 寿樹
- 出版者
- 山形県立米沢女子短期大学附属生活文化研究所
- 雑誌
- 山形県立米沢女子短期大学附属生活文化研究所報告 = REPORTS OF THE INSTITUTE FOR CULTURE IN LIFE (ISSN:0386636X)
- 巻号頁・発行日
- no.49, pp.67-80, 2022-03-15
11 0 0 0 OA 4. 撮像面位相差センサを用いたカメラ
- 著者
- 大貫 一朗
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.3, pp.203-207, 2014 (Released:2016-04-27)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 1 2