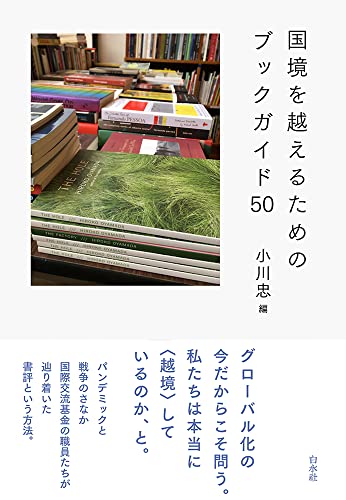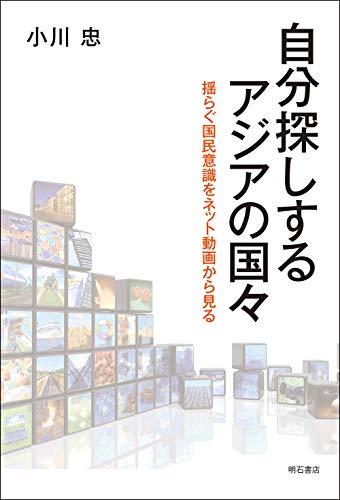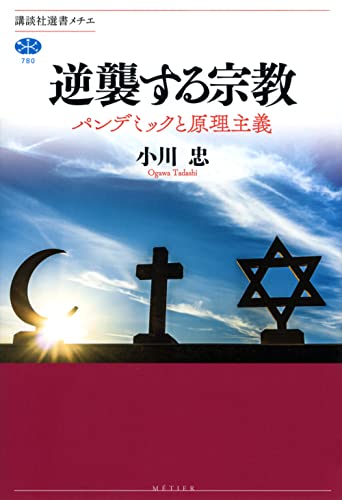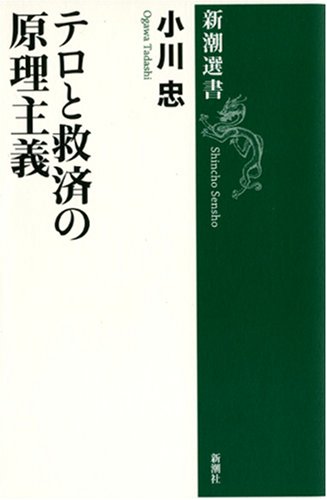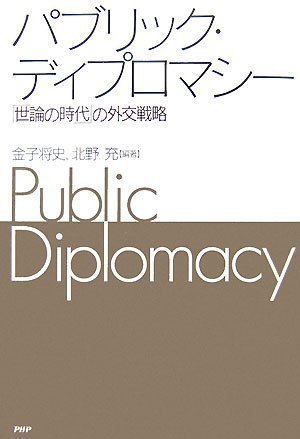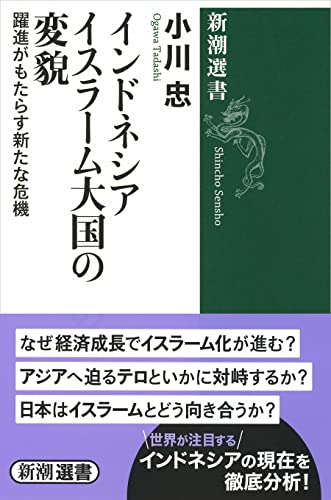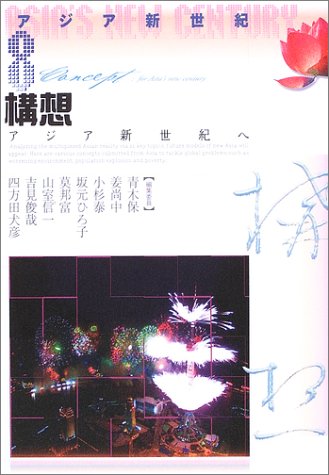1 0 0 0 OA 英語初学者への書字指導に関する一考察-bとdに焦点をあてて-
- 著者
- 鹿住 尚子 KAZUMI Naoko
- 雑誌
- 和洋女子大学英文学会誌 = Language and Literature of Wayo Women's University (ISSN:02893940)
- 巻号頁・発行日
- no.57, pp.1-17, 2022-03-31
アルファベットの書字指導はひらがなの書字指導と比較するとその方法が指導者に委ねれている現状がある。本稿では小学校国語科・英語科、及び英語を母語とする国での手書き文字指導の実態を明らかにした。さらに、ジョリーフォニックスの手法を援用したbとdの文字指導を行い、児童の反応や事前・事後の文字の比較を行った。アルファベット文字指導にはひらがな指導と同様の丁寧な指導が望まれる。
1 0 0 0 OA 呼気筋トレーニングが随意的咳嗽力に及ぼす即時効果
- 著者
- 小畑 大志 横川 正美 中川 敬夫
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.6, pp.793-796, 2017 (Released:2017-12-20)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 2 2
〔目的〕低強度の呼気筋トレーニング(EMT)が,随意的咳嗽力の指標である咳嗽時最大呼気流量(CPF)に及ぼす即時効果を検討すること.〔対象と方法〕呼吸器,循環器の既往,喫煙歴のない健常男性21名を対象とした.背臥位にてEMTを実施し,その直後のCPFを測定した.EMTは最大呼気圧の15%の抵抗で,実施回数は10,20,30回の3条件とした.〔結果〕実施回数に関わらず,EMTを実施することで直後のCPFは向上した.10回と比較して20回および30回条件ではより強い疲労感がみられた.〔結語〕最大呼気圧の15%負荷にて10回EMTを行うことで,疲労感が少なく,かつCPFを増強させることが示唆された.
1 0 0 0 OA 咽頭感覚障害のリハビリテーション医学・医療
- 著者
- 大國 生幸 海老原 覚
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.12, pp.1391-1398, 2021-12-18 (Released:2022-04-13)
- 参考文献数
- 45
摂食嚥下は,食塊を口腔から咽頭・食道を経て胃まで送る一連の過程で,通常5期に分けられる.中でも咽頭期は嚥下反射が中心となり,咽頭感覚は摂食嚥下において重要な役割を担う.咽頭感覚に関連する神経学的または構造的な欠陥は摂食嚥下に影響を及ぼすため,咽頭感覚障害はさまざまな疾患に不随する摂食嚥下障害の要因の1つとなる.咽頭感覚障害のリハビリテーション医療は,実際に食物を用いて行う直接訓練と,食物を用いない間接訓練とに分けられる.近年,感覚および運動経路の刺激に基づく新しい治療法として,刺激療法が着目されている.リハビリテーション医療は,個々の患者の状態や摂食嚥下機能に基づいて行う必要があり,多職種からなるチームによる治療が推奨される.
- 著者
- 栗山 孝祐 原 善一郎
- 出版者
- システム監査学会
- 雑誌
- システム監査 (ISSN:09147446)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.107-116, 2017 (Released:2023-04-07)
- 参考文献数
- 10
2015 年9 月に改正個人情報保護法が成立・公布され、2017 年5 月に全面施行された。個人情報の保有件数の条件が撤廃され、全企業が改正個人情報保護法の適用対象になる。しかし、2017 年3 月時点では改正個人情報保護法への対応が進んでいない状況であった。そこで、システム開発の上流工程の中心である要件定義工程で実施すべきプロセスを研究することにした。本論文では、個人情報保護要件検討シートを作り、改正法への対応漏れを防いだ。実践での使用として、企業2 社の実際の要件定義工程の組織点検に着目し、既存のプロセスに組込みを行った。さらに、組織点検が適切に行われていることを確認するシステム監査で実施すべき10 個のプロセスおよび主な監査項目一覧を具体的に整理した。これから改正個人情報保護法をシステム開発段階で適用される企業の参考になろう。
1 0 0 0 OA シチズン クオーツ クリストロン
- 著者
- シチズン時計株式会社
- 出版者
- 一般社団法人 日本時計学会
- 雑誌
- 日本時計学会誌 (ISSN:00290416)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, pp.88-90, 1975-08-10 (Released:2017-11-09)
- 著者
- 福永 晃太 圓﨑 将大 小味 昌憲 東 美菜子 平井 俊範 藤原 康博
- 出版者
- 公益社団法人 日本放射線技術学会
- 雑誌
- 日本放射線技術学会雑誌 (ISSN:03694305)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.7, pp.663-673, 2023 (Released:2023-07-20)
- 参考文献数
- 29
【目的】Three-dimensional (3D) quantification using an interleaved Look-Locker acquisition sequence with T2 preparation pulse(QALAS)は,緩和時間を測定可能なシーケンスの一つである.3D-QALASは短時間に高い空間分解能で撮像可能な特徴があるが,3.0 Tにおける3D-QALASの緩和時間の測定精度や従来法とのバイアスは明らかになっていない.本研究の目的は,3.0 Tにおける3D-QALASの緩和時間を従来法と比較し,明らかにすることである.【方法】3D-QALASでファントムのT1値とT2値を測定し,それらの精度を評価した.次に,健常者の脳組織のT1値,T2値,プロトン密度を2D multi-dynamic multi-echo(MDME)と3D-QALASで測定し,それらの差を評価した.【結果】ファントムによる評価において,3D-QALASのT1値は,inversion recovery spin-echoのT1値より平均8.3%延長した.3D-QALASのT2値は,multi-echo spin-echoのT2値より平均18.4%短縮した.生体による評価では,3D-QALASの平均のT1値とT2値とPDは,2D-MDMEと比較して,それぞれ5.3%延長,9.6%短縮,7.0%増加した.【結語】3.0 Tの3D-QALASはT1値が1000 ms未満では測定精度が高いが,それ以上では過大評価される.また,3D-QALASのT2値は過小評価され,T2値が長いほどその傾向は大きくなる.
1 0 0 0 OA 人工股関節置換術後に腸腰筋インピンジメントをきたした1例
- 著者
- 石原 昌人 仲宗根 哲 平良 啓之 山中 理菜 親川 知 松田 英敏 東 千夏 神谷 武志 金谷 文則
- 出版者
- 西日本整形・災害外科学会
- 雑誌
- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.4, pp.620-623, 2019-09-25 (Released:2019-12-17)
- 参考文献数
- 6
人工股関節置換術(THA)後の腸腰筋インピンジメントに対して腱切離を行い改善した1例を報告する.【症例】62歳女性.左変形性股関節症に対し左THAが行われた.術後より左股関節自動屈曲時の鼠径部痛を認めていた.歩行は可能であり鎮痛薬内服で経過観察を行っていたが,症状の改善がなく術後6ヵ月時に当院を紹介され受診した.左股関節の自動屈曲は疼痛のため不能で,血液検査で炎症反応上昇はなく,単純X線像でTHAのゆるみは見られなかったが,カップの前方突出を認め,腸腰筋インピンジメントと診断した.キシロカインテストで疼痛は消失し術後8ヵ月で手術を行った.腸腰筋は緊張しカップの前縁とのインピンジメントを認め腸腰筋腱切離を行った.術当日より疼痛は改善し術後3日目に独歩で退院した.術後2ヵ月でADL制限なく職場復帰した.腸腰筋インピンジメントの観血的治療として腱切離は低侵襲で有効な治療法と思われた.
- 著者
- 有谷 航 中山 寛介
- 出版者
- 公益社団法人 日本放射線技術学会
- 雑誌
- 日本放射線技術学会雑誌 (ISSN:03694305)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.7, pp.708-716, 2023 (Released:2023-07-20)
- 参考文献数
- 16
Magnetic resonance cholangiopancreatography(MRCP)は低侵襲に胆汁や膵液を直接画像化できる方法であり,Heavily T2強調3Dマルチスライス法では自由呼吸下で呼吸同期撮像を行うことで高画質な膵胆管の全体像が得られる.1回のデータ収集時間(echo train duration: ETD)を被検者の呼吸状態に合わせることで撮像時間が調整できるが,高速スピンエコー法におけるETDの変化は,画像コントラストや空間分解能に影響を与える.本研究では,ETDが画質に及ぼす影響について,ファントムを用いて評価した.いずれの条件でも模擬膵臓と模擬膵管は高い画像コントラストを示した.また,ETD延長に伴い空間分解能が劣化したが,視覚評価では有意差が認められなかった.より臨床的な条件では一部で視覚的に有意な差が認められ,phase partial Fourier(PPF)による影響が考えられた.PPFを使用せずに被検者の呼吸状態に応じてETDを変化させることで,画質を損なうことなく被写体の動きを抑えた最適な撮像時間での画像取得が可能になると考えられた.
1 0 0 0 OA 地下集塊氷の掘削とコア解析(Ⅰ)
- 著者
- 藤野 和夫 堀口 薫 新堀 邦夫 加藤 喜久雄
- 出版者
- 北海道大学低温科学研究所
- 雑誌
- 低温科學. 物理篇 (ISSN:04393538)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.143-150, 1983-03-22
1 0 0 0 国境を越えるためのブックガイド50
1 0 0 0 自分探しするアジアの国々 : 揺らぐ国民意識をネット動画から見る
1 0 0 0 逆襲する宗教 : パンデミックと原理主義
1 0 0 0 テロと救済の原理主義
1 0 0 0 パブリック・ディプロマシー : 「世論の時代」の外交戦略
- 著者
- 金子将史 北野充編著 小川忠 [ほか] 著
- 出版者
- PHP研究所
- 巻号頁・発行日
- 2007
1 0 0 0 インドネシアイスラーム大国の変貌 : 躍進がもたらす新たな危機
1 0 0 0 構想 : アジア新世紀へ
- 著者
- 青木保 [ほか] 編集委員
- 出版者
- 岩波書店
- 巻号頁・発行日
- 2003
1 0 0 0 OA 指導における「道徳主義」に関する一考察
- 著者
- 白石 陽一 Yoichi Shiraishi
- 出版者
- 熊本大学教育学部附属教育実践総合センター
- 雑誌
- 熊本大学教育実践研究
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.17-23, 2009-02-27
思想史、とくに近代民衆史を学ぶとは、どういうことなのか。厳格な学び方としては、厳密な実証性をもとに、近代の民衆の歴史と現代の大衆の実態の関連を探りあてることだろう。また、いわゆる「歴史から学ぶ」といわれる際の学び方として、現在の問題を根本的に考えるための発想法を得るために、思想史を学ぶという態度もありえると思うのである。このような活用方法は歴史学の学問的成果が市民的教養になるということも意味すると考える。本論は、指導が「道徳主義」に陥らないためにこそ「通俗道徳」に学ぶという方法態度にたっているのであり、教育実践を省察するヒントを得ようとするものである。
1 0 0 0 OA 人工妊娠中絶における看護のエスノグラフィー ―初期中絶における看護に焦点をあてて―
- 著者
- 勝又 里織
- 出版者
- 公益社団法人 日本看護科学学会
- 雑誌
- 日本看護科学会誌 (ISSN:02875330)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.37-45, 2018 (Released:2018-08-02)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1 1
目的:本研究は,人工妊娠中絶の看護において共通する行動パターンやルールを記述することを目的とした.方法:エスノグラフィーを用いた.一産婦人科診療所での約1年間の参加観察によるフィールドノーツと,15名の看護師へのインタビューからデータを収集し,初期中絶時の看護に共通する行動パターンとルールを分析し,記述した.結果:〈女性自身の迷いを感じる〉,〈周囲からの圧力を疑う〉,〈女性の判断能力を危ぶむ〉場合は,【女性の意思決定を疑う】.そうでない限り,看護師は『関わらない看護』をする.『関わらない看護』は,【滞りなく進める】ことおよび【嫌な思いをさせない】ことが共通する行動パターンとなっていた.看護師は,〈予定通りに〉,〈事務的に進め〉,女性と〈距離をおく〉,〈責めない〉,〈傷つけない〉,〈立ち入らない〉,〈深入りしない〉,〈人目を避ける〉,〈身体の不快や苦痛を感じ取る〉といった看護を提供していた.
1 0 0 0 OA 研究倫理審査の質の向上と効率化について—台湾の取り組みから学ぶ—
- 著者
- 安井 涼子 山本 洋一
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床薬理学会
- 雑誌
- 臨床薬理 (ISSN:03881601)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.61-68, 2018-03-31 (Released:2018-04-21)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 2 1
In Japan, the centralization of institutional review boards (IRBs) has been considered with the objectives to standardize the quality of the review process for multicenter studies and to facilitate efficient and speedy implementation of clinical trials and research. Therefore, we visited some core facilities in Taiwan to observe the IRB meetings for clinical studies, and to exchange ideas with staff of the IRB secretariats. Furthermore, we researched the pioneering review mechanisms for multicenter, sponsor-initiated clinical trials in Taiwan. In Taiwan, the Joint IRB (J-IRB: a type of centralized review system) was established in 1997. This review system contributed to improve the quality of ethical reviews in the country. However, because the J-IRB was not fully government-initiated, many co-operating sites gradually started to conduct their own reviews, and this tendency caused a decline in the efficacy of the J-IRB. Following this, the Taiwanese government enacted a law called the Human Subjects Research Act in 2011. Moreover, the government also started the Central IRB (C-IRB) system in 2013, which is a central-local hybrid type of ethical review system for multicenter clinical trials. The establishment of the C-IRB system increased the number of sponsor-initiated clinical trials. The new Human Subjects Research Act allowed each site to develop appropriate organizational structures, and thus maintained the high quality of clinical studies, regardless of whether they were sponsor-initiated or investigator-initiated studies. Considering the future Japanese goals to conduct ethical reviews and to organize the operational structures of medical facilities, we identified many constructive ideas based on the Taiwanese challenges in past decades.