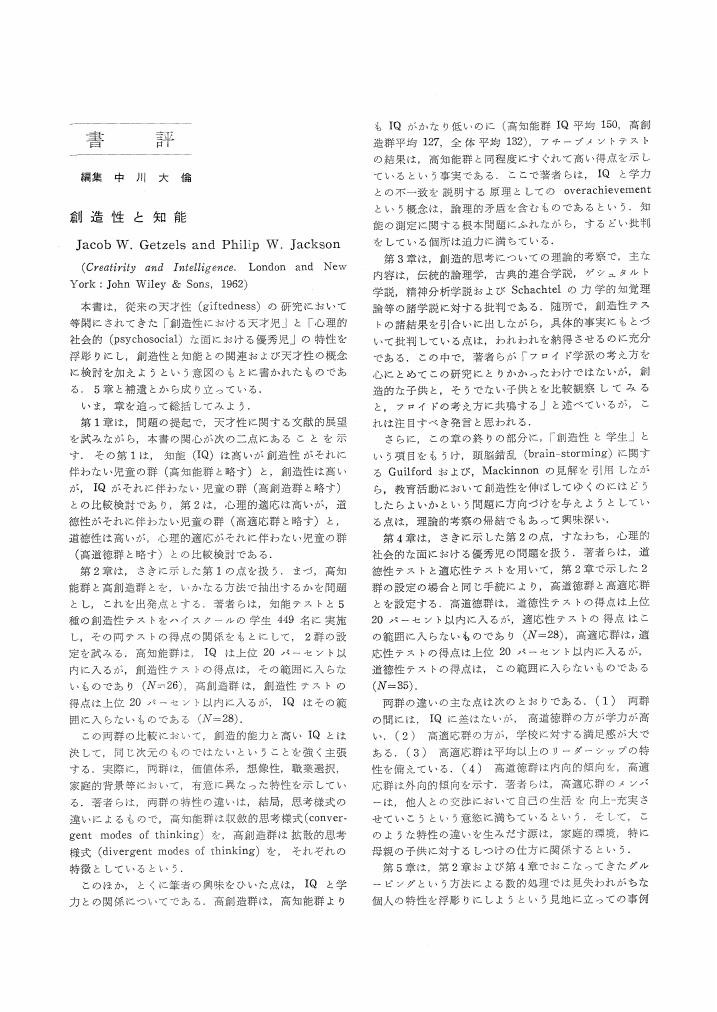1 0 0 0 OA 移動時間を用いた都市圏における自然へのアクセシビリティ評価
- 著者
- 森下 英治 原科 幸彦
- 出版者
- Geographic Information Systems Association
- 雑誌
- GIS-理論と応用 (ISSN:13405381)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.131-139, 1994-03-31 (Released:2009-05-29)
- 参考文献数
- 5
This study aims to evaluate the accessibility to the natural environments of residential environment evaluation in Utsunomiya City. For the purpose, the evaluation functions which use multiple regression analy-sis with residents'evacuation of accessibility as the criterion variable and the traveling time to the destinations as explanatory variables were developed using GIS.As the result, compared with the case which the air distance was used as explanatory variables, the coefficient of determination becomes more than two times. And this result shows that traveling time is an effective factor and GIS is useful tool for this kinds of study.
1 0 0 0 OA 古代インド下層カーストに關する若干の考察
- 著者
- 藤 謙敬
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.486-491, 1965-03-31 (Released:2010-03-09)
- 著者
- 表 英彦 荒井 博史 高橋 典子 勝浦 秀則 鈴木 幸太郎 久保 直樹
- 出版者
- 公益社団法人 日本放射線技術学会
- 雑誌
- 日本放射線技術学会雑誌 (ISSN:03694305)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.10, pp.1525, 1996-10-20 (Released:2017-06-29)
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 海上長距離無線LANの通信安定性の評価
- 著者
- 山口 建太 升屋 正人
- 出版者
- 電気・情報関係学会九州支部連合大会委員会
- 雑誌
- 電気関係学会九州支部連合大会講演論文集 平成20年度電気関係学会九州支部連合大会(第61回連合大会)講演論文集
- 巻号頁・発行日
- pp.598, 2008 (Released:2010-04-01)
ブロードバンド情報基盤としての有効性を検証するため、鹿児島県十島村の悪石島-諏訪之瀬島間19.0km、諏訪之瀬島-平島間17.9kmの二区間に、IEEE802.11g規格に準拠した無線LAN機器およびパラボラアンテナを設置し、長期にわたり通信安定性の評価を行った。 具体的にはすべての機器について、受信電解強度の1分おきに計測し、潮位、風力などの環境要因が、無線LAN通信にどのような影響を与えるのかについて調べた。その結果、海面反射によるフェージングが影響していると考えられる顕著な受信電解強度の低下が見られた。
1 0 0 0 OA 低濃度トリチウムチミジンによる放射線適応応答誘導の検討
- 著者
- 村田 弘貴 藤井 伸之 田内 広 立花 章
- 出版者
- 一般社団法人 日本放射線影響学会
- 雑誌
- 日本放射線影響学会大会講演要旨集 日本放射線影響学会第54回大会
- 巻号頁・発行日
- pp.232, 2011 (Released:2011-12-20)
細胞にあらかじめ低線量の放射線を照射すると、その後の高線量放射線による生物影響を低減する現象を放射線適応応答という。この現象は、ヒトリンパ球を低濃度トリチウムチミジンで処理すると、その後の高線量X線による染色体異常頻度が低下するというWolffらの報告によって初めて示された。その後、トリチウムチミジン以外に低線量X線や低濃度過酸化水素などによる前処理でも同様の現象が観察され、またヒト以外の生物種の細胞や個体でも見られることが明らかにされた。これらのことから放射線適応応答は生物の持つ基本的応答機構であると考えられるが、その分子機構は明らかになっていない。我々はこれまでにマウスm5S細胞を用いて低濃度過酸化水素処理による適応応答誘導について検討し、protein kinase Cα(PKCα)が関与することを明らかにした。本研究では、DNA損傷と適応応答誘導との関連を明らかにするために、低濃度トリチウムチミジン処理による放射線適応応答誘導についてm5S細胞を用いて検討した。まず、Wolffらの実験条件に従い、増殖期のm5S細胞に3.7 kBq/mlのトリチウムチミジンを加えて細胞に取り込ませ、その後confluentにして接触阻止により細胞の増殖を止めた状態を保って、5 Gy X線を照射し、微小核形成を指標として放射線適応応答を解析した。その結果、m5S細胞でも低濃度トリチウムチミジンの前処理により放射線適応応答が誘導されることを確認した。さらに、トリチウムチミジンの至適濃度を検討するために、0.37 kBq/ml及び37 kBq/mlの濃度のトリチウムチミジン前処理も行ったが、3.7 kBq/mlによる前処理が最も効率よく放射線適応応答を誘導した。トリチウムチミジンの至適濃度や処理時間に加えてPKCαの関与についても報告する予定である。
- 著者
- 加藤 貞武 倉田 邦夫 杉沢 慶彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本アイソトープ協会
- 雑誌
- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.4, pp.315-318, 1965-07-15 (Released:2010-07-21)
- 参考文献数
- 5
99Moを親核種として得られる99mTcは, その半減期およびガンマ線エネルギーから, すぐれた生体内診断用核種の1つと考えられるが, 半減期の関係から, 使用直前に製剤化し, 試験されなければならない。本報では, まず99Mo-99mTc generatorの取扱いについて述べ, ついでTcO-4液およびTc2S7コロイド液の注射用製剤の製法および試験法について報告する。これらを実験動物に静注して体内分布を経時的に追跡した結果, TCO-4液は胃に, Tc2S7コロイドは肝に選択的に集積された。
- 著者
- 藤原 一肇 守口 剛
- 出版者
- 日本商業学会
- 雑誌
- 流通研究 (ISSN:13459015)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.1-15, 2021 (Released:2021-06-30)
- 参考文献数
- 113
- 被引用文献数
- 2
本研究の目的は,ラグジュアリー・ブランドの多次元的価値(名声/エリート主義/独創性/洗練性/情趣)が購買意図を形成するメカニズムに対する,財の観察可能性(他者の視線に晒される可能性)の影響を解明することである。検証の結果,相対的に「情趣」は観察可能性の高い財,「名声」は観察可能性の低い財において,購買意図の形成に顕著な正の影響を与えることが明らかになった。そして,観察可能性の高低に関係なく,総じて「独創性」が顕著な正の影響を与え,「エリート主義」が顕著な負の影響を与えることなどが明らかになった。
1 0 0 0 OA グルタミン酸とカルシウムシグナルを介した傷害応答
- 著者
- 豊田 正嗣
- 出版者
- 一般社団法人 植物化学調節学会
- 雑誌
- 植物の生長調節 (ISSN:13465406)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.146-151, 2018 (Released:2018-12-28)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1
Unlike animals, plants do not possess the central nervous system, but they can immediately sense local environmental stresses, such as mechanical wounding and herbivore attack, propagate this information throughout the plant body and activate systemic defence responses in distant organs. However, the molecular machinery underlying such rapid sensory and systemic signal transduction is poorly understood. Using genetically-encoded calcium ion (Ca2+) and glutamic acid (Glu) indicators and a highly-sensitive wide-field fluorescence microscope, we have visualized the plant-wide spatial and temporal dynamics of cytosolic Ca2+ and apoplastic Glu levels in response to wounding in Arabidopsis leaves. Here, we show that glutamate is a wound signal in plants that is leaked to the apoplastic region from damaged cells/tissues. The GLUTAMATE RECEPTOR LIKE (GLR) family of Ca2+-permeable channels act as sensors that convert this damage-associated signal into an increase in cytosolic Ca2+ concentration. This Ca2+ signal propagates throughout the entire plant via the plant-specific tissue/structure, phloem and plasmodesmata, and preemptively activates resistance responses in the distant undamaged organs.
- 著者
- 今出 政明 張 林 飯島 高志 福山 誠司 横川 清志
- 出版者
- 公益社団法人 日本金属学会
- 雑誌
- 日本金属学会誌 (ISSN:00214876)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.4, pp.245-250, 2009 (Released:2009-04-01)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 12 11
The internal reversible hydrogen embrittlement (IRHE) of the thermally hydrogen-charged iron-based superalloy of SUH660 and austenitic stainless steels of SUS 304, 316, 316L, 316LN and 310S was investigated in the temperature range from 300K to 80 K. Hydrogen showed a marked effect on the tensile properties of SUH660 and SUS 304, a minimal effect on those of SUS316 and SUS316LN, and no effect on those of SUS 310S and 316L at room temperature. Although the IRHE of SUH660 decreased with decreasing temperature, those of SUS304, 316 and 316LN increased with decreasing temperature, reached a maximum at around 200 K, and decreased rapidly with decreasing temperature down to 80 K. It was observed that hydrogen caused transgranular fracture along the slip plane in the iron-based superalloy and brittle transgranular fracture along the strain-induced martensite lath in the austenitic stainless steels, respectively. It was suggested that IRHE of the SUH660 depended on the diffusion of hydrogen, and that IRHE of the austenitic stainless steels from 300 K to the maximum IRHE temperature depended on the transformation of strain-induced martensite and the behavior below the maximum IRHE temperature depended on the diffusion of hydrogen.
1 0 0 0 OA 強皮症の患者に鍼治療の併用が効果的であった一症例
- 著者
- 桜田 恵里 星 慎一郎 形井 秀一
- 出版者
- 公益社団法人 全日本鍼灸学会
- 雑誌
- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.1, pp.77-84, 2011 (Released:2011-06-27)
- 参考文献数
- 20
【目的】強皮症を発症し様々な愁訴を持つ患者に、 医学的治療と併用して9ヵ月間の鍼灸治療を行った結果、 良好な経過が見られたので報告する。 【症例】強皮症と診断された50代の女性。 主訴は顔面部の異常感覚、 口腔内の違和感。 薬物治療を継続するが、 顔面の異常感覚、 口腔内の粘り感が続く。 自律神経の調整を目的に鍼灸治療を行った結果、 顔面部違和感に若干の軽減、 レイノー症状、 KL-6値に改善が見られた。 しかし治療の中断、 再開後、 主訴の変化が乏しいため、 触診を重視した治療法に変更した結果、 主訴に対し、 より効果的であった。 【方法】 主訴の自覚症状の変化、 不眠・レイノー症状の頻度、 薬物の服用量、 血液の変化を見た。 【結果】治療開始後、 不眠・レイノー症状の改善、 KL-6値の正常化、 顔面部異常感覚の軽減等が見られた。 触診を重視した治療法は、 より効果的な結果となった。 口腔内の粘り感は不変であった。 【考察】今回の症例は、 継続していた薬物治療に鍼治療を併用することで、 皮膚の異常感覚、 レイノー症状等の強皮症特有の愁訴が改善した。 これらの変化を患者自身が体感することで、 病そのものや、 薬の副作用に対する不安の軽減に繋がったと推察される。
1 0 0 0 OA 316系ステンレス鋼の高圧水素環境脆化特性におよぼすNiおよびCr量の影響
- 著者
- 藤井 秀樹 大宮 慎一
- 出版者
- 一般社団法人 日本高圧力技術協会
- 雑誌
- 圧力技術 (ISSN:03870154)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.2, pp.85-94, 2009-03-25 (Released:2009-04-27)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 2
To accelerate the construction of hydrogen energy society featuring fuel cell vehicles by enlarging the kinds of materials safely used in hydrogen circumstances in addition to JIS SUS316L, several steels having Ni contents lower than SUS316L and Cr contents equivalent to SUS316L are prepared and their tensile properties in high pressure gaseous hydrogen are investigated at room temperature and -40°C. [Ni]+0. 35[Cr] ([Ni] and [Cr] are their concentrations in mass%) is proposed as an indicator to properly indicate whether hydrogen environmental embrittlement (HEE) occurs or not in45MPa hydrogen gas at both temperatures. HEE is basically related to strain-induced martensite having bcc crystallographic structure. However, there are some steels which do not exhibit any significant HEE although noticeable amount of martensite phase forms. In this case, HEE mainly occurs at the later stage of deformation just before fracture. Steels containing more than 12mass% Ni including SUS316L do not show HEE if there is not serious segregation of alloying elements such as Ni, Cr, Mo. It is also indicated that SUS316 probably do not show HEE if more than 12mass% Ni is contained. Furthermore, steels having Ni content close to 10mass%, which corresponds to the lower limit of the standard of JIS SUS316 and AISI 316L, have considerably higher resistance against HEE compared to SUS304 based steels although HEE occurs at the late stage of deformation. It may be possible for them to be used in high pressure hydrogen circumstances if temperature range at which they are used is fully taken into account and small level of HEE is acceptable.
1 0 0 0 OA 平面特徴を用いた3次元点群データの重ね合わせ手法に関する検討
- 著者
- 北川 悦司
- 雑誌
- 阪南論集.人文自然科学編
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.51-55, 2019-03
1 0 0 0 OA 書評
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.4, pp.217-219, 1964 (Released:2010-07-16)
- 被引用文献数
- 1 1
1 0 0 0 OA カントノ自由論―超越論的自由と実践的自由―
- 著者
- 山下 和也
- 出版者
- 京都大学哲学論叢刊行会
- 雑誌
- 哲学論叢 (ISSN:0914143X)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.13-23, 1994-09-01
In "Kritik der reinen Vernunft" ist das Freiheitsproblem ein wichtiges Thema. Kant leitet in der transzendentalen Dialektik von der Kategorie der Kausalität und der Einheitsfunktion der reinen Vernunft die transzendentale Idee der Freiheit ab und beweist, daß die transzendentale Freiheit und die praktische Freiheit alle beide zwei Momente d.i. die absolute Spontaneität und die Unabhängigkeit von der Naturnotwendigkeit enthalten. Dazu unterscheidet Kant die Erscheinung von dem Ding an sich auf Grund des transzendetalen Idealisums und versucht, die Freiheit dadurch zu retten, daß die Freiheit als dem Ding an sich zugehörig angesehen wird. Für Kant ist die praktische Freiheit eine Beschaffenheit der reinen Vernunft, und er betrachtet die Vernunft als dem Ding an sich ähnlich. Aber, weil er zugleich behauptet, daß die Freiheit der Grund der Imputation ist, muß die praktische Freiheit eine wirkliche Eigenschaft der menschlichen Vernunft sein. Trotzdem betont Kant, daß die Idee der transzendentalen Freiheit keine Beziehung auf irgendein Objekt hat. Also ist es unmöglich, da die Idee der transzendentalen Freiheit, wie Kant sagt, die praktische Freiheit begründet. Kant verwechselt die Idee der transzendentalen Freiheit mit der transzendentalen Freiheit als einer Beschaffenheit des Dings an sich. Ich denke, die verschiedenen Probleme der Freiheitslehre Kants entspringen aus diesem Punkt.
1 0 0 0 だれも知らない日本国の裏帳簿 : 国を滅ぼす利権財政の実態!
1 0 0 0 OA 抗うつ薬を使いこなす
- 著者
- 大坪 天平
- 出版者
- 一般社団法人 日本女性心身医学会
- 雑誌
- 女性心身医学 (ISSN:13452894)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, pp.154-158, 2022 (Released:2022-12-06)
- 参考文献数
- 8
1 0 0 0 OA 大東亜聖戦大碑と私の歴史観
- 著者
- 中田 清康
- 出版者
- 金沢大学経済学部 地域経済ニューズレター編集委員会
- 雑誌
- Cures newsletter = 地域経済ニューズレター (Center for Urban and Regional Studies) (ISSN:09137181)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, pp.2-4, 2008-03-25
大東亜聖戦大碑建立委員会
1 0 0 0 OA 就寝時の「快眠音」が不眠症疑いの労働者への睡眠潜時に与える影響
- 著者
- 中田 ゆかり 柴田 英治 角谷 寛 KADOTANI Hiroshi
- 出版者
- 厚生労働統計協会
- 雑誌
- 厚生の指標 = Journal of Health and Welfare Statistics (ISSN:04526104)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.11, pp.1-7, 2021-09
目的:本研究の目的は,不眠症の疑いのある労働者が就寝時に「快眠音」を聞くことにより,睡眠潜時(寝つくまでの時間)が短縮するのかを検証することである。方法:研究デザインは,個々の研究対象者が「介入群(快眠音)」と「対照群(無音)」をもつランダム化比較試験とした。快眠音システムは音源内蔵スピーカー(ヤマハ社製ISX-80)とベッドマット下生体センサー(EMFIT社製EMFIT-QS)を用いた。日本企業4社の従業員1,185名を対象として事前にアテネ不眠尺度を用いてスクリーニングを行い,531名より回答を得た。不眠症の疑いのある6点以上の162名を抽出し,研究同意・データが得られた42名を対象に分析を行った。データ収集方法は,対象者が自宅に設置した快眠音システムを用いて就寝時にランダムに「快眠音」と「無音」を聞き,それぞれ平日5晩ずつ計10晩の睡眠潜時,睡眠時間,睡眠効率のデータを収集した。睡眠潜時のデータを主要評価項目とし,同様に睡眠時間および睡眠効率のデータを副次評価項目とした。分析方法は,「快眠音」と「無音」での対応のあるt検定を行った。結果:睡眠潜時,睡眠時間,睡眠効率すべての評価項目において「快眠音」と「無音」で有意な差は認められなかった。結論:「快眠音」は不眠症の疑いのある労働者に対する睡眠潜時の短縮効果は得られなかった。
1 0 0 0 OA 葉がなければパンを食べる? : オオタバコガ幼虫の奇妙な食性
- 著者
- 山崎 一夫 高倉 耕一 今井 長兵衛
- 出版者
- THE LEPIDOPTEROLOGICAL SOCIETY OF JAPAN
- 雑誌
- 蝶と蛾 (ISSN:00240974)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.2, pp.173-175, 2010-07-30 (Released:2017-08-10)
- 参考文献数
- 14
オオタバコガの幼虫が大阪市の家屋内でパンを摂食しているところを見出された.この幼虫は偶然に人家,食料品店,あるいはパン製造所のいずれかに侵入し,パンを見つけて摂食にいたったものと考えられる.この幼虫はそのままパンを食餌にして飼育したが,蛹化せずに死亡した.本報告は大蛾類が加工穀物食品を加害した稀な報告例であり,本種のパン食の記録としては2例目である.本種は葉以外に花や果実などを好んで摂食する習性があり,鱗翅目幼虫を捕食することも知られている.本種において稀にパン食が見出されるのは,多食性とタンパク質を多く含む食物を選好する習性が原因なのかもしれない.