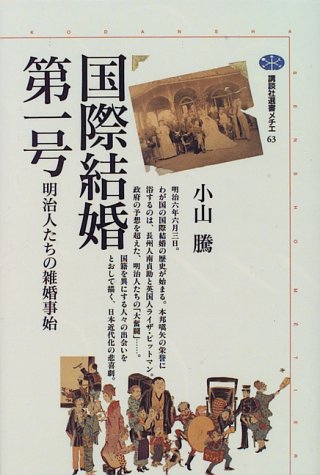- 著者
- 肥田 格
- 出版者
- Hokkaido University
- 巻号頁・発行日
- 2019-03-25
北海道大学. 博士(情報科学)
1 0 0 0 OA 三重県名張市旧町の簗瀬水路
- 著者
- 田中 和幸 南出 博豊
- 出版者
- 近畿大学工業高等専門学校
- 雑誌
- 近畿大学工業高等専門学校研究紀要 = Research reports Kindai University Technical College (ISSN:18824374)
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.89-93, 2021-03-15
“Yanase Suiro” waterway runs through the old town in Nabari City, Mie Prefecture. The total length of it was 15 km in the old cadastral map in 1889. We conducted a field survey and confirmed that “Yanase Suiro” was left 9 km. The 2 km waterway is an underdrain, but the 7 km waterway could be divided into patterns along the road, in the fields, between houses, on the courtyards, and inside the house. We believe that the variety of waterways in the old town of Nabari city can be useful for future town development.
1 0 0 0 OA 日本マンガ学会第7回大会
- 著者
- 木内 英太
- 雑誌
- 情報と社会 = Communication & society
- 巻号頁・発行日
- vol.18, 2008-03-15
1 0 0 0 OA 文末モダリティ表現に焦点を当てた大学生レポートの問題――コーパスを用いた実態調査より――
- 著者
- 酒井 晴香 関 玲
- 出版者
- 全国大学国語教育学会
- 雑誌
- 国語科教育 (ISSN:02870479)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, pp.21-29, 2020-09-30 (Released:2020-10-23)
- 参考文献数
- 15
本研究は、大学生のアカデミック・ライティングの運用能力について、レポートの文末モダリティ表現(「と考えられる」等)に焦点を当てて問題を明らかにするものである。文末に出現する推量、蓋然性、証拠性に当たるモダリティ表現を分析対象とし、学術論文と大学生のレポートを収集して作成したコーパスを用いて調査を行った。その結果、1)動詞の形態に関して、学術論文ではラレル形が多く使用される一方、レポートではル、タ、テイル形の使用が多いこと、2)レポートでは漢語動詞のバリエーションが少なく、また学術論文には出現しない「と考察される」が特異的に使用されていること、3)「のではないか+と考える」のようなモダリティ重複表現がレポートに多く出現していることが明らかとなった。さらに、この結果から、学術論文では文末モダリティ表現がより広範な用法で使用されていること、レポートではモダリティ重複表現が定型化している可能性を指摘した。
1 0 0 0 OA 博物館展示における意図と解釈
- 著者
- 金子 淳
- 雑誌
- 桜美林大学研究紀要.社会科学研究 = J. F. Oberlin University Journal of Advanced Research. Social Sciences (ISSN:24362697)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.16-32, 2021-03-24
1 0 0 0 OA アジアに羽ばたけトットちゃん : 現代子ども労働の一考察
- 著者
- 石原 静子
- 出版者
- 和光大学総合文化研究所
- 雑誌
- 東西南北
- 巻号頁・発行日
- vol.1998, pp.102-114, 1998-03-20
- 著者
- 荒垣 恒明
- 出版者
- 和光大学総合文化研究所
- 雑誌
- 東西南北 : 和光大学総合文化研究所年報 = Bulletin of the Wako Institute of Social and Cultural Sciences
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, pp.89-106, 2012-03-19
1 0 0 0 国際結婚第一号 : 明治人たちの雑婚事始
1 0 0 0 OA 人口動態と参院議員定数
- 著者
- 日野 貴之
- 出版者
- 常葉大学教育学部
- 雑誌
- 常葉大学教育学部紀要 = Tokoha University Faculty of Education research review (ISSN:2188434X)
- 巻号頁・発行日
- no.43, pp.287-294, 2023-03
1 0 0 0 OA 日本語における「怒り」表現の認知言語学的研究 ―身体部位による分類―
- 著者
- 湯川 進太郎
- 出版者
- 日本感情心理学会
- 雑誌
- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.Supplement, pp.PS1-14, 2022 (Released:2023-05-19)
- 著者
- 山本 晶友
- 出版者
- 日本感情心理学会
- 雑誌
- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.Supplement, pp.OS1-08, 2022 (Released:2023-05-19)
1 0 0 0 OA 感動を押しつけないで ―心理的リアクタンスと金銭フレーミングが映像への感動に及ぼす影響―
- 著者
- 加藤 樹里
- 出版者
- 日本感情心理学会
- 雑誌
- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.Supplement, pp.PS2-10, 2022 (Released:2023-05-19)
- 著者
- Sanae Matsuyama Yoshitaka Murakami Yukai Lu Toshimasa Sone Yumi Sugawara Ichiro Tsuji
- 出版者
- Japan Epidemiological Association
- 雑誌
- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.10, pp.456-463, 2022-10-05 (Released:2022-10-05)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 1 3
Background: Although social participation has been reported to be associated with significantly lower risks of mortality and disability, to our knowledge, no study has estimated its impact on disability-free life expectancy (DFLE). Therefore, this study aimed to investigate the association between social participation and DFLE in community-dwelling older people.Methods: We analyzed 11-year follow-up data from a cohort study of 11,982 Japanese older adults (age ≥65 years) in 2006. We collected information on the number of social participations using a questionnaire. Using this information, we categorized the participants into four groups. DFLE was defined as the average number of years a person could expect to live without disability. The multistate life table method using a Markov model was employed for calculating DFLE.Results: The results revealed that DFLE according to the number of social participations was 17.8 years (95% confidence interval [CI], 17.3–18.2) for no activities, 20.9 (95% CI, 20.4–21.5) for one activity, 21.5 (95% CI, 20.9–22.0) for two activities, and 22.7 (95% CI, 22.1–23.2) for three activities in men, and 21.8 (95% CI, 21.5–22.2), 25.1 (95% CI, 24.6–25.6), 25.3 (95% CI, 24.7–25.9), and 26.7 years (95% CI, 26.1–27.4), respectively, in women. This difference in DFLE did not change after the participants were stratified for smoking, body mass index, physical activity, and depression.Conclusion: Social participation is associated with longer DFLE among Japanese older people; therefore, encouraging social participation at the population level could increase life-years lived in good health.
1 0 0 0 OA 遺伝子組換えカイコの飼育における生物多様性影響の評価手法の構築
- 著者
- 河本 夏雄 津田 麻衣 岡田 英二 飯塚 哲也 桑原 伸夫 瀬筒 秀樹 田部井 豊
- 出版者
- 社団法人 日本蚕糸学会
- 雑誌
- 蚕糸・昆虫バイオテック (ISSN:18810551)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.2, pp.2_171-2_179, 2014 (Released:2014-11-03)
- 参考文献数
- 20
養蚕業の振興とカイコを用いた新産業創出のため,蛍光を発するなど付加価値の高い絹糸を生産する遺伝子組換えカイコの開発が進められている。遺伝子組換えカイコを養蚕農家で飼育するための第一種使用規程の承認を得るには,生物多様性への影響が高まることがないことを示す必要がある。カイコは本来,野外で自立的に生存・繁殖することはないが,近縁野生種であるクワコとの交雑による影響を考慮することが求められる。養蚕農家でカイコが屋外に出るのは飼育残渣に幼虫が混入する場合であり,それを想定して屋外にカイコを放飼したところ,鳥類やアリ類等による捕食を受けることにより,交雑可能な成虫が生じることがないことが明らかになった。また,遺伝子組換えカイコの行動特性の評価として,幼虫の行動範囲と雌成虫の産卵範囲を調査する手法を開発した。有害物質の産生性については,遺伝子組換え植物での事例に準じた手法を適用してその有効性を示した。以上のことにより,遺伝子組換えカイコの生物多様性影響を評価する手法が構築された。
1 0 0 0 OA 鳥害とのたたかい
- 著者
- N. Y.
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.179-181, 1981 (Released:2008-11-21)
1 0 0 0 OA 王政復古史観と旧藩史観・藩閥史観
- 著者
- 大久保 利謙
- 出版者
- 法政大学史学会
- 雑誌
- 法政史学 = 法政史学 (ISSN:03868893)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.4-24, 1959-10-10
- 著者
- 上野 悠
- 出版者
- 早稲田大学大学院文学研究科
- 雑誌
- 早稲田大学大学院文学研究科紀要 (ISSN:24327344)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, pp.649-651, 2023-03-15
- 著者
- 望月 敏弘
- 出版者
- 東洋英和女学院大学現代史研究所
- 雑誌
- 現代史研究 = Contemporary history research
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.1-20, 2010-03-31
1 0 0 0 OA Kinectの仕組みとナチュラルユーザインタフェース
- 著者
- 西林 孝
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.9, pp.755-759, 2012 (Released:2014-09-01)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 2 3