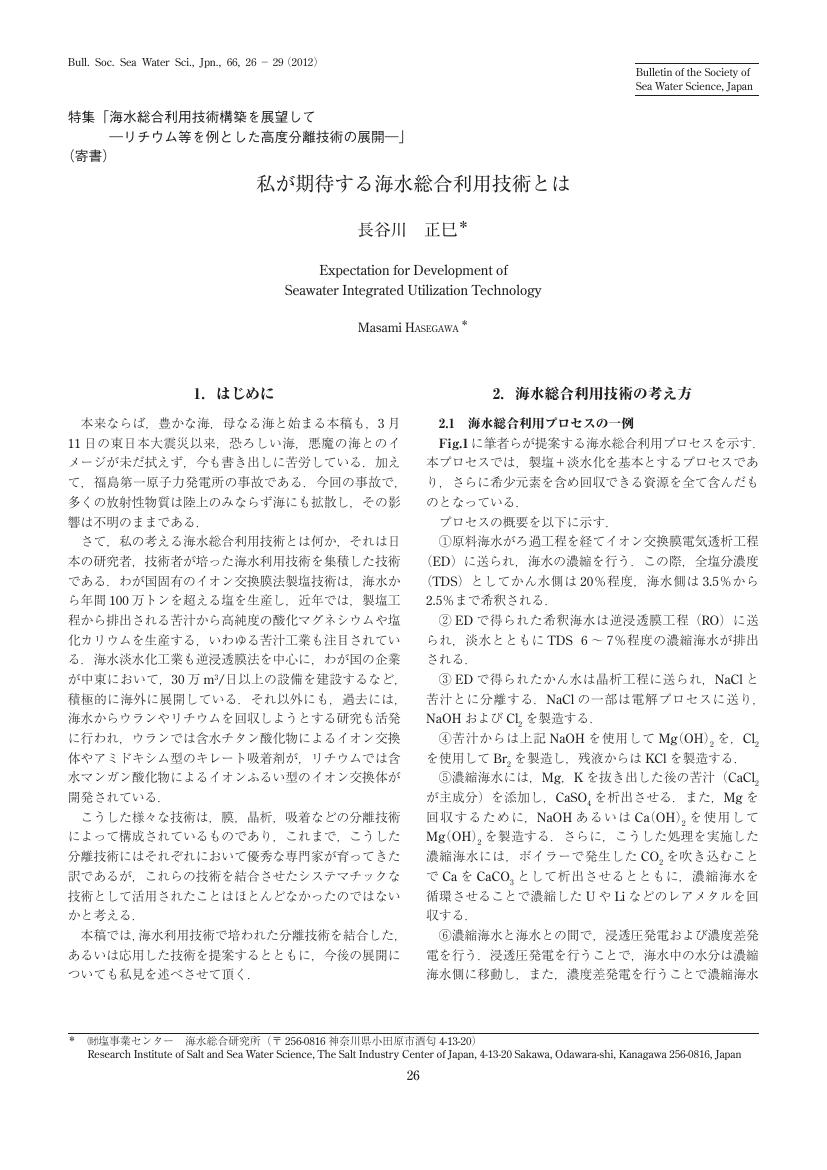1 0 0 0 東南院文書成立過程の研究
1 0 0 0 OA 私が期待する海水総合利用技術とは
- 著者
- 長谷川 正巳
- 出版者
- 日本海水学会
- 雑誌
- 日本海水学会誌 (ISSN:03694550)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.26-29, 2012 (Released:2013-11-01)
- 著者
- 林 美衣 森 直樹
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第35回 (2021) (ISSN:27587347)
- 巻号頁・発行日
- pp.3D1OS12a01, 2021 (Released:2021-06-14)
近年,ファッション分野への人工知能技術の適用が注目されている.本研究は複数の衣服やアクセサリーの画像で構成されたコーディネートを学習した深層学習モデルからコーディネートの出来栄え点を獲得し,それを用いてファッションコーディネートプランを最適化する手法を提案する. 提案手法ではまず学習済みの Bi-LSTM + VSE モデルに手持ちの服を組み合わせたコーディネートを入力し,出来栄え点を獲得する.その点数を元に熱力学的遺伝アルゴリズム (Thermodynamical Genetic Algorithm : TDGA) を用いて複数のコーディネートからなるリスト,つまり着まわしプランを作成した.期間中同じコーディネートを使用してはいけない,3 日以内に同じアイテムを使用してはいけない,期間中一度も使っていないアイテムがあってはならないという制約を課し,多様性を考慮しながら着まわしプランを作成可能とした. 数値実験により,提案手法がユーザが購入を検討しているアイテムが価値があるかを定量的に評価し,どのアイテムを買うべきか推薦するツールとしても活用できることを示す.
1 0 0 0 Geoscientific Setting and Educational Significances of Iheya Island in the Ryukyu Arc, Eastern Asia
- 著者
- 尾方 隆幸 菅森 義晃 小玉 芳敬
- 雑誌
- 日本地球惑星科学連合2023年大会
- 巻号頁・発行日
- 2023-03-24
- 著者
- Eitaro OKUMURA Hiroyuki ONUKI Kunitoshi OTSUKA Shigeki SUNAGA Asashi TANAKA Hiroyuki JIMBO
- 出版者
- The Japan Neurosurgical Society
- 雑誌
- NMC Case Report Journal (ISSN:21884226)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.121-124, 2023-12-31 (Released:2023-05-17)
- 参考文献数
- 8
We present a case of autoimmune-acquired factor XIII deficiency associated with systemic lupus erythematosus, which was diagnosed as a cause of repeated intracerebral hemorrhage. An intracerebral hemorrhage occurred in a 24-year-old female patient. Craniotomy was performed to remove the hematoma, but rebleeding occurred at the same site on days 2 and 11, respectively. Detailed blood tests revealed that factor XIII activity decreased. Although autoimmune-acquired factor XIII deficiency is a very rare disease, it can sometimes be fatal when intracerebral hemorrhage occurs. If there is repeated intracerebral hemorrhage, factor XIII activity should be confirmed.
1 0 0 0 OA 癌患者 (特ニ消化器) ニ於ケル血液酸塩基平衡ノ臨牀的研究
- 著者
- 澤井 英夫
- 出版者
- 財団法人 日本消化器病学会
- 雑誌
- 消化器病学 (ISSN:21851158)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.2, pp.179-210, 1944-03-10 (Released:2011-06-17)
- 参考文献数
- 134
癌患者ニ於ケル血液酸鹽基平衡ト癌腫ノ發生並ビニ發育トノ關係ハ近時著シク興味ヲ喚起シ, 之ニ關スル研究ハ多數發表サレタリ. サレド其ノ意見區々ニシテ未ダ確タル定説ハ無キモ, Moore. R. Balint, R. Reding等多數ノ學者ハ癌患者血液ニ「アルカリ」度増加ヲ認メ, de Raadt, Goldfeder等ハ動物實驗ニ於テ「アルカリ」性環境ノ癌腫ノ發育ヲ促進スルテ報告シ, 略ゝ此ノ方面ニ於ケル主流ヲナシ, 血液中豫備「アルカリ」量ニ關シテハ蜜ロ正常若シクハ輕度ニ減少ストノ説比較的多シ.茲ニ於イテ余ハ癌患者 (特ニ消化器) ノ血液ニ就キ, 水素瓦期電極法ニテ血漿pHヲ測定シ, Van Slykeノ檢壓法ニヨリテ血漿炭酸瓦斯抱容量ヲ求メ, 以テ其ノ血液酸盤基平衡ノ状態及ビ岡田教授ノ創製サレタル癌「エキス」注射ノ之ニ及ボス影響ヲ觀察シ, 次ノ成績ヲ得タリ.先ヅ34名ノ癌患者ニ就キ其ノ血液酸鹽基平衡状態ヲ檢索セルニ血漿pH最高7.74, 最低7.565, 平均7.665ニシテ健常値 (7.637) ニ比シ箸明ニ「アルカリ」側ニアリ.血漿炭酸瓦斯抱容量ハ最高69.218 Vol%, 最低46.347 Vol%, 平均59.072 Vol%ニシテ健常値 (60.415 Vol%) ニ比シ僅カ乍ラ低ク, 即チー般ニ「アルカロージス」ヲ呈シ特ニ瓦斯性ノモノ多キテ認メタリ.癌「エキス」注射ノ癌患者血液酸塩基季衡ニ及ボス影響ニ關シテハ22例ニ就キ癌「エキス」注射約10囘毎ニ観察セル結果17例 (77.3%) ニ於テ「アチドージス」ニ傾クヲ見, 内9例ハ瓦斯性ニシテ臨牀経過比較的良好, 内8例ハ非瓦斯性ニシテ経過概シテ不良ナリ. 爾餘ノ5例ハ (22.7%)「アルカロージス」ニ傾キ内3例ハ非瓦斯性ニシテ経過比較的遷延セリ.次ニ11例ニ就キ癌「エキス」注射ノ及ボス影響ヲ注射前・注射後1, 2, 4, 8時間ト時間的ニ觀察セル結果8例 (72.7%) ニ於テ「アルカロージス」性變化ヲ生ジ, 内6例 (54.5%) ハ瓦斯性ニシテ最モ多ク且其ノ變化ハ敦レモ注射後約2時間ニシテ最高潮ニ達シ8時間ニシテ略ゝ元ニ復セリ.而シテ其ノ變化ノ度ハ注射囘數ノ増加ト共ニ縮小スルヲ認メタリ. 即チ癌「エキス」反復注射ニヨリ患者體内ニハ癌「エキス」ニ對スル或種ノ抵抗力漸次増大スルモノノ如シ.
1 0 0 0 OA 京王プラザホテルにおける重力鉛直勾配の測定
- 著者
- 田島 広一 井筒屋 貞勝
- 出版者
- 日本測地学会
- 雑誌
- 測地学会誌 (ISSN:00380830)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.4, pp.187-190, 1972-08-02 (Released:2011-03-01)
- 参考文献数
- 4
Measurements of vertical gradient of gravity carried out at Keio Plaza Hotel Building which was built recently. This building is in Tokyo (latitude: 35°41.2'E longitude: 139°41.9'N) and its height is about 170 m above the ground. The mean value of the gradient measured was 0.3049 mgal/m ± 0.00032SD. There are four stations where the vertical gradients of gravity have been measured in and around Tokyo. The distribution has a tendency to increase toward north in this area same as the free air anomaly distribution.
1 0 0 0 OA 甲南女子大学に出没するイノシシの食性
- 著者
- 猪俣 伸道
- 出版者
- 甲南女子大学
- 雑誌
- 甲南女子大学研究紀要. 人間科学編 = Studies in human sciences (ISSN:13471228)
- 巻号頁・発行日
- no.43, pp.91-95, 2007-03-20
イノシシは雑食性と言われるが,雑食性の中で何をどのように食べるのかを調査した。人が食べる果物は何でも食べたがレモンは食べなかった。熱帯産の果物も食べた。種子の大きいものは種子を食べたり残したりした。莢付きのエダマメ,オクラとピーマンは食べなかった。ドングリの類は大きさに関係なく皆皮をむいて食べた。根菜類はゴボウを除いてすべて食べたが,ダイコンは時々残した。葉菜類はタケノコとホウレンソウは食べたが,他の物はどれも食べなかった。キノコ類はどれも全く食べなかった。セミの類は皆食べた。
1 0 0 0 OA 短編推理小説の論理構造の分析と推理
1 0 0 0 OA 過飽和水溶液からCo-Mn複合酸化物被膜の生成
- 著者
- 梶田 勉
- 出版者
- The Surface Science Society of Japan
- 雑誌
- 表面科学 (ISSN:03885321)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.5, pp.378-383, 1988-07-10 (Released:2009-11-11)
- 参考文献数
- 8
Co-Mn Conposite oxide films were formed on stainless steel electrodes by polarizing them slightly cathodically in a dilute aqueous solution containing Co2÷ and MnO4- ions. The solutions were supersaturated with sparingly soluble compounds, Co2O3 and MnO2, which were produced as a result of the redox reaction between Co2+ and MnO4- ions. Supersaturation was kept during the film formation. The [Mn] / [Co] ratio of the films varied with the concentrations of Co2+ and MnO4- ions in the solution, the elapsed time from solution preparation, and the electrode potential of stainless steel. This method is applicable to the film formation of sparingly soluble compounds on conductive materials.
1 0 0 0 ヘビ類における帰る捕食への適応と進化の比較研究
調査地域でのシマヘビとヤマカガシの食性は主にカエル類で、共にシュレ-ゲルアオガエルとモリアオガエルが中心であった。このほかに胃内容物からアマガエル、トノサマガエルが少数発見されたほか、ヤマカガシではタゴガエルやヒキガエルを捕食していることもあり、シマヘビに比べてヤマカガシは食べているカエルの種類が多かった。一方、シマヘビはカエル以外にトカゲや小型哺乳類も食していた。捕食していたカモルの大きさを2種のヘビの間で比較したところ、ヤマカガシの方がシマヘビよりも相対的に大きなカエルを食べていた。さらに、呑み込んだ方向を調べたところ、シマヘビは大きなカエルの場合は頭部から呑む傾向が強かったのに対し、ヤマカガシではその様な傾向は見られなかった。しかしながら、ヤマカガシはカエルを後肢から呑み込むときは、両後肢をそろえて呑むという、シマヘビには見られない傾向が観察された。呑み込む方向の違いが、どのような理由から起こっているかを確認するため、飼育下で両者の捕食行動をビデオを用いて詳細に観察し比較した。この結果、シマヘビは大きなカエルを捕食する場合には、最初に咬み付いた場所に関わらず、ほとんど頭部から呑み込んだのに対し、ヤマカガシでは呑み込む方向は最初に咬み付いた場所に大きく依存することがわかった。しかしながら、ヤマカガシは、最初に片方の後肢のみに咬み付いた場合、まず両後肢を呑み込んで続いて胴体へとうつっていき、片方の後肢だけを先に呑んでしまうことはほとんどなかった。このように、ヤマカガシは顎を用いてのカエルの扱い方においてシマヘビよりも器用であることが示唆された。一方、野外での電波発信機を用いた採餌行動の調査は現在も継続中であり、特にヤマカガシについて、さらにデータを追加していく必要がある。
1 0 0 0 一拍脈波特徴量を用いた血圧脈波のフェーズ推定法
1 0 0 0 耐ノイズ性を高めた血圧計測法
1 0 0 0 OA 千葉市稲毛せんげん通り商店街の特徴と商業機能維持に向けての取り組み
- 著者
- 磯部翔 牛垣雄矢
- 出版者
- 東京学芸大学教育実践研究推進本部
- 雑誌
- 東京学芸大学紀要. 人文社会科学系. II (ISSN:24349372)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, pp.109-124, 2021-01-29
- 著者
- Yoshiaki Kaneko Tadashi Nakajima Akihiko Nogami Yasuya Inden Tetsuya Asakawa Itsuro Morishima Akira Mizukami Takashi Iizuka Shuntaro Tamura Chihiro Ota Yasunori Kanzaki Kazuya Nakagawa Makoto Suzuki Masahiko Kurabayashi
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Reports (ISSN:24340790)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.2, pp.46-54, 2019-02-08 (Released:2019-02-08)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 4 4
Background: The existence of atypical fast-slow (F/S) atrioventricular (AV) nodal reentrant tachycardias (NRT) using slow pathway (SP) variants connected to the right atrial (RA) inferolateral (inf) free wall (FW) along the tricuspid annulus (TA), has been neither confirmed nor precisely characterized. Methods and Results: We studied 7 patients (mean age, 48±16 years; 5 men) with F/S-AVNRT with long RP intervals and an earliest atrial activation at the RA inf-FW along the TA (inf-F/S-AVNRT). AV reentrant tachycardia was excluded on observation of the transition zone criteria in all 7 patients. Atrial tachycardia was excluded on the observation of a V-A-V activation sequence after the induction or entrainment of the tachycardia from the right ventricle in all. During the tachycardia, low-frequency, fractionated potentials (LP) preceding the local atrial electrogram were recorded near the site of the earliest atrial activation in 6 patients. Observations of conduction delay and block of the LP during ventricular entrainment or ablation of the tachycardia indicated that LP reflect retrograde activation via the inf-SP. Retrograde SP conduction was interrupted at the site of earliest atrial activation in 3 patients, and in the right posterior septum in 4 patients. Conclusions: inf-F/S-AVNRT are distinct supraventricular tachycardia incorporating an SP variant connected to the RA inf-FW along the TA in the retrograde direction, which were eliminated by ablation.
1 0 0 0 IR 高バックドライバビリティを有するロボット用アクチュエータに関する研究
1 0 0 0 OA 数論から見た跡公式(量子論と古典論,ハミルトン力学系とカオス,研究会報告)
- 著者
- 小山 信也
- 出版者
- 物性研究刊行会
- 雑誌
- 物性研究 (ISSN:05252997)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.4, pp.481-489, 1998-07-20
この論文は国立情報学研究所の電子図書館事業により電子化されました。
- 著者
- 山口 昌也 大塚 裕子
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌教育とコンピュータ(TCE) (ISSN:21884234)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.25-37, 2021-02-22
本論文では,大学生を対象にした話し合い能力向上のためのトレーニングプログラムである「自律型対話プログラム」におけるディスカッション練習とリフレクション活動に観察支援システムFishWatchrを導入する方法を提案する.提案手法では,ビデオ収録したディスカッションをメンバ各自がFishWatchrでビデオアノテーションにより観察したうえで,全メンバの結果を参照しつつ,リフレクションを行う.提案手法を用いた実践は32名の大学生が参加した15コマの集中授業の一環として実施した.実践結果の評価として,(1)フィッシュボウルによる手法と提案手法とを観察とリフレクションの観点から定性的に分析し,提案手法の長所を明らかにしたうえで,(2)受講者へのアンケートとアノテーション結果により,長所が受講者に認識されたか,また,実践で活用されたかどうかを検証する.検証の結果,定性的分析により,提案手法の長所が「アノテーション結果の利用」「自己観察」「実シーンの参照」であることを示した.そして,(a)これらの長所が受講者の93.7%のアンケート結果で指摘されていること,(b)受講者の84.4%が自己観察として自分に対するアノテーションを実際に行っていたこと,(c)アノテーション結果が「他メンバの理解」「シーン理解」「リフレクション時の利便性向上」に活用されうることを確認した.
1 0 0 0 OA スマートフォンを使用した相互評価に見られるアノテーション傾向と問題点の分析
- 著者
- 北村 雅則
- 出版者
- 南山大学
- 雑誌
- アカデミア. 人文・自然科学編 = Academia. Humanities and natural sciences (ISSN:21853282)
- 巻号頁・発行日
- no.25, pp.183-195, 2023-01-31