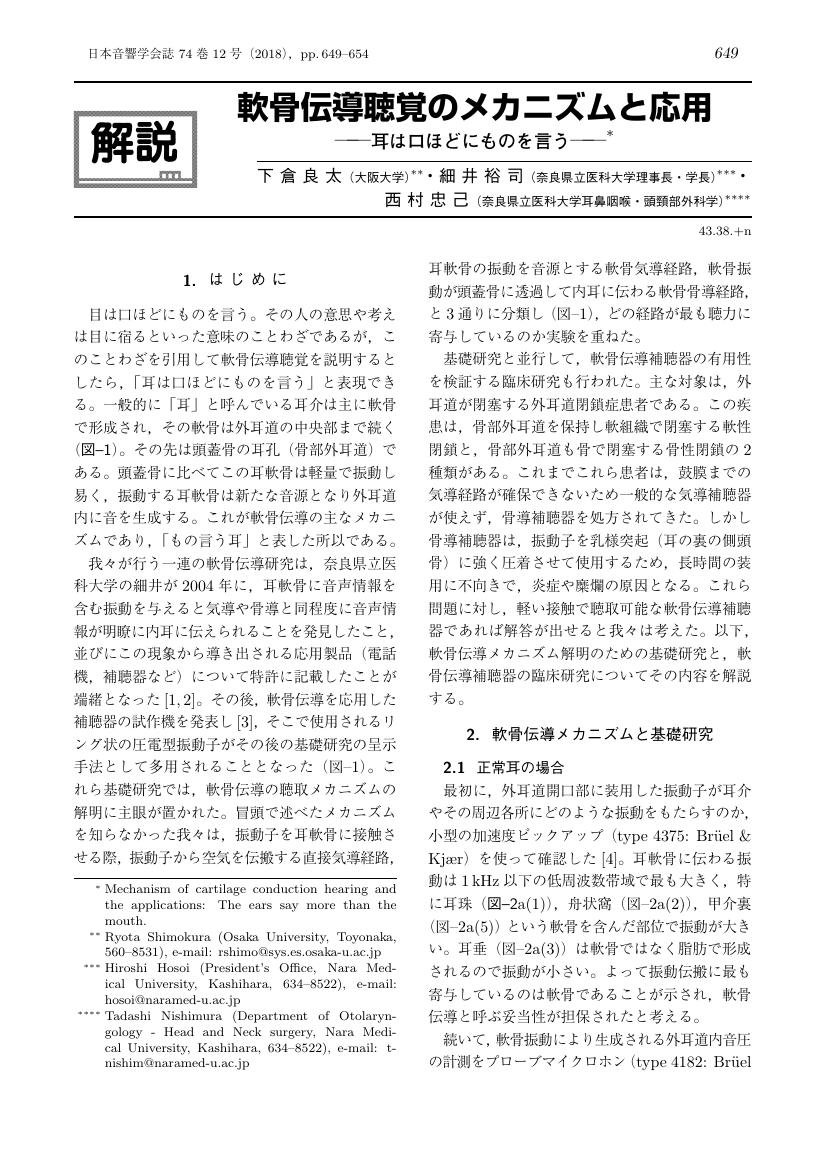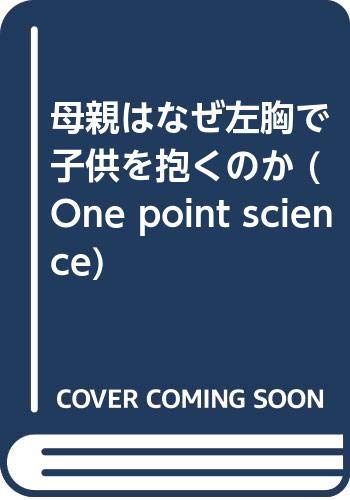1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1922年08月17日, 1922-08-17
1 0 0 0 OA シーリング材の硬化速度の解析
- 著者
- 松井 達郎 小島 裕史 薮 穣
- 出版者
- 公益社団法人 化学工学会
- 雑誌
- 化学工学論文集 (ISSN:0386216X)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.117-123, 1999-01-10 (Released:2009-11-12)
- 参考文献数
- 4
湿気硬化1液型シーリング材の材料設計, 施工設計において硬化速度を把握しておくことは重要である.大気中の湿気によって硬化していく代表的な4種類の素材を用いて硬化速度を実測し, そのモデルについて検討した.擬定常状態を仮定すると硬化時間は硬化厚みの2次関数で表現できる.そのパラメーターを実験により求め, それの物理的意味を考察した.パラメーターは膜素材と硬化機構により決定される.硬化速度を速くするには膜の水分透過速度を速くすれば良くこの相関は実験値と本モデルの計算値と良く一致した.しかし低湿度領域で硬化速度が遅くなる系は反応機構に依る所が大きい.本モデルは逆反応が無視できない硬化機構や, 硬化膜が十分形成されていないで擬定常モデルが成立しない領域では再考を要する.
1 0 0 0 OA 異種材料接着接合
- 著者
- 秋本 雅人
- 出版者
- 一般社団法人 日本接着学会
- 雑誌
- 日本接着学会誌 (ISSN:09164812)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.6, pp.212-218, 2018-06-01 (Released:2018-11-06)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 2
Features of dissimilar materials bonding are surface bonding and several type of adhesives can be used. Bycontrolling thermal expansion coefficient of an adhesive to get middle of dissimilar materials, residual stresscan be reduced, in case of internal stress caused by thermal movement the difference of thermal expansioncoefficient between a metal and a plastic.Also it is possible to reduce a stress which is caused by thermalmovement, by adjusting the elastic modulus of adhesive. We introduce structural and elastic adhesives usedfor dissimilar materials bonding and their characteristics and applications. We also would like to introduce ourSTPE base adhesives which newly developed for the purpose of dissimilar materials bonding. It is known that asea-island structure can be obtained by curing a STPE and an epoxy resin in mixture. The sea-island structureis that the epoxy resin is dispersed in the elastic matrix of STPE. New polymers which shows high strength,toughness and durability has been being developed as a sea matrix by blending and hybridization STPE andacrylic resin having silyl group. The development goals of the adhesive are 15-20MPa strength and more than100% of elongation. And also the curing trigger will be UV, not heating. UV cure can provide very fast cureand on-demand cure which is stably uncured until UV irradiation. We believe that our new technology couldprovide non-heating for application and curing of adhesive in production line in the future.
1 0 0 0 OA ゴムと金属の接着
- 著者
- 芝崎 一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本ゴム協会
- 雑誌
- 日本ゴム協会誌 (ISSN:0029022X)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.10, pp.870-886, 1966-10-15 (Released:2009-10-20)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 4 2
1 0 0 0 OA 幕末京都の政治都市化と寺院の生存戦略 宗派横断的な視点から
- 著者
- 髙橋 秀慧
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.1, pp.127-150, 2021 (Released:2021-09-30)
本稿では、幕末維新期の政局に相対した寺院の動向を「生存戦略」と捉え、妙法院と智積院の陣所化の事例を中心に、西本願寺との比較検討を行い、横断的に考察する。まず、妙法院は、財政難から陣所化を積極的に受け入れたが、智積院は、学問所の機能維持を重視し、陣所化に消極的であった。次に、この事例分析を通じて、諸寺の生存戦略及びその実行プロセスには、近世的社会関係に起因する、寺院(宗派)の性格・機能や内部の「組織力」が強く影響していたことを指摘する。そして妙法院や智積院と比較し、西本願寺は、宗派内で教義的・宗教的権威を補完する独自の制度が整っており、門跡の格式と血統を備えた宗主がリーダーシップを発揮することができたと考えられる。さらに、こうした組織力は、生存戦略を進めるための意志決定や、それを実行に移すプロセスを他宗派よりスムーズなものにしたといえよう。
- 著者
- 本勝 千歳 稲田 真梨江 湯地 健一 戸敷 正浩 黒木 重文 神崎 真哉 鉄村 琢哉
- 出版者
- THE JAPANESE SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE
- 雑誌
- Journal of the Japanese Society for Horticultural Science (ISSN:18823351)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.1, pp.27-34, 2012 (Released:2012-01-20)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 7 9
マンゴーはこれまで偶発実生からの優良系統の選抜によって品種が育成されてきたが,望ましい形質を持った個体同士の交雑による計画的な育種が今後行われる必要がある.しかしながら,マンゴーの花は 1 cm 以下で非常に小さく,また結実率も低いため,人工受粉による十分な数の交雑後代の獲得が困難であった.そこで,日本の独特なマンゴー栽培様式(閉鎖的な温室内での栽培,ミツバチ導入による自然交配)を利用して,‘アーウィン’と‘紅キーツ’の二品種を導入した温室内で,まずミツバチにより自然交配させた後,得られた実生を SSR マーカーによって花粉親を識別することによって,効率的に交雑後代が獲得できるのではないかと考え,その検証を行った.その結果,‘アーウィン’では 239 個体の実生が得られ,そのうち 185 個体で花粉親を判別することができ,他家受粉果は 106 個体,自家受粉果は 79 個体であった.‘紅キーツ’では 20 個体の実生が得られ,そのうち 14 個体で花粉親を判別することができ,他家受粉果は 12 個体,自家受粉果は 2 個体であった.‘アーウィン’実生で判別された花粉親の比について,温室内での両品種の花房数を期待比としてカイ二乗検定を行ったところ,積極的に他家受粉が起こっていることが示された.また‘アーウィン’について判別された花粉親に基づき,花粉親が果実形質に及ぼす影響について調査したところ,‘アーウィン’自家受粉果では Brix 値が有意に高くなったが,果皮色に関するいくつかの値で他家受粉果より低い値となった.
1 0 0 0 OA 舌口唇機能訓練が高齢者の認知機能および舌筋力と口唇閉鎖力に及ぼす影響
- 著者
- 長棹 由起 富田 美穂子 金銅 英二
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年歯科医学会
- 雑誌
- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.3-12, 2022-06-30 (Released:2022-07-25)
- 参考文献数
- 28
目的:多くの高齢者施設では,オーラルフレイルの予防として,舌口唇機能訓練である「パタカラ体操」が実施されている。しかし,舌口唇機能訓練による認知機能や口腔周辺の筋力への効果は明確にされていない。そこで,舌口唇機能訓練が認知機能および舌筋力と口唇閉鎖力に与える効果を明らかにすることを目的とした。 方法:高齢者(66~98歳)60名を舌口唇機能訓練有群(T群)と訓練無群(N群)に分け,T群には舌の出し入れと「パ」「タ」「カ」の各音の5秒間連呼を1日3回実施させた。両群全員に対して,認知機能(MMSE),舌の口腔湿潤度,舌口唇機能(舌口唇運動機能),舌筋力,口唇閉鎖力を3カ月おきに21カ月後まで測定した。各群内の各回の値を比較するとともに,初回時に対する各回の差(MMSE)や変化率(舌の口腔湿潤度,舌口唇運動機能,舌筋力,口唇閉鎖力)を両群で比較検討した。 結果:群内の比較では,MMSEと舌口唇運動機能において各回に有意差は認められなかった。T群の口腔湿潤度は,訓練前に比べ訓練21カ月後,舌筋力と口唇閉鎖力は,訓練12カ月後以降に有意に上昇した。差や変化率を用いた両群の比較では,MMSEは18カ月後以降,舌口唇運動機能は9カ月後と21カ月後に有意差が認められた。T群の舌筋力の変化率は9カ月後以降N群より高く,口唇閉鎖力は21カ月後にN群より高かった。 結論:舌口唇機能訓練の継続は,舌筋力や口唇閉鎖力を上昇させるとともに,認知機能や発音機能の維持に有効であることが示唆された。
1 0 0 0 OA アメリカ大統領選挙のコミュニケーション: オバマは何を語ったか
- 著者
- 市島 清貴
- 出版者
- 新潟経営大学
- 雑誌
- 新潟経営大学紀要 (ISSN:13412604)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.57-72, 2009-03
1 0 0 0 OA 明治丸要目考
- 著者
- 庄司 和民 Kazutami Shoji
- 雑誌
- 東京海洋大学研究報告 (ISSN:21890951)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.1, 2007-03-30
東京商船大学名誉教授
1 0 0 0 形成期中学校教育の展開 : 「淘汰と管理」の諸相
- 著者
- 斉藤利彦 [著]
- 巻号頁・発行日
- 1992
1 0 0 0 OA 軟骨伝導聴覚のメカニズムと応用 ――耳は口ほどにものを言う――
- 著者
- 下倉 良太 細井 裕司 西村 忠己
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.12, pp.649-654, 2018-12-01 (Released:2019-06-01)
- 参考文献数
- 21
1 0 0 0 母親はなぜ左胸で子供を抱くのか
- 著者
- L.ソールクL.I.ガードナー原著 日経サイエンス編集部編 小林登訳
- 出版者
- 日経サイエンス
- 巻号頁・発行日
- 1984
我々はこれまでにParkinson病(PD)の発症要因および増悪因子を検討する中で,PD患者における血漿高ホモシステイン(Hcy)の存在を報告してきた(Yasui et al.,2000).今回高Hcy血症の生じる機序を検討するため,20例の未治療PD患者において,L-dopa内服前後の血漿Hcy及びメチレンテトラヒドロ葉酸還元酵素(MTHFR)遺伝子多型を検討した.PD患者のL-dopa内服前の血漿Hcy値は11.0±4.5μMで健常対照群(n=55)の10.2±5.3μMと有意差を認めなかった.一方,L-dopa内服後の血漿Hcy値は18.8±13.5μMであり,内服前と比較して有意な上昇を認めた.さらに血漿Hcy値をMTHFR遺伝子多型別にみると,C/C型(wild)では10.9±1.6μMから14.6±2.4μMへ,C/T型では10.3±4.0μMから14.1±4.2μMへ,T/T型では11.9±7.1μMから29.3±21.8μMへと上昇し,いずれも有意な上昇であり,特にT/T型では顕著だった(Yasui et al.,Acta Neuro Sca in press).さらに,高Hcy血症は血管障害の危険因子であるため,L-dopa内服PD患者における動脈硬化性変化を頸動脈超音波検査で検討した.PD群(n=100)では健常群に比して有意に中内膜複合体厚が高値であったが,L-dopa非投与PD患者では健常群と有意な差を認めなかった.さらに血漿Hcy値,MTHFR多型を同時に検討したところ,MTHFR 677T/T多型を有するL-dopa投与PD患者においては高Hcy血漿を伴う頸動脈中内膜肥厚が認められた.以上よりPD患者群における頸動脈中内膜肥厚への,L-dopa内服に伴う高Hcy血症の関与が示唆された(Nakaso et al.,J Neurol Sci 2003).また,53例のPD患者においてHcy産生の中間代謝産物s-アデノシルメチオニン(SAM)およびs-アデノシルホモシステイン(SAH)を測定してSAM/SAH比を算出し,臨床型と比較検討した.同比は罹病期間が長くなる程,またwearing off現象を有するPD患者において低値であったが,有意差は無かった.
- 著者
- 江本 弘
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.735, pp.1277-1283, 2017 (Released:2017-05-30)
- 参考文献数
- 9
Having remained in oblivion for three quarters of a century, the reevaluation of Horatio Greenough’s “functionalist” theory during the mid-20th century had its due start in the 1910’s, when literary men like Van Wyck Brooks and Lewis Mumford became alarmed by the increasingly broken pace of a materialistic world, and encouraged the revival of the mid-19th century American spirit, when the harmony of spiritual and material life had been successfully achieved. Through this academic line of inquiry, Greenough’s critical efforts were thus gradually salvaged during the following two decades. Mumford would then function as a central node, spreading information that enhanced Greenough’s popularity and significance not only among foreign architects, but also among domestic scholars from other disciplines.
1 0 0 0 OA L1ノルム最小化を用いた高速3D超音波イメージング
- 著者
- 三村 祐輝 阿部 光 齊藤 直 杉本 俊之 高橋 龍尚 柳田 裕隆
- 出版者
- 公益社団法人 日本生体医工学会
- 雑誌
- 生体医工学 (ISSN:1347443X)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.25-31, 2022-03-10 (Released:2022-05-20)
- 参考文献数
- 30
In ultrasound systems, there is a trade-off between image quality and the number of transducers (elements) placed in the array probe, and to achieve a high resolution, the array probe must be created with additional elements. In 3D/4D echo, a significant number of elements are required compared to 2D echo, because imaging is performed using a two-dimensional array probe. As a result, 3D/4D echo inevitably has the problem of increasing equipment costs. To solve this problem, it is necessary to develop a method to reconstruct images with higher resolution using fewer elements than conventional imaging methods. The L1-norm minimization method has attracted much attention in recent years because of its ability to reconstruct high-resolution images even from incomplete data. In this study, we investigated whether high quality images can be reconstructed by minimizing the L1 norm for an object with an orientation, height, and depth of the imaging area (3D object). We also used image quality evaluation methods (MSE: Mean Squared Error, PSNR: Peak Signal to Noise Ratio, and SSIM: Structural SIMilarity) to quantitatively evaluate the obtained images. The results confirmed that L1-norm minimization is capable of reconstructing high-quality images with high evaluation values in all image quality evaluation methods compared to conventional methods.
- 著者
- 時田 章史
- 出版者
- 公益社団法人 日本ビタミン学会
- 雑誌
- ビタミン (ISSN:0006386X)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.9, pp.477-481, 1998-09-25 (Released:2017-12-26)
- 参考文献数
- 24
1 0 0 0 OA 北米図書館でのRDA実践に関する調査報告
- 著者
- 村上 遥
- 出版者
- 国公私立大学図書館協力委員会
- 雑誌
- 大学図書館研究 (ISSN:03860507)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, pp.53-60, 2014-12-26 (Released:2017-10-31)
北米で新しい目録規則RDAが導入された。本稿では2013年8月に行った米国議会図書館,シカゴ大学図書館,コロンビア大学図書館での調査をもとに,RDA導入後の実態について報告する。調査から,RDAはスムーズに導入されたことが分かった。この理由としては(1)研修の成果,(2)RDAテストによる段階的な知識の普及に加え,(3)メタデータフォーマットが変更されなかったことが挙げられる。したがってMARC21の次のメタデータフォーマット,BIBFRAMEの動向は今後もその動きに注意が必要だ。