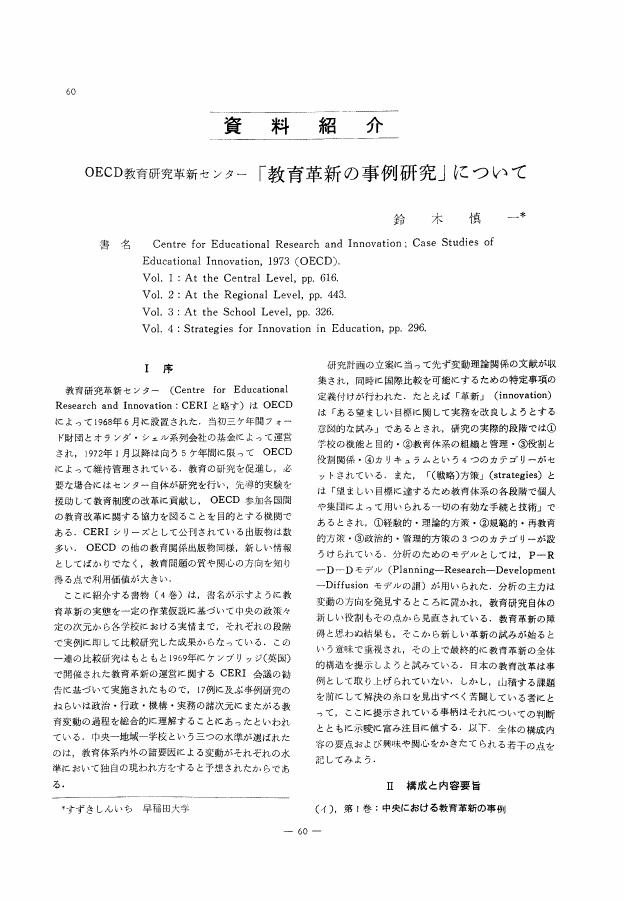1 0 0 0 OA OECD教育研究革新センター「教育革新の事例研究」について
- 著者
- 鈴木 慎一
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.60-63, 1976-03-30 (Released:2009-01-13)
1 0 0 0 OA 視覚表示と表現の記号論 (1) : 視覚記号の原理について
- 著者
- 雨宮 俊彦
- 出版者
- 関西大学社会学部
- 雑誌
- 関西大学社会学部紀要 (ISSN:02876817)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.89-141, 2000-09-25
本論文では,視覚記号の基本的な問題をあつかった。第1部では,視覚記号と聴覚記号の比較,音声言語と絵的記号の比較がなされた。そして,著者は,種々の視覚表示と視覚表現が,マー(1982)のとなえる視覚的情報処理における諸段階の表象と諸側面に関連して位置づけられることを指摘した。第II部では,グッドマン(1968)による記譜性にかんする記号論とデイーコン(1997)によるシンボリック・レファランスの成立についての説が,それぞれ批判的に検討された。最後に著者は,視覚記号における四種類のレファランス(外延指示、共示、例示、表現)のしくみの解明をこころみた。付録では,マンガ(日本のストーリーコミックス)表現が,音声言語表現と絵的表現の融合したものとして分析された。
- 著者
- 山田 雅子
- 出版者
- 一般社団法人 日本色彩学会
- 雑誌
- 日本色彩学会誌 (ISSN:03899357)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.3, 2019-01-01 (Released:2019-01-29)
- 参考文献数
- 31
日本人女子学生による肌の色の言語的表現を探った調査では,男性の方が女性よりも色黒,女性の方が男性よりも色白と表現される傾向が捉えられている(山田, 2017).だが,色みについては不明瞭なままであった. 調査方法に若干の変更を加え,97名の日本人女子学生を対象として新規に調査した結果,男性の方が女性(回答者自身を含む)よりも色黒で黄み寄り,女性(同)の方が男性よりも色白で赤み寄りといった意識が持たれていることが判明した.また,当該傾向は現実に対する評価よりも理想において顕著となることが捉えられた. 更に,肌の色の明るさに関する言語表現の選択パタンには両調査で共通する部分が多分に見られ,日本人女子学生というほぼ同質の対象者ならば一定の反応パタンが安定的に存在することが推察された.同時に,こうした肌の色に対する選択パタンによって,人物の美的評価における肌の要素(色白肌,肌のきめ細かさ)の重視特性が異なる傾向も確認された.
1 0 0 0 OA 初会金剛頂経降三世品の一節について
- 著者
- 白石 真道 酒井 真典
- 出版者
- 密教研究会
- 雑誌
- 密教文化 (ISSN:02869837)
- 巻号頁・発行日
- vol.1958, no.41-42, pp.99-118, 1958-11-10 (Released:2010-03-12)
1 0 0 0 OA 社交要録
- 著者
- ジャパン・マガジーン社 編
- 出版者
- ジャパン・マガジーン社
- 巻号頁・発行日
- vol.大正7年用, 1918
- 著者
- 風野 春樹
- 出版者
- 日本精神神経学会
- 雑誌
- 精神神経学雑誌 = Psychiatria et neurologia Japonica (ISSN:00332658)
- 巻号頁・発行日
- vol.122, no.1, pp.41-46, 2020
1 0 0 0 慶應義塾史跡めぐり(第38回)避暑地軽井沢とA.C.ショー
- 著者
- 大澤 輝嘉
- 出版者
- 慶応義塾
- 雑誌
- 三田評論 (ISSN:1343618X)
- 巻号頁・発行日
- no.1126, pp.58-61, 2009-08
1 0 0 0 OA コミュニティ・プロジェクトの成功要因:プリマス町の事例研究
- 著者
- 佐藤 智子
- 雑誌
- 総合政策 = Journal of policy studies (ISSN:13446347)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.125-138, 2015-03-01
アメリカ合衆国マサチューセッツ州プリマス町は、宮城県七ヶ浜町と20 余年に及ぶ姉妹都市交流を続けている。2011 年3 月11 日に七ヶ浜町が地震と津波により壊滅的な被害に見舞われたという一報が入るや、いち早くプリマス町は支援に乗り出した。最も大きな取り組みは、町議会、プリマスロータリークラブ、そしてプリマス町周辺を拠点とするテレビ局が連携して行った募金活動のテレソンであった。町民が一丸となって取り組んだこのプログラムは、想像以上の成果を上げた。 本論では、テレソンというこのコミュニティ・プロジェクトの成功の要因を、直接的そして物理的な面と、プリマス町そのものの特性という間接的な面から考察した。第一義的には、両町の強固な関係、七ヶ浜町の甚大な被害に寄せるプリマス町民の共感、前述の三機関の精力的、そして広範囲にわたる働きかけなどを指摘することができる。さらに、もっと本質的な要因(遠因)として挙げることができるのは、プリマス町には日頃からボランティア活動などに励む人々が多く、互酬性と信頼性の社会関係資本が十分に蓄積されていたことである。この「資本」が募金活動の成功に大きく寄与している。
1 0 0 0 OA 第二次世界大戦以前の日本のリゾート(外人避暑地)について
- 著者
- 上田 卓爾
- 雑誌
- 名古屋外国語大学現代国際学部紀要 = Journal of the School of Contemporary International Studies, Nagoya University of Foreign Studies
- 巻号頁・発行日
- no.5, pp.89-127, 2009-03
1 0 0 0 IR 第二次世界大戦以前の日本のリゾート(外人避暑地)について
- 著者
- 上田 卓爾
- 雑誌
- 名古屋外国語大学現代国際学部紀要 = Journal of the School of Contemporary International Studies, Nagoya University of Foreign Studies
- 巻号頁・発行日
- no.5, pp.89-127, 2009-03
- 著者
- 増田 金吾
- 出版者
- 美術科教育学会
- 雑誌
- 美術教育学:美術科教育学会誌 (ISSN:0917771X)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.471-483, 2014
本研究は,東京府青山師範学校教諭・赤津隆助と彼の教え子たちとの関連について検討したものである。教え子たちの中でも,特に武井勝雄と倉田三郎の美術教育者としての存在意義は大きい。赤津の指導,並びにそれが彼らに及ぼした影響関係を赤津隆助や教え子たちの執筆した文献等を読み解き,考察した。その結果,赤津は「感じとらせるという方法」により,教え子たちに対し幅広い人格の育成を行い,労苦を惜しまず美術教育界や教育界そして社会に貢献する態度を身をもって教えたこと,また美術教育における思想や方法論として,創造主義を基本としながらも,造形主義と生活主義の美術教育を伝えていたこと,が明らかとなった。
- 著者
- 浅野 智
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究特集号 (ISSN:09196803)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.20-23, 2011-06-01 (Released:2017-11-27)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 OA COVID-19流行と脳卒中
- 著者
- 和田 邦泰 橋本 洋一郎 中島 誠 植田 光晴
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.12, pp.822-839, 2020 (Released:2020-12-26)
- 参考文献数
- 118
- 被引用文献数
- 4
新型コロナウイルス感染症(corona virus disease 2019,以下COVID-19と略記)の流行により,脳卒中診療は大きく変貌しており,受診数減少,受診遅延,recombinant tissue plasminogen activator静注療法や機械的血栓回収療法の施行数減少などが報告されている.既報告ではCOVID-19患者の1.1(0.4~8.6)%程度に脳卒中が合併している.特徴は,虚血性脳卒中,特に潜因性脳梗塞や大血管病変合併例が多く,D-ダイマー高値例が多く,心血管危険因子を持つ患者での発症が多く,転帰不良例が多いことなどである.また本疾患では動脈血栓塞栓症より静脈血栓塞栓症が多く,急性冠症候群より脳卒中発症が多い.安全で有効かつ迅速な治療を完全な感染対策下で行うprotected code strokeが提案されている.
1 0 0 0 IR 中国映画経営の現状に見る政府方策の問題点
- 著者
- 楊 紅雲
- 出版者
- 名古屋外国語大学
- 雑誌
- 名古屋外国語大学外国語学部紀要 (ISSN:13479911)
- 巻号頁・発行日
- no.40, pp.277-300, 2011-02
1 0 0 0 日本人とキリスト教 ー日本人の宗教意識とキリスト教ー
- 著者
- 深津 容伸
- 出版者
- 山梨英和学院 山梨英和大学
- 雑誌
- 山梨英和大学紀要 (ISSN:1348575X)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.1-7, 2013
これまで日本人とキリスト教の主題について、キリスト教に焦点を当て、キリスト教が日本人にどう関わってきたか、今後どう関わるべきかを論じてきた。本論文においては日本人に焦点を当て、日本人の宗教観、宗教意識を探り、それらに対し、キリスト教はどのように関わりえるかを考察したい。日本人は古来から大陸からの影響を多大に受けてきたが、政治的に支配を受けることはなかった。そのためかどうかは定かではないが、原始宗教であるアニミズム・シャーマニズムの宗教意識を、今日に至るまで持ち続けている(外来の宗教である仏教もこれらと同化することにより土着することができた)。その結果、日本人は宗教意識の中には、呪いや汚れに対する恐れが潜在的に存在する。こうした日本人の宗教意識に対し、キリスト教はどのように関わってきたか、また関わりえるかを論じたい。
1 0 0 0 OA 中国映画経営の現状に見る政府方策の問題点
- 著者
- 楊 紅雲
- 雑誌
- 名古屋外国語大学外国語学部紀要 = Journal of School of Foreign Languages, Nagoya University of Foreign Studies
- 巻号頁・発行日
- no.40, pp.277-300, 2011-02
1 0 0 0 連結・免震による墓石の耐震性向上効果の実験的検証
- 著者
- 清野 純史 三輪 滋 古川 愛子
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 地震工学論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.412-419, 2007
地震時の墓石の転倒現象については, 実験と解析の両面から多くの研究が行われているが, 耐震補強された墓石の地震時挙動や補強効果について検証を行った研究は見当たらない. 本研究では, 墓石の代表的な耐震補強工法の効果を検証することを目的として, 墓石の実寸大模型を用いた振動台実験を実施した. 現在多く採用されている耐震補強工法の中から, 連結工法と免震工法に着目した. 連結工法の中からダボ工法と長ボルト工法, 免震工法の中から免震金具工法, 免震ゴム工法, エアーダンパー工法を採用した. デジタルカメラで撮影された画像と墓石試験体の加速度記録から, 各補強工法の効果と問題点について検討・考察を行った. 連結工法である長ボルト工法と免震工法である免震金具工法の効果が確認できた.