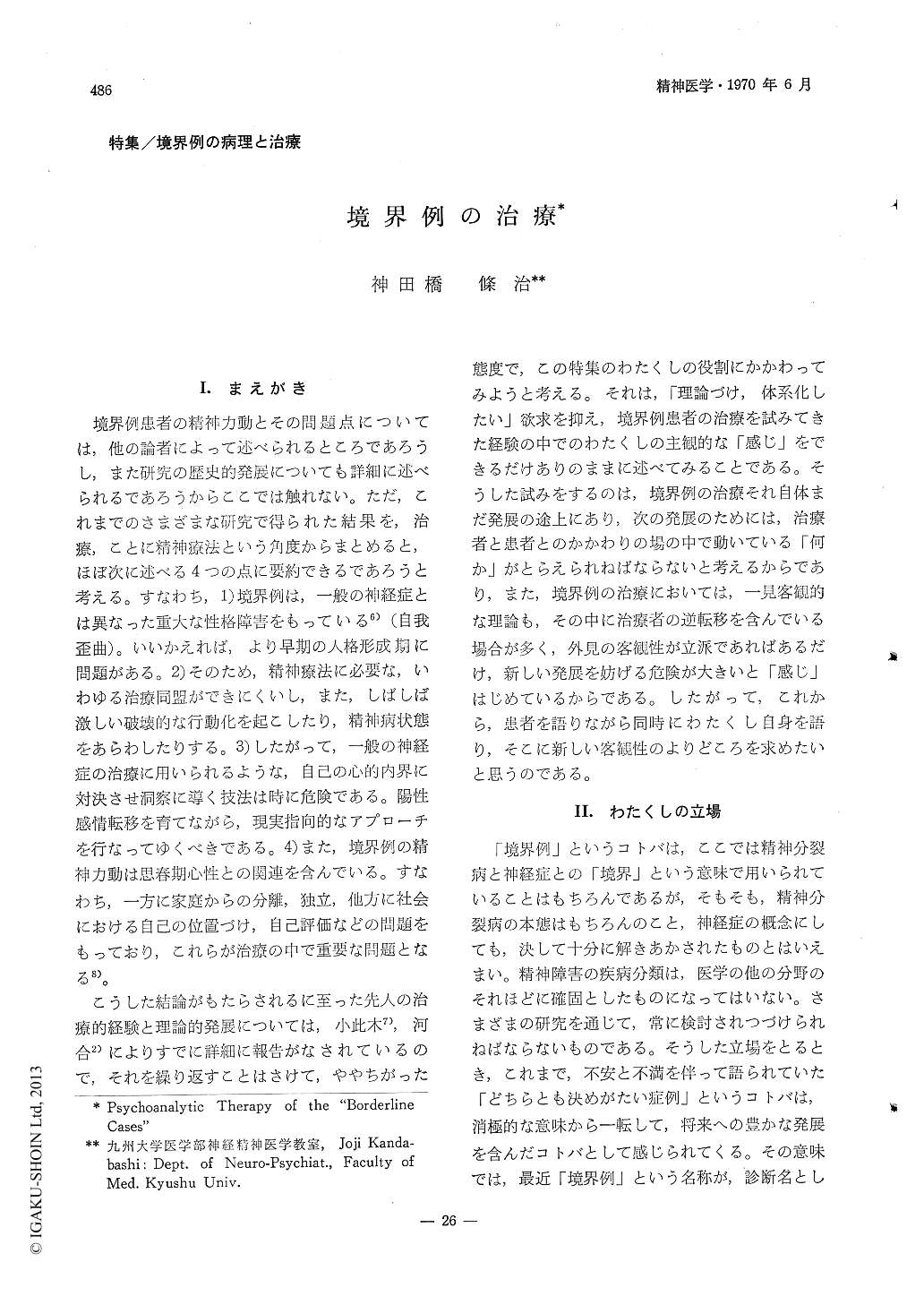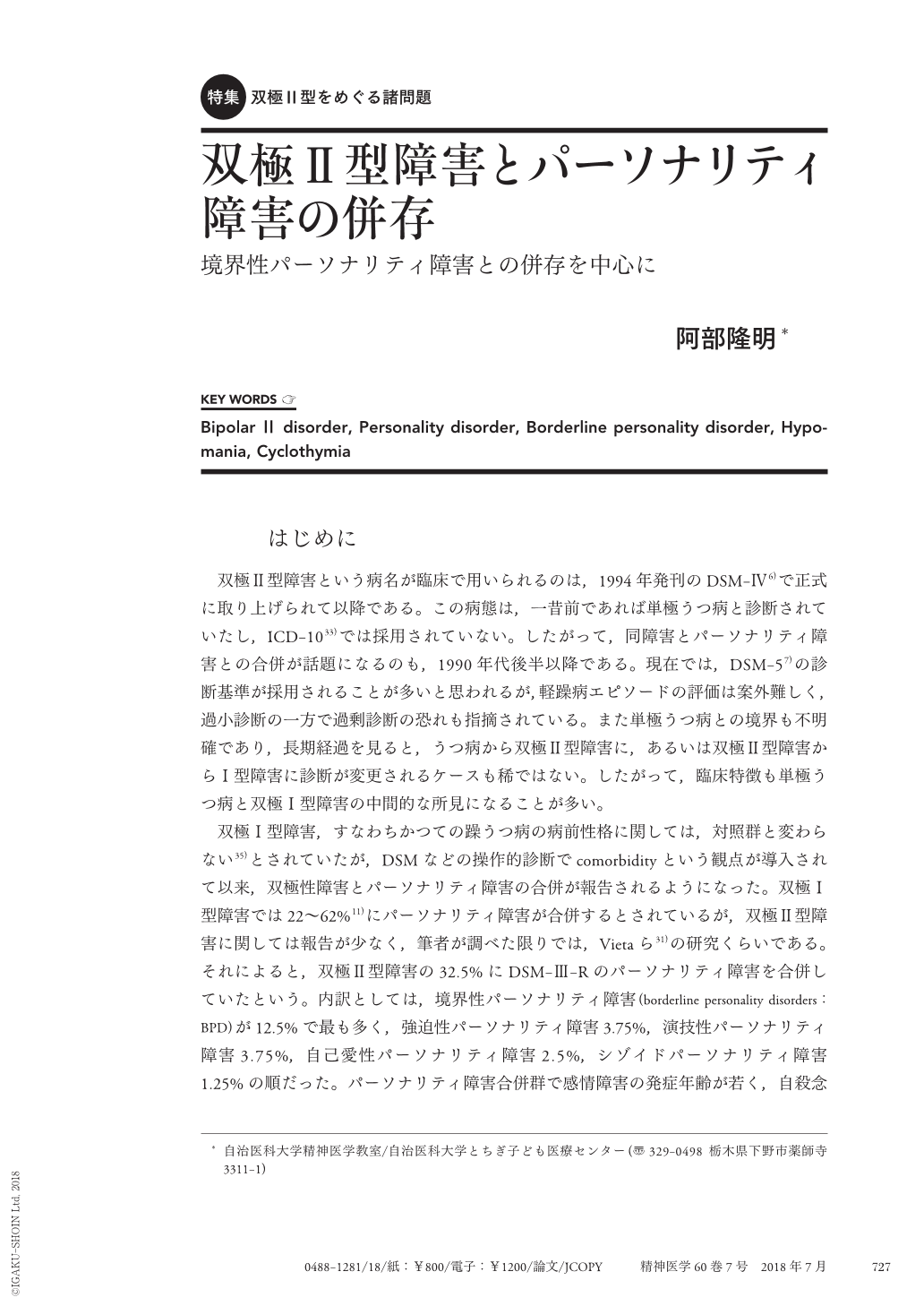1 0 0 0 関西空港・陸上ルート問題 : 環境影響評価の再検討と今後の展望
- 著者
- 早川 裕子 小森 康永 浅野 正嗣
- 出版者
- 日本家族療法学会 ; 1984-
- 雑誌
- 家族療法研究 = Japanese journal of family therapy (ISSN:09106022)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, pp.273-280, 2019
1 0 0 0 OA 子宮内膜細胞診における性周期推定に関する研究
- 著者
- 鳥居 貴代 布引 治 甲斐 美咲 野田 定
- 出版者
- 公益社団法人 日本臨床細胞学会
- 雑誌
- 日本臨床細胞学会雑誌 (ISSN:03871193)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.604-611, 1994 (Released:2011-11-08)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1 1
性周期各相の子宮内膜変化について, 内膜細胞診と同時に施行された内膜組織診とを比較し, 性周期各相に対応する細胞集団および構成細胞の形態変化から組織構築を推定し得る細胞診断基準を求め, 内膜細胞診における性周期推定の応用を試みた.性周期は, 増殖期は前期・後期, 分泌期は前期・中期・後期にわけ, それぞれの特徴的所見をNoyesのDating the endometriumや五十嵐のEndometriogramを参考として10項目-(1) 腺細胞の核分裂 (2) 核の偽重層 (3) 核下空胞 (4) 分泌像 (5) 間質の浮腫 (6) 間質の偽脱落膜様変化 (7) 問質細胞の核分裂 (8) 白血球浸潤 (9) 腺管の蛇行 (10) 螺旋動脈-からなる診断基準を作成し, その有用性を検討したととろ, 個々の細胞所見のみならず被覆上皮, 腺管, 間質細胞などの組織構築をふまえた出現様式を判定基準に取り入れたことで, より組織診に近い診断が得られることがわかった.
1 0 0 0 IR 流動性の罠と金融政策
- 著者
- 渡辺 努
- 出版者
- 岩波書店
- 雑誌
- 経済研究 (ISSN:00229733)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.4, pp.358-379, 2000-10
大規模な負の需要ショックに対応するために名目短期金利をゼロまで下げているにもかかわらずも需要が不足している場合に,中央銀行は何ができるだろうか.この問いに答えるために,本稿では,名目短期金利の非負制約を明示的に考慮しながら中央銀行の最適化問題を解く.最適な政策は,「ショックの発生移行のインフレ率や需要ギャップの累積値がある一定の水準に達するまでゼロ金利政策を続ける」とコミットすることであり,歴史依存性 (history dependence) が重要な特徴である.このように,政策ラグを意図的に発生させることにより,足元の名目長期金利が下がる一方,期待インフレ率は上昇するので,負の需要ショックの影響は和らげられる.日本銀行が1999年2月から2000年8月にかけて採用したゼロ金利政策は,(1)長めの金利への波及を当初から意図してきた.(2)ゼロ金利の継続期間を物価上昇率に関連づけながらコミットした,という点で最適解に近い性質を持つ,しかし,「デフレ懸念の払拭が展望できるまでゼロ金利を続ける」という日銀のコミットメントでは,ゼロ金利解除の条件が先見的 (forward looking) な要素のみで決まっており,最適解のもつ歴史依存性が欠落している.典型的な最適解ではインフレ率が正の値まで上昇するのを待ってゼロ金利を解除するのに対して,日銀のコミットメントはインフレになる前の段階でゼロ金利を解除するため,ゼロ金利期間が短すぎるという難点がある.
1 0 0 0 OA 韓国と日本のファッション事情
- 著者
- 南 始賢 ナム シヒョン
- 出版者
- 東京家政大学生活科学研究所
- 雑誌
- 東京家政大学生活科学研究所研究報告 (ISSN:09145192)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.1-10, 2000-06
1 0 0 0 マネーの目利き(上)住宅ローン ゼロ金利解除、狂騒始まる
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1350, pp.114-117, 2006-07-17
消費者にとって、ゼロ金利政策の唯一の恩恵とも言えたのが住宅ローン。大量供給が続く空前のマンションブームの中、住宅ローンが勝負どころとばかり、各金融機関は低金利を競い、融資残高を増やしてきた。 「頭金が物件価格の最低2割は必要」と言われたのは過去の話。融資の現場では、今や「頭金ゼロ」や「諸費用込み」も当たり前になった。
- 著者
- 杉本 良男
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:00215023)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.39-62, 1978
This paper is an attempt to present a structural analysis of the religious system of the Sinhalese of Sri Lanka (Ceylon). Anthropological study of the religion and society in South Asia has made great progress since SRINIVAS'S classic "Religion and Society among the Coorgs of South India" first published (1952). SRINIVAS pointed out two major problems in his monograph. On the one hand, he introduces the concept of 'spread' in Hinduism (All-India, Peninsular, Regional and Local). He emphasized the relation between all-Indian and Local Hinduism, or the sanskritic and the non-sanskritic Hinduism. The idea of this separation has been developed by some investigators, e. g. REDIFIELD(Great Tradition/Little Tradition), MARRIOTT (Universalization/Parochialization), and MANDELBAUM (Transcendental/Pragmatic) , in the studies of peasent society. On the other hand, SRINIVAS demonstrates how the religious notions of good-sacred (pure) and bad-sacred (impure) determine Hindu caste hierarchy and caste behaviours. The 'pure-impure concept' (or 'pollution concept') correlating religion with social structure has been assumed to be the basis of the Indian caste system. Especially, HARPER demonstrates how there is a broad reflex of three-class-caste system (high-middle-low) in three grades (gods, deities, spirits) and of ritual status (pure, pure/impure, impure) . HARPER'S idea is a knot of SRINIVAS'S two problems. First, I examine the utility of the hypotheses of SRINIVAS and HARPER critically, and then outline the total religious system of the Sinhalese through the structural analysis of rituals. The doctorine of Theravada Buddhism and primitive religion has been fused in Sri Lanka since 3c B. C., but people's religious behaviour now is that of a single religious tradition that is Sinhalese Buddhism, which is closely linked with the great tradition (Theravada Buddhism) . Sihhalese Buddhism includes various levels of Supernatural beings. This 'Pantheon' is neither Theravada Buddhist nor a magical animist one, but a 'Sinhalese Buddhist Pantheon'. The 'Pantheon' is hierarchically structured as follows. (1) The Buddha : the repository of power and divine authority, (2) Gods (deviyas) : Guardian deities and local gods who have power and divine authority over a certain area, and subordinate to the Buddha as a super deity, (8) Demons (yakas) : demons, dead relatives, goblins, and ghosts who are completely malevolent, punitive, and causing fear in men's hearts. Besides these Supernatural beings, there are some mediators who mediate between men and the supernatural beings. (1) The Buddhist monks (bbikkhu) : Mediators between men and the Buddha who is an other worldly being, (2) The astrologers (sastra kariyas) : Mediators between this world and the other world. Buddhism is connected with other-worldly oriented things (lokottara), while Magical-animism (god worship and demon worship) is connected with things of this world (laukika). Both systems are not contradictory but complementary. So, Buddhist monks may visit an exorcist to obtain cures in the case of irrational illness. This self-contradiction can be solved by the clear distinction between lokottara and laukika. The binary opposition between Buddhism and Magical-animism may be seen in the opposition between Buddhism and god worship as well. The Buddhist temple (vihara) and the shrines for the gods (devale) are often housed under one roof or at the same site. There are regular rituals in the vihara (Buddha pujava) and the devale (devapujava).
1 0 0 0 IR 金融政策の金利期間構造に与える影響について : 構造VARによる検証
- 著者
- 中島 清貴 Kiyotaka Nakashima 京都学園大学経済学部
- 出版者
- 京都学園大学経済学部学会
- 雑誌
- 京都学園大学経済学部論集 (ISSN:09167331)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.75-115, 2006-03-01
本稿は,Christiano, Eichenbaum, and Evans [1996a][1996b] のアプローチを援用することで外生的な金融政策ショックの識別を図り,金融政策ショックの金利期間構造に与える影響を構造VAR の方法に則って分析している。また,日本のマクロ経済に構造変化が生じていることの可能性を統計的に吟味すべく,誘導形のVAR モデルに対して構造変化の検定を適用したところ,1995年頃に構造変化が生じていることの可能性が指摘される。この1995年の時期は,バブル崩壊以降の不況に対応すべく,日銀がその操作目標であるコール・レートの誘導水準を0.5%以下に設定することに始まった低金利政策の開始時期と期を一にしており,この低金利政策を端緒として国債のイールド・カーブは下限へと推移するに至った。本稿では,この1995年の構造変化時点を,日本のマクロ経済・金融政策・金利期間構造,以上3つの分析対象に対する結節点と捉え,構造変化時点の前後で,金融政策ショックに対する金利期間構造への影響の仕方が如何様に変質しているのかを議論している。そこで,本稿の分析から得られた事実は以下の通りである。第一に,金融政策ショックの国債イールドに与える影響は,1995年以前においては,短期の国債ほど大きな影響が付与され,残存期間の長い国債ほど影響は小さくなっていく。ここでの結果は,米国の戦後の国債データを用いて同様の研究を行ったEvans and Marshall [1998] の指摘するところと同じものである。第二に,1995年以降においては,逆転現象が起きており,短期の国債ほど金融政策ショックに対する影響は小さく,残存期間の長い国債ほど影響は大きくなっていく。第三に,金融政策ショックに対する期間プレミアムへの影響に関して,1995年以前においては,全ての残存期間の国債に負の期間プレミアムが課されることの可能性が指摘される一方,1995年以降においては,全ての残存期間の国債に正の期間プレミアムが課され,両期間共に残存期間の長い国債ほどその影響が大きくなっていくことの可能性が指摘される。第四に,金融政策ショックに対する期間プレミアムの動向を受けて,前期では,金融政策引締めに伴って生じる将来消費の落ち込みというリスクに対して,無担保翌日物コール・レートを安全資産収益率と位置付けた時,国債市場が依然リスクのヘッジ機能を果たしていた可能性が指摘され,対して後期では,金融引締めに伴って,日本の国債市場がリスクのヘッジ機能を果たさなくなってしまう可能性が指摘される。このことから,ゼロ金利政策を解除するための要件として,ゼロ金利解除の時期までの将来の短期誘導金利の経路を日銀が明確にアナウンスすることを通じ,市場参加者の期待形成の大幅な改訂を伴うような事態をあらかじめ回避していくことが求められる。
1 0 0 0 IR 日本復帰後23年の沖縄における学校教育の展開
- 著者
- 藤原 幸男 Fujiwara Yukio
- 出版者
- 琉球大学教育学部附属教育実践研究指導センター
- 雑誌
- 琉球大学教育学部教育実践研究指導センター紀要 (ISSN:13425951)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.59-69, 1995-11
沖縄は終戦後すぐにアメリカ占領統治下に置かれ,アメリカ的な教育の側面を織り込みながら,日本本土とは相対的に独自な歩みをしてきた。ところが1969年に日本復帰が決まり,1972年の日本復帰によって日本本土の教育と同じ歩みが要求された。財政的援助によって学校施設・設備は全国水準に近づいたが,他方で,これまで国費学生制度・米国留学生制度によって沖縄県内の選抜で大学進学できたのが,急に全国の学生と対等に競争することになった。そのため,学力の低さが自覚され,学力向上を希求する意識が高まり,そこから学力問題が浮上してきた。また県教育庁は文部省中央の指示・助言を受けて全国並みの教育施策の実現に力を注いだ。授業についていけない子どもは,旧来の沖縄のテーゲー(適当・いい加減)文化に加えて,急速な観光地化にともない,金銭恐喝・集団暴行などの問題行動に走った。その背後に教師の体罰があるとも言われ,校則・体罰・人権が大きく取り上げられた。以下で,第一期(1972年~1981年),第二期(1982年~1987年),第三期(1988年~現在)に時期区分して,日本復帰後23年の沖縄における学校教育の展開を概観する。
1 0 0 0 境界例の治療
Ⅰ.まえがき 境界例患者の精神力動とその問題点については,他の論者によって述べられるところであろうし,また研究の歴史的発展についても詳細に述べられるであろうからここでは触れない。ただ,これまでのさまざまな研究で得られた結果を,治療,ことに精神療法という角度からまとめると,ほぼ次に述べる4つの点に要約できるであろうと考える。すなわち,1)境界例は,一般の神経症とは異なった重大な性格障害をもっている6)(自我歪曲)。いいかえれば,より早期の人格形成期に問題がある。2)そのため,精神療法に必要な,いわゆる治療同盟ができにくいし,また,しばしば激しい破壊的な行動化を起こしたり,精神病状態をあらわしたりする。3)したがって,一般の神経症の治療に用いられるような,自己の心的内界に対決させ洞察に導く技法は時に危険である。陽性感情転移を育てながら,現実指向的なアプローチを行なってゆくべきである。4)また,境界例の精神力動は思春期心性との関連を含んでいる。すなわち,一方に家庭からの分離,独立,他方に社会における自己の位置づけ,自己評価などの問題をもっており,これらが治療の中で重要な問題となる8)。 こうした結論がもたらされるに至った先人の治療的経験と理論的発展については,小此木7),河合2)によりすでに詳細に報告がなされているので,それを繰り返すことはさけて,ややちがった態度で,この特集のわたくしの役割にかかわってみようと考える。それは,「理論づけ,体系化したい」欲求を抑え,境界例患者の治療を試みてきた経験の中でのわたくしの主観的な「感じ」をできるだけありのままに述べてみることである。そうした試みをするのは,境界例の治療それ自体まだ発展の途上にあり,次の発展のためには,治療者と患者とのかかわりの場の中で動いている「何か」がとらえられねばならないと考えるからであり,また,境界例の治療においては,一見客観的な理論も,その中に治療者の逆転移を含んでいる場合が多く,外見の客観性が立派であればあるだけ,新しい発展を妨げる危険が大きいと「感じ」はじめているからである。したがって,これから,患者を語りながら同時にわたくし自身を語り,そこに新しい客観性のよりどころを求めたいと思うのである。
はじめに 双極Ⅱ型障害という病名が臨床で用いられるのは,1994年発刊のDSM-Ⅳ6)で正式に取り上げられて以降である。この病態は,一昔前であれば単極うつ病と診断されていたし,ICD-1033)では採用されていない。したがって,同障害とパーソナリティ障害との合併が話題になるのも,1990年代後半以降である。現在では,DSM-57)の診断基準が採用されることが多いと思われるが,軽躁病エピソードの評価は案外難しく,過小診断の一方で過剰診断の恐れも指摘されている。また単極うつ病との境界も不明確であり,長期経過を見ると,うつ病から双極Ⅱ型障害に,あるいは双極Ⅱ型障害からⅠ型障害に診断が変更されるケースも稀ではない。したがって,臨床特徴も単極うつ病と双極Ⅰ型障害の中間的な所見になることが多い。 双極Ⅰ型障害,すなわちかつての躁うつ病の病前性格に関しては,対照群と変わらない35)とされていたが,DSMなどの操作的診断でcomorbidityという観点が導入されて以来,双極性障害とパーソナリティ障害の合併が報告されるようになった。双極Ⅰ型障害では22〜62%11)にパーソナリティ障害が合併するとされているが,双極Ⅱ型障害に関しては報告が少なく,筆者が調べた限りでは,Vietaら31)の研究くらいである。それによると,双極Ⅱ型障害の32.5%にDSM-Ⅲ-Rのパーソナリティ障害を合併していたという。内訳としては,境界性パーソナリティ障害(borderline personality disorders:BPD)が12.5%で最も多く,強迫性パーソナリティ障害3.75%,演技性パーソナリティ障害3.75%,自己愛性パーソナリティ障害2.5%,シゾイドパーソナリティ障害1.25%の順だった。パーソナリティ障害合併群で感情障害の発症年齢が若く,自殺念慮も高率だった以外は,パーソナリティ障害の合併の有無で社会人口学的なデータに差はなく,他の臨床的な変数,すなわち,軽躁ないしうつ病相の数,精神病的な特徴,急速交代,季節性,精神疾患の家族歴にも有意な差はなかったという。また,双極Ⅱ型障害におけるBPDの合併に関しては,Benazzi8)も12%という数字を挙げている。 パーソナリティ障害ではなく,気質やパーソナリティという観点から,Perugiら26)は気分循環気質(cyclothymic temperament)が双極Ⅱ型障害の中核的な要素かもしれないと報告している。また,単極うつ病の患者に比べて,双極Ⅱ型障害の患者では,外向性が高く,神経質が低く,易刺激性が高いとする研究がある一方で,依存性,強迫性,演技性の特徴が多く,報酬依存的,受動回避/依存的という単極うつ病の患者と似たパーソナリティが認められるという研究もある9)。この矛盾した所見は,前者では双極Ⅰ型障害寄りの,後者は単極うつ病寄りの双極Ⅱ型障害が対象になっていたことを示唆するのかもしれない。結局,これまでの諸研究からは,双極Ⅱ型障害では他のパーソナリティ障害に比べて,BPDが多いというのが,唯一の最も一貫した所見である。逆に,BPDと診断された患者を調べると,約66%が感情障害の診断を合併していて,双極Ⅱ型障害が特に多い20)。そこで,以下では双極Ⅱ型障害とBPDとの関係を中心に論じてみたい。
1 0 0 0 地域構造分析による県境部の道路整備の方向性に関する基礎的研究
- 著者
- 川本 義海 伊豆原 浩二 本多 義明
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木計画学研究・論文集 (ISSN:09134034)
- 巻号頁・発行日
- no.16, pp.801-808, 1999
本研究は、地域構造分析により交通制約の大きい県境部の道路整備の方向性を提起することを目的としたものである。ここではまず県境部の道路の実状を把握した。次に北陸3県 (富山県、石川県、福井県) において、社会・経済指標の時系列データを用いて地域特性を説明する諸要因を明らかにした。さらにこれらの地域特性を説明する諸要因から市郡を分類し、北陸3県と隣接する中部・近畿の県との県境市郡の地域特性を示すとともに、県境部の道路整備状況との対比により県境地域の課題を示した。最後にケーススタディを通じて、県境地域において地域間の交流と連携を進めるに当たって重要とされる項目とそれらの相互関係をデマテル法により相対的に示し、県境部の道路整備の方向性を示した。
1 0 0 0 IR 気管・気管支癌への高線量率管腔内照射
- 著者
- 池田 恢 井上 俊彦 藤田 昌宏 村山 重行 手島 昭樹 池添 潤平 竹内 規之 河野 伸明 小塚 隆弘 Ikeda Hiroshi Inoue Toshihiko Fujita Masahiro Murayama Shigeyuki Teshima Teruki Ikezoe Junpei Takeuchi Noriyuki Kohno Nobuaki Kozuka Takahiro イケダ ヒロシ イノウエ トシヒコ フジタ マサヒロ ムラヤマ シゲユキ テシマ テルキ イケゾエ ジュンペイ タケウチ ノリユキ コウノ ノブアキ コズカ タカヒロ
- 出版者
- 日本医学放射線学会
- 雑誌
- 日本医学放射線学会雑誌 (ISSN:00480428)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.6, pp.841-843, 1992-06-25
- 著者
- 手島 昭樹 茶谷 正史 井上 俊彦 広川 裕 和田﨑 晃一 柏戸 宏造 影本 正之 勝田 静知 本家 好文 小山 矩 槇殿 洋子 片山 泰 木曽 哲司 Teshima Teruki Chatani Masashi Inoue Toshihiko Hirokawa Yutaka Wadasaki Koichi Kashiwado Kozo Kagemoto Masayuki Katsuta Shizutomo Honke Yoshifumi Koyama Tadashi Makidono Youko Katayama Hiroshi Kiso Tetsusi テシマ テルキ チャタニ マサシ イノウエ トシヒコ ヒロカワ ユタカ ワダサキ コウイチ カシワド コウゾウ カゲモト マサユキ カツタ シズトモ ホンケ ヨシフミ コウヤマ タダシ マキドノ ヨウコ カタヤマ ヒロシ キソ テツヤ
- 出版者
- 日本医学放射線学会
- 雑誌
- 日本医学放射線学会雑誌 (ISSN:00480428)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.4, pp.439-444, 1989-04-25
- 著者
- 古本 奈奈代 正満 敏雄 大松 繁 岡久 俊郎
- 出版者
- 一般社団法人 システム制御情報学会
- 雑誌
- システム制御情報学会論文誌 (ISSN:13425668)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.80-82, 1992-02-15
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1
生活環境政策を計画立案するときは, 住民のニーズを反映させるため, アンケートを行うことがよくある.アンケート項目間の内容は, 物理データと違って複雑に関連し合っているが, それを具体的にどのように扱うかについては充分な検討がなされていない面があった.そのため, ここではまず, デマーテル手法を適用して専門家などの意見を参考に, 項目間の階層的な繋がりや関連度を調べてその構造を分析し, つぎに, それらをもとに, 実質的なニーズを求めることを考えた。これによって, 環境政策をたてる際の無駄な投資は避けられるのではないかという見通しをたてた.また, ここで提案した手法は, 計画立案に当り, コンピュータとの対話型支援システムとして役立てることができると思われる.
- 著者
- 稲田 隆之
- 雑誌
- 武蔵野音楽大学研究紀要 = Bulletin of Musashino Academia Musicae (ISSN:05802466)
- 巻号頁・発行日
- no.49, pp.19-37, 2018-03-31
1 0 0 0 IR 学級内の人間関係に苦戦している生徒の見取りと支援プロセスについて
- 著者
- 村松 健太郎
- 出版者
- 静岡大学大学院教育学研究科教育実践高度化専攻
- 雑誌
- 教育実践高度化専攻成果報告書抄録集
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.97-102, 2014-03
1 0 0 0 OA 中医栄養学について IV 食物の作用
- 著者
- 山崎 民子
- 出版者
- 帯広大谷短期大学
- 雑誌
- 帯広大谷短期大学紀要 (ISSN:02867354)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.21-26, 1999-03-25 (Released:2017-06-16)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 OA 文法誤り訂正の参照文を用いない自動評価の人手評価への最適化
- 著者
- 吉村 綾馬 金子 正弘 梶原 智之 小町 守
- 出版者
- 一般社団法人 言語処理学会
- 雑誌
- 自然言語処理 (ISSN:13407619)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.404-427, 2021 (Released:2021-06-15)
- 参考文献数
- 35
信頼できる文法誤り訂正の自動評価手法の構築は,文法誤り訂正の研究および開発の発展に有用である.可能な参照文を網羅することが難しいため,先行研究では参照文を用いない自動評価手法が提案されてきた.そのうちの一つは,文法性・流暢性・意味保存性を評価する 3 つの評価モデルを用いることで,参照文を用いる手法よりも人手評価との高い相関を達成した.しかし,各項目の評価モデルは人手評価には最適化されておらず,改善の余地が残されていた.本研究では,より適切な評価を行える自動評価手法の構築を目的として,各項目の評価モデルを事前学習された文符号化器を用いて人手評価に対して最適化する手法を提案する.また,最適化に理想的である,訂正システムの出力文に対して人手評価が付与されたデータセットの作成を行う.実験の結果,項目ごとの評価モデルおよびそれらを組み合わせた手法の両方で,従来手法と比べて人手評価との相関が向上し,事前学習された文符号化器を用いることおよび訂正文の人手評価に最適化することの両方が貢献していることがわかった.分析の結果,提案手法は従来手法に比べて多くのエラータイプの訂正を正しく評価できていることがわかった.