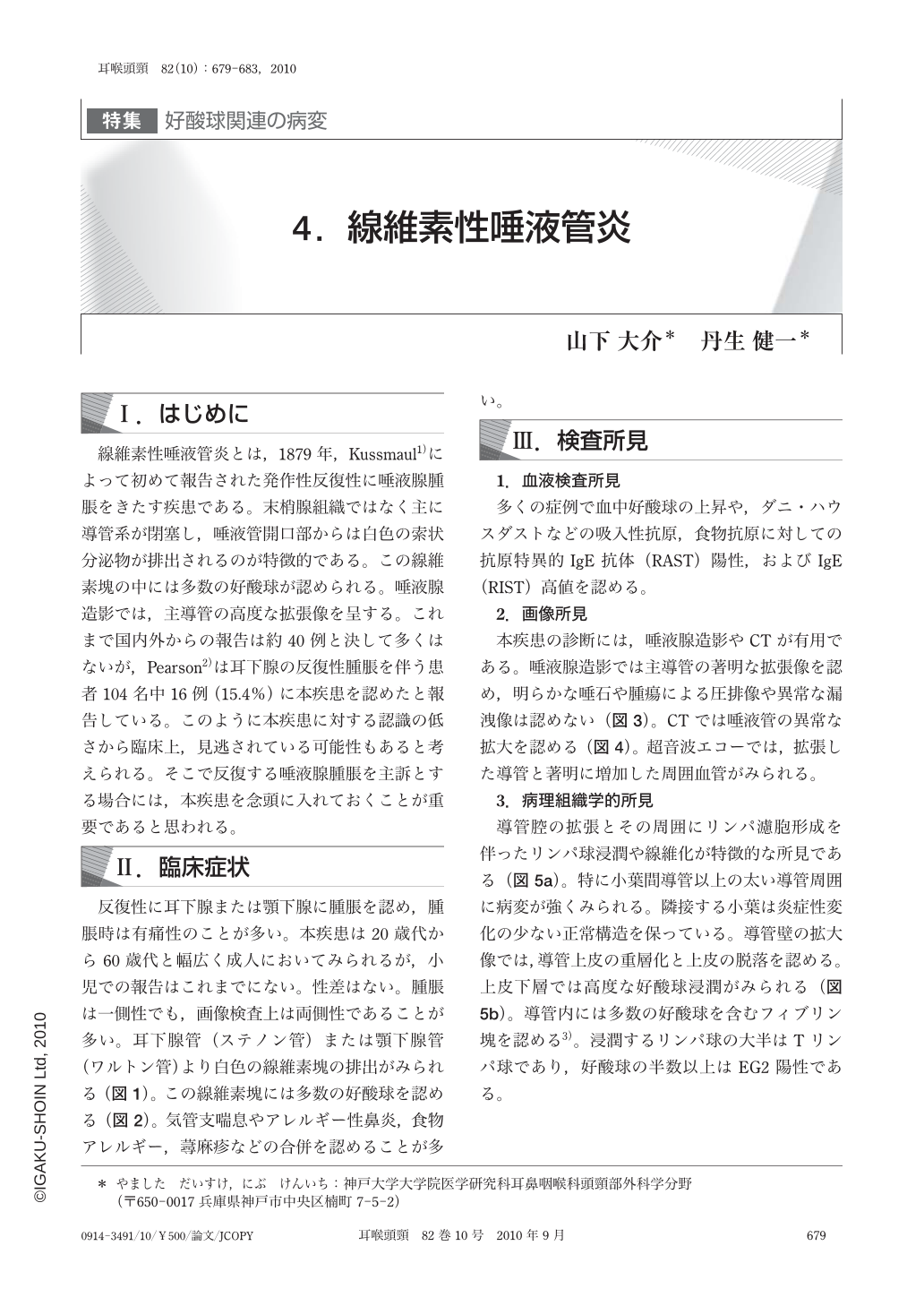1 0 0 0 OA Sexual Mythology in India and the West
- 著者
- 芸林 民夫 Thomas Guerin
- 雑誌
- 比較文化論叢 : 札幌大学文化学部紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.A1-A30, 2004-03-31
2003年11月のインドでの2週間の研究活動を通して、特に印象に残ったのはカジュラホの神殿を飾る性的な彫訓群だった。疑問は、このような彫刻がなぜ神殿という聖なる建築物を飾るのか。カジュラホだけではなく、インドのいたるところの神殿に西洋の目で見れば「汚い」性的な表現が多いので、性に対するインドと西洋の違いを探ることにした。結論として西洋とインドの大きな違いは、インドの宗教と神話には、当たり前のように、男女の神々が現在まで国民の宗教活動の対象になっている。それに対して、西洋の神は一人の「父神」であり、「母神」はいない。そのために、性は宗教の中からは排除され人間の社会でもタブー視されるようになってしまった。インドでは「男根」の意味の「リンガム」や女性の「外陰部」の意味の「ヨニ」は崇拝の中心になる。現在インドでは多くの神々の中で一番人気のあるシバ神の神殿の聖なる場所で神体として「リンガム」が拝められている、その近くには必ず女性の本源シャクテイの象徴「ヨニ」が一緒に信者の崇拝を受けている。西洋の世界では、「リンガム」や「ヨ二」のような物を神とすること、または、神と関係あることは、タブー以上に冒涜になる。シバ神と奥さんパルバティ神の性交は理想的な愛の表現であり、パルバティ神は若いインド人女性たちの憧れの的である。同じように、西洋でポルノとして見られている「カマ・スートラ」は、インドでは結婚前の女性に理想的な結婚生活の手引書として渡されることもある。「悟り」(ヒンズ教では「モクシャ」)への道として、ヒンズ教の中に在るタントラは性行為を含めて、人間のあらゆる欲を清めながら実行する。特にタントリック・ヨーガの中では、性行為の「アーサナ」(ヨーガの種々の姿勢)は悟りに導くとされている。西洋の世界では、人間の死んでからの世界は「天国」で、「悟り」や「涅槃」ではない。しかし、「天国」に達するために、罪のない人生を過ごすことが条件であり、「性行為」=「罪」という考えが多く、「天」に到達する一番の妨げになる。それに対してインド(また仏教を含めてインドから始まった宗教)では、輪廻から開放する「涅槃」が目的で、性欲を含めて人間のあらゆる欲をルールにのっとって清めることにより達する。要するに、父神しかいない西洋では、性行為はタブーとされ(自然の世界では当然行われているが、神に対する良心の呵責の原因となる。)、インドでは、父親の神もいるが当然母親の神もいるから、性行為はいとも自然なことであり、そこが世界の始まりとされている。
- 著者
- Rajalakshmi Parthasarathy ラジャラクシュミ パルタサラティ Parthasarathy Rajalakshmi
- 雑誌
- Gender and Sexuality : Journal of the Center for Gender Studies, ICU
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.51-66, 2006-03-31
このペーパーではインドにおける現代に至るまでのジェンダー表象およびグローバル化の中での変化のありかたの包括的分析を行う。インドの社会実情は多文化混在性と密接に結びついており,それは地域により父権主義的なものからから女系制まで存在するジェンダー関係の現状にも反映されている。ここでは,ジェンダー観の発達および内在化に強い影響を与えた5個の要素に焦点を当てて議論したい。具体的には,インド神話体系・宗教・歴史・文学およびマスメディアを取り上げる。多面的なインド文化では,多くの対立的要素,例えば伝統とモダニティ,都市文化と地方文化、精神主義と現実主義、識字文化および非識字文化といった事柄が共存するパラドクスが見られる。他言語・他宗教・他民族・階層社会というインド社会の多様性にも関わらず,そこにある統一的アイデンティティが確実に存在しているのは,やはり文化活動の影響に負うところが大きいだろう。神話体系はインド文化にとって最も豊饒な基盤のひとつであり,現在に至るまでインド社会の精神性の根源はヒンドゥー教聖典であるプラーナの編まれた時代にある。ジェンダーによるステレオタイプや役割の発展過程の研究において,叙事詩や民話,伝説が参照される要因はここにある。インド社会内の父権的構造によって採用されてきた宗教原理や伝統についての議論は,ジェンダーによる差異化がいかに着実に男性の社会における優位性を確立し女性の生を周縁化してきたか,また寡婦殉死や持参金制度,女児殺し,寡婦や未婚婦人の蔑視,強姦をはじめとする女性に対する暴力全般などの社会悪の根源がここにあることを明らかにする。外国勢力の侵入の歴史を辿ると,紀元前325 年のギリシャによるパンジャブ地方浸入および紀元747 年のアラブ浸入,15 世紀に始まるムガール帝国による支配,イギリスによる植民地支配などによる数次にわたる男性優位性思想導入の影響を見て取ることができる。文学はそれを生んだ社会を映す鏡の役割を果たす。一般大衆向け作品に見られるジェンダー表象は男女に対するステレオタイプ化されたイメージとアイデンティティの変化を見せてくれる。過去において,そしておそらく現在においても,女性に対するイメージには両義的なものがあり,神格化されたイメージと侮蔑的で貶められたイメージが並立して見られる。男性キャラクターの描かれ方と照らし合わせるとき,現代社会における女性の地位および役割の変化の中,アイデンティティクライシスが進行しつつあることが見て取れるだろう。映画やテレビドラマ,広告や印刷メディアが男女の生活におよぼす影響は非常に大きい。映画は現在の社会の傾向を指し示す理想的なメディアである。年間製作本数の膨大さにおいてインド映画界は世界最大規模を誇る。メディアテクストの多義的な意味性に女性性の現実ではなく男性の幻想の反映を見て取るのは難しくない。娯楽映画では,男女を伝統的アイデンティティのもとに表現するため,さまざまな方策をとっている。採算性が最優先されるため,男性観客向けアピールとしてセックスと暴力に力点が置かれている。インド社会全域に浸透しているテレビも映画に影響を与えている。連続ドラマの多くは女性を中心に据えているが,否定的な側面が強調されている。そこでは女性は悪意に満ちているか,あるいは弱い人間として描かれる。広告で男性の下着からトイレ・浴室用製品にいたるまで,グラマラスな人形として女性イメージが多用されている。締めくくりとして,インド社会の精神性と文化構造の継続性および安定性が,黙々たるインド女性によって保たれてきたことを示したい。この文脈において,女性の人生は徳性の担い手として娘・妻・母としての義務と役割を果たすことにあると考えられてきた。全人格的存在としての個人が役割の枠組みから離れることは許されず,女性の多くが,既成の枠組みを超えるのではなく,その枠組みを尊厳あるものとして扱い,結果としてそれを保持してきた。しかし現在,成長と生活の場には新しい状況がある。現在女性が立っている空間はいまだかつて存在たことのない場所だ。そこには新しい指針が打ち立てられなければならない。女性が旧来の世界を脱却し,新しい世界に足を踏み入れ,新しい意味性を獲得し作り出すためには,まず自らの内面に潜む因習を乗り越える必要がある。現在の世界的および地域的状況は,女性と男性が対話に基づき,平等で幸福な人間社会を協力して築くことを行動に移す環境を整えつつある。
1 0 0 0 OA インドのマスキュリニティと現世放棄
- 著者
- 國弘 暁子 Kunihiro Akiko
- 出版者
- 群馬県立女子大学
- 雑誌
- 群馬県立女子大学紀要 (ISSN:02859432)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, pp.111-118, 2012-02-29
1 0 0 0 OA (36)自動前立腺マッサージ装置によるprostatodyniaに対する治療効果
- 著者
- 吉田 正林
- 出版者
- 一般社団法人 日本医療機器学会
- 雑誌
- 医科器械学 (ISSN:0385440X)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.4, pp.214, 1992-04-01 (Released:2021-05-28)
1 0 0 0 自生ふん囲気下での硫酸マグネシウム水和物の熱分解
- 著者
- 伊佐 公男 野川 正弘
- 出版者
- 日本熱測定学会
- 雑誌
- 熱測定 (ISSN:03862615)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.2-7, 1983
Thermal decomposition of magnesium sulfate heptahydrate was studied by TG-DTG-DTA under various sealed atmospheres (open, quasi-sealed, and completely sealed). In the case of open system, stable hexahydrate was obtained, and in the case of quasi-sealed system (29.8μm∅ and 130μm∅ tungsten wires), stable tri-, di-, and mono-hydrate were obtained. However in the case of completely sealed system, mono-hydrate was only obtained. Concerning the condition of completely sealed system, there is some relation between the results of MgSO<sub>4</sub>·7H<sub>2</sub>O and CaSO<sub>4</sub>·2H<sub>2</sub>O. In the case of CaSO<sub>4</sub>·2H<sub>2</sub>O, the hemihydrate was obtained under completely sealed system. The results explain directly that self-generated atmosphere plays an important role of dehydration reaction. The intermediate stages of dehydration were easily obtained by this method.
1 0 0 0 OA 社会的逸脱行為の促進・抑制要因としての恥意識に関する基礎的検討
- 著者
- 中村 真
- 雑誌
- 江戸川大学紀要 = Bulletin of Edogawa University
- 巻号頁・発行日
- vol.28, 2018-03-31
本稿は,恥意識が社会的逸脱行為に対して促進・抑制の両面にわたって影響を及ぼすことを首都圏の四年制大学に通う学生を対象とする質問紙調査を行って実証的に検討した。先行研究の知見をふまえて,自分の行動が自ら立てた目標や基準に合致しないときに生じる「自分恥」,および,自分の行動が社会一般の常識やルールと一致しないときに生起する「他人恥」が社会的逸脱行為に対する許容性を抑制すること,自分の考えや行動が身近な仲間集団と一致しないときに生じる「仲間恥」が社会的逸脱行為に対する許容性を促進するという仮説を設定し,これらを概ね支持する結果を得た。また,「仲間恥」が社会的逸脱行為を促進する背景に,規範意識の低い仲間との同調傾向があることを裏付ける因果モデルの検証をパス解析により行った。
1 0 0 0 OA 唐土訓蒙図彙 : 14巻
- 著者
- 平住専庵 [編]
- 出版者
- 河内屋吉兵衛 [ほか]
- 巻号頁・発行日
- vol.[1], 1802
1 0 0 0 OA 織部灯籠 : 「キリシタン灯籠」の遺品は存在しない : (附)広島県織部灯籠一覧表
- 著者
- 松本 真 マツモト シン Shin Matsumoto
- 雑誌
- 広島修大論集. 人文編
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.49-113, 2000-03-10
The Oribe-style stone lantern used in a garden for tea ceremony has its origin in the time around 1600. On the remains of those lanterns is engraved the year 1615. Their formative characteristics are found at the three parts of stone poles. First, the top part of stone poles, projecting right and left, has a shape Τ (Egyptian Cross), and a shape † (Latin Cross). There's a theory from this that it's the symbol of the Holy Cross. However, I think this theory is wrong. The design Τ is not limited to the Holy Cross. Second, in the center of the shape † are engraved hieroglyphic characters. There's another theory from this that these characters mean IHS (Jesus; lesus Homium Salvator), or IHP. This theory is also wrong. I think it's the ideogram of the old form of a Chinese character Tatsu. Tatsu means the year of the birth of Furuta Oribe (1544-1615). Tatsu is one in Eto (or, Chinese sexagenary cycle), and the character means the North Star. It also has its original meaning of "being the best season for crops in fine spring weather." Third, at the base of the stone pole is a figure in relief. There's a theory from this that this is an image of Jesus Christ or of a missionary. I think this is wrong, too. I think it's an image of a bonze (or, priest) style of the master of tea ceremony and its variation.
- 著者
- 城 惣吉 間塚 真矢 門脇 正行 佐伯 雄一
- 出版者
- 一般社団法人 日本土壌肥料学会
- 雑誌
- 日本土壌肥料学雑誌 (ISSN:00290610)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, no.3, pp.255-262, 2021-06-05 (Released:2021-06-15)
- 参考文献数
- 26
地球温暖化に伴う気候変動の作物生産への影響に関する基礎的知見の蓄積の一環として,異なる栽培温度環境下におけるダイズの生育と有用ダイズ根粒菌の接種効果および感染ダイズ根粒菌群集構造への影響について調査を行った.供試ダイズ品種として,‘オリヒメ’,‘ボンミノリ’,‘フクユタカ’を用い,供試菌株としてBradyrhizobium diazoefficiens USDA110Tを用いた.栽培は温度傾斜型チャンバー内で行い,低温区,中温区,高温区を設けた.異なる温度環境下での栽培試験の結果,無接種区と比較して,USDA110の接種により主茎長,主茎節数,茎葉乾物重,莢数,莢乾物重,地上部乾物重,根粒数が有意に増加したが,栽培温度の上昇により根粒数を除く項目が有意に減少した.各調査項目間の相関係数は根粒数と茎葉乾物重との関係など多くの組み合わせにおいて有意な正の相関関係を示した.USDA110の根粒占有率は,全ての温度区で接種したUSDA110が優占したが,低温区と中温区,低温区と高温区を比較すると栽培温度の上昇により減少する傾向を示した.以上の結果から,高温環境下では根粒数が減少することでダイズの生育が抑制され,その後の生育や収量に影響すると考えられた.しかし,根粒数とUSDA110の根粒占有率を確保することができれば栽培温度の上昇によるダイズの生産性低下を抑制することができると考えられる.
1 0 0 0 OA 全国所得納税者姓名録 : 一名・代議士撰挙の台帖
- 著者
- Joon-Hee Lee
- 出版者
- The Society of Physical Therapy Science
- 雑誌
- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.274-277, 2016 (Released:2016-01-30)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 20 54
[Purpose] To determine the effects of forward head posture on static and dynamic balance control. [Subjects and Methods] This study included 30 participants who were included into a forward head posture group (n = 14) and a control group (n = 16) according to their craniovertebral angles. Static balance control was assessed according to center of gravity sway velocity and total sway distance using an automatic balance calibration system. Dynamic balance control was assessed using the diagnosis mode of a body-tilt training and measurement system. [Results] Sway velocities on a hard surface with eyes open and closed and those on an unstable sponge surface with eyes closed were significantly higher in the forward head posture group than in the control group. Furthermore, on both the hard and sponge surfaces in the eyes open and closed conditions, total sway distances were significantly higher in the forward head posture group than in the control group. Results of dynamic balance control were not significantly different between groups. [Conclusion] Forward head posture has a greater effect on static balance control than on dynamic balance control.
1 0 0 0 OA 可視光増感型酸化チタン光触媒
- 著者
- 西川 貴志
- 出版者
- 一般社団法人 色材協会
- 雑誌
- 色材協会誌 (ISSN:0010180X)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.10, pp.446-450, 2004-10-20 (Released:2012-11-20)
- 参考文献数
- 7
1 0 0 0 乳化重合
- 著者
- 本山 卓彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本油化学会
- 雑誌
- 油化学 (ISSN:0513398X)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.9, pp.574-581, 1969
1 0 0 0 OA 戦前大阪の鉄道とデパート―都市交通による沿線培養の研究―
- 著者
- 谷内 正往
- 出版者
- 近畿大学
- 雑誌
- 博士学位論文/内容の要旨および審査結果の要旨(平成28年度授与)
- 巻号頁・発行日
- pp.1-5, 2017-05-01
学位の種類:商学 学位授与年月日:平成29年3月21日 主査:山田,雄久 教授 報告番号:乙第687号 学内授与番号:商第18号
1 0 0 0 OA 近代における都市空間形成を通じた「市民」形成―米騒動後の湊川公園の変容過程を事例として―
- 著者
- 中川 祐希
- 出版者
- 一般社団法人 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.3, pp.221-244, 2019 (Released:2019-10-29)
- 参考文献数
- 70
- 被引用文献数
- 4
本稿は,神戸市の湊川公園の変容過程を事例とし,米騒動後における「市民」形成によって,いかなる都市空間が形成されたのかを明らかにした。米騒動と労働争議を契機に,都市行政は,湊川公園に公設市場や職業紹介所といった施設を設置した。都市行政は,「貧民窟」や労働者地区,歓楽街と近接するがゆえに,湊川公園にこのような整備を施した。さらに音楽堂と児童遊園地が設置されたことで,湊川公園は,諸階層を「市民」へと教化する空間に変容した。このように「市民」が湊川公園の利用者として想定される一方で,不況により公園内には数多くの野宿者が姿を現していた。はじめ都市行政は野宿者を救済の対象として認識した。しかし,「市民」を想定した公園の整備が進展し,昭和天皇の即位を祝う記念事業が開催されたことで,野宿者は排除や抑圧の対象に位置づけられた。湊川公園が私生活を積極的に管理する「勤勉」な「市民」によって利用される公園に変容する過程で,野宿者はこの規範から逸脱する「怠惰」な主体として捉えられた。こうして米騒動後の湊川公園は,「市民」への主体化の成否によって,諸階層が選別される空間へと変容した。
1 0 0 0 FM補完中継局 ~ワイドFM始まりものがたり~
- 著者
- 冨澤 淑光
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.1, pp.63-68, 2018
1 0 0 0 4.線維素性唾液管炎
Ⅰ.はじめに 線維素性唾液管炎とは,1879年,Kussmaul1)によって初めて報告された発作性反復性に唾液腺腫脹をきたす疾患である。末梢腺組織ではなく主に導管系が閉塞し,唾液管開口部からは白色の索状分泌物が排出されるのが特徴的である。この線維素塊の中には多数の好酸球が認められる。唾液腺造影では,主導管の高度な拡張像を呈する。これまで国内外からの報告は約40例と決して多くはないが,Pearson2)は耳下腺の反復性腫脹を伴う患者104名中16例(15.4%)に本疾患を認めたと報告している。このように本疾患に対する認識の低さから臨床上,見逃されている可能性もあると考えられる。そこで反復する唾液腺腫脹を主訴とする場合には,本疾患を念頭に入れておくことが重要であると思われる。
1 0 0 0 OA 火山活動と環境の酸性化
- 著者
- 藤田 慎一
- 出版者
- Japan Society for Atmospheric Environment
- 雑誌
- 大気汚染学会誌 (ISSN:03867064)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.72-90, 1993-03-10 (Released:2011-11-08)
- 参考文献数
- 107
- 被引用文献数
- 5
日本列島は世界でも有数の火山地域である。このため, 火山活動により大気中へ放出される硫黄化合物は, 量的にみて人間活動に匹敵するものと推定されている。本報では, 硫黄化合物の物質収支における火山活動の役割を整理するとともに, 環境の酸性化に及ぼす火山活動の影響について, 最近の研究動向をとりまとめた。日本列島を対象にして, 火山噴出物の輸送をモデル化していくうえで, 検討すべき問題点についても考察を加えた。
- 著者
- 西村 正男
- 出版者
- 中国人文学会
- 雑誌
- 饕餮 (ISSN:13441485)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.30-63, 2005-09