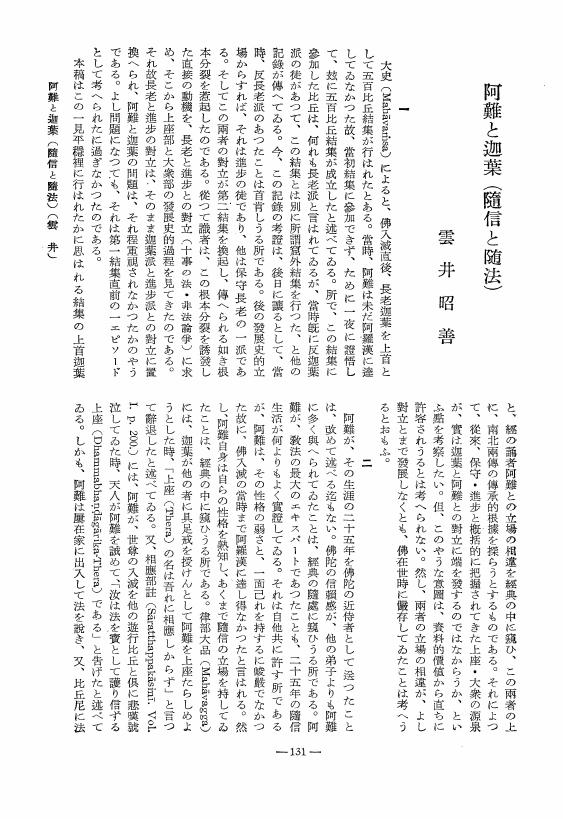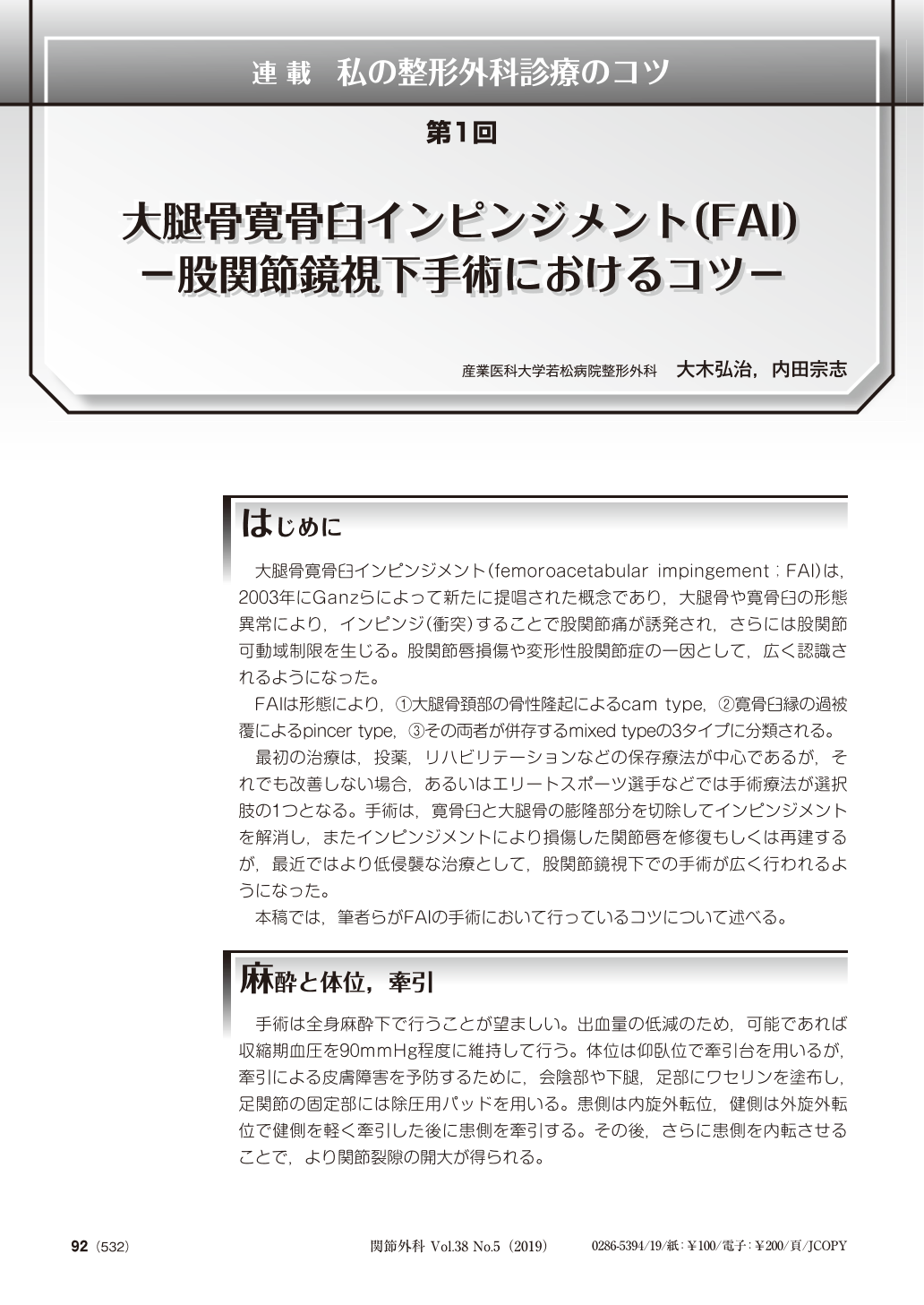1 0 0 0 原始技術史入門 : 技術の起原をさぐる
1 0 0 0 あかりと火の信仰 : おこす・ともす・いのる
- 著者
- 天理大学附属天理参考館編
- 出版者
- 天理ギャラリー
- 巻号頁・発行日
- 2007
1 0 0 0 OA 北海道、大雪山白雲小屋における1990~1993年の気温観測資料
- 著者
- 曽根 敏雄
- 出版者
- 北海道大学低温科学研究所
- 雑誌
- 低温科学. 物理篇. 資料集 (ISSN:03853683)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, pp.33-50, 1995-03-30
1 0 0 0 英国の2010年総選挙と連立新政権の政治改革
- 著者
- 齋藤 憲司
- 出版者
- 国立国会図書館調査及び立法考査局
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:00342912)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.9, pp.7-34, 2010-09
1 0 0 0 OA 阿難と迦葉 (隨信と随法)
- 著者
- 雲井 昭善
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.131-132, 1953-09-30 (Released:2010-03-09)
- 著者
- 末冨 芳
- 出版者
- 日本教育行政学会
- 雑誌
- 日本教育行政学会年報 (ISSN:09198393)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.160-178, 2008-10-10 (Released:2018-01-09)
- 被引用文献数
- 1
This article aims to clarify the importance of the devolution of power and authority to schools in the Japanese educational finance system. With this goal in mind, the systems of educational finance in Japan, the United Kingdom, and Sweden are analyzed from the perspective of authority distribution between the central government, local government, and schools. "School" here is defined as public compulsory primary and secondary schools. In the United Kingdom's educational finance system, the central government has great power, while in Sweden local government is the main authority in the educational finance system, yet both countries promote reform decentralization at the school level. There is, however, the reality that in the Japanese educational finance system the school is not actually given much authority or power. Japanese elementary and secondary schools thus have many difficulties facing them in terms of acquiring adequate school budgets for school administration and effective budget allocation. In recent years, contract research by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) has shown that approximately 70-80% of Japanese head teachers feel a deficiency of budget and a lack of authority. On the other hand, MEXT has been emphasizing a policy of building up "attractive schools." Not surprisingly, this policy has not made much progress because of this lack of ultimate authority. In the international context countries such as the U.S.A., Australia, New Zealand, and various EU nations have seen decentralization at the school level in terms of teacher salaries, the right of employment, and allocation of the school budget. The actual situation of school decentralization, especially the political context in the U.K. and Sweden, are clarified here with the aim of promoting Japanese decentralization to schools. Nowadays, the Japanese government promotes not so much decentralization to schools but to local governments to build up effective and attractive schools. The importance of school-based management and budgets must therefore be recognized. Comparative analysis of the U.K, Sweden and Japan points to the importance of schools in the system of educational finance and administration. This paper first outlines the educational finance system of Japan, the U.K. and Sweden. Then the relevancy between the level of decentralization at the school level and the features of educational finance systems in general are examined. One finding is that there is little direct relevance, in terms of the level of decentralization for schools, concerning the political context of each country. The political background and context of decentralization to school are then investigated, followed by a discussion of the theoretical importance of decentralization to the school level, referring to the theory of School Based Management (SBM) and School Based Budget (SBF). Finally, the importance of the promotion of decentralization to schools, and the conditions needed to achieve this, are examined.
- 著者
- 有森 裕子 高島 三幸
- 出版者
- 日経BP社 ; 2002-
- 雑誌
- 日経ビジネスassocie (ISSN:13472844)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.4, pp.78-80, 2016-03
第21回2大会連続五輪メダリストという女子陸上界初の快挙を成し遂げた有森裕子さん。ここぞという大舞台で、継続的に結果を出し続ける考え方と、方法論を聞いた。──前号では、バルセロナ五輪で銀メダルを獲得されてからアトランタ五輪までの4年間、思い通り…
1 0 0 0 OA 公教育費・私教育費のグラデーション構造 ―その戦後日本的特質の解明-
- 著者
- 石井 拓児
- 出版者
- 日本教育制度学会
- 雑誌
- 教育制度学研究 (ISSN:2189759X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2014, no.21, pp.159-164, 2014 (Released:2020-11-29)
1 0 0 0 OA デンマークの職業教育改革から何を学ぶのか
- 著者
- 中島 広明
- 出版者
- 学校法人 敬心学園 職業教育研究開発センター
- 雑誌
- 敬心・研究ジャーナル (ISSN:24326240)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.37-44, 2020 (Released:2020-07-15)
- 参考文献数
- 13
デンマークの職業教育において、早期離学(ドロップアウト) が社会問題となっている。そのため2015年に職業教育改革が行われた。なぜ、デンマークの職業教育で早期離学問題が起きているのか。そして、デンマークではどのようにして、早期離学問題に対処しようとしているのか。デンマークの教育や教育改革の概説をしたうえで、日本の高校、大学等へのアクセスを対比させて検討し、わたしたちがデンマークの職業教育改革から何を学ぶことができるのかを議論したい。
- 著者
- 河辺 峻 古谷 英祐
- 出版者
- 明星大学情報学部研究紀要編集委員会
- 雑誌
- 明星大学研究紀要. 情報学部 = Bulletin of Meisei University. School of Information Science (ISSN:13444379)
- 巻号頁・発行日
- no.23, pp.2-1-2-14, 2015-03-20
- 著者
- 有森 裕子 高島 三幸
- 出版者
- 日経BP社 ; 2002-
- 雑誌
- 日経ビジネスassocie (ISSN:13472844)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.74-76, 2016-02
第20回2大会連続五輪メダリストという女子陸上界初の快挙を成し遂げた有森裕子さん。前例がないからこそ、「抱えた苦悩と困難を乗り越えるヒント」を聞いた。──取材や講演会などで、度々〝あきらめないことの大切さ〟について発信されています。
1 0 0 0 OA 薬剤師が経営・管理の場で活躍するために
- 著者
- 赤瀬 朋秀 植木 哲也
- 出版者
- Japanese Society of Pharmaceutical Health Care and Sciences
- 雑誌
- 日本医療薬学会年会講演要旨集 (ISSN:24242470)
- 巻号頁・発行日
- pp.371-376, 2018-11-23 (Released:2019-12-02)
- 著者
- 関根 道和
- 出版者
- 日本医学教育学会
- 雑誌
- 医学教育 (ISSN:03869644)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.6, pp.435-438, 2010 (Released:2012-03-27)
- 参考文献数
- 5
1) 医療の成熟度の高まりとともに,人材管理,技術管理,財務管理のバランスが求められるようになり,医師の生涯学習の一環として経営学習得の重要性は高まっている.2) 経営学は医学部の卒前・卒後教育のなかで学ぶ機会が少なく,多忙な生活の中で自身のキャリアパスを中断することなく学習する方法として,遠隔学習は有用な手段である.3) 中途退学等を防ぐためには,受講側の時間管理やモチベーションの維持とともに,提供側の管理運営システムの構築やリアリティを高める工夫が必要である.
1 0 0 0 P1405 上流設計の重要性とその手法
- 著者
- 小林 孝 吉村 忍 Jeong M. J.
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 設計工学・システム部門講演会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2003, pp.174-176, 2003
- 被引用文献数
- 2
1 0 0 0 1型ヒト免疫不全ウイルスのVpr蛋白質の構造と機能に関する研究
HIVのインテグラーゼに対するマウスモノクローナル抗体を作製し、このマウスモノクローナル抗体から単鎖抗インテグラーゼ抗体分子(scAbE)を作製した。scAbEとHIVのアクセサリータンパク質であるVprとの融合タンパク質(scAbE-Vpr)、およびVprと結合することが明らかになっているペプチドモチーフ(WxxF)を付加したscAbE分子(scAbE-WxxF)を作製した。さらにscAbEとHIVのキャプシッドタンパク質(CA)との融合タンパク質(scAbE-CA)も作製した。これらタンパク質を発現するヘクターDNAをHIV infectious clone DNA(pLAI)とともにヒト細胞293Tにtransfectして培養上清中のウイルスを回収した。ウイルス粒子のタンパク質について、ウェスタンブロット法で調べたところscAbE-VprとscAbE-WXXFは効率よくウイルス粒子内に取り込まれていた。しかし、scAbEあるいはscAbE-CAはウイルス粒子には取り込まれなかった。これらウイルスの感染性をMAGIアッセイ法にて調べた。同じ量のRT活性で比較した場合、野生型ウイルスに比べてscAbE-Vprを取り込んだウイルスとscAbE-WxxFを取り込んだウイルスとでは、感染性が最大で、それぞれ10^3倍、10^4倍低下した。scAbE-WxxFを安定に発現するHeLa細胞を樹立できたが、その一方で、scAbE-Vprを安定に発現するHeLa細胞は得られなかった。このようにウイルス粒子に取り込まれてそのウイルス粒子の感染性を低下せしめる分子は全く新規の抗ウイルス治療分子であるので、packageable ativiral therapeutics(PAT)と命名した。scAbE-Vprとは異なりscAbE-WxxFは細胞毒性を呈さず、より理想的なPAT分子と思われた。この分子はAIDSの遺伝子治療に応用できるだろう。
1 0 0 0 OA 国際裁判における文化的考慮の意義
- 著者
- 高崎 理子
- 出版者
- 中央大学大学院事務室
- 巻号頁・発行日
- 2019-03-15
【学位授与の要件】中央大学学位規則第4条第1項【論文審査委員主査】西海 真樹(中央大学法学部教授)【論文審査委員副査】北村 泰三(中央大学法務研究科教授),宮野 洋一(中央大学法学部教授),目賀田 周一郎(中央大学法学部教授),中坂 恵美子(中央大学文学部教授)
はじめに大腿骨寛骨臼インピンジメント(femoroacetabular impingement;FAI)は, 2003年にGanzらによって新たに提唱された概念であり,大腿骨や寛骨臼の形態 異常により,インピンジ(衝突)することで股関節痛が誘発され,さらには股関節 可動域制限を生じる。股関節唇損傷や変形性股関節症の一因として,広く認識さ れるようになった。 FAIは形態により,①大腿骨頚部の骨性隆起によるcam type,②寛骨臼縁の過被 覆によるpincer type,③その両者が併存するmixed typeの3タイプに分類される。 最初の治療は,投薬,リハビリテーションなどの保存療法が中心であるが,そ れでも改善しない場合,あるいはエリートスポーツ選手などでは手術療法が選択 肢の1つとなる。手術は,寛骨臼と大腿骨の膨隆部分を切除してインピンジメント を解消し,またインピンジメントにより損傷した関節唇を修復もしくは再建する が,最近ではより低侵襲な治療として,股関節鏡視下での手術が広く行われるよ うになった。 本稿では,筆者らがFAIの手術において行っているコツについて述べる。
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経レストラン (ISSN:09147845)
- 巻号頁・発行日
- no.446, pp.37-44, 2011-11
飲食業では、20歳代で店長になる人は、珍しくありません。今回の例のように、初めてお店を任された店長は、スタッフとの人間関係で悩むことがあると思います。若くして店長に抜擢される人は、人一倍努力するタイプが多いはず。そのため、経験の浅いパートやアルバイトのスタッフの未熟な点が目に付いて、厳しく指導したくなるかもしれません。