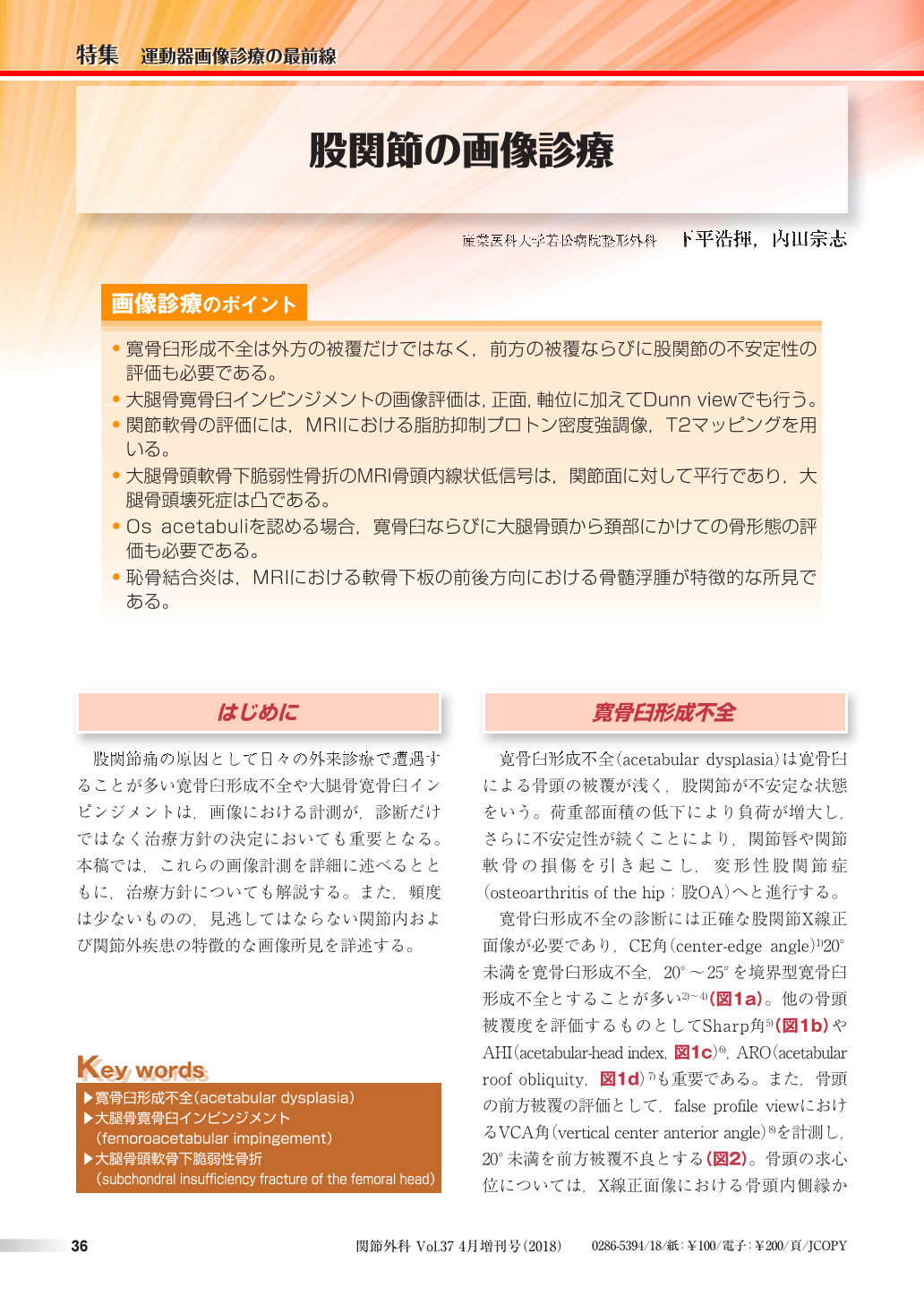1 0 0 0 OA 日本で採集されたシロクラハゼ属の2新種
- 著者
- 明仁親王 目黒 勝介
- 出版者
- The Ichthyological Society of Japan
- 雑誌
- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.4, pp.409-420, 1988-02-25 (Released:2011-02-23)
- 参考文献数
- 6
ロクラハゼ属の2種キマダラハゼAstrabe flavima-culataとシマシロクラハゼA. fasciataを新種として記載し, シロクラハゼ属の模式種であり, 今まで知られていた唯一の種であるシロクラハゼA. lactisellaについても前2種と比較して再記載した.キマダラハゼは日本産魚類大図鑑の中でキマダラハゼAstrabe sp.として明仁親王 (1984) が解説を付したものである.キマダラハゼはシロクラハゼとは眼の上縁にある皮摺の上後部が突出しないこと, 縦列鱗数が少ないこと, 第1背鰭前方と腹部に鱗があること, 胸鰭基部を通る白色横帯の幅が狭いこと, 生時には胸鰭基部を通る白色横帯を除き, 暗褐色地に黄色模様が見られることによって区別される.シマシロクラハゼはシロクラハゼとは横列鱗数が少ないこと, 体側の鱗のある部分の幅が狭いこと, 胸鰭基部を通る白色横帯の幅が狭いこと, 第1背鰭前部から体の腹側に向かう白色横帯があることによって区別される.この度の標本の調査により, Snyder (1912) が記録した種子島産のA. lactisellaはキマダラハゼであり, 本間・田村 (1972) が記録した佐渡島達者産のシロクラハゼはシマシロクラハゼであることが判明したので, これらの標本はそれぞれの種の副模式標本とした.また道津.塩垣 (1971) がシロクラハゼとして扱ったものの中, 標本を調べることが出来た鹿児島県馬毛島産のものはキマダラハゼであった.長崎県野母崎産の標本は図から判断するとシマシロクラハゼと考えられる.明仁親王 (1984) のシロクラハゼとキマダラハゼの解説は訂正しなければならない.
- 著者
- 石塚 正英
- 出版者
- 特定非営利活動法人 頸城野郷土資料室
- 雑誌
- 頸城野郷土資料室学術研究部研究紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.6, pp.1-21, 2021
- 著者
- 田岡 久雄
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会誌 (ISSN:13405551)
- 巻号頁・発行日
- vol.140, no.1, pp.18-19, 2020
<p>1.はじめに</p><p>原島文雄氏は,ロボット工学,制御工学,電気工学分野の研究の第一人者として,国内外を問わず第一線にて活躍されるとともに,東京都立科学技術大学,東京電機大学,首都大学東京の学長を歴任された。</p><p>2.聞き取りの概要</p><p>2.1 生い立ち</p><p>原島文雄氏は1940年東京都に生まれ,生後間もなく,</p>
1 0 0 0 部位別・疾患別画像診療の最前線 股関節の画像診療
<画像診療のポイント>●寛骨臼形成不全は外方の被覆だけではなく、前方の被覆ならびに股関節の不安定性の評価も必要である。●大腿骨寛骨臼インピンジメントの画像評価は、正面、軸位に加えてDunn viewでも行う。●関節軟骨の評価には、MRIにおける脂肪抑制プロトン密度強調像、T2マッピングを用いる。●大腿骨頭軟骨下脆弱性骨折のMRI骨頭内線状低信号は、関節面に対して平行であり、大腿骨頭壊死症は凸である。●Os acetabuliを認める場合、寛骨臼ならびに大腿骨頭から頸部にかけての骨形態の評価も必要である。●恥骨結合炎は、MRIにおける軟骨下板の前後方向における骨髄浮腫が特徴的な所見である。
1 0 0 0 OA 高圧自家用設備の雷サージ解析例と雷保護対策について
- 著者
- 大崎 栄吉
- 出版者
- 一般社団法人 電気設備学会
- 雑誌
- 電気設備学会誌 (ISSN:09100350)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.3, pp.188-191, 2017 (Released:2017-03-17)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 OA 地方圏の乗合バス需要に関する実証分析
- 著者
- 宇都宮 浄人
- 出版者
- 日本交通学会
- 雑誌
- 交通学研究 (ISSN:03873137)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.91-98, 2013 (Released:2019-05-27)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 1
本稿では、地方圏の乗合バスについて、1985年度から2009年度までの県別のパネルデータを整備し、需要関数を推計する。この結果、バスの需要は、運賃や所得、バスのサービス水準などが影響していること、乗用車がバスの代替手段として影響を与えていることなどが明らかになる。バス需要の価格弾力性は、絶対値が1より小さく、規制緩和前後からの運賃引下げ局面では弾力性が低下する傾向にあるが、今後、バスという公共交通利用を促進すると言う観点からは、バス事業単体として増収が見込めるものではなくとも、公的な助成も活用した運賃の引下げ、バスのサービス水準の向上が政策課題となる。
1 0 0 0 OA 江戸時代,静岡北部井川村における大面積伐採
- 著者
- 高尾 和宏 大村 寛
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 日本森林学会誌 (ISSN:13498509)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.2, pp.121-125, 2007 (Released:2008-05-21)
- 参考文献数
- 13
17世紀,江戸時代の元禄期に,江戸町人の紀伊国屋文左衛門と駿府町人の松木屋郷蔵は,共同で幕府御用材の伐採と運材を請け負った。御用材の伐採場所は,静岡県中央部に位置する大井川上流部の森林であった。その伐採期間は元禄5年(1692年)から元禄13年(1700年)までの9年間で,幕府へ納入した材積は6万尺締(20,160m3)である。御用材は,駿河湾まで大井川を管流され,駿河湾から江戸湾まで船輸送された。大井川での管流は,木材の損傷が大きく,材引取りの合格率は低かった。また,労務者の賃金が低かったことから,収入を得るために細い立木までも伐採をしたとされている。このため,推定3,600haの森林が皆伐状態にされた。御用材の伐採場所は,3,000m級の高山に囲まれた急峻な森林地域で,静岡県内でも降水量の多い地域である。
1 0 0 0 OA 在宅中心静脈栄養患者における院内セレン製剤の投与量についての検討
- 著者
- 田附 裕子 米山 千寿 塚田 遼 當山 千巌 東堂 まりえ 岩崎 駿 出口 幸一 阪 龍太 上野 豪久 和佐 勝史 奥山 宏臣
- 出版者
- 日本外科代謝栄養学会
- 雑誌
- 外科と代謝・栄養 (ISSN:03895564)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.100-106, 2021 (Released:2021-05-15)
- 参考文献数
- 16
われわれは, 2019年の市販セレン製剤の販売まで, 低セレン血症を認める在宅中心静脈栄養(HPN)患者に対して院内調剤のセレン注射剤(セレン製剤)の提供を行ってきたので, その投与量と安全性について報告する. 対象および方法 : 2019年末においてセレン製剤を6カ月以上当科で継続処方している27名のHPN患者を対象とし, セレン製剤の使用量, 使用期間, 血清セレン値の変動, 有害事象の有無などを後方視的に検討した. 結果 : 患者の年齢は2~78歳(中央値22歳)で, うち16歳以上は17例であった. 基礎疾患の内訳では短腸症が13例と最も多かった. 血中セレン値をモニタリングしながら正常値を目指して投与した. 最終的に1日のセレン投与量は, 市販製剤の推奨(2μg/kg/日)より多く, 25~200μg/dL/日(4μg/kg/日)で, 血清セレン値(正常値:13‐20μg/dl)は8.3‐23μg/dL(中央値14.8μg/dL)で調整された. 血清セレン値に変動はあるが有害事象は認めなかった. まとめ : HPN患者におけるセレン製剤の必要量は市販製剤の推奨量より多く, また長期投与が必要であった. 市販セレン製剤の販売によりセレン製剤の供給は安定したが, 長期投与の症例では今後も血清セレン値を定期的に確認し, セレン製剤の投与量の調整が必須と思われる.
1 0 0 0 OA 中堅看護師の職業継続に関する文献検討-「離職」と「職業継続」の理由に焦点をあてて-
- 著者
- 中野 沙織 岩佐 幸恵
- 出版者
- 国立大学法人 徳島大学医学部
- 雑誌
- The Journal of Nursing Investigation (ISSN:13483722)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1-2, pp.10-22, 2019-03-31 (Released:2019-04-19)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 2
要 旨 目的:本研究は,日本における中堅看護師を対象にした先行文献から,中堅看護師の離職と職業継続に影響を与える要因を明らかにし,職業継続支援への示唆を得ることを目的とする.方法:文献は,「医学中央雑誌Web(ver.5)」,「メディカルオンライン」,「CiNii」を使用し,「看護師and離職」,「中堅看護師and離職」,「中堅看護師and職業継続」,「中堅看護師and職務継続」というキーワードで検索をした.検索の範囲は,2005年から2017年までとした.対象文献は,「辞めたいと思った理由」と「働き続ける理由」について記載がある21文献で,「辞めたいと思った理由」と「働き続ける理由」を類似性に基づいて帰納的に分類し,カテゴリー化を行った.結果:中堅看護師が「辞めたいと思った理由」として,【キャリアプランとの不一致】【やりがい不足】【人間関係によるストレス】【労働環境が悪い】【看護実践能力についての不安】【自己効力感の形成阻害】【特に働き続ける理由がない】のコアカテゴリーが抽出された.また,中堅看護師が「働き続ける理由」として,【キャリアプランとの一致】【やりがいがある】【良好な人間関係】【労働環境が良い】【看護実践能力についての自信】【自己効力感を高める体験】【特に辞める理由がない】【ストレス・マネージメント】のコアカテゴリーが抽出された.考察:看護師が離職を考える要因には,キャリアプランや,仕事のやりがい,職場の人間関係,職場の労働環境,自身の看護実践能力と自己効力感が大きく関わっており,それらは共通して職務継続の要素にもなっていた.しかし,ストレス・マネージメントは,職業継続にだけみられる要因であり,効果的なストレス・マネージメントは,離職を思い留まらせることが示唆された.中堅看護師の職業継続には,ストレス・マネージメントに着目した支援が重要である.
1 0 0 0 IR 山姥とハッグ妖精の比較研究 : 日本とブリテン諸島における民間信仰の女神とその源流
1 0 0 0 OA 漆-日本・アジアから世界資源に
- 著者
- 熊野谿 從
- 出版者
- マテリアルライフ学会
- 雑誌
- マテリアルライフ学会誌 (ISSN:13460633)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.4, pp.151-160, 2001-10-31 (Released:2011-04-19)
- 参考文献数
- 43
- 著者
- 三木 千壽 町田 文孝 伊藤 博章
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集A1(構造・地震工学)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.2, pp.283-293, 2011
- 被引用文献数
- 3
こガセット継手に生じる疲労き裂の応急補修対策および疲労き裂の発生を抑制するための応力改善対策について,大型の梁試験体を用いて検討した.ストップホール,ストップホールの高力ボルトによる締め付けおよび添接板補修をそれぞれ対策方 法とし,疲労き裂が発生した箇所に用いて,その効果を確認した.また,ガセット継手の疲労き裂の発生の抑制を目的として,当て板補強による応力改善についても検討した.疲労き裂の補修対策としては,疲労き裂先端にストップホールを明け,その孔を用いて添接板補修を行う対策が最も効果があること,ガセット継手部の当て板による応力改善では,応力集中部に高力ボルトが配置されることにより,応力の低減効果が上がることが確認された.
1 0 0 0 「反日教育」とはなにか
- 著者
- 吉岡 吉典
- 出版者
- 新日本出版社
- 雑誌
- 文化評論 (ISSN:0521789X)
- 巻号頁・発行日
- no.56, pp.77-90, 1966-06
1 0 0 0 押しつけられた「これでもか」の反日教育
- 著者
- 深田 萌絵 小林 ゆみ
- 出版者
- ワック
- 雑誌
- Will : マンスリーウイル
- 巻号頁・発行日
- no.172, pp.293-301, 2019-04
1 0 0 0 韓国高校生は「反日教育」に反対します
- 著者
- 秋田 真
- 出版者
- 経済教育学会
- 雑誌
- 経済教育 (ISSN:13494058)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.37, pp.138-144, 2018-09-30 (Released:2019-05-13)
小学校社会科の授業で扱われる基本的人権の尊重を児童に主体的に学ばせるための試みとして,J.ロールズが提唱した「無知のベール」を用いることの効果を検証した。青森県内の小学6年生に,経済的公正を勘案させる教材を用いて,4つの立場(会社社長,サラリーマン,大学生,失業者)でロール・プレイングをさせた。プレイでは,税制や年金制度について意見を述べ,政策判断をするよう指示した。その後に,「無知のベール」を被り自分の立場が分からない状況で,再び,同様の政策判断をさせた。その結果,「無知のベール」を用いることによって,児童の判断がより基本的人権を重視したものに変化することが確認された。
1 0 0 0 OA 自閉症の子を成人に育てるまでの母親心理
- 著者
- 宇津 貴志 伊藤 弥生
- 出版者
- 九州産業大学 人間科学会
- 雑誌
- 人間科学 (ISSN:24344753)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.15-26, 2019 (Released:2019-03-29)
- 参考文献数
- 16
自閉症児の母親の長期的心理過程の探索的理解を試みた。先行研究を精査し,①子の発達や将来への不安,②情緒的混乱,③とらわれ,④否認/気にしない,⑤努力/あがき,⑥障害の認知/あきらめ,⑦手ごたえ,⑧安堵,⑨受容という心理変数を用意し,それぞれ三つずつを否定,中間,肯定的心理とした。仮説Ⅰ:①~⑨の流れで展開する。仮説Ⅱ-A:常に肯定・中間・否定の多層的心理が存在する。Ⅱ-B:徐々に肯定的心理が多い状態へ移行する。Ⅱ-C:肯定的感情が多い状態に移行後は発達の節目に否定的感情が強まる。自閉症児の母親8名に半構造化面接を実施した。その結果,仮説Ⅰ:概ね支持されたが,誕生直後から障害が強く疑われる場合には障害告知が『安堵』をもたらし『障害の認知』を速やかに生じさせたことが想定外であった。仮説Ⅱ-A,C:概ね支持されたが,自閉症児とその母親に適したサポートを必ずしも専門家が提供しなかったことがⅡ-Cの特筆点であった。仮説Ⅱ-B:安心できない状態は続き,肯定的心理が多い状態へ移行する時期は定め難かった。
1 0 0 0 OA 憲法に関する主な論点(第6章司法)に関する参考資料
- 著者
- 衆議院憲法審査会事務局
- 出版者
- 衆議院
- 巻号頁・発行日
- 2013-04
1 0 0 0 OA 憲法に関する主な論点(第5章内閣)に関する参考資料
- 著者
- 衆議院憲法審査会事務局
- 出版者
- 衆議院
- 巻号頁・発行日
- 2013-04
- 著者
- Hirosuke Takahashi Masako Nagata Tomohisa Nagata Koji Mori
- 出版者
- Japan Society for Occupational Health
- 雑誌
- Journal of Occupational Health (ISSN:13419145)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.e12205, 2021 (Released:2021-03-25)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 5
Objectives: The working-age population is rapidly declining in Japan, so the government has adopted “health and productivity management” (HPM). This policy initiative aims to encourage corporations to view health promotion activities as an investment in their employees’ health. The objective of this study was to examine the association between organizational factors and knowledge of the organization's effectiveness and program participation levels, and to understand the factors that affect effectiveness of corporations’ activities.Methods: We used data from all corporations that completed the HPM Survey Sheets in 2018 (n = 1800). The explanatory variables were organizational factors: written company-wide policy, agenda item at management-level meetings, regular education for managers, and full-time occupational health staff. The outcome variables were knowledge of the corporation's status on the effectiveness indicators (employees’ exercise habits, risk for high blood pressure, visiting hospital after a health examination, and long-term sickness absences) and rates of participation in four areas (health education, exercise program, dietary program, and influenza vaccination). The associations between organizational factors and knowledge on effectiveness indicators and rates of program participation were analyzed using multiple logistic regression analysis.Results: All the organizational factors were related to knowledge of effectiveness indicators, but only some were associated with the program participation indicators in the model, including all explanatory variables.Conclusion: Enhancing organizational factors may lead to improvement of HPM programs and higher program participation among employees in corporations.