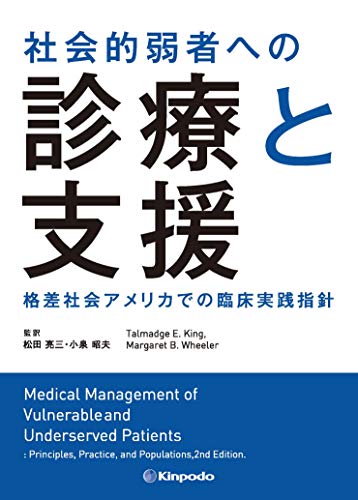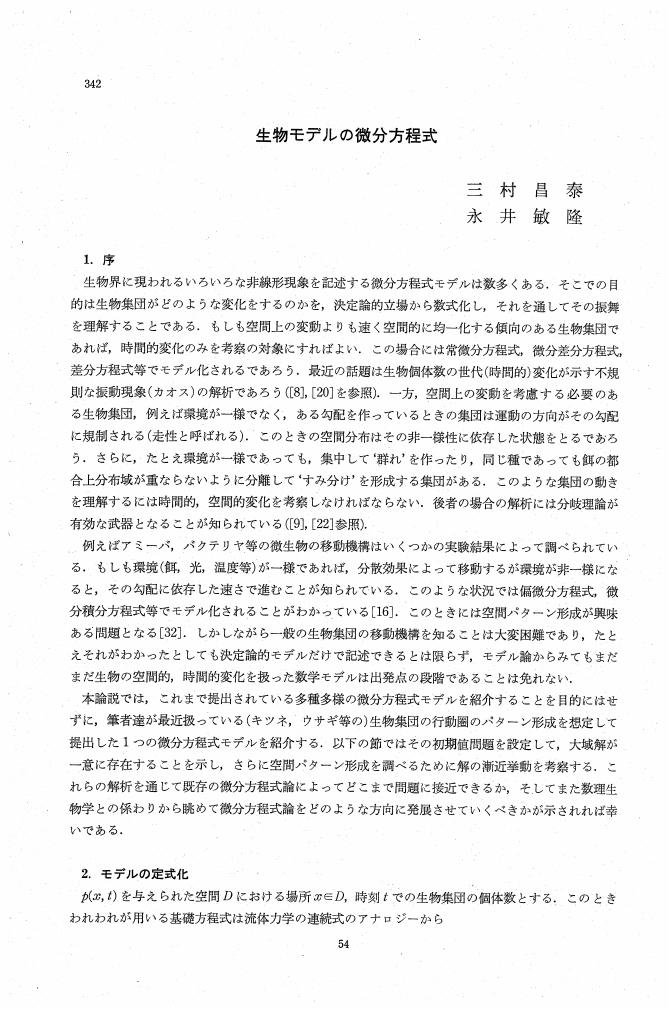1 0 0 0 航空戦力 : その発展の歴史と戦略・戦術の変遷
1 0 0 0 OA イギリス文学に於ける<窓> : その翻訳と文化的背景
- 著者
- 三谷 康之
- 出版者
- 東洋女子短期大学
- 雑誌
- 東洋女子短期大学紀要 = The Toyo review (ISSN:02865254)
- 巻号頁・発行日
- no.21, pp.13-26, 1989-03-15
1 0 0 0 OA 孤独感の内包的構造に関する仮説
- 著者
- 落合 良行
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.3, pp.233-238, 1982-09-30 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1 1
1 0 0 0 自殺未遂者の生命保険の加入状況について
- 著者
- 岩崎 康孝 黒沢 尚
- 出版者
- 日本保険医学会
- 雑誌
- 日本保険医学会誌 (ISSN:0301262X)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, pp.275-279, 1990-12-15
第三次救急施設に搬入される自殺未遂症例100例の保険加入状況を調査した。さらに症例の他の属性(性,精神疾患圏,自殺企図手段,家族の有無,配偶者の有無,子供の有無)との関係を調べた。対象となった自殺未遂者症例の生命保険加入率は33%であり,一般人口に比べ低かった。生命保険加入率と患者の属性との関連では,精神疾患圏,自殺企図手段,家族の有無,配属者の有無,子供の有無とは有意な相関を認めた。性との有意な関連は認めなかった。生命保険加入率の低い群は,精神疾患圏では,精神分裂病圏症例,自殺企図手段では服薬による症例,家族の無い症例,子供の無い症例,配偶者の無い症例であった。特に服薬自殺企図症例は性,精神疾患圏,家族・配偶者・子供の有無などの要因によって生命保険加入率が低いとは言えず,他の方法を選択する自殺企図症例とは異なる母集団を形成している可能性を示唆した。
- 著者
- Yasuo Uchida
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.4, pp.465-473, 2021-04-01 (Released:2021-04-01)
- 参考文献数
- 41
- 被引用文献数
- 6
From the viewpoint of drug discovery, it is an important issue to elucidate the drug permeability at the human central nervous system (CNS) barriers and the molecular mechanisms in the cells forming CNS barriers especially during CNS diseases. I introduced quantitative proteomics techniques into the blood–brain barrier (BBB) study, then quantitatively investigated the transport system at the human BBB and clarified the quantitative differences in protein expression levels and functions of transporters and receptors between animals and humans, or in vitro and in vivo. Based on the difference in the absolute expression level of transporters between in vitro and in vivo, I demonstrated that the drug efflux activity of P-glycoprotein (P-gp) at in vivo BBB can be accurately reconstructed from the in vitro system, not only in mouse models but also monkeys similar to humans and pathological conditions. Furthermore, I discovered Claudin-11 as another tight junction molecule expressed at the CNS barriers, and clarified that it contributes to the disruption of the CNS barriers in multiple sclerosis. Furthermore, it was also elucidated that the P-gp dysfunction causes excessive brain entry of glucocorticoid which causes a nerve damage in cerebral infarct, and it can be suppressed by targeting Abl/Src kinases. These suggest that targeting the tight junctions and transporters, which are important molecules at the CNS barriers, would potentially lead to the treatment of CNS diseases. In this review, I would like to introduce a new CNS barrier study opened by quantitative proteomics research.
1 0 0 0 OA 最近の大手私鉄の不動産事業について(その4)阪急電鉄の不動産事業について
- 著者
- 森谷 英樹 Hideki Moriya
- 出版者
- 敬愛大学経済学会
- 雑誌
- 敬愛大学研究論集 = Keiai University staff papers (ISSN:09149384)
- 巻号頁・発行日
- no.76, pp.3-21, 2009-12
- 著者
- Yoshihiro Kobashigawa Mana Namikawa Mitsuhiro Sekiguchi Yuki Inada Soichiro Yamauchi Yuu Kimoto Kyo Okazaki Yuya Toyota Takashi Sato Hiroshi Morioka
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.1, pp.125-130, 2021-01-01 (Released:2021-01-01)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 7
The constitutive active/androstane receptor (CAR) is a nuclear receptor that functions as a xenobiotic sensor, which regulates the expression of enzymes involved in drug metabolism and of efflux transporters. Evaluation of the binding properties between CAR and a drug was assumed to facilitate the prediction of drug–drug interaction, thereby contributing to drug discovery. The purpose of this study is to construct a system for the rapid evaluation of interactions between CAR and drugs. We prepared recombinant CAR protein using the Escherichia coli expression system. Since isolated CAR protein is known to be unstable, we designed a fusion protein with the CAR binding sequence of the nuclear receptor coactivator 1 (NCOA1), which was expressed as a fusion protein with maltose binding protein (MBP), and purified it by several chromatography steps. The thus-obtained CAR/NCOA1 tethered protein (CAR-NCOA1) was used to evaluate the interactions of CAR with agonists and inverse agonists by a thermal denaturation experiment using differential scanning fluorometry (DSF) in the presence and absence of drugs. An increase in the melting temperature was observed with the addition of the drugs, confirming the direct interaction between them and CAR. DSF is easy to set up and compatible with multiwell plate devices (such as 96-well plates). The use of DSF and the CAR-NCOA1 fusion protein together allows for the rapid evaluation of the interaction between a drug and CAR, and is thereby considered to be useful in drug discovery.
1 0 0 0 IR 大学院生対象情報教育コンテンツの開発と評価
- 著者
- 西端 律子 宮本 友介 能川 元一 能川 元一 関 嘉寛 川野 英二 Nishibata Ritsuko Miyamoto Yusuke Nogawa Motokazu Utsumi Hirofumi Seki Yoshihiro KAWANO Eiji ニシバタ リツコ ミヤモト ユウスケ ノウガワ モトカズ ウツミ ヒロフミ セキ ヨシヒロ カワノ エイジ
- 出版者
- 大阪大学大学院人間科学研究科
- 雑誌
- 大阪大学大学院人間科学研究科紀要 (ISSN:13458574)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, pp.93-111, 2006
1 0 0 0 OA 肥育去勢牛における胆嚢内胆汁量および胆汁酸組成
- 著者
- 蓮沼 俊哉 久保 博文 伊奈 隆年 廣瀬 富雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本畜産学会
- 雑誌
- 日本畜産学会報 (ISSN:1346907X)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.3, pp.313-318, 2015-08-25 (Released:2015-09-30)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1 1
食肉処理場に出荷されて肝臓に異常所見を認めなかった肥育去勢牛524頭の胆嚢内胆汁について胆汁量の測定を行い,品種,枝肉重量,および出荷日齢との関連性について検討した.また,そのうち111頭について胆汁酸組成の分析を行った.胆汁量は,品種による違いはあるものの,枝肉重量や出荷日齢との関連性は認められなかった.胆汁酸組成は,品種による差はないが,いずれの品種においても胆汁酸濃度の標準偏差が大きく,個体によって胆汁酸組成がかなり異なることが明らかになった.このことは,腸内細菌の持つ胆汁酸合成能力の違いによって生じていると考えられ,育成期での給与飼料や疾病,消化管の炎症の有無より腸内細菌叢が影響を受けた結果,出荷時の胆汁酸組成に影響を与える可能性が推察された.
1 0 0 0 社会的弱者への診療と支援 : 格差社会アメリカでの臨床実践指針
- 著者
- Talmadge E. King Margaret B. Wheeler編
- 出版者
- 金芳堂
- 巻号頁・発行日
- 2020
1 0 0 0 OA 横須賀市震災誌 : 附・復興誌
- 著者
- 横須賀市震災誌刊行会 編
- 出版者
- 横須賀市震災誌刊行会
- 巻号頁・発行日
- 1932
1 0 0 0 OA 生物モデルの微分方程式
- 著者
- 三村 昌泰 永井 敏隆
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.342-354, 1981-10-30 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 32
1 0 0 0 OA 米国におけるメディアとジェンダー 若年女性のエンパワーメントの視点から
- 著者
- 野澤–竹田 努 閻 美芳 小寺 祐二 青山 真人 西尾 孝佳 小笠原 勝
- 出版者
- 日本雑草学会
- 雑誌
- 雑草研究 (ISSN:0372798X)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.129-139, 2020
<p>地域住民の雑草管理能力が過疎高齢化に伴い低下するなかで,一般市町村道から交通量の多い広域農道や土地改良事業で設置された農業用水路の畦畔に至るまで,地域自治体の雑草管理に関する負担がますます増加する傾向にある。また,イノシシなどの鳥獣害が中山間地域を中心に問題になっている。そこで,地方行政担当者が雑草や鳥獣害に対してどのような問題意識を有し,いかに対処しているのかを明らかにする目的で,栃木県全域の市町を対象としたアンケートを実施した。2018年7月にアンケート調査票を,栃木県内の全25市町の雑草と鳥獣害対策に関連する137部署に返信用封筒と共に郵送し,回答を83部署から得た。集計は複数回答の場合も単純に加算し評価した。また,回答した市町の部署を生活系部署,土木系部署,農業系部署に分けて,部署間における問題意識の共通性を解析した。これらの結果から,雑草と鳥獣害対策において,殆どの市町が人員,予算不足および土地の権利に関する問題を抱えており,限られた予算の中での問題解決には生活系部署を中核にした部署連携が有効であることが示唆された。</p>
1 0 0 0 モデル植物となったエノコログサ―その雑草生物学への適用
- 著者
- 福永 健二 大迫 敬義
- 出版者
- 日本雑草学会
- 雑誌
- 雑草研究 (ISSN:0372798X)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.140-149, 2020
1 0 0 0 OA 寄生植物ストライガの養水分奪取機構の解明 生存戦略のために魔女の雑草が獲得した変異
- 著者
- 岡本 昌憲 藤岡 聖 杉本 幸裕
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.138-140, 2020-03-01 (Released:2021-03-01)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 放牧草地における雑草管理の今後についての問題提起
- 著者
- 北川 美弥
- 出版者
- 日本草地学会
- 雑誌
- 日本草地学会誌 (ISSN:04475933)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.31-33, 2020-04
放牧草地は牧草が生産される畑であるが,野菜等が生産される一般の畑とは異なる点を持つ。例えば,(1)造成後は,長期間耕起されない,(2)家畜が放牧される,(3)地形が複雑,といった点である。このため雑草管理においても,一般の畑とは異なった視点で対応することが求められる。これまで,日本草地学会誌において草地の雑草管理についてさまざまな報告がなされている。しかし近年,専門とする研究者は減少し,報告数も減っている。2019年度日本草地学会広島大会の発表における関連発表は4課題である。一方で,雑草管理に苦慮している牧場・農家は依然として多い。加えて地球温暖化の影響などから各雑草の生育地域に変化が生じているのみならず,新たな雑草の侵入も報告されている。これまでの研究結果をもとに対応することが可能な問題もあるが,現状に即した対応のためには,継続的な研究は不可欠である。そこで,放牧草地における雑草管理について整理を行い,これを通じて今後必要な対応を検討するきっかけとしたい。
1 0 0 0 OA 精密加工技術プラスアルファによる新展開を目指して
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.2, pp.167-168, 2014-02-05 (Released:2014-02-05)