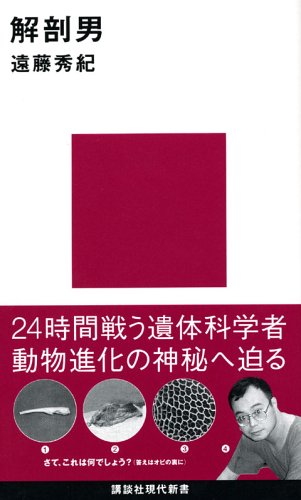1 0 0 0 鍵盤を駆ける手 : 社会学者による現象学的ジャズ・ピアノ入門
- 著者
- D. サドナウ著 徳丸吉彦 村田公一 卜田隆嗣訳
- 出版者
- 新曜社
- 巻号頁・発行日
- 1993
1 0 0 0 水不足が世界の食糧生産に及ぼす影響に関する研究
- 著者
- 乃田 啓吾 岡根谷 実里 沖 大幹
- 出版者
- 水文・水資源学会
- 雑誌
- 水文・水資源学会研究発表会要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.25, 2012
水資源は人間生活にとって必要不可欠なものであるが、将来的な人口増加、生活水準の向上によって、その需要が逼迫すると言われている。特に淡水利用の約70%を占める農業用水の不足は、世界的な食糧問題を引き起こすものと懸念されている。元来、水が時間的・空間的に偏在する資源であることに加え、農業生産システムは気候、作物等によって地域・国ごとに大きく異なる。そこで本研究では、水不足が引き起こす食糧問題に注目し、その影響を受けやすい地域を特定することを目的とする。具体的には、食糧生産のために使用された水の総量を農業投入水量定義し、これと農業生産量に正の相関が認められる国を、食糧生産が水不足の影響を受けやすい国として判別する。人口1,000万人以上かつデータを入手できた155カ国を解析の対象とした。国ごとに各年の農業投入水量と主食作物の農業生産量の相関係数Rを求め、R>0.33の場合に水不足によって食糧生産が減少する国と判定した。ここで、主食作物とは小麦、トウモロコシ、米の三種の穀物のうち、最も生産量の多いものとした。 米を主食作物とする国は、他の二作物を主食作物とする国比べて、水不足により食糧生産が減少する国が少なかった。米は他の二作物と異なり、主に水田で栽培される。水田は貯水機能により、降雨を有効に利用できるため、水不足による農業生産量の減少が生じにくいものと考えられる。日本のように十分な灌漑設備を有する国や東南アジアのように降水量が多い地域では、降水量の多い年には日照が不足し農業生産量が減少することから、農業投入水量と農業生産量の間には負の相関がみられた。また、インドは米を主食作物としながらも水不足の影響を受けやすい国として判定された。インドは将来の人口増加による水需要の逼迫が特に懸念されている国であり、食糧生産が大きな影響を受ける可能性が高いことが確認された。 一方、小麦を主食作物とする国では、先進国・発展途上国問わず多くの国で水不足による農業生産量の減少が生じると判定された。1960年代の緑の革命以降、小麦の単収は、窒素肥料の投入により飛躍的に向上したが、広範囲で渇水が生じた場合、大幅に総生産量が減少する可能性が示唆された。
1 0 0 0 National technical report
- 著者
- 松下電器産業 [編]
- 出版者
- 松下電器産業
- 巻号頁・発行日
- 1955
1 0 0 0 OA マウスの皮膚表面における蚊の穿刺時の下唇の観察
- 著者
- 北田 博之 酒井 裕也 駒走 仁哉 高橋 智一 鈴木 昌人 青柳 誠司 細見 亮太 福永 健治 歌 大介 高澤 知規 引土 知幸 川尻 由美 中山 幸治
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会学術講演会講演論文集 2018年度精密工学会秋季大会
- 巻号頁・発行日
- pp.742-743, 2018-08-20 (Released:2019-02-20)
蚊の針は細いが穿刺時に折れず,皮膚にたわみが生じない.本研究では,麻酔したマウスの皮膚に対する蚊の穿刺を顕微鏡で観察し,蚊の針が皮膚を貫く仕組み,ならびに口針を包む鞘である下唇の役割を解明しようと試みた.その結果,皮膚表面における蚊の針の挿入時の下唇の動きを観察できた.
1 0 0 0 OA 半田元夫・今野国雄著『キリスト教史I、宗教改革以前』(山川出版社、一九七七年、五〇四頁+二八頁) 藤代泰三著『キリスト教史』(日本YMCA同盟出版部、一九七九年、六三二頁+四六頁) 歴史神学
- 著者
- 宮谷 宣史
- 出版者
- 日本基督教学会
- 雑誌
- 日本の神学 (ISSN:02854848)
- 巻号頁・発行日
- vol.1980, no.19, pp.107-112, 1980-12-25 (Released:2009-09-16)
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 喜多崎 親
- 出版者
- 国立西洋美術館
- 雑誌
- 国立西洋美術館年報 = Annual Bulletin of The National Museum of Western Art, Tokyo (ISSN:09190872)
- 巻号頁・発行日
- vol.27-28, pp.51-57, 1996-03-30
1 0 0 0 OA 京都第二赤十字病院小児科における川崎病急性期治療結果について
- 著者
- 清沢 伸幸 小林 奈歩 木村 学 東道 公人 藤井 法子 大前 禎毅 長村 敏生
- 出版者
- 京都第二赤十字病院
- 雑誌
- 京都第二赤十字病院医学雑誌 = Medical journal of Kyoto Second Red Cross Hospital (ISSN:03894908)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.2-11, 2014-12
京都第二赤十字病院小児科に川崎病として1978年4月から2014年6月までに入院し、急性期の治療を行った1,109例(男児650例、女児459例)の治療成績に関する検討を行った。治療プロトコールから4期に分類した。第I期(1978.4~1984.3)は心エコー検査機器がなく病初期の冠動脈評価が出来なかった時期で164例。第II期(1984.4~1994.3)はアスピリン治療を主体とした時期で197例。第III期(1994.4~2003.12)はγグロブリン療法(γ-gl)を行うも、1日用量が統一されなかった時期で212例。第IV期(2004.1~2014.6)は初回投与量を2g/kgとして使用している時期で516例である。γグロブリン療法を行うようになった第III期以降は冠動脈障害を残す割合は著減し、1ヵ月を過ぎても拡大や瘤を残す症例の割合(表3)は第I期が4.3%、第II期が8.1%、第III期が0.9%、第IV期が1%であった。第I期の初回の評価が回復期を過ぎて行っている症例が含まれていることからその割合は第II期と変わらないと考えられる。第III期、第IV期の治療成績は川崎病全国調査成績(拡大1.75%、瘤0.72%、巨大瘤0.018%)からみても極めて優れているもので、巨大瘤はいない。現在、当院で行っている治療プロトコール(表2)は日本小児循環器学会のガイドラインや世界標準とは少し異なっている。γ-glの投与開始時期は少なくとも発症後第5病日まで待つべきである。次に、γ-glの投与時間は24時間以内ではなく、32-36時間かけることである。再投与は原則1回とし、第10病日以内に投与する。アスピリンはγ-gl投与中は併用しない。再投与でも効果がない場合は経過をみることである。結論的にいえば、γ-glの投与の仕方を工夫すれば、血漿交換療法、副腎皮質ホルモン剤、免疫抑制剤、抗TNFα剤の必要性はほとんどないと考える。また、γ-glとアスピリン剤の併用はすべきではない。
1 0 0 0 OA 歴史教育における価値注入回避の論理 : 中等ホルト社会科『新合衆国史』を手がかりとして
- 著者
- 山田 秀和
- 出版者
- 日本教科教育学会
- 雑誌
- 日本教科教育学会誌 (ISSN:02880334)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.4, pp.79-88, 2008-03-25 (Released:2018-05-08)
歴史教育における永続的な問題の一つに,「価値注入」がある。歴史を描こうとすれば,必然的に何らかのものの見方が入り込む。そして歴史を一つの通史として描き,系統的に教授するとき,事実の名のもとに価値を注入する可能性は高くなる。この問題を克服するべく,本研究では,アメリカで開発された中等ボルト社会科『新合衆国史』(第11学年)の分析を通して,歴史教育における価値注入回避の論理を明確にする。分析の結果,以下の二点の方法論を抽出し,具体的な内容編成のしかた(カリキュラムから単元まで)を明らかにした。(1)視点を段階的に変えながら歴史を解釈させることによって,一面的で偏狭な決定論的認識を与えないようにすること。すなわち,様々な角度から因果関係を引き出させることによって,特定の見方に偏った知識が子どもに内面化されるのを防ぐこと。(2)歴史を解釈させる際に,その根拠となる法則的知識(主に社会諸科学から援用される)をたえず明示させ,批判吟味させる過程を学習に組み込むこと。すなわち,法則性を帯びた知識が,明示されないまま,無批判に子どもに内面化されるのを防ぐこと。
1 0 0 0 脳の形態を指標に用いた鰭脚類の適応進化の解析
本年度の研究では、仙台の中新統から産した最古のセイウチ科鰭脚類、Prototaria Planicephala Kohno,1994(以下化石セイウチ)のタイプ標本の頭蓋腔を完全に剖出した上で、脳の印象模型(エンドキャスト)を作製し、各部位の比較神経解剖学的な記載を行なった。この過程で、化石セイウチの大脳表面の各機能単位を決定するため、現生鰭脚類および陸生食肉類との解剖学的特徴を比較検討し、とくに現生食肉類との相同関係に基づいて各大脳溝および大脳回(いわゆる脳の皺)を同定した。さらに、電気神経生理学によって明らかにされている現生食肉類の脳の機能分布との比較から、化石セイウチの脳の機能分布地図の復元を試みた。化石セイウチの脳神経は、現生鰭脚類と異なり嗅神経(嗅球)の発達が比較的よく、嗅感覚は海洋生活への依存度がより強い現生鰭脚類に比べて鋭かったことがわかった。また、三叉神経第2枝(上顎神経)が極めてよく発達しており、上唇部を中心とした上顎神経支配領域の感覚がすでに現生鰭脚類と同程度に発達していたことがわかった。大脳形態については、全体に側方への拡大が目立ち、とくに冠状脳回(前側頭部)が目立って拡大していることから、吻部の触覚機能の強化(洞毛の発達)が推定認された。また、後S字状脳回(最前側頭部)も拡大の傾向が認められることから、顔面の運動機能と感覚を司る領域全体が著しく発達していることが改めて確認できた。しかしながら、初期のセイウチ科鰭脚類が、まず最初に魚食適応したのか、あるいは沿岸域の雑食性であったのかを明かにするために、更に詳しい大脳表面の解析が今後の課題となる。
1 0 0 0 OA イギリスの書評文化(1) : 文化としての書評
- 著者
- 楚輪 松人 Matsuto Sowa
- 出版者
- 金城学院大学
- 雑誌
- 金城学院大学論集. 人文科学編 = Treatises and studies by the Faculty of Kinjo Gakuin College (ISSN:04538862)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.2, pp.1-16, 2006
1 0 0 0 OA 与党による閣法事前審査制の見直しに関する考察
- 著者
- 武蔵 勝宏 Katsuhiro Musashi
- 出版者
- 同志社大学政策学会
- 雑誌
- 同志社政策科学研究 = Doshisha University policy & management review (ISSN:18808336)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.157-170, 2020-03-01
日本の国会は、政府に議事運営権や審議促進手続に関する権限が付与されておらず、凝集性の低い自民党内で造反を回避するためには、事前の調整で政府と与党を一体化する必要性がある。そのため、自民党政権では与党による事前審査が行われ、国会提出の段階から党議拘束がかけられてきた。本稿は、こうした事前審査制に代えて、閣法草案を国会の委員会において予備審査を行う方法を提案し、国会審議の形骸化の解消に取り組むことを提案する。
1 0 0 0 小説テキストを対象とした人物情報の抽出と体系化
- 著者
- 馬場こづえ
- 雑誌
- 言語処理学会第13回年次報告, 2007
- 巻号頁・発行日
- 2007
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 辻村 誠三 Seizo TSUJIMURA
- 出版者
- INSTITUTE OF PHILOSOPHY THE UNIVERSITY OF TSUKUBA
- 雑誌
- 哲学・思想論集 = Studies in philosophy (ISSN:02867648)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.(1)-(13), 1983-03
- 著者
- 青柳 英司
- 出版者
- 宗教法人 真宗大谷派 親鸞仏教センター
- 雑誌
- 近現代『教行信証』研究検証プロジェクト研究紀要 (ISSN:24337536)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.108-135, 2020
1 0 0 0 IR 「教行証」研究の方法論的反省
- 著者
- 日野 環
- 出版者
- 大谷学会
- 雑誌
- 大谷学報 (ISSN:02876027)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, 1957-10
1 0 0 0 中古天台における教行證について
- 著者
- 小方 道憲
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.518-519, 1954