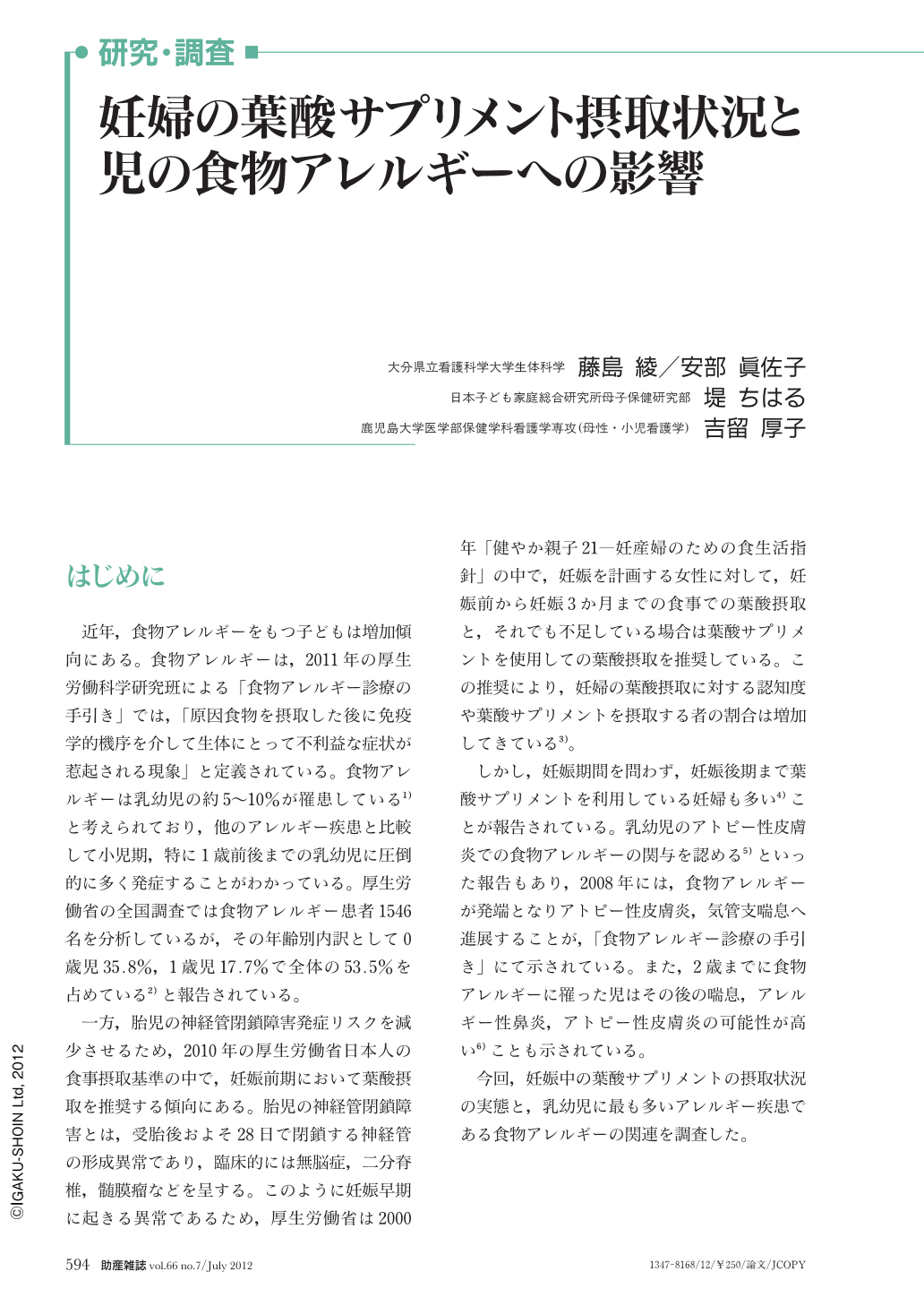1 0 0 0 北日本における地方霊場への寺社分布の影響について
- 著者
- 田上 善夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, pp.53, 2004
_I_ はじめに 中世以降,近世を中心に開創された地方霊場の多くは現在も存続するとともに,さらに新たな開創が続いている。こうした地方霊場の種類,開創年代,範囲,巡拝路の形態,さらに霊場数あるいは霊場密度などには,全国的に差異がみられる。地方の三十三観音霊場などでは,観音像は本堂でも脇侍とされたり,境内の観音堂にまつられたりする。さらに堂庵や神社,石塔などのことも多い。そもそも霊場はその起源においても仏教のみならず修験との深いかかわりが認められ,神仏習合のもとでは観音を本地とする神社も多いため,札所は神社の内や隣接することも多く,さらに背景に民間信仰が認められるものも多い。_II_ 霊場と寺社の調査 北海道から北陸に至る北日本において,主要な地方霊場について施設や景観などを調べるとともに,それらの分布と関連する寺社などの分布との比較をとおして,霊場の開創の要因や経緯などについて明らかにする。まず,歴史が古く代表的な霊場を選び,霊場および札所寺院の位置や景観,宗派などの特色を,現地調査にもとづいて明らかにする。次に,現在の宗教法人の寺院の主要宗派別の分布を明らかにし,それとともに著名神社を選んでその分布も明らかにする。さらに主要仏教宗派の分布が成立した経緯や,著名神社の成立の経緯などにもとづいて,霊場開創地域の宗教的基盤の特色を明らかにする。さらに,それらを通して明らかにされた地方霊場開創にかかわる要因の中から,とくにかかわりが深い山岳信仰について分析を加え,霊場の開創とその地域的差異の検討を試みる。_III_ 地方霊場と寺社分布 各県ほどの規模の霊場では,札所はおよそ平野や盆地の縁である山麓にみられ,札所は岩や沢の傍らなどに設けられている。札所として,真言系寺院をはじめ,天台系や禅系の寺院が多く選ばれているが,修験の寺院もあり,神社境内にある観音堂のこともある。寺院は当該地域の南西部では浄土系,北東部では禅系などが多く,平野では浄土系,山地側では禅系,天台系,真言系が多い。この天台系・真言系寺院は古くから進出し,霊場と深くかかわり,禅系寺院も霊場とのかかわりを保つ。一方神社は,当該地域には八幡社が広く分布し,稲荷社は北部に多く,神明社は南部に,熊野社は内陸部に多い。_IV_ 山岳信仰の影響 とくに熊野社は,熊野三山や天台系と結びつき,霊場とかかわりが深い。もともと巡礼では札所のほかに多くの霊山が参詣されており,巡礼には山地での修行が含まれる。 廻国巡礼は富山では立山に至り,西国・坂東・秩父巡礼は出羽三山参詣と類似のものとみなされていた。東北地方北部でも,地方霊場は山岳霊地に連なり,お山参詣は修験の影響を受けて,山岳信仰の要素を含んでいる。霊場と結びつく,天台系・真言系や熊野社などが深く結びついており,これらは開創年代が古く,周辺に位置し,とくに観音とかかわっている。さらに修験や山岳信仰と結びついており,それらは霊場の基本的性格を形成したと考えられる。
1 0 0 0 妊婦の葉酸サプリメント摂取状況と児の食物アレルギーへの影響
はじめに 近年,食物アレルギーをもつ子どもは増加傾向にある。食物アレルギーは,2011年の厚生労働科学研究班による「食物アレルギー診療の手引き」では,「原因食物を摂取した後に免疫学的機序を介して生体にとって不利益な症状が惹起される現象」と定義されている。食物アレルギーは乳幼児の約5~10%が罹患している1)と考えられており,他のアレルギー疾患と比較して小児期,特に1歳前後までの乳幼児に圧倒的に多く発症することがわかっている。厚生労働省の全国調査では食物アレルギー患者1546名を分析しているが,その年齢別内訳として0歳児35.8%,1歳児17.7%で全体の53.5%を占めている2)と報告されている。 一方,胎児の神経管閉鎖障害発症リスクを減少させるため,2010年の厚生労働省日本人の食事摂取基準の中で,妊娠前期において葉酸摂取を推奨する傾向にある。胎児の神経管閉鎖障害とは,受胎後およそ28日で閉鎖する神経管の形成異常であり,臨床的には無脳症,二分脊椎,髄膜瘤などを呈する。このように妊娠早期に起きる異常であるため,厚生労働省は2000年「健やか親子21―妊産婦のための食生活指針」の中で,妊娠を計画する女性に対して,妊娠前から妊娠3か月までの食事での葉酸摂取と,それでも不足している場合は葉酸サプリメントを使用しての葉酸摂取を推奨している。この推奨により,妊婦の葉酸摂取に対する認知度や葉酸サプリメントを摂取する者の割合は増加してきている3)。 しかし,妊娠期間を問わず,妊娠後期まで葉酸サプリメントを利用している妊婦も多い4)ことが報告されている。乳幼児のアトピー性皮膚炎での食物アレルギーの関与を認める5)といった報告もあり,2008年には,食物アレルギーが発端となりアトピー性皮膚炎,気管支喘息へ進展することが,「食物アレルギー診療の手引き」にて示されている。また,2歳までに食物アレルギーに罹った児はその後の喘息,アレルギー性鼻炎,アトピー性皮膚炎の可能性が高い6)ことも示されている。 今回,妊娠中の葉酸サプリメントの摂取状況の実態と,乳幼児に最も多いアレルギー疾患である食物アレルギーの関連を調査した。
1 0 0 0 IR 朝顔・昼顔・夕顔・夜顔--体系化を目指した花の名
- 著者
- 吉野 政治
- 出版者
- 京都
- 雑誌
- 同志社女子大学日本語日本文学 (ISSN:09155058)
- 巻号頁・発行日
- no.22, pp.1-13, 2010-06
「朝顔」は奈良時代には特定の花の名ではなかった。現在の牽牛花を「朝顔」と呼ぶようになったのは平安時代からのことだとされるが、同じ頃に同じく蔓性草本で夕方に漏斗状の花を開くものが「夕顔」と呼ばれるようになるのは、「朝-夕」という語の対応が前提となっている。江戸時代には「昼顔」という名が現れるのも「朝-昼-夕」という語の体系がその前提としてあり、明治時代に新渡来種に「夜顔」の名が付けられたのも「昼-夜」という対語が基になっているのである。本稿はこれまで植物学的な類似によって注目されてきたこれらの名前を語の体系という観点から捉えてみたものである。それによって、夕顔と夜顔との混同の理由が理解されることになる。
- 著者
- 水野 博介
- 出版者
- 埼玉大学教養学部
- 雑誌
- 埼玉大学紀要. 教養学部 = Saitama University Review. Faculty of Liberal Arts (ISSN:1349824X)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.2, pp.115-122, 2009
- 著者
- 奥村 隆 Takashi Okumura
- 出版者
- 関西学院大学先端社会研究所
- 雑誌
- 関西学院大学先端社会研究所紀要 = Annual review of the Institute for Advanced Social Research (ISSN:18837042)
- 巻号頁・発行日
- no.17, pp.67-90, 2020-03
1 0 0 0 OA 佐藤春夫「更生記」論 : 「狂気」をめぐる語り
- 著者
- 西川 貴子 Atsuko Nishikawa
- 出版者
- 同志社大学国文学会
- 雑誌
- 同志社国文学 = Doshisha Kokubungaku (ISSN:03898717)
- 巻号頁・発行日
- no.81, pp.266-277, 2014-11-20
1 0 0 0 遷移図によるディジタル伝送符号の一般的解析法とその応用
1 0 0 0 OA 「一帯一路」構想の中の「鄭和」言説 : 中華民族の英雄か,回族の英雄か
- 著者
- Masumi Matsumoto 松本 ますみ
- 出版者
- 国立民族学博物館
- 雑誌
- 国立民族学博物館調査報告 = Senri Ethnological Reports (ISSN:13406787)
- 巻号頁・発行日
- vol.142, pp.31-54, 2017-11-15
1 0 0 0 IR スウェーデンの保育(研究所プロジェクト報告)
- 著者
- ウェンドラー 由紀子 山本 理絵 Yukiko Wendler
- 出版者
- 愛知県立大学生涯発達研究所
- 雑誌
- 生涯発達研究 (ISSN:21883661)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.37-52, 2014-03-31
1 0 0 0 新聞V.S.雑誌(兄弟対談)
- 著者
- 石澤 和彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.693, pp.297-303, 2011-10-05 (Released:2017-09-22)
- 参考文献数
- 8
1 0 0 0 OA 箱庭療法の砂色に関する基礎的研究
- 著者
- 大宮 秀淑
- 出版者
- 札幌学院大学総合研究所 = Research Institute of Sapporo Gakuin University
- 雑誌
- 札幌学院大学心理学紀要 = Bulletin of Faculty of Psychology Sapporo Gakuin University (ISSN:24341967)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.35-56, 2018-10-31
本研究の目的は,箱庭療法で使用される砂の色が異なる箱庭作品に違いが認められるか否かを検討することである。対象は大学生55名(男子:22名,女子:33名)である。対象者は2種類の砂(白砂・茶砂)を用いて各砂色につき1回ずつ箱庭作品を制作した。制作終了後,質問紙による回答を求め作品の印象を訊ねた。結果として,白砂による作品は未熟な印象を与え作品に対する満足度が低いことが明らかとなった。白砂という素材が持つ様々かつ曖昧なイメージを刺激する働きによる影響が認められた。イメージ内容には性差が認められ,男子学生は否定的イメージを持つことが示された。一方,茶砂に関しては作品に対する満足感が高く,性差が認められるとともに茶砂が持つ大地の役割や母性とのつながりが示唆された。制作回数の効果については,1回目よりも2回目の作品の方が成熟度に関して深まりが感じられる結果となった。他の砂色に関する比較検討が今後の課題である。
- 著者
- 杉浦 勢之
- 出版者
- 社会経済史学会
- 雑誌
- 社会経済史学 (ISSN:00380113)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.4, pp.514-542,604-60, 1986
- 被引用文献数
- 1
The scheme of the postal savings was established in 1875 after the model of the Post Office Savings in Great Britain. This scheme was from the very beginning expected to target such low-income class as workers and peasants rather than ordinary depositors with a proper level of income whom banking institutions usually deemed as their clients. Nevertheless, such socio-economic factors as prematurity of money economy and concentration of modern banking in cities spurred the development of this scheme centering on rather well-to-do olocal landlords. A change in the nature of the postal savings apparent in those initial years surfaced in the mid-1890s. In this period of the so-called Japanese Industrial Revolution after the Sino-Japanese War, modern banking rapidly expanded into the rural areas. Because of this modern banking's advancement, the postal savings experienced an alarming level of decrease in the amount of saving having lost long-standing depositors, wealthy farmers in particular, to modern banking institutions. What must be noted here is that this decrease led to an increase in relative share of low-income depositors in the total composition of the postal savings clients. At the end of the 19th Century, on the other hand, there emerged a need in the Administrative concerns to increase the savings ratio in the low-income class and then lure their petty savings to the postal savings scheme. While, after the Sino-Japanese War, the Administration expanded the fiscal expenditure year after year, a boom in enterprises occured at the same time which led to a spiral growth of the capital outlay on the top of expansion of personal consumption, altogether resulting in a rapid development of demestic demand. All these factors caused a steep rise in prices and a marked decrease in the specie reserve affected by an adverse balance of trade with a consequence of a crisis of the gold standard which had just been effected in 1897. The Government deemed the growing consumption an unproductive one and was determined to adopt a savings promotion policy with an aim of restriction on consumption. As the boom in enterprises negated a possibility for raising government bonds which should have been used for raising of funds to be earmarked for fiscal projects centering on military and infrastructure as well as national economic management in the post-war era of the Sino-Japanese War, the Government had no other choice to subscribe to the bonds by using the postal savings as the fiscal resource. The saving promotion policy at first did not work so effectively as expected. But when the political relation of Japan and Imperial Russia became aggravated and the war broke out, the Government organized a nationalistic savings promotion campaign and created a network of the thrift and saving association nationwide for rather forced saving among the populace. Thus the Government succeeded in reorganizing the postal savings scheme as a national savings institution concentrating on the low-income class during the Russo-Japanese War. The postal savings began to be recongnized as an effective instrument of maintaining the demand control policy necessary to achieve a rapid economic growth under the low "ceiling" of Japan's international payments capacity.
1 0 0 0 OA 傾斜地における火炎・熱気流性状の計測とモデリング
- 著者
- 今村 友彦
- 出版者
- 諏訪東京理科大学
- 雑誌
- 研究活動スタート支援
- 巻号頁・発行日
- 2009
林野火災など、傾斜地で発生した火災による火炎の形状は、水平面におけるそれとは異なり、火炎が斜面へ倒れ込み、延焼拡大を助長する要因となる。そのため、傾斜地における火炎形状を把握・予測することは、防火対策上非常に重要であるが、現在までに詳細な研究はなされていない。本研究では、傾斜地における火災性状を体系的に解明することを目的とし、その第1段階として、火炎形状に及ぼす傾斜角度の影響を実験的に検討した。その結果、(1)傾斜面における火炎は、周囲空気の巻き込みが不均一であることから、負圧になりやすい斜面上方向へ吸いつき、斜面上を這うこと、(2)斜面における火炎は、全体としての長さは発熱速度のみに依存して決まり、傾斜角度によって決まる長さ分だけ斜面上を這い、その後、発熱速度と傾斜角度のつりあいに応じた長さだけ立ち上がる。発熱速度に対する依存性は、水平面上で発生した火炎同様Q^<*2/5>に比例すること、が明らかとなった。
1 0 0 0 OA 麹菌のタンパク分解酵素
- 著者
- 一島 英治
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.97, no.1, pp.7-16, 2002-01-15 (Released:2011-09-20)
- 参考文献数
- 50
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA パーソナルエリアネットワークを実現する技術─Bluetooth─
- 著者
- 酒井 五雄
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン (ISSN:21860661)
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, no.2, pp.2_55-2_61, 2007-08-25 (Released:2011-06-03)
- 参考文献数
- 5
Bluetoothは2.4GHz帯域を使用する「パーソナルエリアネットワーク」(後述)のための近距離無線規格で,1998年4月に1Mbit/sの伝送速度をもつ基本仕様が発表された.本論文ではBluetoothのハードウェア,ソフトウェアの基本構成及び動作を説明し,「だれでも手軽に使うことを目指した無線規格」としての観点から,無線LANとの競合回避,接続時間の短縮及び伝送速度高速化というこれまでの仕様更新の要点に関して述べた後,将来に向けたBluetoothの動向を紹介する.
1 0 0 0 OA P値の呪縛
- 著者
- 北 洋輔
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児神経学会
- 雑誌
- 脳と発達 (ISSN:00290831)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.6, pp.386, 2017 (Released:2017-12-12)
1 0 0 0 OA カツオの品質保持に脱水シートの及ぼす影響
- 著者
- 加藤 裕朗 村山 裕佳 濱田 奈保子 和田 俊
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成23年度日本調理科学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.32, 2011 (Released:2011-08-30)
【目的】浸透圧を利用して食品から水分を取り除くことができるシートとして開発された脱水シート(商品名:ピチットマイルドシート, オカモト社製)は2枚の食品用半透膜フィルムの間に,高濃度の食用糖類と食用糊料をはさんだ構造になっている.鮮魚の品質保持効果に関しては,サバ類,イワシ類,タラ類,ブリ及びサンマについて,VBN抑制効果とK値の上昇抑制効果があることを精査してきた(*濱田ら 2002,2003).本研究ではカツオを対象として,多角的角度から品質保持に及ぼす脱水シートの影響について検討を行った. 【方法】カツオを脱水シート,対照としてポリ塩化ビニリデンシート(サランラップ 旭化成製)で包装し,5℃の冷蔵室で0~4日間貯蔵した.脱水率,水分含量及びATP関連化合物量を経日的に測定した.色彩に関しては,血合肉と普通肉においてL*a*b*値を測定及びL*a*b*値とそれらの値から求められるΔEとΔEに彩度を加えたΔE00を求めた.また,におい識別装置(島津製作所 FF-2A)を用いた総合的なにおい分析の計測を貯蔵2日目と4日目に計測した. 【結果】脱水シート包装の脱水率は貯蔵1日目で6.2%,貯蔵4日目には14.4%であり,水分含量は貯蔵2日目から4%以上の差が見られた. ATP関連化合物量については有意差は見られなかった.色彩に関しては,ΔE及びΔE00ともに脱水シート包装において色彩の保持効果が観察された.また血合肉でより高い効果が見られた.においに関しては,貯蔵4日目において類似度と多変量解析の結果に差が見られた.以上の結果から,カツオの品質保持に関して色彩とにおいにおいて脱水シートによる優位性が示唆された. *日食科誌, 49, 781-785 (2002). 日調理科誌, 36, 354-359 (2003).
1 0 0 0 OA 臨海工業都市における製造工業の地域構造とその形成過程
- 著者
- 河地 貫一
- 出版者
- The Human Geographical Society of Japan
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.16-33,94, 1961-02-28 (Released:2009-04-28)
- 参考文献数
- 31
1) The manufacturing industries in Nagasaki are forming a seaside-industrial area standing for an exclusive accumulation, in a limited area which is closely related with labour and production. This geographical fact in a spatially-occupied area shows the economic structure of industry, as described in the following 2), 3), and 4).2) Nagasaki is a mono-industrial city, in which the production of a metal-machine industry accounts for over 80% of all industrial productions.3) The main metal-machine industry is ship-building of all-round assembly ndustries, and nearly all of them are carried on by correlated enterprises or subcontracted enterprises.4) A colossal monopolistic enterprise, named “Mitsubishi”, is responsible for over 90% of all productions of the metal-machine industries, and over 80% of all manufacturing industries. This is a regional characteristic of Nagasaki depending upon authority, of course, though these structures are observed in Japanese economics as a general tendency.5) A specially fixed area as described in 1) is the old Fuchi Mura village, portion of Nagasaki City, which was incorporated with Nagasaki at the time of the expansion of the first municipal area, in the 31st year of the Meiji era: 1898. This area had already become an industrial area, at the time when the Mitsubishi ship-building yard and its correlated industries were located.6) As this area was incorporated with Nagasaki City, the port of Nagasaki, which was once a luxury-consuming city, began to show to signs of being newly reconverted to an industrial city in many sections. It was, so to speak, a spatial proclamation.7) The center of the present industrial area in the city is a district belonging to the old Fuchi Mura village, a portion of Nagasaki, just as it was. This indicates that only an exclusive accumulation by regional groups was set forward, not carrying out spatial expansion from the 31st year of the Meiji era: 1898, and later, notwithstanding the industrial extensive growth of Nagasaki after that.8) The industries of Nagasaki have been growing together with the Mitsubishi ship-building yard, and the correlated industries……especially the metal-machine industry, located in the interior of the ship-building yard or in the neighborhood. As other industries in this area repeated the rise and fall of prosperity in proportion to Japanese capitalism, there was no formation of an extensive industrial area with mentioning in this area.9) The industry did not expand spatially, the geographical facts setting forward the exclusive accumulation to the old Fuchi Mura village are nothing else but having a spatially-represented, historical process of which the interior structure of industries shows extreme patterns, as described in 2), 3), and 4).