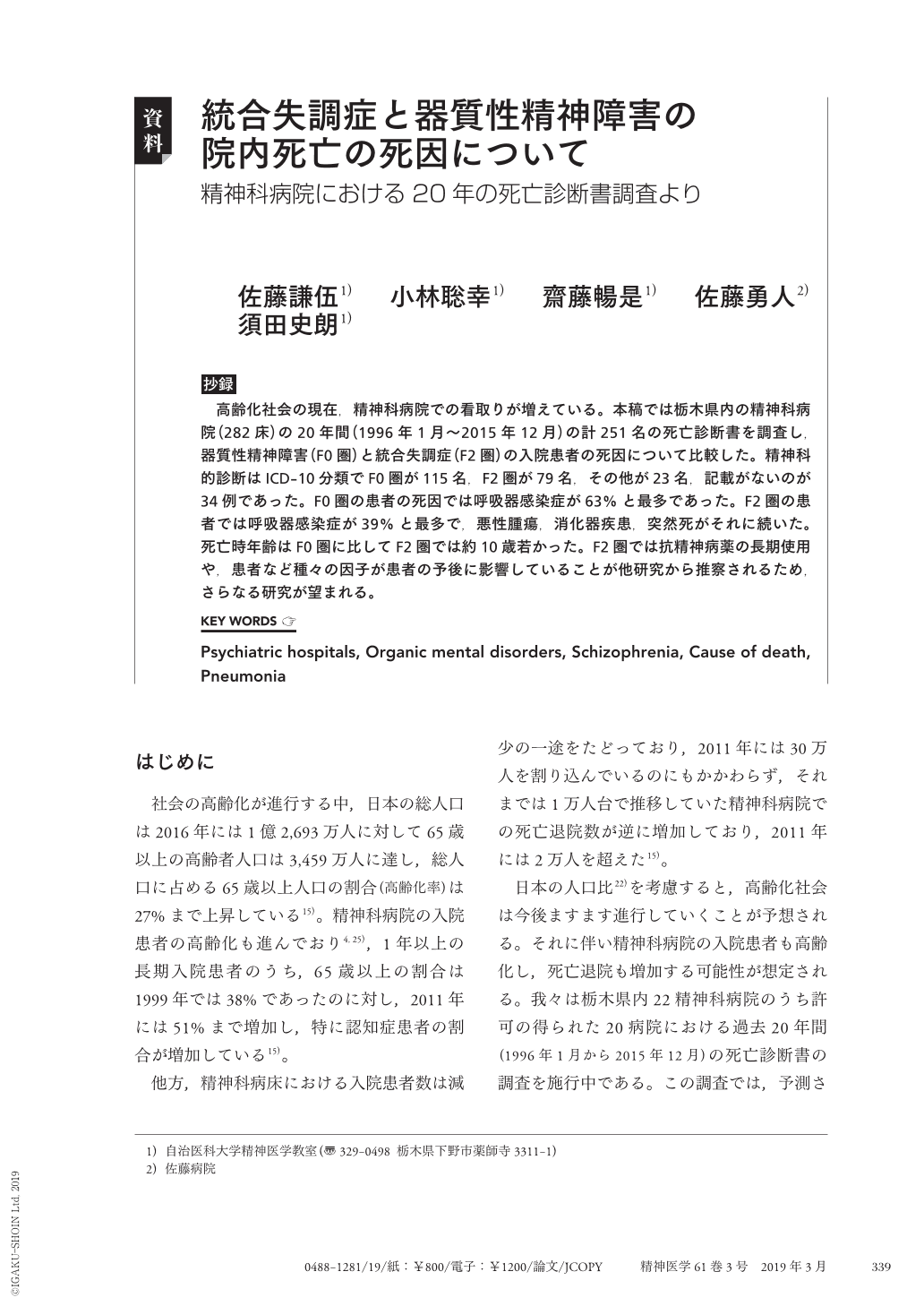1 0 0 0 OA 私は有機合成化学者である!
- 著者
- 田中 克典
- 出版者
- 公益社団法人 有機合成化学協会
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.10, pp.1110-1112, 2018-10-01 (Released:2018-10-09)
- 参考文献数
- 1
- 著者
- Izumi Mishiro Norie Sawada Motoki Iwasaki Kayo Ohashi Shoichiro Tsugane
- 出版者
- Japan Epidemiological Association
- 雑誌
- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.10, pp.522-529, 2016-10-05 (Released:2016-10-05)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1 1
Background: Some recent molecular epidemiology studies of the effects of genetic and environmental factors on human health have required the enrollment of more than 100 000 participants and the involvement of regional study offices across the country. Although regional study office investigators play a critical role in these studies, including the acquisition of funds, this role is rarely discussed.Methods: We first differentiated the functions of the regional and central study offices. We then investigated the minimum number of items required and approximate cost of a molecular epidemiology study enrolling 7400 participants from a model region with a population of 100 000 for a 4-year baseline survey using a standard protocol developed based on the protocol of Japan Public Health Center-based Prospective Study for the Next Generation.Results: The functions of the regional study office were identified, and individual expenses were itemized. The total cost of the 4-year baseline survey was 153 million yen, excluding consumption tax. Accounting difficulties in conducting the survey were clarified.Conclusions: We investigated a standardized example of the tasks and total actual costs of a regional study office. Our approach is easy to utilize and will help improve the management of regional study offices in future molecular epidemiology studies.
- 著者
- 向後 千春 冨永 敦子 石川 奈保子
- 出版者
- 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, pp.281-290, 2012-12-20 (Released:2016-08-09)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 5
eラーニングと教室でのグループワークを週替わりで交代に行うブレンド型授業を設計し,3年間に渡って実践した.1年目は通信教育課程向けのeラーニングコンテンツを流用し,2年目以降はブレンド型授業用に新規に開発した.ブレンド型授業導入以前の対面授業,ブレンド型授業の1年目,2年目,3年目の成績分布を比較したところ,1年目はほかに比べて成績高群が有意に少なく,成績中群が有意に多かった.しかしながら,2年目以降は,対面授業と有意な差はなかった.また,学習者のブレンド型授業に対する好みは,1年目よりも2年目以降が有意に高くなった.このことから,ブレンド型授業用に授業を設計すれば,対面授業と同程度の学習効果を上げることができ,かつ受講生からも受け入れられることが示唆された.しかしながら,一方で,対面授業に比べて,ブレンド型授業は不合格者が有意に多く,ブレンド型授業に馴染めない学習者が一定の割合で存在していることが示唆された.
1 0 0 0 OA 歯周病原性細菌は口腔内にどのように定着するか
- 著者
- 阿座上 弘行 湯本 浩通 恵比須 繁之
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.12, pp.848-853, 1997-12-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 16
1 0 0 0 OA 日本建築生産システムとしての番付の歴史的変遷に関する研究
- 著者
- 清水 真一
- 巻号頁・発行日
- 1996-03-31
第1章 序 論 番付は、様々な部材を組み上げてモノを造る際に、各部材の据え付け位置を示す心覚えとして記される符丁である。木造建築は特に構成部材が多いことから、手仕事に伴う誤差に対処するために仮組をして部材調整をした後、改めて番付を頼りに組み上げることとなる。このように番付は建物の出来映えに直接関わる生産の技術として書要であるが、建物形態ばかりでなく生産工程や造営組織の在り方によっても番付の必要性や用い方は様々であったと考えられる。番付はモノと人を結びつける中心的な役割を担い、生産システムとしての性格を備えているといえる。番付は個々の建物の建立や修理の沿革を知る資料として重視されているに関わらず、番付そのものについての体系的な研究は行われずにきた。本研究は生産システムに関わる有用な資料としての番付について、その歴史的変遷とその背景について考察し、併せて番付からみた大工の系統や地域性など建築界の諸相を明らかにする。番付は見え隠れ部分に記されるのが常であり解体の機会を除いては確認は困難である。したがって基礎的な資料の収集については文化財建造物の保存修理工事の成果に負うところが大きい。対象とした時代は、古代から中世前期(鎌倉・室町前期)にかけてのもっぱら方位番付が用いられた時代と、中世後期(室町中・後期)から近世初斯の慶長年間にかけて各種の新しい番付形式が普及し地方色が形成された時代との二時期に大区分した。 第2章 古代・中世前期の番付 新築当初の組上番付は、法隆寺五重塔などの諸例から大和では古代以来用いられたことがわかる。極めて限られた部位に適用されたものであったが、中世前期にかけて次第に地方に普及するとともに側廻りの組物などを対象に用いられて、六技掛けの成立にも象徴されるような軒廻り整備の進展にとって重要な技術的裏付となったと考えられる。方位番付の形式は、塔婆や三間堂のような求心的平面の場合には中心からみた四面と四隅の方位で示すが、横長平面の場合には、唐招提寺講堂や法隆寺東大門では棟通りから前後に振分けて表記する形式が採られ、構造主体が前後対称な古代建築にふさわしいシステムといえる。また、中世前斯には密教本堂に代表される奥行の深い建物が現れたことから、四面の方位を記した上でさらに各面毎に一端からの数を追う形式が現れるなど、番付形式自身にも時代の要求に応じての変化をみることができる。 第3章 中世後期・近世初期の番付 14世紀末から15世紀初頭にかけて、数字のみで表記する回り番付・時香番付・組合番付の使用が相次いで確認できる。回り番付は、中世前期以来の軒廻り整備に対する技術的要求から考案きれたと考えられる。室町中期には京都を中心とする一帯を挟んで、東日本と西日本の広範な地域での使用が確認でき、本来は京都を中心に用いられた形式が地方に普及した結果と考えられる。南北朝の兵乱後、幕府の造営を中心に京都の造営活動が再び活性化するとともに、建物内部の各柱筋にも適用することを前提とする形式である時香番付が考案された。畿内から西は山陽道、東は東海道へと主要街道筋に沿って普及していった様相が窺える。京都では、近世初頭にはさらにイロハ組合番付という小屋雑専用の番付が考案される。一方、大和では古代以来の方位番付を踏襲し、地方においても方位番付は新番付の補助的役割にとどまることになる。番付には建築界の移り変わりが反映している。また、播磨や近江湖東地方では、直行座標によって位置を示す合理的な形式である数字組合番付が用いられた。中央の動向とは異なる独自の形式が考案された背景には、地方建築界の活発な造営活動があったことを示すものとして注目できる。 第4草 番付からみた中世後期と近世初期の建築界 生産システムとしての番付の在り方にも大きな変化が現れた15世紀前半までには、縦挽鋸の使用、請負工事の出現、職名としての「棟梁」の登場など建築生産に関わる諸事象が現れたことは既に知られており、これらは生産技術の向上と造営形態の組織化が進展したことを物語る。中世後期に登場した各種の新番付は、起点と進行方向を定めて数字のみで表示することから、抽象的、数学的思考方法の成熟が窺えるし、正面柱筋を優先とする形式は奥行の深い平面形態が現れて構造主体に正面性が芽生えたことを反映している。また、次第に野小屋にも規矩的な納まりが重視されて小屋組番付を用いるようになるが、近世初期には軸部とは異なった番付形式を充てるものが現れ、軸部と小屋組とが構造的な分離を遂げたことを示している。番付は工匠集団内で一定の形式が踏襲されるから作事の分担や工匠の交流があったことが確認できる。特に姫路城など近世初期の城郭建築の造営においては、地元工匠に加えて遠方の工匠を招いて建物毎、階毎の作事分担があったことがわかる。また、地域の中で番付形式の混在が著しい所は、概して工匠の交流など建築活動が活発であったことを示し、円教寺や大徳寺などでは番付から寺外工匠による活躍の様も窺える。中世新番付の分布状況をみるとそれぞれ地域性が認められる。番付形式と建築様式の地域性を比較してみると、直接的な関係を明らかにすることはできない。しかし、中部地方南部で西日本と関東の主流形が交錯すること、東日本では定型的であるのに対して、西日本では特に近畿から山陽にかけて混在傾向が著しいことなど、番付形式、様式ともに一致した傾向が見受けられる。 第5車 中世法隆寺大工とその造営形態本章では棟札や棟木銘のような銘文墨書ばかりでなく番付を含めた建築墨書全般についての総合的な資料分析を通じて、法隆寺大工の特異な造営形態である四箇末寺大工職と四人大工制度について、その成立から解体に至る経緯を追跡した。四人大工制度は、弘安元年(1278)に四箇末寺大工職を得た四姓の工匠達を構成員として四姓が対等な立場で参画して惣寺の作事を独占するものである。番付に併せ用いられた特有な用語を追跡することで、法隆寺大工が旧興福寺大工を主体として成り立っていることがわかる。治承兵火後の興福寺復興に続く時期に行われた法隆寺東院修造は興福寺工を主体として行われ、その後の作事の縮小に伴って職場独占の機運がおこり四人大工制度が成立したと考えられる。この制度は室町後期に末寺の大工職が消滅した後も維持されたが、中井家配下に組み込まれて行われた慶長大修理をもって解体に向かったことが知られる。これを契機に再び寺外工匠の参画と部位別作事分担が行われたことも番付から裏付けられる。 第6章 結 語 古代から近世初期にかけて、番付が限られた部位から次第に建物全体へと適用されるに至った経緯を追跡すると、整った納まりを追求したり、複雑化する建物形態への対処方法を模索し、あるいはより雑織的な造営形態を追求する申で、工匠達が様々に工夫を凝らしながら番付を様々に変化発展させてきたことが明かとなった。古代代以来の方位番付を頑なに踏襲しながら対処した大和の工匠、はた目にはやや不便なシステムであっても独自の番付形式を斯いた延暦寺工匠、時香番付、さらにはイロハ組合番付という進んだシステムを積極的に採用した大徳寺工匠を始めとする京都の工匠、中央での動向にとらわれずさらに進んだシステムを早くから採用した円教寺工匠をはじめとする播磨の工匠など、番付形式やその用い方には時代の要請に対する工匠例の対処の在り方が現れている。また、番付を通じて、建築活動の中心が移り変わり、あるいは地方建築界が勃興した様など、建築界の動向を時代や地域を越えて見通すとともに、工匠の交流や作事分担の様などモノ造りに直接関わった工匠達の動向をも描き出すことができた。本研究では、建築生産のシステムとしての重要な役割を担う番付について、その性格と研究の意義を明らかにし、歴史的な変遷課程をたどる基礎的な作業を通じて、番付を建築史研究の重要な方法論のひとつとして提示できたと考えている。
1 0 0 0 OA 莫切自根金生木 : 3巻
1 0 0 0 OA 奈良県南部山間地域における小中学校統廃合後の空き校舎の活用状況
- 著者
- 岩本 廣美 河本 大地 板橋 孝幸
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集 2020年度日本地理学会春季学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.320, 2020 (Released:2020-03-30)
奈良県南部の野迫川村を事例に、山間地域で小中学校の統廃合が進行した結果発生した空き校舎を地域社会がどのように活用しているのか、を明らかにしようとした研究である。山間地域における地域社会のあり方の一端を探ろうとする研究であり、教育地理学の延長に位置付けられると考えられる。
1 0 0 0 OA Gene-expression profile reveals the genetic and acquired phenotypes of hyperactive mutant SPORTS rat
- 著者
- Taigo Horiguchi Yumiko Miyatake Keiko Miyoshi Ayako Tanimura Hiroko Hagita Hiroshi Sakaue Takafumi Noma
- 出版者
- The University of Tokushima Faculty of Medicine
- 雑誌
- The Journal of Medical Investigation (ISSN:13431420)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1.2, pp.51-61, 2020 (Released:2020-05-02)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 3
Spontaneously Running Tokushima Shikoku (SPORTS) rat is a hyperactive rat strain. However, the causative mutation of this phenotype has not yet been identified. To investigate the molecular basis for the unique phenotype of SPORTS rats, we examined gene-expression profiles by microarray analyses. Among adenylate kinase isozymes that maintain the homeostasis of cellular adenine nucleotide composition in the cell, only adenylate kinase 1 is highly up-regulated in both exercised and sedentary SPORTS rats compared with wild-type (WT) rats, 5.5-fold and 3.3-fold, respectively. Further comparative analyses revealed that genes involved in glucose metabolism were up-regulated in skeletal muscle tissue of exercised SPORTS rats compared with sedentary mutants, whereas genes related to extracellular matrix or region were down-regulated compared with WT rats. In brain tissue of sedentary SPORTS rats, genes associated with defense and catecholamine metabolism were highly expressed compared with WT rats. These findings suggest that genetic mutation(s) in SPORTS rat remodels metabolic demands through differentially regulating gene expression regardless of exercise. Therefore, the SPORTS rats are useful animal model not only for further examining the effects of exercise on metabolism but also for deeply studying the molecular basis how mutation affect the psychological motivation with spontaneous voluntary exercise phenotype. J. Med. Invest. 67 : 51-61, February, 2020
- 著者
- 柳田 さやか
- 出版者
- 書学書道史学会
- 雑誌
- 書学書道史研究 (ISSN:18832784)
- 巻号頁・発行日
- vol.2015, no.25, pp.109-123,175, 2015
As part of an inquiry into changes in the modern concept of "art," in this article I examine the scope of "art" and the position of calligraphy in the Ryūchikai 龍池會, which was founded in 1879 as the first Japanese art association (and was later renamed Japan Art Association). Prompted by the Ryūchikai's treatment of calligraphy as art, in 1882 Koyama Shōtarō 小山正太郎 published an essay entitled "Calligraphy Is Not Art" ("Sho wa bijutsu narazu" 書ハ美術ナラス). But following a careful examination of the official organs of the Ryūchikai and Japan Art Association, it has become clear that already prior to the publication of this essay there were differences of opinion among members of the Ryūchikai about whether or not to include calligraphy in "art." Furthermore, while a small number of early pieces of calligraphy were exhibited as examples of old works in exhibitions sponsored by the Ryūchikai and Japan Art Association, no requests were made for exhibits of new pieces of calligraphy, and it was confirmed that in effect there was a strong tendency to exclude calligraphy from "art." <br> In response to this state of affairs, calligraphers led by Watanabe Saō 渡邊沙鷗 established the Rikusho Kyōkai 六書協會 within the Japan Art Association with the aim of having calligraphy treated in the same way as painting. But the Japan Art Association instructed them to disband four years later, and so the calligraphers decided to resign from the Japan Art Association. The following year they established their own Japan Calligraphy Association and actively campaigned to have calligraphy exhibited at art exhibitions sponsored by the Ministry of Education and at other exhibitions and expositions. The Rikusho Kyōkai merits renewed attention as a pioneering group that aspired to have calligraphy recognized as a form of "art" and held exhibitions of only calligraphy on a continuing basis.
1 0 0 0 OA 腹臥位での下肢空間保持課題が反対側の僧帽筋下部線維の筋活動に与える影響
- 著者
- 池澤 秀起 高木 綾一 鈴木 俊明
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.41 Suppl. No.2 (第49回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.0690, 2014 (Released:2014-05-09)
【はじめに,目的】肩関節疾患患者の上肢挙上運動は,肩甲骨の挙上など代償運動を認めることが多い。この原因の一つとして,僧帽筋下部線維の筋力低下が挙げられるが,疼痛や代償運動により患側上肢を用いた運動で僧帽筋下部線維の筋活動を促すことに難渋する。そこで,上肢の運動を伴わずに僧帽筋下部線維の筋活動を促す方法として,腹臥位での患側上肢と反対側の下肢空間保持が有効ではないかと考えた。その結果,第47回日本理学療法学術大会において,腹臥位での下肢空間保持と腹臥位での肩関節外転145度位保持は同程度の僧帽筋下部線維の筋活動を認めたと報告した。また,第53回近畿理学療法学術大会において,両側の肩関節外転角度を変化させた際の腹臥位での下肢空間保持における僧帽筋下部線維の筋活動は,0度,30度,60度に対して90度,120度で有意に増大したと報告した。一方,先行研究では両側の肩関節外転角度を変化させたため,どちらの肩関節外転が僧帽筋下部線維の筋活動に影響を与えたか明確でない。そこで,一側の肩関節外転角度を一定肢位に保持し,反対側の肩関節外転角度を変化させた際の僧帽筋下部線維の筋活動を明確にする必要があると考えた。これにより,僧帽筋下部線維の筋活動を選択的に促す因子を特定し,トレーニングの一助にしたいと考えた。【方法】対象は上下肢,体幹に現在疾患を有さない健常男性16名(年齢25.6±2.1歳,身長168.5±2.5cm,体重60.4±6.7kg)とした。測定課題は,利き腕と反対側の下肢空間保持とした。測定肢位は,腹臥位でベッドと顎の間に両手を重ねた肢位で,下肢は両股関節中間位,膝関節伸展位とした。また,空間保持側の上肢は肩関節外転0度で固定し,反対側の上肢は肩関節外転角度を0度,30度,60度,90度,120度と変化させた。肩関節外転角度の測定はゴニオメーター(OG技研社製)を用いた。測定筋は,空間保持側と反対の僧帽筋上部,中部,下部線維,広背筋とした。筋電図測定にはテレメトリー筋電計MQ-8(キッセイコムテック社製)を使用した。測定筋の筋活動は,1秒間当たりの筋電図積分値を安静腹臥位の筋電図積分値で除した筋電図積分値相対値で表した。また,5つの角度における全ての筋電図積分値相対値をそれぞれ比較した。比較には反復測定分散分析及び多重比較検定を用い,危険率は5%未満とした。【倫理的配慮,説明と同意】対象者に本研究の目的及び方法を説明し,同意を得た。【結果】僧帽筋下部線維の筋電図積分値相対値は,肩関節外転角度が0度,30度,60度に対して90度,120度で有意に増大した。広背筋の筋電図積分値相対値は,肩関節外転角度が30度,60度,90度,120度に対して0度で有意に増大した。僧帽筋上部線維,僧帽筋中部線維の筋電図積分値相対値は,全ての肢位において有意な差を認めなかった。【考察】先行研究と今回の結果から,腹臥位での下肢空間保持における僧帽筋下部線維の筋活動は,空間保持側と反対の肩関節外転角度の影響が大きいことが判明した。つまり,腹臥位での下肢空間保持は,空間保持側と反対の肩関節外転角度を考慮することで僧帽筋下部線維の筋活動を選択的に促すことが出来る可能性が高いと考える。まず,腹臥位での下肢空間保持は,下肢を空間保持するために股関節伸展筋の筋活動が増大する。それに伴い骨盤を固定するために空間保持側の腰背筋の筋活動が増大し,さらに,二次的に脊柱を固定するために空間保持側と反対の腰背筋や僧帽筋下部線維の筋活動が増大することが考えられる。このことを踏まえ,僧帽筋下部線維の筋活動が肩関節外転0度,30度,60度に対して90度,120度で有意に増大した要因として,肩関節外転角度の変化により脊柱を固定するための筋活動が広背筋から僧帽筋下部線維に変化したのではないかと考える。広背筋の筋活動は肩関節外転30度,60度,90度,120度に対して0度で有意に増大したことから,肩関節外転0度では脊柱の固定に広背筋が作用したことが推察される。一方,肩関節外転角度の増大により広背筋は伸長位となり,力が発揮しにくい肢位となることが推察される。また,広背筋は上腕骨,僧帽筋下部線維は肩甲骨に停止することに加え,肩甲上腕リズムから肩関節外転角度の増大に対して,広背筋は僧帽筋下部線維と比較し伸長される割合が大きいことが推察される。その結果,肩関節外転角度の増大に伴い脊柱を固定するために僧帽筋下部線維の筋活動が増大したのではないかと考える。【理学療法学研究としての意義】腹臥位での下肢空間保持において,僧帽筋下部線維の筋活動は先行研究と同様の結果であったことから,空間保持側と反対の肩関節外転角度が僧帽筋下部線維の筋活動を選択的に促す要因となる可能性が高いことが示唆された。
1 0 0 0 OA 小麦の収量・倒伏に及ぼす播種様式の影響 : 倒伏と倒伏関連形質について
- 著者
- 佐藤 一 広川 文彦 江口 久夫 島田 信二
- 出版者
- 日本作物学会中国支部
- 雑誌
- 日本作物学会中国支部研究集録 (ISSN:09134670)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.53-55, 1985-07-30 (Released:2018-01-30)
前報と同一の試験において実際の倒伏と倒伏関連形質との関係を調査したので報告する。
1 0 0 0 OA ナッツの知識
- 著者
- 清水 喜三男
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.191-194, 1997-05-20 (Released:2013-04-26)
- 参考文献数
- 7
1 0 0 0 جامع تاریخ ہند
- 著者
- محمد حبیب خالق احمد ںظامی
- 出版者
- ترقی اردو بیورو
- 巻号頁・発行日
- 1984
抄録 高齢化社会の現在,精神科病院での看取りが増えている。本稿では栃木県内の精神科病院(282床)の20年間(1996年1月〜2015年12月)の計251名の死亡診断書を調査し,器質性精神障害(F0圏)と統合失調症(F2圏)の入院患者の死因について比較した。精神科的診断はICD-10分類でF0圏が115名,F2圏が79名,その他が23名,記載がないのが34例であった。F0圏の患者の死因では呼吸器感染症が63%と最多であった。F2圏の患者では呼吸器感染症が39%と最多で,悪性腫瘍,消化器疾患,突然死がそれに続いた。死亡時年齢はF0圏に比してF2圏では約10歳若かった。F2圏では抗精神病薬の長期使用や,患者など種々の因子が患者の予後に影響していることが他研究から推察されるため,さらなる研究が望まれる。
1 0 0 0 書評 寺島俊穂著『政治哲学概説』
- 著者
- 村井 洋
- 出版者
- 島根県立大学総合政策学会
- 雑誌
- 総合政策論叢 (ISSN:13463829)
- 巻号頁・発行日
- no.38, pp.121-125, 2019-10
1 0 0 0 矢内原忠雄が見たまぼろし
- 著者
- 赤江 達也
- 出版者
- 三田文学会 ; 1985-
- 雑誌
- 三田文学. [第3期]
- 巻号頁・発行日
- vol.93, no.117, pp.218-226, 2014
1 0 0 0 IR 帝国日本の植民地における無教会キリスト教の展開
- 著者
- 赤江 達也
- 出版者
- 立命館大学社会システム研究所
- 雑誌
- 社会システム研究 (ISSN:13451901)
- 巻号頁・発行日
- no.29, pp.157-167, 2014-09
- 著者
- 赤江 達也
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, pp.33-35, 2015
- 著者
- 岡村 達雄
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.282-286, 2001-09-14 (Released:2017-08-10)