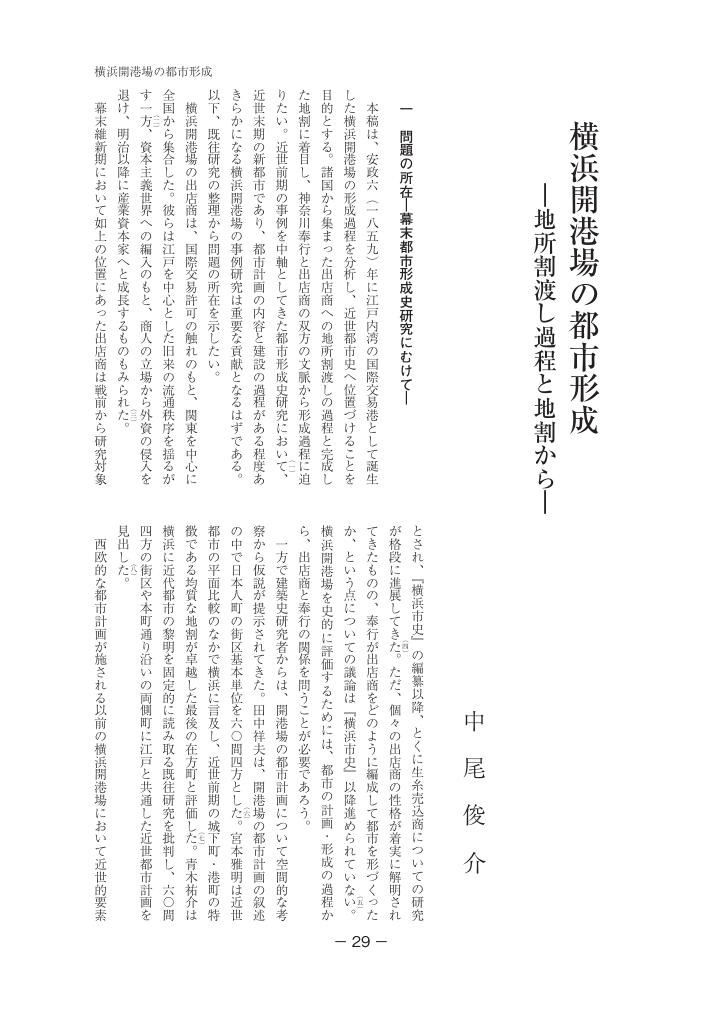1 0 0 0 IR ウェールズの聖杯伝説--「エヴラウクの息子ペレドゥルの物語」から
- 著者
- 中野 節子
- 出版者
- 大妻女子大学
- 雑誌
- 大妻女子大学紀要 文系 (ISSN:09167692)
- 巻号頁・発行日
- no.37, pp.422-410, 2005-03
1 0 0 0 13世紀における古フランス語散文「聖杯物語群」の成立
- 著者
- 渡邉 浩司
- 出版者
- 中央大学人文科学研究所
- 雑誌
- 人文研紀要 (ISSN:02873877)
- 巻号頁・発行日
- no.73, pp.35-59, 2012
- 著者
- ヴァルテール フィリップ 渡邉 浩司
- 出版者
- 中央大学仏語仏文学研究会
- 雑誌
- 仏語仏文学研究 (ISSN:02865920)
- 巻号頁・発行日
- no.44, pp.211-234, 2012-03
1 0 0 0 OA エドマンド・バークの政治思想
- 著者
- 高橋 和則
- 出版者
- 中央大学大学院事務室
- 巻号頁・発行日
- 2017-03-16
【学位授与の要件】中央大学学位規則第4条第2項【論文審査委員主査】星野 智(中央大学法学部教授)【論文審査委員副査】石山 文彦(中央大学法学部教授),廣岡 守穂(中央大学法学部教授),齋藤 俊明(岩手県立大学総合政策学部教授)
1 0 0 0 奈良の伎楽平安の雅楽 : 温故知新
- 著者
- 坂西 友秀
- 出版者
- 埼玉大学教育学部
- 雑誌
- 埼玉大学紀要. 教育学部 = Journal of Saitama University. Faculty of Education (ISSN:18815146)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.2, pp.135-154, 2019
1 0 0 0 OA 醫學中央雜誌 = Japana centra revuo medicina
- 出版者
- 医学中央雑誌刊行会
- 巻号頁・発行日
- no.217, 1915-11
1 0 0 0 OA 二軸延伸ポリプロピレンフィルムの粗面化
- 著者
- 藤山 光美
- 出版者
- 公益社団法人 高分子学会
- 雑誌
- 高分子 (ISSN:04541138)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.6, pp.443, 1990-06-01 (Released:2011-10-14)
- 参考文献数
- 1
1 0 0 0 工学叢誌・工学会誌総索引 : 日本工学会100周年記念出版
- 著者
- 日本工学会創立100周年記念実行委員会編
- 出版者
- 日本工学会
- 巻号頁・発行日
- 1979
1 0 0 0 OA 鉄鋼技術の進歩発展と将来展望
- 著者
- 三好 俊吉
- 出版者
- The Iron and Steel Institute of Japan
- 雑誌
- 鉄と鋼 (ISSN:00211575)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.11, pp.N534-N540, 1995-11-01 (Released:2009-06-19)
- 著者
- 戸本 幸亮 TOMOTO Kosuke
- 出版者
- 筑波法政学会
- 雑誌
- 筑波法政 (ISSN:21880751)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, pp.159-196, 2017-03
1 0 0 0 アスピリン・エイジ : 1919-1941
- 著者
- イザベル・レイトン編 木下秀夫訳
- 出版者
- 早川書房
- 巻号頁・発行日
- 1971
1 0 0 0 OA 共有知問題のラカン的解釈
- 著者
- 樫村 愛子
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.3, pp.3-18,184, 1998-02-28 (Released:2016-11-02)
The discussions about the "common knowledge" which criticize the code model haven't ever explained with the real process of the communication. So I want to explain it by examining the game theory's approach which tries to explain the connection between the micro and macro phase and elaborating this approach by the Lacanian analytical logic. Lacan presents that the real communication depends on the emergent knowledges which others give. This idea presupposes that the subject is ambiguous with his knowledges and that he doesn't know himself (his unconsciousness). So he should depend on the other and accept the emergent knowledges. Lacan points out that this process is governed by "the logic of precipitousness", which is discovered by the treatments of the neurotics. The neurotics can't accept the ambiguousness of their knowledges and they adhere to the determinable. For example, ordinary man is convinced that he loves somebody in the ambiguousness, but the neurotics can't do it and so they can't love anybody. This phenomenon also makes clear the universal condition of the knowledge. The knowledges are always based on this process through which we accept emergent knowledges in the ambiguousness. The axiom about the "common knowledge" by the game theory has the possibility that describes this process mathematically and the connection with the micro and macro phase, though in fact at the actual level of the mathematics it is difficult.
1 0 0 0 OA 横浜開港場の都市形成
- 著者
- 中尾 俊介
- 出版者
- 建築史学会
- 雑誌
- 建築史学 (ISSN:02892839)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, pp.29-56, 2018 (Released:2019-04-18)
1 0 0 0 OA 中学校における自主性尺度項目の開発
- 著者
- 井上 史子 沖 裕貴 林 徳治
- 出版者
- 日本教育情報学会
- 雑誌
- 教育情報研究 (ISSN:09126732)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.3, pp.13-20, 2006-02-28 (Released:2017-05-19)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
本研究は,自主性をはじめとする教師の主観に頼りがちな情意的教育目標の達成度を客観的に測定することにより,それらを育成するための有効な方法論を確立することをめざした実証研究の第一弾である.中学校教育現場においては,教育目標としてしばしば主体性や自主性という言葉が用いられる.主体性とは,学校教育の中で,子どもたちが何ものにもとらわれずに自らの言動の主体として自己決定する態度や,自ら課題を選択・判断する力を意味する.しかし,これまでの先行研究[1]において,これらの力を学校教育の中で育成することは極めて困難であることが明らかにされてきた(井上・林,2003).学校社会で子どもたちに求められるのは,教師があらかじめ設定した課題や役割に対して積極的に取り組む姿勢や態度である.それはむしろ主体性と言うより,自主性と呼ぶ方が適切であると考えられる.本論文では,中学校において,生徒の自主性を測定するため,20の質問項目からなる100点満点の尺度を構成した手続きと,今後の研究の方向性について述べた.
1 0 0 0 スピノザの心理学を基盤にした目的論の研究
1.スピノザ心理学における目的論の位置づけ;スピノザ『エチカ』における目的論の扱いを考察した。彼の目的原因論批判は目的論全般の否定とは区別されなければならないこと、また彼の体系において目的論は排除されているのではなく、むしろその心理学の根本をなしていることを、彼の目的論を個物について成立する法則的言明として解釈することにより示した。2.生物学的な機能に関する問題;生物学の哲学において議論が交わされている二つの機能解釈、すなわち起源論的機能と因果役割機能について、それぞれの批判を検討したうえで、それぞれは互いに相互背反な関係にあるのではなく、生物を理解するための二つの異なったアプローチを示していることを明らかにした。3.目的論全般に対する考察;現在主流である、目的論の因果的な由来による解釈(etiological view)に対し、目的論の本来的な役割は事物の因果的基盤に関するのではなく、むしろ対象を現象論的・統合的に説明する方式であるという、異なった目的論解釈を示した。4.古生物学での機能推定に関する考察;機能推定メソッドとして古生物学で用いられている「パラダイム法」を,3の考察に基づき形質を統合する目的論的な説明とみなした上で,その説明仮説の真偽を,その仮説がどの程度データを説明するか(尤度)に基づき,ベイズ的手法にのっとって判定する,というアイデアを示した。
1 0 0 0 学生相撲における肩関節障害
- 著者
- 中川 泰彰 松末 吉隆 中村 孝志
- 出版者
- Japan Shoulder Society
- 雑誌
- 肩関節 (ISSN:09104461)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.161-164, 1998
Purpose: We have previously reported that shoulder pain was the fourth, and disability was the second problem for sumo* wrestlers. We examined sumo wrestlers directly in order to study the shoulder problems in sumo.<BR>Materials and Methosds: Forty-three major league Western Japan Student Sumo Federation sumo wrestlers were examined from February to April 1997. Their means were as follows: height-174.4cm,ght-106.2kg, body mass index-34.9, age -19.3 years old and length of sumo career- 9.5 years. We obtained their past histories, present disabilities, physical examination, ranges of motion and shoulder joint laxities. Results Twenty-two cases (51%) had past histories of the shoulder problems, which were 10 cases (23%) of shoulder dislocations,5 cases (12%) of contusions,4 cases ( 9 %) of acromioclavicular dislocations and so on. Seven cases (16%) had present disabilites, which were 2cases of shoulder dislocations,2 cases of acromioclavicular joint dislocations and so on. According to this study, the less heavy sumo wrestlers tended to injure and dislocate their shoulders more, and the number who complained of shoulder problems increased, with the length of sumo careers. There were no significant influences seen between the ranges of motion, shoulder joint laxities and shoulder problems.<BR>Conclusion: The lighter sumo wrestlers tended to injure and dislocate their shoulders more. It interfered with the wrestling of sumo, who had previously dislocated their shoulder.