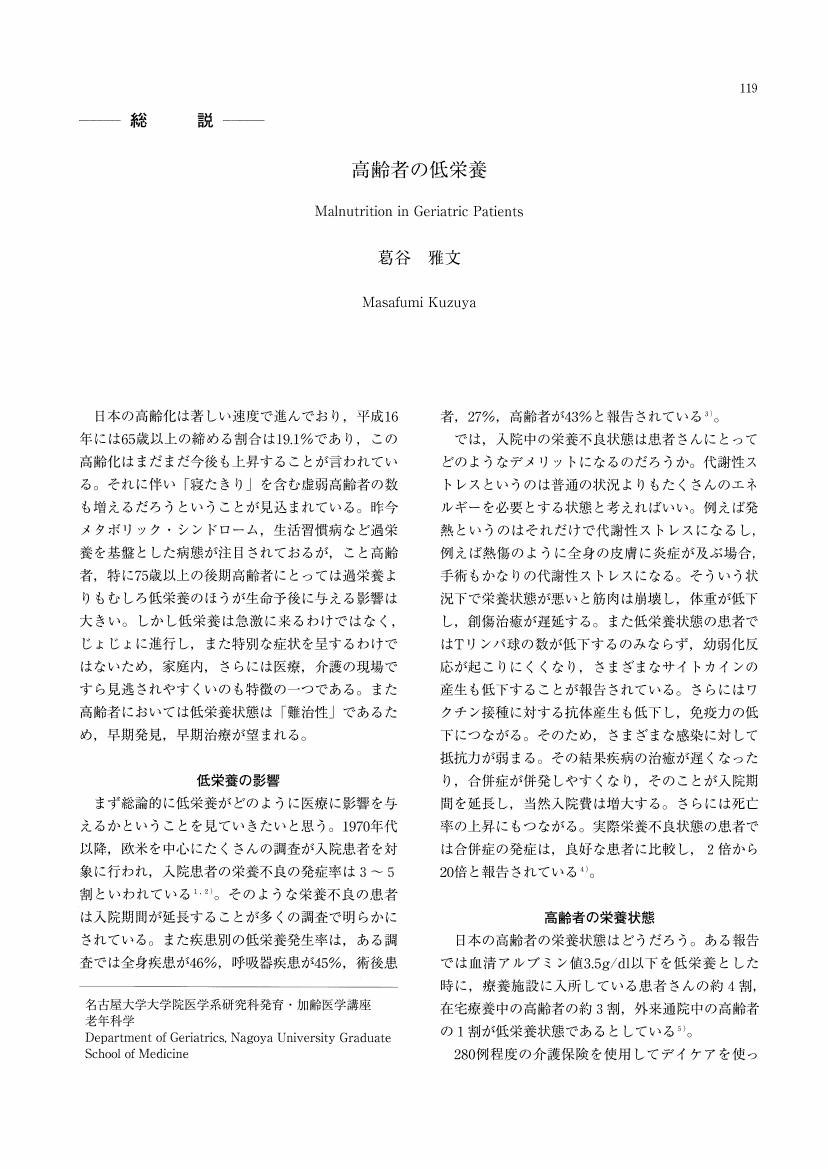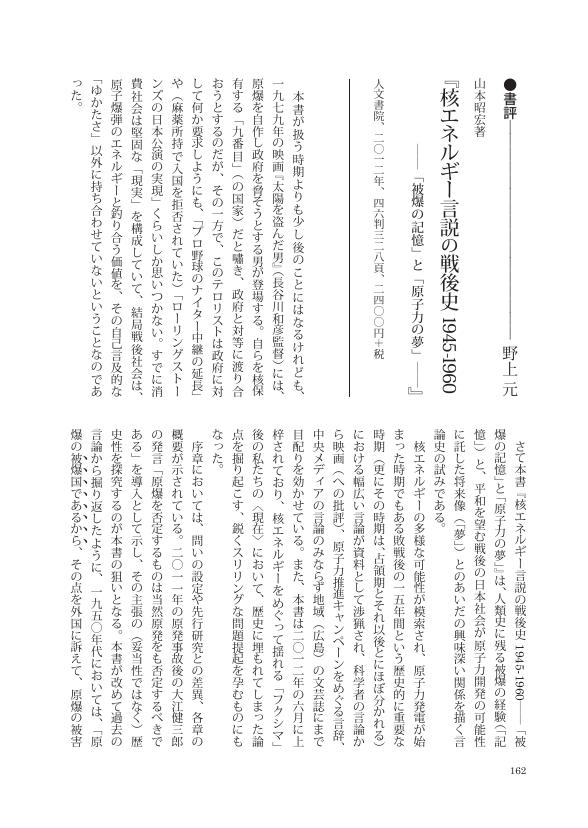7 0 0 0 OA 「白衣募金者」とは誰か : 厚生省全国実態調査に見る傷痍軍人の戦後
- 著者
- 植野 真澄 ウエノ マスミ UENO Masumi
- 出版者
- 大阪大学大学院文学研究科
- 雑誌
- 待兼山論叢. 日本学篇 (ISSN:03874818)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.31-60, 2005-12
7 0 0 0 OA 高齢者の低栄養
- 著者
- 葛谷 雅文
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年歯科医学会
- 雑誌
- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.119-123, 2005-09-30 (Released:2014-02-26)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 2
7 0 0 0 OA 16世紀イングランド文学における浮浪者の表象研究
本研究は16世紀イングランド文学における浮浪者(vagabond)表象の分析である。本研究がこの社会集団に注目する理由は、16世紀の浮浪者が社会変化によって生みだされた近代最初の公的な貧困者たちであり、同時代のイングランド文学がこの集団に対して差別的イメージの原点となる負のステレオタイプを貼りつけたことにある。本研究は引籠りや離職者から、特定の外国人(ジプシーやアイルランド人など)、特定の職業(鋳掛屋や行商人など)まで一括して浮浪者と呼ばれた社会集団の表象において、16世紀イングランド文学が議会制定法、歴史書、パンフレットとの相互影響関係の中で特異なイメージを発達させた過程を歴史的に解明した。
7 0 0 0 OA かみさまをHAIの視点から捉える
- 著者
- 高橋 英之 寺田 和憲 上出 寛子
- 出版者
- 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, 2015
その実在の議論とは別に,我々がかみさまを知覚する際に,他者やエージェントを知覚するのと同様な神経回路を用いていることが近年示唆されている.我々は,宗教,そして神は古代から人が作り上げてきた最も成功したHAIの一つであるという仮説を提起し,その誕生と機能について,宗教の歴史や形態と既存のHAI研究との比較を行いながら議論を行いたい.
- 著者
- 今野 元 Hajime KONNO
- 出版者
- 愛知県立大学外国語学部
- 雑誌
- 紀要.地域研究・国際学編 = Journal of the Faculty of Foreign Studies, Aichi Prefectural University: Area Studies and International Relations (ISSN:13420992)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, pp.289-308, 2015-03-22
7 0 0 0 OA 法律家に求められる力と心 : みなさんに伝えたい
- 著者
- 梓澤 和幸
- 出版者
- 山梨学院大学
- 雑誌
- 山梨学院ロー・ジャーナル (ISSN:18804411)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.315-327, 2012-07-30
7 0 0 0 OA 日本人と中国人の死生観を読み解く : 文化の違いに基づき、実践調査を参考に
- 著者
- 徐 静文
- 出版者
- 大阪大学大学院文学研究科臨床哲学研究室
- 雑誌
- 臨床哲学 (ISSN:13499904)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.35-54, 2013-10-25
- 著者
- 田代 加奈
- 出版者
- 龍谷大学
- 雑誌
- 龍谷大学大学院国際文化研究論集 (ISSN:13491342)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.82-88, 2012-03
- 著者
- 石塚 倫子
- 出版者
- 学校法人 須賀学園 那須大学 都市経済学部
- 雑誌
- 那須大学 論叢 (ISSN:13455788)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.25-35, 2002
7 0 0 0 ウミガメの繁殖生理と人工繁殖に関する研究
和歌山県日高郡南部町千里の浜と愛知県渥美郡渥美町恋路が浜に産卵のため上陸したアカウミガメから採取した卵を用いて、1)受精卵の移植前後の発生率の変化と最適な移植時期の検討、2)発生の進行に伴う胚の固着現象の意義、3)発生過程で生じる卵殻の白濁現象の組織学的解明並びに卵白蛋白質成分の変化、5)飼育下の雌雄アカウミガメの繁殖生理に関する内分泌学的研究について実施した。1)産卵直後から産卵後16時間以内に転卵(移植)を行うと発生の停止が起こらないことや、産卵後約30日以降に行った場合でも発生率の低下が抑えられる可能性も推察できた。2)胚が固着する卵殻上部(切断径3cm/卵殻径4cm)の卵殻と卵殻膜を切断除去した状態で培養を進行させると、卵黄上部に位置した胚が培養7日目には卵殻(膜)切断面まで移動し、培養後約30日を越えると胚の固着強度が弱まり、培養後50日以降に水分吸収による卵殻内圧の上昇が起こった後、2個体正常に孵化した。3)卵殻の白濁部と非白濁部を詳細に検討した結果、組織学的な違いは認められなかったが、水分の透過性の違いが卵殻の両域を形成するものと思われた。また、発生の進行に伴って分子量約40000の蛋白質の出現と消失が認められた。5)飼育下雌個体の血中エストロジェン濃度と非透過性カルシウム濃度は6〜8月から上昇し、翌年の4〜5月に最も高い値を示し5〜6月に低下する年周期を示した。また、血中プロジェステロン濃度は4〜5月中旬に急激に上昇した。一方、雄の血中テストステロン濃度は、測定開始時の1月以降5〜6月にかけて高い値を維持し、特に3〜4月で激しい変動幅が確認され、同時期に追尾などの性行動も観察された。以上の研究より、アカウミガメの発生学的または繁殖生理学的な基礎的知見を明らかにすることができ、これらの結果は今後の保護対策に大いに役立つものと考えられた。
7 0 0 0 OA スラムダンク
- 著者
- 井田 茂
- 出版者
- 日本惑星科学会
- 雑誌
- 遊・星・人 : 日本惑星科学会誌 (ISSN:0918273X)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, 2008-06-25
7 0 0 0 OA マクスウエル光学系による広視野立体ディスプレイ
- 著者
- 稲見 昌彦 川上 直樹 柳田 康幸 前田 太郎 舘 暲
- 出版者
- 日本バーチャルリアリティ学会
- 雑誌
- 日本バーチャルリアリティ学会論文誌
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.287-294, 1999-03
Conventional stereoscopic displays have inconsistent accommodation against convergance, which dengrades sensation of presence. We developed a stereoscopic display applying Maxwellian optics to avoid such inconsistency by realizing large depth of focus. The display was also designed to provide large field of view (about 110 degree) with the simple optics. And this display allows an operator to observe real and virtual images in focus for wide range of depth.
7 0 0 0 芸術文化政策をめぐる政府の中立性の考察
- 著者
- 石川 涼子
- 出版者
- 立命館大学国際言語文化研究所
- 雑誌
- 立命館言語文化研究 (ISSN:09157816)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.3, pp.79-90, 2015-02
- 著者
- 水沢 光
- 出版者
- 日本科学史学会
- 雑誌
- 科学史研究. [第III期] (ISSN:21887535)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.272, pp.379-396, 2015-01-31
This paper analyzes the distribution of the Subsidiary Fund for Scientific Research, a predecessor to the Grant-in-Aid for Scientific Research (KAKENHI), which operated in Japan from the 1930s to 1950s. It reveals that the Japanese government maintained this wide-ranging promotion system since its establishment during the war until well into the postwar period. Previous studies insist that, at the end of the war, the Japanese government generally only funded the research that it considered immediately and practically useful. In contrast to this general perception, my analysis illustrates that both before and after the war, funding was allotted to four research areas: natural science, engineering, agriculture, and medicine. In order to illuminate this continuity, I compare the Subsidiary Fund with another research fund existing from 1933 to 1947: the Grant of the Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). The comparison demonstrates that the JSPS received externally raised capital from the military and munitions companies. However, while this group focused upon engineering and military-related research as the war dragged on, the Subsidiary Fund has consistently entrusted scientists with the authority to decide the allocation of financial support.
7 0 0 0 OA 芸術作品の可能性
- 著者
- メンケ クリストフ 田中 均
- 出版者
- 東京大学大学院人文社会系研究科・文学部美学芸術学研究室
- 雑誌
- 美学藝術学研究 (ISSN:13426095)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.195-215, 2011-03-29
特別寄稿
7 0 0 0 OA 規制緩和時代の私立大学運営と税財政法務
- 著者
- 石村 耕治
- 出版者
- 獨協大学法学会
- 雑誌
- 獨協法学 = Dokkyo law review (ISSN:03899942)
- 巻号頁・発行日
- no.91, pp.横25 (552)-横108 (469), 2013-08
- 著者
- 河本 大地
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.120, no.5, pp.775-785, 2011-10-25 (Released:2012-01-17)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 12 7
Arguments on geoparks and geotourism have grown heated in recent years. However, few people can understand what “geo” means. This study considers how to share viewpoints of “geo” to build sustainable regional societies from a geographical perspective. First, the author defines geotourism as a type of ecotourism mainly focusing on the Earth's scientific resources. Second, the author argues that the concept of regional diversity proposed by the Japanese Geographical Union in 2005 is the core of Geography. The author has this concept connect the three existing concepts of the geosphere: biodiversity, cultural diversity, and geodiversity. Then, the author discusses promoting geotourism with the concept of regional diversity and familiar geographical views that are important for building sustainable societies. A geographical approach is inevitable for showing the relationship between our lives and “geo”. Humankind will have a better future by locating the geotourism as the main practice of “Earth Science for Society,” which was the slogan of the International Year of Planet Earth 2007-2009 (IYPE), and sustaining activities to develop ways of looking at “regional diversity”.
- 著者
- 鈴木 潤
- 出版者
- 二松学舎大学人文学会
- 雑誌
- 二松学舎大学人文論叢 (ISSN:02875705)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, pp.73-88, 2015-03