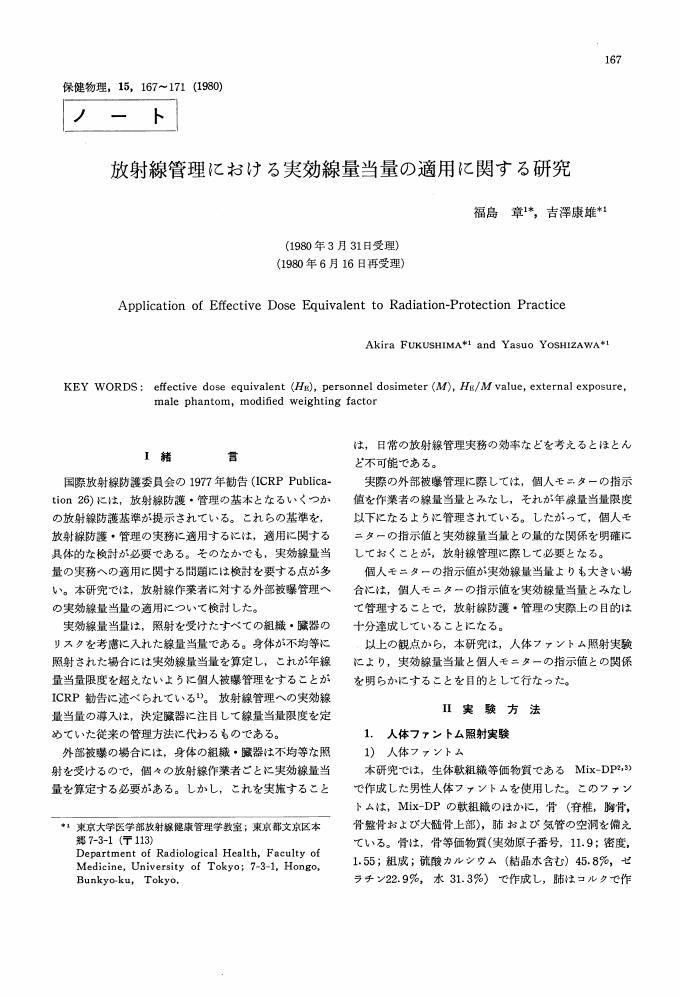7 0 0 0 OA ピタリ効果による食生活の改善
- 著者
- 岡 駿一郎 山根 承子 松村 真宏
- 出版者
- 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, 2012
本研究は仕掛けによる食生活の改善を目指す。まず、生協食堂年間利用定期券(ミールカード)のデータを用いて大学生の食生活の実態を把握した。その結果、カードの利用限度額ちょうどで商品を購入する傾向があることがわかった。この傾向を利用し、「目につきやすい場所に南瓜の小鉢を置く」という簡易な仕掛けを設置した。実験の結果、この仕掛けはより健康的な食選択に誘導する効果をもつことが明らかになった。
- 著者
- 片岡 直樹
- 出版者
- 診断と治療社
- 雑誌
- 小児科診療 (ISSN:03869806)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.11, pp.1925-1927, 2008-11
7 0 0 0 OA 対人的共創知能研究
- 著者
- 國吉 康夫 森 裕紀
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.14-19, 2012 (Released:2012-02-15)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 2 1
7 0 0 0 OA ディープ・エコロジー思想の再検討-社会哲学的射程から-
- 著者
- 有泉 はるひ
- 出版者
- 早稲田大学大学院社会科学研究科
- 雑誌
- ソシオサイエンス = Waseda Review of Socio-science (ISSN:13458116)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.14-29, 2006-03
論文
- 著者
- Kazuhiro NAKAMURA Kei HASHIMOTO Yoshihiko NANKAKU Keiichi TOKUDA
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems (ISSN:09168532)
- 巻号頁・発行日
- vol.E97-D, no.6, pp.1438-1448, 2014-06-01
This paper proposes a novel approach for integrating spectral feature extraction and acoustic modeling in hidden Markov model (HMM) based speech synthesis. The statistical modeling process of speech waveforms is typically divided into two component modules: the frame-by-frame feature extraction module and the acoustic modeling module. In the feature extraction module, the statistical mel-cepstral analysis technique has been used and the objective function is the likelihood of mel-cepstral coefficients for given speech waveforms. In the acoustic modeling module, the objective function is the likelihood of model parameters for given mel-cepstral coefficients. It is important to improve the performance of each component module for achieving higher quality synthesized speech. However, the final objective of speech synthesis systems is to generate natural speech waveforms from given texts, and the improvement of each component module does not always lead to the improvement of the quality of synthesized speech. Therefore, ideally all objective functions should be optimized based on an integrated criterion which well represents subjective speech quality of human perception. In this paper, we propose an approach to model speech waveforms directly and optimize the final objective function. Experimental results show that the proposed method outperformed the conventional methods in objective and subjective measures.
7 0 0 0 OA 後藤朝太郎の支那学の構想
- 著者
- 石川 泰成
- 出版者
- 九州産業大学
- 雑誌
- 九州産業大学国際文化学部紀要 (ISSN:13409425)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.1-18, 2001-08
7 0 0 0 OA 地球温暖化
- 著者
- 向井 人史
- 出版者
- 公益社団法人 大気環境学会
- 雑誌
- 大気環境学会誌 (ISSN:13414178)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.3, pp.A2-A9, 2013-05-10 (Released:2013-08-28)
- 参考文献数
- 20
- 著者
- 瀧澤 純 渡辺 未由希
- 出版者
- 首都大学東京都市教養学部
- 雑誌
- 首都大学東京東京都立大学心理学研究
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.1-8, 2012-03-20
- 著者
- Yu Suzuki
- 出版者
- 一般社団法人 情報処理学会
- 雑誌
- Journal of Information Processing (ISSN:18826652)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.22-30, 2015 (Released:2015-01-15)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1 18
In this paper, we propose a method for assessing quality values of Wikipedia articles from edit history using h-index. One of the major methods for assessing Wikipedia article quality is a peer-review based method. In this method, we assume that if an editor's texts are left by the other editors, the texts are approved by the editors, then the editor is decided as a good editor. However, if an editor edits multiple articles, and the editor is approved at a small number of articles, the quality value of the editor deeply depends on the quality of the texts. In this paper, we apply h-index, which is a simple but resistant to excessive values, to the peer-review based Wikipedia article assessment method. Although h-index can identify whether an editor is a good quality editor or not, h-index cannot identify whether the editor is a vandal or an inactive editor. To solve this problem, we propose p-ratio for identifying which editors are vandals or inactive editors. From our experiments, we confirmed that by integrating h-index with p-ratio, the accuracy of article quality assessment in our method outperforms the existing peer-review based method.
7 0 0 0 京大「大惣本」購入事情の考察
- 著者
- 広庭 基介
- 出版者
- 大学図書館研究編集委員会
- 雑誌
- 大学図書館研究 (ISSN:03860507)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.106-121, 1984-05
7 0 0 0 分娩の曜日・時刻からみた周産期医療の問題点と課題
- 著者
- 山岡 久美子 齋藤 いずみ 西 基
- 出版者
- 日本母性衛生学会
- 雑誌
- 母性衛生 (ISSN:03881512)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.2, pp.412-420, 2006-07
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
札幌市内のA病院で2001年1〜12月までになされた分娩1,008例について,曜日・時刻との関連を検討した。分娩数は,水曜日が最も多く(全体の18.45%),かつ在胎週数34週未満の児と出生体重1,500g未満の児が多く出生していた(それぞれ全体の30,35%)。母児の生命にかかわる胎児心音低下・弛緩出血などの件数は金曜日が最も多く(全体の18.18%),かつ午後14時ころがそのピークであった。また,金曜日には緊急帝王切開(全体の22.77%)・母体搬送(全体の26.09%)が多かった。水曜日に未熟児分娩が集中したのは,以前から入院していたハイリスク児を計画的にマンパワーの手厚い週の半ばに分娩させるためと考えられた。原因の特定には至らなかったが,金曜日に異常分娩が多いことが明らかであった。ハイリスク児出生が同じ日に集中した場合,NICUの負担が過大となる危険性,および土・日曜日に治療・検査を強いられる危険性がそれぞれ危惧された。産科部門・検査部門・NICUの人的資源の配分の際には,このような時間的な要素を考慮すべきこと,地域における関連病院・NICUの相互の連携体制を充実すべきことなどが必要と考えられた。
7 0 0 0 OA 放射線管理における実効線量当量の適用に関する研究
7 0 0 0 OA 近世関東の村における剣術流派の普及に関する基礎的研究
この研究は、江戸時代を通して、関東(上野国(群馬県)、武蔵国(東京)、常陸国(茨城県)、安房国、下総国、上総国(ともに千葉県))の農村において剣術流派がどのように存在し、継承されたかを調査することで、農民の身体観を明らかにしようとする試みである。特に剣道場の場所(上野国群馬郡金古村・小野派一刀流中澤清忠、上野国・馬庭念流の江戸道場)、門弟の援助(馬庭念流20世樋口定廣の例)、流派による奉納額(中沢清忠、樋口定廣の奉納額)を調査した。また、下野国の剣術流派の分布をみた。また武蔵国八王子犬目村の八王子千人同心家、斎藤家が所蔵した文書を整理し、2013年までに、4,600のリストを作成した。
7 0 0 0 家族メンバーによる高齢者介護の継続意志を規定する要因
- 著者
- 唐沢 かおり
- 出版者
- 日本社会心理学会
- 雑誌
- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.172-179, 2006
- 被引用文献数
- 3
This study explored the determinants of intent of primary caregivers to continue taking care of elderly family members. The exploration was guided by two previous lines of study, one arguing the additive effect of positive and negative aspects of caregiving, and the other arguing the effect of attitude towards family caregiving. Four hundred and forty-five family caregivers answered questions relating to depression, caregiving intent, attitude towards family caregiving, and positive and negative aspects of caregiving. Structural equation modeling revealed that attitude to wards family caregiving increased both depression and intent to continue family caregiving. It is argued that when constructing a support system for family caregivers one must consider the possibility of family members being trapped by their attitude towards family care.
7 0 0 0 OA 学会ニュース
- 出版者
- 日本結晶学会
- 雑誌
- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.News3-News3, 2014-06-30 (Released:2014-07-09)
7 0 0 0 OA 家族の介護により経口摂取が可能となり, 胃瘻から脱却した症例
- 著者
- 松香 芳三 笈田 育尚 熊田 愛 縄稚 久美子 西山 憲行 菊谷 武 窪木 拓男
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年歯科医学会
- 雑誌
- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.91-96, 2009 (Released:2010-10-19)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1
摂食・嚥下機能が低下している高齢患者において, 胃瘻を造設することにより胃腸の機能を残存させながら栄養管理が可能となる。しかしながら, 胃瘻には種々の問題点が存在するため, 胃瘻の早期脱却を目標にして, リハビリテーションを実施するべきである。今回, 胃瘻造設を行ったが, 家族の介護ならびに義歯作製によって経口摂取が可能となり, 胃瘻脱却が可能になった症例を経験したので報告する。患者は脳梗塞, 老年性認知症を原疾患として有していた82歳女性であり, 認知症のために, 自発的な摂食行動はみられず, 食物を口腔内に溜め込み, 嚥下運動に移行しにくい状況であった。摂食・嚥下機能の回復が十分に認められたため, 胃瘻造設術が実施された。また, 同時期に旧義歯の適合不良のため, 家族から義歯作製を依頼され, 全部床義歯を作製した。義歯作製により, 家族の食介護に対するモチベーションが向上し, 積極的に経口摂取を進めるようになった。その結果, 全量経口摂取することが可能となり, 胃瘻から脱却することが可能となった。観察期間を通して, 血清アルブミン値の大きな変化はみられなかったが, 義歯装着後には体重増加が観察され, 胃瘻脱却後も体重は維持されていた。その後, 摂食・嚥下に対する直接訓練が効を奏し, 自分で摂食する場面も観察されるようになった。
7 0 0 0 OA 『女性における「処女性」に関する臨床心理学的研究』 : 「少女性」との対比から
- 著者
- 藤澤 佳澄 フジサワ カスミ Fujisawa Kasumi
- 出版者
- 大阪大学大学院人間科学研究科教育学系
- 雑誌
- 大阪大学教育学年報 (ISSN:13419595)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.155-166, 2002-03
- 著者
- 池内 裕美 藤原 武弘
- 出版者
- 日本社会心理学会
- 雑誌
- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.92-102, 2000
The main purpose of this study was to investigate the effects of loss of material possession and social support network on QOL (Quality of Life). In this study, QOL was defined as "the subjective feeling of satisfaction or happiness" and was measured by "the grade of well-being" and "the state of mind and body health." Three hundreds and sixty-five victims of the Great Hanshin Earthquake(105 males, 256 females, and 4 undetermined sex) who lived at temporary houses in Nishinomiya City were asked to complete a questionnaire by personal interview method. The main findingswere as follows: (1) the victims who had lost their important possessions were higher in well-beingscore than ones that did not. On the other hand, the victims who had not lost them were higher inmind and body health score than ones that did. (2) The number of social support network had no effect on well-being score. But the victims who had a large number of social support network stended to be higher in mind and body health score than ones that had a small number of them.
7 0 0 0 阪神・淡路大震災の避難所リーダーの研究
- 著者
- 清水 裕 水田 恵三 秋山 学 浦 光博 竹村 和久 西川 正之 松井 豊 宮戸 美樹
- 出版者
- 日本社会心理学会
- 雑誌
- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.1-12, 1997
- 被引用文献数
- 1
The purpose of our study on the 1995 Hanshin Earthquake was twofold. First, we investigated the operation of the relief shelters, including relief activities. In this part of the study, we focused on the leaders of the shelters. The second purpose of this study was to reveal factors contributing to the effective management of the shelters. About three weeks after the Hanshin Earthquake, we conducted interviews with 32 leaders of the relief shelters and of volunteer workers. We were mainly concerned with the conditions of the emergency facilities, how leaders were selected and what managerial problems they faced. The result of our study showed three types of motivation for becoming leaders. The first occurred naturally as an outcome of their activities; the second by their own choice; and the last because of their regular job positions. These results were analyzed and categorized by the type three quantification analysis. We found that the most effective management of the relief shelters was under leaders chosen by the last method; that is, those who held positions of leadership in their regular jobs.