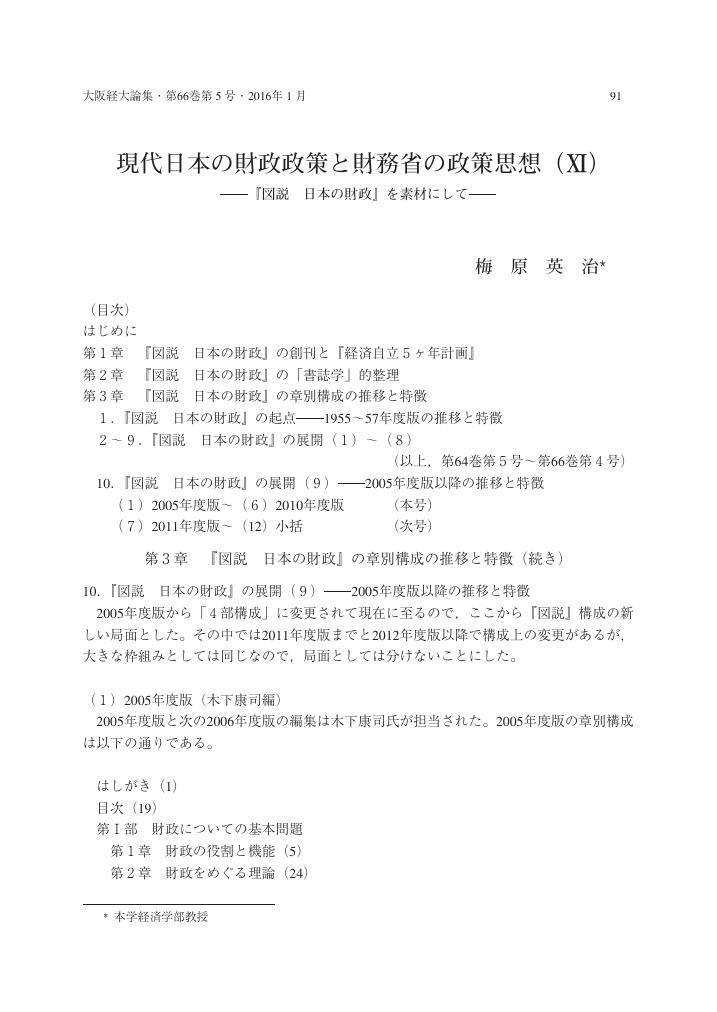- 著者
- 作田 はるみ 片寄 眞木子 坂本 薫 田中 紀子 富永 しのぶ 中谷 梢 原 知子 本多 佐知子
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.27, 2015
<br><br><br><br>【目的】兵庫県は南北を海に接して大小の島を擁し,中央部には東西に山地が横たわっている。河川の下流には肥沃な平野が開け,多彩な産物に恵まれるとともに,都市としても発展してきた。日本の縮図ともいわれる気候風土の違いが,地域ごとに伝統的な食文化を形成してきた。本研究では,各地域で昭和30・40年代に食べられていた家庭料理の中で主食となる「ごはんもの」と「もち・もち米」について,各地域の内容や背景を比較し,その特徴を明らかにすることを目的とした。<br><br>【方法】神戸,東播磨(瀬戸内海沿岸),東播磨(平野),北播磨,中播磨(平野),西播磨(山地),但馬(日本海沿岸),丹波,淡路の9地域を選定して平成25,26年に調査し,平成24~25年度『次世代に伝え継ぐ日本の家庭料理』聞き書き調査報告書(日本調理科学会)を資料とした。本研究では,家庭料理のうち,「ごはんもの」と「もち・もち米」について各地域の日常食と行事食について検討した。<br><br>【結果】日常の主食は,西播,丹波,但馬では麦飯,他地域では白米飯,神戸の朝食はパンであった。山地では山菜や野菜,沿岸部では魚介や海草といった季節の食材を使用した炊き込み飯や混ぜご飯,寿司も食べられていた。特に行事食では,秋祭りに鯖寿司が作られている地域が多かった。巻き寿司やいなり寿司は,運動会などの行事でよく作られ,具材の取り合わせに地域の特徴がみられた。もちについては,正月の雑煮として各地域で食べられていた。雑煮は,丸もちとみそ仕立ての地域が多かった。西播磨では,すまし仕立てで蛤が入り,淡路では,三が日はもちを食べず4日目に食べられていた。また,もちはあられやかきもちに加工され,ひなまつりやふだんのおやつとして食べられていた。
- 著者
- 吉江 真 大石 彰誠 尼岡 利崇
- 雑誌
- 研究報告ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI)
- 巻号頁・発行日
- vol.2010-HCI-138, no.5, pp.1-4, 2010-05-07
本論文は汎地球測位システム(GPS)と社会的ネットワークサービス(SNS)を用いた聴覚による拡張現実感を体感できる情報提供システム(twiwave)を提案する.本システムを使用することで、ユーザーは現在地周辺で過去にSNSに投稿された情報を音声で聞きながら公共スペース内を移動することが可能となる.本システムを従来の拡張現実感と比較すると、音声により情報提供を行うことで文字などの視覚情報を注視する必要がなくなったことから、別の活動をしながらの使用に適しているという利点がある.
1 0 0 0 ポリオレフィンの分子構造解析における進展
- 著者
- 坂田 和也 山田 芳佳 飯場 顕司 田谷野 孝夫
- 出版者
- 公益社団法人 石油学会
- 雑誌
- 石油学会 年会・秋季大会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2015, 2015
ポリオレフィンの分子構造解析について、最近の技術的な進展を紹介する。温度変調昇温溶離分別による結晶性分布解析、相互作用クロマトグラフィーを用いた組成分布解析、二次元NMRによる微細構造解析などを報告予定。
- 著者
- 宮脇 岑生
- 出版者
- 札幌大学
- 雑誌
- 札幌法学 (ISSN:0915809X)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.A95-A121, 2003-03-31
1 0 0 0 OA 視覚と聴覚に訴える避難行動体験システム
- 著者
- 佐々木龍之介 千種康民 服部泰造
- 雑誌
- 第73回全国大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, no.1, pp.651-652, 2011-03-02
本研究では、拡張現実感(Augmented Reality:AR)を利用して、避難訓練をより効率的なものとするための手法を研究した。具体的には、建築物内にARマーカーを設置し、3Dモデルにより火災や崩壊を視覚的に表現する。さらに、現実味・緊張感を増すために、サイレンなどの効果音を加える、タイムリミットやユーザの体力なども設定する。一般的な避難訓練というと退屈なイメージが強く、子供などの低年齢層に対しては訓練の意味を理解されることなく行われてしまうことが多々あると考える。そういった対象に対しても、本研究を利用することにより意欲的な訓練への参加を促せ、また実際の消火訓練などでは火を焚くなどの訓練内での危険が伴うが、そういったリスクを回避することも可能である。
1 0 0 0 OA 正本写『松の栄千代田の神徳』の周縁
- 著者
- 山本 和明
- 出版者
- 国文学研究資料館
- 雑誌
- 国文学研究資料館紀要 = National Institure of Japanese Literature (ISSN:18802230)
- 巻号頁・発行日
- no.32, pp.185-208, 2006-02-28
『松の栄千代田の神徳』は、仮名垣熊太郎を作者とする明治期正本写である。本作品を調査することによって明治十年代の一時期に、なぜ正本写が流行したのか、その要因を考察する。“Matsu-no-sakae Chiyoda-no-shintoku” is “Shôhon utsushi” (a novel like the scenario of kabuki) with which Kanagaki Kumataro is made into the author.By investigating this work considers the factor for why “Shôhon utsushi” was in fashion to one time of the Meiji 10s.
1 0 0 0 OA 正本写『松栄千代田神徳』の一資料
- 著者
- 山本 和明
- 出版者
- 相愛大学
- 雑誌
- 相愛大学研究論集 = The annual research report of Soai University (ISSN:09103538)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.160-141, 2007-03
1 0 0 0 OA 空間把握性に注目した音響案内システムの開発に関する研究(感性とメディア及び一般)
- 著者
- 梅津 直貴 井ノ上 寛人 堀内 恒 佐藤 美恵 小黒 久史 春日 正男
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会技術報告 35.39 (ISSN:13426893)
- 巻号頁・発行日
- pp.41-44, 2011-10-06 (Released:2017-09-21)
- 参考文献数
- 5
近年,博物館や舞台,旅行ツアーなどの分野では,観賞対象に合わせて音声やBGMを提供する音声案内システムが検討されている.これらのシステムでは音響情報を実空間に整合させて提示することができ,この方法は実空間に情報を付加提示する拡張現実(AR)として知られている.しかし,ARに関する多くの研究は,主に視覚情報の提示方法について注目したものであり,聴覚情報と組み合わせた提示方法の研究は未だ十分とはいえない.本稿では,観賞者の注意に応じて空間の音響制御を加えることにより,音声の位置や方向がより分かり易くなるAR空間を創出する音声案内システムを検討する.
1 0 0 0 OA 視覚と聴覚のクロスモーダル知覚を用いた音像定位システムに関する基礎検討
- 著者
- 王 夢 小川 剛史
- 雑誌
- 研究報告デジタルコンテンツクリエーション(DCC)
- 巻号頁・発行日
- vol.2013-DCC-4, no.7, pp.1-6, 2013-06-20
拡張現実感における現実世界に重畳表示した仮想オブジェクトのリアリティを向上させるためには,視覚的な提示だけでなく,触覚や聴覚など,より多くの感覚刺激を提示することが重要である.本研究では,聴覚刺激の提示のみで任意の場所に音像を定位することは困難なため,視覚と聴覚のクロスモーダル知覚を用いたシステムを提案する.本稿では,提案システムの実現に向け視覚刺激が音像知覚に与える影響を調査した初期実験について報告する.実験により,視覚と聴覚のクロスモーダル知覚を用いることで,聴覚刺激のみを与えたときと比較して,被験者が音像の位置をより強く認識できることが分かった.
- 著者
- 太田 奨 石井 晃
- 雑誌
- 情報科学技術フォーラム講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.4, pp.569-572, 2013-08-20
- 著者
- 小倉 修 前田 昭三郎 山田 一隆 石沢 隆 島津 久明 永井 志郎
- 出版者
- The Japan Society of Coloproctology
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.75-78, 1992
- 被引用文献数
- 1
大腸内視鏡検査で虫体を確認し,これを内視鏡下に除去しえた大腸アニサキス症の1例を経験した.症例は37歳の女性で,鯖寿司を摂食し,1日後に心窩部痛が出現した.その後,右下腹部痛,嘔気,下痢がみられるようになり,当院を受診した.問診,超音波断層所見,経口腸X線造影などより大腸アニサキス症が疑われ,前処置後大腸内視鏡検査を施行した.盲腸部に4匹の虫体が認められ,これらを内視鏡的に除去した.併せて20例の本邦報告例に関ずる文献的考察を行った.
1 0 0 0 OA 印南数馬・奴袖助実ハ大高主殿/あざみのお花・白坂甚平
1 0 0 0 OA 江戸城諸役人勤向心得
1 0 0 0 OA 無人航行制御技術の最前線
- 著者
- 松田 秋彦 橋本 博公 谷口 裕樹 寺田 大介 三好 潤 溝口 弘泰 長谷川 勝男 世良 亘
- 出版者
- 海洋理工学会
- 雑誌
- 海洋理工学会誌 (ISSN:13412752)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.47-51, 2017 (Released:2017-07-07)
- 参考文献数
- 12
As seaborne trade has greatly increased in recent years, it becomes more difficult to secure crew of ships. Therefore, it is an important issue how to realize unmanned robot ships which can automatically navigate without collisions even in congested waters. Although Rolls-Royce is planning to build a remotely controlled ship in 2020, standard control technology for unmanned ships has not been developed yet. Therefore an automatic collision avoidance system is discussed by carrying out not only computer simulations but also model experiments prior to the tests using actual vessels. For this purpose, the authors built an experimental system for the validation of automatic collision avoidance algorithm. In this paper, model experiments using multiple ships conducted at Marine Dynamics Basin at National Research Institute of Fisheries Engineering are introduced. Through comparisons with numerical simulations which the same algorithm for collision avoidance is implemented, it is found that there is a discrepancy in occurrence of collision in extremely congested situation.
1 0 0 0 敗軍の将、兵を語る 高橋一男氏「岩手県平泉町長」
- 著者
- 高橋 一男
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1456, pp.116-119, 2008-09-08
私は平泉町議会の議長だった1999年頃から、平泉の世界文化遺産登録を目指して活動してきました。しかし、今年5月に国連教育科学文化機関(ユネスコ)世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議(イコモス)が、登録を見送って審査をやり直す「登録延期」を勧告しました。そして、7月にカナダで開かれた委員会でも、結果は覆りませんでした。
1 0 0 0 OA 日本博物誌雑話(5)
- 著者
- 磯野 直秀
- 出版者
- 日本動物分類学会
- 雑誌
- タクサ:日本動物分類学会誌 (ISSN:13422367)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.6-9, 1999-08-20 (Released:2018-03-30)
1 0 0 0 OA 現代日本の財政政策と財務省の政策思想(XI)-- 『図説日本の財政』を素材にして--
- 著者
- 梅原 英治
- 出版者
- 大阪経大学会
- 雑誌
- 大阪経大論集 (ISSN:04747909)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.5, pp.91, 2018 (Released:2018-02-15)
- 著者
- GREYDANUS Donald E. BACOPOULOU Flora TSALAMANIOS Emmanuel
- 出版者
- The Keio Journal of Medicine
- 雑誌
- Keio journal of medicine (ISSN:00229717)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.95-102, 2009-06-01
- 参考文献数
- 87
- 被引用文献数
- 27
The tragedy of suicide in adolescents is experienced by all countries of the world with as many as 200,000 youth and young adults ending their life in the prime of their life because of self-murder each year. Such a tragedy should be unacceptable to clinicians of the world and this article examines factors leading to such death in our youth with recommendations on how to prevent such a worldwide carnage. A major issue in suicide prevention is to screen all children and adolescents for depression and other factors that may trigger suicide in adolescence.