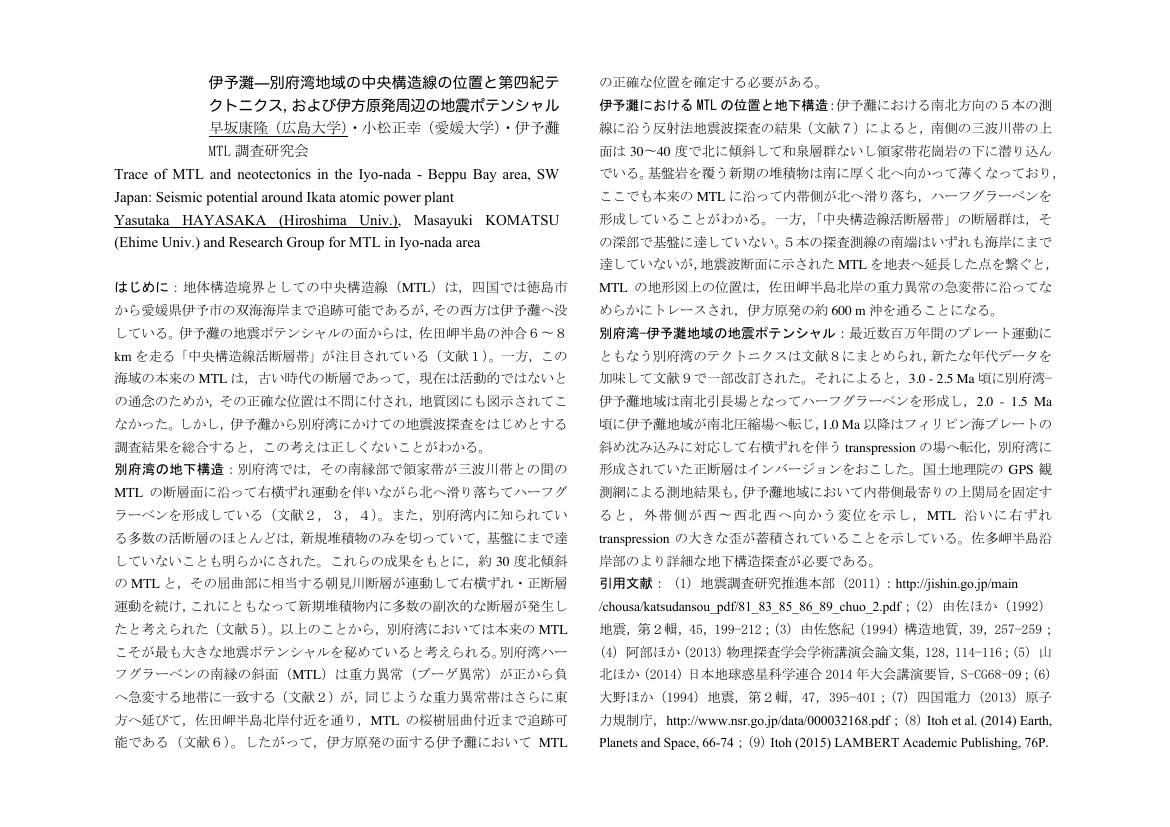1 0 0 0 OA ベーシック・インカムとスピーナムランド制
- 著者
- 小沢 修司 Shuji OZAWA 京都府立大学公共政策学部公共政策学科
- 雑誌
- 京都府立大学学術報告. 公共政策 = The scientific reports of Kyoto Prefectural University. Public policy (ISSN:18841740)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.19-30, 2009-12-01
1 0 0 0 OA スリーマイル島原発事故の化学工学による検証
- 著者
- 大江 修造
- 出版者
- 日本開発工学会
- 雑誌
- 開発工学 (ISSN:13437623)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.19-22, 2011 (Released:2012-12-20)
- 参考文献数
- 5
The Three Mile Island Unit-2 accident was examined from the view point of chemical engineering. It was concluded that preventive measures for the TMI atomic power plant were insufficient compared with those of a chemical plant. Zirconium alloy cladding reacts with steam and generates a hydrogen and zirconium oxide, which loses mechanical strength. As a result, the fuel element melted. At the temperature of 871°C, zirconium alloy starts to react with steam.Zr + 2H2O → ZrO2 + 2H2 + 141 Kcal (1)The reaction rate was observed by Pawel et al., and they presented a rate equation called the Cathcart-Pawel equation. According to the Cathcart-Pawel equation , zirconium alloy cladding was oxidized for 40 minutes at 1649°C (Schneider, 1980). This paper will state that the simulation of a hydrogen explosion at a higher temperature results in a significantly shorter reaction time. For example, at 1000°C the time is 100 hours, whereas at 1500°C it is two hours.
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1951年10月11日, 1951-10-11
1 0 0 0 OA 行動履歴から導き出す行動変容前の利用者像
- 著者
- 澤田 典宏 紅谷 光 大柿 徹 野島 隆志
- 雑誌
- 行動変容と社会システム vol.02
- 巻号頁・発行日
- vol.2017, 2017-06-26
情報通信機器の高度化,パーソナル化により,個人の行動履歴の取得が容易となった.これに伴い,ユーザのライフスタイルを改善する手法のひとつとして行動変容が挙げられている.行動変容には行動への介入前,介入中,介入後の観察が重要とみなされているが,特に介入前のデータについては関係者の間でも充分な知見の共有がなされてはいない.本稿ではスマートフォン向けアプリケーションから取得した行動履歴を使って都市部にある駅前商業施設を利用しないユーザのライフスタイルを分析,考察し,介入前データのひとつの形を提示する,
1 0 0 0 IR 万得(徳)領再考
- 著者
- 日隈 正守
- 出版者
- 鹿児島大学
- 雑誌
- 鹿児島大学教育学部研究紀要. 人文・社会科学編 (ISSN:03896684)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.23-38, 2003-03-18
本稿では,大隅・薩摩両国に存在する万得(徳)領について再検討を加えた。その結果万得価は,11世紀末から12世紀初期の間に大隅・薩摩両国の国管に拠り設定されたと考えられる。万得領の設定目的は,大隅・薩摩国内の主要な神社の神事用途を弁済するためであると考えられる。大隅国内においては,大隅国正八幡宮が国内最有力の神社であるので,大隅国内の万得価の年貢は,主に大隅国正八幡宮の神事用途に使用された。この事実が前提となり,大隅国内では,荘園公価制の大枠が形成された12世紀前期に,大隅国内の万得領は大隅国正八幡宮の半不輸価化した。薩摩国内の万得領は,当初新田八幡宮等国内の有力神社の神事用途を負担していた。しかし平安後期薩摩国管と新田八幡宮とが浮免田設定や修造に関して対立する様になると,薩摩国管の在庁官人達は自分達が領有している万得領を大隅国正八幡宮に半不輸領として寄進した。その結果,薩摩国内の万得領も大隅国正八幡宮領化した。
- 著者
- 岩田 剛典 山口 玲美 堀 正幸
- 雑誌
- ホルモンと臨牀 (ISSN:00457167)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.2, pp.71-74, 1995-02-01
- 著者
- 藤原 和好
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.8, pp.11-19, 2007
感動は教育できない、教えられないということは、まったく当然のこととして、圧倒的多数の教師・研究者に信じられている。そういう信念の背後には、教育とは計画的な営みで、その結果は評価可能なものでなければならないという教育観・学力観がある。そして、さらに、感情は不可知のもので、科学的分析の対象にならないという認識がある。それが文学教育否定の根拠となっている。しかし、はたしてそういう前提は正しいのか。揺るぎないものなのか。
1 0 0 0 ファインバー:―最新型リファイニングプレートの紹介―
- 著者
- 川井 利克
- 出版者
- JAPAN TECHNICAL ASSOCIATION OF THE PULP AND PAPER INDUSTRY
- 雑誌
- 紙パ技協誌 (ISSN:0022815X)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.31-36, 2012
昨今の電力供給事情の悪化により,日本の産業界は省エネルギーへの取組みを強化せざるを得ない環境にあり,省エネルギーの進んだ製紙業界においても,更なる取り組みが必要となっている。このような状況の中,製紙工程の中でも,とりわけ大きな動力を消費する叩解工程は,これまでも日々改善を積み重ねられてきたが,今また注目しなければならない工程となった。<BR>また古来より紙製品の品質を左右する重要な工程である叩解技術は,製紙原料,抄紙技術とともに変遷してきたが,主原料であるバージンパルプや古紙原料の短繊維化が進行している今日においては,叩解処理技術は新たなる転換期を迎えていると考える。<BR>本稿では,この様な背景に合致した低動力で製品品質のアップグレードを可能とする弊社の最新型リファイナー用刃物である"Finebar"に焦点を当てる。<BR>この"Finebar"は,刃幅,溝幅を究極まで狭小化すること可能な刃物であり,その特徴を生かして得られる様々な優れた叩解性能を紹介するとともに,"Finebar"の技術を更に展開した新しい叩解技術への弊社の取り組みを紹介,報告するものである。<BR>紙面の関係上,導入メリット,ミニセグメント等,一部の内容の報告に留まったが,Finebarは,国の内外を問わずL,N混合叩解や家庭紙用叩解などあらゆる叩解工程で,極めて高い叩解性能が実証されており,叩解工程の省コストに貢献できる優れた技術であるといえる。
1 0 0 0 都市における生鮮食料生産の多面的意義
- 著者
- 古在 豊樹
- 出版者
- 養賢堂
- 雑誌
- 農業および園芸 (ISSN:03695247)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.10, pp.994-1006, 2014-10
日本の都市における農業の現状(農地・農業就業者・生産額の動態など),多面的機能(生産,環境保全,防災,レクリエーション,市民農園,コミュニティー,教育など),法律(都市計画法,農業振興地域整備法など)・税制などに関しては,数多くの識者により報告され,また都市の農地・農業・緑地のあり方や解決すべき課題が論じられている(たとえば,進士 2003,蔦屋 2005,樋口 2008,東 2011)。本稿では,都市の住民が消費する生鮮食料を都市で生産することの意義を,(1) 都市への有用資源流入と都市からの劣化資源排出,(2) 都市での植物生産による資源内部循環,(3) 輸送に伴うCO2排出(すなわち,石油資源消費),(4) 都市に適した植物生産方式,(5) 都市住民の生活の質の向上,および(6) 都市における農業以外の諸活動との関係などに留意しつつ考察する(古在 2014)。
1 0 0 0 横浜市における都市の農地、農村環境の整備施策について
- 著者
- 糸井 定雄
- 出版者
- 農村計画学会
- 雑誌
- 農村計画学会誌 (ISSN:09129731)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.2, pp.36-38, 1988-09-30
- 著者
- 鈴村 幸太郎
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経systems (ISSN:18811620)
- 巻号頁・発行日
- no.261, pp.30-35, 2015-01
SPAを適用したWebアプリの開発では、フレームワークが活用される。SPAはクライアントサイドでの処理が前提であるため、今までのWebアプリケーションフレームワークとは方式が異なる。 従来のWebアプリ開発は、Apache Strutsなどを使ってサーバーサイドのアプリをMVC…
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1374, pp.58-61, 2007-01-15
日中、車がまばらな駐車場が午後7時を過ぎる頃になると軽自動車や小型乗用車などが1台、2台と吸い込まれていく。まるで暗闇の中にある明かりを求める虫のように。静岡県浜松市街から北へ車で20分ほどにあるこの場所は、紳士服専門店や自動車ディーラー、家電量販店などが立ち並ぶ。全国どこにでもあるロードサイドの郊外型商業立地だ。
1 0 0 0 OA 「新しき村」と『或る女』 -『或る女』成立前夜の問題-
- 著者
- 宗像 和重
- 出版者
- 早稲田大学国文学会
- 雑誌
- 国文学研究 (ISSN:03898636)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, pp.191-203, 1982-10-15
- 著者
- OKUGAWA Ikuko
- 出版者
- Graduate School of Humanities and Social Sciences, University of Tsukuba
- 雑誌
- Inter Faculty (ISSN:18848575)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.119-132, 2014
The influence of internationalization on higher education is rapidly growing throughout the world. In Europe, the interrelation between universities, including the exchange of students and faculty members, has been stimulated through the Erasmus and the Erasmus Mundus Programs and the Bologna process. As for the United States, many of their universities are placed high in world university rankings, attracting many intelligent international students, and both the universities and the federal government constantly pursue strategic methods for strengthening their presence in the international community. In Japan, the accumulated total number of international students reached 110,000 students in 2003, and now the government is aiming to increase this number to 300,000 by 2020. As is evident from the figures disclosed by the government and by the university rankings, statistically speaking, Japan has a low ratio of international students and faculty members in comparison to other countries whose universities rank high on the chart. Focusing on increasing the number of international students is one immediate strategy for concerted action toward internationalization. However, it is important to note that a high ratio of international students and faculty members does not necessarily lead to true internationalization; rather it is the quality of the programs and output that need to be focused upon. This paper explores the current situation of internationalization and its effect through a comparison of Japanese universities with universities of other countries. By examining examples of actual programs currently offered at the University of Tsukuba for meeting the needs and education of students for the globalized world, this paper will also discuss how Japanese universities will be able to grow and strengthen their status in comparison to their competitors.要旨高等教育の国際化は世界中で急速に進んでいる。ヨーロッパではエラスムス計画、ボローニャプロセス、エラスムス・ムンドゥスにより、ヨーロッパ内の学生や教員の流動化、大学間の協力関係を促進している。一方、アメリカでは世界大学ランキングのトップを占める大学も多く、既に優秀な留学生を引き寄せているようにも思えるが、それでも多くの大学やアメリカ政府が国際化戦略を強化し、国際競争力の一層の向上を図ろうとしている。日本では、2003年に留学生受け入れ数が約11万人となり、さらに政府は2020年までに30万人の留学生受け入れを目指している。実際、日本の大学は欧米のトップランクの大学に比べ、留学生や外国人教職員の数が少ないことが世界大学ランキングや政府の調査等で明らかになっており、国際化というとまず留学生の数を増やすことが考えられる。しかし、単に留学生の数を増やすだけが国際化とはいえず、大学の国際的な質の保証を図っていくことが重要である。本稿では、世界の大学と日本の大学の国際化の現状について概観した上で、グローバル化に対する高等教育の国際化の一つとして現在筑波大学で行われているプログラムの紹介を行い、高等教育の国際化という世界の動向の中で、どうすれば日本の大学が国際競争力の一層の向上を図ることができるか示す。
- 著者
- 早坂 康隆 小松 正幸
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 日本地質学会学術大会講演要旨 第123年学術大会(2016東京・桜上水) (ISSN:13483935)
- 巻号頁・発行日
- pp.326, 2016 (Released:2017-04-25)
1 0 0 0 IR 世界大学ランキングの動向と課題
- 著者
- 渡部 由紀
- 出版者
- 京都大学国際交流センター
- 雑誌
- 京都大学国際交流センター論攷 (ISSN:2185680X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.113-123, 2012-02
世界大学ランキングが始まって、間もなく10 年が経過する。ランキングは技術的な問題点を指摘されながらも、大学の「質」を評価する一資料として広く利用されるようになり、その存在感を増している。しかし、既存のランキングが知識基盤社会を支える多様な高等教育システムの発展に与える影響を懸念し、新たなランキング・ツールの開発も始まっている。本稿では、文献調査を用い、5つに類型化されたランキングの特徴を検証し、近年の世界大学ランキングの動向と課題を分析する。ランキングは、大学のエクセレンスを一元的な基準で包括的に評価するリーグテーブルから、大学のパフォーマンスを多面的な視点で捉え、大学の多様性に応じた比較へと変化してきている。しかし、世界の多様な高等教育システムを多面的に比較できるデータの不足が大きな課題となっている。高等教育市場のグローバル化が進む中、日本の大学や政府は、日本の大学のパフォーマンスの国際的な発信力が問われている。
1 0 0 0 IR 世界大学ランキングにおける日本の大学 : ある大学を一例とした考察
- 著者
- KELLEM Harlan Harlan Kellem
- 出版者
- 関西学院大学国際学部研究会
- 雑誌
- Journal of international studies = 国際学研究 (ISSN:21868360)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.99-105, 2016-03